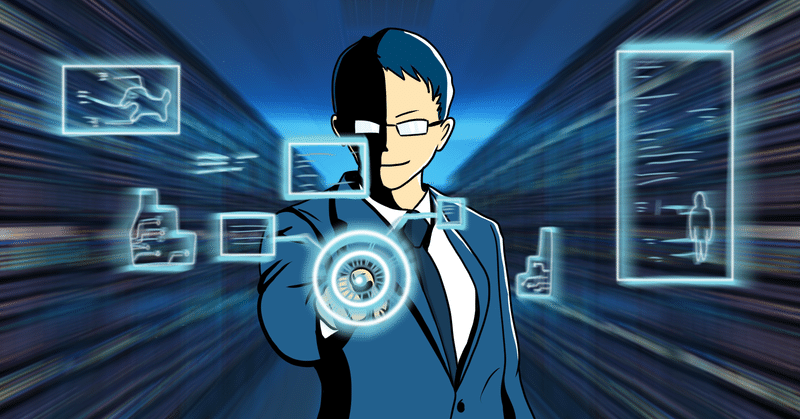
「ビッグデータ」で、企業の“個性”は消え去る!?
現在、飲食店チェーンが、店舗運営にビッグデータ分析を導入し始めている。客の嗜好の多様化や少子高齢化など、経営環境の変化に対応するためである。
客の求めるものを的確に把握することができれば、メニューの改善、新商品開発、店舗の改装・移転、従業員教育にいたるまで、もっとも効率の良い方法を知ることができる。
すなわち、ロスの少ない店舗運営、失敗の少ない経営を実現できるということである。チェーン店を運営する上で、これほど価値のある経営資源は他にあるまい。
だが、懸念材料はある。ビッグデータの活用法。ビッグデータの読み方と言っても良い。
ビッグデータが導き出す結論は、消費者の大多数の嗜好であり、意見である。もちろん、少数意見も導き出してはいるが、読み取る側が大多数のデータに注目してしまう。
最終的には「一番売れるもの」を知りたいので、当然、数の多い客層データを採用する。すると、客に受け入れられるものが開発でき、収益を安定させることができる。だが、はたしてそれは正しいことなのか。
もし、同業種がビッグデータを活用したら……。
大多数の嗜好は同じ結論となり、結果的に、同じ店、同じメニュー、同じ新商品が生まれる。つまり、同業種間で差がなくなるということである。
こう言うと、「それは経営陣次第だろ」と反論が出るだろうが、目の前の“失敗しない経営”を無視して、挑戦・冒険ができるだろうか。
また、ビッグデータによる成功は、人の能力を衰えさせる。すべてをデータに頼ってしまうので、経験や勘といった経営能力が育たない。データを読み解く、“技術者”でしかなくなる。
さらに、データによって成功した人間は、それを自分の才能だと勘違いする。そして、単なる“ビッグマウス”となってしまう。
データによるマーケティングは、一時的には成功をもたらすが、最終的に必要となるのは、経営感覚である。長年積み重ねてきた経験と勘こそが、ビジネスを大きく成長させる要素となるのである。
よろしければサポートをお願いします!頂いたサポートは、取材活動に使わせていただきます。
