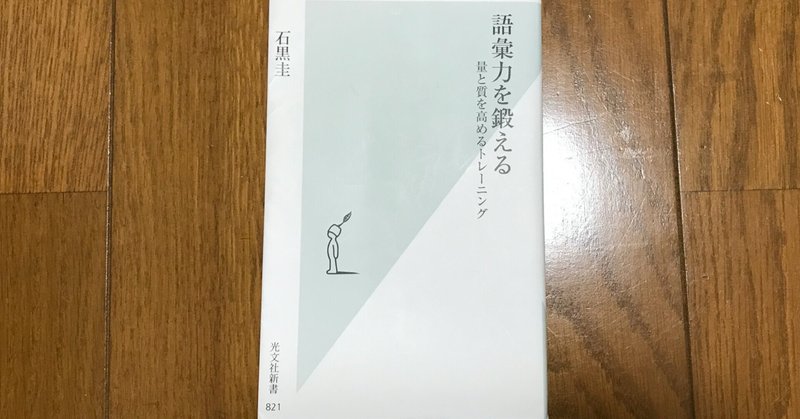
【読書記録】『語彙力を鍛える 量と質を高めるトレーニング』
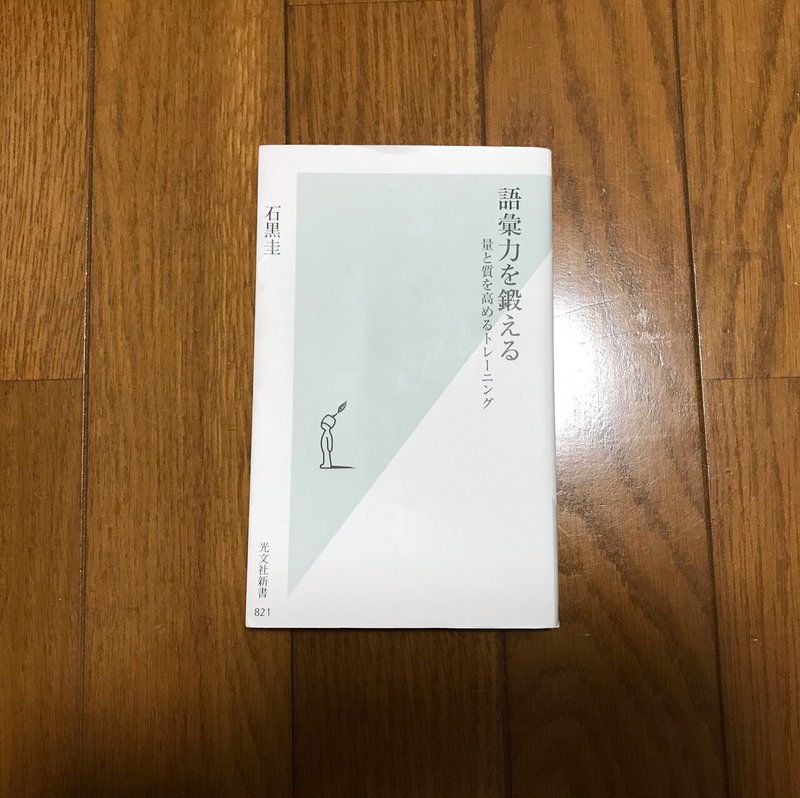
『語彙力を鍛える 量と質を高めるトレーニング』
思考力は言語力に規定され、言語力の基礎になるのが語彙力なのだという筆者が、語彙力を「量」と「質」の両方から高めるメソッドを伝える一冊。
筆者の主張は、語彙力=語彙の量(豊富な語彙知識)×語彙の質(精度の高い語彙運用)という等式に基づいている。
感想
言葉を知っていれば表現できるものが増え、仕事や創作などでも相手を感心させられますが、反対に語彙が少なければ話が薄く、冗長で、嫌な言い方をすれば「バカっぽく」見えてしまうものです。しかし語彙が多くても使い方に難があれば、インテリ気取りの何を言っているかわからない人になってしまうというのは、上記の等式を見れば明らかなことで、そして私にとって耳が痛いものです。言葉は物事を記述するツールであり、ツールはうまく使わなければ宝の持ち腐れ、真珠を豚にやったようなものとなります。その意味で語彙力というものは、ネットで「語彙力がない」と簡単に使われる割にはよっぽど重要なものだと気がつきました。
第三章で筆者は語彙の質について論じていますが、かなり主観的な印象を受けます。しかし言葉の運用とは極めて主観的なものです。例えば「バカ」と言ってのけるにしても、「バカ」と言う人、「バカ」と言われる人、「バカ」という言葉から連想される人や言動、全て同じ「バカ」ではないと思われます。おかしみをもって言い放った「バカ」が、パワハラになってしまうかもしれません。
主観的なものは芸術に通じます。表現者、鑑賞者は芸術作品を介して、想いと想いのコミュニケーションをとります。作り手の自由な発想と伝えたいものを作品に吹き込み、見る人は作品から抽出したアウラを自分の好きなように、自分の経験や文化資本を駆使して解釈します。ですから冗談で言った「バカ」も、小さい頃からお笑い番組を見て育ってきた人と神童のように扱われてきたプライドが高い人とでは、解釈の仕方も異なります。
芸術が主観的なもので、語彙の質も主観的なものだとするなら、語彙を形成する言葉そのものにも美しさを見出すことができます。アニメや漫画のキャラクターの苗字に珍しいものを使う(小鳥遊、巴、黒磯、利根川など)、観光列車に言葉遊びや記号を用いた名前をつける(「あそぼーい!」や「越乃✳︎ShuKura」、アナグラムを用いた「おいこっと」など)、威力と名前の仰々しさが比例するドラクエの呪文(イオ→イオラ→イオナズン→イオグランデなど)、こうした例は字面を重視した結果生まれたものではないかと思っています。山手線の品川〜田町間に開業した最新駅「高輪ゲートウェイ」が猛反対を受けたのも、カタカナ駅名に対する違和感(日本全国、特に東京23区内では極めて珍しい)、異物感が強かったからかもしれません。
使い方次第でその文字が持つ意味以上の情報を与えられるのが言葉の面白いところであり、この本はそれを再認識させてくれました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
