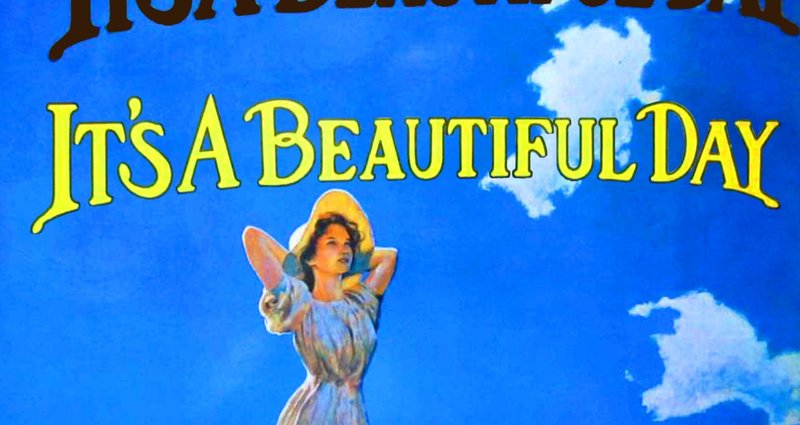#人生

「男はつらいよ」の宣伝担当をされていた方が語った、渥美 清さんの言葉は、アンガーマネージメントとして、人生の生き方として有効である
BSテレ東で毎週土曜日に放送されている「男はつらいよ」シリーズ。 映画が始まる前に当時のエピソードを紹介するコーナーがあります。 この時は、「男はつらいよ」の宣伝担当をされていた方でした。 当時の渥美さんについて、以下のようなお話をされていました。 「普段の渥美さんは、寅さんとはまったく違う。寡黙でよく本を読んだり芝居を観たり・・・」 そして、心に残る言葉として、次のような言葉を紹介されていました。(正確ではありません) この言葉、誰にでも当てはまりますね。 人は誰