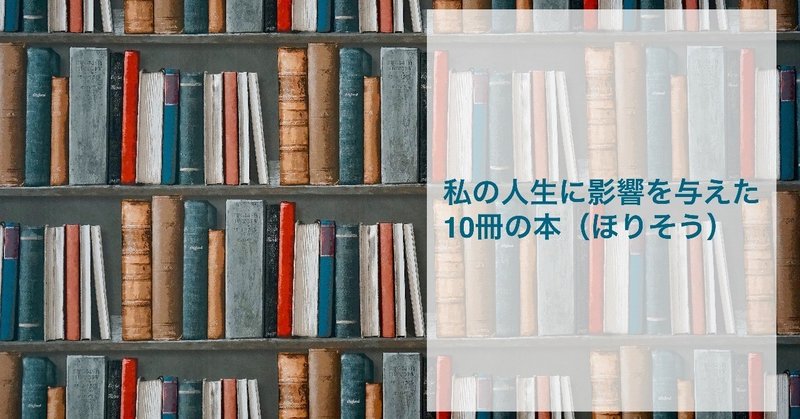
私の人生に影響を与えた10冊の本
5月末に同エントリをFacebookで見つけ、「面白そう」ということでコツコツまとめていました。
最後まで書いてみて「ぶっちゃけ恥ずかしい」という思いを抱いています。何だかカミングアウトしているみたいで…。
もちろんこれ以外にも面白い本はたくさんあるし、知人に薦めるという観点から見れば全く別の本を紹介すると思います。あくまで僕自身に影響を与えた本ということで。
(「あんまりnote更新していない=僕自身の性格が知られていない」という状況でエントリするのもアレですが、自分の備忘録も兼ねて投稿します。超長文ですが、ご笑覧ください!)
*
那須正幹『それいけズッコケ三人組』
もともと本好きの少年でした。
小学生のときは同級生と競うようにして、学校の図書室で本を借りていた気がします。
その中でも那須正幹『ズッコケ三人組』シリーズが大好きで、関連作品を何度も読み返しました。
『とびだせズッコケ事件記者』で新聞記者に憧れたし、『あやうしズッコケ探検隊』で無人島暮らしにワクワクしたし、『花のズッコケ児童会長』で弱者の戦略を学んだような気がします。
スペック的には決して恵まれていないズッコケ三人組。そんな三人が身を以て「ズッコケ=ユニーク」であることを示してくれました。
芥川龍之介『羅生門』
いわゆる古典作品を読むきっかけになったのは、当時通っていた公文式教室の影響でした。
その教材の中で異彩を放っていたのが芥川龍之介『羅生門』。不気味な作品で、読み解くのが非常にしんどかったです。
「死骸の髪を抜く老婆に対して、はげしい憎悪や反感を覚える」下人の心模様が分かるようで分からない。
「正義感を振るって老婆に対した下人が、結局は老婆の着物を剥ぎ取って立ち去っていく」エピソードの意図に気持ちを寄せられない。
未だに謎多き作品ですが「善悪の境界って一概に測れない」というガンダムにも通ずる世界観に影響を受けました。
司馬遼太郎『世に棲む日日』
中学、高校と読書量はめっきり減ってしまったのですが、歴史小説にはハマりました。
その中で一番影響を受けたのは司馬遼太郎『世に棲む日日』です。吉田松陰、久坂玄瑞、高杉晋作の無鉄砲さ、純粋さ、激烈さに心が奪われました。若さゆえ、時代ゆえと一蹴するのは簡単ですが、一人の人間として学ぶべきことが幕末からは凄く多いように思います。
「武士は料簡がせまい。しかしこの狭さがあってこそ、主君に忠義などという、町人がきけばばかばかしいかもしれぬことで腹を切り、命も捨てられるのだ」
絶対に真似できないし、応用することも僕にはできません。ただただ幕末のエネルギーを浴びた思春期でした。
村上春樹『風の歌を聴け』
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないよう」という書き出しで始まる村上春樹『風の歌を聴け』。今ではすっかり彼のファンですが、一番最初に読んだ作品です。
どんな風に影響を受けたのか端的に語るのは難しいですが、彼の作品に出会っていなければ「自分でも小説を書いてみよう」とは思わなかったでしょう。
小説に出てくる登場人物「僕」は、まるでvehicleで、読み手を旅に誘ってくれる感覚があります。決められた旅ではなく、自由な旅。読み手の解釈を尊重してくれる彼のスタンスは、とても信頼できます。
山岸俊男『信頼の構造』
信頼という言葉が出てきたので。
「信頼とは何か(安心とは何が違うのか)」ということを学術的な観点から詳述された山岸俊男『信頼の構造』。
「「大企業に勤めていれば安心」というのは相互の信頼に基づいているわけではない」というのは僕にとってのコペルニクス的転回でした。「何となく設計されている従来の仕組みが何となくでしかない」と自覚したとき、相当の衝撃を受けました。そういったこともあり「信頼をベースにした緩やかな共同体を作ろうとされている」家入一真さんの活動にはいつも共感しています。
「じゃあ今後どうしたら良いの?」っていうのが、実は、僕の人生にとってのテーマなのかもしれません。
原研哉『デザインのデザイン』
大学の授業で最も影響を受けた領域が「デザイン」でした。
原研哉『デザインのデザイン』から表層的な目に見えるものだけでなく、人間の情緒的・倫理的な側面から語られるものこそデザインの本質だということを学びました。同タイミングで発売されたiPodの衝撃も凄くて、そのまま雪崩れるように僕自身の価値観形成が行なわれていった気がします。
書きながら気付いたのですが、僕がSFCという環境で学んだことは、全て広義の意味で「デザイン」だったのではないかなと。特に國領二郎先生が提起されていたネットワーク時代の協業モデルは、まさにそういうことだったんじゃないかなと。当時学んでいたことは当然僕の財産になっているんですが、もうちょっと知恵がついてから学べたら良かったなあ。
スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』
社会に出て、スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』を先輩に薦めていただきました。
この本を読んで「言い訳しない」ことを学びました。当たり前のことなんですけど。
そうなんですよね。ここに書かれていることを未読の方に説明するたび「俺はなんて当たり前のことを言っているんだろう」と絶望してしまうんですが、少なくとも僕にとっては読み返すたびに毎回新しい気付きがある本です。
人が成長し、色々なフェーズを経験することで、学びの幅や深さが変わっていくということだと思います。そんな名著に出会えた自分は本当にラッキーだったなと。
イヴォン・シュイナード『社員をサーフィンに行かせよう』
パタゴニア創始者・イヴォン・シュイナード『社員をサーフィンに行かせよう』はビジネスパーソンとしてだけでなく、一人の人間として感銘を受けました。地球を見据えた事業を構想し、それを愚直に実行しているパタゴニアの姿勢。少しだけですが、自分の視座も高くなったような気がします。
本のタイトルからスローライフな印象を受けていたのですが、実際はそんなことなくて。ページを繰るたびに付箋を貼ったのはドラッカー『マネジメント』と本書の二冊だけです。
沢木耕太郎『深夜特急』
読み物としてダントツで面白く、僕の原点を思い出させてくれたのが沢木耕太郎『深夜特急』です。
今だから言えますが、うっかり現実世界からドロップアウトし、香港に飛び出してしまいそうな衝動にも駆られていました。(という経緯もあるので、人事をやっている以上、若手社員には教えたくない作品だったりします。笑)
この本からの大きな学びは「旅(≒経験)しないと人生のことは分からない」「伝聞情報で物事の真偽を判断するなんて勿体ない」ということです。未だにコテコテと失敗ばかり積み重ねていますが、人生はマラソンだと思っているので、今後も性懲りもなく「旅」を続けていくのでしょう。
村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』
走ることを公言するようになってから「なんで走ってるの?」「走ってて何が面白いの?」と聞かれます。そのたびに抽象的な返答をするんですが、たいていポカーンとされます。
「走ることは人生そのもの」という赤面しそうなことを言う方もいます。それを受けて申し上げるならば「走ることは、自分の人生に加えて、もう1本の人生を歩むことだ」という感じでしょうか。仮想世界、仮想通貨と仮想が流行中ですが、僕にとってマラソンは、仮想人生と言えます。
村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』を読まなければ走ることはありませんでした。人生観にも深い考察を与えてくれた村上春樹さんには、感謝しかありません。
*
まとめ(紹介した10作品)
・那須正幹『それいけズッコケ三人組』
・芥川龍之介『羅生門』
・司馬遼太郎『世に棲む日日』
・村上春樹『風の歌を聴け』
・山岸俊男『信頼の構造 こころと社会の進化ゲーム』
・原研哉『デザインのデザイン』
・スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』
・イヴォン・シュイナード『社員をサーフィンに行かせよう』
・沢木耕太郎『深夜特急』
・村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』
記事をお読みいただき、ありがとうございます。 サポートいただくのも嬉しいですが、noteを感想付きでシェアいただけるのも感激してしまいます。
