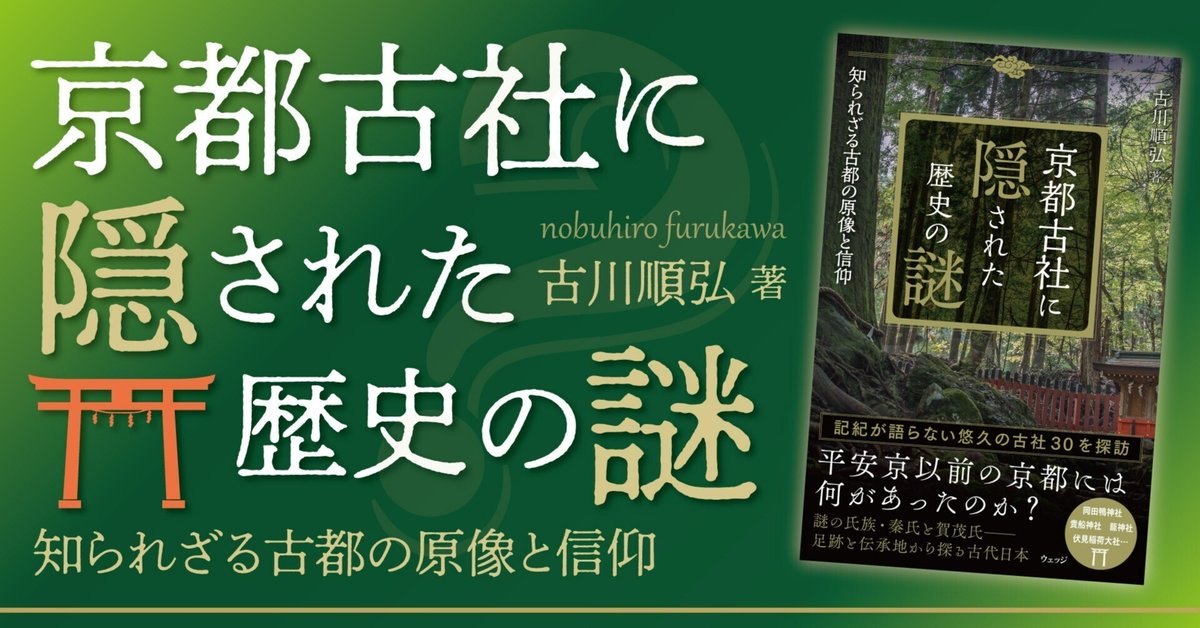
平安京以前の京都には何があったのか?
京都というと、遷都後の平安時代以降の仏教・寺院というイメージが強いかもしれない。だが、遷都前からの歴史の古い神社もじつは多く、これらは平安時代以降のイメージに隠されてきた。意外にも、京都市周縁部には、平安京成立以前から祀られていた古社が多い。
この記事は、『京都古社に隠された歴史の謎』(古川順弘著、ウェッジ刊、2024年6月20日発売予定)の「はじめに」の部分をベースに著者に書き下ろしていただいたものです。

文=古川順弘(文筆家)
喧騒の京都を離れて辿る静謐の古社たち
日本の観光地として長らくナンバーワンの人気を誇ってきた京都だが、近年は観光客の過剰さが話題にのぼることが多い。とくに目を引くのは外国人観光客の多さだ。そして観光客の大幅な増加は、騒音・ゴミ・渋滞・マナー違反などのトラブルを引き起こし、いわゆるオーバーツーリズム(観光公害)という問題を生じさせている。
インバウンドも含め、京都を訪れる観光客はコロナ禍で一時は激減したものの、コロナへの警戒が薄れるにつれて着実に需要は回復。今年のゴールデン・ウィークでは、京都の観光名所はどこも大混雑となった。これには、円安の影響で外国人が日本を訪れやすくなったことも大きく関係していたようだ。「京都の観光客の8割は外国人」という話も聞く。
名勝・嵐山なども連休中は大にぎわいだった。ここはもともと京都でも一、二を争う人気観光スポットだが、しかしその人込みに出くわして、さすがに辟易した人も少なくはなかっただろう。
ところが、渡月橋を西に渡り、川岸に沿って下流方向に10分も歩くとどうだろう。さっきまでの喧騒は嘘のように消え去り、通りを往来する人の姿もまばらとなる。さらにもう10分ほど歩けば、右手に大きな赤鳥居が見えるはずだ。神社の多い京都でも指折りの古さを誇る、松尾大社である。
松尾大社は平安京が造営されるはるか以前からこの地に鎮座していたと言われる古社で、神体山である松尾山の麓に広がる境内には、重要文化財に指定されている1542年建造の本殿をはじめ、見どころとなる社殿やスポットが多い。

もし嵐山の人込みに疲れたとしたら、少し足を延ばして松尾大社を参詣してみてはどうだろうか。閑静な雰囲気の中で、落ち着いて古都の歴史を味わうことができるはずだ。
平安遷都以前からあった古都の地主神
京都の歴史は、桓武天皇が新しくこの地に造営された平安京に入った794年にはじまる──そう思われることが多い。
たしかに、「都」としての京都の歴史はそうである。そもそも、「天子が居住する場所」という意味をもつ「京都」という普通名詞がこの土地を指す地名となったのは、平安遷都以後のことだ。
しかし、平安遷都以前には、「京都の地」が未開の原野で、人がほとんど住んでいなかったのかというと、そんなことはまったくない。水の豊かなこの土地には、縄文時代・弥生時代から人が住んでいた。
そして、古墳時代・飛鳥時代・奈良時代と、時代をへるごとに独特の発展を遂げてきている。794年の平安遷都を基準に「京都1200年の歴史」などとよく謳われるが、じつは京都は、平安遷都を迎えるまでに長い前史を経ていたのだ。
そして人間が生活していれば、そこには必ず信仰というものが生じる。古代日本の場合で言えば、住民たちはその土地に根ざした神を崇め、祠をつくったり社をもうけたりして、その神を祀る。つまり、神社を創祀して、豊穣や幸福を祈った。このことを証言するように、京都市街地とその周辺には、平安京が出現する以前からの歴史をもつ神社がいくつも鎮まり、住民たちから手厚く祀られてきた。
今紹介した松尾大社や、賀茂川べりに鎮座する賀茂神社(上賀茂神社・下鴨神社)、洛北の貴船川沿いに鎮座する貴船神社などは、その代表的な例である。

龍穴という大きな穴が空いているという伝説がある
「あまり名前は知られていないが、じつは歴史はすごく古い」という神社もある。京都盆地北東部の岩倉には山住神社という小さな神社があるが、山腹に鎮まる巨岩を御神体としており、古代神道の磐座信仰のかたちを今なお色濃く残している。この神社のルーツはおそらく平安遷都以前にまでさかのぼるのだろう。これらの古社はいわば京都の地主神であり、そしてまた京都の守護神でもあるのだ。

巨石が御神体である
山城国と丹後国に根ざす知られざる古社たち
京都市街地を含む現在の京都府南東部は、明治維新以前は山城(山代、山背)国と呼ばれたが、目をこの山城国全般に向けるなら、平安遷都以前に歴史をさかのぼる「京都古社」の数はぐっと多くなる。とくに南部に多い。
たとえば、賀茂信仰のルーツのひとつに挙げられる木津川べりの岡田鴨神社や、やはり木津川沿いにあって、「居籠祭」という原始神道の面影を残すユニークな祭礼を伝える祝園神社などがそうだ。
また、京都南郊の宇治といえば、何といっても国宝の鳳凰堂がある平等院が有名だが、宇治川をはさんだ平等院の対岸には、応神・仁徳天皇の時代にルーツをもつ古社、宇治神社と宇治上神社が鎮座している。平安時代後期の建造とされる宇治上神社の本殿は、神社建築物としては現存最古のもので、鎌倉時代建造の拝殿とともに国宝に指定されている。

宇治上神社は川沿いに鎮座する
山城南部にこのような由緒ある古社が意外に多いのは、奈良時代までは北部(現在の京都市街地)ではなく、こちらが山城国の中心であったことが関係している。ちなみに、ほんの数年間だが、奈良時代には岡田鴨神社の近くに聖武天皇によって恭仁宮が営まれ、日本の都が平城京からここへ遷されていたこともあった。


また、京都府北部は古くは丹後国に属した地域だが、ここにも、平安遷都以前からの古い歴史を誇る神社は多い。浦島太郎伝説の原郷である浦嶋神社、伊勢神宮の元宮とする伝承のある皇大神社・豊受大神社や籠神社……。これらの古社は、『古事記』や『日本書紀』などともつながる豊潤な神話や伝説を伝えているところも大きな魅力だ。
日本の古層を知るもうひとつの京都巡り
これら「京都古社」の多くは京都の混雑エリアの外にあり、さほど観光名所化していない。したがって、ハイシーズンであっても、オーバーツーリズムに惑わされずに、自分のペースで参拝し、じっくりと旅をたのしむことができる。
しかも、これらの神社はいずれも京都の古層を形成してきた神社であり、平安遷都後の京都は、これらを土台にして発展をつづけたと言っても過言ではない。そして、京都の歴史は日本の歴史の真髄でもある。その意味では、京都古社は日本そのものの古層を形成してきたとも言えよう。
埋もれた京都の歴史に目を向け、古都郊外の山野にこだまする神々の声に耳を傾ける。そろそろ、そんなスローな京都旅に出かけてみてはいかがだろうか。
──本記事で紹介した京都の古社については、『京都古社に隠された歴史の謎』(古川順弘著、ウェッジ刊、2024年6月20日発売予定)の中で詳しく触れています。ただいまネット書店で予約受付中です。
<本書の目次>
第1章 京都の地主神をめぐる
宇治上神社、貴船神社、石座神社 他
第2章 賀茂神の軌跡をたどる
岡田鴨神社、久我神社、賀茂御祖神社 他
第3章 古都を育んだ渡来人の信仰
松尾大社、大酒神社、八坂神社 他
第4章 神話・伝説の舞台を訪ねる
葛野坐月読神社、籠神社、浦嶋神社 他
あわせて読みたい7冊
よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。
