
バーワンを齧りながら台湾新文学の父に思いを馳せる(彰化)|岩澤侑生子の行き当たりばったり台湾旅(3)
この連載は、昨年まで現地の大学院に留学されていた俳優の岩澤侑生子さんが、帰国前に台湾をぐるりと一周した旅の記録(2022年8月1日~9日)です。前回は、京都にあるご実家と所縁の深い台中のお寺を訪ねた岩澤さん。今回は、“台湾新文学の父”が生まれ育った彰化を訪ねます。行き当たりばったりの旅をぜひ一緒にお楽しみください。
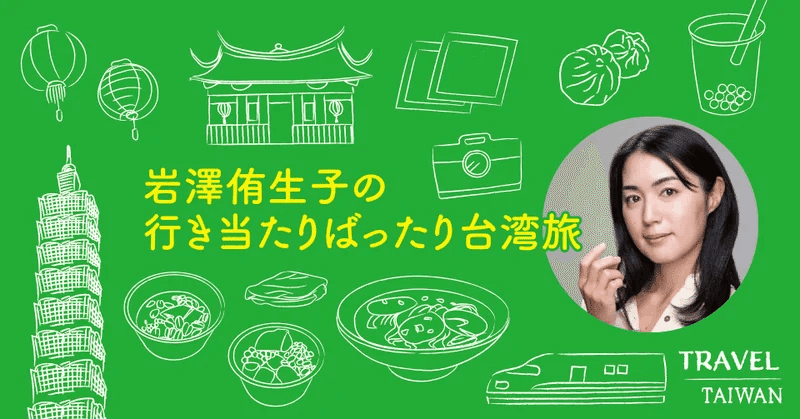
>>>第1回から読む
台中駅から台湾鉄道に乗っておよそ20分、台中に隣接する彰化に到着した。彰化駅は台湾鉄道の山線と海線の終着点。この旅で初めて降りた竹南駅から分岐した山線と海線が、ここで交差する。
駅の構内で「洪瑞珍」のお店を見つけたので、サンドイッチを購入。日本にもファンが多い「洪瑞珍」は、元は彰化で創業されたお店。ほんのり甘みを感じるサンドイッチは、シンプルなのに一度食べたらやみつきになる味だ。

彰化駅の観光スポットといえば、たくさんの列車が並ぶ扇形車庫が有名だが、まずは日本統治時代を生きた台湾人作家で、「台湾新文学の父」や「台湾の魯迅」とも呼ばれる頼和の紀念館へ向かう。大学院で日本統治時代の演劇の脚本や文学作品について研究したので、当時の作家たちについてもっと知りたくなったのだ。彰化駅から徒歩で東へ進むことおよそ15分、目的地に到着。早速扉を開けようとしたが、鍵がかかっている。

えっ、また休館日?(第1回目参照)。慌てて確認するも、ウェブページに休業のお知らせは出ていない。呼び鈴を鳴らしても、電話をかけても、SNSにショートメッセージを送っても、応答がない。諦めて帰ろうとした矢先、「ごめんなさい、トイレに入っていて呼び鈴に気が付きませんでした。今開けますね!」と連絡が入った。どうやら表の扉は常に開放されているわけではないようだ。
エレベーターに乗って4階へ。マンションのワンフロアが紀念館になっている。先ほど連絡をくれたスタッフの方がにこやかに出迎えてくれる。来訪者は私ひとり。訪問した理由を伝えると、顏がいっそう明るくなって、つきっきりで展示を解説してくれた。台湾では「○○を知りたいから教えてほしい」と素直に聞くと、惜しみなく知識を共有してくれる人が多い。そうした台湾人の優しさや思いやりに触れると、普段は遠慮がちで細かいことを気にしがちな自分も、おおらかな気持ちになれるから不思議だ。
頼和の反骨精神に触れる
「頼和は1894年にここ彰化で生まれました。日本統治時代が始まる1年前ですね。頼和の祖父は結婚式やお葬式で鐃鈸(シンバル)を打つことを生業にしており、父親は道教の道士でした。小さいころから台湾の古い風習や生と死の存在が、彼の身近にありました」
頼和は16歳のときに台湾総督府医学校に合格、その後医者になった。厦門(アモイ)の病院に勤務していたとき、中国の白話文運動*に影響を受け、台湾に戻ってからは台湾新文学(近代文学)運動や政治的な文化活動に関わった。
*白話文運動:1917年から中国(中華民国初期)で起こった、文語文(文語体)から白話文(口語体)への文体に関する改革運動。従来の文語体ではなく、民衆が読みやすい口語体を用いた文学作品で人々を啓蒙した。白話文運動は、1919年に発生した五・四運動(反帝国主義を掲げた全国規模の大衆・学生運動)とも結びつき、言語だけではなく、新しい文化運動への発展へと繋がった。
「1923年12月に治警事件*で収監された後も、頼和は積極的に執筆活動を続けながら、医師として多くの患者の命を救いました。貧しい人のために、無償で診療にあたることもあったそうです。しかし、1941年12月8日に再び投獄されると、約50日間を牢獄で過ごしました。そのときに記した「獄中日記」は、日本統治時代に生きる台湾人の苦しい心境を描いたものです。心臓病の悪化を理由に釈放されましたが、1943年1月31日に50歳の若さで亡くなりました」
*治警事件(治安警察法違反検挙事件):台湾人の政治運動を警戒した台湾総督府によって多くの知識人が検挙された事件。

(画像引用元:賴和文教基金會)
http://cls.lib.ntu.edu.tw/laihe/B1/b_12.htm

日本統治時代の始まりとともに生まれ、その終焉を待たずにこの世を去った頼和だが、日本語で書かれた作品もあるのだろうか。
「頼和は幼いころから漢文に親しんで、古典文学の素養もあったので、詩、小説、随筆など多岐にわたるジャンルの作品が残っています。ただ、彼は日本語教育を受けましたが、日本語で創作することはありませんでした」
植民地統治下の台湾社会の矛盾やそこに生きる人々の苦しみを描いた作家は、当時の「国語」であった日本語を使わずに台湾新文学の創作に邁進したという。
日本人が台湾の歴史を知る意味
台湾で日本統治時代の歴史を学ぶと、これまで知っていた歴史が少し違って見えてくる。聴講していた台湾史の講義で、台湾人の教授が語った言葉を思い出す。
「台湾の歴史を知らなければ、日本の近現代史を知ったとは言えない」
台湾の教科書には日本統治時代のことがたくさん書かれているけれども、日本の教科書ではどうだろう。ある時代を捉えるには、一方からみた歴史だけだと足りないのではないか。歴史を多角的に捉えるためにも、日本統治時代を生きた台湾人作家の人生や作品がもっと日本で知られるといいなと思う。
1926年に発表された頼和の作品「一桿『稱仔』」(日本語:一台の秤)が、2000年に台湾の高校の国語の教科書に掲載され、校外学習で多くの学生が頼和紀念館を訪れているそうだ。頼和紀念館を運営する頼和文教基金会は、彰化を「文学の街」にすることを目指し、頼和作品の出版のほかに、高校生向けの文学コンクールの創設や、頼和の作品に登場する場所をめぐる街歩きイベントなどを定期的に開催している。日本統治時代を生きた作家は、今も彰化の街で生きている。


時の流れを感じさせないくらい、綺麗な状態で保存されている。
彰化のローカルフードを食す
「修論頑張ってね!」とエールをもらい、紀念館をあとにする。小腹が空いたので、何か口に入れようと辺りを散策すると「肉圓」と書かれた看板が目についた。そうだ、彰化といえば「バーワン(肉圓)」だ。台湾のローカルフードのバーワンは、彰化が発祥と言われている。1898年に彰化県の北斗地方で発生した大洪水により食べ物が不足した際、寺廟にいた写字生が、さつまいもの粉をこねたものを被災した人々に分け与えたのが由来とされる。
「阿三肉圓」というお店に入る。お昼時を過ぎているのに賑わっている店は間違いがない。壁には「King of 肉圓 阿三」と書かれた張り紙。調べてみると、かつて台湾バーワンフェスティバルで一位を獲得した有名店だった。ぷるぷるのバーワンが次々と大きな鍋に入れられ、パチパチと音を立て油で揚げられていく。バーワンは地方によって味や作り方が異なる。彰化より北は油で揚げ、南は蒸すのが主流らしい。台北では筍が、彰化ではしいたけが入る。食べ比べてみるのも楽しそう。

外はパリッとしているが、中はもっちりとした食感。弾力ある皮に新鮮な豚肉、北海道産のホタテ、しいたけ、鴨の卵などが包まれている。噛むほどに食材のうまみが口の中に溢れてとても美味しい。これまでバーワンを特に美味しいと思ったことはなかったけれど、このバーワンを食べに彰化まで来る価値があるとさえ思う。
頼和もバーワンを食べたのかな、と想像する。互いに寄り添いながら食し人々をつなぎあわせた食べ物の記憶。日本統治時代に自分たちの言葉を通じて互いの存在を確かめ合いながら生きたその記憶。
食べ物も文学も、それを守り受け継ぐ人がいる限り、時代を超えて出会うことができる。
【参考文献】
財団法人頼和文教基金会『勇士當為義鬥爭』
陳芳明『台湾新文学史 上』東方書店(2015)
遠流台湾館 編著『台湾小事典 第三版』中国書店(2016)
赤松美和子・若松大祐 編著『台湾を知るための72章』明石書店(2022)
>>>次回に続く
文・写真=岩澤侑生子

岩澤侑生子(いわさわ・ゆきこ)
1986年生まれ。京都出身の俳優。京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)映像舞台芸術学科卒。新国立劇場演劇研修所7期修了生。アジアの歴史と中国語を学ぶため、2018年から台湾に在住。これまでCM、MV等の映像作品の出演や台湾観光局のオンライン講座の司会を務めた。2022年8月に淡江大学外国語文学院日本語文学科修士課程を修了し、日本へ帰国。
HP:https://www.iwasawayukiko.com/
Twitter:https://twitter.com/iwabon
▼この記事で紹介した場所
▼関連のおすすめ記事

最後までお読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは、ウェブマガジン「ほんのひととき」の運営のために大切に使わせていただきます。
