
5月1日 種まきなおし
タネのパッケージは裏面に育て方の概要が書いてあって、
詳しいことはQRコードの読み取り先見てね!って仕様になってる。
で、わたしのようなアホは概要の「ポットに種を撒く。」の文面だけ見て、
「あ~、撒く。…”撒く”、ね。オッケ~!」って感じで、
土の表面にタネを置いて、水をかけて、ヨシ!種撒きました!って
達成感なんか感じちゃったりしてね。
でもさすがにもう四半世紀生きてきてますからね。
「いや、種まきってなんか…、もっと埋めたりするよな……。」って
数日後に怪しみ始めたりしてね。
三日後になってようやく、QRコードを読み取って、詳細を見てみました。
埋めるじゃん!!!!!

あたりめぇだよ……。
てなわけでまき直ししました。
可愛いのがね、土もかけてもらえず地表で寒かったろうに、
キュウリがもうちょっと芽が出てた。
培養土がカップ数に対して少なかったので、
6カップ分は、うちの裏庭の土を入れているんだけど、
そこに”置いておいた”キュウリの種から白くて小さな芽が顔を出してて、
もうキュンキュンだよね。
キュンキュンしながら土かけて埋めたよね。さよなら……。
改めてゴマ、大根、ネギの上方も調べて、
詳しい育て方を手書きでメモ。勉強しました。
畑の間取りも考えました。
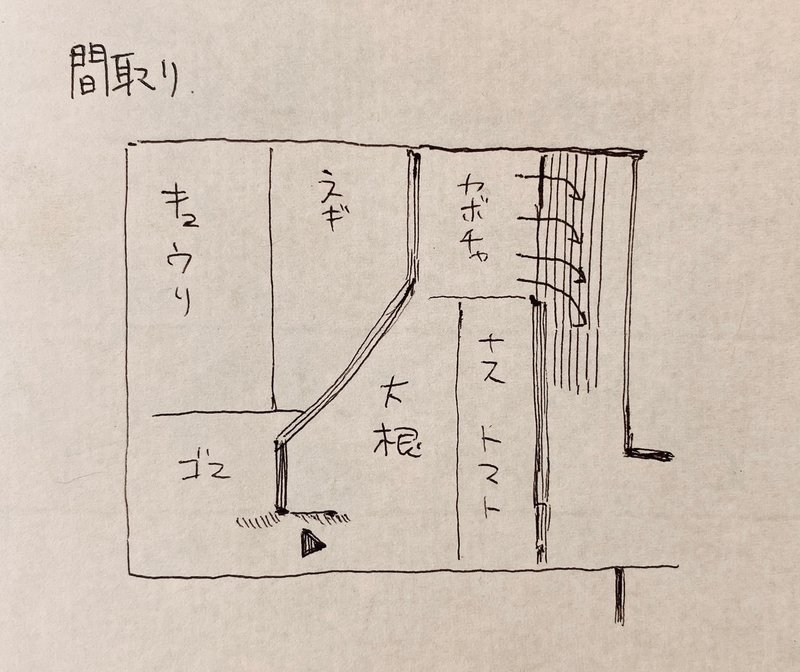
カボチャは、畝の横に敷き藁を敷いて、
蔓を伸ばしていきます。
そういえば多摩美の紙漉きの先生が、和紙の原料になる楮(こうぞ)を育てるついで(?)にカボチャを育ててたんだけど、そのカボチャも貯水槽(?)か何かの格子の上に蔓を伸ばしてた。
あの格子の天井が、敷き藁の役割を果たしてたんだなぁ。

土づくりも「株式会社トーホク」さんのサイトを見て、
バーク堆肥、苦土石灰、化成肥料を用意して行うことにしました。
ポット苗が育つ間に土づくりをやっていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
