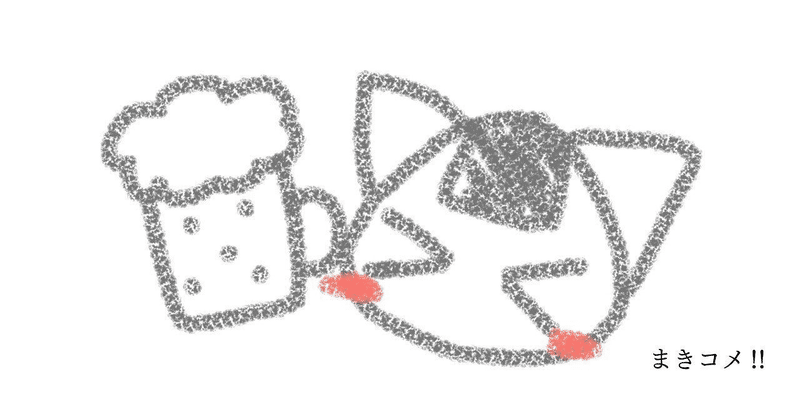
「上機嫌」はリーダーの最低必要条件
転職した3月1日以降、特に気をつけていることがあります。それは、常に「楽しそう」にすること。
組織マネジメントとプロジェクトマネジメント、どちらにおいてもリーダーが「楽しそうであること、上機嫌であること」は物凄い威力を発揮すると共に、プロジェクト成功の絶対的な必要条件だと信じています。
ヒトはコミュニケーション時に凄く色々考えている
13年間の社会人生活と4年間の大学体育会生活を振り返って思うのは、「ヒトはヒトにコンタクトするとき、本当に色んなことを考えている」ということ。
・眉間に皺寄ってるし、今日不機嫌なんじゃないか。
・いつもは挨拶あるのに今日は無かった。何かあったのかな。
・カレンダーがパツパツ。この時間は空いてるけど、考え事したいかな。
・プロジェクトも後半。こんな生煮えのアイデア持っていったら怒られるかな。
…etc
こういったことを「瞬時に」考え、判断し、その上でコンタクトします。もしくはコンタクトを諦めます。
これは「空気を読み過ぎる」と言われる日本人に限ったことではありません。コミュニケーションが生きる術の一つである人間として、大なり小なり行っている話であり、海外の会社の方がもっと露骨なケースも全然あります。
ヒトは基本的にはリスク回避的であり、ここに組織のヒエラルキーが組み合わされば、その傾向はさらに顕著になります。つまり、「コンタクトしようと思ったけど、しない」、というケースは日常的に起こり得る話なのです。
人によっては、上記事項などに思い当たる節があれば、すぐに諦めるかもしれません(後述のポイント次第で)。
リーダーへのコンタクト数が減ると、何が起こるでしょうか。組織・チーム全体の情報総量が減るのです。
情報の「総量」は物凄く大事
私は、冒頭の「楽しそうにすること」は結構出来ていると思います。でも、もう一つやろうとしていて、出来ていないことがあります。
それは「どんなに忙しくても忙しそうにしないこと」。でも、つい「やること塗れだ。。。」みたいなことを呟いてしまいます。ダメですね。
この2点は同じことを目的にしています。それは、「気軽に話しかれられる存在であり続けること」。言い換えると、「自分に入ってくる情報量、そして組織・チーム全体に流れる情報の量を極力最大化すること」が目的です。
これは、結果として「心理的安全性を担保する」ことと同義になっていきます。
山口周さんの「外資系が教えるプロジェクトマネジメント」に以下の記述がありました。
チームの中で流通する情報の量が減ると、必ずといっていいほど、プロジェクトは危険な状況に陥ります。
(中略)
失敗に終わったプロジェクトについて分析してみると、この「情報流通」に大きな問題があったことが少なくない……いやむしろ、失敗したプロジェクトでは必ず、何らかの形で情報流通に問題があったと筆者は考えています。
まさに、です。
膨大な情報から本質的で大事な情報を抜き取るのは「大変」ですが、共有されてない情報から正しく状況を把握するのは「不可能」です。
だから、優れたリーダーはオープンで、明るくて、そして聞き上手なのです。出来る限り、情報が出てくる蛇口が開いたままになるようにしている。
話が長いリーダーは効率が悪いだけでなく、「この人に1言ったら、10返ってくるのか。。。時間勿体無いからやめとこ」となるのが自然であり、蛇口が閉まります。
ファースト・ストライクを絶対に見逃さない
オープンで明るくて、楽しそうで、聞き上手だと情報が流れてくるようになります。声を掛けて貰えるようになります。でも、まだ大事なステップがあります。
それは、「あ、この人に言っても無駄なんだな」と思われないこと。周囲を見ていると、この「諦め」がとても多くの組織・プロジェクトを停滞させています。
折角リーダーに対して進言・提案をしても、そこで「全く聞いてもらえなかった」、「聞いてくれたと思ったのに、何一つ動いてくれなかった」と思ったら、どう動くでしょうか。
人間はこういう時とても合理的なので、「言っても無駄な人」カテゴリーにその人を押し込み、もう何もしなくなります。
その先にはどんな未来が待っているか。その業務に関する勉強をしない、心を押し殺して働く、転部・転職・副業に力を入れる、、、こういったチーム員が増え、チーム全体の温度が下がります。
そんなに人間何度もトライしません。1・2回だとしても全く不思議ではありません。だから、ファースト・ストライクは絶対に見逃してはいけないのです。
私の考える、ファースト・ストライクに対して意識すべきことは以下の2点です。
①その場でミニマム・コミットメントをし、それを絶対に実現すること
②Readyじゃなかったら、正直にその旨を伝えること
①は「言ってくれてありがとう。Aはやる。Aから先は約束できないが、頑張る。でも、Aは絶対にやるから」と伝え、期待値を揃えます。「言ったことをちゃんとやってくれた」、これが健全な信頼を醸成します。
②は、もし自分に余りに余裕がなく動ける状況でなければ、内容を聞いた上でしっかりとそれを伝えるのです。
緊急度によってはそうもいかないものもありますが、相手は「伝えた。きっとすぐ動いてくれるだろう」という期待を必ず抱くので、自分の状況を真摯に伝えることも時には必要です。それで「ふざけんなよ」と思う人は少ないと思います。
つまり、
・ちゃんと用意してバッターボックスに立ち、
・ちゃんと構えて、
・ちゃんとヒットを打つ(ホームランを狙ってもいいけど、それは宣言しない)
これがファースト・ストライクに求められるリーダーの姿勢だと信じています。
おわりに
偉そうに「リーダー論」みたいなことを書いてますが、まだまだリーダー新米です。特に日本では初めてのことです(ウクライナではそういう役割でしたが)。
ですが、私はリーダーというのは「そのうちリーダーらしくなる」という漸進的なものではなく、「なれる人はなれないし、なれる人はなれる」性質のものだと思っています。
なので「理想のリーダーに今日なること」を常に目指していきたいと思いますし、自分に適性がないと思えば、リーダーを諦める日が来るかもしれません。
こういうNoteも自分にプレッシャーをかける意味で書いている部分もあります。「なんや、偉そうに」と思われるくらいの内容を書いていきますので、これからもよろしくお願いいたします。
では、また来週。
細田 薫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
