
おすすめノンフィクション~「北方領土」、「密漁」、「カニ」
(こちらの文章は、今年2月に一度投稿したものを、再度、加筆訂正して
今回改めて投稿いたしました)
世界を騒然とさせた、ロシア、プーチン大統領によるウクライナへの侵攻が始まってから、およそ1年と半年近く経った。
電光石火の如く、ウクライナの首都キーウを制圧し、傀儡政権を樹立させるロシアの目論見は早々に破綻し、米国やNATO加盟国からの兵器供与で反転攻勢を強めるウクライナとの間で、戦況は双方一進一退の様相を呈している。
今後、劇的に状況が変化することはあるのだろうか。侵攻開始当初、米国とNATO加盟国が戦禍の拡大を危惧して供与をためらっていた主力戦車や、
F-16戦闘機も、なし崩し的に供与が決まり、対するロシアも兵士の消耗、
兵器の枯渇が叫ばれるるなかでの、窮余の一策が戦術核の使用にまでエスカレーションする事態は避けられるのであろうか。
我が日本も直接国境を接していないにせよ、自国領土の一部がロシアの実効支配下にあるという点ではウクライナと同じであり、今回のロシアによるウクライナ侵攻はまったく対岸の火事ではない。日本が対ロシア制裁、ウクライナ支援に参加したことによるロシアの反発は、予想されていたとはいえ、今後のサハリンでの液化天然ガスの権益を巡る協議や、長年両国の最大の懸案である北方領土の今後の見通しに暗い影を落とす。
その北方領土に関するノンフィクションの書物が未読のまま、自宅本棚に埋もれていたのを、今回のロシアによるウクライナ侵攻でふと思い出したことがきっかけで、読み出した。それがこの作品である。
「密漁の海で~正史に残らない北方領土」
2004年、本田良一(著者)、凱風社
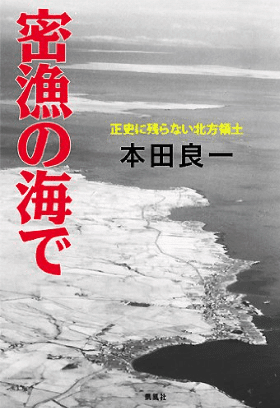
ロシアと領土の帰属をめぐる紛争が戦争の発端となったウクライナと同じく、我が国も戦後旧ソ連時代から続く北方領土問題がある。
地図をひろげれば一目瞭然だが、北方領土を構成する四島(歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島)は、根室海峡をはさんでオホーツク海上にそれぞれ連なっている。
日本は戦後一貫して、この四島を固有の領土として領有を主張し続けている。一方ロシア(当時はソ連)は1945年以降、"実効支配"を続けている。
この北方四島周辺の海域は、カムチャッカ半島沿いに南下してくる水温の冷たい親潮(千島寒流)の一部と、南から日本列島の太平洋沿岸を北上してくる水温の高い黒潮の一部とがぶつかるエリアで、この親潮と黒潮が混ざり合うことで海中のプランクトンが増殖して、これを目当てに多くの魚が集まってくる。
本書によると、根室沖から千島列島の西側は「世界三大漁場」に数えられるほどの水産資源の豊かな海域であり、カニ、ウニ、サケ、タラ、ニシン、ホタテ貝などの魚貝類の宝庫とある。
しかしその豊な漁場であっても、現実の北方四島及びその海はロシアの実効支配下にある。その豊富な水産資源は、日本側の、根室の漁業従事者だけでなく、対岸の北方四島側のロシアの漁業従事者にとっても生活の糧となる欠かせない海だ。
しかしその世界でも有数の漁場は、両岸の漁業従事者、日本政府(現地海上保安部)、ロシア政府(国境警備隊)、水産物の利権を巡り裏で暗躍する日ロ双方のアンダーグラウンド勢力が、複雑に組み合わさってせめぎ合いを繰り返した最前線でもあった。
本書は、その熱い北方の海にまつわる"密漁"、そしてソ連崩壊後に日ロ間で再び議題に上がった"北方四島の帰属を巡る両政府による熾烈な外交の駆け引き"を、北海道新聞の記者である著者が独自に取材をして、あらゆる角度から切り込んだ力作である。
・レポ船
レポ船とはつまりレポート船を略した呼び方で、日本側からの様々な情報を提供する見返りに北方四島のソ連側が実効支配する海域での操業が黙認される日本漁船のことである。
冷戦時代、ソ連側の国境警備隊と目と鼻の先で対峙する根室海峡は、ソ連との諜報戦の主な舞台のひとつであった。
本書の前半は、根室海峡をはさんだ北方四島の海域で、レポ船、根室海上保安部、公安調査庁、ソ連国境警備隊らが繰り広げる攻防の様子を、レポ船が組織化されてくる1960年から、80年代のソ連によるアフガニスタン侵攻によってレポ船を巡る風向きが大きく変わるあたり迄を、いろいろなエピソードを交えながら、その変遷を克明に描いている。
日ソ両国がそれぞれの立場で領有を主張し、未解決のままである以上、国境という境界線は存在していないが、実際的には根室海峡の中央を二つに分けた危険推定ライン(中間ライン)が双方暗黙の境界になる。
その中間ラインを境に根室側を"青い海"、北方四島側を"赤い海"と根室の漁業従事者の間では呼ばれていた。本書によると、ソ連時代、オホーツク海で操業するソ連漁船は遠洋漁業が主体で、北方四島沿岸の水産物は漁の対象となっておらず、その沿岸の"赤い海"は大型のカニ、ウニ、ホタテ、スケソウダラなどの水産物は手つかずのままで、根室の漁師の中で一攫千金を目論む強者にとっては宝の山であった。
時代は冷戦の真っただ中。赤い海で宝の山をものにすべく中間ラインを越えて操業しようとする日本の漁船と、それを取り締まろうとするソ連国境警備隊との接触は、本書によると「道内の自衛隊、米軍の動向」、「日本政府関係者、警察関係者の名簿」、「右翼などの反ソ団体動向や北方領土返還運動にかんする情報」及び当時のソ連では入手困難な日本製家電製品、タバコ、ウイスキーなどの嗜好品を提供する見返りとして、赤い海での操業を黙認してもらう「レポ船」の誕生へとつながっていく。
その後、レポ船は有力な元締の下、数隻のまとまった単位に集約されて組織化されていく。本書の説明では、70年代のレポ船最盛期には、一隻当たりの水揚げ額がおよそ三億円までになったこともあるという。
中間ラインを越えて赤い海で操業すること自体は、当初は違法行為として取締りの対象にはならなかったそうだが、冷戦下、本書曰く"最大の仮想敵国"であったソ連側と接触し、日本側の情報を提供する(レポ)行為は、日本の公安、警備当局にとっては国益に反する行為と見なされた。
しかしそのレポ行為そのものを処罰する"反スパイ活動法"のような法律が、日本にはない為、本書曰く、家電製品や嗜好品の提供は関税法違反、国境警備隊との接触は検疫法違反、赤い海での操業は漁業法の区域外での操業ということで違法操業(密漁)として摘発を進めたという。
ただ公安調査庁側も、北方四島周辺でのソ連側の国境警備隊、軍の動向やソ連側がどのような情報を求めているのかなどについての関心があり、ソ連側と同様にレポ船とは持ちつ持たれつの関係を維持していたという。これがこのレポ船の問題を複雑にしていく。
操業が日本側に摘発され、レポ船主、元締めは逮捕起訴される。それらの情報はソ連側へも伝わり、その船主、元締めはソ連側に警戒され、やがて切り捨てられる。すると他の有力な船主が後釜になり、その船主の下にレポ船組織は再編されていく。
ソ連側国境警備隊内でも、定期的に綱紀の引き締めが行われて、特定の船主との癒着が問題視されると、その船主は用済みとなる。これらソ連側の事情もレポ船再編に拍車をかけた。
1985年5月、ソ連はアフガニスタンからの撤退を開始する。時代は、東西冷戦の終結へとむかっていく。
1989年12月、ゴルバチョフソ連大統領とブッシュ米国大統領のマルタ会談において東西冷戦の終結宣言。そして1991年、かつてソビエト連邦を構成していた各共和国が連邦を離脱、独立によってソ連は崩壊する。本書では、この同じ年に、北の国境の海で、冷戦下、時代に翻弄されたレポ船の最後の一隻が姿を消したとある。
・特攻船
冷戦が終結し、ソ連が崩壊しても、カニなどの水産物が豊富なのは、海峡の中間ラインの先にある、かつての赤い海にであることに変わりはない。レポ船が消えた後、入れ替わるようにその水産物を狙って、国境の海で台頭し始めたのが特攻船だ。
本書の説明では、特攻船自体は、まだ冷戦下、レポ船が暗躍していた時代から、レポ船の組織にも加入できない「不良漁民」たちで形成され、赤い海に進出して、ウニやカニが生息する特定の場所で、密漁をしていた。
10トン以上の延縄船、引き網船、刺し網船などが主体のレポ船と異なり、特攻船は2~5トンの小型FRP船に高馬力の船外機2基を装着して、40~50ノットの高速で、中間ラインを越えて、北方四島周辺の沿岸で密漁を行い、ソ連の警備艇に発見、追跡されると一目散に中間ラインの日本側へ逃げ込む。
レポ船のように、ソ連側と持ちつ持たれつの関係などない特攻船は、ソ連の実効支配地域で意図的に密漁を行う確信犯であり、ソ連の警備艇も特攻船を見つけ次第、容赦なく追跡、拿捕しようとする。
本書によると、主にウニが密漁の対象で、一回の密漁で100万円ほどの水揚げに達するという。もともとは、根室一帯を活動拠点にしていた指定暴力団の二次団体が、配下の組員を使って密漁を行っていたところ、その稼ぎの大きさを聞きつけた他の指定暴力団の傘下団体も進出してきて、1980年頃には人口約4万人程度の小さな根室市に、多くの暴力団が事務所を構えたという。
根室の海上保安部や地元警察署も、手をこまねいているわけではなく、一時はヘリコプターも投入して、特攻船の摘発を強化したが、細長い根室半島の海岸線は、正規の漁港以外でも密かに船を泊めて、陸上に待機しているトラックへ密漁したウニを届けることができる場所が多いらしい。
またたとえ摘発できたとしても、本書によると、適用される罰則は漁業法の無許可での操業にかんするもののみで、略式起訴で1万円程度の罰金で済む。よっていくら摘発してもまた密漁に戻ってくるようで、まさにいたちごっこである。
さらに本書は、当時特攻船が無くならない背景として、根室側に特攻船を"擁護"する空気があり、それはレポ船のようにソ連側と通じているわけでもなく、日本が主張するところの「領土内」で、漁を行い、その水揚げは根室を潤しているではないか、というものらしい。
本書は、1980年代後半にレポ船が衰退し、特攻船が根室の漁業や経済にとって欠かせない存在になっていく様子を克明に描いている。
もともとは暴力団系の特攻船が主体であったが、1986年、ソ連政府による北方領土海域内の三角水域での全面禁漁によって、操業可能な漁場が減った結果、行き場を失った漁船員が特攻船に乗るようになり、その数は全体の半数以上を占めるようになる。また、この頃から特攻船の密漁対象がウニからカニへと変わっていく。
1990年の特攻船による密漁での水揚げ金額の全体は、推定で30~40億円にまで達し、さらに本書の説明では、根室市内の他の産業(船の艤装品、通信装置、燃料その他)への波及も合わせると、その経済波及効果はなんと100億円産業までの規模を誇ったという。
ソ連側は、政府を通した正式な外交ルートで、特攻船の侵入、密漁行為を抗議する。しかし、本書によれば、ソ連側は日本政府が意図的に特攻船をソ連側の実効支配地域に侵入させて、間接的に日本の主権を主張しているのでは?と疑心暗鬼になるほど、外務省は反応が鈍かったらしく、外務省からすれば、ソ連側の主張はソ連側の領有を前提としたものである以上、それにまともに対応すればソ連側の領有を認めてしまうことになる、という警戒感が外務省側に終始一貫してあったという。
しかし、そんな膠着した状況を動かす転機がやってくる。本書の表現では、それまでの日ソ関係が、大きく変わるきっかけになったゴルバチョフの訪日である。
・特攻船の終焉
冷戦下、社会主義体制を維持して、一党支配をつづけたソ連共産党も、アフガニスタンへの介入失敗、深刻な経済の停滞で行き詰っていく中、1985年共産党書記長に選出されたゴルバチョフによるペレストロイカ政策は、やがてグラスノスチへとつながり政治の民主化へと発展していく。
1991年4月、ゴルバチョフは共産党書記長及びソ連大統領として来日する。本書の説明では、改革によるソ連の混乱とこのゴルバチョフ来日は、1973年の日ソ共同声明以降、停滞している北方領土問題を進展させる千載一遇の機会だと、日本政府側はとらえたとある。
このゴルバチョフ来日の予定が具体的になり始めた前年の1990年6月頃を境に、今まで特攻船問題の解決に冷淡だった外務省や、地域経済への影響を憂慮して及び越しだった根室海上保安部や警察も本腰を入れて特攻船の撲滅を考えるようになったそうだ。長年日ロ両国の間で進展がなかった領土問題の協議再開の見通しの芽が出そうな微妙なこの時期、特攻船問題はのどに刺さった魚の骨のようなものだったのであろう。
特攻船が実際に海上で操業ができないようにする法改正や罰則規定の強化が図られた他、本書によると一番効果的だったのが、特攻船に装着する船外機のながら販売元であるヤマハ発動機への行政指導だったとある。
本来、レジャーボート用の200馬力船外機を特攻船に装着すると知りながら販売することは「密漁幇助罪」にもあたる可能性を示唆しながら、根室やその近隣の地域で200馬力の船外機の新規販売、修理作業を控えることをヤマハ発動機側へ要請、最終的に応じさせた。
このあたり、たとえ社会倫理に反していたとしても、直接法に触れなければ、その後社会的に糾弾され、企業イメージに影響がでる直前まで、徹底的に利潤を追求するのは、バブル期の金融機関の例をあげるまでもなく、企業にとっては至極当然の商行為で企業活動なのであろう。
前にも述べた通り、根室にとって特攻船は100億円の経済波及効果をもたらす一大産業であった。この国を挙げての取締りで、これまで特攻船のおかげで隆盛を極めていた根室の経済、特にカニに関連する産業全体が大きな打撃を被った。しかし領土問題の協議再開を目論む国の意向の前に、特攻船の摘発は続けられた。根室の窮状を訴える声も届かなかった。
1991年4月16日、ゴルバチョフが来日する。この時点で、かつて最盛期には36隻あった特攻船は、一部の暴力団系の船を除いて、本書によると事実上消滅した。
東西冷戦の落とし子ともいうべきレポ船及び特攻船が、冷戦終結とともに姿を消したのは必然の運命であったのだろう。国境が存在しているようでしていない、しかし他国に実効支配されているいびつな状況で、活路を見出さざるをえなかった根室の漁業者のおかれた過酷な環境が窺い知ることができる。
この後本書は、崩壊したソ連から新生ロシアに引き継がれた、北方領土返還交渉を巡る日ロ両国のそれぞれの物語を軸に話が展開していく。
・異能の外交官とソ連崩壊
1991年1月に起こったリトアニアの血の日曜日事件は、軍事介入したソ連及び介入を"承認"したゴルバチョフ大統領のイメージを失墜させた。
この混乱のさなか、現地で情報収集に奔走していたのが、後に鈴木宗男衆議院議員(当時)とスキャンダルに連座して逮捕される、当時モスクワ大使館三等書記官だった佐藤優だった。
本書によれば、佐藤は情報の収集だけでなく、事件の当日、独立か従ソかで揺れたリトアニア共産党内の対立にも、モスクワの日本大使館へ相談なしに、独断で深く関わって、リトアニア共産党が分裂し衝突する事態を未然に回避するうえで一役かったとある。現地大使館の一担当書記官の枠を超えた奮闘ぶりがうかがえるエピソードである。
このあたりから後の橋本内閣から始まったロシアとの北方領土問題を巡る交渉の陰で、"異能の外交官"と呼ばれたほどの光彩陸離たる活躍が始まると同時に、一方の”異能の叩き上げ政治家"である鈴木宗男に深く関わり、共にスキャンダルで失脚する萌芽も芽生え始めているように思える。
その後同年8月、ソ連共産党や軍部の一部保守派らによるゴルバチョフ打倒クーデター未遂事件から、ゴルバチョフが主導した新連邦条約のとん挫、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ三国の首脳同士で合意、署名された「独立国家共同体(CIS)」発足、そしてソ連邦崩壊へと続くまでの舞台裏を、著者は主要な関係者へのインタビュー内容も交えて、詳細に綴っている。
ソ連邦を維持して自らの権力維持を図ろうとするゴルバチョフは、ライバルであるエリツィンロシア共和国大統領の裏面工作によって結果的に梯子を外された形になり、敗北するに至る。歴史的な重要局面での政治的駆け引きの切所は、主要登場人物の寝技で動く。これは日本の政治だけではく、国際政治でも同じようだ。
ここでもウクライナが重要な位置を占めている記述がある。「ウクライナは、ソ連邦内でのロシアに次ぐ第二の規模の大国で、新連邦条約にせよCISにせよ、ウクライナ抜きではありえない」。ゴルバチョフやエリツィンにとっては、ウクライナを取り込めるかどうかが勝敗の帰趨だったようで、今のプーチンにしてもウクライナを西側から死守することが、ロシア大統領としても、また彼個人がロシアを支配する権力を維持する上でも、絶対に死守しなければならない生命線である。
・市場経済の導入とカニの密輸
物語は再び国境の海に戻る。東西冷戦は、ソ連邦の崩壊で幕を下ろしたが、国境の海では、根室の漁船と今度はロシアになった国境警備隊とが対峙する構図は変わらない。しかしソ連が実効支配をしていたころとは、様子が全く異なる。
相手がまだ社会主義国の頃は、レポ船はソ連側へ西側の情報を与える見返りに、中間ラインを越えて、ソ連側が領海を主張する海域での操業を黙認されていたが、ソ連が崩壊し、民主化、市場経済化へ移行したロシアでは、情報の代わりに今度はカネである。
ここから本書は、日ロ双方のアンダーグラウンド勢力や漁民、ロシア国境警備隊とが複雑に絡み合いながら、国境の海をはさんで繰り広げられるカニなどの水産物の密輸のエピソードが語られる。
前述したように、ソ連時代、極東や北方四島に拠点を置くソ連側の漁業は遠洋が主体だった。そのため北方四島周辺の浅い海域の水産資源は、根室の特攻船などによる密漁以外は手つかずのままであった。
ソ連崩壊後、新生ロシアでの市場経済導入後の混乱は、北方四島を含む極東地域全体を経済的に孤立化、疲弊させた。そんな中、カニなどの水産物を日本へ密輸することは外貨を手っ取り早く稼ぐ方法となる。
本書によると、 カニ、ウニなどを日本側へ密輸する場合、洋上で日本の漁船がロシアの漁船から受け取る方法と、ロシアの運搬船に洋上でロシアの漁船が水産物を渡して日本の港へ運搬船が入港後、密かに陸揚げして闇のルートへ流通させる、二通りが主な方法だったという。
いずれのやり方も、洋上でロシア国境警備隊に臨検、摘発のリスクがあるが、事前に様々なルートを通じて国境警備隊に接触して、摘発を免れるようにわたりをつけておく。
道内の港で水揚げされたこれらの密輸水産物は、本書に何度か登場する根室市内を拠点とする某広域暴力団参加の組や、道内の他の広域暴力団系列のフロント企業である水産業者を通して、それぞれ闇のルートを経由して、最終的に正規の販売ルートに乗る。
レポ船が暗躍していた時代に、ソ連支配の海域で獲れた「赤いカニ」と、日本側の「青いカニ」が、様々な仲介業者を経由して、最後に正規の業者の水槽で一緒になり、全国の販売ルートに乗るのと同じ構図である。
特攻船が壊滅して、水産物の激減で打撃を受けた水産業者にとって、これらは特攻船に代わる水産物ルートの復活となった。
当初は北方四島側の漁民が、個々にカニなどを細々と密輸してカネにしていたが、やがて密漁から国境警備隊の取り込み、密輸までを組織的に取り仕切る水産マフィアが幅を利かせはじめて、日本側の暴力団と独自のルートで結びつき、"密漁ビジネス"を形成していく。
市場経済に移行した後のロシアにおいて、根室は北方四島から、カニ、ウニ以外の他の水産物の輸入も次第に増えていき、根室の経済は再び活況を呈していく。
この活況に一役買っている、ロシア水産マフィアと日本の暴力団の密輸ビジネスは、一方では北方四島のロシア側の漁業関係者、国境警備隊や税関関係者の"懐"も潤した。そしてその金で購入した日本の家電製品、生活雑貨、野菜などの食料品が北方四島に出回る結果となった。
・北方四島の日本化から返還交渉再開
北方四島と直接交易を認めない日本政府の建前とは裏腹に、密輸を含む水産物を介した北方四島との経済交流は拡大していく。その流れに目をつけた日本政府・外務省は、1997年以降「北方四島の日本化」という戦略の下、領土返還交渉の土台作りを模索していくが、皮肉にも、それらは後の外務省を揺るがした鈴木宗男衆院議員のいわゆるムネオスキャンダルへつながっていった。
本書はここから、ロシアとの平和条約締結の前提となる北方領土の返還を巡る外務省を含めた日本政府内の熾烈な駆け引きに焦点が移っていく。
1994年10月に発生した北海道東方沖地震で、大きな被害を受けた北方四島への日本の人道支援から話は始まる。支援によって北方四島との交流を更に緊密化して、将来の領土返還交渉の足掛かりにしたいと日本政府は目論む。これらの支援活動は、後に問題となる外務省の"支援委員会"が主要な役割を果たした。
第二次橋本内閣(1996~1998年)においてのグラスノヤルスク合意から川奈会談までのいきさつを、本書は詳細に描いている。著者も取材で同行していたようで、橋本、エリツィン両首脳と日ロ政府高官の間で行われた交渉を巡る描写は、とても臨場感があふれている。
ソ連崩壊による混乱が続き、市場経済への転換も思うように進まないなかで、日本を含む主要先進国から支援を模索するロシアに対して、1956年の日ソ共同宣言以来、長年の懸案である領土問題での進展を目論む橋本内閣にとっては、千載一遇の機会到来だったのであろう。
領土返還に関するロードマップを文章化して、返還への道筋をつけようとする日本に対して、まかり間違えば第二次世界大戦での戦勝で得た領土を譲り渡そうとしていると、国内保守派から攻撃をうける恐れを抱えているロシアが、たやすく言質を日本に与えるはずもなく、日本側からすれば満を持して行われた川奈会談も、日本側の期待した結果にはならなかった。
日本側へ歩み寄ろうとするような素振りを見せるエリツィンと、後にロシア側が不利になるような言質を与えさせないよう、エリツィンの手綱をしっかりと握る硬軟織り交ぜた対応をするロシア政府高官に、結果的に日本側は手玉にとられたような印象だ。
日本側は、単に1956年の日ソ共同宣言に遡及して、それとの整合性だけを背景に、ロシア側へ"進展"を迫っているに過ぎず、会談でいくら日本側が「いつ返還するかは置いておいて、国境線だけでも引かせてほしい」と頼んだところで、ロシア側からすれば本質は"領土を譲渡する"という美辞麗句なだけで、領土を実行支配している"力"に対抗できる"もう一方の力"には到底なりえない。
外務省の思い描いたシナリオは、「ロシアへ施政権は認める」が「日本化がすすんで北方四島が日本側の経済圏に依存」していくと、「いずれ柿が熟して落ちるよう」に北方四島は日本のものになるというものらしい。
相手は、ルールではなく力で国民を、周辺の連邦諸国を抑えていた共産党独裁の時代から、冷戦終結、ソ連崩壊、新生ロシア誕生までの激動期を、"権力"を巧みに操りながら生き残ってきた連中であることを思えば、そのシナリオは甘いと言わざるを得ない。
ロシアとの交渉の本質を一番理解していたのは、国境の海で、ある時はレポ船で、またある時は特攻船で、常に力の脅威にさらされていた根室の漁民ではないだろうか。
・川奈会談後と二島先行か四島一括返還か
1998年7月の参院選で大敗し、退陣した橋本内閣の後を継いだ小渕恵三内閣は、同年11月に訪ロ、クレムリンでエリツィン大統領と会談する。
先の川奈会談での日本側の提案(ロシア側へ施政権の付与・国境線の画定)へのロシア側の反応が最大の懸案だった。
本書はこの辺りで、先に登場した"異能の外交官 "と呼ばれた外務省職員の佐藤優について、数ページをさいてエピソードを伝えている。佐藤は小渕首相の訪ロに先立って、外務省内において課長職に相当する「主任分析官」に任命され、自ら人選した省内の若手、中堅8名で構成する特命チームの長となる。
特命チームは外務省の欧亜局長に直属し、任務は本書曰く「川奈提案へのロシア側の本音」、「エリツィン大統領の健康状態」にかんする情報収集とある。佐藤のロシア人脈とリトアニア動乱、ソ連の保守派クーデターの際に発揮した卓越した情報収集能力が買われたのであろう。
しかし、ロシア側は日本側の提案に対して、本書曰く「ゼロ回答」、それに対して日本側は「唖然とする」とある。まさしく醜態をさらしたわけである。
本書このくだりを読んでいて疑問に感じたのが、このロシア側の回答を佐藤は事前に把握できなかったのであろうか。日本側からすれば進展が提案に前向きな回答が見込めない以上、首相自ら訪ロして会談する意味がない。またロシア側も進展が見込めないのなら、訪問を受けても仕方ないはずだ。
本来、日本側が期待する回答が困難であれば、いくらロシアの外交がソ連時代から譎詭に満ちていたとしても、非公式のルートを通じて、佐藤あたりに伝達して、会談を見送らせるのが常識なのではと思う。
それとも前向きな回答が用意されていたが、小渕首相がモスクワ到着後のギリギリの段階で、何らかの事情でロシア側が態度を翻したのだろうか。もちろんこの辺りのやりとりは、非常に両国にとっても微妙な部分ゆえ、随行した記者団にも窺い知ることが困難だったのかもしれないが、舞台裏で起こったであろうドラマが知りたかった。それにしても、これに関して言えば日本の外交は真っ正直過ぎるように思える。
1999年12月31日にエリツィン大統領が電撃辞任、翌年の2000年4月には小渕首相が脳梗塞で帰らぬ人となり、森喜朗が後継総理となり森内閣を発足させる。グラスノヤルスクで合意した平和条約締結は、目標年である2000年のを迎えた。
同年の9月、ロシアではエリツィンの後継として、プーチンがロシア第二代大統領に就任、本書の解説では、プーチンは1956年の日ソ共同宣言の有効性は認めるが、国境線の策定を盛り込んだ川奈提案は拒絶する。
ここから本書は、日本政府内で意見が二つに分かれた、北方領土の返還に関しての「二島先行返還」か「四島一括返還」かについて、いろいろな政府関係者のエピソードを踏まえながら、話を進めていく。
冷戦時代は、北方四島の主権及び施政権はひとつにひっくるめて、日本側にあることを日本政府は主張し続けていたが、ソ連崩壊後、ロシアと行った幾度かの首脳会談で、四島の主権を日本側に認めてくれるのであれば、施政権の返還に関しては、実情に即して柔軟に対応する段階論が主流となる。
「四島一括返還」はこの段階論の枠の中にとどめておけるが、「二島先行返還」は、本書の説明では、二島(歯舞、色丹)の主権及び施政権を同時に日本へ返還、残りの二島(国後、択捉)は将来的には返還を目指して協議を継続するというもので、四島の主権を一括で求めるのではなく、色丹・歯舞と国後・択捉とに主権を二つに分けているところが特徴である。
この「二島先行返還」を強く主張していたのが、当時釧路、根室の選挙区を地盤としていた鈴木宗男衆議院議員だった。
本書では、2000年8月に行われた当時の日ロ議員連盟主催の総会の席で、招かれた著名な専門家が行った北方領土に関する講演を巡るエピソードを紹介している。その専門家の講演内容は「四島一括返還」を軸にしたものだったようだが、講演が終わるやいなや出席していた鈴木議員は、専門家に対して因循であるがのごとく強くなじり詰め寄ったとある。
鈴木議員は、何かしら意図するものがあってそのような行動にでたのかもしれない。「叩き上げの政治家」としての面目躍如たる場面であるが、本書の表現では「異様な光景」であったらしい。あくまで講演会であって、議論する場ではないと鈴木議員はたしなめられ、その場はおさまったとある。
叩き上げゆえ行動は強引かつ拙速なのは理解できても、政治家であるならば場の空気を読む(尊重する)ことはある程度必要であろう。周囲の人間には、政治家というよりは人としての視野が狭く、余裕がない印象を与えたのではないだろうか。このあたり、後に政敵に足元をすくわれ、スキャンダルで失脚する遠因がうかがえるような気がする。
・プーチンの反応
2000年に大統領に就任したプーチンも、平和条約締結後、二島(色丹・歯舞)を返還する1956年の日ソ共同宣言の有効性は"口頭"で認めつつも、日本側が二島返還で具体的に詰め寄ってくると、言葉を曖昧にして先延ばしするこれまでのロシア側のやり方を踏襲する。
何度も繰り返すように、北方領土を実行支配するロシアにとっては、領土での妥協は、いくらそれに相応する経済的な見返りが期待できても、国内の反発を招く。また日本以外、領土での紛争を抱える周辺国からも同様な要求をされるリスクを招く。日本は過去の日ソ共同宣言や東京宣言での合意に遡及ばかりして、「四島一括返還」か「二島先行返還」か、もしくはそれらを足して二で割ったような「同時並行協議」とか、やたら法的な、文書の整合性ばかりを追求して、肝心のロシア側の深刻な内情についての認識を深めようとしないような、そんな印象をぬぐえない。
本書で「ロシア外務省には明確な対日戦略はなかった。それはロシア外務省の官僚には、荷が重過ぎる問題であり、自分の考えをあえて提案して、自ら責任を取ろうとする人間もいなかった」とある。これは日本の外務省の官僚にもあてはなるであろう。また「ロシア国内では、1956年の日ソ共同宣言の存在さえ、よく知られていない。またそれを国民に周知することもしてこなかった。ここでプーチンが二島返還を容認した、となればロシア国内の保守派は強く反発するだろう。プーチンはそれを懸念した」。これが北方領土問題の本質だと思う。
・外務省の分裂と鈴木、佐藤の独走
「二島先行返還」か「四島一括返還」かで外務省は分裂した。本書によると省内では、「四島一括返還」が従来通りの主張であり主流であった。「二島先行返還」では二島の返還だけで終わってしまうのではないかとの危惧が「四島一括返還」派には根強く、「二島先行返還」派は少数派であった。
しかし少数派には協力な後ろ盾があった。急逝した小渕恵三の後を継いだ森喜四郎首相である。森は「二島先行返還」を念頭に、再びプーチン大統領と会談する腹積もりでいた。
その森内閣を頂点に、当時の鈴木宗男衆議院議員、東郷外務省欧亜局長、そして佐藤外務省主任分析官が「二島先行返還」の一つのラインとなって、一方の省内の「四島一括返還」派と鋭く対立するようになる。
佐藤は、外務省内ではいわゆるノンキャリアで、先の冷戦終結、ソ連崩壊の激動期、現場での卓越した情報収集能力も、キャリア職員の陰にかくれて日の目をみなかった。
そんな鬱屈した佐藤は、本書によると1991年ごろ、当時外務省政務次官でモスクワを訪問した鈴木と面識をもつ。親の地盤を引き継いだ二世議員ではなく、また官僚出身のエリート議員でもない、本人曰く叩き上げの鈴木と、佐藤は馬があったのだろう。以後、鈴木のロシア、旧東欧諸国への訪問には佐藤は毎回同行するようになる。
鈴木は佐藤に、外務省から派遣された通訳兼お世話係以上の信頼を寄せていた。その後、佐藤は鈴木の関係を足掛かりに、外務省内での存在感を徐々に増していく。そして森内閣の意向と鈴木の影響力を背景に、省内での「四島一括返還」派を排除していく。本書曰く、この間の情景が省内で「恐怖のスターリン支配」と呼ばれて、佐藤は一時期、局長の東郷もしのぐ隠然たる力を持っていたようだ。
2000年12月25日に、「二島先行返還」を推し進める鈴木-東郷-佐藤ラインは、モスクワを訪問し、プーチン政権のナンバー2であるイワノフ国家安全保障会議議長と会談する。その会談で、翌2001年3月に予定されているプーチン、森会談を見据えて、「二島先行返還」に関する内容の非公式メモを渡したとある。
本書を読んで驚いたのは、この会談を、その当時の外務省ロシア課長はまったく知らされていなかったそうだ。このロシア課長は「四島一括返還」派と見なされていたためだという。またイワノフとの会談も、局長である東郷は出席せず、鈴木と通訳の佐藤のみで臨んだとある。
このあたり、「二島先行返還」にかける鈴木、佐藤の意気込みまさに天を衝くといった感がうかがえるが、この二人が後にスキャンダルに連座して失脚していく流れを思うと、このイワノフ会談あたりが鈴木、佐藤両氏の運命の峠であったように感じる。
2001年3月の森、プーチンのイルクーツク会談では、結局日本側の「二島先行返還」案に対して、プーチンは"継続協議"という言葉で巧みにかわして、日本側の期待に応えなかった。
同年4月、首相の森は、漁業実習船「えひめ丸」事故を巡る失態やその他一連の失言騒動による内閣支持率の低迷、世論の強い批判で退陣、入れ替わって同じ森派の小泉純一郎が首相に選出、小泉内閣が発足する。それは外務省内で「スターリン支配」とまで称されて、「四島一括返還」派から忌み嫌われた鈴木、佐藤を照らし続けた陽ざしが、陰り始めたときでもあったのだろう。
・「四島一括返還」派の反撃
本書によると、小泉は森派所属だが、森と違って当初から「二島先行返還」には懐疑的であったとある。
外務大臣に任命された田中真紀子も、従来通りの「四島一括返還」の立場から、鈴木らが進める「二島先行返還」には否定的で、外相就任会見の席ではその見直しも示唆した。
本書に解釈では、父角栄の田中派を乗っ取った経世会に所属し、会の重鎮である野中広務の威光をバックに、強引な手法で「二島先行返還」を推し進める鈴木への強い対抗心があったという。小泉にしても、出身派閥の清和会時代から、長年経世会と対峙してきただけに、鈴木のやり方に反感を強めていたとある。
とは言っても、小泉は首相として、外交の継続性は尊重したようで、2001年7月のジェノバサミット、10月の上海APECで立て続けにプーチンと会談、森前首相の時と同じ「二島先行返還」に加えて、国後・択捉の帰属も同時に協議する「同時並行協議」を提案、本書曰く、プーチンは"口頭"で同意したとある。
しかし、領土で妥協することは国内の反発を招き、周辺諸国へも波及する状況は変わってない以上、それ以上の進展は望めるべくもなく、その後は、川奈会談後と同じく、言葉の解釈、整合性をお互いが主張しあうだけの協議に終始する。
キューバ危機で、かつてのソ連と対峙して、最終的に妥協を引き出した米国の背後には巨大な軍事力と大量の核兵器が存在した。ソ連がアフガニスタンから撤退したのは、一万人以上の戦死者を出し、自らの経済的苦境の一因となったからだ。背景には実質的な力の増減が、大きく影響しているからだ。これが国際政治の現実である以上、外務省の「整合性」と「期待」だけではロシアは決して動かない、その現実を直視すべきだったのではと思う。
・ムネオスキャンダル
ここで思わぬ事態が、外務省を襲いかかる。2001年4月に就任した田中真紀子外相と事務方との対立が、数々のトラブルを引き起こし、外務省内は迷走の末、2002年1月に田中本人と事務次官が更迭されるまで、本書曰く、省全体が「機能停止状態」に陥る。これらの騒動が、後のいわゆる「ムネオスキャンダル」へ発展していく。
この間小泉内閣は、これまで橋本、小渕、森内閣で進められてきた「二島先行返還」から、従来通りの「四島一括返還」へ再び転換する。本書はここから最後まで、小泉政権下でのこの政策転換とムネオスキャンダルのエピソードを織り交ぜながら話を展開させていく。
ムネオスキャンダルに関して言えば、本書に詳述されているような事は、事実として実際あったのであろう。しかし、それらの事は自民党系の議員であれば国、地方のレベルに関係なく、自分たちの選挙区内の講演会や業者との「日常的なかかわり」のなかで、ごく普通にある「接触」のようにも見えるし、通常であれば「ただそれだけのこと」ですむ話だったのであろう。
しかしそれらが「政治」の中で、周辺の人間の「事情」「利害」、そして「憎悪」が絡んだ場合、そのひとつひとつが白日のもとに晒され、やがて一連の政治事件へ変化していくのではないか。政治スキャンダルと言われるもののほどんどは、この類のものだと私は思う。
ただそれにしても、鈴木はいろいろ「やり過ぎた」のだろう。本書では「強力な支援と恫喝」という表現で、鈴木が巧み外務省に貸しをつくり、官僚に人事面での恐怖を与えながら影響力を強めたエピソードが書かれてある。
本書では、鈴木は北海道十勝の開拓農家に生まれ、大学を卒業後、地元選出の中川一郎元農水省の秘書から身を起こした。親の地盤を引き継いだ二世議員や官僚出身の政治家のように、何らかの力の背景があったわけではない。
スキャンダルに連座して、有罪判決を受けた佐藤も、外務省内ではいわゆるノンキャリアであり、キャリアが要職を占める中央省庁では、いくら世界各国の情報機関を出し抜いて、極秘情報を入手する敏腕ぶりを発揮しても、それが正当に評価されて昇進に反映されない環境でくすぶっている時代に、鈴木の目に留まり重用されたことは、一気に鬱懐が晴れる思いであったであろうことは想像に難くない。
そんな二人が、外務省を二分する政策の、一方を担いで、たとえ時の内閣の後押しがあったとはいえ、推し進めていくやり方には、本書を読んでいてどこか無理を感じる。その無理を二人とも承知していたのかもしれないが、「四島一括返還」派の向こうに、鈴木にすれば二世議員や官僚出身のエリート議員の、佐藤はキャリア官僚の姿を見て強烈な対抗意識を抱いていたのではないであろうか。それがひいては彼らの視野を狭めさせ、ごり押しを続けた結果、無用の敵をつくるはめになり、気が付けば二人とも孤立し、やがて身の破滅を招いた。バブル期の大手銀行を舞台にした、いわゆるノンキャリア行員が引き起こしたは経済事件も、似たような構図だったような気がする。
鈴木、佐藤の二人も、それぞれ属する世界で、無理を避けて安全な道を選ぶことも可能だったであろう。しかし突出した能力が強烈な個性の中に宿ってしまった時、それが絶妙な巡り合わせで世に出た場合、制御ができなくなる場合が往々にしてあるようだ。二人の生き方にそれを強く感じた。
本書は、後半の最後の部分で、外務省内でキャリアの立場から、現実的かつ国益に準ずる道として「二島先行返還」を進めた東郷や、同じ外交官だった祖父のエピソードと、佐藤が背任や北方領土支援にかかる偽計業務妨害罪で逮捕される際の検察とのやりとりを交えながら、筆者は日ロ両国で、北方四島の帰属、平和条約締結が議題にあがった93年の東京宣言から、迷走を続けた外交を総括している。
「背景には、対ロ関係よりも対米関係や対欧州との協調を優先させるべきだとする日本の戦後外交を貫く"外務省多数派の考え"があった」と筆者は本書の後半で述べている。言い換えれば、「二島先行返還」派と「四島一括返還」派の対立は、親ロ路線と対米重視路線の対立とも解釈でき、さらに言えば独自外交かそれとも米国追従外交かになる。
外務省では省のトップは、他省のように事務次官ではなく、駐米大使だと聞いたことがある。その意味するところ、外務省にとっては、米国との関係こそが唯一無二の外交であり、対米関係を起点に、米国以外の他国との距離感が決まっていくとする考えなのではないか。
沖縄は米国海兵隊の大きな拠点である。横須賀は米国太平洋第七艦隊の拠点であり、所属する原子力空母の母港である。青森県三沢は米空軍の拠点である。
以上の事実は、米国から見れば、日本列島は極東に展開する米軍が、ロシア、中国、北朝鮮への軍事活動をおこなう上での橋頭堡であり、日米安保のタガをはめていたとしても、その拠点を構える国の政情は、米国政府からすれば最大の関心事であるはずで、もし日本政府が独自にロシアや中国との外交関係を進めていこうとしたとしても、米国政府が陰に陽に足を引っ張ろうとするのは、彼らの国益上それは当然の事である。
その意味からすれば、日本がロシアと平和条約を締結して、二国間の関係を深めていくことは、米軍の極東最大の軍事拠点に対するなんらかの悪影響を及ぼす可能性がある以上、米国が容認などするはずがない。
グラスノヤルスク合意以後の、日ロ二国間の交渉を、米国はどのように見ていたのだろうか。日ロというよりは実際のところは、日(米)ロなのである。
ロシア側も領土交渉を進めていけばいくほど、日本の外交の本質が露わになって、ロシアの国益からしても到底譲歩できる問題ではなくなる。この現実が変わらない以上、北方領土問題の前進、そして更なる先の返還などは、到底困難なのであろう。
・水産マフィア
本書は「密漁の海で」が題名だが、前半はレポ船、特攻船とソ連国境警備隊の北方領土海域での密漁をめぐる攻防が描かれていて、後半はこれまで述べてきたロシア政府との平和条約を見据えた北方四島の返還交渉、ムネオスキャンダルに焦点があてられているが、本書の第10章に「水産マフィアの抗争」がおよそ20ページを費やして描かれている。
密漁を構成する要素として、密漁する者、密漁で獲たカニ、ウニなどの水産物、その水産物を流通にのせる者の3つがある。ソ連時代は、根室の漁業従事者や広域暴力団参加のフロント水産会社がこれらの要素を担っていた。
しかし、新生ロシアになり市場経済が導入されて、北方四島周辺の海域で獲れるカニ、ウニなどの水産物が高値で売れる情報が、ロシア側へ行きわたると、ロシア極東沿岸の漁業従事者やその周辺者が、先を争うようにこぞって利を求めて密漁のスキームへ参入してくる。
カニ、ウニを獲って日本へ売れば金になる、ソ連崩壊から新生ロシアによる市場経済導入による混乱で、大きく衰退した北方四島を含む極東沿岸地域は、これらの水産物の輸出に活路を見出す。
本書では、ロシア政府が1993年にこれら水産物を「重要戦略物資」に指定したとある。これはつまりロシア政府が指定した「特別輸出業者」でなければ、カニやウニなどの重要戦略物資は輸出できないことを意味する。
しかし日本へ輸出すれば、大きな利潤をもたらす以上、それを政府が指定する輸出業者だけに限定することは、単に漁業従事者や指定から外れた業者を密漁、密輸出へと向かわせる結果となった。
本書の統計によると、根室を含めた日本のカニの輸入量が、1997年ではロシア政府が設定した極東全体でのカニ漁獲許容量を上回ったとあり、密漁ガニの輸入が定着しているとの分析だ。
日ロ両政府もただ黙って手をこまねいていたわけではない。日本政府はロシア側の要請を受けて、2002年には日本で輸入の際に、従来以上にロシア税関が発行した申告書の提出を厳しく義務付けて、さらに水産物の荷揚げ以外の目的で日本の他の港へ寄港することを禁じたりして、密輸の取り締まりを強化していった。
これらの規制強化の影響をうけるのは、ロシア側の漁業従事者、輸出業者だけではなく、カニの輸入やロシア船が入港した際の船用品の調達、上陸した船員による買い物などに地域経済が依存している根室の水産関係者も打撃が大きかったとある。「領土問題が存在するゆえに、密漁に頼らざるを得ない地域経済のいびつさ」と本書は表現している。
水産物の密漁、密輸出が大きな利権になっている以上、日ロ双方で規制を強化したところで、抜け道はいくらでも出てくる。またそれらを仲介したり、書類などを偽造するブローカーも暗躍する。
そうなると当然、取り締まる側のロシア国境警備隊との癒着が始まり、密漁、密輸出が組織化され、大きないくつかの密漁組織、いわゆる水産マフィアによる密漁ビジネスの寡占化が進んでいく。
やがてライバル組織同士の利権拡大を巡る抗争も頻発し、本書で取り上げられている、2000年にユジノサハリンスク市内で発生した国境警備隊長の殺傷事件へと発展していく。
この事件は当初は、密漁の取締りを強化したために、 それを恨んだ水産マフィアによる報復という構図で、ロシア治安当局は捜査を開始したが、本書では、事件の裏側にある国境警備隊と水産マフィアの「複雑に入り組んだ」関係をレポートしている。
密漁に従事する漁船を多く傘下に従えた水産会社は、自分のところの漁船が、洋上で国境警備隊に臨検を受けても見逃してもらえるように、警備隊の現場責任者やその上層部へ様々な便宜を図る。いわゆるワイロだが、本書の説明では、一回の密漁で入る利益の3~5%が警備隊に支払われるそうで、臨検の現場責任者クラスいなると、2、3か月で数千万程度のカネが懐に入ると言われる。
本書にははっきりと書かれてないが、想像するに、その稼ぎはその上役、つまり国境警備隊長に上納されて、さらに上の連邦保安局や内務省、検察にまでカネが行きわたっていたとしても不思議ではない。
水産会社側も自らの密漁グループへのお目こぼしを最大にするべく、それぞれが国境警備隊の幹部や上級官庁の役人クラスに食い込もうとしのぎを削るなかで、今回の国境警備隊長の殺害事件が起きた。
本書の推測によれば、この警備隊長は水産会社を陰で操る水産マフィアの抗争に巻き込まれたのか、もっとうがった見方をずれば、特定の水産マフィアと懇意にしていた警備隊長が、それを妬むライバルの水産マフィアに殺されたのか、または警備隊長自身が他のマフィアへ鞍替えしようとしたところを殺されたか、いずれにせよ本書の言葉通り「複雑に入り組んで単純でない」様相を呈している。
水産マフィアも、本書によれば、モスクワを拠点とするモスクワグループと極東のサハリン、ウラジオストックを拠点とする極東グループに分かれて激しく対立しているという。
その極東グループの草分け的存在として、「ヤクート」という名前のマフィアが存在する。このマフィアはユジノサハリンスクを拠点に、水産物を扱う多数のフロント企業を傘下に従えて、その内の一つが北海道の稚内にも水産貿易会社を設立、密漁で獲たエビ、カニ、ウニなどを日本へ輸入して、当然のことながら、日本の広域暴力団とも密接な関係にある。
密漁のエビ、カニ、ウニは輸入後、暴力団系のフロント水産会社を経由して、巧妙にロンダリングされて正規の流通にのるスキームが出来上がっている。また日本からは、主にRV車などの盗難車両を中古車両として、ロシアの水産物運搬船などに船積みして輸出、ロシア側からは水産物に紛れ込ませてピストルなどの武器を密かに輸入するルートが出来ているという。
本書では2001年に稚内市内で起きたロシア国籍の男性殺害事件と、それに関連するヤクートマフィアの領袖の一人の足どりを、細か追跡しながら、最後に潜伏していた韓国釜山で殺害されるまでをレポートしている。
ソ連崩壊後わずか10年足らずで、ロシアの極東一帯は、マフィアがはびこる無法地帯になってしまったようである。
私は書店で、この本を手に取った最初の動機は、この密漁に絡んで、日ロのアンダーグラウンド勢力が蠢く魑魅魍魎の世界が、主に詳しく描かれているのではと思ったのだが、著者は北海道新聞で政治部、国際部で主に活躍されたようで、巻末の参考文献の量も、この第10章に使われた文献が他の章と比較して少ないあたり、このようなテーマは社会部の守備範囲で、あえて最小限に筆を抑えてかいたのかと想像してみたりもした。
本書とは趣を異にするが、このヤクートマフィアが絡んだ北海道での殺人事件は、フリージャーナリストである曽我部司氏が2006年に出した「白の真実」に詳しくレポートされている。この本でもヤクートマフィアと北海道にあるそのフロント企業が、日本の暴力団や驚いたことに警察と癒着しながら、ロシアからはカニなどの水産物に紛れ込ませて、旧ソ連軍が使用していたピストル、さらに北朝鮮原産の覚せい剤がロシア船で日本に持ち込まれ、日本からは盗難品を含む中古車両が輸出されている実態を細かくレポートしてある。
また、2018年にフリージャーナリストの鈴木智彦氏が、小学館から刊した「サカナとヤクザ」にも、第五章でこの根室とロシア、そして密漁に関する話を詳述している。「密漁の海で」とかぶるところもあるが、この「密漁の~」の内容を振り返りながら、著者が根室に足を運んで綿密に取材されている。
この2冊も、とてもノンフィクションとして力作である。一読をお勧めしたい。
以上私の好きなノンフィクションとしてこの「密漁の海で」を取り上げました。最後までお付き合いいただき、大変ありがとうございました。
石本克彦
#ノンフィクション
#読書感想文
#外交問題
#北海道
#北方領土
#根室
#プーチン大統領
#ロシア
#ウクライナ侵攻
#カニ
#密漁
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
