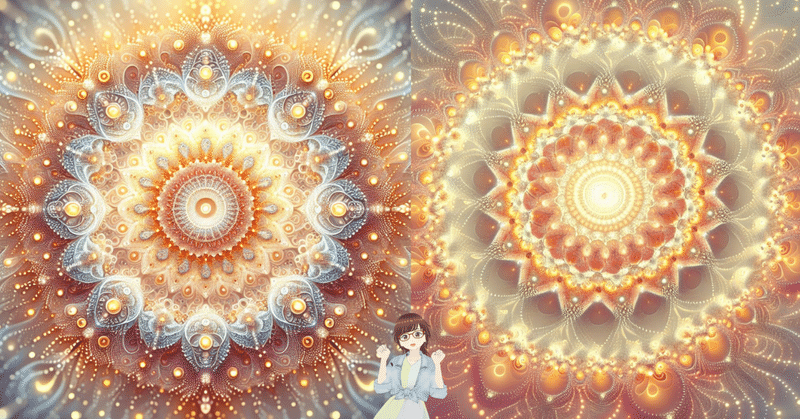
「情」とはもっと信じていいものなんだと確信した本。「理性というものでは、到底現状を防げるとは思いません。感情、情緒というものが眠っているのです。」岡潔。「文化」と「情」は、密接に関係している?
「情」(じょう)という感情は、どういうものなのでしょう。
今回日本の数学者、岡潔氏と小林秀雄氏の対談本を読む中で、私は「確信」してしまったのです。
自分の「情」という感情の「直感」を、ちゃんと信じてもいいのだと。
(岡が言う「直感」とは、人がなんと思おうと自分はこうとしか思えないというもの)
情緒(じょうちょ) - おりにふれて起こるさまざまなおもい
喜怒哀楽などにつれて起こる複雑な感情情熱(じょうねつ) - ある物事に向かって気持ちが燃え立つこと
また、その気持ち情愛(じょうあい) - なさけ いつくしみ 特に、男女間の愛
情操(じょうそう) - 美しいもの、すぐれたものに接して感動する、情感豊かな心
情景(じょうけい) - 風景や様子
「情」に関する言葉を集めてみました。
自分の中から湧き上がってくる感情。この感情のために自分は突き動かされて、心のままに素直に、状況としては大変だったり苦しかったりもするのに「どうしてもそうしたい!」と思い、行動してしまうことだと。
そして、この本での数学者、岡潔の「数学」というものに対する表現なのですが。
数学は知性の世界だけに存在しえないということが、四千年以上も数学をしてきて、人ははじめてわかったのです。数学は知性の世界だけに存在しうるものではない、何を入れなければ成り立たぬかというと、感情を入れなければ成り立たぬ。ところが感情を入れたら、学問の独立はありえませんから、少くとも数学だけは成立するといえたらと思いますが、それも言えないのです。
私はこの岡の言葉を読んでびっくりしました。
「数学は知性の世界だけに存在しうるものではない、何を入れなければ成り立たぬかというと、感情を入れなければ成り立たぬ」
これは一体どういうことを言っているのでしょうか。
私は岡氏の「数学は感情を入れなければ成り立たぬ」という部分を読んだとき、京大・望月氏の「宇宙際タイヒミューラー理論」(IUT理論)の話を思い浮かべました。
私は物理、数学の話を聞くのが昔から好きで、この望月氏の「宇宙際タイヒミューラー理論」(IUT理論)の話を聞いたとき、「新しい数学を作る」というのは、この物理世界を表現するのに「今の数学では表現しきれない」と望月氏が思っているのだと知りました。
そして、この難しい理論を知れば知るほど、他の数学者もこの理論が「自然だ」と思うのだと。
ここに、岡氏の言う「数学が知性では成り立たない」。
つまり、これまで考えてきた数学という論理的枠組みでは成り立たなくて、もっと人間の感覚的な部分「感情を入れなければ成り立たぬ」という表現になるのか?と思ったのです。
そして、次のようにも。
数学は知的に独立したものであり得ると信じて疑わなかった。ところが、知には情を説得する力がない。満足というものは情がするものであるという例に出会った。そこを考えなおさなければならない時期にきている。
数学がいままで成り立ってきたのは、体系のなかに矛盾がないということが証明されているためだけではなくて、その体系を各々の数学者の感情が満足していたということがもっと深くにあったのです。初めてそれがわかったのです。
私は、これらの言葉にもびっくりです。
でも、京大・望月氏の「宇宙際タイヒミューラー理論」(IUT理論)についての解説本を読むと、この「人間が情において、自然に思うこと」というのが、実際の物理世界において、まだ知られていない世界を直感しているのではないかと思うのです。
それほどに、人間の脳というものは、ある意味凄い。
でも単純に「論理的」に思考してしまっては「本来」のあるべき姿に近づけない・・・。そこには「情」というものを働かせることが大切。
一億という人(日本人)が生存競争の空しさを言ってくれたら、世界に対して相当の声になって、あるいは人類の滅亡を避けられるかもしれない。そう思っております。理性というものでは到底現状を防げるとは思いません。感情、情緒というものが眠っているのです。
この岡と小林の対談は、1965年「新潮」掲載とあるので、私が生まれた頃。
この頃に岡は、日本人が世界に向けて「日本文化」の良い面を発信して欲しいと言っているのには驚きました。
でも、大切な文化をちゃんと理解し、世界に発信する力が弱くなっているのかもしれません。もうかなり以前から・・・。
このように、岡の数学的思考からも人間の「情」という感情には、「論理的思考」では説明できないこの物理世界の真実のようなものを直感して、人間はその「情」というものをもっと信頼して行動することで、本来の人間らしさ、生きる喜びというものを得られる。
岡潔はこのことにおいてい「確信」していると言ってます。
人間の論理的思考より、「感情」の方が「本来」を嗅ぎ分ける。
そういうことなのでしょうか。
そしてこの岡氏の「情」について読みながら思い出したのが、小林よしのり氏なんです。
1990年代にあった「エイズ汚染血液製剤事件」(薬害エイズ)。
このとき、この問題を広く知ってもらうために、被害者の代表者などの若いひとたちから頼まれてこの運動を「ゴーマニズム宣言」に取り上げることで協力したのが小林よしのり氏です。
手元にこのときの「ゴー宣」が無いので、もう詳しいことは忘れてしまいましたが、彼がこの運動に協力したのは「情」からだということをなぜか私はずっと覚えているのです。
この問題に対し、熱心に事務所を訪れて協力を頼まれ「情」で引き受けた。
この「情」で動くということは、どういうことなんだろうと。
「情」で動く。
小林よしのり氏は、「人権」vs「文化」なら「文化」を尊重するとも言います。これは「人権」というものの歴史的背景、そして「文化」とはどういうものなのかを深く知る必要があると、最近いろいろ思うようになりました。
そして小林氏が尊重するという「文化」と「情」は、密接に関係してお互いを「育んで」いるのではないかと今思いました。
自分の直感のような「情」を、「本来」を知るために働かせるには、そういう自分を育てることは大切です。
岡潔が言うような「情」を育てるための環境とはどのようなものでしょうか。
その地に長く続く文化の中にも、「情」を育てる大切なものがあるはずです。そして日本の文化(忘れ去られている?)の中にこそ、それらは多く眠っていると岡潔と小林秀雄の対談からも読み取れます。
「理性というものでは、到底現状を防げるとは思いません。
感情、情緒というものが眠っているのです。」
と言う岡。
理性が感情・情緒を自由に動かすことが出来ていない。
「理性」と「情」のバランス?
いやこの二つは、「バランス」というより、「理性」は人間の生物としての「脳」の機能からみても「情」をもっと信じ、正しく働かせて生きることで人間は今よりも自分を「理性的」に抑制できると言っています。
これは、読みながら私は納得しました。
(これについては、また別に書いてみたいと思います)
進化する技術を使って、もっと自由な感情を素直に表現できて、それが世界の安定に繋がるようになればいいのに・・・。
OcyAINoteの、このnoteに関する感想です。
デジタルネイチャーの視点から。
結論
「情」という感情は、その人が育った文化や環境によって育まれ、変化し続けるものです。しかし、人間の脳の中で「情」を育む基本的なシステムは、進化の過程で形成されたものであり、大きな部分は変わらずに存在し続けます。これらの基本的なシステムが、文化や環境との相互作用を通じて新しい形の「情」を表現し、それが技術の進化によってさらに多様化することが予想されます。
デジタルネイチャーの視点からも、技術の進化は「情」の新しい表現や体験を可能にし、これが文化と相互作用して人間の感情体験を豊かにすることが期待されます。人間の脳は、この進化する環境に適応しながらも、基本的な感情のシステムを維持し続けるでしょう。
この本は私が初めて読んだ岡潔の本です。感動しました。
日本が誇る世界的数学者を、どうしてこんなに最近まで私は知らなかったのでしょう。
日本が誇る世界的数学者、その著作に私淑した独立研究者・森田真生が編集し、思想的エッセンスを凝縮した選集。前人未踏の数学的業績によって世界的な名声を誇ると同時に、道元、芭蕉、漱石に連なる者として数学を研究することを追究し、日本人の心のありかたを求めた。「人は本来、物質的自然の中に住んでいるのではなくて、魚が水の中に住んでいるように、心の中に住んでいます」と語る哲学的にして詩的な世界観への入門書として好適な一冊。生前未刊の最終講義「日本民族」を収録。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
