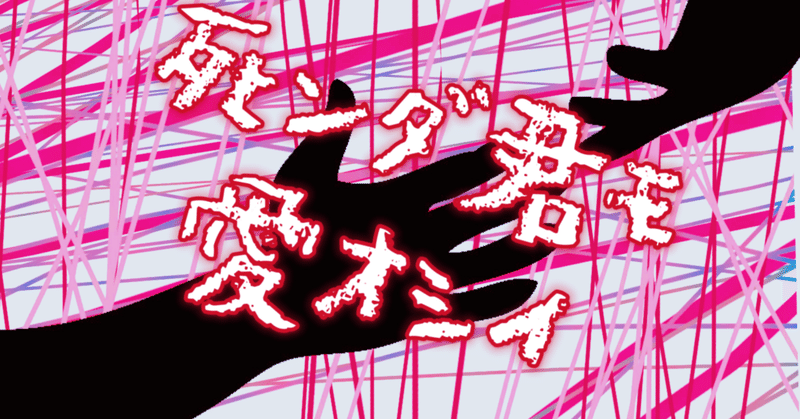
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第15話
Prev……前回のお話
なぜ佐倉への不信感が募ってしまうのだろう。ほんの些細なことだったはずだ。アズサがホワイトメールに拾われたのが二十歳だと、佐倉が勘違いしただけのことだった。なのにそれがきっかけで、アズサを紹介した時の佐倉を思い出してしまったり、その後のアズサへの執着が今更気になってしまったり、そう、今更だ。なぜこんなに不安に陥るのだろう。気にしても自分を苦しめるだけなのに。これでは誰も幸せになれない。不快な思考を止めたいのに、暴走したトロッコが火を噴きながら頭の中を駆け巡る。つい数日前まで信頼できる相方だったはずなのに、ほんの些細なきっかけで、こんなにも見え方が変わってしまう。本当になにもなかったら、どうするんだ。腹でも斬るか? いや、その可能性が高いのだから余計なことは言わない方がいい。ぞっとして、一矢は自分の腹を摩った。本当になにもなかったら、それが一番いいに決まっている。たとえ腹を斬ることになったとしたって、それが一番いい。
せっかく会社を休んだのだ。貴重な一日を有効に使いたい。それはひたすら休むこと。身体は勿論、心の休息が必要だということに気がついた。だから今日はもう、なにも考えたくない。しかし休むって、どうやればいいのだろう。寝る以外に思いつかない。映画を観たり、本を読めば、余計なことを考えずに済むかもしれないが、どうもそんな気力がないようだ。ゆっくり風呂に浸かるとか。それもいいなと頭では思うけれど、なぜか身体が動かない。はあ……。頭が重い。気がつくと項垂れてしまう。ソファで溜息を吐きながら項垂れて、これは休んでいることになるのだろうか。瞼が熱くて、じりじりと痛む。泣きそう? なぜ? いつからこんな泣き癖がついたのだ。色んな不調を疲れのせいにしてきた。なにに疲れているのか考えもせずに。思ったより、自分は強くなかったのかもしれないな。休めば治るはず。明日には、もう少しマシになっている。
結局、あれこれ考えたけれど何も実行することはできずに、寝ることに落ち着いた。アズサの部屋で寝たいな、なんて思いつつ、自分のベッドに向かう。アズサの部屋に自由に行き来できるのは、アズサが死んだという証拠でもあり、なんとなくまだ抵抗がある。全く眠くないけれど、寝られるだろうか。別に寝なくてもいいか。横になっているだけで回復すると聞いたことがある。明日までに気力を回復させないといけない。二日も休むつもりはないし、これ以上、自信をなくしたくなかった。
そんな休日を過ごした翌朝。無事に一矢は出勤した。完全に回復したとも言えないけれど、よく考えたらもともとそれほど元気が有り余っていたわけでもないし、テンションも低いし、多分、普段とそれほど変わらないだろう。ただ、昨日は結局なにも口にすることができなかった。水と……、ああ、水だけだ。これは流石にまずいな。そう思い、一矢はデスクに荷物を置いてから、下のコンビニに食べ物を買いに行くことにした。
「あ、おはようございます、広川さん」
「ああ、おはよう……」
オフィスのドア付近で木橋に声を掛けられる。大事そうに両手に何かを持っているが、どうせ碌でもないものに決まっているから、一矢はさりげなく目を背けた。自衛は基本だな。
コンビニでハム卵サンドを一度手に取ってから、考える。いつもこれ食ってないか? 特別サンドイッチが好きなわけではないのだけれど、食べやすさを重視して、つい手を伸ばしてしまう。今は、自分らしくないことがしたい。ハム卵サンドをそっと戻し、軽くうろつきながら棚のラインナップをチェックする。とはいえ、朝だしデスクで軽く食べられるものがいい。やっぱサンドイッチなのでは。……いや。これだ。
「ありがとうございます」
自分らしくないものを手に入れて、小さなコンビニ袋を片手にエレベーターを上がる。缶コーヒーを買うために自販機に寄ると、佐倉がゴミ箱の前でエナジードリンクを飲んでいた。
「朝から気合い入ってんな」
「お、広川おはよう」
飲み干した缶をスコン、とゴミ箱に投げ入れ、佐倉は笑顔で答えた。
「なんか昨日あんま眠れなくてさ。あ、そういえばお前、大丈夫か?」
「ああ、急に休んで悪かったな」
「いやいや、こっちはいいんだよ。ずっと心配だったから、むしろ休んでくれて安心したっていうか。少しは良くなったか?」
「うん、大丈夫」
ありがとう、と言いながら、缶コーヒーのボタンを押す。ガコン。屈んでボトルを取り出しながら、横目に佐倉の姿を見る。やっぱり、いい奴だと思う。疑ってしまったりしたのは、自分の頭が正常ではなかったからだろうか。じゃあ、今は正常なのか? どうだろう。自信がない。いつだって、正常なつもりなのだが。
「なあ、佐倉」
「ん?」
スマホでなにかを確認していた佐倉は、顔を上げて一矢を見る。
「昼、一緒に食わないか」
「えっ?」
大袈裟に驚くから、少し不安になった。
「ああ、弁当持ってきてたか?」
「いやいやいや。弁当はないし、なんの予定もない! お前から誘ってくるなんて珍しいな。昨日の休みが効いてるのか? いいぞ、どこ行こうか。そうだ、駅の裏の蕎麦屋とかどうだ?」
「うん、どこでもいいよ」
嬉しそうな佐倉を見て、少し、胸が痛む。話せるだろうか。聞き出せるだろうか。今後の俺たちはどうなってしまうだろう。一矢は、肺の中に砂利が詰まっているような息苦しさを覚えながら、開け放されたオフィスのドアを抜けた。
「お、メロンパンとか食うんすね。はは、似合わねー」
「うるせぇぞ、井田。何の用だ」
モニターの前でメロンパンを齧っている一矢に、オレンジ頭の井田が分厚いファイルを差し出す。
「なんだそれ」
「いや、なんかわかんねぇけど、持ってけって言われたんで」
「誰に」
「柿谷先輩っす」
「ああ」
こいつ、ほんとに柿谷に引き継がせたのか。先輩にケツ拭かせて、いつまでもこのままでいられると思うなよ。とりあえず、佐倉とのことが片付いたら、こいつを一から叩き直してやる。それにしても、このメロンパンはなかなか美味い。コンビニを舐めていた。
「広川さん」
「あ?」
「俺、広川さんみたいになりたいっす」
「どういうこと?」
「アホな部下も薄い胸板で受け止めてくれるっつーか……包容力は感じねーけど」
「それ、褒めてんのか? まずはアホな部下を卒業しろ」
「っす」
「あと、胸板は別に薄くない。ちゃんと鍛えてる」
「あいあい」
じゃ、よろしくっす、と言いながら井田はファイルをデスクの端に置いて、ふらふらと去っていった。一矢は食べ終わったメロンパンの袋をくしゃくしゃとコンビニの袋に押し込み、残っていた野菜ジュースを一気に飲み干した。ずぞぞっ。
なんやかんや一抹の不安を残しつつも、午前の仕事は問題なく進んだ。そろそろ昼の時間。佐倉のことだから、席まで迎えに来るだろう。ああ、やっぱり来た。
「おつかれ」
「ああ」
軽く伸びをして、PCをスリープモードにすると、一矢は立ち上がって上着を手に持った。ふと改めて佐倉を見ると、少しさっぱりした気がする。
「あれ、お前髪切った?」
「髪くらい、切るだろ」
「まあ、たしかに」
そう言いながら、椅子をデスクに寄せて、佐倉と並んで歩き出す。
「お前こそ、そろそろ切った方がいいんじゃないか? だいぶ伸びたよな」
「そうかな」
言われてみれば、いつから切ってなかったっけ。あれは、休日なのにアズサの帰りが遅かった日だ。たしか二か月前の土曜。いや、もう三か月か。あの日も、アズサは気が立っていて、マグカップを粉々に割ったのだ。思い出しながら、一矢は改めて自分の髪に触れてみた。前髪も襟足もだいぶ長く伸びている。
「まあ、雰囲気があってそれも似合ってるけど」
佐倉の言葉には嫌味がない。週末にでも、切りに行くか? なんとなく、気が進まない。アズサのことを知っている体の一部が、少しずつ削り落とされていく感覚になる。
駅の裏の蕎麦屋は小綺麗な佇まいで、まだ新しそうだった。「大泰庵」という群青の暖簾が掛かっているドアをスライドさせ、佐倉は店に入っていく。すぐに「らっしゃーい」という若めの男の声が響き、席に案内された。メニューを眺めながら、ふふふ、と佐倉は笑っていた。
「なんだ?」
「いや、ここさ。大泰庵っていうんだけど」
「うん」
「仕事で行き詰まった時とか、よくひとりで来るんだよ。なんか代替案が思いつきそうで」
「ふっ、なるほどな」
代替案か。佐倉の言葉に軽く笑ったものの、すぐに真顔になって一矢は考えた。代替案。佐倉に直接聞く以外に、真実を知る方法はないだろうか。いや、直接聞くのが悪いわけではない。なにもないなら、問題はないのだし、あったとしても……、うーん。そもそも、自分はなにを疑っているのだろう。自分が知らないところで、ふたりが会っていたとして、なにか問題があるだろうか。いや、あるよな。なぜ隠していたのかとか、会ってなにをしていたのかとか。でも飽くまでも、一矢の憶測に過ぎない。それをどうやって確認したら、気が済むのだろう。代替案、仕事してくれ。
そんなことを考えながら、気づけば蕎麦を啜っていた。山菜おろし蕎麦。
「普通に美味いだろ?」
「うん、普通に」
はは、と佐倉は笑いながらコップの水をひと口飲んだ。
「俺さ、意外と普通が好きなんだな。特別じゃなくていいんだよ」
「それはなにに対して言ってるんだ? 場合によっては奈津美に失礼だぞ」
「まあな。でも、特別綺麗だったり、特別かわいかったら、手が出しにくいだろ」
「あんまそういうこと言うなよ」
ずずっ。一矢は蕎麦を咀嚼しながら、佐倉の言葉を咀嚼した。
「なにか、疑っちゃったりしないか? こんな綺麗なのに、なにか、あるんじゃないか、とか」
ごくり、と一矢は飲み下した。どういう意味だろう。アズサのこと?
「佐倉、お前さ……」
「ん?」
「アズサ……」
なんて言うんだ。よく考えもせず、いや、よく考えはしたが、結論も出さないまま、アズサの名前を出してしまった。この話の流れで、いったいなにを聞けばいい?
「アズサのことは、どう思う?」
「え……」
妙な沈黙が流れた。黒? 白? いったい黒ってなんだ?
「あ、梓さん……? すごく、綺麗な人だったとは、思うけど……」
一矢が黙って佐倉の次の言葉を待っているから、佐倉の目は少し泳いだ。
「ああ、なんか俺、変なこと言ったかもな。梓さんは、その、なんていうか、まあ、俺にはよく、わかんねぇや」
わかんない、ほんとに、と何故か悲しそうに佐倉は呟いた。一矢の死んだ恋人だからだろうか。それとも、なにか別の意味が? 考えても仕方ないか。なぜか一矢もとても悲しくなってきた。理由はたくさんあり過ぎてもうわからない。悲しい要素に溢れていた。これ以上、聞けそうにない。結局、代替案も思いつかないまま、会社に戻ることにした。
「お前、今日はまっすぐ帰るのか?」
「え?」
一昨日、佐倉からの焼き鳥を断って静流と行ったのがバレていないか、内心ヒヤッとした。
「そのつもりだが、どうかしたか?」
「ああ、俺、今日鍵山商事の会食入ってるからさ。早めに上がるけど、何かあったらよろしくな」
「わかった」
情けない。自分の中で疑いを消化することもできないくせに、正面切って尋ねることもできない。なにが大事な友人だ。この腹の内を知ったら、なんと思われるだろう。自分がこれほど煮え切らない人間だとは思わなかった。もう、このままではどちらにせよ、今まで通りにはなれないのではないか。一矢の問題である。多分だけど、佐倉はなんとも思っていない。後ろめたいことがなければ、一矢の不安にも気づいていないに違いない。
告知通り、佐倉は夕方6時頃には会社を出た。会食前に寄る場所があるらしい。一矢はいつも通り仕事をこなし、まあ、せっかくだから自分も早めに上がるかと、7時過ぎには会社を出た。一応、病み上がりってことになっているしな。
「あ、あの、広川さん……!」
「えっ?」
エレベーターが閉まる寸前に乗り込んできたのは、やはり木橋。閉まるボタンを連打しておくべきだった。両端からドアに挟まれながらも、諦めずに体を捻じ込んでくる木橋の姿を眺めつつ、誰だこいつを大人しい真面目な女性とか思ってたやつは、と溜息をついた。
「お、おつかれさまです」
「ああ、おつかれさま」
無事、隣に落ち着いた木橋は、やはり両手に大事そうになにかを抱えているが、一矢は決してそれが視界に入らないように、顔を逸らした。間違いなく、妙なものを持っている。気にならないかといえば、気にならなくもないが、見たら絶対後悔するのだ。
「あの……私、今日これからご飯を……」
「うん、しっかり食え」
「えっと、広川さんはイタリアンと和食だったら……」
エレベーターが一階に到着し、扉が開くなり一矢は大股で進み出た。慌てて木橋が小走りについてくる。参ったな。もしかして、食事に誘われているのだろうか。こいつだけは絶対に無理だ。どんなグロテスクなものを食わされるかわかったもんじゃない。
「広川さん……あの……」
いつからこいつはこんなキャラになったんだ? 地味で大人しくて真面目な、あのキャラはどこにいったんだ。こんなぐいぐい来るような変人ではなかったはずなのに。一矢が適当に返事をしながら、オフィスビルを出た瞬間。
「あれ? 一矢じゃん!」
少し鼻にかかった、聞き覚えのある元気な声に、心底救われた。
「奈津美。なんでここにいるんだ?」
「この近くのビルにヨガ教室があるのよ。その帰り」
「佐倉なら、今日は会食で遅くなりそうだぞ」
「あ、うん、聞いてるよ」
そう言いながら、奈津美は一矢の背後を少し気にしている。
「そちらは……」
「ああ、うちの会社の木橋」
一矢は木橋にも、彼女が佐倉の嫁だと紹介した。
「はじめまして、木橋さん。素敵な鉢植えだね」
「あ、ああ、ありがとうございますっ、形見でして」
誰、いや、なにの形見なのか知らないが、素敵な鉢植えだったのか。警戒し過ぎただろうか。
「一矢、どう? せっかくだから飲みにでも行こうよ」
「んー、そうだな」
一矢はそう言いながら、奈津美からなにか情報が聞き出せるかもしれないと閃いた。これはチャンスに違いない。しかし、斜め後ろから視線を感じる。どうしよう、この妖怪女。ああ、妖怪女は言い過ぎか。
「えっと……奈津美に話したいことがあるんだ。いや、聞きたいことというか……」
正直に言うことにした。小細工するから面倒なことになるのだ。
「私に? なんだろ? うん、じゃあ、いこっか」
「あっ、じゃあ、私はこれで……」
木橋も流石に空気を読んだ。少しだけ申し訳ない。
「ああ、ごめんな。また明日、会社で」
「はい……おつかれさまです……」
あからさまに肩を落として、木橋が背を向けた。
「いいの? なんか一矢に気があったみたいだったけど」
「それはない」
一矢ははっきりと否定した。以前なら一矢もなんとなくそう思っていた。しかし、あいつは一矢をあの手この手で脅かしにくるのだ。今だって彼女の後ろ姿からしっかりとはみ出している。なにかの形見らしき素敵な鉢植えから無数の触手が蠢きながら伸びているのが。
Next……第16話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
