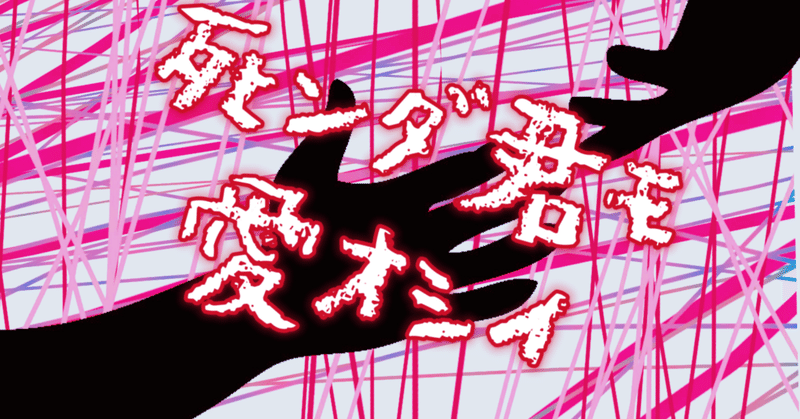
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第14話
Prev……前回のお話
「本当に大丈夫ですか?」
「大丈夫です、お世話になりました」
心配そうな駅員に一矢はぺこりと頭を下げて、駅の救護室を出た。まだどこか覚束ない足取りで出口を横切り、屋根の向こうに黒く湿った道路を見て、雨が降っていたことをぼんやり思い出した。救護室で寝ている間に、止んでいたようだ。濡れずに済んだのは不幸中の幸いか。一矢はじっと手のひらを見つめた。倒れた時に擦りむいたらしく、側面の皮が剥けて血が滲んでいる。頭を打ったかもしれないから、念のため病院に行くように繰り返し言われたが、まあ、大丈夫だろう。特に痛む部分はない。抜群の運動神経で、意識を失いながら受け身を取っていたのかもしれない。流石にそれはないか。頑丈な肉体のおかげ、ということにしておこう。
妙な顔をされた。目が覚めたら駅の救護室。駅員はこんなことには慣れている様子で、ちらっと一矢の方を向いてから、作業をしながら「大丈夫ですか?」とか「救急車を呼びますか?」とか声を掛けただけで、酔っ払いの軽い脳貧血くらいに思っていたようだ。しかし一矢が内臓露出狂の話をすると、駅員は少し顔色を変えて、もうひとりの駅員を呼んできた。事の重大さに気づいてもらえたと一矢は安心したが、駅員たちは一矢の頭の様子を心配しているらしく、しつこく救急車を勧めてくる。まあ、つまり露出狂は発見されていないってことなのだが、一矢はなんとなく自信をなくした。何の自信かはよくわからない。ついでに気力もなくして、話すのをやめた。なんかもう、いいや。
重くて怠いのに浮遊感のある不思議な体の感覚と、疲れ果てた脳のせいで、一矢はどこに向かっているのかわからなかった。なんだったんだろう。すべてのものが幻に思える。昨日も、今日も、明日も、その次も。すべてが幻のような、それでいて鮮明で、温度、感触、空気、脈、匂い、血色、鳴き声、羽音、ああ、リアルじゃないのは自分かもしれない。靴が汚れている。汗のような臭い。不快だ。気のせいか。アズサはどこに行ったんだろうな。鞄は……持ってる。耳鳴りがする。静かだ。あれは。二本、三本、いっぱい。ついてけないよ……。空腹。生肉が食べたい。レア。レア。レア。レア。救急車。赤。はあ……、なんだっけ。なにもないな。空っぽだ。なんだっけ。なにが?
気づいたら、見覚えのある建物の前にいた。そう、このマンションに住んでいる。なんかおかしいな。今ちょっと変だった気がする。疲れているのだろう。そう、このマンションに住んでいる。帰ろう。そして寝る。うわー、赤いペンキがまた。最悪だ。階段、8、はあ、疲れた。3、てくてくてくてくてく。5、6、7、0、到着。4、2、はあ、疲れた。5。
「ただいま」
オカエリ。
「ただいま」
オカエリ。
なぜだか涙が勢いよく溢れだした。なんだこれ。はは、最高だ。どこにいるんだろう。誰か。誰か。おーい。何も見えないよ。
――可哀想なイチヤさん。もう大丈夫。
「あ、栞さん。はは」
――大丈夫。全部悪い夢のせいですから。
「やっぱり……はは……」
――明日になれば、良くなります。
「良く、なる……」
――さあ、思いっきり泣いて、寝てしまいましょう。
もう、なにがなんだかわからないけど、とまらないなみだがきもちいい。いきができないけど、くるしくてきもちいい。からだがおもちゃみたい。ああ、しんぞうが
アズサ。
会いたいな。
今、何時だ。暗い部屋の中で目が覚めた。暖かいベッドで布団に包まり、熟睡しきっていたようだ。でも、ここは――。
アズサの部屋。入ることも許されなかったのに、勝手にベッドで寝たのがバレたら、どんな酷い目に遭わされることだろう。記憶がぼやけて、昨日のことがよく思い出せない。でも最悪な一日だったことは身体が覚えている。そして細かいことは思い出さない方がいいような気もする。なんだか……怖い。もう少しだけ、寝たい。まだ外は暗いし、構わないだろう。そうだ、今日くらい、休んでもいいかもな。次に目が覚めたら、会社に連絡をしよう。
アズサの匂いがする。
午前8時過ぎ。一矢は会社に連絡をして、スマホを片手にアズサのゲーミングチェアに座っていた。座り心地は、特によくはない。組み立てるのを手伝わされたのに、座らせてもらったことは一度もなかった。アズサの自慢の椅子だったようだが、大したことはないな。
ぼーっと部屋の中を見回して、改めて襲ってくる寂しい感情を紛らわせるように、いや、むしろ思う存分浸るように、遺品の整理をしてみようかと思い立った。できればこの部屋はもう少しこのままにしておきたい。でも、もしも腐るものでもあれば、気づかないうちに悲惨なことになってしまう。食べかけのお菓子とか、アズサのことだから、あってもおかしくはない。それとも、死ぬ前に自分で整理したのだろうか。自殺する人間の思考がわからない。そもそも、アズサはいつから自殺するつもりだったのだろう。あの朝、ごはんを作ってあげようかと言った時は、きっと……。
立ち上がった時に気がついた。腰の横の部分に痛みを感じる。ぼんやりと昨日の夜の救護室の景色が蘇り、慌てて忘れようとした。今は考えたくない。
アズサの部屋は、思ったより整理されていた。それは普段からこの程度片付いているのか、それとも死ぬに当たって片付けたのかわからない、微妙なラインだった。しかし、明らかにおかしい点がある。カメラがないのだ。あの、Nikonのカメラがどこにも見当たらない。遺品の中には例の、小さなデジカメしかなかったはずで、ならば仕事に使っていたはずの一眼レフはどこにあるのだろう。アズサが隠した? なんのために? 普通に、誰かに見られたら都合が悪いからだと考えられるが、不動産屋の仕事のカメラがどんな秘密を抱えているというのか。
妙だ。どこにもない。職場に置いてきた? 仕事のカメラだから、あり得るか……? いや、あいつはいつも持ち歩いていたはずだ。間違いなく、意図的に隠されている。
一矢は黒いスチールの収納ラックを無駄にペタペタと触れながら、上から下まで見回したが、やはりどこにも見当たらなかった。気にし過ぎだろうか。たまたま、どこかに行ってしまっただけとか。深い意味はないって? 少し冷静になろう。
――ねえ、ごはんは?
リビングのドアを開けた途端、アズサの苛立った声が聞こえた。慌てて声の方を振り向くと、栞さんがふわふわと小さな雲を縫いながら泳いでいる。
「栞さん。お前、アズサなのか?」
そう言ったものの、どういうこと? と自分の言葉に首を捻った。
――おかしなイチヤさん。そんなわけ、ないじゃないですか。
まあ、そんなわけないか、と納得しかけてから、そもそも金魚が喋るわけないような気もする。どんなわけがあってどんなわけがないのか、もう、わけがわからない。
一矢が思考を諦めた瞬間、小さな金魚が心臓に飛び込んできた。
はっ……あぁ……。
頭の中が真っ白に眩しく光る。一瞬にして汗ばんだ体の力が抜けて、一矢はよろよろとソファにもたれるように片膝をついた。荒い呼吸に胸や肩が上下する。
――複雑な味ですね。今日のイチヤさんは。
「えぇ……?」
情けない声で返事をしてから、消耗しきった瞳で栞さんを見上げる。
――ちょっと話してみましょうか。
なにを……と言いかけて、話すことがあったような気がしてきた。こいつと話すことなんて、アズサのことしかない。間違いは見つけたか? 昨日、なにかあったよな。
「佐倉が……なにかを隠している気がする。いや、気がするだけなんだが……」
何度も胸の奥にしまったはずだったのに、やはりまだ引っ掛かっている。思いついたままを口にしてみたけれど、栞さんの反応は特になかった。佐倉のことを知らなかったかもしれない。説明するか? しかし、説明が必要だとしたら、それは間違いとは関係ないということだろうか。
――もしそれが間違いならば、なにを隠しているのかが「答え」ですね。
一矢はごくりと喉を鳴らした。そうか、そうだ。やはり知らなくてはならない。直接聞いて、話してくれるだろうか。また誤魔化されるのではないか。よく考えたら、あいつはずっと誤魔化してきたのだ。アズサに限らず、自分自身のことも。心を開いているようで、曝け出すことはなかった。奈津美、なら知っているだろうか。知っていたとして、話してくれるとも思えない。そもそも、明確な根拠のない疑惑であって、ただの勘違いだという可能性もあるのだ。こんな、探るようなことをして、佐倉とアズサが何もなかったらどうすればいい?
「あいつは大事な友達なんだ。できれば疑いたくない」
誰に向かって言い訳をしているのか。疑い始めたのは自分なのに。自己嫌悪になりながら、栞さんの姿が見当たらないことに気がついた。
「栞さん?」
ぽちゃん、と音がして水槽を覗くと、妖艶な金魚がこちらを揶揄うように長い尾鰭をゆっくり振っていた。
「こいつ、都合がいい時だけ金魚になりやがって」
いや、どちらが本当の姿なのだろう。なんだかもやもやして、水槽をコン、と指で弾いた。餌はさっきやったから要らないか。心臓を右手でぎゅっと押さえる。どくん、どくん、どくん。異常なし。
リビングの床に投げ出されていた、仕事の鞄を拾い上げながら、この鞄を放り出した経緯を思い出す。あれは、パニック状態とは違うと思うけれど、なにかがおかしかった。初めての経験で、思い出すだけで身の毛がよだつ。もしかして、静流の専門なのでは? いや、そういうあれじゃない。うん、違う。今は普通だし。普通だよな? 生きていれば、誰だってあんな経験はするものだ。色んなことが重なり過ぎたのだ。一時的に、ほんの一瞬、頭がおかしくなった。誰だってあるだろ。
ソファに腰かけて、拾い上げた鞄の内ポケットから銀色のチューブを取り出した。ハンドクリーム。心が落ち着くって? 一矢は蓋を開けて、ほんの少しだけ、手の甲に出してみた。鼻を近づけてみると、たしかにいい香りがする。塗り方がよくわからないけれど、適当に手の甲を合わせて塗り込めばいいだろう。すぐに優しい香りが広がって、嘘みたいに手がしっとり滑らかになった。知らなかった。こんなに効果があるものなのか。たしかに、触ると心地よい。気持ちが落ち着くというのも理解できる。こういうことか。一矢は右手を顔の前で振って、香りを吸い込んだ。
「助けが必要な時は、すぐに呼んでほしい。絶対に力になるから」
どんな時だろう。今は、助けは、必要、ないと、思うけど。でも、あいつは佐倉の親友だ。もし佐倉との間になにかあったら、きっと助けてはくれないよな。
Next……第15話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
