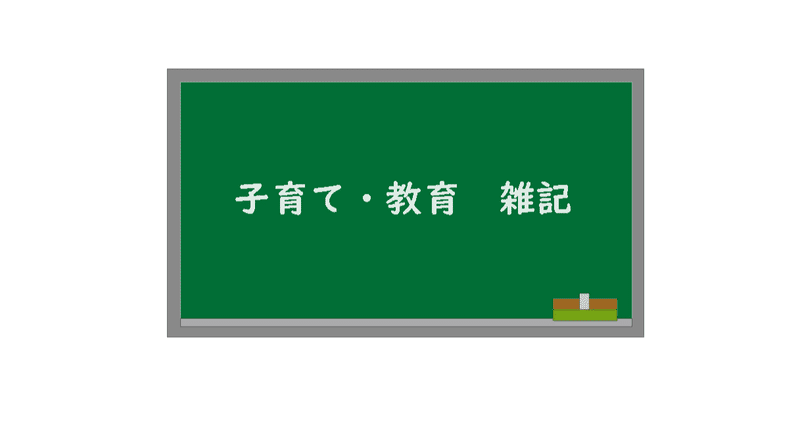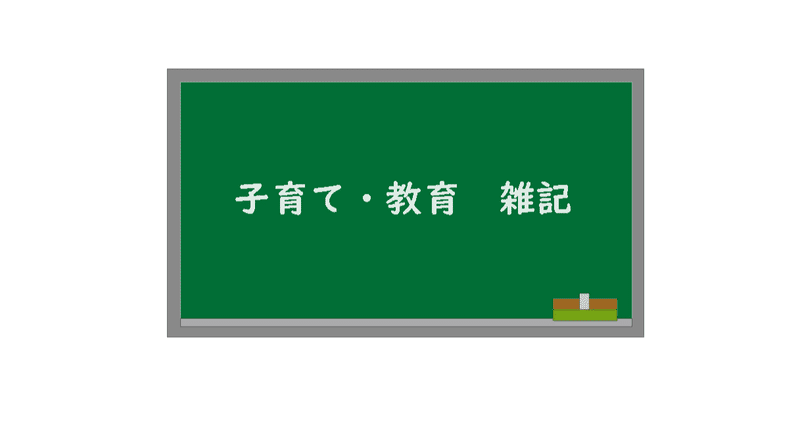最近、中学生の事件が多いですね"(-""-)"
19日には、北海道根室市の
ショッピングセンターで
店員が包丁で切りつけられた事件
殺人未遂の疑いで
逮捕された14歳の男子中学生
「むしゃくしゃしていた」
「誰でもよかった」
と供述しているらしい。
24日日朝、
愛知県弥富市の中学校で、
14歳の3年生の男子生徒が
同学年の14歳の男子生徒に
包丁で刺され死亡。、
被害者に嫌なことをされ、
恨みを募らせていたと
の趣旨の供述をしているようです。
私の知り合いの方の中学生も、
先日、学校で悪質陰湿ないじめにあっ