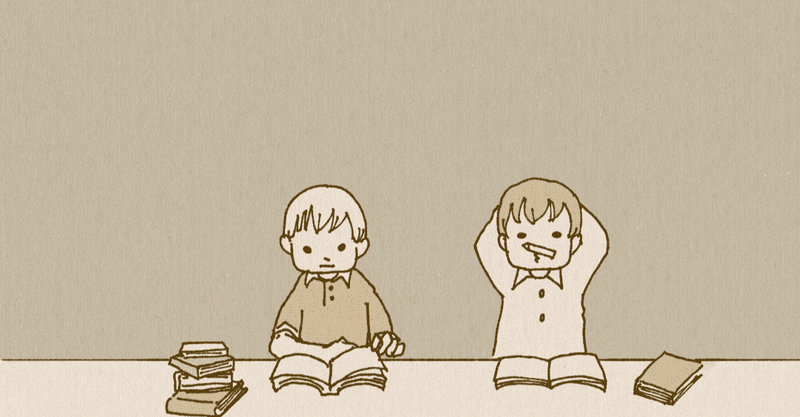
【学習環境】「勉強好き」と「勉強嫌い」の戦い。~環境の力で学習効率を上げる方法~
引っ越ししようか割と真剣に考えているJUNです。
人生を大きく変えるには、「仕事」、「住む場所」、「人間関係」と言いますからね。かといって、何かしらの不満があって引っ越しを考えているわけでもなく、単なる好奇心です。
本日は、そんな話題。
「環境」が子どもに与える影響の絶大さは、これまで散々主張してきました。しかし、常に僕の中には疑問があったのです。
「勉強好き」と「勉強嫌い」がガチで戦ったらどっちが勝つのか。もちろん、殴り合いではなく「環境」の力でですよ。
その世紀の戦いに終止符が打たれましたので、ぜひとも、子どもさんの学習環境を整える際に、参考にしてみてくださいね!
▶「勉強好き」と「勉強嫌い」の勝負の行方。
では、勝負の結果から。結果は・・・。
「痛み分け!!」
です。 なんだそりゃ。と思いました。期待させておいてすみません。実は、「勝敗がつけられなかった。」というのは本当のところ。その理由は、
「集団の大きさが鍵を握っている。」
ところにあります。
ざっくり言うと、
「数が多い方がより影響力を行使し、数の少ない方が影響を受ける。」
ということだからなのです。
メキシコある2つの村の例を紹介しましょう。「#子育ての大誤解(下)」
その2つの村の文化は対照的で、片方は、「攻撃的」、もう一方は、「穏やか」としましょう。両方の村からそれぞれの子どもたちが、中間地点にある学校へ通ってきます。さて、学級内の雰囲気はどうなると思いますか。
これは、もう想像するだけで恐ろしくやりずらい状態になることは間違いありません。なぜか、
「それぞれが、自分の育った文化を主張し合った結果、学級真っ二つ状態。」
となること確定だからです。
では、また違った想定にしてみましょう。
中間地点の学校へ、「攻撃文化村」から1人だけ。あとは「穏やか文化村」出身だったらどうなると思いますか。そうです、この状態だと、
「『攻撃文化村出身』の子どもも穏やかに振舞う。」
ようになるのです。多数派の文化に従うことになります。さらにおもしろいのは、学校では穏やかに振舞っていた彼は、自分の「攻撃村」に戻ると、
「攻撃型人間に元通り。」
となるわけです。しかし、おもしろいのは、「攻撃文化村出身」の子どもが「穏やか文化村」の友達と放課後や休日も共に遊ぶようになるとですよ、
「生まれ育った攻撃文化を失うことになる。」
というのです。
ここから分かることは、生まれた環境がどうのこうのというよりも、やはり
「友達関係の影響力が大きい。」
ということなのです!!
さて、教師の責任が一段と重くなってまいりました。そんな先生方の悲鳴を少しでも軽減できるよう次章を書いておこうと思います。
▶そうは言っても、「教師」の難しさ。
ここまで、「生まれた環境よりも、子どもの友達関係。」という内容を書いてきました。そして、子どもが友達関係をつくるのは、多くの場合「学校」でしょう。ということは、「学校の環境」が勉強向きである方が、子どもの学習への取り組み方を前向きになるということが言えます。
しかし、先生方も分かっていながら難しいこともあります。望ましい環境を簡単に言ってしまうと、
「みんなが学習に対してやる気をもって、前向きにチャレンジする環境。」
を作り上げることが学習効果を上げるためには最適です。もちろん、教師であれば、誰しもがそんな学級を受け持ちたいと望んでいることでしょう。では、なぜ、そのような理想的な学級は早々生まれてこないのか。実は、その原因は、
「子どもの社会的経済地位が広範囲に及んでいる。」
からなのです。難しいのでざっくり言うと、「勉強に対する価値観やモチベーションが多様すぎる。」ことにあるのです。
このような集団を「学習前向きチャレンジ村」にするのは、なかなか難しいです。
「いやいや、攻撃さんを穏やかさんに変えられるくらいだから、頑張ればなんとかなるんじゃん。」
と、思われるかもしれませんが、そこがなかなか歯がゆいところ。ちなみに、みなさんは、「集団」とは何人からだと思いますか?
もちろん、一人は「集団」ではありません。ということは、「二人以上」ということになるのですが、その「集団」の中で「規範意識」が生まれるのは、どうやら「三人以上」です。
どういうことか。
「学級の中に『学習前向き集団』をしこたま集めたとしても、『学習絶対やらない軍団』が3人集まると、そのグループの学習効果はあがらない。」
ということなのです。
そして、現実問題、「学習モチベーションは多種多様。」です。ということは、「学級を1つにまとめる」なんてことは、本当に力のある教師のみぞたどり着ける「神」の領域なのです。
▶まとめ。
本記事では、「集団を的確に捉えてからが勝負!」という内容をまとめました。
もちろん、地域によっては「学習」に対する価値感が似通っているが故、まとまりやすい学校もあるでしょう。しかし、全ての学校で、「学級というのは、1つのチームである。」という価値観を押し付けると、僕たちのような真面目教師は、若干負担に感じるかもしれません。
それよりも、「自分の目の前の子どもたちの価値観を捉え、『みんなが安心できる環境』を目指して、無理なくじりじりと!」という戦術の方が、現実味があるのではないでしょうか。
「環境命!!」という事実を頭の隅におき、理想に向かうのではなく、現実を受け止め、できることから環境調整に励みましょう!!
いただいたサポートは、地域の「居場所」へ寄付させていただきます!
