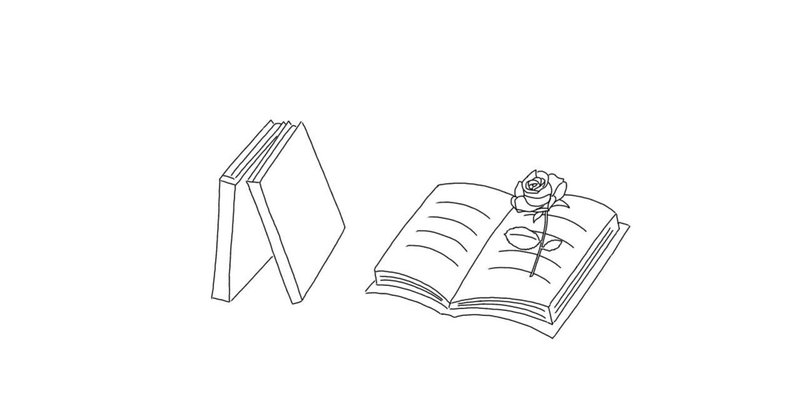
下書きの下から十一番目
「人から勧めてもらったものか、適当に手に取ったものか、重みが全然違う
どうしても噛み砕いているときに進めてくれた人を考えてしまう」
これは父にある本を勧められた時に感じたことだ。
私は小学生の時、図書館が好きだった。だけど小学校6年感の間で、いつの間にか図書館に一人でいることが恥ずかしくなった。明るくワイワイみんなと外で遊ぶことが一番いいことなんだと何も疑いなく思っていた。だから、必死にそうなろうと努めていた。その時は、自分がどうしたいのか、自分が何を感じたのか、なんて考えることなんてほとんどなかった。一般的にこうであるから自分もそう思うんだ。そうしている自分は正しいんだ。と思っていた。
小学生の頃考えていたことは、思い返せば思い返すほど、いまの自分の醜い部分を反映していることを実感する。時々思い出しては、反省したりとても恥ずかしい気持ちになったり。
中学生、高校生で本を読んだ記憶はほとんどない。国語の授業で好きな評論や小説、古文に触れた時はワクワクしていた。だけどそれまで。それ以上探究心はなかった。恋愛に夢中だった。(これまた恥ずかしい。)
そんな高校時代でも、詩集だけは読んでいた。これはトイレにポンっといつも置いてあったからだ。私の家には、整理整頓が苦手な父のせいで?おかげで?そこら中に本が散りばめられている。父は私が高校生の頃、トイレで詩を読むことが習慣だったのだろうか。それはともかく、父は本が大好きである。
大学生になって一人暮らしを始めると、知らないことの多さに圧倒された。どの本屋さんだったか忘れてしまったけど、ある本屋さんの前を通った時に、「本はいろんなことを教えてくれるよ。本の中で起きたことを経験した気になってしまうこともあるよ。」と父に言われたことをふと思い出して、本屋さんに入った。何を読めばいいのかさっぱりわからない。このころはまだ、自分のなんとなく、という感覚をあまり信じていなかったから、好きなモデルさんが好きだと言っていた本を買った。それは小説だった。面白かった。大げさな言い方になってしまうけど、世界が広がった感じがした。それからは本屋さんに行くことが習慣になった。(トイレに置いておくことなんてなかったけど)
大学でできた素敵な友人二人は、本に詳しかった。よくオススメの本を教えてもらってそれに対する感想を言い合った。もう、本を読みながらその感想会で言いたいことをまとめている勢いで、その時間が大好きだった。とにかく、この友人二人も本が大好きである。
こんな感じで本が好きな人に勧めてもらったものをたくさん読んだのが大学一年生だった。
この下書きは、父に勧められた遠藤周作のエッセイを読み終わった後に書いた。恋愛と愛について、あなた自身が知らないあなた自身に気づいているのか、など、横文字を使っていえば、その時の私にとってタイムリーな本だったと思う。いまでも読み返してしまう好きな本の一つだ。
だけどこの本を読む時、時々父がどういう意図で勧めてきたのか考えてしまう。この本を勧めたってことは、あの事件のこと知っているの?この本を勧めてきたってことは私にこういう部分があるから気をつけろよって言いたいの?なんて何度も感がえてしまう。それに少しうんざりして、本屋さんで偶然手に取りたかったな、と理不尽に父を腹を立てたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
