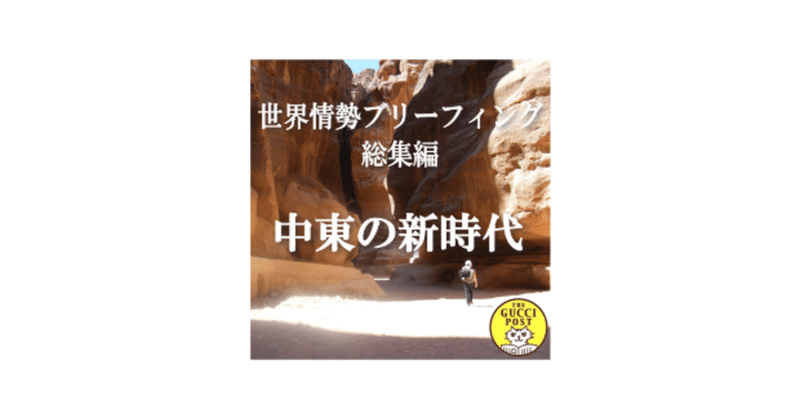
世界情勢ブリーフィング 総集編第3号 中東の新時代 サウジ、イラン、トルコの挑戦
2018年11月16日
The Gucci Postで好評配信中のメルマガ「世界情勢ブリーフィング」の総集編第3号です。
テーマは「中東の新時代 サウジ、イラン、トルコの挑戦」です。
今年10月までのメルマガとブログの記事のうち、中東に関するもので、今読んでも示唆に富む重要なものを網羅的に厳選し、一つに統合した上で大幅に加筆修正しました。分量は約200ページです。
主に最近このメルマガを読み始めた方を対象としていますが、大幅に加筆修正しており、構成も工夫していますので、以前から購読している方にも楽しんでいただけると思います。
冒頭に「中東の基本構造」という書き下ろし記事を掲載しています。その中で、読者の方からのご要望にお応えして、中東を理解する上で役立つ参考文献も紹介しました。
中東は政治の激動が激しい地域です。民族、宗教、資源、権威主義と民主主義・・様々な要素が複雑に絡み、イラン、サウジ、トルコ、エジプト、イスラエルといった大国が莫大な富と武力をもってお互いを牽制し、そこに湾岸諸国やシリア、イラク、クルドなどが巻き込まれ、むき出しのパワーポリティクスが展開されています。世界全体に与えるインパクトも大きく、今や日本にとっても目が離せない重要な地域です。
その変化は激しく、解説書を読んでも最新の状況までフォローできていないことが多々あります。特にサウジ、イラン、トルコの3つの大国は、かつてない変革に挑もうとしており、この1年間のうちに状況が激変しています。
この総集編を読めば、こうした激動を理解し、正確な知識に基づいて今後の展望について考察することができるようになるでしょう。
【目次】
0.中東の基本構造
1.サウジアラビア
(1)サウジアラビア
・「ムハンマド・ビン・サルマンの皇太子就任」(17/6/23)
・「サウジアラビアの新時代(1)」(17/10/3)
・「サウジアラビアの新時代(2)」(17/10/4)
・「サルマン国王のロシア訪問」(17/10/9)
・「サウジ・イラク首脳会談」(17/10/30)
・「ティラーソンの中東訪問」(17/10/30)
・「サウジの強権発動の衝撃」(17/11/14)
・「サウジの文化改革」(17/12/18)
・「サウジの人事異動」(18/3/5)
・「ムハンマド・ビン・サルマン皇太子の訪米」(18/3/19)
・「ムハンマド・ビン・サルマン皇太子の訪米」(18/3/26)
・「サウジの映画解禁」(18/4/16)
・「サウジ・カナダ関係の悪化」(18/8/13)
・「サウジアラムコのIPOの延期」(18/8/27)
・「サウジ記者のトルコでのサウジ総領事館における殺害疑惑」(18/10/15)
・「サウジ記者のトルコでの総領事館における殺害事件」(18/10/23)
・「カショギ記者殺害事件」(18/10/29)
(2)アラビア半島
・「カタールの国交断絶とトランプ政権の混沌(1)」(17/6/14)
・「カタールの国交断絶とトランプ政権の混沌(2)」(17/6/15)
2.イラン
・「トランプ政権の新イラン戦略」(17/10/17)
・「イラン核合意」(17/12/18)
・「イランの反政府デモ」(18/1/4)
・「イラン核合意」(18/1/8)
・「イランの反政府デモ(1):国内政治への影響」(18/1/10)
・「イランの反政府デモ(2):米国との関係」(18/1/11)
・「トランプ外交の先鋭化:イラン核合意の行方」(18/1/17)
・「米国のイラン核合意離脱(1):トランプの思惑とイランの対応」(18/5/15)
・「米国のイラン核合意離脱(2):世界への影響と米国・民主主義の将来」(18/5/16)
・「ポンペオ国務長官のイラン戦略」(18/5/28)
・「イラン制裁の包囲網」(18/7/2)
・「トランプとロウハニの舌戦」(18/7/30)
・「米国とイランの対立と対話」(18/8/6)
・「イラン制裁法の復活」(18/8/13)
3.トルコ
・「トルコのクーデター未遂と非常事態宣言」(16/7/27)
・「米・トルコのビザ発給停止」(17/10/19)
・「米・トルコ関係」(17/11/13)
・「トルコによるシリアのクルド攻撃」(18/1/30)
・「シリアとトルコの激突の危機」(18/2/28)
・「シリアでのトルコ進軍」(18/3/26)
・「米・トルコ外相会談とクルド軍の撤退」(18/6/11)
・「トルコ大統領選挙・議会選挙」(18/6/18)
・「トルコ現代史(1):アタテュルクとエルドアン」(18/7/20)
・「トルコの政策金利の据え置き」(18/7/30)
・「トルコ現代史(2):エルドアンの憲法改正」(18/8/3)
・「トルコ現代史(3):新たなるエルドアンの時代(米国との衝突と通貨危機のリスク)」(18/8/15)
・「トルコリラの下落」(18/8/20)
・「トルコリラの展望」(18/8/27)
・「エルドアンのイラン訪問の可能性」(18/9/3)
・「トルコ中銀の利上げ」(18/9/17)
・「トルコの米国人牧師の拘束」(18/10/8)
・「トルコにおける米国人牧師の釈放」(18/10/15)
4.エジプト
・「エジプトでのテロ」(17/11/27)
・「エジプト現代史(1):栄光と革命」(18/5/4)
・「エジプト現代史(2):大統領選挙」(18/5/9)
5.イスラエル
・「米国のエルサレム首都認定(1):背景」(17/12/12)
・「米国のエルサレム首都認定(2):意図」(17/12/13)
・「米国のエルサレム首都認定(3):影響」(17/12/14)
・「米国のエルサレム首都認定(補足):クシュナーとサウジ皇太子」(17/12/20)
・「米国大使館のエルサレム移転」(18/2/26)
・「安倍首相のイスラエル訪問とネタニヤフ首相のチョコレート」(18/5/11)
・「米国大使館のエルサレム移転」(18/5/21)
・「ドゥテルテのイスラエル訪問」(18/9/10)
6.イラク
・「クルドの独立投票とイラクの進軍」(17/10/24)
・「クルドの独立問題と内戦の危機」(17/11/10)
・「イラク議会選挙(1):『イスラム国』との戦い」(18/6/1)
・「イラク議会選挙(2):ムクタダ・サドルの挑戦」(18/6/6)
・「クルド議会選挙」(18/10/1)
・「クルド議会選挙」(18/10/8)
7.シリア・レバノン
(1)シリア
・「『イスラム国』の崩壊」(17/10/23)
・「ロシア・トルコ・イラン首脳会談」(17/11/20)
・「プーチンのシリア・エジプト・トルコ訪問」(17/12/18)
・「シリアをめぐるグレートゲーム」(18/4/9)
・「米英仏のシリア攻撃」(18/4/16)
・「トルコ・イラン・ロシア首脳会談」(18/9/10)
(2)レバノン
・「レバノンの混乱」(17/11/13)
・「レバノン現代史(1):『歴史的シリア』と宗派体制」(18/6/8)
・「レバノン現代史(2):独立と内戦、シリアの盛衰」(18/6/13)
・「レバノン現代史(3):ヒズボラと総選挙」(18/6/22)
【あとがき】
中東は、我々日本人にとって遠い地域です。その遠さは、物理的のみならず心理的にもかなり大きいのではないかと思います。
その歴史、文化、宗教・思想は、日本とまったく異なります。欧米も遠い地域ですが、それでもその価値観や文化はなじみ深いものです。日本が自ら積極的に取り入れたこともあるでしょう。
中東には、そうした共通の精神的基盤がありません。専制的な王政、軍のクーデター、ユダヤとアラブ、イスラエル・・こういったテーマは多くの人にとって別世界の話のように聞こえるのではないでしょうか。
また、イスラム教の前近代的な性格と原理主義、武力紛争、テロの問題は、とても理解できないというネガティブなイメージを多くの人に与えていると思います。
さらに、欧米との関係の複雑性がさらに理解を困難にさせています。冷戦期のパワーゲーム、資源の争奪戦、そして今なお米国、ロシア、欧州など域外の大国は様々な形で自らの都合で地域に介入し、絶えざる合従連衡を生じさせています。
しかも、日本では中東に関する情報が極めて限られています。たとえば米国でワシントン・ポストなど代表的な新聞を読むと中東に関する報道が大きな部分を占めています(その代わりアジアに関する報道は極めて少ない)。日本から見える風景は、日本企業や日常生活に直接関わりのあるものに重点が置かれているため、米国から見える風景、それは世界の重心がどこにあるかをほぼそのまま示したものといえますが、それとはズレていることが分かります。
また中東に関するニュースは、他の地域に関するニュースと比べて客観的で公平中立といえるものが少ない状況にあります。国家や組織など関係者が意図的に情報を操作しているからです。それはメディアやNGOも例外ではありません。このため「ニュースを読むリテラシー(能力)」が他のトピックと比べてよりシビアに求められます。
このように非常に難解な地域です。しかしこの地域は、今や私たちにとっても座視することができない、非常に重要な地域になっています。
かつては石油危機を契機に、資源外交の観点から重視されました。近年ではこれにテロとの戦いが加わっています。また、欧米の外交戦略とイスラエル・ロビーなどを見極めるためには中東の動きを知る必要があります。さらに近年は、トルコの工業化、サウジの改革、イランの制裁解除(これは状況が変化)により、日本企業にとって新たなビジネスチャンスも生まれています。
かつて日本の外務省では、アラビア語使いや中東専門家は傍流に追いやられ、人気もありませんでした。それが、近年は、存在感が急速に大きくなり、もはや花形のポジションになっています。中東を知らずして米国や外交を語ることはできない・・という雰囲気すらあります。私が官庁に入った90年代と比べると、時代が大きく変わったことを実感します。
実際に現地に行ってみると、中東の人々の親日感情に驚かされます。私がイランを訪問したとき、当時放送されていた数少ない外国のテレビ番組が『おしん』と『キャプテン翼』でした。
この二つのコンテンツの人気はすさまじく、『おしん』が放映されている時間帯には通りから人が消え、最高指導者(当時)のホメイニ師の演説にも人がこないので、ホメイニが激怒した、というエピソードがあるほどです。私もイラン人の子どもたちからあるキャラクター(私の名前と響きが似ている選手)の名前で連呼され、なぜかどこに行っても人気者でした。
イラン以外の国でも、日本に対する尊敬の念やシンパシーを強く感じました。当時の私には中東は「よく分からない」「危ない」「怖い」というイメージがあったのですが、その固定観念は覆され、地域に対する猛烈な興味と愛着がわきました。私の海外に対する好奇心を開いてくれたのは中東だったような気すらします。
かつてフランクリン・ルーズベルトは、世界恐慌の最中に大統領に就任した際、「我々が恐れなければならないものはただ一つ、恐れそのものである」と述べました。人間は、未知なこと、分からないことに恐れを抱きます。これは中東を見る目にも通じる面があると思います。
知識を得て、実際に現地を見て、人々と交われば、私がそうであったように、中東に対するイメージは変わるでしょう。この総集編とメルマガがそうした体験を得る上で少しでも役立つことを願っています。
※記事を購入すると、本編のPDFファイルがダウンロードできます。
ここから先は
¥ 1,430
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
