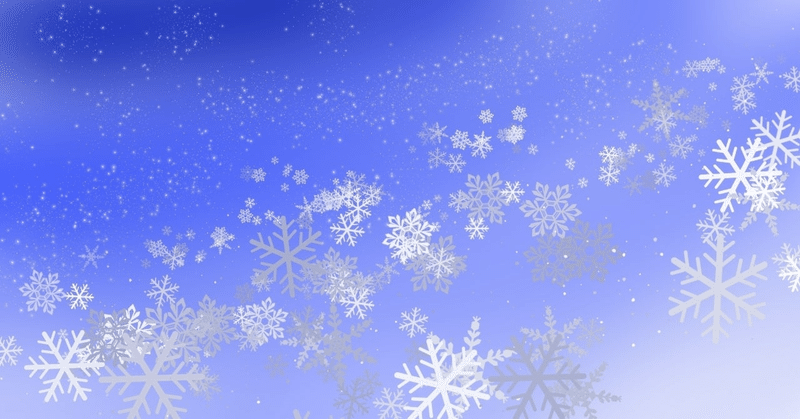
脱恋社会 前編
あらすじ
恋をしなくなった未来の若者たち。結婚相手はAIによって選出される。フリーライターをしている主人公の紫乃は、AIが選んだ清雲という女性と出会い交際を重ね、やがて結婚を決意する。性交の経験のない紫乃は、子作りのトレーニングとして風俗店に通いはじめる。そこでトレーナーの雪恵と出会い、彼女の魅力に吸い込まれていく。やがて、雪恵のことばかり考えるようになった紫乃は、清雲がそばにいても心ここにあらずの状態となり、トレーニングのない日も会いたいと思うようになる。そして、紫乃は雪恵につきまとうようになり、彼女が店を辞めると取材と銘打って居場所と突き止めようとするのだが、そこである真実を知る。
プラントノベル
1:温泉
夜空を見上げて露天風呂に浸かる。火照った体には吹き抜けていく夜風が心地よい。赤く光るペテルギウス、中央に三ツ星、三角形が二つ重なり合ったような形、そこから伸びた二本の腕、オリオン座だ。温泉だけではなくこの星座も満喫して帰りたい。
「気持ちいいよね」
「うん、気持ちいいね」
両脇にいる喜伝と柚都も、僕と同じように岩の壁面に背中をつけて、足を伸ばして頬を赤らめているようだ。もう十一月も下旬なので周囲の木々も葉を落として裸になろうとしている。時折その木々の脱ぎ捨てた葉が、ヒラリと風に乗って宙を遊び、力尽きた頃に湯船に舞い落ちてくる。
晩秋の箱根路にライター仲間の三人でやって来た。黄金色に燃える仙石すすき草原に癒され、北風が水面を撫でる芦ノ湖を眺め、落ち葉を踏みしめながら箱根神社を参拝して、この温泉宿にやって来た。
夜空を眺めていると喜伝が僕の脇腹を突っついてきた。
「ねぇねぇ、柚都のオッパイ大きいね」
僕は柚都を直視しては悪いと思い、前方に目を向ける。目線の先にいる初老の女性が恥ずかしそうに腕で体を隠す。
「そんなことないよ、喜伝のだって大きいじゃん、紫乃見てあげて」
今度は喜伝を見ないように視線を上に向ける。僕が、もう一度夜空を見上げるとその様子を見て二人はゲラゲラと笑いはじめた。
正面にいる初老の女性が怪訝な目でこちらを見ていたので、
「すいません、騒がしくて」
と声をかけると、その女性は、
「いいえ」
と小さく返して、頭に載せていたタオルを広げて体を隠しながら湯船を上がっていった。そういえばさっき洗い場で僕たち三人が背中を流し合っていたときも、その女性は端の方で体をかがめて隠すように洗っていたことを思い出した。
「あんたたち、どこから来たの」
近くにいる白髪頭の男性が声をかけてきた。
「東京からです」
と僕が答えると、
「まあ、さっきのオバサンが恥ずかしがるのもムリないよ。俺だってこんな若い姉ちゃんたちと一緒に風呂に入れる日が来るなんて思ってもみなかったから。まったく、いい時代になったもんだよ。だからもう最近は温泉に来るのが楽しみでさぁ」
笑いながらその男性が言うと、喜伝と柚都もつられて笑っていた。
平成時代の中期に台頭してきたジェンダーフリーという考え方が加速度をつけて拡大し、現代では、ほとんどの施設や物が男女分け隔てなく使われている。学校生活においても昔は男子と女子で更衣室が分けられていたらしいが、僕たちの世代は更衣室などなく、男女同じ教室で着替えをしていたし、トイレも共同で使っていた。
性差をなくせば男女分けて設備投資する必要もなくコストもかからずにすむ。なので、最近では公衆トイレや温泉施設も、ほとんどが男女兼用になっている。これによってネット上に蔓延していた盗撮動画やサイトは淘汰されていったという。
それにしても、見知らぬ男女が一緒に温泉に入るなど、ひと昔前の日本人が聞いたら、とんでもない時代が来たと思うだろうか。しかし、断じてそれは違う。
僕たち日本人は、千年以上に渡る長い歴史の中で既に経験してきたことである。中世の頃、混浴の温泉など珍しくなく、江戸の町人たちも男女ともに丸裸で銭湯に入っていた。男女が分かれて公衆浴場入ることが一般的になったのは近代以降の歴史にほかならない。
ちなみに現代でも中世の頃の慣習に用いて、男性は女性の裸体を凝視してはならないということになっている。
湯船から上がり脱衣所に立つと、少しフラフラしていることに気づいた。額に汗がにじんでいる。疲れをとるために温泉に入ったのにかえって疲れていないか心配になってしまう。
秋風が冬を連れてきているのだろうか、さっきからゴウゴウと音をたてて吹き荒れ、結露した窓を叩いている。僕たち三人は、湯気の上がるほんのり赤く染まった肌を拭き浴衣を着ようとしていた。
「ねぇさっきのオジサンのアソコ見た」
「見ちゃったグロテスクだったよね」
喜伝と柚都がさっき浴場で声をかけてきた白髪頭のオジサンのことを話している。
僕たち若者世代にとっては髪の毛、眉毛、まつ毛以外の毛はムダ毛と認識している。つまり、ツルツルが普通である。なので、さっきの男性のように未処理の人の体を見ると血の気がひいてしまうのだ。男性でも肌がツルツルなのでスカートも履く。
今やロングスカートを履くことは珍しくないし、男子高校生たちは膝丈までのヒラヒラのスカートを履いていたりしている。
お年寄り世代の人にとっては男性の履くスカートには抵抗があるらしいが、僕が今から着ようとしている浴衣だって、日本古来よりある物だが、ワンピースのように見えなくもない。似た様なものは昔から男性も着ていたのだ。
つまり、現象や流行というのは直線上に進化してくものではない。歴史は繰り返されるという、そして、それはらせん階段を昇るように同じような場所を辿りながらも、着実に進化していくものではないだろうか。
2:信長さん
箱根の小旅行から帰ってきて翌日からは仕事に没頭した。僕はフリーライターをしていて、得意分野は昭和と平成の歴史だ。特にこの時代に隆起した情報通信産業は現代の社会に大きな影響を与えており、大学・大学院時代に夢中になって勉強した。
数日かけて原稿を書き終え出版社にデータを送信した後は開放感に浸り、しばらくボーっとしたり、ゲームをして遊んだりしていた。ああ、この瞬間がたまらなく心地よい。なんて思っていたら鈴木信長さんからメッセージが届いた。
そのメッセージを見ると今日の夜一緒にメシを食おうというものだった。ふと、時計を見る。約束の時間まであと一時間程しかない、僕はイスから飛び上がり、慌てて身支度を整える。部屋着から外出用の服に着替え、寝ぐせを直し、ファンデを塗る暇はないのでスッピンのまま家を飛び出して駅まで急いだ。
ここ数日、ずっと家で仕事をしていたから電車に乗るのは久しぶりだった。山手線は来年から半浮遊の線路に変わるらしく車内広告で大きく謳っていた。恵比寿駅で降りて夕暮れの街を僕は走った、相変わらずこの街は飲食店が多い。僕は、信長さんが指定した居酒屋に先に入って待っていなければならない。とにかく彼の誘いを無下に断るわけにもいかず、遅刻などありえない。その店に入って狭い店内を見渡して姿がないことにホッとしてカウンター席に腰を下ろした。
それからほどなくして信長さんはやってきた。二人きりで酒を飲むなど初めてだ。彼は酒が回り出すと僕が書いた原稿を褒めてくれた。面白い特集記事になりそうだとか、目の付けどころがいいとか、背景の画像の雰囲気が出ているとか。僕たちのような現代のライターは文章だけではなく、背景や挿画までプログラミングして提出している。AIが進化してもそれを操るのは人であり、センスを問われるのも人だ。
「ここ最近ずっとリニアが通らなかった都市の特集ばかりだっただろ」
「ええ、どの都市もジリ貧でしたね」
「正直、飽きてたんだよ。だから今回のお前の記事は良かった」
信長さんは僕がお世話になっている出版社の社長さんだ。彼の経営する信長プレスは出版業界では新進気鋭の存在であり、そのなかでも僕が記事を書いた『楽市楽座』という雑誌は世相を風刺するもので、この会社のフラッグシップでもある。
「キラキラネーム世代の改名かぁ」
「はい、ちょうど僕の母が改名したところなので記事にしてみました」
「小川のお母さん、どんな名前なんだ」
「円に踊る曲とかいてワルツという名前だったんです」
僕は指で漢字を書いてみせた。
「ちなみに父は騎士と書いてナイトと読みます」
「まぁ俺たちの世代にはそういう名前の人が多いよ」
「歳をとるにつれて、それ相応の名前に変えたいみたいで」
「昔に比べて手続きも簡単だしなぁ、俺も改名するか」
信長さんの言葉に僕が驚いた顔をすると、冗談だと言わんばかりに笑ったので、僕も合わせて笑ってみせた。
キラキラネーム世代の子供にあたる僕たちの世代は日本語の語感、響きの美しさを強調する名前が多い。シノ、キデン、ユズトのように、国際化社会の中で、日本人であることを意識する機会が増えたためともいわれており、男女分け隔てなく名前が付けられているという特徴もある。
「あの喜伝と柚都の記事はまだまだ甘い、独りよがりなところがある。これを機会にお前は伸びろ、あの二人の手の届かないところまで行け」
信長さんはそう言って僕の背中を叩いた。喜伝も柚都も僕に勝るとも劣らないライターなのだが彼女たちの記事が甘いとは、やはり彼の見る目は厳しい。遠回しにお前もまだまだと言われているような気がして、酒が回った体でも背筋が伸びる思いだった。
二・三時間飲んで、店の前で信長さんと別れた。僕は鼻歌を唄いながら駅前の商店街を歩く、僕の書いた記事が高く評価されたことは嬉しかった。陽はすっかりビルの谷間に隠れてしまったけど、空を見上げても箱根の温泉で見たような星空はなかった。
その代わり相も変わらず巨大な広告があった。
昭和・平成の頃にビルの屋上に取り付けられていた巨大な看板は姿を変え、スペースアートという空をキャンバスに画像や動画を投影するものへと変化している。食品、金融、家電、様々な商品の宣伝がせわしなく切り替わり都会の夜空を彩っている。
そこに婚活データバンクの宣伝が映ると僕は思わず足を止めた、手を繋ぎ微笑む男女の画像に、データが導く素敵な出会いと明るい未来、という御馴染みのキャッチフレーズが載っている。僕はそれをフワフワとした頭で、夜風に吹かれながら、ただぼんやりと眺めていた。
3:婚活データバンク
ステンドグラスに陽がさしている。店内には木目調のテーブルやイスが置かれ教会を思わせるような造りだ。さりげなくショパンがBGMに流れているところがいい。
長い耳を揺らして白いシャツと黒いスラックスを身に付けたウサギが僕の前で一礼してブレンドコーヒーを置いて去っていく。僕はそれを口に運ぶ、もちろん味などするはずもない。
「いいなぁ、いいなぁ、紫乃、いいなぁ」
そういって柚子をモチーフにした柚都のアバターが手足をバタバタとさせている。僕と喜伝は、自分のアバターにアニメのように大きな水滴を頭に垂らしてみせた。
「柚都のところにも、もうすぐ届くと思うよ」
喜伝が笑いながらなだめた。
現代では、三十歳が近づくと婚活データバンクからお見合い写真が届くことになっている。届いたら三人とも見せ合う約束をしていて、前回は喜伝が見せてくれた。僕のところにも届いので、その写真を彼女たちに披露するため仮想空間に入室した。
婚活データバンクとは国営の結婚相談所といったところだろうか。そこに個人のデータを十代のころから入力していく。
例えば、趣味や特技、自覚している性格はもちろんのこと、体験したことや経験したことから何を学んだか、どう感じたのかをポジティブとかネガティブとか関係なく正直に入力していく。
また、芸術なら何が好きか音楽か絵画か、音楽ならばどんなジャンルが好きか、読書や映画はどんなものに感銘を受けたかなどなど、その人の細かい情報を集めて、個人のビックデータのようなものを形成し、それを基にコンピューターがマッチングをおこない、その人に適した結婚相手を割り出すというもの。
あくまでも、フィーリングの合う相手を探すものなので、相手の容姿や財産を目的にすることは出来ない。
僕はアバターに指でピストルを作らせ、白い壁に向かって撃った、するとそこにドロンと煙を立てて額縁に入ったお見合い写真がアップされた。
「鈴木清雲さん、シンクタンクで働いているらしい」
黒く長い髪、肌はそれほど白くない。でも、それゆえに健康的な感じがするし、何よりもこの人には知性のある雰囲気が漂っているというのが僕の第一印象だ。
昔はお見合い写真というと、男性はスーツ、女性は振袖を着て写っていたらしいが、性差をなくす現代では男女とも婚活データバンクから支給された制服を着て写ることになっている。紺のスラックスに水色のシャツ、その上にグレーのカーデガン羽織っている。きっと、この清雲という人も、今頃同じ服装をした僕の写真を見ていることだろう。
「なんか清純派って感じだよね」
「シンクタンクにお勤めって。要するにエリートってこと」
「裏表激しそうじゃない」
「ああ、わかる。顔で笑って腹の中は煮えくり返ってるタイプ」
喜伝と柚都の反応はイマイチだ。え、何、素敵な人って喜んでくれると思ったのだが。
「でも、会ってみないと、どんな人か判らないだろ」
僕は反論したのだが、
「ちょっと何、かばってるわけ」
「まだ会ってもいないのに」
「昔はこういう女がモテたんだって」
「やだ紫乃、恋しちゃったの」
なんだか、エスカレートしてしまったようだ。
「そういえば、喜伝はお見合いどうだったの」
僕は話題を変えてみた。
「ああ、あれ断わっちゃった」
喜伝のアバターが腕組みをした。
「なんか紹介された人が失業しちゃったらしいよ」
そう言って、柚都のアバターが柚子レモンケーキをパクっと食べた。
「工場で働いてたんだけど、ロボットに仕事をとられて解雇されたって。まぁ今どきそんな人って珍しくないけど。でも、なんかがっかりした。夢がないっていうか」
喜伝はそう言い終えると、アバターは頬杖をつき、ストローで氷をかき回していた。
現代社会において、ロボットに仕事を奪われる人が後を絶たない。政府はこれを見越して、数年前から全ての国民に毎月金銭を給付するベーシックインカムの開始を検討しているのだが、未だに実現の見通しは立たず、既存の失業給付に頼らざるを得ない状況だ。
その後は話が脱線して、恋が流行っていたころの時代を揶揄するような話を三人でして盛り上り、それが飽きたころに仮想空間から退室した。
僕たちの世代は恋をしない、ゆえに脱恋世代と呼ばれている。
性差をなくす教育をしたからだ。仮想空間ばかり使っているから、現実逃避している。などと年寄りたちは批難するが、しかしあの恋という自己中心的な行為を肯定する気にはなれない。
なぜ、相手の良いところばかり見ようとするのか。なぜ、一時的な感情に任せて行動するのか。
見た目や表面的な部分に囚われて心を燃やすなど他者への妄信であるとしか言いようがない。こんなことを言えば、冷血な人間に思われるだろうか、でも、そんな僕たちでも愛は受入れる。
愛は恋と違って普遍的だ。恋は自らの願望を他者へ求めてばかりいるが、それに対して愛は様々なものに与えることができる。家族を愛す、仲間を愛す。人に限らず植物や動物にも与えられるし、仕事や芸術、あるいは思想といった無形のものにも与えられる。
また、愛は享受することも出来て、それによって人は守られ育っていくのだと思う。
正直に言おう、恋はダサい。恋の話など聞いただけで眉間にシワが寄ってしまうし、背中のあたりがムズムズとしてしまう。
でも、お爺ちゃん世代の若い頃、一九九〇年代の音楽シーンはラブソングばかりだったというのだから驚きである。大人たちが必死になって若者の恋心を煽り、それは正しい事だと正当化し、そのような唄を作り、CDとかいう円盤に吹き込んで、それが飛ぶように売れていたというのだから驚きである。
テレビドラマもまた然り、当時は男女の恋心を基軸に物語を展開するものが多く、トレンディードラマといった括りをしたそうだ。
つまりこの頃の人たちは、恋をすることを当然のことのように考えていて、むしろ、しない人は変な人ぐらいに思っていたのだろう。
僕たちの世代にも恋をする人はいる。
それはどういう人かというと、昼間から路上に座り込んで酒を飲んだり、些細なことで言いがかりや、因縁をつけたりする人。
他人の物を平気で盗み、心身を傷つけるようなことをしても何食わぬ顔をしている人たちだ。
そういう人たちは自らの勝手な思い込みを尊重するので、恋をして、結婚して、子供を作る。
でも、その恋という魔力が解けてしまうと、次第に罵詈雑言が増え、やがて暴力をふるうようになり、離婚してしまう。これが現代において、恋愛結婚というヤツをする人間の顛末である。
現代ではお見合い結婚が主流である。僕のように婚活データバンクを利用する人が多い。そして、恋をしない風潮は日本のみならず、先進国で同じような現象が起きているのだ。僕は将来的に恋をしないことが、グローバルスタンダードになっていくと思っている。
婚活データバンクは比較的新しい国営機関である。僕らが幼い頃に設立されたのだから二十数年前に出来たものだ。
当初は求婚者の紹介はせず、僕らが入力したデータの管理のみをおこなっていた。数年前から、そのデータのマッチング作業を開始し、求婚者の紹介及び仲介もおこなわれるようになった。あくまでもこの機関が対象としているのは僕たち以降の世代である。
設立の目的は持続可能な婚姻世帯の増加と深刻なる人口減少への歯止めとされている。
昭和の末期から平成にかけて我が国では自由に恋愛を謳歌し、その上で愛を育み結ばれることこそが男女における優美なる姿であるとされてきた。僕は大学生頃のレポートでこの時代を自由恋愛時代と華やか言葉で括ったことがある。
しかし、この時代が現代にもたらしたものは、未婚老人の大量発生と膨大なる離婚件数なのである。自由とは、その雄大且つ甘美なイメージとは裏腹に残酷さを秘めたものだ。
そもそも、恋愛というのは学問や運動と同様にその資質により左右されやすいものである。その才覚に恵まれた者は、容易に成果を出し、そうでない者は辛酸を舐め続けることになりかねないのだ。
それにもかかわらず、恋の洗脳を受けた世代は、まるで呼吸や睡眠のごとく、すべての者が出来ることのように扱ってしまっていたのだから。
平成の終り頃には、これらの恋の実らぬ人たちは恋愛弱者と呼ばれていた。もちろん、未婚老人大量発生の理由はこれだけではない。ライフスタイルの多様化、経済的不安、地域社会というコミュニティーの減退など、理由は多々あったようだが。
また自由な恋愛をすれば、別れることも自由ということになるようで、離婚件数も多い。無論、心身に危害を加えられたり、生命の危機を脅かされるようなことがあれば、別れを選ぶことは当然かもしれないが。
ただし、そもそもの出会いが恋という魔力のようなものである限り、解けた後は、配偶者に幻滅したり、極度な我慢を強いられることになりかねないのだ。
そんな結婚生活は、想像することすらお断りだ。生涯の伴侶となる者は、もっと冷静かつ論理的な根拠に基づいて探すべきである。
さらに言えば、離婚してしまったかつての夫婦にも、この国のどこかには、その別れた相手以上に相性が良く、共にトラブルを乗り越えて生きて行けるパートナーがいるかもしれないのだ。
婚活データバンクは、最新のテクノロジーを駆使し、それぞれの個人のデータから相性の良い相手を導き出してくれる。皆に等しくチャンスが与えられ、結婚後のトラブルも少なく離婚件数は激減するとの予測が出ている。
また、喜伝のように一度断ってしまっても、次のチャンスが与えられるまで待てば良いのだ。利用は決して強制ではないが、これらのメリットから利用者は多い。
そして、国家はもう一つ僕たちの世代に対して、巨大なプロジェクトを用意していた。それは、未来を担う者たちとして、日常生活をより良い健康な状態で維持させるというもの。
僕らは子供の頃から国が配布するサプリメントを飲んでいる。若いころから飲み続けると、風邪の予防、生活習慣病の緩和、老化の抑止に効くという。
これは、夢咲ハツラツサプリメントというもので、通称、夢サプと呼ばれている。
健康でなければ、明るい家庭を築くことも、職務に邁進することも難しいだろう。いつの時代も体が資本だ。
しかし、これは強制ではないため、低所得者層や反社会的な者は購入していないことが多い。そして、このサプリメントには、最近妙な噂を聞くことがある。
それは、夢サプを継続的に飲んでいると、恋をしたくなくなるという副作用が起るらしい。あくまでも都市伝説に過ぎないのだが。
4:お見合い
几帳面に刈り取られた芝生、丸みを帯びた上品な植木たち、シアンの空には絵の具を薄く引き伸ばしたような雲が所々にかかり、冷めた空気の中には、もう冬の香りが混ざっていた。
今日は日曜日なので、この中庭には僕と同じ制服を着た人たちをチラホラと見かける。初冬の穏やかな日差しの下で、若い男女が池にかかる小さな橋から鯉を覗いてみたり、野点傘の下のベンチで談笑したりしていた。
僕は、正午頃に婚活データバンクが指定したホテルに両親とやってきた。まずは、そこの職員から、形式的なあいさつがあり、その次に両家の紹介があり、その後は食事をしながら、職員が取り持つようにして、当たり障りのない話をし、食べ終わった頃に二人で外に出ることになった。
清雲は、今日の空のようにさわやかな雰囲気の人だった。こういう清々しい人と一緒にいると、この先に続く未来が明るく開けていくような気がしてくるから不思議だ。
実際に見た彼女はお見合い写真と変わらないビジュアルをしていた。たまに写真と実物が違っているというトラブルがあるらしいが、彼女はありのままの姿で写っていた。
僕と同じくらいの背丈に、パッチリとした瞳、鼻筋はクッキリと通っているけれど高すぎず、尖った鼻先に繊細さを感じる。口は少し大きい気がするが不快に感じるほどではない。
お互いに、しばらくは何も話さず肩を並べて歩いていたので、周囲の人の話声や風の通り抜けていく音が耳に届いていた。黙っていた僕に清雲が不意にカーデガンの刺繍を指して、
「これカワイイですよね」
と言ったので、僕は微笑みながらうなずいた。
胸に桃色の糸で婚活データバンクのロゴが縫ってある。僕が緊張していると思い、彼女は気をつかってくれたのだろう。
しばらく何も話さなかったのは、清雲の容姿に見とれていたからでも緊張していたからでもない。ついさっき知ってしまった事実をまだ受け入れられずにいたからだ。
待ち合わせ場所であるホテルのロビーに先に着いたのは僕たちの家族だった。父と母に挟まれてソファーに座り傍らには職員が立っていた。僕はコンパクトを開いて、メイクをチェックした。十代二十代前半の男の子たちのようにリップやマスカラは塗らないが、大事な席ではファンデを塗ることぐらいはもはや常識である。
このホテルは昭和初期の大邸宅をイメージしているらしく西洋風の造りの中に和が織り込まれている。天井の模様は万華鏡のような柄で一定の時間が経つと姿を変えるようになっていて。エントランスを歩くポーターの姿は学ランの上にマントを着て、学帽をかぶり。受付の女性は、モガハットをかぶり、帽子と同じ色のワンピースを着て腰元はリボンでしばられていた。
しばらくはその光景をぼんやりと眺めていたが、それに少し飽きた頃に清雲の家族がやってきた。
「どうもすいません、遅くなりました」
職員の陰に隠れて聞き慣れた声がしたので、僕はその声の主を見た。清雲と並んで立っていたのは信長さんだった。
ホテルに併設された和食レストランの個室に通されて僕たちは向かい合って座った。真ん中に僕と清雲、僕の右に父、その向いに信長さん。左に母、その向いの席は空いている。
信長さんの家は子だくさんだと聞いたことがある。一人っ子が当たり前の時代に、三人の子供がいるのだと。そして、その末っ子が清雲だったようだ。信長さんが僕を居酒屋に呼び出したあの日、彼はお見合いの話など一切していなかった。でもあのとき、もう信長さんは今日のことを知っていたのだろう。
僕の記事が褒められたのは、このことがきっかけなのだろうか。
会食の間、僕は動揺し続けていて、ご馳走を食べた気になどならなかった。
とにかく周囲に悟られないように茶碗蒸しや天ぷらを口に運んだ。うちの母が今日は天気が良いけれど明日からは崩れるとか、この近くにある神社は参拝客が多いとか、そんな話を始めて信長さんも軽やかに応じていた。
僕も適度にうなずいていたが、しかしどうしてもこの清雲との出会いを素直に受け止められずにいた。
自宅に帰った後、ベッドの上に寝転んで今日のことを思い出してみた。ホテルの中庭を清雲と歩いて野点傘の下にあるベンチが空いたので、どちらからともなく腰かけた。
一緒に歩いていると肩が並ぶほどだったのに隣に座った清雲は随分小さくなった。彼女の髪型はお見合い写真とは少し違っていて、長い髪にゆるくウエーブがかかりそれを後ろで束ねていた。
まだ清雲とは何を話していいのか分らず、下手な事を言うわけにもいかず、なんだかお見合いというヤツは気まずいものだと思いながら、池の橋へと続く石畳をわけもなく眺めていた。 ふいに視線を感じたので目線を上げると清雲が僕の方を見て微笑んでいた。
「さっき驚きました。父と小川さんが知り合いだったなんて」
「僕はもっと驚きましたよ」
と返すと清雲は笑い、つられて僕も笑った。少し気持ちがほぐれた気がした。
その後は、お互いの仕事の話をして、それから学生時代の話をした。僕が高校・大学時代にeスポーツをしていた話をしたら、彼女はその話を興味深く聞いてくれた。そして趣味の話になった。清雲は星が好きだと言っていた。
「今度、プラネタリウムに行ってみませんか、行ってみたい所があって」
こういうときに誘われるのを待つだけの女性は今の時代にもいるけれど、僕はアプローチしてくれた清雲の前向きな気持ちを、快く受け入れたいと思った。
初めて婚活データバンクの存在を知ったのは中学一年のとき、入学式後の教室で担任の先生から聞いた。
「みなさんにとって結婚なんてまだ遠い先のことかもしれませんが、今のうちから少しずつでもデータを入力してきましょう」
そう先生から言われ、事あるごとに入力していった。あの頃から、コツコツと入力していったデータを見返してみると自分の半生を見ているようでもある。
そのデータを基にサーチした結果辿り着いたのが信長さんの娘とは、なんとも世間とは狭いものである。清雲と結婚したら、今以上に信長さんにビクビクしながら生きていくのだろうか、でも彼女の人柄はとても良かった。
結婚なんて案外こんなものなのだろうか、生まれる前から運命の人というのは決まっていて、この果てしなく続く人生の中で巡り合うのかもしれない。きっとこの出会いには深い意味があって、共に力を合わせていきてゆけという天のお告げなのだろうか。
そんな神事深いことを考え出した頃には、僕はもうウトウトとしていて、気がつけばそのまま布団に潜りこんで眠りにつこうとしていた。
脚にフィットした細身のパンツがスタイルの良さを際立たせている。ブルゾンを着て、髪を下ろした姿で歩く清雲を横目で見ながら、僕はロングスカートにして良かったと思った。
先日のお見合いのときには、同じ制服を着ていたので僕の足が妙に短く見えた。足が短いのはコンプレックスだから、ロングスカートを穿いて誤魔化してみた。
最寄り駅からプラネタリウムまで歩きながら、クリスマスをお互いにどのように過ごしたかという話題になった。
僕はその日は仕事をせず、昼間少しだけ聖書を読んで、夕食は両親とチキンを食べ、夜は仮想空間で友人たちとキリスト教について語り合った。清雲は仕事だったそうだが、家に帰ってから家族とケーキを食べ、遊びに来た姪っ子たちにプレゼントを渡して過ごしたそうだ。
「バブル景気の頃の日本人は今とは違う過ごし方をしていたそうですね」
「ええ、赤坂にある有名なホテルは毎年満室になっていたそうです」
清雲の問いかけに僕がそう返すと彼女は吹き出した。
「でも、あの頃の日本人は勤勉ですから、きっとクリスマスもビジネスに結び付けようと躍起になっていたんでしょうね」
聖なる夜が、精なる夜と化していたあの時代を茶化すことなく、勤勉さゆえの現象と結びつける清雲は聡明な人なのだと思った。
新しくできたプラネタリウムは、年末ということもあり混みあっている。僕たちは長蛇の列に並び、一時間程してようやくシアターに入ることができた。ギリシャ神話と北斗七星にまつわる映像を見たあとに、今話題の無重力体験となった。
重力がなくなり体が自然に浮き上がると、シアターが歓声で満ちた。僕の体はグングン上昇していった。
天井に背中がくっつくと、その状態で清雲を探した。彼女は座席から半分ほど浮き上がったところで、グルグルと宙返りをしていた。僕は泳ぐようにして近くまでいくと、
「小川さん、助けて」
と彼女は手を伸ばしてきた。
僕はその手を掴もうとするが、流されてしまう。
グルっと一回転して体制を整えて、再度泳ぐようにして近づく。何度か、すれ違いながら、その都度腕を回したり、体を伸ばしたりして、清雲に近づきやっとの思いで彼女の手を握りしめた。
「ああ、助かった」
そう言って清雲は笑った。
気が付くとスクリーンには太陽系の惑星が映っていた。
僕たちは、その惑星たちの真ん中で、まるで周囲の者たちを照らすように、誰よりも明るく笑い声を上げながら両手を握って見つめ合い、フワフワと浮かんでいた。
5:風俗店
街路樹の葉が露を嫌うように水玉を落とし、雨上がりの香りを放つ。僕は乾ききらない路面を歩きながら、空を見上げた。陽はもう一番高い所まで上がっているから、肌を刺す光が強いのだと思った。今年は例年よりも早く梅雨が明けたせいで、真夏日が長く続くそうだ。
あのプラネタリウムの後から、僕と清雲の距離は急速に縮まっていった。
正月には、eスポーツを楽しみ、二人でオリンピックでも使用されたゲームソフトをクリアした。
春には薄紅色に染まるソメイヨシノの並木道をリアルの世界で歩き、初夏には新緑の輝くハイキングロードをお互いのアバターでサイクリングした。
フリーライターをしている僕が清雲の休みに合わせ、現実と仮想両方使えば二人が会うことは容易であり、会うたびに僕たちの仲は深まっていった。やはり、婚活データバンクのサーチ力は凄かった。
そして、僕が清雲にプロポーズする日がやってきた。東京湾の波音を聞きながら満天の星空を眺めた後、天の川の下で。清雲は微笑みながら、うなずいてくれた。
スペースアートが映し出す幾千もの星に見守られながら僕はそのとき初めて清雲の細い体を抱きしめた。
そのプロポーズから半月後、僕は風俗店にやってきた。僕たち脱恋世代は結婚するまで性交はしない。
平成時代の人が聞いたら驚くだろうか。でも考えてみていただきたい、性交とは元々子孫を繁栄させるための行為である。
かつては結婚前からこの行為をおこなってしまい、誤って妊娠したので結婚するという現象が起きていたというのだから呆れてしまう。
そもそも他人と性交済の男女が、更に別の人と出会って性交して、そんなことを繰り返して結婚するなんて、想像しただけで気味が悪くて背筋がゾクゾクしてくる。
僕はこのあいだ清雲のことを抱きしめたけれど、それ以上のことは何もしていない。
結婚するまで僕たちは未経験なのでスムーズに子作りが出来るよう、風俗店でトレーニングすることになっている。
昔は、ソープランド、ファッションヘルスと呼ばれていたが、今ではメンズリフレッシュサロン、通称メンリフと呼ばれている。
店内に入ると待合室は白い壁に囲まれていて窓はなかった。ヒーリング系の音楽が控え目の音量でかかり、観葉植物が置かれている。受付のロボットに要件を伝えてからは、ハーブティーを飲みながら順番を待っていた。
ちなみにメンリフにはドレスコードがあり、スカートは不可、ズボン着用の上、ノーメイクで来なければならないのだ。
早く清雲との間に子供が欲しい。結婚式の夜に僕たちは初夜を迎えることになっている。まだ見ぬ我が子を想像してみると、胸がワクワクしてきた。
「お待たせ致しました。トレーナーの御案内です」
ロボットの声がして待合室とカウンターの間にあるカーテンが開いた。丈の短い白いワンピースを着た女性が、ロボットの隣に立っていた。
トレーナーに連れられて個室に入る。ベッド以外は何も置かれていない部屋だった。渡された名刺にはフィジカルトレーナー土本雪恵とあった。
黒い髪は顎のラインで切り揃えられていて、目は細く、鼻はそれほど高くない。名刺を渡すと彼女は僕の隣に座ってきた。待合室にいたときから緊張していたのだけれど、それに恥ずかしさが混ざってどうすればいいのか分からず、
「あの、よろしくお願いします」
と言って頭を下げた。彼女は静かに笑うと、
「雪恵と呼んでください」
そう言ってベッドから立ち上がった。
雪恵という女性らしい名が古めかしくもあり、新鮮にも思えた。歳は僕とそれほど変わらないのに珍しい。
「ねぇ」
雪恵さんの声がして彼女を見た、僕のことを見つめている。
「どうしたの」
そう言われて、僕はキョトンとしたまま固まった。彼女の顔のパーツは、それぞれの存在感が薄い、それゆえ涼しげな印象がある。
「脱がして」
もう始まっていたのだと思い慌てて立ち上がった。急に足が震え、胸の音が聞こえてきた。こわばっている僕の顔を見て、雪恵さんは微笑んだ。
「早くして」
その言葉に背中を押されて、胸元にあるチャックに手を伸ばした。
「ゆっくりね」
僕は、うなずきながらチャックを下ろすと、白いワンピースはストンと落ちた。雪恵さんは下着姿になった。
その姿を僕が凝視すると雪恵さんはまた静かに笑う。どうしてだろう脱がした僕の方が恥ずかしくなってきた。
彼女の乳房は、温泉で見た喜伝や柚都ほど大きくないが、白さは別格だった。雪恵さんはゆっくり後ろを向く、僕は震える手を抑えながらブラジャーを外す。
彼女は向き直るとショーツに目を落とした。僕は膝まずいて息を呑む。
ただショーツを下ろせばいいだけなのに体がこわばってしまう、僕は自分に言い聞かせた、これは誰もが通る道、脱恋世代なら皆が経験すること、いや僕たちの世代だけではないだろう。中世の頃、武士の子は傅役の女性に性の指南を受け、その経験を基に姫との子作りに勤しんだという。そんな妙な理屈まで引っ張り出して来て、気持ちを落ち着かせようとした。
思い切ってショーツを下ろす、もう震えた手を隠し切れなかった。荒い息づかいのせいで喉がカラカラになっているのがわかる。
雪恵さんの肌はホイップクリームのように白い。そして、そのホイップクリームの上に粉チョコレートを落としたように雪恵さんの性器には陰毛があった。
「これが、本当の姿」
彼女の言葉に僕はうなずく事すら出来ず、何も考えられず、ただそれを見つめた。
「立って」
フリーズした僕の頭の中に声が響く。立ち上がると雪恵さんは僕の体を抱き寄せる。
「お疲れさまでした」
彼女に耳元で、そう囁かれると僕はその柔らかい肌の中で、とろけてしまいそうになった。
昭和の時代に流行ったスキップをしてみる。嬉しいこと、楽しいことがあったとき、当時の人はこうやって踊るように歩いたのだという。
女性の裸なんて、温泉や脱衣所で見慣れていたはずなのに、密室で二人きりになったら体が震えていた。
でも、乗り越えてしまったら、なんだかスッキリして華やいだ気分になった。
あの後、女性の体の特徴や触るときの注意事項について、雪恵さんからレクチャーを受けた。次回からは彼女と実際に肌を合わせて愛撫や前戯を学んでいくという。
自宅に帰ってベッドに体をダイブさせる。布団に体を沈めると雪恵さんの肌の感触が蘇ってきて、くすぐられてもいないのに、なんだか体がくすぐったくなったような気がして、転げまわったりしていた。
翌日、仕事をしようとデスクに向かってみたが原稿を書く気になれず、昨日のことばかり思い出していた。
レクチャーを受けたあと、雪恵さんは慣れた手つきで僕のズボンとパンツを脱がして性器を触ってくれた。VR空間にはない温もりを感じ、彼女の手中でリフレッシュした。
ちなみに女性にも性交のトレーニングがあり、ドリームエンジェルサポートと呼ばれている。初めての性交から快楽を得られるようにトレーニングを積んでいくものだ。専門店もあるし、エステやアロマセラピーのお店でオプションとして付けることも出来る。
しかし、メンリフには健康保険が適用されるが、ドリサポは非適用なため不公平だとして国会で議論されている。いつの時代も男女平等とは難しいものだ。
そうだこれを記事にしよう、なかなか面白いじゃないか。そうすれば信長さんもまた喜んでくれるはず。信長さん・・・・・・。
一瞬、頭の中が真っ白になって次の瞬間清雲の姿が浮かんだ。僕は呆然とした。昨日、待合室のカーテンが空いて、雪恵さんの姿を目にしてから今まですっかり忘れていた。僕と清雲の子供の事を考えたのが随分昔のように感じられた。
僕は慌てて首を振り、窓を開けて深呼吸をしてみたり、両手を上げて体を伸ばしてみたりしてから仕事に取りかかった。
それでいつもの自分に戻れた気になっていた。しかし、そんなことで、この心の蠢きを抑えられるはずもなかった。
その後もレッスンは続いた。雪恵さんは相変わらず物静かだった。
この人といるとなぜだろう、なんだか懐かしくて嬉しい気持ちになる。子供の頃、玄関のドアを開けて、雪化粧した街並みと透き通るような青い空を見た朝のことを思い出す。
いつまでもこうして二人で肌を寄せ合っていたかった。
僕が雪恵さんの肌を触る。その触り方がイヤなら彼女は首を横に振り、気持ち良ければ、ゆっくり縦に振ってくれた。
四回目のレッスンのとき、僕は雪恵さんからたっぷり前戯をうけて、彼女の体内に性器を挿入した。くすぐったい生温かさから、安らぎのある生温かさに切り替る。
そうしたら、なんということだろう入った瞬間に発射してしまった。
雪恵さんの指先や舌先に触れて、気持ち良さや緊張感や高揚感に包まれて、入った瞬間に目的地にたどり着いたと思ってしまったのだ。
「すいません」
くやしさと恥ずかしさが絡み合いながら込み上げてきて、僕はそんな言葉をつぶやいた。何度も繰り返しつぶやいた。
雪恵さんは首を横に振りながら、縮こまった僕の性器をてのひらに乗せて慰めるように拭いてくれていた。
教会の前で頬を寄せ合いながら幸せそうに微笑む男女。ディスプレイは小刻みに映像を変える。外観、庭園、式場、神父。
僕はその映像を消して、瀬戸内海の島々を見ることにした。淡路島、小豆島、向島、因島。どの島で彼女は暮らしていたのだろう。
一度も腰を振らずに雪恵さんの中で果てたあの日、彼女は僕をそっと抱きしめて背中をさすってくれた。
「紫乃さんの肌っていいね」
彼女がそう言ってくれたので、僕は照れくさいような嬉しいような気持になった。
「雪恵さんて、素敵な名前だね」
雪恵さんのやわらかい肌に包まれながら、僕はそんな言葉を漏らした。
瀬戸内の島に数年ぶりに雪が降った夜に生まれたのだと、彼女はいつものように言葉少な目に教えてくれた。
どうしてだろう、雪恵さんと会った後は、なんだか胸の内がほんのり温かくなって繰り返し交わした言葉や肌のぬくもりを思い出してしまう。
そんなことを思い出して、しばらくぼんやりした後、ディスプレイの映像を元の教会に戻した。
清雲からどの結婚式場が良いか選んでおくように言われていたからだ。
最近、清雲と会っていると僕は不安だった。女性が利用するドリサポは、器具を使って女性器を慣らしていくものなので、異性と肌を重ねない。
そのため、メンリフで性交を教えるスタッフに対して焼きもちをやく女性が稀にいるらしい。
幸いにも清雲は理性的で合理主義の人だから、そのようなことはないようだが、いつか雪恵さんとのことをあれこれと聞かれるのではないかと内心ヒヤヒヤしている。
清雲がピックアップした数件の教会の資料を、まるで原稿を書いているときのように努めて冷静になって眺めていく。
日本は宗教が混在した国だ、それは今の時代も変わらない。
お葬式には坊さんを呼び、初詣には神社へ行き、結婚式では神父さんの前で永遠の愛を誓うのだから。
いつか僕たちが歳をとってお爺ちゃんになる頃には、こんな宗教の良いとこ取りをしていた時代のことを子供や孫の世代が笑ったりするのだろうか。
僕はそんなことを考えながら、淡々と画像を切り替えていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
