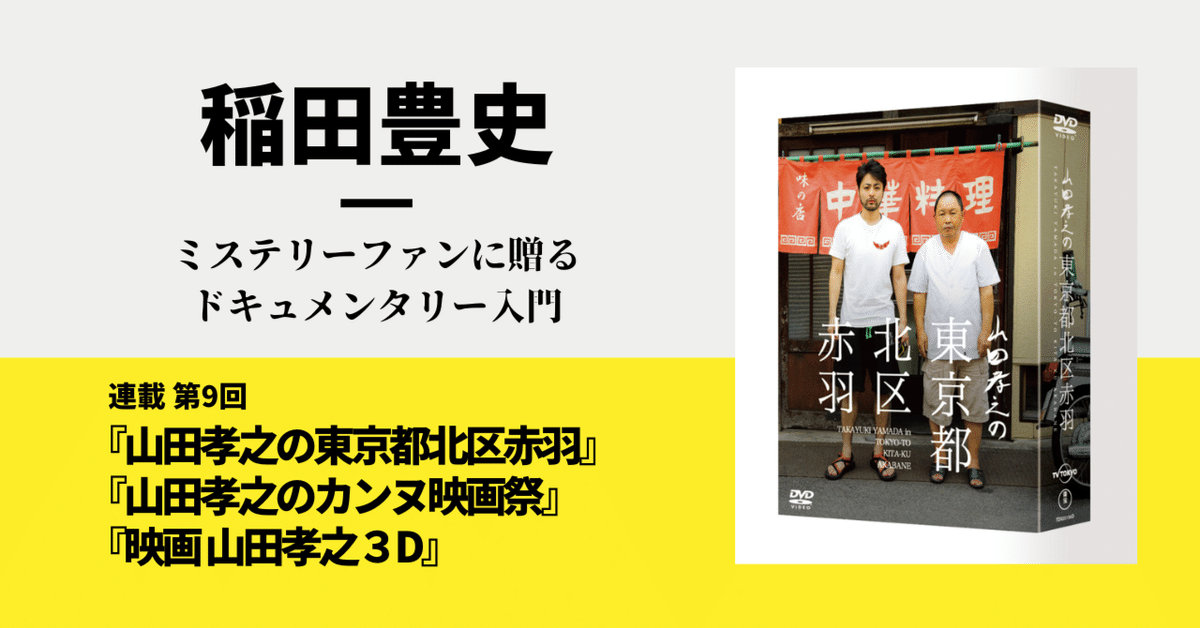
『山田孝之の東京都北区赤羽』『山田孝之のカンヌ映画祭』『映画 山田孝之3D』|稲田豊史・ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門【第9回】
▼前回はこちら
文=稲田豊史
『山田孝之の東京都北区赤羽』
2015年1月、テレビ東京系の深夜帯で突如始まった『|山田孝之《やまだたかゆき》の東京都北区赤羽』(監督:松江哲明、山下敦弘/30分×12話)という番組に、筆者を含む多くの視聴者は当初たいそう困惑した。
第1話冒頭は、『天然コケッコー』『苦役列車』などで知られる山下敦弘監督の新作映画『己斬り』という時代劇の撮影現場。ラストシーンで自死する主役にして侍役の山田孝之の芝居が止まってしまう。「(作り物の刀では)死ねないっすね」「僕、慎之助(役名)じゃないですか」などと面倒なことを言い出す山田。役と自分を切り離せなくなってしまったのだ。
結局、撮影は中止。後日、山田は山下を呼び出し、『東京都北区赤羽』(清野とおる・著)という漫画に出てくる赤羽の住人たちが「すごく人間らしい」「ありのまま生きてる」と感銘を受けたから、赤羽に行きたい。そこでの自分を撮影してほしいと依頼する。自分には役者としての軸がないが、赤羽の人たちは軸がしっかりしている。赤羽で自分が軸を見つける過程を記録してほしい、というのだ。山下は山田に振り回されつつ、それを承諾する。
山田は赤羽在住の漫画家・清野とおるを仲介者として、クセの強い赤羽の住民たちとの交流をスタート。赤羽に部屋を借り、赤羽で生きていこうとする。なんと役者を休業するとも宣言。そうして失いかけた自分を取り戻そう
とする。
……というのは、あくまで宣伝文句的な内容紹介であって、これはフェイクドキュメンタリー(和製英語/正式にはモキュメンタリー)、つまりドキュメンタリーの手法で撮られたフィクション、筋書きのあるドラマだ。『己斬り』という作品は存在しないし、山田も役者を休業などしていない。
ただ、だからといって本作が1から100まででっち上げかというと、そうとも言い切れない。『東京都北区赤羽』という漫画も、その漫画に登場する赤羽のエキセントリックな住人たちも実在し、番組にも登場するからだ。真正のドキュメンタリーとはまた違った意味で、虚実が入り交じっている。
「自分探し」をでっち上げる
多くの視聴者は、本作がフェイクドキュメンタリーであることに早い段階で(少なくとも前半数話目で)気づく。しかし、だからといって白けたりはしない。前回や前々回で論じたように、プロレスやお笑いに「アングル」や「仕込み」の存在を察知したとしても、エンタテインメント性は阻害されるどころか、むしろ加速するからだ。
『~東京都北区赤羽』が設定する「アングル」や「仕込み」に込められた制作者の意図、皮肉や毒の配合具合は実に巧妙だ。
たとえば、山田がカメラの前で執拗に繰り返す役者論。「自分らしく、己を持って生きたい」「俳優以外にいろんなことをしたい。いろんなことが繋がってくると思う」。真面目は真面目だが、典型的な意識高い系、どこか空回りしていてやや痛い。しかし有名俳優の言うことであり、かつ目があまりにも真剣なので、山下はじめ周囲はそれを無下に否定することができない。そのもどかしい空気、居心地の悪さが、よくできたコントのような空気を醸している。
実は山田が発するこのような言葉は、雑誌などでのぬるい俳優インタビュー記事上では大量に散見される。内容がありそうでない、何か言っていそうで何も言っていない。血気盛んな意識高い系発言の典型。フェイクドキュメンタリーと知って見れば、これほどまでに陳腐で〝置きにいった〟セリフはないが、『情熱大陸』や『プロフェッショナル』といった巷のドキュメンタリー番組では、ともすればよく耳にする発言ではある。『~東京都北区赤羽』は、山田孝之という役者を使って、いかにもいそうな若手役者の面倒くさい「自分探し」を精密にでっち上げ、その「あるある」を露悪的に告発しているのだ。実に意地が悪い。
しかも山田は「自分探しを模索する芝居」が圧倒的に上手い。もっともらしいが、たいして内容のないつぶやき。それっぽい自己啓発ワード。核心的な質問に対して、言い淀みながら、懸命に言葉を探しながら、何度も言い直しながら、答えになっていない答えを返す芝居。どれも絶品だ。山田が用意された台本を一字一句忠実にしゃべっているのか、山田のアドリブなのかはわからないが、とにかく上手い。引き込まれる。
最終話では、赤羽の地元劇団と出会った山田が、彼らと赤羽住人を出演者として自分主演のチープなオリジナル劇『桃太郎』を上演し、役者として大切なものを取り戻すという――実に安っぽい、ありきたりな――結末を迎える。
山田をアシストする地元劇団の劇団員は、いかにも小演劇界隈で迷いなく頑張っている、ポジティブ全開の男性(つまり山田とは対照的)。彼は子どもたちを相手にダンスや演劇の児童教室を主宰している。それを見た山田が〝大切なものに気づく〟のだ。この「スランプに陥った一流の役者が、場末の小規模舞台で自分探し完了」という、いかにも聞いたことのある陳腐な構図の設定は、もちろん制作側の仕組んだ「あえて」の愉快犯的しつらえであろう。
山田が考えたという劇の内容も、悪意のこもったひどさだ。山田演じる桃太郎は、鬼退治の途中で立ち寄った自由な動物の村(=赤羽のアナロジー)に居心地の良さを見出すが、最後の敵(鬼)は「自分自身の中にいた」――という、今どきなかなかない、ストレートに観念劇じみた結末。その劇を、今まで赤羽で出会った住人たちや山田の盟友たちが皆、見届けに来ている。観客席から湧き起こる拍手。『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズ最終回並みの「全キャラ集合祝福」。それまでの赤羽での山田の体験がフラッシュバック。「あたたかい感動」をあえて安っぽく演出している。
最後まで、凄まじい切れ味の皮肉。ラストカット、満足げな山田の横顔は会心のオチと言ってよいだろう。
フェイクとの適切な距離感
本作においては、フェイクであることを時折忘れさせてくれる工夫、さし挟まれる「真実」の配分も見事だ。
たとえば、赤羽の実際の住人にジョージさんという強面の男性がいる。普段は気のいいおじさんだが、全12話のうち都合2回、山田に真剣に説教をした。その1度目、第2話で、赤羽は素晴らしい、ここに住んで自分を変えたいと演説する山田に対して、「本読んだだけでわかるのか? 赤羽の人たちなめてねえか? じゃあお前が今まで住んでた街はどうなんだ」と凄む。
これは「キラキラした芸能界で生きている山田が、赤羽の猥雑さに安易に惹かれる」ことに対して抱くであろう視聴者側のある種の嫌悪感を予想した制作サイドが、先回りして、第2話という早い段階でジョージさんというキャラクターに「番組としての自己批判」を担わせた措置だ。
そう、これは本連載第4回で言及した「未開のエンタメ化」問題である。同稿では『ザ・コーヴ』や『地獄の黙示録』を例に挙げ、「西洋的な視線からは理解しがたい、得体の知れない状況を興味本位で観察すること」のエンタメ化を問題としたが、恵比寿(山田の所属事務所:スターダストプロモーションの所在地)あたりを生活圏とする芸能人の山田が、23区の北の果てである赤羽を〝異郷〟として面白がることへの安直さを、作中で牽制したのだ。
また、第6話で役者を10年ほど休業すると宣言した山田は、THE YELLOW MONKEYのボーカリスト吉井和哉、『バクマン。』で仕事をした大根仁監督、『クローズZERO』で共演したやべきょうすけ、同世代役者として親交のある綾野剛に会いに行くが、それぞれの反応と山田評の虚実入り交じり具合も、実に興味深い。
基本的に皆、山田の才能を高く評価しているが、中でも大根仁はもっとも視聴者に近い普通の感覚で、メタな突っ込みを入れまくる。山下と山田が赤羽住人たちと即席で撮った『ザ・サイコロマン』というひどい出来の短編実写を見て、「え、山田君、これ人様に見せるレベルだって思ってる?」「これを(山下と山田が)本気で撮ってるっていうことが、俺は一番ダメっていうか……」と冷静に言い放つ。大根は山田がいないところで清野と山下に対してはっきりと「山田君のキャリアも山下君のキャリアも棒に振るぜ」と容赦ない。
そう、大根だけがこのフェイクドキュメンタリーの構造を〝外側から〟剥がしにかかる役なのだ。そして大根がいることでむしろ視聴者は、作り込まれたフェイクの狂気に一定の距離を置いたまま、安心感をもって楽しく付き合い続けられる。この回がシリーズの折返し地点である第7話に配置されているのは、実に適切だ。ここまで付き合った視聴者に「大丈夫ですよ、異常なのは彼らのほうですから」と、大根を通じて改めてメッセージしているのだ。
視聴者は、虚と実の比率が一体どの程度なのかを毎週、慎重に推測しながら、もっとも快適な距離に身を置き、毎週行われる異常に完成度の高い茶番を存分に楽しむことができたのである。
『山田孝之のカンヌ映画祭』
『~東京都北区赤羽』の2年後、2017年1~3月に放送された『山田孝之のカンヌ映画祭』(監督:山下敦弘、松江哲明/30分×12話)は、山田がカンヌ映画祭で賞を取るためにプロデューサーとして映画を製作する過程を追ったフェイクドキュメンタリーだ。
第1話は、山田が山下を呼び出し、「カンヌで賞が欲しい」と言い出すところから始まる。カンヌで賞を取るために自分がプロデュースする作品を山下に監督をしてもらいたいと言う山田だが、カンヌ国際映画祭の最高賞を「パルム・ドール」と呼ぶことも知らず、1997年にパルム・ドールを受賞した今村昌平監督の『うなぎ』(97)についても「昔見た気がする」程度の認識。この時点でフェイク度は推して知るべし。
山田は「合同会社カンヌ」という馬鹿丸出しの社名の製作会社を立ち上げ、実在の殺人鬼であるエド・ケンパー(男性、逮捕時24歳)を題材にした作品をプロデュースしたいと言い出す。エド・ケンパーは幼い頃から動物虐待を行い、15歳で祖父母を銃殺、ヒッチハイカーを次々と惨殺し、最終的には母親を殺した、アメリカ犯罪史に残るシリアルキラーだ。
しかも山田はエド・ケンパー役を、当時まだ小学生だった芦田愛菜に演じさせようとする。タイトルは『穢の森』。言うまでもなく、カンヌ国際映画祭で審査員特別大賞である「グランプリ」を受賞した河瀨直美監督の『殯の森』(07)のもじりだ。
カンヌ映画祭を「攻略」すべく識者に話を聞きに行く、山田・山下・芦田。プロットもなにもないまま、製作資金を獲得するためのパイロットフィルムを作り、資金集めのため映画会社やゲーム会社を回る(無論、玉砕)。そのさなか、山田は山下とともに無計画にカンヌへ飛んで現地の映画人にアドバイスをもらう。帰国したふたりと芦田は河瀨直美に会い、辛辣なアドバイスを受けるとともに、山田は大きく触発される。
こうして『穢の森』の制作はスタートするが、なんと山田は脚本を用意しない。山田が懇意の漫画家に描かせた「イメージ画」をもとに映画を作るというのだ。困惑する現場、暴走する山田。芦田の母親役として起用されかけた長澤まさみとも、ヌードシーンの有無をめぐって決裂し、クランクイン当日に現場は崩壊する。これが大方のあらすじだ。
アーティスト気取りのプロデューサー
『~東京都北区赤羽』がフェイクだったことが広く認識された後で放送されただけに、『~カンヌ映画祭』は当初からかなり開き直った作りになっている。『~東京都北区赤羽』が、もしかして、そういうことが本当にあるかも?と幾分か感じられたのに比べ、今回は「フェイクであることはバレバレでもいいから、もっと見せたいものがある」という意図に満ちている。
そのひとつが、山田が憑依的に演じる、アーティスティックなものづくりにかぶれてしまった(しかし底は浅い)意識高い系プロデューサーしぐさだ。
山田は、今までの日本映画の作り方ではカンヌを目指すものは作れないと思い込み、脚本も絵コンテもなしで自分のイメージをあやふやな言葉で説明するだけで、スタッフを動かそうとする。山下や他のスタッフがシーンの具体的な状況設定を聞いても「あんま詮索しないでほしいんですけど」「本当のリアルってリアルに見えないんで」などとわけのわからない、理想論的なうわ言ばかりを口にする。
オーディションではリアリズム追求のためにと「実際に前科のある人から選びたい」などと言い出し、現場を動かすために山下が脚本家に仮で作ってもらった脚本も「俺は見ないっすよ」と頑なに読むのを拒む。俳優・村上淳に本物の首吊りの練習をさせては、目も当てられないミュージカルのマネごとをさせた挙げ句、「歌唱力がきつい」という理由で降板を告げる。
抽象的な理念ばかりを口走り、現場はどう動いていいかわからない。コンセプトと高尚な理念をディスカッションするばかりで全然ものができていかない、どこぞの頭でっかちな映画研究会のような地獄が続く。
頭の中にある理想を言語化できないまま、理想とは乖離したものしかできそうにない現場を見て苛立ちまくる山田は、クランクイン日にせっかく作った大道具にケチをつけ、山下もその場でクビにして、すべてをダメにしてしまう。
「告発」とブラックコメディ
『~カンヌ映画祭』が皮肉っているのは、理想ばかりを追い求めるアーティスト気取りの口だけプロデューサーが、いかに現場に迷惑をかけるかという状況である。
また、予算が少ないばかりに実現できることがどんどん限られ、チープになってしまうという小規模予算日本映画あるあるや、難解で芸術性の高い映画は資金が集めにくいというリアリティも、実際の映画人にそれらを語らせ、演じさせることで、現役映画人である山下や松江が実態の「告発」をしていたとも取れよう。
本作が巧妙だったのは、前半と後半の虚実の配分である。前半ではかなり実際的な「カンヌ攻略法」ノウハウや映画製作プロセスの一端が描かれていた。山田・山下・芦田は東京国際映画祭のスタッフや日本映画大学に赴いてカンヌ映画祭の性質をしっかり勉強し、パイロットフィルムの制作や資金集め(最終的には、山田のファンであるというガールズバーの怪しいオーナーに出資を約束させる)の模様を収める。山田と山下はパリの映画人たちにパイロットフィルムを見せて忌憚ない意見をもらう。このあたりは、なんならフェイクのつかないドキュメンタリーだ。
しかし後半ではそれが一転し、その〝学び〟を思い切り曲解した山田がとにかく暴走する。つまり「虚」がトップギアに入る。高い理想を追い求め、妥協することができない山田。現場に漂う、気まずく険悪な空気。それがあまりによくできすぎて、質のいいブラックコメディにすら見える。
第11話のラストで芦田愛菜は山田に愛想を尽かして去る。そして最終12話、山田は自分の意志で生まれ故郷である鹿児島に赴き、かつて実家があった、今は更地となっている場所で泣き、父親に会い、自分の原点を見つめ直す。これは『~東京都北区赤羽』の小劇団で自分探しが完了した件に勝るとも劣らない、〝置きにいった〟結末だ。
「自分のルーツたる故郷の地で自分を思い出す」という結末はたしかに収まりがいい。しかしこれが、通常のドキュメンタリー以上に1から100まで恣意と意図で固められたフェイクドキュメンタリーだと思うと、ここに巧妙な皮肉や高度な嘲笑が詰まっていると考えるのが自然だろう。
「山田孝之の100のコト」
2017年6月に公開された『映画 山田孝之3D』は『山田孝之のカンヌ映画祭』の事実上の続編だ。『山田孝之のカンヌ映画祭』最終話のラスト、芦田愛菜の仲介で山田と山下が和解し、山下が山田主演で映画を撮る、という流れになる。それで作られたのが本作というわけだ。
しかしその内容がまた問題である。着席した山田に、山下が70分あまりずっとインタビューするだけの代物なのだ。
話題に対応して、山田の背景には合成でさまざまなビジュアルが映し出されるが、基本はカメラ手前の山下と山田の一問一答。『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』をご存知の方なら、同番組でたまに企画される「△△(著名人の名前)の100のコト」という企画を想像してほしい。スタジオとは別室のソファーなどに座った著名人に100の質問を投げかけ、スタジオのダウンタウンらレギュラーメンバーが答えを予想して当てるものだ。
ポイントは、その質問があえてひねりのないものである、ということだ。趣味や特技、子供の頃の夢、穿いているパンツの色、初恋はいつ、など。そういった凡庸な質問が凡庸であることそれ自体をメタに笑い、解答者側が突っ込むという、高度なお笑いである。アイドル雑誌のグラビアページに添えられている読み物記事「100の質問コーナー」を想像されたい。そこには「好きな食べ物:いちご」「尊敬する人:お母さん」など、ファン以外にはどうでもいい情報が並んでいる。その無為さを解答者側が「どうでもええわ」と呆れながら解答するのが「△△の100のコト」の真骨頂だ。
『映画 山田孝之3D』は、それをやってのけた。山田は俳優になった経緯を丁寧に説明したりするが、特にメリハリもなければ、特に面白くもない。たいしたオチもない。芸能人インタビューの経験がある筆者からすれば、まるで、「撮れ高の低いアーティストインタビューの現場を、パロディとしてまんま再現している」かのようなつまらなさだ。山下が時々変化球的に「どんなおっぱいが好きですか」「イッツコムチャンネルは好きですか」などと聞くが、特に面白い展開には転がらない。
山田は持論を語る。生い立ちを語る。その言葉数はたしかに多い。しかし、全く頭に入ってこない。言葉は多いが、薄いのだ。本当にどうでもいい話が多い。怪我をして幼稚園の先生に病院へ連れて行ってもらった話などを延々としている。はっきりと退屈だ。
それにしても、松江や山下ほど実力のある監督が、こんな冗長なシーンを編集で切らないはずがない。つまり、冗長さを残すこと自体に意味をもたせている。そう、「つまらない状況」をあえて演出している。
観客は不安になってくる。いったいこの映画はどこに向かっているのか?
終盤、山下はようやく核心じみた質問を投げる。「お芝居を嘘って感じたことはある?」「……ってしゃべってる山田君は、芝居してんの? どっちなの?」しかし山田はあやふやにはぐらかす。「今日……今日芝居したかな。意図的にしたの1回だけです」と答えるが、その1回がなんなのかは言わない。
やがて、最後のくだり。
山下「最後に何か言い残したことありますか?」
山田「長澤まさみさん、オーロラとか興味ありません? 野菜のスープとか……作って……」
これはインタビュー中に長澤のことが好きだと言ったことを受けての、特に意味のない冗談だ。言った山田は自分で吹き出してしまう。
山下「はいカット、以上で大丈夫です。お疲れさまでした」
その後、椅子から立ち上がった山田は、一度画面からはけたあと、再び戻ってきて衝撃の一言を言い放つ。
「全部ウソ」
その言葉を最後に、エンドロールの音楽が始まる。
役者のパーソナリティなんて、誰にもわからない
「全部ウソ」が、直前の山田の発言に対してだけのものなのか、『映画 山田孝之3D』全体を指すのか、はたまた『~東京都北区赤羽』『~カンヌ映画祭』すべてに対してなのかは、明かされないし説明もされない。しかし視聴者としてはやはり、2015年から17年という足掛け3年にわたる「山田三部作」の壮大な冗談を、このたった一言のおちゃめな「全部ウソ」で締めくくってもらったほうが、むしろ気持ちがいい。
ちなみに、『映画 山田孝之3D』公開にあたり、山田はこんなコメントを寄せている。
2016年、僕と山下さんは手を取り合い、衝突を重ね、決別し、再び手を取り合い一つの映画を完成させました。(略)僕は芦田さんと出会ったことでたくさん失い、たくさん発見することができました。いつか芦田さんのような大人になるため、山田孝之は現実をぶち壊し続けて生きていきます。(傍点筆者)
これは「オールフェイク(全部ウソ)」であることのヒントだったのか?
いずれにしろ、山下敦弘や松江哲明という才能が中心となり、著名な俳優や錚々たる映画人たちが総出で協力し、この壮大なおふざけを作りあげたことに、なんというか、快哉を叫びたくなる。
彼らはなぜ、このような壮大なフェイクドキュメンタリーサーガを製作したのか。それは、「ある役者の本当のパーソナリティなど、誰にもわからない」ことを、山田孝之に敬意を払いながら、それでいて茶目っ気たっぷりに示したかったからではないか。
世の中に俳優を追ったドキュメンタリーの類いは山ほどある。しかし、自らをブランディングする義務を課されている彼らが、果たしてカメラの前で本当の心情など吐露するものだろうか。やすやすと本音など語るだろうか。彼らの演技力や監督の演出力をもってすれば、それをでっち上げて視聴者の印象をコントロールすることなど、実にたやすいのではないか?
その実験体として山田孝之が選ばれ、山田は見事、それに応えた。
最高にクールないたずらではないか。
「翻案元」としての『容疑者、ホアキン・フェニックス』
実は「山田三部作」には、明らかに参照元と思われるフェイクドキュメンタリーがある。アメリカで2010年に製作された『容疑者、ホアキン・フェニックス』(監督:ケイシー・アフレック)だ。
内容は、アカデミー賞はじめ数々の賞を受賞しているホアキン・フェニックスが突如俳優を辞めてヒップホップアーティストになると宣言してからの行動を、当時義理の弟だったケイシー・アフレックがカメラで追う、というもの。役者としての自分に嫌気が差して苦悩する序盤、突然俳優を廃業して周囲を驚かせる展開、突然奇天烈なことを言い出す滑稽さ、うわ言のような芸術論を唱えて周囲を困惑させる困ったちゃんぶりなどは、明らかに「山田三部作」のインスパイア元であるといってよい。
ただし『容疑者~』が「山田三部作」ともっとも異なるのは、なんとホアキンたちはこのプロジェクトで、マスコミ・芸能界・アメリカの一般大衆を実際に騙そうとしていたということである。
『容疑者~』は2008年10月にホアキンがヒップホップアーティストに転向した、という設定で始まるが、その後はマスコミにその旨を発表したり、実際に一般客のいるハコで(下手な)ラップを披露してブーイングを浴びたり、トーク番組に出演して奇行を見せたりしている(以上すべて、本編に収録されている)。
無論、これがフェイクドキュメンタリーのための芝居なのではないか? という疑念は湧き起こっていたが、製作サイドは2010年9月、ヴェネツィア国際映画祭上映後の会見までは沈黙を守った。その間の「奇行」やヒップホップアーティスト転身という迷走的行動が、一時的にではあれホアキン・フェニックスという俳優の株を下げたことは明白であり、そのリスクを負ってでも2年近くにもわたりこのプロジェクトをやり遂げたホアキンの役者(?)魂には恐れ入る。
ちなみに同作のラストは失意のホアキンが彼のルーツであるパナマに赴いて父親に会うというものだが、『~カンヌ映画祭』の最終話での山田も、失意のうちに故郷鹿児島に赴き、父親に会う。
『容疑者、ホアキン・フェニックス』が辛辣に描いた2つの皮肉、「有名俳優がアイデンティティを模索」部分は『~東京都北区赤羽』に、アーティストとして新しい表現をしたいという意識高い系の驕りは『~カンヌ映画祭』に、それぞれ振り分けられて〝翻案〟されたわけだ。
なお、『~東京都北区赤羽』第1話で映る山田の部屋の棚には、『容疑者、ホアキン・フェニックス』のDVDが確認できる。
フェイクドキュメンタリーの分類
フェイクドキュメンタリーは大きく3つに分類される。
ひとつは、最初からフィクションであることを明示して作られた、ドキュメンタリータッチの作品。映画作品では『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(99)、『パラノーマル・アクティビティ』(07)、『クローバーフィールド/HAKAISHA』(08)あたりが有名どころだ。いずれも撮影者が行方不明になり映像データが後で発掘された――という設定のフィクション作品(ファウンド・フッテージ)である。
もうひとつは、フェイクであることを先にあまり言わず、「わかる視聴者にだけはわかる」ような遊び心をもって製作されたもの。起源については諸説あるが、世界各地の奇習や奇祭をグロ映像を交えて綴った『世界残酷物語』(62年、グァルティエロ・ヤコペッティ監督)、密林地帯で発見されたフィルムに食人や強姦が映っていた――というファウンド・フッテージものである『食人族』(80年、ルッジェロ・デオダート監督)あたりが、よく知られた作品だろう。
特に『食人族』は1983年の日本公開時、フィクションであることをあえて言わずに宣伝したため、観客の中には「発見されたフィルム」の内容を本物だと誤解する者もいたという。同作は1980年代後半の日本で、レンタルビデオショップの台頭とともにさらに知名度を上げ、知識のない小中学生はこれまた「本物」だと勘違いした。
日本のTV番組で有名なフェイクドキュメンタリーといえば、『水曜スペシャル』の「川口浩探検シリーズ」をおいて他にない。これはテレビ朝日系で1978年から1985年まで断続的に放送されたシリーズで、俳優の川口浩が探検隊を率い、世界のジャングルや洞窟、未開の地などを訪れ、未確認生物や猛獣などを探索するもの。後に元スタッフが語っているように、これは基本的にはすべてやらせと演出で、隊員が罠にかかるといったアクシデントも含めてすべて仕込みの産物である。タイトルで「猿人」「獣人」「怪獣」「双頭の巨大怪蛇」などと煽ったりもしているが、無論そのような生物は発見できずじまい、もしくは全くの羊頭狗肉オチ、もしくは見世物小屋ばりの嘘くさい見せ方でお茶を濁して終わる。
いい大人は「川口浩探検シリーズ」を馬鹿にしていただろうが、子どもたちの間では大人気だった。それは、放送当時同じく大人気だったプロレス中継と同じような「虚実皮膜」の魅力が同番組にあったからだろう。
3つめは、『容疑者、ホアキン・フェニックス』のように、現実世界を巻き込んでまでひとつの作品とするもの。実際のマスコミや大衆を「騙す」ことになるため、並大抵の根性で作ることはできないが、成功すれば多大なインパクトを残す。
その金字塔的作品として近年もっとも有名なのは、2006年のアメリカ映画『ボラット 栄光ナル国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習』(監督:ラリー・チャールズ)だろう。主演のサシャ・バロン・コーエンを一躍スターにした本作で彼は、カザフスタンの田舎者テレビリポーター・ボラットに扮し、アメリカで好き放題に大暴れする。ボラットは何も知らないアメリカ市民に対し、文化の違いを盾に失礼を働きまくり、呆れさせたり怒らせたりするのだ。ここまで来ると、フェイクドキュメンタリーというよりは過激なお笑い番組のドッキリ企画に近い。
危うい境界線
この分類で「山田三部作」は2つめに分類される。少なくとも放映当時、「これはフェイクドキュメンタリーです」と宣言されて放送されてはいなかったからだ。特に『~東京都北区赤羽』の場合、わかる者は最初から勘づき、何かがおかしいとは感じるものの、企画主旨がいまいちつかめないまま不思議な気持ちで見続けていた。ちなみに赤羽での撮影時期は放送前年の夏だが、その頃「赤羽に山田孝之がいるらしい」という情報がネットで飛び交っていたという。
ところで、『カンヌ映画祭』では山下が山田と共に、長澤まさみに「脱ぐ」ことを説得するくだりがある。そこで山下は「俺も現場で、全裸で演出してもいいですよ」などと馬鹿なことを口走るが、山田のほうはその後、Netflixドラマ『全裸監督』(19)で実在のアダルトビデオ監督・村西とおるを演じ、実際にパンツ一丁でカメラをかついでいる。ある種のアダルトビデオが醸す劣情がフェイクドキュメンタリー的な作りから生成されている(*1)という事実を考えると、この配役には何やら因縁めいたものを感じよう。
なお『全裸監督』はフィクションドラマ作品としては上々の評判を得て続編も製作されたが、一方で村西が美化されすぎていること、実名で登場しているAV女優本人にコンタクトを取らないまま製作されていたことが問題にもなった。
また、三部作すべてに共同監督として関わった松江哲明は、前回の『俺たち文化系プロレスDDT』や『あんにょんキムチ』といったドキュメンタリーの監督として名を馳せているが、2007年に発表して話題になったドキュメンタリー監督作『童貞。をプロデュース』において、出演者に性行為を強要したことが出演者自身から2017年に告発され、2019年に謝罪している。
フェイクドキュメンタリー(「山田三部作」)の虚と実、フィクション(『全裸監督』)の虚と実、そしてドキュメンタリー(『童貞。をプロデュース』)の虚と実。どの境界線も実に危うい。その危うさに、作り手はどうしようもなく惹かれてしまうのだろうか。
ハードな海外ロケドキュメンタリーとしてギャラクシー賞を受賞した『ハイパーハードボイルドグルメリポート』などを手掛ける元テレビ東京ディレクターの上出遼平は、2021年にモキュメンタリー『蓋』をプロデュースしたことについて、こう語った。
「僕は事実と虚構の境界を常に考えているんです。というか、ドキュメンタリーをやっていればその境界をどう認識するかが常に問われます。それを突き詰めていくと、モキュメンタリーをやらざるを得ない」(*2)
*1 『新映画論 ポストシネマ』(渡邉大輔・著/ゲンロン、2022年)P.89「このドラマで山田が演じた主人公は、一九八〇年代に一世を風靡したアダルトビデオ(AV)の監督・村西とおるだったが、現代のフェイクドキュメンタリー的想像力のひとつにAVがあることを併せ考えると、ここには映像史的な符合があるといえる」
*2 「BRUTUS」2021年12月1日号 特集「沸騰!ドキュメンタリー好き。」
《ジャーロ NO.88 2023 MAY 掲載》
「山田孝之の東京都北区赤羽 DVD BOX」
DVD 発売中 16,720円(税抜価格15,200円)
発売元:「山田孝之の東京都北区赤羽」製作委員会 販売元:東宝
©「山田孝之の東京都北区赤羽」製作委員会
▽過去の記事はこちらから
▽稲田豊史さん近著
■ ■ ■
★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!
ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。
お気軽にフォローしてみてください。お気軽にフォローしてみてください。
この記事が参加している募集
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
