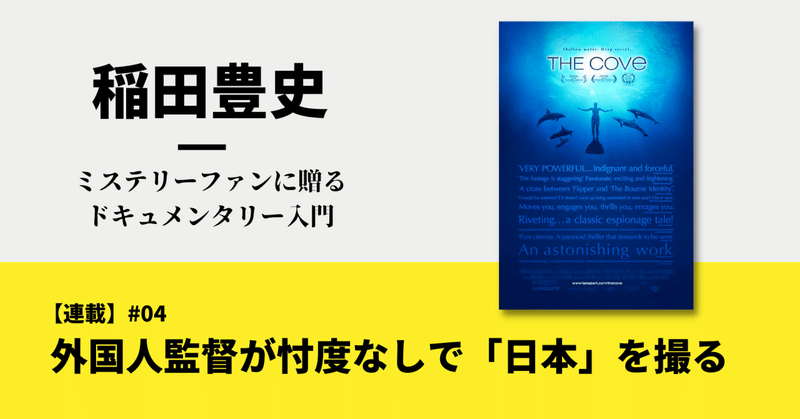
【連載 #04】外国人監督が忖度なしで「日本」を撮る|稲田豊史・ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門【第4回】
文=稲田豊史
外国人監督が日本の題材を撮る
観ごたえのあるドキュメンタリーには、はっとする視点が設定されている。見慣れた/聞き慣れた題材に、視聴者が想像もしていなかった角度からカメラを向ける。それはまるで、『桃太郎』を鬼側の視点から描くことで、「正義を掲げる侵略者に住まいごと蹂躙される異民族の悲劇」に仕立て上げるがごとし。
その、はっとする視点がもっとも顕在化しやすいのが、日本人に馴染み深い題材を外国人監督が撮ったドキュメンタリーだ。そこには、日本に生まれ育った者からすれば意外な視座が設定されることも少なくない。
『ザ・コーヴ』(’09)は、和歌山県太地町で行われているイルカの追い込み漁を、アメリカ人監督ルイ・シホヨスが追った作品だ。端的に言えば、反捕鯨(注:イルカは鯨の一種)の立場から描いた、糾弾色の強いドキュメンタリー。第82回アカデミー賞で長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。
先に言っておくが、本稿の目的はドキュメンタリーの観方指南なので、イルカ漁そのものの是非は論じない。また、同作には事実誤認や偏向的な編集、問題のある撮影がなされているという指摘があり、公開後に物議を醸したが、とりあえずそれも無視する。
注目したいのは、シホヨス監督がこの題材にどんな視座を設定し、劇映画としてどんなストーリーテリングを施したか、だ。
その前に、日本人監督がこの題材を扱ったら、と想像してみよう。ある世代以上の日本人にとって「捕鯨」はかなりデリケートな題材だ。国際世論でみられる「絶滅の危機に瀕している動物の保護」「鯨やイルカを知性ある生き物として扱う際の感情的な抵抗感」というプレッシャーは了解しつつも、同じ日本人としては「日本の食文化」「漁師たちの生活」にも心情的に寄り添いたい。監督自身がイルカ漁や捕鯨に賛成であれ反対であれ、かなり慎重に、バランスを取った生真面目な作りにせざるをえなくなる。作品発表後の日本国内からの反応も考えると、なおさらだ。
スパイ映画さながらの『ザ・コーヴ』
しかしシホヨス監督は、本作を危険区域の潜入アドベンチャーのように撮った。言ってみればサスペンスタッチのスパイ映画。『ミッション:インポッシブル』のごときエンタテインメント性が満載なのだ。
シホヨス監督は、立ち入り禁止になっているイルカ追い込み漁のための入り江(the cove)に狙いを定め、そこで行われている〝残虐行為〟を世界中に知らしめるべく、夜間の盗撮を計画。海外から各分野のプロフェッショナルが集まってチームが組まれ、ミッション遂行のためのハイテク機材が宿泊している部屋へ大量に運び込まれる。スパイガジェットさながらに石の中にカメラを仕込むシーンでは、彼らはいかにも楽しそう。「秘密の入り江はまるで要塞」という言葉も、どこかスパイ映画っぽい。
シホヨス監督はチームを『オーシャンズ11』にたとえる。『オーシャンズ11』はスティーブン・ソダーバーグ監督による2001年製作の犯罪映画で、各種犯罪のプロたちが集結してビッグな仕事を遂行するストーリー。ジョージ・クルーニーやブラッド・ピットなどのハリウッド俳優が多数出演するエンタテインメント作品である。
イルカ漁反対派のキーパーソンは冒頭で登場するなり、太地町を「大きな秘密を隠す小さな町」と説明し、太地町の漁師たちを「奴ら」と呼ばわりして「(太地町の人間は)私を殺したがってる」と敵意剥き出し。まるで麻薬カルテルにまるごと支配されている中南米あたりの街のような言い草だ。きわめてハリウッド映画的な、わかりやすい悪者集団設定。「良心に駆られた先進国の進歩的ジャーナリストが、モラル後進国の犯罪(イルカ漁)現場に潜入し、危険を冒してでもその実態をカメラに収めて世界に告発するのだ!」的な正義感が滲み出ている。
一応言っておくと、本作では国際捕鯨委員会の欺瞞やイルカ肉に含まれる水銀の問題なども並べて語られる。そこはしっかり社会派だ。しかし映画全体が観客に用意するカタルシスは、明らかに『ミッション:インポッシブル』的な潜入ミッションのそれである。このように思い切ったエンタメ的な視点設定は、たとえ反捕鯨の立場をとる日本人監督であってもなかなかやらないだろう。一言、新鮮だ。
「アメリカ人は休日に石なんか見に行かない」
シホヨス監督および本作に登場するイルカ漁反対派の根底にあるのは、「イルカには人間並みの知性がある。そのような生き物を殺すのは許されない」という倫理観だ(繰り返すが、その是非を本稿では問わない)。彼らからしてみれば、イルカという知性ある生き物を殺すのは野蛮人の所業なのかもしれない。実際、太地町の漁師たちは、「荒い言葉で我々を威嚇してくる、現地の野蛮人」のように撮られている。
「太地町の漁師たち、ひいてはイルカ漁を問題視しない日本人は野蛮だ」はさすがに大袈裟な形容だとしても、「未開」くらいには捉えている気がしてならない。というのも、入り江盗撮のために石の中にカメラを仕込むアイデアを思いつくくだりで、ある寺の石庭が映る。そこでのナレーションはこうだ。
「僧侶が砂を掃いていて、世界中の人が見に来る石がある。アメリカだったら誰も休日に石なんか見に行かないけどね」
前半はいい。しかし後半は明らかに、「未開人の奇妙な趣味を不思議がる」物言いだ。ここに引っかかる日本人は少なくないのではないか。実際、このシーンで流れる劇伴(BGM)は、寺院や石庭の神秘性や文化的奥深さを感じさせるものではなく、「奇妙な国の奇妙な習慣」とでもタイトルをつけたくなるようなものだった(ぜひ実際に聴いてみてほしい)。
彼らに大文字の日本文化をディスっている意識はないのだろう。ただ、西洋文明が非西洋文明を「奇異の目で珍しがる」点において、「イルカを殺すなんて野蛮人の仕業、という言い切り」と「石を眺めるなんてちょっと意味がわからない」は、ほとんど同じグループに入る感受性ではないだろうか。
この無邪気な感受性にもし名前をつけるなら、「未開の発見」とでもするのが適当だ。
『地獄の黙示録』と「未開のエンタメ化」問題
「未開の発見」が不遜な態度であるとする批判は、歴史が長い。
「コロンブスがアメリカ大陸を〝発見〟した」が、ヨーロッパ中心主義に基づく不適切極まりない言い方だというのは長らく常識だし、キリスト教の宣教師が植民地に派遣されて「野蛮な現地民を文明化した」も同じ。
ここで連想する映画がある。フランシス・フォード・コッポラ監督がカンヌ国際映画祭の最高賞パルム・ドールを獲得した『地獄の黙示録』(79’)だ。舞台はベトナム戦争。カンボジアの奥地に独立王国を築いたカーツというアメリカ人の大佐を暗殺すべく、ウィラード大尉が船でジャングルの奥深くに赴く物語だ。
カーツが従えているカンボジアの現地民は、ウィラード大尉の目には「未開で得体の知れない集団」として描かれている。その頂点に立っているカーツは、明らかに「精神に変調をきたした西洋人」だ。これは何を意味するか。
『地獄の黙示録』の面白さは、船で川を上るウィラードが次々と狂気的なシチュエーションに遭遇するという、地獄めぐりアトラクションのごとき立て付けにある。ナパーム弾による爆撃、プレイメイトの慰問、燃料と交換のバニーガールとのセックス、罪のない現地民の殺#さつ$戮#りく$、戦時下にもかかわらず不気味な優雅さを保つフランス人たち――。その行き着いた先に、つまりそれらの狂気の最高峰として、カーツと現地民の〝異様な〟コミュニティが描かれる。
西洋的な視線からは理解しがたい、得体の知れない状況を興味本位で観察すること。踏み込んで言うなら、「未開のエンタテインメント化」だ。
『地獄の黙示録』は、イギリスの小説家ジョゼフ・コンラッドによる『闇の奥』(1899年発表、1902年出版)を大幅に翻案して作られた。『闇の奥』の舞台は19世紀末のアフリカ、コンゴ川だが、当時のコンゴ川流域はベルギー国王レオポルド2世の私有地であり、現地民をひどく搾取していたことでも知られている。同作はヨーロッパの植民地支配の本質、西洋文明の闇を突いた作品として高い評価を受け、多くの文学作品に多大なる影響を与えた。
ただ、『闇の奥』は発表から何十年も経過したのちに批判も浴びている。1975年、アフリカ・ナイジェリアの作家チヌア・アチェベが、同作にはアフリカ人の内面が描かれていないとして、コンラッドを人種差別主義者だと糾弾したのだ。ナイジェリアの作家からすれば、これも立派な「未開のエンタテインメント化」。不遜の極みというわけだ。
『ザ・コーヴ』における太地町の漁師たちの描き方は、これに該当するだろうか、しないだろうか。
オタクとマイルドヤンキーは〝発見〟されたのか
実は「未開のエンタテインメント化」は日本人同士でも行われている。
2014年の「新語・流行語大賞」にノミネートされた「マイルドヤンキー」という言葉がある。これはマーケティング・アナリストの原田曜平が唱えた概念で、郊外や地方に住み、地元指向が強く、内向的で上昇志向が低い若者たちのことを指す。彼らの「ショッピングモールを好み、高級ミニバンに憧れ、低学歴・低収入ながら生活満足度は低くない」といった特徴は当時メディアで興味本位にたいそう面白がられ、日本人の新しい若者像として話題になった。
しかし、批判もあった。「都市生活者が郊外生活者である彼らを勝手に〝発見〟した気になっているだけで、もともとそういう人は存在していた」「知的エリート層が郊外住まいの低所得者を面白がって見下しているだけ」など。
実際に見下していたかどうかは別として、マイルドヤンキーと称される彼らを「物珍しげに笑う」空気が当時のメディア内に存在した事実は否定できない。その点において、アメリカ大陸の〝発見〟と構図的には変わらないとも言える。
オタク文化の〝発見〟にも同様の構図がある。「オタク」という言葉や概念自体は1980年代から存在し、界隈では長らく蔑視の対象となっていたが、2000年代に入るとマスコミが一斉にオタクの奇妙さ、生態の面白さを〝発見〟して騒ぎ立てた。きっかけは、秋葉原のメイド喫茶が話題になったこと、お笑い番組などで誇張されたオタクキャラが人気を得たこと、2005年公開の映画『電車男』のヒットなど。オタクは「奇妙で、異常で、面白い存在」として鑑賞され、見世物にされ、消費されていった。
〝一般市民〟から見たマイルドヤンキーやオタクは、ウィラード大尉から見たカンボジアの現地民やカーツ大佐と同じなのだろうか? あるいはまた、〝善良で進歩的で知性的な正義のアメリカ人〟から見た、イルカ殺害という残虐行為を繰り返しながら西洋人に威嚇的な言葉で歯向かう太地町の漁師たちとも同じなのだろうか?
西洋人によるヨーロッパ中心主義の自己批判としてもっとも有名なのが、フランスの文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースが1962年に著した『野生の思考』という書だ。内容をごく簡単に説明するなら、ヨーロッパ人が長らく抱いてきた「文明が進んだ我々は、未開で野蛮な人々よりも進歩的な存在である」という優越感を無効化するもの。ヨーロッパ人の考える「文明的であること」と「未開状態」の間に優劣はなく、それぞれがそれぞれの社会構造のなかで生きている、というのがレヴィ=ストロースの主張だった。
取材相手と親しくなると、ロクなことがない?
ドキュメンタリーに話を戻そう。ドキュメンタリストがある被写体を撮影する場合、被写体を分析的に、言ってみれば「上から目線」で捉えがちになる。記録したものを恣意的に編集し、徹底的な制御を施して作品化するのだから、当然といえば当然なのだが。
日本を代表する社会派ドキュメンタリストである小川紳介(「三里塚シリーズ」『ニッポン国古屋敷村』)原一男(『ゆきゆきて、神軍』『全身小説家』)のように、被写体の人物と長く一緒にすごす、なんなら文字通り寝食をともにすることで「上から目線」を極力排除するという手法もある。そうすることで被写体から信頼を得てはじめて撮れる画、引き出せる言葉もあるだろう。なにより、そのアプローチは往々にして誠実だと形容される。
しかし一方で、あえて被写体から物理的・心理的距離を置き、情にほだされないようにして撮影する方法もある。東海テレビで物議を醸すドキュメンタリー番組を多数プロデュースする阿武野勝彦は言う。
「カメラマンが取材の途上で取材相手と親しくなると、ロクなことがない。それは、撮影という行為が、関係性を冷徹に映し込む作業だからだ」(*1)
カメラマンを映画評論家に置き換えるなら、「監督と知り合いではないほうが、歯に衣着せぬ批評ができる」というやつだ。
そう考えると、ドキュメンタリーのカメラマン(監督)が被写体とは異なる国の人間であることで、つまり第三者であることで生じるある種の無遠慮さが、「同国人なら撮りづらいものが、撮れてしまう」というメリットを生み出すこともあるだろう。
こんな話もある。東日本大震災を取材した『境界の町で』などの著書がある作家の岡映里は、ある日本人の写真家が、毎日のように殺人のあるメキシコでは大胆に死体を撮影していたのに、その写真家が撮った東北被災地の写真は「お行儀が良くて『遠慮』を感じた」という。その理由について岡は「メキシコ人の死体を驚くほど大胆に撮影しても、それを発表するのは日本なので、遺族の目に触れることはほぼない」が、「東日本大震災の取材では『ひどい扱いをするなら許さない』という『当事者からの目』に取材者が逆照射される」からだと分析した(*2)。
また岡は、被災地での外国人カメラマンの様子を所感と併せて綴っている。「ロングレンズで葬儀を盗撮している場面や、一時帰宅の人の家に靴も脱がずに上がりこんで挨拶すらしないでシャッターを切りまくっているところなどに出くわしたりしたとき、その『自由さ』にクラクラしたものだ」(*3)
ここで外国人カメラマンの行動の善悪は論じない。本稿で強調したいのは、「A国人なら撮影を躊躇する場面でも、B国人なら躊躇しない場合がある」ということだ。
『主戦場』と『クナシリ』の「自由さ」
A国人とB国人で撮ることのできる素材に差がつくのは、静止画の写真だろうが動画のドキュメンタリーだろうが同じ。当然、出来上がりの作品には違いが出る。
日本に生活の拠点を置いていない外国人監督は、取材時においても使用素材の選択時においても、「隣人に対する忖度」を必要以上に働かせる必要がない。徹底的に第三者の顔でふるまえる。良くも悪くもズケズケものを言いやすく、対象に土足で踏み込みやすい(言うまでもなく、日本人写真家のメキシコでのふるまいも同じ)。岡の言う「自由さ」だ。
日系二世のアメリカ人であるミキ・デザキが日本の従軍慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー『主戦場』(’19/パッケージ化も配信もされていない)には、彼が「ネオナショナリスト」と呼ぶ日本人右派論客たちへのインタビューが多数収録されている。その無邪気で無遠慮な切り込み方と、七面倒臭い物議を一切恐れない姿勢は、やはりデザキが「日本社会に暮らす日本人」ではないがゆえに獲得できている「自由さ」ではないか。ちなみに、本作内で取材を受けた出演者の5人は「合意なしに映画を商業公開された」として民事訴訟を起こしている。
本連載第1回の新作紹介コラムで言及した『クナシリ』('19)も、日本人にとってはかなりデリケートで複雑な題材である北方領土問題を扱ったドキュメンタリーだが、監督は旧ソ連(現ベラルーシ)出身でフランスを拠点に活動している人物。つまり日本人でもなければ、ロシアで暮らしているわけでもない。題材にしがらみがない「自由さ」がある。
その「自由さ」は、島の描写に特別な意味や感情を盛り込むことを退けた。ただただ、とくに観光的な見どころもない荒涼としたゴミ溜めのような町並みを映し、時代の役割を終えた、忘れ去られた土地の寂しさを前景化した。日本人の撮影クルーならば、そこにもっと政治的な深刻さを盛り込んだだろう。
刀匠に聖性を見いださない『靖国 YASUKUNI』
中国人監督の李纓が、靖国神社を訪れる人やそこで展開される政治的行動、小競り合いなどをカメラに収めたドキュメンタリー『靖国 YASUKUNI』(’07)も挙げておこう。
いわゆる「靖国問題」は、日本人にとってはトップクラスにデリケートな案件であり、A級戦犯の分祀問題や公人の参拝是非については長らく議論が続いている。日本人監督が取り上げるには、相当な熟慮と覚悟が必要であるばかりか、商業映画として成立させるには多方面にわたる「配慮」や「忖度」も欠かせない。
『靖国 YASUKUNI』は一部で「反日プロパガンダ映画」と呼ばれたり、取材の方法に問題があるのではないかという指摘があったりと、公開時は相当に物議を醸したが、本稿でそれらは重視しない。注目したいのは、本作でもっとも外国人視点が顕著な部分だ。
それは、90歳になる刀匠の「見え方」である。
本作は冒頭のテロップで、「昭和8年から終戦までの12年の間、〝靖国刀〟と呼ばれる8100振の軍刀が靖国神社の境内において作られた」と説明される。その現役最後の靖国刀匠として登場するのが、この老刀匠だ。彼の作った靖国刀はかつて戦場の将校たちに供給されたという。そしてテロップには、「246万6千余の軍人の魂が移された一振りの刀が靖国神社の御神体である」と表示される。
刀を御神体とする神社の現役刀匠と聞けば、多くの日本人は当然、彼がいかに靖国神社の象徴する聖性と一体化した存在であるかをロマンチックに想像するだろう。特にある世代以上の日本人からすれば、古き良き日本文化を担う刀匠という職業は無条件にリスペクトすべし、といった不文律が確固としてある。その意味でも、彼にカメラを向けるなら、相応の「ただ者ではない人間国宝的存在」として撮るのが定石だ。日本人監督が日本人の製作チームとともに撮るならば。
しかし中国人監督である李纓にとっては、そのような文化背景が決して所与のものではない。了解事項でもなんでもない。しがらみなき「自由さ」がある。
結果、李監督は老刀匠をどう撮ったか。
刀匠の作業場は、まるで零細鉄工所だか下請け部品メーカーだかを彷彿とさせる、粗末で黒ずんだ古ガレージといった印象。作業用の容器として使われている何かの食べ物の空き缶も映る。その薄暗い場所で、機敏とは言いがたい老人が黙々と刀を作っている。「英霊を祀る神社」から想像する威容とか、聖性とか、オーラのようなものはあまり感じられない。否、感じられないように撮っている。
刀匠が生活する居室も同様だ。壁にかけられたカレンダー、小さな電気ストーブ。積まれた段ボール箱には「西瓜」と書いてある。「靖国」というビッグネーム、「刀匠」というリスペクタブルな職業イメージからは大きく乖離した、剥き出しの生活感が漂う。
カメラを回したらそう撮れてしまっただけだ、とは言わせない。撮り方はいくらでも工夫できるからだ。「現役最後、90歳の刀匠」として、あるいは「国家神道の代表的施設である靖国神社の刀匠」として、崇高なる存在に見せる撮り方もあっただろう。
しかし李監督はそう撮らなかった。彼が反日思想かどうか、靖国問題に対する政治的な気分がいかなるものであるのかを考える以前に、これは確実に「外国人目線」だ。李監督は、一般的な日本人なら描き込まざるをえない、あるいはスルーしにくい刀匠の聖性イメージを重要視せず、90歳の老人を「時代的役割をとっくに終えた存在」としてドライに撮り上げた。
まるで、『クナシリ』で描かれた国後島の町並みのように。
〝外国人監督〟だからこそ引き出せる言葉
いっぽう被写体の立場からすれば、インタビュアーの文化的背景や母国語が自分たちと異なる場合と同じ場合とでは、おのずと態度が変わってくる。結果、引き出される言葉も違ったものになるはずだ。
ニューヨークで生まれ育った日系二世のリサ・モリモトが、元特攻隊員の生存者や親族などにインタビューを重ねるドキュメンタリー『TOKKO 特攻』(’07)は、日本人であればかなり投げにくい「素朴すぎる質問」を彼女が投げ続けることで、彼らから赤裸々な言葉を引き出すことに成功している。モリモトもそのことに自覚的で、彼女自身が冒頭のナレーションでこう言う。「日本人には聞きにくい質問も(日本人ではない)私なら…」
老いた元特攻隊員からは、かなりストレートな言葉が飛び出す。「天皇陛下のために痛めつけられて、みんな死んじゃったからな。昭和天皇に対して違和感は感じるけどさ」「せめて半年早く天皇陛下が『もういいから、俺が犠牲になるからやめよう』って言ってくれたら、何万人という人が助かったでしょ」
生まれも育ちもニューヨークだけあって、モリモトの日本語はネイティブ日本人よりわずかに拙い。そのような日本語を聞いた元特攻隊員たちは、モリモトが日本文化圏で育っていないことを察知し、婉曲的な言い回しや行間を読ませる物言いをなるべく避けようとしたに違いない。〝外国人〟である彼女が理解できるよう平易で直接的な言葉を使い、噛み砕いてわかりやすく話そうとしたはずだ。明快に、簡潔に、率直に。それが結果として、赤裸々で強度のある言葉となったのではないだろうか。
鮨のBGMに和楽器を使わない
ある文化圏の視線が別の文化圏を捉え、解釈し、何かしらの判断を下すとき、そこに悪意や侮蔑があろうがなかろうが、どうしても一定の齟齬やハレーションが発生する。レヴィ=ストロースの『野生の思考』にすら「未開人を美化し過ぎていないか」という批判があった。そもそも「未開人を研究する」という態度や視点そのものが、構造的に「上から目線」でしかありえないのではないか? という意見にも一定の説得力がある。
ただ、〝発見〟された側がむしろ晴れやかな気分になれるドキュメンタリーもある。そのひとつが、アメリカ人監督のデヴィッド・ゲルブが銀座の鮨屋「すきやばし次郎」の店主・小野二郎とその息子たちを追った『二郎は鮨の夢を見る』(’11)だ。同店はミシュランガイド東京で三つ星を獲得した名店中の名店。2014年には当時のオバマ米大統領と安倍晋三首相が会食した店としても知られている。
ゲルブは宝石のように光り輝く鮨ネタの美しさを表現する際、あるいは二郎の鮨職人としての高みや神秘性、完璧主義ぶりを描写する際、劇伴に弦楽器やピアノによって奏でられるコンチェルト(協奏曲)を多用した。たとえば、二郎の鮨職人としての粋が結集した「おまかせコース」が供されるシーンの劇伴は、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第21番」だ。
これは劇中に登場する日本人の料理評論家が、「おまかせコース」の展開をコンチェルトの楽章にたとえて説明したことが着想の元と思われるが、ハリウッド映画における日本のシーンでわざとらしく流れる尺八や琴や和太鼓などを一切使用しないところに、ゲルブなりの視点設定がある。
おそらくゲルブは、至高の鮨職人である小野二郎の握る芸術的な鮨や語る仕事の哲学を、「日本ぽさ」などというお仕着せの概念では捉えていない。国を超えた、もっと普遍的な聖性や神性を当時85歳の鮨職人に見出していた。比べるものでもないが、『靖国 YASUKUNI』で李纓が90歳の刀匠に見出したものとは実に対照的だ。
「見る者」と「見られる者」の力関係
自分たちとは異なる文化的バックボーンをもつ外国人監督がドキュメンタリーの題材に日本を選ぶとき、我々は自分たちが、日本人という国民ごと、あるいは日本の文化ごと、あるいは日本の歴史ごと、ひっくるめて「見られている」ことを強く意識させられる。
ドキュメンタリーは、「見る者」である監督が、「見られる者」である被写体にカメラを向ける、という図式で成り立っている。「見られる者」は、時に「野蛮」と謗られたり、「未開」として腑分けされたり、「聖なるもの」として崇められたりする。なんだか心穏やかではいられない。
ただ逆説的だが、「見る者」より「見られる者」のほうが、より多くのものが見えていることも、往々にしてある。カメラが被写体を凝視している間、被写体はカメラマンとその背後に広がる風景を一望しているからだ。このときの被写体の視野は、カメラマンのそれよりもずっと広い。
ニーチェが『善悪の彼岸』で記した有名な言葉、「深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ」が思い起こされる。深淵とは水が深く淀んだ暗い場所のこと。日本人である我々が『ザ・コーヴ』『靖国 YASUKUNI』『二郎は鮨の夢を見る』といったドキュメンタリーを観るとき、我々は言ってみれば深淵の側に立たされているが、暗がりから明るい場所を見るほうが、その逆よりも多くのものを見ることができるのだ。
*1 『さよならテレビ ドキュメンタリーを撮るということ』(阿武野勝彦・著、2021年、平凡社新書)
*2 『21世紀を生きのびるためのドキュメンタリー映画カタログ』(寺岡裕治・編、2016年、キネマ旬報社)
*3 前掲書
© Oceanic Preservation Society
《ジャーロ NO.83 2022 JULY 掲載》
■ ■ ■
▽過去の連載記事はこちらから
▽稲田豊史さん最新刊
▼ジャーロ公式noteでは、「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
