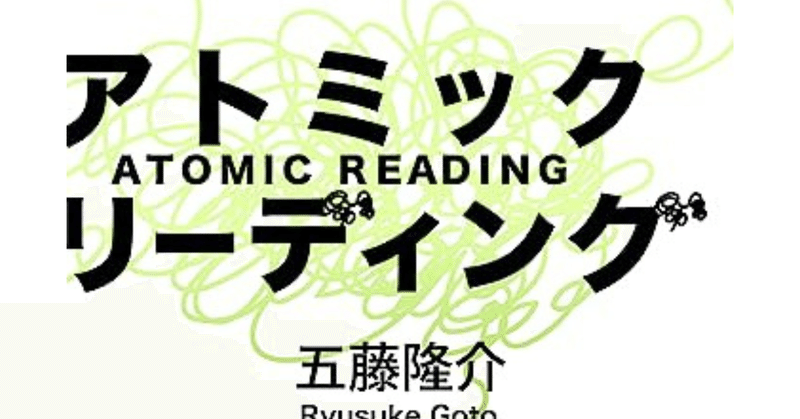
いつも読書したあとの感想が「面白かった」だけしかない人間だったので『アトミック・リーディング: 読むことと書くことから考える読書術』を読んだ
きっかけ
いつも読書するときは「この本を読み終わったら読書記事書くぞ〜」って意気込んでいるんだけど、実際に本を読み終わって記事を書こうとすると「面白かった」以外のアウトプットがないことがコンプレックスだった。
自分は本を読んで何か得ることができたのか? 他の読書記事を書いている人となにが違うんだ? なにをすれば読書記事を書けるようになるんだ? 自分には感情がないのか? みたいなことを考えていた。
そんなことを悶々と考えながら amaozn を徘徊していると『アトミック・リーディング: 読むことと書くことから考える読書術』という書籍がおすすめに出てきた。
書籍の詳細情報の目次を見てみると、第一章の中に『十時間かけて読んだ本の感想が「すごい」だけだった』という見出しがあって、おれか? 著者、おれなのか? という凄まじい共感が湧いていた。
kindle unlimited で配信されているということもあって、速攻で購入して読み始めることになった。この本を読めば自分も、「面白かった」以外の感想をアウトプットできるようになるのではないかという期待を込めて。
読後の感想が「面白かった」だけなのは、読書メモを書いていなかったから
本を読み終わり、本を閉じる。そのとき「面白かった」以外の感想がないのは、読書メモを取っていない自分にとって当たり前のことだったのかもしれない。
そもそも人間というのは忘れる生き物で、昨日の晩ごはんすら思い出せないこともあるのに、どうして自分は数百ページのテキストを記憶できると思っているのだろうか。しかもいちど読んだだけで。そんなのはどだい無理な話で、せめて読んでいる最中に自分が面白いと感じた部分に関してはメモを取っておかないといけなかった。
じゃあ読書メモをとりさえすれば読書記事を書くことができるようになるのか。これはそうなのだけど、今の状態ではじゃあどんな読書メモを取ればいいのかということがわからない。
面白かった文章にアンダーラインを引けばいいのか、覚えておきたい文章を写経すればいいのか、それが読書メモと呼べるのか、何もわからない。でもそれでは意味がないと本書には書かれている。そうじゃなくて、自分の言葉に変換することが必要らしい。
つまり「面白かった」以外の感想を持つためには、自分の言葉で書かれた読書メモが必要になる。
読書メモは自分の言葉で書かれなければいけない
自分はこれまで書籍の気になった文章にアンダーラインを引いたり、文章をそのまま引用の形式でメモしておくというようなことはすることがあった。でも本書ではそうではなく、自分の言葉で読書メモを書けという。
その理由は自分の言葉で書くためには、まず本の内容を理解していなければいけないから。それがアンダーラインを引いたり、写経したりするのとの大きな違いになる。
アンダーラインを引く行動はべつに内容を理解していなくてもできる。線を引くだけだ。写経も内容を理解していなくてもできる。テキストを書き写すだけだ。でも内容を自分の言葉でまとめたり、整理したりするためには理解が必要になる。これを本書では知的負荷という言葉で表現されている。
自分の言葉で読書メモを作成する行動には知的負荷が伴うけれども、そもそも知的負荷を伴わなければ知識は身につかない。ちょうどアンダーラインを引いただけの文章が記憶に残らないように。だから自分の言葉で読書メモを書くのはしんどいけど、そのしんどさの正体は知的負荷であって、知識をみにつけるためには必要な負荷なのだから乗り越えないといけない。だって読書の最大の目的はページにアンダーラインを引くことでなく、内容を理解して自身の知識を豊かにすることだから。
知的負荷の伴わない読書はただの消費活動でしかない。けれど知的負荷を伴う読書は生産的なものになる。
だから生産的な読書を望むのなら、読書メモを作成しないという選択肢はありえないということになる。
読書メモは理解するために書くというよりは理解できていないことに気づくために書く
ここまで読んで自分も読書メモを作成し始めた。そして本の内容を自分の言葉に変換しようとして、手が止まった。読んでいるときは理解しているつもりだったのに、いざ自分の言葉で要約しようとすると何も書けない。自分の言葉に変換するという行動によって、いかに自分がわかったつもりで読書をしているかに気付かされる。
とはいえ、理解できていないことに気づけたというのは理解に一歩近づいたとも捉えることができる。理解できていない事に気づけたのなら、自分が何を理解できていないのかを洗い出してみて、もういちど本のテキストを読み返してみる。そうすると一周目でも読んでいたはずの文章をいかに取りこぼしていたかに気づくことができる。
これは絵を書いているときに対象の細部に初めて気づくのに似ているなと思った。知っているはずのてんとう虫を書こうとして、あれてんとう虫の脚って何本だっけ、模様ってどんなだっけ、目ってどこに着いてるっけ、触覚ってあったっけ、羽って何枚だっけって初めて疑問と対峙する。その感覚に似ていた。本の内容を自分の言葉に変換しようとして初めて、あれ、そもそもなんで自分の言葉に直さないといけないんだっけ、知的負荷ってなんのために必要なんだっけ、そういうただ流し読みするだけでは取りこぼしてしまうようなことに気づくことができるようになる。
この辺は以前読んだ『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因 』にも通じるところがあるなと思った。
読書メモは自分が面白いと思ったところだけでいいし、それこそが個性的な読書メモ
「面白かった」以外の感想を発信するためには、つまり生産的な読書のためには、読書メモの作成をしないといけないことはわかったけど、本全体の読書メモを作成しないといけないと思うとどれだけ時間がかかるんだと気が遠くなる。
でもそんなことはしなくていい。そんな事していたら読書が嫌いになってしまう。読書は楽しくないといけない。読書メモは読書をより良く、より楽しくするためのツールでしかない。だから読書メモを作成するのは、自分が面白いと感じた内容についてだけでいい。むしろそれがいい。そうすることで自分だけの個性のある読書メモになる。
読書というのは本全体を暗記することが目的じゃない。本を読んで少しでも自分の知識システムが充実して、人生がより良くなることが目的のはず。だから本を読むことで自分の関心があることだけでも知識を得られたのならそれで十分。
読書記事を書くときは読書メモを組み合わせて書けばいい
自分はこの『アトミック・リーディング』を読みながら読書メモを作成していた。そこには「面白かった」以外の自分の言葉がたくさんあった。そしてその読書メモをパズルみたいに並び替えて、この記事をここまで書いてきた。
これからは生産的な読書をするために読書メモを欠かさず書いていくつもりだし、読書メモさえあればこうして読書記事も書けることが分かったし、これからの読書がいっそう楽しみになった。
おわりに
『アトミック・リーディング』の本懐はおそらくタイトルにもあるアトミックなメモの取り方や、そのメモが知識ネットワークを構築する面白さみたいなところにあると思ったけど、この記事ではその点にはほとんど触れていない。
自分の読書メモを見返して見たら、自分がもっとも面白いと感じていたのはメモを詳細というよりは、どうすれば「面白い」以外の感想をアウトプットできるかの方だった。人によってその本をどういう角度で面白がるかというのは違って当たり前だと思うし、本について語るとき、本の内容すべてを語ることなんて出来ない。語ることができるのは自分が面白いと思った中の、さらに一部分を語ることくらい。そのことにも気付かされた。
これまで読書記事には本の要約から入らないといけないみたいな息苦しさがあって尻込みしてしまっていた。けれど自分の言葉で作成した読書メモは、書籍に依存しないテキストになっているので、本の全貌を説明する必要なく、ただ自分が面白いと思った知識だけを読書メモベースに記事を書くことが可能になった。
また今回触れなかった読書メモの作成ルールみたいなものについては、本書をよむというよりは本書のベースになっているらしい evergreen note のサイトを見てみたり、あるいはその evergreen note のベースになっているっぽい zettelkasten という情報整理術についての書籍を読む方がいいような気がする。
自分は zettelkasten の情報整理術について調べたけど割りと感銘を受けた。ドイツの有名な学者が考案した情報整理術で、この学者はこの情報整理術を活用してめちゃめちゃ多数の書籍と論文を発表したらしい。
『アトミック・リーディング』を読んでいちばんよかったのは、実のところ引用の孫引きで zettelkasten を知れたことかもしれない。
『アトミック・リーディング』は amazon unlimited にある(2023/09/24 時点)ので、何を読んでも読後の感想が「面白かった」だけで悩んでいる方はぜひ。
おわり
参考文献
アトミック・リーディング
今回の記事の題材。
何を読んでも読後の感想が「面白かった」だけで悩んでいる方は読んでみて損はしないかもしれない。amazon unlimited で読める (2023/09/24 時点)。
わかったつもり 読解力がつかない本当の原因
いかに「わかったつもり」状態から先に進めばいいのかが丁寧に書かれている。以前、この本の読書記事を書いたのでぜひ。
勉強の哲学 来たるべきバカのために
読書メモは使い捨てではなく、常にメンテナンスして更新していくというのは、『勉強の哲学』で言われていた、知識は常に仮固定と再構築を繰り返しているというのと繋がっている気がした。
あとメモ同士のネットワーク的なものも『勉強の哲学』でスキーマの知識があったので腑に落ちた。
TAKE NOTES!――メモで、あなただけのアウトプットが自然にできるようになる
zettelkasten という情報整理術について書かれている書籍。
『アトミック・リーディング』で述べられてた読書メモのルールの出典らしきもの。evergreen note が元になっていると書いてあったけど、evergreen note は zettelkasten を元にしてるっぽいので、たぶんこれを読むのがいちばんいい気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
