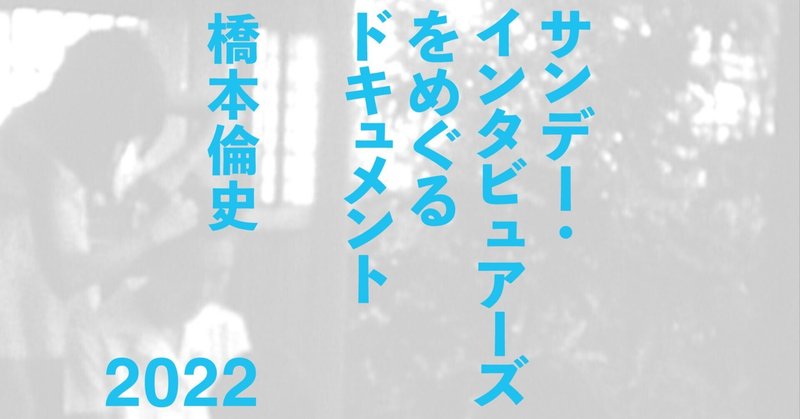
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」(文=橋本倫史)
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地”をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる〉〈はなす〉〈きく〉に取り組みます。2022年度に公募で集まったメンバー6名による活動記録。ライターの橋本倫史さんのドキュメントです。
連載第2回(全9回)
古い映像を見ると、昔の記憶がよみがえる。そこに自分の姿が記録されていなくても、かつて目にした光景が思い出されることがある。
aki maedaさんが No.31『東京転勤』の映像でタイムコードを切ったのは、00:38のところ。フェンス越しに飛行機が見える映像からmaedaさんが思い出したのは、幼い日の記憶だった。

「私は1977年生まれで、父と母の故郷が高知だったんですけど、生まれてから高校生ぐらいまでは毎年高知に帰っていたんです。母方の祖父母のうちが高知空港からすごく近くて、至近距離で飛行機が飛んでいるような風景を見ていたのを思い出しました。飛行機が身近だったこともあって、1985年の日航機墜落事故がすごく衝撃的でした」
1985年8月12日、羽田空港から伊丹空港に向けて飛び立った日本航空123便は、伊豆半島付近で機体を破損し、操縦不能に陥った。迷走しながら飛行を続けたものの、群馬県に位置する御巣鷹の尾根に墜落した。単独の航空事故としては過去最多となる520名もの方が命を落とし、衝撃を与えた。
当時8歳だったmaedaさんも、事件のことははっきりおぼえている。ただ、自分はどこでそのニュースに触れたのかとなると、記憶が曖昧だった。ちょうどお盆も近い季節だから、家族で高知に帰省していたのか、あるいは自宅で墜落事故を知ったのか──。
ニュースで報じられる社会的な出来事は、それが幼い日に起きたものだとしても強く記憶に残っていることがある。ただ、そのときテレビ画面の外側に広がっていたはず風景は、記憶から欠落している場合もある。フレームの外側に存在していたはずの営みを探るのも、サンデー・インタビュアーズの取り組みのひとつだ。
サンデー・インタビュアーズの活動は、3つのステップからなる。まずは「ひとりで“みる”」。毎月開催されるワークショップの前に、課題となる「世田谷クロニクル1936-81」の映像を見て、自分が気になったポイントのタイムコードを切る。オンラインで開催されるワークショップのときに、それぞれが気になった点を持ち寄って、「みんなで“はなす”」。これがステップ2だ。最後のステップ3は、「だれかに“きく”」。気になった点や、そこで得た気づきをさらに深めるべく、誰かにインタビューしたり、資料にあたったり、自分自身の経験を振り返ったりする。その内容を「ポストムービー」という名の葉書にまとめて、次回のワークショップで発表する。
初回のワークショップを終えたあと、maedaさんは家族に連絡をとり、当時の記憶をさぐることにした。日航機の墜落事故があった1985年というのは、お父さんが大阪に転勤することになり、maedaさん一家は1年ほど兵庫県西宮市に暮らすことになった時期だった。
ステップ3の「だれかに“きく”」を実践するにあたり、maedaさんは両親に電話をかけるのではなく、手紙でやりとりをする方法を選んだ。「大阪転勤が決まったとき、どう思いましたか?」という問いに、父は「忙しくなるな。大阪でも仕事やってみたい」と書き、母は「子供達の学校。幼稚園 慣れるかどうか心配。でも住んでみたいと思った」と綴った。また、西宮での生活で印象的だったこととして、「一人一人の個の力強さ」「自分では意識していないが光っている人が多い」と母は書き記している。
「これは母にも言ったんですけど、直接会話するのと、『どうだった?』って聞いて紙に書いてもらったことは、なんかちょっと違うなっていう感じがあって」。両親が書き綴った文面について、maedaさんはそう漏らす。「自分のことを書いているはずなのに、どこかの誰かが引っ越して、その記録を他人事のように見てる感じがして。こういうふうにテキストにしてもらうと、すごく客観性が生まれるんだなと思いました」
書きことばと話しことばには、大きなひらきがある。明治時代に原文一致運動が興り、近年はSNSを通じて誰もが言葉を発信できる時代になったとはいえ、質問に書きことばで回答するとなると、どこかよそいきの内容になる。また、語られる記憶はその時々で揺らぎが生じるのに比べて、活字として記された文字は、永遠に揺らぐことがない。だから、自分が知らない時代をさぐるとき、活字はわたしたちの助けとなる。
『東京転勤』の中で、まるやまたつやさんがタイムコードを切ったのは00:28、転勤する家族の姿が映し出されている場面だ。映像に映る父親は、びしっとスーツで決めている。九州から東京まで長旅に出るというのに、どうしてわざわざスーツを着ているのだろう?

「この映像を見たときに、なんでそこが気になったんだろうってことを考えて見たんです。自分の中の認識として、『スーツ姿というのはホワイトカラーの制服みたいなもので、休みの日に着るようなものじゃない』という前提のもと見てたから、スーツ姿のお父さんが印象に残ったんだと思ったんです。自分のまわりは自営業が多かったこともあって、スーツを着ていたのは曽祖父ぐらいしか浮かんでこなくて。その曽祖父は縫製工場を経営していたから、スーツ姿は社長さんスタイルだと自分の中で思っていたこともあるんだと思います」
あの時代だと、休日でもスーツを着て外出することが一般的だったのかどうか。
まるやまさんはまず、客観的な資料にあたってみることにした。明治以降に背広が日本人に広まっていく時代背景や、大正時代にモダンガールが登場したことで洋装が普及したことを調べた上で、身近な人たちにインタビューを実施した。
「まずは自分と同年代の祖父を持つ妻に話を聞いてみたら、妻の祖父も『出かけるときは普通に背広を着ていた』という話をされて。家にいるときはスウェットを着ていたけど、内と外で分けて服を着ていたよ、と。その方はのちに牧師さんをされるんですけど、休日は教会に行くことも多かったみたいで、たしかに教会に集まる方ってそういう格好をしているよなと思いました。もうひとり、僕よりちょっと上の年代の方にも話をみたんですけど、その方は『東京転勤』に出てくるぐらいの年齢の方を義理のお父さんに持つ人なんですね。その義理のお父さんに結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて、『すごいおしゃれな人なんだな』と思ったそうなんですけど、結婚して何度か顔を合わせるうちに、『自分が結婚の挨拶に行くから、ちゃんと着飾った格好で会ってくれていたんだ』と気づいたそうなんです。そういうことは今でもあると思うんですけど、上の年代の人たちはきっちりやってたんだなということを思ったりもしました」
誰かと連絡を取り、待ち合わせをして、直接顔を合わせる。携帯電話やインターネットが普及する前の時代には、そのことの重みが異なっていたのだろう。
「自分の引っ越しを振り替えてみると、当日は常にバタバタしていて、しっかり着飾ったり誰かに挨拶に行ったりする余裕がないことが多かったので、この『東京転勤』の映像が浮かばなかったんですよね。この当時は今ほど東京都の距離が近くない中にあって、しばらく会えなくなるということで別れを大事にしていたんだとしたら、そういうときに着飾るのは当然だなと、自分の中ですごく腑に落ちました」
小島和子さんが注目したのも、映像に記録された服装だ。
「01:30あたりに写っている吊りスカートを見て、『私もこういうの履かされていたな』と思ったんですけど、このおかっぱの髪型というのも当時はすごくオーソドックスだったんだろうなと思いました。さきほどのまるやまさんも洋服に注目されてましたけど、服装や髪型には世相や流行があらわれるので、そういう点で少し似たような視点をお持ちだったのかなと思いながら話を伺っていました。髪型や洋服の歴史というのは、きっと今和次郎さんあたりがカバーしてらっしゃるフィールドかな、と」

考現在学の提唱者・今和次郎の著書に、『ジャンパーを着て四十年』がある。1967年に文化服装学院出版局より刊行され、今年の夏にちくま文庫に入った。この本の中で、今和次郎は礼儀作法と衣服の歴史を辿っている。明治以前の慣習を打破したのは、ひとつには「文化生活」を提唱した有識者がいたからだと今和次郎は記す。それに加えて、関東大震災と戦災によって物資が不足したことが、日本人の慣習を変え、衣服も変えたのだ、と。
ところで、タイトルにもある通り、今和次郎はずっとジャンパーを着て暮らしていた。彼がジャンパーを着て暮らすようになったきっかけもまた、関東大震災がきっかけだった。「震災のときも、戦災のときも、乱世の昔ではないが、みんなの服装はぎりぎりの粗服になってしまった」。震災のときは、やがて世の中の服装は元に戻りかけたが、「ぼんやり者のわたくしの服装だけは、手遅れになって、震災当時のままでストップしたのである」。
ストップした、と今和次郎は書くが、「ストップさせた」といったほうが正しいのではないか。どこへ行くにもジャンパーを着ていると、世間との間に摩擦が生まれるし、何より家族にも反対されたけれど、それでもジャンパー姿を貫いたのだ。
家庭の妻や子供たちは、どうみていたかというと、はじめは大まさつだった。みっともないとか、失礼だとかいう世の中の通念をふりまわした。世の中でのなやみ以上にこれにはまいったのだが、そこは根性の問題だと思ってがまんした。慣れてしまうと小言も消えるだろうと待ったのである。
ジャンパーが「失礼」だと受け取られるのは、礼儀作法に反している服装だと見做されるからだ。だが、今和次郎は「世の中の通念」に従うのではなく、礼儀作法とは、エチケットとは何かと問い続けた。そして、自分の結婚式も、教え子の結婚式にも、宮様からお招きを受けたときにも、アメリカ大使からパーティーに招かれたときにも、ジャンパー姿を貫いた。
今和次郎が亡くなって、もうすぐ半世紀が経つ。今ではラフな格好で出歩くことに抵抗を感じる人は少ないだろう。その背景には、常識を疑い、信念を貫いた誰かがいる。普段からラフな格好で暮らしているけれど、誰かの結婚式で、伴侶の葬儀で、ジャンパー姿を貫けるだろうかと自問自答する。
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2022
第1回「時間が経てば経つほど、見えないものが見えてくる」
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
第6回「電子レンジがあるはずなんだけど、ないんだよね」
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」(最終回)
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
