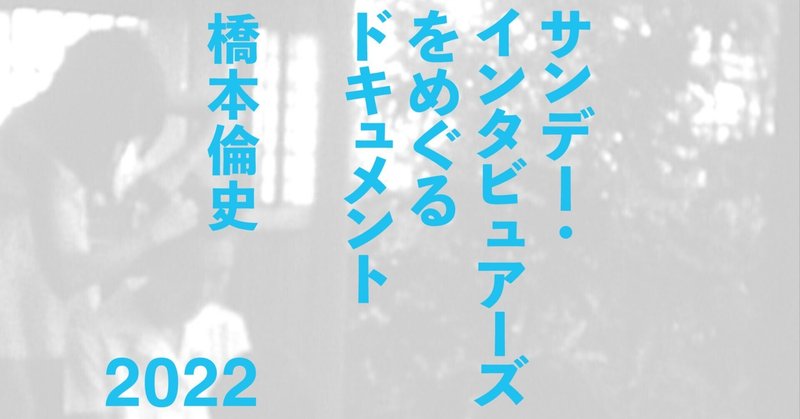
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」(文=橋本倫史)
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地”をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる〉〈はなす〉〈きく〉に取り組みます。2022年度に公募で集まったメンバー6名による活動記録。ライターの橋本倫史さんのドキュメントです。
連載第3回(全9回)
8月のワークショップで新たな課題となった映像は、No.69の『新百貨店落成式など』だった。映像の冒頭に記録されているのは、世田谷の大通り沿いに新装開店した“百貨店”の落成式の様子だ。
「この映像で一番気になったのは、写っている対象よりカメラワークのことで」と、参加者のアキさんがタイムコードを切ったポイントについて発表する。「たとえば00:37のところ、花輪の送り主の名前を全部カットに収めていたり、会場の様子や来賓もすごく細かなショットで押さえていて、記録を残そうという意識がすごく感じられるなと思いました」

アキさんがもうひとつ気になったのは、この映像がどのようにアーカイヴされたのかということだった。
『新百貨店落成式など』には、落成式の映像の他に、戦友会の集まりや家族旅行、屋上のプールで遊ぶ家族の姿など、バラバラの場面がひとつにまとめられている。しかも、昭和45年に撮影されたフィルムと、昭和55年に撮影されたフィルムがひとつにまとまっていて、再生時間は36分4秒に及ぶ。「世田谷クロニクル1936-83」としてアーカイヴされている映像の中でも最長のフィルムだ。
「ご提供いただいた8ミリフィルムをデジタル化するとき、どんな工程を経ていたかというと、基本的には編集はしていない状況です」。松本篤さんがアーカイヴの手続きについて説明する。「個人情報が入っている箇所に関しては、フィルム提供者に『ここ、カットしますか?』と確認して、ご本人を守るための選択はしてもらっていますけど、『別にそのままでいいよ』と言っているものはそのままデジタル化しています。なので、こちらで恣意的に繋げ直したり、カットしたりした部分はない状態になっています」
デジタルの時代を迎えた今では想像しづらい話になりつつあるが、フィルムには撮影できる時間に限りがある。8ミリフィルムの場合、短いものだと1本で3分半しか撮影することができない。フィルムを現像し、繋ぎ合わせることで、長い映像として映写することが可能となる。
『新百貨店落成式など』もまた、複数のフィルムが繋ぎ合わされ、直径30センチ近いボリュームになっていた。撮影された時代も違えば、シチュエーションもまるで異なるフィルム同士を、どうして一本に編集しようと思ったのか。映像を撮影・編集した誰かはもう他界されていて、その理由を解明することはできないけれど、そのままの状態で「世田谷クロニクル1936-83」にアーカイヴされている。
二人目の発表者・小島和子さんがタイムコードを切ったのも、映像の編集にまつわる箇所だ。
「アキさんもご指摘されてましたけど、18:52あたりでムービータイトルが入ってますよね。23:50のところにも『伊東一碧湖へ/いこひの二泊三日/昭.55.8.20.21.22.作品』とタイトルが入っているので、こうやってタイトルを入れるのを習慣にされていたんだなと思ったんですけど、18:52のほうは『店を閉め家族揃って天下の剣』という言葉が書かれていて──これはご自身のポエムなんですかね? 『作品』と書かれているぐらいなので、こういうポエムがあったほうが作品らしくなるという感覚がおありだったんでしょうか。それで言うと、昔のドラマはやけに説明調のナレーションが入ることがありますけど、そういうトーンに近いのかなと思いました」

8ミリフィルムの時代に比べると、気軽に映像を撮影できる時代になり、映像に文字を入れる作業も手軽におこなえるようになった。SNSで映像をのせる場合に、文字を添える場合もある。
「小島さんからご覧になって、今のSNSのおこないとこの映像はちょっと違う感じがありますか? それとも、時代が変わっても、形式は違っても自己演出があるという部分では共通する部分があると思いますか?」と、松本篤さんが尋ねる。
「“それっぽさ”を意識するというのは、この『新百貨店落成式など』のほうが強く感じますよね」と小島さん。「今はもう、共通の“それっぽさ”を持っていないということかも思いますけど。この8ミリを撮影された方は、アングルに気を配っているのはわかりますし、一碧湖の映像では女性二人を主人公のようして、ずっと追っていますよね。それを観ていると、テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうなというのはすごく感じます。今、SNSにあげているものを作品と思っている人がどれだけいるだろうかとも思います」
8ミリフィルムが登場したばかりの時代にはまだ、映像を撮影して記録に残すことができるのは限られた人たちだけだった。撮影機材を初めて手にしたとき、映画表現で目にする“それっぽさ”を踏襲してしまう部分もあったのだろう。
一碧湖への家族旅行を記録した映像は、カメラをゆっくり横にフレーミングして、宿泊する施設や湖を収めている。湖上でボートを漕ぐ様子がしばらく映し出されたあと、場面は宿に切り替わる。宿泊施設の片隅にある荷物に目を留めた事務局の水野雄太さんが「これ、映写機っぽいですね」とつぶやく。
「映写機やね」と松本さん。
「映写機が写ってるってことは、旅行先で映像を見ようとして持ち込んだのか──でも、撮影した8ミリフィルムは現像しないと映写機で見れないですよね。奥に編集機も映っているから、別の時に撮影したフィルムを編集しようとしていたようにも見えますね」

家族で旅行に出かけるとき、8ミリフィルムを持参することは理解できる。旅先でなにかの映像を皆で見ようと、映写機を持っていくというのも、今のようにオンデマンド配信で好きな映像を観るどころか、ビデオすら普及していなかった時代だということを考えれば納得がいく。でも、家族旅行に編集機を持ち込むというのは、一体どういうことなのだろう? この映像を見ていると、現在と比べて、旅にかける意気込みがまるで違っているように思えてくる。
思い出されたのは、民俗学者の柳田國男のエピソードだ。
民俗学者の柳田國男は、太平洋戦争を目前に控えた昭和16年に、講演旅行に出ている。この旅に鞄持ちとして同行した今野圓輔は、その様子を『柳田國男先生随行記』として出版している。今野は数十年前の旅をこう振り返る。
さて、この随行でいちばんつらかったことは、一日中、窓外を眺めていなければ、先生のご機嫌が悪いことだった。東京の中学に転校したばかりのころ、東京の景色が珍しくて、池袋駅から田端駅まで、窓から顔を出しっぱなしで風に吹かれながら眺め眺めしていて、顔面神経痛になったことが思い出された。二、三時間ならともかく、私にとって何ともない野や山や農村風景などを、汽車が走っているあいだじゅう、窓外を眺め続けることは難行苦行であった。先生にとっては、幾十度となく通りなれていても、その都度、新鮮な喜びだったらしいが、私にとっては、ただ退屈な窓外の景色にすぎなかった。しかし、先生は、
「人々の暮らしが少しずつ推移することもあるが、風景というものは君、同じ風景は、二度とはけっして観られないものなんだよ。来年の今月の今日、まったく同じ時刻に通ったとしても、天候も風の具合も光の加減も違っているだろう。だから、まったく同じ景色というものは、けっして二度と見られるものではない」
とおっしゃる。それはなるほど、そのとおりにちがいないが、だからといって、五日も窓の外ばかり見ているわけにはいかないのが、素人の悲しさというもの。(…)
ある評論家は、柳田國男の名前を挙げ、「日本人にとって、列車の旅行はすべて物見遊山」だと書き記していた。
「物見遊山」と書けば、いかにもお気楽な旅のように思える。でも、何時間も窓外の景色を見つめ続けた柳田國男や、旅先に映写機や編集機を持ち込んだ誰かのことを考えると、その「物見遊山」の真剣さが伝わってくる。わたしたちは今、それほどの真剣さを持って風景を凝視し、記録を残しているだろうか?
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2022
第1回「時間が経てば経つほど、見えないものが見えてくる」
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
第6回「電子レンジがあるはずなんだけど、ないんだよね」
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」(最終回)
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
