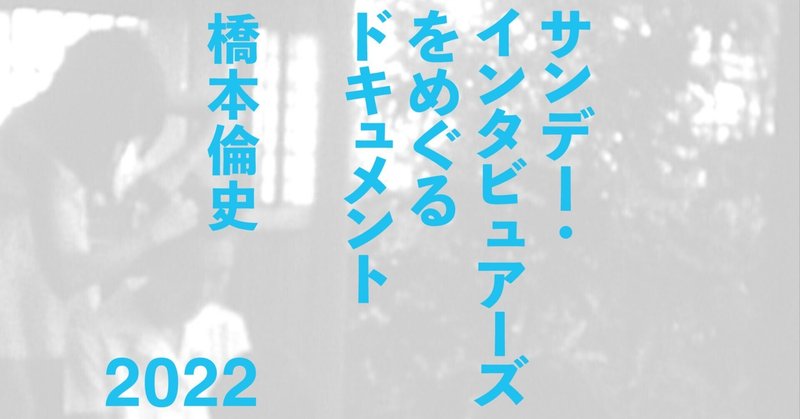
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」(文=橋本倫史)
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地”をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる〉〈はなす〉〈きく〉に取り組みます。2022年度に公募で集まったメンバー6名による活動記録。ライターの橋本倫史さんのドキュメントです。
連載第4回(全9回)
サンデー・インタビュアーズのワークショップには、毎回“帰り道の時間”が30分ほど設けられている。ワークショップが終わったあと、時間に余裕がある参加者だけが残り、その日の感想や雑談をする時間だ。
8月のワークショップの“帰り道の時間”で、その日の感想を語り合っていたとき、Zoomの画面には『新百貨店落成式など』の映像に収録された、一碧湖を旅する様子が映し出されていた。8ミリフィルムは、一碧湖の湖上でボートを漕ぐ女性を映し出す。

「今のシーンでふと目を取られたのは、被写体になっている女性がカメラを取り出して、こっち側を撮るところで」。松本さんが話を切り出す。「8ミリフィルムはお互いの距離が映りやすい媒体だなと思っているんですけど、こういう映像を観ているとなんとも言えない気持ちになりますね。このとき撮った写真は、今もどこかにあるのかなって考えてしまう」
こうして「みんなで“はなす”」時間が、次のステップの「だれかに“きく”」に繋がってゆく。
翌月のワークショップで小島和子さんが注目したのは、まさに女性がカメラを向け返す場面だ。
「このシーンは一瞬だったので、最初にひとりで観たときには見過ごしてたんですけど、前回言及されているのを聞いて『ああ』って気づいたんですよね。あらためて見返してみて、あそこで撮る/撮られるが反転した感じが面白いなと思いました」
その映像から小島さんが思い浮かべたのは、ノンフィクションライター・最相葉月による『れるられる』だった。人生の「受動」と「能動」が転換する境目について、「生む・生まれる」、「支える・支えられる」、「狂う・狂わされる」など、6つの動詞をもとに綴られる随筆集である。
「この本のひとつの章の中で、癌を患ってお話しができなくなってしまったお父様とのやりとりに関するエピソードが綴られているんです。お父様は筆談で意思を伝えることはできるんだけれども、自分の言葉で伝えられないことにすごくストレスを感じてらして、最相さんとしても筆談だとコミュニケーションができている感じがしないことに気づかされた、と。その話を読み返して、聞いてもらうことがどれほど大事なのかと、改めて思いました」
撮影するという誰かがいるとき、そこには撮影される誰かがいる。
『新百貨店落成式など』の映像をもとに、アキさんが「だれかに“きく”」のステップで思いを巡らせたのは、8ミリフィルムで撮影された記憶だ。アキさんのお父さんは8ミリフィルム用のカメラを所有しており、幼い日のアキさんを撮影していた。そのフィルムをもとに、家族だけの上映会を開催したこともある。その上映会は、アキさんにとって楽しい記憶として残っている。
父はなぜ、8ミリフィルムを撮影し、上映会をひらいたのだろう──?
アキさんの質問に、「写真が好きだったから」とお父さんは答えた。お父さんがまだ小学生だった頃、雑誌の付録に組み立て式のカメラがついてきたことがあった。そのカメラで近所の下級生を撮影したりするうちに、写真に対する興味が膨らんでいく。大学生になると自分でカメラを買い、こどもが生まれてからはよく写真を撮り、自分で現像までしていたのだという。
ただ、写真だと動いている姿は記録できなかった。あるとき、富士フイルムから格安の8ミリフィルムが発売されると、アキさんのお父さんはこれを買い求めて、映像も撮影するようになった。フィルム代もかかれば、現像や編集に手間がかかることもあり、当時でもあまり一般に普及していた趣味ではなかったけれど、アキさんのお父さんは娘の姿を記録に残そうと撮影した。
時代が下り、VHSビデオカメラが普及し始めると、「8ミリフィルムを保存するにはVHSで記録し直すほうがよいだろう」とアキさんのお父さんは考えた。古い8ミリフィルムカメラでは音声が記録できず、無声映画のようになっている。せっかく記録し直すのであれば、これに音声を加えようと、アキさんのお父さんは上映会を企画した。そうして娘であるアキさんにアフレコをさせたり、キャプションを加えたり、音楽を入れたりした。そんな時間が、アキさんの中に楽しかった記憶として蓄積されていたのだ。
「今日参加されている方の中で、8ミリフィルムが家に残っている方はどれぐらいいますか?」と、松本さんが質問を投げかける。
「うちはないです。カメラはあったけど、ビデオカメラはなかったです」とaki maedaさん。
「私もちょっと、年代的に8ミリはなかったです」と、たにぐちひろきさん。「ただ、カセットテープで撮影するビデオカメラは実家にありました。買ってすぐの頃は父親も色々撮っていたんですけど、私も親も撮られるのがあんまり好きじゃない性格だったので、写真ばかりになっていった記憶があります。ビデオはむしろ、ディズニーランドに出かけたときにパレードを撮るとか、家族以外のものを撮ることが多くなったような気がします」
家族の距離感というのは独特なものがある。友達のように仲が良い親子であれば、お互いに動画を撮りあうこともあるのだろう。でも、家族同士でカメラを向け合うことに抵抗をおぼえる人も少なくないはずだ。
「うちも動画はなくて、カメラしかなかったです」と小島さん。「撮り手は父でしたけれども、それもそれほど熱心にやっていたわけではなくて。私はたぶん、撮られることが嫌いだったんですけども、自然なショットを撮ろうとすると不意打ちをするわけじゃないですか。それで出来上がった写真を見せられて、『こんなものいつのまに撮っていたんだろう?』となるのが嫌いでした。母親としては、いかにも女の子らしい感じで写っているのは嬉しかったらしく、そういうショットが撮れていると喜んだりしてましたけど、自分の意思とは関係ないことをされているのは気持ち悪いので、なんか嫌でした」
小島さんのお父さんは、さほど熱心に写真を撮っていたわけでもなかったという。それでもカメラを購入し、娘の自然な姿を写真に記録しようとしていたのは、「そういうことをするのが、核家族の父親としてあるべき姿とまでは言いませんけども、どこの家庭でもやっていたんじゃないですかね」と小島さんは振り返る。
“核家族の父親としてあるべき姿”という規範は、時代が移り変わった今でも、どこか残り続けているような気がする。ただ、その規範は、時代の変化とともに変容しつつある。
『新百貨店落成式など』で、まるやまたつやさんがタイムコードを切っていたのは、22:40のところ、家族で温泉に入る場面だった。
「この映像を見ると、8ミリとは別に写真も撮っているんだと思うんですけど、カメラに向けてポーズをとっているところが映っていて。自分のアルバムや知人のアルバムを見ると、お父さんと一緒にお風呂に入っている写真ってなぜか残っているなと思いました。もし今の自分にこどもがいたとして、お風呂で裸のこどもの写真を撮ることって倫理的に許されるのかなと思いました」

言われてみると、幼い日にお風呂場で撮影された写真というのは、何度となく目にしたことがある。今のようにスマートフォンを気軽に風呂場に持ち込める時代ならともかく、湿気が天敵となるフィルムカメラを風呂場に持ち込んでまで入浴風景を撮影しようとしたというのは、ちょっと不思議な感じがする。
こどもの人権に対する意識が高まっている今では、こどもの写真を撮影したとしても、インターネットにアップする場合は必ず顔を隠すという親も増えている。そんな時代にあって、風呂場で写真を撮るというのは、たとえインターネットで公開しないとしても、今の時代には許されないことなのかもしれない。
「今のお話は、社会的に許されるのかって倫理観もありますし、個人的な倫理観もありますよね」と松本さん。「それに、この8ミリフィルムはこうして公開されることを予測されていなかったもので、家の中で閉じられた記録として撮っていたはずのものなので、それを公開する倫理についても考えさせられました」
「これは撮影者の了承を得て公開されているものなので、そこは気にしていなかったんですけど、たとえばスマートフォンで撮影してしまうと、その中だけで完結しない感じがあるというか」と、まるやまさん。「スマートフォンで撮ると、外側に繋がりやすいから、個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまうのかもしれないです」
8ミリフィルムの時代に比べると、手軽に映像を記録できる時代になった。スマートフォンの中には、膨大な記録が残されている。その膨大な記録は、たとえば50年後の未来に、どんなふうに見返されるのだろう。ニュース映像にさえモザイクがかかる時代の街並みは、アーカイヴして参照することが可能なのだろうか?
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2022
第1回「時間が経てば経つほど、見えないものが見えてくる」
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
第6回「電子レンジがあるはずなんだけど、ないんだよね」
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」(最終回)
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
