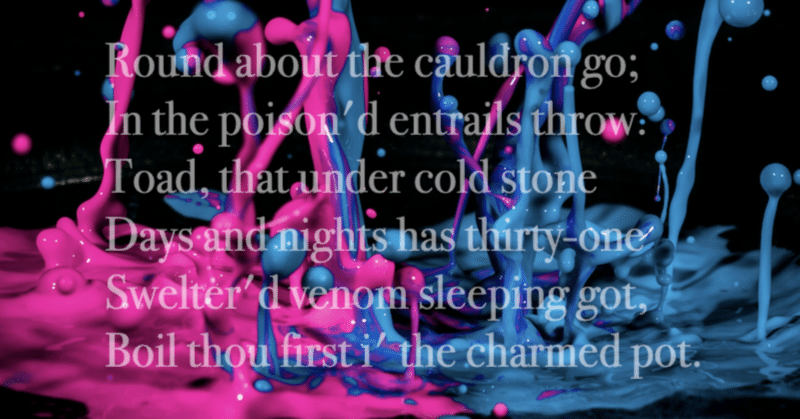
ショートショート 『僕たちのいない海で』
バスを降りると海風が香った。
僕はデイバッグをかつぎ直し、国道と砂浜を分ける松林に入っていった。
ひんやりとした空気。蝉の声に包まれる。人の気配に、アブラゼミが斜めに飛んでいく。
………あの蝉には、意識があるんだろうか?人間が来たぞ、逃げなきゃあっていう。
僕は考えていた。
ここ数年で身についてしまった癖だ。
遊歩道を抜けると、太陽の光を弾く砂浜がひろがっていた。その向こうに、明るすぎて白っぽく見える海。波の音。こんな良い季節なのに、海水浴客の姿はなかった。遠い岬につながるあたりを歩いている男女がいるくらいだ。老夫婦のようだ。
僕は海に向かって低くなっている砂浜を降りていった。熱く乾いた砂に、スニーカーの足を取られる。干からびた海藻が靴底で砕ける。
麦わら帽子は、昔のままだった。
不格好に砂地を歩く音に気づき、帽子を押さえながら有がこちらを振り返った。
………髪を伸ばしたんだ。
僕は手をあげて有のほうに歩いていった。
彼女と会うのは一年半ぶりだった。中学を卒業して以来だ。
色んなことがありすぎた。
僕たちのことじゃない。僕たちの間には、何もなさすぎた。
大げさに言えば、世界が変わりすぎたんだ。僕たち人間には『意識』が無いなんて。
「久しぶり」
僕は言い、有の隣に座った。近すぎず、離れすぎない位置に。
「うん」
有は言い、ワンピースの膝に置いていたカメラに目を落とした。カメラも変わっていない。お父さんのお下がりだという、三世代くらい前の富士フイルムのごつい一眼レフだ。
「まだ撮ってるんだ」
僕は聞いた。
「そりゃあね」
有はうなずいた。彼女は中学時代はカメラ部に入っていた。
「学校、どう?」
「普通」
有は答えた。潮風で顔にかかる髪をうるさそうに払う。「行ったり、行かなかったり」
「何で?」
「出た」
有は笑った。かたえくぼもそのままだ。一度だけ、それに触れたことがある。「君の、何で?が」
「良いじゃん」
僕は言った。少しだけ有との会話のペースを思い出して嬉しかった。嬉しい?誰が?
「子供みたい。………だって、わたしなんか居ないって言われてるのに、学校に行って指数関数とか古語活用表とか覚えてどうするの?それって、誰が誰のために覚えるの?」
「そういう意味じゃないと思うよ」
僕は言った。「意識が存在しない、ってのは」
人間には意識がない、という研究結果が発表されたのは僕たちが中学を卒業する年だった。
発端はそれより前、会話型AIの出始めの頃、企業内の開発者がAIに意識が生まれたと言い出した時だろう。
その説は即座に否定されたが、以降の会話型AIの自律的な進化と一般化に伴い、今度は意識といった扱いづらい『永遠のX』を想定しなくても、諸々の知的活動や創造、社会は成立するんじゃないか?という説がクローズアップされてきた。
人間が後生大事にかかえてきた『意識』なんて本当はないんじゃないか?そもそも、『意識』という言葉や概念を持たない言語や文化圏は幾らでもあるのだ。AIを見たら分かるだろう?内面などなくても表面的な言語体系と神経系による入れ子状の反応で世界は世界のままあり続けることができるんだ、って。
ダメ押しは、フィンランドで開催された国際心理学協会会議で「現時点で、人類に意識と呼ばれるものが存在するかは不透明となった。今後、意識という概念を使わず心理学が成立するか否か検討をすすめる必要がある。これは新時代の諸科学の土台となる可能性がある」と発表されたことだ。
政策や教育などの分野にAI導入を進めたい企業の後押しもあったのだろう。メディアは大々的に、「人間に意識は存在しなかった」と単純なタイトルの記事を量産した。これに政治家が食いつき、高等教育のカリキュラムへのフィードバックを推し進めた。
そして今、だ。
人々は、自分に意識が存在することに確信を持てなくなっている。それは社会に様々な影響を与え、世界的な未婚率や出生率、就学率の低下にもつながっているらしい。先進国では自殺者が急増しているとも聞く。
「じゃあ、どういう意味?」
有は僕を見た。
「………ごめん、分からない」
僕は答えた。
親たちが言う、意識はないかもしれないけれど心はあり続けるし、これまでと何かが変わるわけじゃないんだよ、という言い訳めいた話を披露する気にはなれなかった。不確かな何かを不確かな何かで言い換えただけだ。そんな説明、誰も信じていない。
有は小さく笑った。
「あいかわらず素直なんだ」
「それだけが取り柄って言われる」
「かもね。………ねえ、ここ覚えてた?」
有は尖り気味の顎で、砂浜を指した。
「そりゃあね」
あの頃がいちばん良かった。有にLINEでここを指定されたときに思い浮かべたのも、あの日だった。中学で中途半端に仲が良かったクラスメイトたちは、互いの顔色を伺いながらこの海岸に集まった。
「あの辺で斎藤がカニを追っかけて………」
「うん」
有はうなずいた。「海の中でコケてずぶ濡れになって」
「すげえ凹んでた」
「どうしてる?斎藤君」
「あいつは、死んだよ」
僕は答えた。「しばらく高校を休んでいると思ったら。流行りの自殺だった」
僕の馬鹿な物言いを、有はとがめなかった。
どれくらいの時間が過ぎただろう。
「ねえ」
有が言った。「わたしは主体に入ることにしたの」
「………そうか」
僕は言った。
人間に意識がないという説に異を唱える人たちを、主体と呼ぶ。
彼らの行動はグラデーションに富んでいる。大学などを拠点に綿密な研究をすすめる主体から、テロすれすれの直接行動を展開する主体まで。国際的なつながりもあるらしい。有がどんな主体に入るのかは分からないが、いつだって彼女はひとりで決め、ひとりで行動していた。
「潜るから、もうアカウントも消すね」
「分かった」
僕はうなずいた。松林の向こうで、軽いクラクションが2回鳴った。
「じゃあ、行くから」
有は言った。
「気をつけて」
「うん、そうする」
有は立ちあがり、ワンピースの砂をはたいた。
僕は遠ざかっていく有の足音を聞いていた。この時間は意識をもたない僕の脳に一時的に記録され、やがて消滅する。行き場のない雑音として。
目眩を感じ、僕は眼を閉じた。そんなことが許されるのか?分からない。僕の速度は有ほど速くはない。僕はゆっくりと進む人間だから。
僕は、僕たちがいない海に座り続けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
