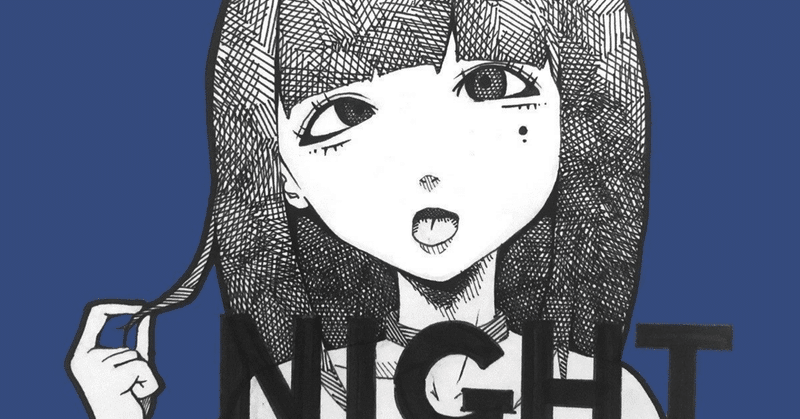
歌作りはどう生きるか
昨日「なにか創り出す際に罪悪感とか持たないで発出すること」について考えてたら、割とずっとその考えに囚われているので書いています。ヘッダ画像をお借りしています。
それはガラス工芸の人が「あたしはガラスを造るけど、そこに何を背景とすしたかみたいなテーマは確かにあるけど、見た人がそれを注文通り受け止める必要はない、当該物体を見て何か欠片でも心になにか思い浮かんだのであれば、それに勝ることはない」と言ったことでした。
それまでぼくは歌を書いても、ぼくが散々ここで書き散らしているように恋愛についてなんて書きたくないからそういう言葉を載せられず、一般受けしないことを織り込み済みで作り続けていたのだがそれは別に問題なかった。恋愛を求めてる層にぼくの歌を聴かれてぼくは嬉しがらないだろうという図に乗り方をしていた。
歌とはメロディありきなわけです。この泣きメロにはこの単語が似合う、というような作業を3分~8分ぶんの歌の歌詞がある部分すべてに打ち込んでいくのが、歌を造るという作業です。もちろんそうじゃない人もいます。さらにはぼくは言葉を先に造ってからメロディを乗せたこともあり、何が普通の作り方なのかわからない。
先に歌詞がある状態で歌を造るのはメロディが浮かばないと地獄だった。できたとて何かこれまでぼくが異様に入れ込んでた歌のフレーズを丸ぱくりしてしまう現象さえ起きてしまう。
そのため先にメロディがあり、このコード進行そしてこのメロディに合う母音とは何かを探すというパズルみたいな作業の方がぼくにとって正しかった。
自然偶発的に浮かんだメロディに対し、自己判断で正しそうな日本語を生めていく行為に対し正当性的なものを感じていた。神聖ローマ帝国的なものを感じていた。たぶんこのメロディにはこの言葉を当てるのが正しいのだろうと。
だから自分でメロディを編み出し、コード進行を授け、正しいとされる言葉を当てはめて歌が完成する。なんかすげー正しいものを生み出しているように見えるわけです。
もちろんその後楽器で演奏して、うたいづれ~ってなったら単語を直したり2番が邪魔だったら削ったりするわけですが、ひとまず歌を生み出すまでの過程にはそれだけで完結してしまうような「何か感」があったものでした。
だから正しいことをした結果その歌が(スタジオの)スピーカーとかから流れてるんだし、受け取る側が違うメッセージを得てしまったのであればそりゃぼくが悪いのか、受け取った人が悪いのか解ってなかったしどちらと言い切ることもできなかったんですね。
でもそれだと自己満足なのでは?って言われるかも知れない。だからそう言われたらそりゃその通りですよと、自己満足以外に何か造るって別に職の業じゃないんだから、と思っていた。
でも別に良かったんですね。0から造られた歌を聴いた人がほんとどうでもいいことでも何かを思ったのであれば、その歌は存在した意味がある。作者が「いい歌、造ってやったぜ」と思うこと以外にもです。
どころか、翻って誰かに何かを思わせたのであればその歌は尊いしその歌を聴いて何かを思った人も尊いのだろう。思わせられなかった歌に価値がないとはぼくは思わないわけです。造った人が満足したからリリースするわけですし。。
そう思うと、別に満足してもいないのに歌をリリースるなんてそんなバブル期以降の産業ロックじゃないんだから、ノルマみたいに作らされる量産歌謡じゃないんだから、今この時代にそんな歌は流れてるわけないだろうと思うと価値がない歌なんてないことになる。さらに翻ってぼくが苦手とする恋愛を歌ってしまう歌にも……
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
