
目からウロコの法華経講話〈第1巻〉(2010/12/01)/久保田尭隆【読書ノート】

序品じょほん第一
序品第一のあらすじ
マガダ国の首都、王舎城(ラージャ・グリハ)の東北に霊鷲山(グリドゥラ・クータ)があります。この地にお釈迦さまはとどまっていらっしゃいます。ご年齢もすでに七十歳を越えていらっしゃいます。
さて、今しも、お釈迦さまはお説法をなさろうとするのでしょうか、無量義処三昧という深い瞑想のなかにいらっしゃいます。周囲には多くのお弟子がひかえています。また菩薩やその眷属、さらには神々や鬼人たちもひかえています。
おりしも、不思議な現象が次々に起こりはじめるのでした。あまりの不思議のため、弥勒(マイトレイヤー)菩薩は、この不思議現象の意味を知っていると思われる文殊師利(マンジュ・シュリー)菩薩に、「どうしてこんな不思議が起こるのでしょう?」とたずねます。すると、文殊師利菩薩がこう答えるのでした。
「ずっと昔、日月燈明仏という仏の時代に、これとまったく同じ光景がくり返されたことがあります。その時、日月燈明仏は法華経という教えを説かれました。お釈迦さまもおそらく法華経を説かれるのだと思われます」と。
お経が「如是我聞」で始まる意味
「一番いいのはな、どんどん勉強してな、それを片っ端から忘れていくことなんじゃ」
「人間の頭とか心に扉があるとする。するとな、扉を開けると、手を突っ込んで中身を出せる部分があるんじゃ。そこに貯めておくのが、普通に言うところの〝覚えている〟ということでな。これは、いつでも好きな時に、手を突っ込んで取り出すことができる。だから、聞かれたら、何でも答えられる。しかし、奥の奥にしまいこんだものは、外から手を突っ込んでも取り出せない。これは、はたから見たら〝忘れている〟ように見える。しかし、本当はそうではないんじゃ……。だからな、一番いいのは、どんどん勉強することであり、それを片っ端から忘れていくことじゃ」
***
皆さんも、ここで知識を増やしていこうなどと考えないで、反対に、どんどん忘れていってほしいのです。なぜなら、私は覚えておいて役に立つような経文の解釈などは、あまりするつもりがありませんし、やりたくないからでもあります。
舎利弗→大迦葉(だいかしょう/マハー・カッサパ)頭陀第一:結集(けつじゅう)
阿難(アーナンダ)多聞第一:お釈迦様の侍者(従兄弟の関係・美男・結集前夜に悟りを開く)⇒如是我聞(かくの如く我聞けり)⇒口伝
法華経という経典を理解するコツ
"百聞は一見にしかず"の「一見」がなにより大切な経典。
語句の解釈や教義の解釈ではない法華経の話をしたいと言ったのは、そのため。
「どんなふうに見るか」「どんなふうに聞くか」という基本姿勢を常に意識しながら、自分自身の舵取りをおろそかにしないこと。
モーツアルトの手紙
純度一〇〇パーセントの教え
法華経の学びとは、単なる文字の解釈を超えた深遠な旅路である。まず目に見える層、すなわち経典の文字に刻まれた言葉の海を渡る。ここには、壮大な物語、多様な登場人物、そして緻密な構成が織りなされている。文字としての法華経を知る旅は、学術的な論文や専門家の解説を通じて、さらに深く、詳細に理解を深めることができる。
しかし、法華経の学びはそれだけに留まらない。文字を超えた「法華経独特の世界」への旅がある。これは言葉では捉えきれない、経文の背後にある精神性や哲学、感覚の世界である。まるで経文の文字が消え去り、そこに残された真実のエッセンスを感じ取るような旅。この世界を真に理解するためには、一瞬で全てを見渡すような広い視野や、微細な感覚が必要とされる。
かつて、霊鷲山の静けさの中で、仏陀は大比丘衆に囲まれて座っていた。万二千人の弟子たち、それぞれが阿羅漢として、煩悩や束縛から解放された者たちである。彼らは心の自由を得て、仏陀の教えを実践していた。
そこには、お釈迦さまの養母である摩訶波闍波提(まかはじゃはだい/マハー・プラジャパティー)比丘尼もいた。彼女は、仏陀の生母が亡くなった後、彼の育ての母となり、女性として初めての出家者となった。また、仏陀のかつての妻であった耶輸陀羅(耶輸陀羅/ヤショーダラー)比丘尼も、彼の教えを求めて出家した。
その中には、多くの菩薩たちの名前も並び、さらにはインドの神々やバラモン教の神々までもが、仏陀の説法を聞くために集まっていた。その光景はまさに圧巻であり、それぞれの存在が独自の物語を持ち、それぞれが仏陀の足元に集い、彼の教えを受け取っていた。
そして、阿闍世王もそこにいた。彼はマガダ国の王であり、この王舎城の支配者である。彼ら全員が仏陀を中心に集い、それぞれが順に仏陀に敬意を表し、教えを聞いたのだ。
この時、仏陀は「大乗経の無量義・教菩薩法・仏所護念」と名付けられた経を説いた。これは菩薩のための教えであり、しかし、そこにはさまざまな存在が集まっていた。仏陀の言葉は、菩薩たちだけではなく、すべての者たちに向けられていた。
『法華経』は八巻・二十八品から成り立ち、法華三部経として知られるようになった。この経典には、『無量義経』と『仏説観普賢菩薩行法経』が加わり、これら三つの経典が合わさって大きな意味を持つことになった。
これらの経典が一つになることで、仏陀の教えはさらに深い意味を持つようになった。霊鷲山のその日、多くの者たちが集い、仏陀の教えに耳を傾けた。それは、知恵と悟りの旅の始まりであり、彼ら一人一人にとって、心の変革の瞬間であった。
「妙法蓮華経」という、壮大なスケールを持つ教えが説かれる前に、序章として「大乗経の無量義・教菩薩法・仏所護念」という経典が位置しています。この経典は、妙法蓮華経の開始部分を形成し、その深い教えへの入り口となっています。この経典には、仏の姿が具体的に見えるとしても、その本質が全ての存在に遍在し、生命を育む根源的な力であるという思想が語られています。この考え方は、法華経の核心である「如来寿量品」に通じるものです。また、「実相」という概念が詳述され、これは法華経の重要な教えである「方便品」へと繋がります。さらに、この経典は多様な菩薩の生き方を説いており、教えの多面性を示しています。
法華経という経典は、お釈迦さまが悟りを開いてから四十数年の後、初めて悟りの内容を、純度100パーセント、混じりっ気なしで説いた真実経である。
特に印象的なのは、仏が自己の悟りを他者に伝える難しさを示す経文です。それは、「悟りを開いて気づいたことを、そのままの形で説いても、多くの人々が理解できないだろう」という内容です。これは、人々の性格や能力の違いに配慮し、法華経での真実の教えが、仏が悟りを開いてから約四十年後に初めて純粋に説かれたことを示しています。
★一切衆生=すべての生きとし生けるもの
宮沢賢治は、大乗仏教の理想を求めつづけた人ですが、この人の言葉で、よく出てくる言葉があります。
「ほんとうの、ほんとうの、まことのさいわい」という言葉です。
この「ほんとうの、ほんとうの、まことのさいわい」という幸いこそが仏教の理想なんですね。これは、「私のさいわい」とは別のものです。と同時に、「私たちのさいわい」というのとも違います。かといって、「私たち人間のさいわい」というのとも違うものなのです。まさに、「ほんとうの、ほんとうの、まことのさいわい」と言うしかないものなのですね。
次々に起きる超常現象の意味するもの
霊鷲山で起こった超常現象は、深遠な意味を秘めています。お釈迦さまが王舎城近郊の霊鷲山に滞在していた時、『無量義経』の説法とともに、彼が深い三昧に入ると、天界からは曼陀羅花や摩訶曼殊沙華が降り注ぎ、六種の震動が世界を揺るがしました。これらの現象は、単なる奇跡ではなく、仏教の深い教えと直接関連しています。まず、天から降る花々は、仏の教えが天上からも賞賛されていることを象徴しています。大地が揺れるのは、仏の教えが世界の根底を動かす力を持っていることを示しています。これらの現象は、仏教徒にとって大いなる喜びとなり、信仰の深化を促します。
さらに注目すべきは、お釈迦さまの額から放たれる光です。この光は、仏の智慧が照らす真理の象徴であり、東方の万八千の世界を照らすことで、仏教の教えが限界なく広がることを示しています。仏の眉間白毫相から放たれる光は、仏陀特有の身体的特徴の一つであり、彼の悟りの深さと智慧の大きさを表しています。
また、お釈迦さまが三昧に入ることで現れる光景は、私たちの住む娑婆世界だけでなく、他の数多くの世界が存在するという仏教の教えを具現化しています。例えば、西方の極楽世界のように、様々な仏が教えを説く世界があり、これらの世界が光の中に現れることで、仏教徒にはさらなる信仰の深みがもたらされます。
これらの超常現象が示すのは、仏教の教えが現実世界においてどのように現れ、どのように人々の心を動かし、信仰を深めるかということです。お釈迦さまの三昧とその際に起こる現象は、仏教の教えの不思議さと奥深さを物語っています。
このように、霊鷲山で起きた超常現象は、仏教の教えと深く結びついており、仏教徒にとっては、その教えをより深く理解し、信仰を確固たるものにする機会を提供しています。
深い三昧から生じる不思議な力
三昧(さんまい)=サマーディ
形態形成場/敬体共鳴
八木重吉の詩
沈黙に耳を傾ける
さてここで、ちょっと考えてみたいことがあるんです。それは何かといいますと、沈黙と言葉との関連性についてなんです。
私はいつもクドイくらいに、経文の言葉、つまり「仏語」と文学書の文章を同列に考えてはいけないと言っているのですが、そのことなんです。私たちの心身には現代文明が染みついています。具体的に言うと、文字文化に慣らされてしまっています。ですから、死角といいますか、盲点みたいな部分を持っているんです。情報と文字によって成り立っているのが現代ですから、ある意味ではしかたがないのかもしれませんけどね。
ただ、仏語というのは、仏さまの深い三昧から出てくるものだということと、文学というのは、作家の豊かな才能と知性から出てくる芸術なんだという、この本質的な違いを見失わないようにしてほしいのです。
***
当たり前に考えたら、言葉というのは、コミュニケーションをするための手段ですよね。まあ、極端に言ったら、人間が発明した記号といってもいいんじゃないですか。ところが宗教の世界では、この「言葉=記号」という考え方はだんだん薄れてきます。むしろ、言葉が持っている、もっと違った部分が重要になってくるんです。
仏法はどのように伝承されてきたのか
昔々、日月燈明如来(にちがつとうみょうよらい)と名付けられた仏がいた。この仏は、正しい教えを説いて、四諦、十二因縁、六波羅蜜といった法を教えた。その後、同じ名前を持つ仏が二万人も現れ、どの仏も善い教えを広めた。最後の日月燈明如来には、出家する前に八人の子供がいた。父親が仏になったと知ると、彼らは出家し、父親の教えを学んだ。
ある時、日月燈明如来は大乗経を説いた後、深い瞑想に入った。天からは花が降り、大地が震動し、彼の額から放たれた光によって遠い世界が映し出された。日月燈明如来は、妙光菩薩という弟子に大乗経を説き、六十小劫に渡る説法を行った。その後、日月燈明如来は涅槃に入ることを宣言し、徳蔵という菩薩に浄身如来となることを授記(予言)した。
日月燈明如来の死後、妙光菩薩は教えを広め続けた。八人の子供たちは彼を師とし、仏となった。最後に仏となったのは燃燈仏だった。
また、妙光菩薩の弟子の中には求名という者がおり、彼も多くの善を積んで、後に仏となると予言された。そして、妙光菩薩は文殊師利菩薩であり、求名は弥勒菩薩だったのだ。
この話から、お釈迦さまもいずれ大乗教の教えを広めるだろうと示唆されている。この物語の核心は、「仏の継承」であり、弥勒菩薩が次に仏となることが示されている。彼は四千年後(私たちの時間では五十六億七千万年後)に地上に降りて、多くの人々を救うと言われている。これはお釈迦さまが予言した通りである。同様に、文殊師利菩薩の話に出てきた燃燈仏も、お釈迦さまの成仏を予言していた。
「ジャータカ」という、お釈迦さまの前世のお話を集めた経典のなかに、燃燈仏がお釈迦さまに授記をされる、こんなお話がある。
昔、遠いアマラバティーの都に、スメーダという賢者が住んでいた。彼は、世間の迷いから離れて真理を追求しようと、両親から受け継いだ財宝をすべて貧しい人々に施し、無一文になった。彼は、物質的な所有物がなければ、心が自由になり、悟りに近づけると信じていた。スメーダはヒマラヤのダルマカ山近くで庵を構え、修行に励んだ。やがて、彼は衣を脱ぎ、樹皮を纏い、木の実だけを食べながら厳しい苦行に打ち込み、神通力を得た。
この頃、ディーパンカラ(燃燈仏)という仏が人々を導いていた。スメーダはディーパンカラ仏の存在を知らず、山中で瞑想に耽っていた。ディーパンカラ仏はラムヤカのスダルシャナ精舎に滞在し、多くの人々が彼の教えに感謝し、供養を捧げていた。
スメーダは都の人々が道を整えているのを見て、何事かを尋ねた。人々はディーパンカラ仏を迎えるための準備をしていると答えた。スメーダは、仏に仕えたいと願い、道の修復を手伝うことにした。彼は神通力を使わず、手作業で道を修復し始めた。しかし、ディーパンカラ仏が到着すると、道はまだ未完成だった。
やがてディーバンカラ仏は、厳かな、そしてしみ通るような声で人々に予言したのである。
「ラムヤカの人々よ、ここにひとりの修行者がいる。名をスメーダという。スメーダは仏となる誓願を立て、こうしてどろの中にうつ伏せになっている。わたしは今スメーダの未来の姿を探ってみた。人々よ、しっかりと覚えておくがよい。気も遠くなるほどの遠い未来のことではあるが、このスメータは必ずその願いが達せられてガウタマという仏となるであろう。その母の名はマハーマーヤー、父の名はシュッドーダナである。生まれて住む都はカビラバストゥという。長じて知恵が熟した後に出家し、並々ならぬ苦行を重ねるであろう。そしてニャグローダ樹の下で乳がゆの供養を受け、ナイランジャナー河に入って沐浴し、アシュバッタ樹のもとに座してついに悟りを得
るであろう。(『仏教説話大系1釈尊の生涯』青春編、すずき出版)
この、燃燈仏がお釈迦さまに授記をするお話は、数多い文献の中に見られ、物語もさまざまなバリエーションがあります。そこでもう一つのお話を読んでみましょう。仏の継承についてもわかりやすく解説されています。
仏教のおしえによると、仏陀はシャーキャムニお一人ではなく、遠い過去の世にも、久しい間隔をおいて次々に仏陀が世に現われました。
今の私たちの経験している世の仏陀はシャーキャムニでありますが、これからのち将来、世の中が移りかわってシャーキャムニの教えを人々がすっかり忘れるような時がくると、次には弥勒菩薩がこの世に現われてシャーキャムニと同じように生まれ、出家修行し、成道して仏教を世におひろめになることになっています。弥勒菩薩はそういう使命をシャーキャムニから授けられたのです。
それと同じように、遠いむかし、今のシャーキャムニは燃燈仏という過去仏からその使命を授けられました。のちに仏陀となる約束を授けることを授記といい、授記をうけた人はさらに修行を続けますが、こうして修行を続けて仏陀になるまでをボサツ(菩薩)といいます。ボサツとは仏陀の候補または後任という意味です。
色々の書物の記事を要約すると、シャーキャムニの授記は次のようにして行なわれました。
むかし燃燈仏(または定光仏ともいいます)がこの世においでになったころ、儒童(じゅどう/弥却:みぎゃくともいいます)という青年が人里はなれたところで一心に修行していましたが、仏陀が世に現われたということを聞き、鹿の皮の衣を着て山から降りて来ました。
途中で修行者たち五百人に遇い、夜も昼もぶっつづけに論議したところ、一同はその教えを聞いてたいそう喜び、別れるときに餞別として一人が銀貨一枚ずつ、合せて五百枚をくれました。
青年はそれをもらって都に来ると、人々はみないそがしそうに道路をなおし、掃除したり香をたいたりしています。それを見た青年がそのわけをたずねると、ちょうどその日に燃燈仏が都に来られるということなので、青年はたいそう喜んで、ぜひ仏陀にお目にかかって自分の願いを聞いて頂きたいと考えました。
ちょうどそこにゴービーという王家の女が通りかかりました。水瓶を脇にかかえ、その中には七本の青蓮華(しょうれんげ)がさしてありました。青年がよびとめて「銀貨百枚あげるから、その花をゆずってくれないか」と頼みましたが、女は「仏陀が都に来られるので、王さまは斎戒沐浴してこの花を献上なさるのです。ゆずるわけには行きません」。
そこで青年は銀貨二百枚、三百枚とせりあげて、とうとう五百枚ぜんぶ渡して、七本のうち五本の青蓮華を手に入れました。
やがて燃燈仏が都にお着きになると、国王はじめ一般民衆まで揃って出迎え、みな花を投げて歓迎しました。投げられた花はもちろん地上に落ちましたが、儒童青年の投げた五本の青蓮華だけは空中にとどまって、燃燈仏の頭上を飾りました。それを御覧になった燃燈仏はその青年にむかって「汝は過去久しいあいだ、多くの生涯において修行を続け、身命をなげうって人々のためにつくし、欲望を捨てて慈悲ぶかい行ないをしてきた。それだから今から九十一劫(劫というのは非常に永い時間の単位)たつと、汝は仏陀になってシャーキャムニとよばれるであろう」。
こうして燃燈仏から授記を得たその青年はその時また、燃燈仏の通り路が泥々なのを見て、自分の着ていた鹿の皮の衣をぬいで道にひろげましたが、それでもまだ十分でなかったので、自分の髪の毛を解いて地面にひろげ、燃燈仏にそれを踏んで通っていただきました。
(渡辺照宏『新釈尊伝』前世の物語、大法輪閣)
かつて、日月燈明如来から弥勒菩薩に至るまでの壮大な「仏の継承」がありました。この系譜は、時間の流れに沿って上から下へと進むもので、二万人の日月燈明如来から始まり、浄身如来、燃燈仏、釈迦牟尼仏、そして弥勒仏へと続きます。これはまさに仏教における、重要な歴史的系列を示しています。この伝統は、仏が涅槃に入った後の「無仏の時代」を通じても続いています。つまり、すべての仏が涅槃に入った後も、仏教の教えは引き継がれ、新たな仏が現れるまでの時を経ているのです。

経典には、「初めも善く、中ほども善く、終わりも善い」という、仏の教えを評する表現があります。これは、仏の教えが常に一貫して質の高いものであることを示しています。お釈迦さまは「律蔵・大品十一」において、伝道への熱情と誠意を込めてこの言葉を述べました。これは、彼自身の伝道宣言でありながら、彼の弟子たちへのはなむけの言葉でもあったのです。
比丘たちよ、私は、神々のものにせよ、人間たちのものにせよ、あらゆる絆から解脱した。比丘たちよ、あなたたちもまた、神々のものにせよ、人間たちのものにせよ、あらゆる絆から解脱した。
比丘たちよ、遊行せよ、多くの人々の福利のために、多くの人々の安楽のために、世の人々への憐愁のために、神々と人間たちの利益・福利・安楽のために。一つの道を二人で行くな。比丘たちよ、初めも善く、中も善く、終わりも善い、意味もよくそなわり、文句もよくそなわっている教えを説け。まったく完全で、高潔、清浄な修行を説き明かせ。この世には、心の眼の汚れの少ない類の人々がいる。教えを聞いていないので退歩しているが、聞けば教えを了解する人々はあるであろう。比丘たちよ、私もまたウルヴェーラーのセーナ村に行こう。教えを説くために。
仏教において、正しい教え、正しい法を説くことの重要性は非常に強調されています。特に興味深いのは、仏教の教えが個々人に対して、独立した精神の育成を促していることです。例えば、お釈迦さまは、弟子たちに一人で道を歩くことの大切さを教え、見知らぬ人々の中へと独りで出て行くことを戒めています。これは、連れがいることが心強いかもしれないが、それに依存してはならないという教えです。また、仏教は、心が清らかな人々が真理に目覚める可能性を強調しています。このことから、僧侶たちには正しい法を説くことが強く求められています。
僧侶にとって最も大切なことは何かと問われれば、多くは「仏法を伝えること」と答えるでしょう。これはキリスト教や他の宗教の教えとは異なり、仏教では「仏法を伝えること」が最優先される傾向があるのです。しかし、一般の人々からは、僧侶たちが貧しい人々や困難に直面している人々への具体的な援助に乏しいと批判されることもあります。キリスト教の修道女のような献身的な活動と比較されることもあります。
筆者も大学時代に、日蓮聖人の御遺文を勉強していた時、日蓮聖人が極楽寺の良観を批判していたことに疑問を感じたことがあります。良観は、当時「生きぼとけ」として崇められ、その慈悲行に感動する人も多かったにも関わらず、日蓮聖人は彼を厳しく批判していました。このことについて、先生は日蓮聖人が仏法を伝えることを何よりも重視していたからだと説明してくれました。つまり、日蓮聖人にとっては、正しい法を伝えることが最も重要であり、貧民救済などはその次にあるという考え方だったのです。
このように、お釈迦さまや日蓮聖人、親鸞や道元などの宗祖たちは、現実の救済よりも正しい仏法を優先するという立場をとっています。この姿勢は、一見冷淡に見えるかもしれませんが、宗教的な教えの核心に迫るものであり、深く考察する価値があります。
そこで、これらの教えや宗祖たちの本心について、私たちも一緒に考えていきたいと思います。それぞれが自分なりの解釈を持って、これらの深い教えを理解し、内面化していくことが重要です。正しい法を理解し、それに基づいて真理に目覚め、社会に貢献していくことが、仏教の理想なのかもしれません。
法華経という経典には、推理小説的な要素が多分にふくまれていて、トリックや謎が、さりげなく所々に伏線としてはりめぐらされています。ご存じのように、推理小説というものは、トリックの出来いかんで作品が決まりますよね。しかし、ただトリックの鮮やかさだけでもダメで、小説全体にわたって、この謎解きへとつながっていく伏線をどんなふうにはりめぐらされているかも大切です。それがないと、全体の緊密感がゆるんでしまいますから。
そこで、今、読んできた部分には、こういう謎が含まれているということを、ちょっと箇条書きにしてみました。
一、どうして文殊菩薩は、この長い期間の出来事を全部知っているのか?
二、二万以上の仏が説き、妙光菩薩も説いたという、この無数の教えが、すべて『法華経』だとすると、それはどう理解すればいいのか?
三、かつて妙光菩薩と名乗っていた人物と、今の文殊菩薩とは、どんなふうに別人で、どんなふうに同一人物であるのか?
四、弥勒菩薩はなぜ、求名と呼ばれていた自分を知らないのか。そもそも、自分が自分を覚えていないとはどういうことなのか?
五、一人の人間の生命を、生まれてから死ぬまでの数十年だと見たら、この人物関係の図式がなりたたなくなるのはなぜか?
六、仏から、次の仏までの長い無仏の時代に、救済はどんな形で求めればいいのか?
こういうふうに、法華経では、この序品の中ですら、もういくつかの謎、キーワードが伏線として、たくみに張りめぐらされているわけなんです。この疑問点をジッと眺めていたら、なんとなくですが、法華経というお経は、どうも、自分が今まで持っていた仏教のイメージとは違う。なにか、とんでもなく奥がありそうだなと感じませんか。
これらの謎は、ズーッと先になりますが、如来寿量品第十六という章で解明されることになるんです。
以前、禅宗のお坊さんと話した時、私が、「人間という存在は、生まれてくる前にとてつもなく大きなものがあり、死んだ後にも、なにかゆったりと大きなものがあって、その大きなもののはざまで、仮のものとして生きているんでしょうね」と言ったら、あにはからんや、まったく受けつけてくれませんでした。
「人間は今だけを見つめればいい。今を生ききれば、死にきることもできる」と言われるんです。現世と自分以外信じる必要はないとも言われるんです。ずいぶん極端な考えだなと感じたのですが、こういう発想をしたら、おそらく法華経は、「さっぱりわけのわからない教えだ」ということになるんじゃないでしょうか。
こういった禅宗的なところで発見する「自己」というものと、法華経が説く「自己」とは、ずいぶん違うような気がするんです。法華経の見性は、自分の中に眠っている本当の自分を発見したら、それでよしとする世界ではなく、自分ですら知らない自分を「深く思い出さなくてはいけない」のだと思うんです。では何のために、自分でも知らない自分が大切なんでしょうか?
法華経という経典は「教菩薩法」という別名を持っています。つまり菩薩のための教えであり、菩薩道を教えるものだということなんです。
そこでです、菩薩という存在には、かならずズーツと昔、過去の過去にどこかで仏道に発心し(これを発菩提心とも言います)、この発心した時に、誓願を起こしているわけなんです。つまり、仏道における最初の始まりがあるわけなんです。この誓願は、生命の連鎖と同じように、自分すら知らない、深い深い心の根底を、長い長い年月のあいだ、一つの河の流れのように流れつづけているわけなんです。
法華経という経典に、人物の過去世の話が多いのは、そういう過去・現在・未来にわたった願いや、仏縁が重要視されているからでもあります。
方便品ほうべんほん第二
方便品第二のあらすじ
三昧(深い瞑想)から出られると、お釈迦さまは立ち上がられました。そして、智慧第一と称せられるお弟子の舎利弗(シャーリ・プトラ)に、こう語りかけるのでした。
「仏の智慧というものは、はかりしれないほど深いものである。それゆえ、正しく悟り、その中に入っていくということは、なみたいていのことではない。声聞や辟支仏(縁覚)にはわからないだろう。なぜなら、悟りとは、諸仏にだけわかりあえる独自の世界であり、諸法を究めつくした世界であるからだ」
お釈迦さまはこれまで、お弟子たちには、お弟子たちの能力に合わせた教え(声聞乗。これに縁覚乗を加えて二乗という)を説いてきましたが、今から説く教えは、そういうものとは、まったく違った教えであるとおっしゃるのです。
舎利弗は三度にわたって、「ぜひ、お説きください」と懇願します。しかし、お釈迦さまはなかなか説こうとはされません。そのうち、五千人にもおよぶ人たちが、席を立つと退座していきました。声聞乗の教え以外、今さらあらたまって聞くような教えなどないと考えている人たちです。お釈迦さまは、去っていく彼らを黙って見送ります。そして、それでも教えを聞きたいと残っている者たちのため、ようやく語り始められるのでした。「たくさんの仏が、この世に出現するには理由がある。それは一大事の因縁といって、まずもって人間の中に眠っている仏の知見を開かせ、そして仏の知見を示し、悟らせ、その中に導き入れるためである。これが諸仏の本当の願いなのだ」と。
さらには、こんなことも言われるのでした。「仏の願いが、人々を真実の教えに導き、安らぎを与えるのが目的だとすれば、お前たちの仏道における行為がどんなにささやかなものであろうと、それはすべて仏の眼で見たら、成仏のための道にほかならない。子供たちがたわむれに砂を集めて仏塔をつくるような行為も、仏の眼で見ると、成仏のための確かな道筋だと言ってよいのだ」と。
名訳「安詳として起つ」にこめられた深い意味
「安詳」という短い言葉のなかに、鳩摩羅什はこういったニュアンスを全部こめたようなんです。お釈迦さまが三昧に入られた時、その深い深いこころの中では、いったいどんなことが起きているのでしょうか。
実は、阿含経などの初期経典に、ところどころその内容が表現されております。これはその一つで、『中部経典』の「双考経」の一節です。ちょっと長い引用ですが、皆さんには、〈なるほどな、お釈迦さまというかたは、こういう深い考察をして、そのあとで三昧から立ち上がられるわけなのか〉と理解して欲しいんです。
そこで、無数に配置された過去の生活の場面を、すなわち、一つの生涯、二つの生涯、三つの生涯、四つの生涯、五つの生涯、十の生涯、二十の生涯、三十の生涯、四十の生涯、五十の生涯、百の生涯、千の生涯、十万の生涯、無数の世界破壊期、無数の世界生成期、無数の世界破壊・生成期にわたって、『そこでは、私はこのような名前であり、このような家系であり、このような階級であり、このような食べものをとり、このような楽しみと苦しみを受け、このような寿命の終わりがあった。そこで死ぬと、かしこに生まれた。また、かしこでは、私はこのような名前であり、このような家系であり、このような階級であり、このような食べものをとり、このような楽しみと苦しみを受け、このような寿命の終わりがあった。かしこで死ぬと、ここに生まれた』と思い起こした。このように、私は、あらゆる状況とともに、詳細にわたって、無数に配置された過去の生活の場面を思い起こした。
この経文で明らかなのは、「思い起こす」という行為が、この現世における自己一身についての考察ではなく、ものすごい時間の流れを全部ひっくるめた考察だということなんです。仏さまの瞑想というのは、こういうものなんです。つまり、こういう「思い起こし」を、ひととおり全部やりおおせたと確信なさった時点で、お釈迦さまは立ち上がられる……、これを「安詳として」と表現しているわけなんです。
お釈迦さま一流の作戦
難解難入の法華経
お釈迦さまは三昧から出られ、そしてゆっくりと立ち上がり、おそばにいる舎利弗に語りかけられた。その時の第一声「諸仏の智慧は、甚だ深くして無量なり。その智慧の門は解り難く入り難くして、一切の声聞・辟支仏の知る能わざる所なり」
実は、法華経という教えは、一面では難しいことこの上ないという部分を持っている教えなんです。しかし、難しいといってもそれが本質ではなく、反対にこの教えほど誰にでも理解でき、どんな人にもなじめるものはない……、そういう、まったく相反した二面性を持つ教えでもあるわけなんです。こういう矛盾した性格を、いきなり、不意打ちのように、ドッとぶつけてきたのが、お釈迦さまの第一声だったわけです。
実は、これはお釈迦さま一流の作戦なんです。
「ここを取り違えたら、おそらく、最後までわからなくなってしまうかもしれないぞ。だから、くれぐれも気をつけるんだぞ」と、暗に示唆していらっしゃるわけです。
ここを、よーく、注意してください。お釈迦さまが最初に口に出された言葉ということは、この言葉こそ、法華経と名づけられた、未曾有の大説法に入る前提になっているってことなんです。それも、ただの前提ではなく、大、大、大前提だということなんです。
「難しさと易しさが同居している」って、どういうことなんでしょう。これはつまり難しさの性格が、きわめて特殊だということなんです。仏さまのお説法というのは、学者さんが研究発表をする時のように、無数の本を読み、そこから獲得した情報を、頭脳のなかでまとめたり、組み立てたりして発表するものではないんです。つまり、頭脳の方からやってきて、口から出る言葉ではないんです。
深い、深い三昧の境地、つまり心の深奥から溢れてくる智慧が、口をついて出る言葉なんです。お釈迦さまがなによりも危惧なさっているのはこの点なんです。
法華経はどんなに面白い物語に見えたとしても、小説ではないんです。
どれほどたくさんの思想が表現されているからといって、思想書でも哲学書でもないんです。
無門関第五則:香厳~撃竹の話
忘れていたものを思い出すようなおののきの中で
生まれつきの盲人の方が鏡を理解するような難問。
ヘレン・ケラーの話:何かしら忘れていたものを思い出すような……
病的なワーカホリック/大佛次郎:冬の紳士(雲雀の話:出家願望の物語)
⇒法華経を聞きたければまずはあの雲雀の声を聞け
法華経の重大テーマ「一仏乗」とは
法華経という経典は、大きな二つのテーマを持っている。
一つは「一仏乗」、もう一つは「久遠実成」。この一仏乗というテーマに深くかかわっているのが三乗という考え方だが、法華経を大切な経典としている宗派のお坊さん、あるいは信者さんと話をしているとと、「二乗が…三乗が…」といった会話をしているけれども、よーく耳を傾けていると、二乗が何なのか、三乗が何なのか、ちゃんと理解していない方が随分多い。そこで、法華経前半の最大のテーマ、「一仏乗」を学んでいくために、この考えの基本になっている三乗について考えてみたい。
仏教には十界という考え方がある。人間の心、迷いや悟り、そのすべてを含んだ非常に大きな世界観。それらを十の世界に区分している。
一番上は仏さまの世界から、一番下は地獄の世界までがある。
実は、この十界というものは、一から四までの世界と、五から十までの世界に大きく二つに分けられる。それで、この五から十までの世界を六道といい、輪廻をする世界。つまり、車の車輪のように経巡っていく世界。
人間の世界にいると思っていたら、なにかのきっかけで畜生界や地獄界に落ちたり、ところがそういう世界に落ちていても、またなにかのきっかけがあると天上界のような喜びを覚えたりするが、この六道の世界にいるものは、六道輪廻の絆からは抜けきれない。ですから、仏教では、この六道輪廻の絆から抜け出ることを、大きな意味で、一応「悟り」だと考える。そして、この悟りには四つの悟りがあって、それが仏の悟り、菩薩の悟り、縁覚の悟り、声聞の悟りというす。この四聖界に入った方たちは、もう輪廻をしない。

この十界の中で、二、三、四の、菩薩界、縁覚界、声聞界、この三つの世界を対象としたものを三乗という。「乗」というのは「乗り物」、あるいは「教え」という意味。この「界」という言葉を「乗」という言葉に置き換えて、菩薩乗、縁覚乗、声聞乗と表現し、これを三乗と呼ぶ。そして、この三乗というものが、法華経の中で、非常に重要な位置を占めてくることになる。そこで、仏教では一般的に、この三乗をどんなふうに説明しているか『佛教大事典』にはこんなふうに書かれている。
【菩薩乗・ぼさつじょう】自分よりもまず他者を救うことを理想とする菩薩の立場をいったもの。乗は乗り物、教えの意味。それまでの、自分の救いのみに関心が向きがちであった小乗の修行僧たち(声聞・縁覚)に対して、大乗側が自らの立場を鮮明に表わしたもの。
【独覚・どっかく】師なくして独力で悟り、他人に教えを説こうとしない聖者の一種。古くは辟支仏と音写し、縁一覚・因縁覚・緑覚などと訳された。新訳では独覚という。
【声聞・しょうもん】釈迦の教える声を聞いて修行し悟る人の意。仏弟子のこと。元来は釈迦在世のころの弟子を出家・在家を問わずにこうよんだ。
二乗(声聞乗・縁覚乗)の説明。
【二乗・にじょう】悟りまたは救いへと運ぶ二つの乗り物のことで、声聞乗と縁覚乗をさしていう。声聞とは仏の説法を直接に聞いて悟りを得る人であり、縁覚とは独覚ともいわれるように、独りで悟りが得られる人である。しかし、彼らは自らの悟りないし救いだけで満足し、他人のことはまったく顧みない。彼らの乗り物には他の人々は乗れないのである。大乗仏教徒たちはそれをとがめて、彼らの立場を劣った乗り物=小乗と軽蔑的によんだ。そして自分たちの立場を、だれでもが乗れる優れた乗り物=大乗と宣言し、他人の救済に努める菩薩乗、あるいはすべての人が仏となることをめざす仏乗とよんだ。
***
「大乗からは、声聞は自己の悟りのみを求めて衆生済度に努力しない、すなわち自利のみで利他に励まない宗教者であると批判された。ただし、事実は声聞乗には自利も利他も存するのである」
声聞という生き方
保育園の幼児たちのこと。
私が思うに、声聞乗、縁覚乗、菩薩乗という違いは、制度とか政策とか、そういうふうに、あとから線引きをして区切ったものではないと思うのです。人間が本来的に、潜在的に持って性向、感性とでもいいますか、そういう根源的なものと深く関わった「ありかた」じゃないでしょうか。ですから、人間が、「はるかに遠いもの」とか「かぎりないあこがれ」とか、「なによりも純粋な真理」といったものを求め始めた時、自然に表面化してくる傾向だと考えたいのです。
この基本を、キチンと捉まえてない人が、ただ大乗仏教関係の本を読んだだけで、三乗を論じはめるから、どうしても妙な具合になるんじゃないでしょうか。
仏教において、声聞という道を進む者は、師匠によって自分を形作ってもらうことが重要です。彼らは何もかも捨てて師匠に従い、その指導の下で自己を形成するのが出発点となります。これは日本の社会にも根付いている伝統で、若者が職人の親方の元で修行し、その人の影響を強く受けるような生き方です。お釈迦さまの時代にも、彼に弟子入りした者は、お釈迦さまによって自分自身を作り上げてもらうことを望んでいました。お釈迦さまが亡くなった後、彼の偉大な弟子たちが師匠の役割を引き継ぎました。女性が白無垢を着て新たな家庭に嫁ぐように、彼らも新たな人生を歩み始めたのです。
舎利弗は仏教の中で声聞の代表的な人物で、お釈迦さまによって彼の最優秀の弟子と称されました。しかし、彼がお釈迦さまの教団に入ることになった経緯には興味深い話があります。
舎利弗は仏教教団に入る前、サンジャヤの元で出家し、教団内で優秀な立場にありましたが、心の奥底で真の教えを求める思いがありました。彼は王舎城の街で托鉢するアッサジという修行者に出会います。アッサジの立派な姿に舎利弗は強く引かれ、彼に教えを求めました。
アッサジは「ものみなは成るに因縁あり、壊れるに因縁あり」と答え、舎利弗はこの言葉に深い啓示を受けました。すべては因縁によって生じ、滅するという縁起の教えが、舎利弗にとって重要な真理でした。彼はこの短い言葉から、深い思想を汲み取り、自分が求めていた真理だと確信しました。
しかし、彼がお釈迦さまを選んだのは、アッサジの言葉だけでなく、アッサジ自身が放つ輝きにも影響されたと思われます。舎利弗は無意識のうちに、アッサジの背後にいる偉大な存在、お釈迦さまに目を向け始めていたのです。このようにして、舎利弗はお釈迦さまの弟子となり、その教えを深く学んでいきました。
縁覚という生き方
縁覚、または独覚は、独りで悟りを開く人々を指します。彼らは他人に教えを説くことを求めず、自己の内面の洞察を通して真理を悟る聖者たちです。別名で「辟支仏(びゃくしぶつ)」とも呼ばれています。この生き方は、師匠に導かれる声聞とは正反対で、独立して悟りを追求するものです。彼らが悟るのは、仏教の基本思想である「諸行無常諸法無我・一切皆苦」といった真理です。時には、山奥やジャングルの奥深くに隠れた聖者たちの存在を想像することもあります。
この縁覚のイメージを伝えるため、ヘルマン・ヘッセの小説『シッダールタ』を参照することが適切です。この小説は、お釈迦さまの若名を借りた一人の若者シッダールタの物語で、彼の人生と悟りへの道のりを描いています。ヘッセは、お釈迦さまの心の過程をたどり、主人公にシッダールタという名前を与えています。
物語の舞台は、お釈迦さまの時代のインドで、バラモン階級の家庭に生まれた優れた若者シッダールタが登場します。彼は親友のゴーヴィンダとともに世俗の喜びに虚しさを感じ、出家して沙門となります。教えを習得するものの、虚しさを感じ続けます。ある時、ゴータマという聖者の存在を知り、ゴーヴィンダと共に彼に会いに行きます。ゴーヴィンダはゴータマの弟子となるが、シッダールタは異なる道を選び、世俗の世界へと戻ります。商人として成功し、富と快楽を追い求めますが、やがて沙門の心が戻り、遍歴の旅に出ます。
川のほとりでヴァズデーヴァという渡し守に出会い、渡し守としての生活を始めます。ゴータマの死を知り、多くの人々が彼に別れを告げるために川を渡ります。その中には、シッダールタがかつて愛したカマーラもおり、彼女はシッダールタの子を連れていましたが、毒蛇に噛まれて亡くなります。
シッダールタは、残された子供を育てながら渡し守をつづけていくのです。 しかし….....子供は父親に少しもなつきません。それどころか放蕩息子となり、父親を捨てて家出をしてしまいます。なにもかもなくしたシッダールタに残されたのは、川だけなんですね。
こうしたある時、シッダールタは川が笑う声を聞くんです。そのことをヴァズデーヴァに言うと、もう高齢で働けなくなっていた彼は、うれしそうに微笑んで、「やっとここまで来たな」という感じで、川からもっともっとたくさんの声を聞こうと、川のほとりへ誘うのです。これは、その部分です。一緒に読んでみましょう......。
ふたりは耳をすました。川の多声の歌は穏やかにひびいた。シッダールタは水の中をのぞきこんだ。流れる水の中にさまざまの姿が現われた。彼の父が現われた、寂しく、子どもを悲しんでいる父が―彼自身が現われた、寂しく、彼も遠く離れたむすこにあこがれのきずなで縛られて。――彼のむすこが現われた。彼も寂しく、若い願いの燃える軌道をむさぼり突進する少年として。めいめい目標をめざし、めいめい目標にとりつかれ、めいめい悩みながら。――川は悩みの声で歌った。慕いこがれるように歌った。慕いこがれるように目標に向って流れた。その声は訴えるようにひびいた。
「聞えるかい?」とヴァズデーヴァの無言のまなざしはたずねた。シッダールタはうなずいた。
「もっとよく聞け!」とヴァズデーヴァはささやいた。
シッダールタはもっとよく聞こうとつとめた。父の姿、むすこの姿が流れあった。カマーラの姿も現われて、溶けた。ゴーヴィンダの姿やほかのさまざまの姿も現われ、溶けあい、みんな川になった。みんな川として目標に向って進んだ。慕いこがれつつ、願い求めつつ悩みつつ。川の声はあこがれにみちてひびき、燃える苦しみに、しずめがたい願いにみちてひびいた。目標に向って川はひたむきに進んだ。川が急ぐのをシッダールタは見た。川は彼や彼の肉親や彼が会ったことのあるすべての人から成りたっていた。すべての波と水は急いだ。悩みながら、目標に向って、多くの目標に向って、滝に、湖に、早瀬に、海に向って。そしてすべての目標に到達した。どの目標にも新しい目標が続いて生じた。水は蒸気となって、空にあがり、雨となって、空から落ちた。泉となり、小川となり、川となり、新たに目標をめざし、新たに流れた。しかし、あこがれる声は変った。その声はなおも悩みにみち、さぐりつつひびいたが、ほかの声が加わった。喜びの声と悩みの声、良い声と悪い声、笑う声と悲しむ声、百の声、千の声がひびいた。
シッダールタは耳をすました。彼は傾聴者になりきり、傾聴に没頭しきった。空虚になりきり、ひたすらに吸いこみながら。彼は今や傾聴を究極まで学んだ。これまでにもうたびたびそのすべてを、川の中のこれら多くの声を、彼は聞いたが、きょうは新しく聞えた。もう彼は多くの声を区別することができなかった。泣く声から楽しい声を、おとなの声から子どもの声を区別することができなかった。それはみないっしょになった。あこがれの訴えと、知者の笑いとが、怒りの叫びと死にゆく人のうめき声とが、すべてが一つになった。すべてがもつれあい、結びつき、千様にからみあった。すべての声、すべての目標、すべてのあこがれ、すべての悩み、すべての快感、すべての善と悪、すべてがいっしょになったのが世界だった。すべてがいっしょになったのが現象の流れ、生命の音楽であった。シッダールタがこの川に、千の声のこの歌に注意ぶかく耳をすますと、悩みにも笑いにも耳をかさず、魂を何らか一つの声に結びつけず、自我をその中に投入することなく、すべてを、全体を統一を聞くと、千の声の大きな歌はただ一つのことば、すなわちオーム、すなわち完成から成りたっていた。
「聞えるかい?」とヴァズデーヴァのまなざしはまたたずねた。
この小説『シッダールタ』の全体像を抜粋だけで捉えるのは難しいですが、人生の苦難を経験した人が最終的に透明な世界を見出す様は、非常に感動的です。人間は経験を積むにつれて、汚れることもあれば、逆に透明になっていくこともあります。氷を重ねることで生まれる透き通った藍色のように、独りで悟りの世界へと進む人がいる。これが独覚(縁覚)と呼ばれるものでしょう。私たち凡人には計り知れない世界です。
仏教では、縁覚と声聞を「二乗」と称しています。大乗仏教の教義から見れば、彼らは二乗根性を持つ、自己中心的で他人を顧みない人間とされがちです。しかし、仏教史を考慮すると、これは誤った論理だと思います。私は声聞も縁覚も、彼らの偉大さに深い尊敬と敬愛を感じています。だから「小乗」という言葉は、正直なところ好きではありません。
この小説は、シッダールタの人生と悟りへの道のりを通して、人生の複雑さと精神の深遠さを探求しています。それは縁覚や声聞が目指す精神性の旅と重なり、私たちにも大いに示唆を与えてくれます。人生の体験を通じて得られる知恵と悟りは、誰にでも訪れる可能性があるのです。
人間をかぎりなく豊かにしていく智慧
菩薩乗について考えてみましょう。「菩薩」という言葉は、一般に、自己犠牲を惜しまず他人のために尽くす人という固定的なイメージを持たれがちです。多くの人がボランティア精神を代表するものとして菩薩を想像することでしょう。しかし、実際には菩薩はもっと幅広く多様な要素を持つ存在です。例えば法華経における菩薩は、単なるボランティア的な存在ではなく、仏法を求め、仏法を広める人々を指します。観世音菩薩のように慈悲深く人々に接する菩薩のイメージは一部に過ぎません。日蓮宗では、特に観音信仰が薄いことも興味深い事実です。
菩薩とは根本的に、仏の悟りや智慧を求める人のこと。つまり、自己犠牲の行為だけでなく、その行為を通じて仏の智慧をどう獲得していくかが重要なのです。菩薩は単なる普通の人間とは異なり、深い智慧を持つ存在として理解されるべきです。
ここで、畑山博さんによる『教師宮沢賢治のしごと』という本を例に挙げます。この本は、賢治が教師としてどのような人物だったかを探求しています。賢治の元生徒たち、現在は八十歳を超えたお年寄りたちが、彼の教えや人柄について語る記録です。この本を読むと、賢治の人間性、彼が及ぼした影響の深さ、彼の持っていた智慧について深く考えさせられます。彼らの心には今も賢治の思い出が鮮明に残り、その影響は計り知れません。
賢治は詩人、童話作家、宗教的人物として知られていますが、それと同じくらいに教師としても素晴らしい人物でした。畑山さんが賢治の授業を受けた生徒たちから収集した話は、賢治の人間性を浮き彫りにします。彼らの記憶から湧き出る言葉には感動が溢れています。
畑山さん自身も、この取材を通じて賢治に魅了されていったことが伝わってきます。このように人々を魅了し、深い影響を与えた賢治の智慧は、特別な種類のものです。私は、このような人間的魅力として人を豊かにしていく智慧を、「菩薩の智慧」と考えます。それは通常の智慧とは異なる、特別な種類のものなのです。
皆さんは、「小説家にはエリートコースがない」という言葉を知ってますか?全国に無数の大学があり、文学部という学部を持つ大学も無数にあります。学部の上には大学院だってあります。そして、毎年ここからはおびただしい数の学生が卒業しています。秀才と呼ばれる人だって、無数にいるはずです。ところが、こういう文学エリートたちが小説を書くというのは、ビックリするくらいに少ないんです。いや、皆無に近い状態なんです。
だったら、小説はどんなところから生まれてくるかというと、極端な話が、廃品回収業をしていたおじさんが、突然、小説を書くとか、風呂屋の番台に坐っていたおばさんが、突然、小説を書くとか、そういった感じで生まれてきたりするんです。一方、文学エリートたちは、小説を書こうとしても書けなくて、ノイローゼになったりするんです。
どうしてこんなおかしなことが起きるんでしょう。私が考えるに、小説を書いたりする人には、非常に特殊な智慧が必要になるからじゃないでしょうか。小説というのは、まずなによりも知的な仕事です。ですから知的な要素を持たない人には無理だと思うんです。じゃ、知的であればいいかというと、ただ知的でもダメで、その知が「世間知」にまで広がっていないと無理かもしれません。
しかし、それだけでも充分ではないんですね。小説家に必要なのは、どこかで人生に絶望したようなものを持ってないとダメみたいなんです。でも、頭がよくて、世間のことを知っていて、人生に絶望したような人間ならどこにでもいます。しかし、そういう人が小説を書くことはあまりないですよ。だとしたら、その他に、どんな要素が必要なのかと考えてみると、人生に絶望したような心の裏に、美しいものへの強い憧れを持つような人でないと、やっぱりダメじゃないかと思うんです。
しかし……これらの条件だって、充分に満たしている人はけっこういると思うんです。だったら、それ以外に、どんな条件が必要なんでしょう……
考え始めると、けっこう面白いでしょ。
最終的には、小説を書き始めるような人というのは、人間とか社会などを慈しみというか、哀しみというか、そういう目でジーッと見つめるところがないとダメなんだと思うんです。おそらく、こういう要素が、文学エリートには絶対的に欠けているんでしょう。反対にこういう作家は、風呂屋の番台あたりから、突然生まれたりするんじゃないですか。「小説家にはエリートコースがない」というのは、奥深い言葉だと思います。ですから、言葉の意味を考えていると、人間には、知識でもなく知恵でもない、仏教的な表現ですが、「智慧」でしか見えてこない世界が、厳然としてあるんだろうなと思わせられたりするんです。
増上慢の人は、退くもよし
方便品という章は、その内容の豊かさと長さから、経文の重要な箇所が随所に見られる章です。特に後半部分には、言葉が宝石のように輝き、まるで宝石箱のような印象を与えます。この章を深く掘り下げると、時間がいくらあっても足りず、全体像を見失いがちです。そこで、経文そのものよりも、方便品の意味合いに焦点を当てることが重要だと思います。
この章で、お釈迦さまが三味から出て最初に口を開かれた際の言葉は、仏の智慧の広さと深さを示しており、教えを理解することの困難さを強調していました。この「拒絶の姿勢」により、期待していた聴衆の間に動揺が生じました。その後、舎利弗が熱心にお釈迦さまに説法を求める「三止三請」のやりとりが繰り広げられ、この緊迫した状況の中で、約五千人の聴衆が退場するという出来事が起こります。お釈迦さまはこの退場を黙認し、「黙然として制止せず」と言及しています。
このエピソードは、お釈迦さまが初めから「説くべき対象」を選抜しようと考えていたことを示唆しています。五千人の退場した聴衆は、法華経を聴く資格がなかったとも言えます。法華経は大平等の精神を持ちながらも、聴く側と語る側の世界には選抜が必要でした。退場した五千人は、増上慢の気持ちが強く、教えを謙虚に受け入れることができない人々だったのです。
このような逸話は、私たちが持つ増上慢や自己中心性について深く考えさせられます。実際には、我々凡夫のレベルでの増上慢にはある種の可愛げがありますが、より高いレベルに達した人々の増上慢は、その罪の根が深いものかもしれません。この話は、自己の限界を認識し、謙虚に学ぶことの大切さを教えてくれます。
著者がカラヤンに感じた増上慢体験エピソード。
音楽評論家のカラヤン評
「カラヤンは芸術家ではない。一流のデザイナーなのだ。魂の深遠さ、その苦しみや痛み、情熱や歓喜といったものとはまったく無縁、ただ表面が美麗でこころよく、スマートならばそれでよいのである」
「私はカラヤンの芸の本質は美容師のそれであると思っている……」
「何よりも、彼の引き出したサウンドが、心に残らないのが不満だった。軽快なテンポと、豪快な迫力と、麗々しいまでの美しさとが、不思議なまでに共存し、一点の翳りもミスもない爽快感を与えてくれるアンサンブルの裏から、このくらい簡単なものよ、という声が聞こえてくるように感じられた。そもそもベートーヴェンの交響曲を次々と全曲演奏するという企画そのものが、芸術にたずさわる人間の有り様とは、どこか乖離しているようにも思われた。颯爽とメルセデスベンツのリムジンか何かでコンサート会場に乗りつけ、さっと演奏して引きあげる。その一陣の疾風のようなカッコよさにシビレル聴衆もいるのかもしれないが、わたしには、権力志向をむき出しにしたような彼の容貌とともに、そんなふうに自信満々の態度をとることのできる人間が、非人間的な存在のようにも思われた。そして、最も人間的な営為であるはずの、ミューズの神[芸術の神]との交流とは相容れない、奇妙な齟齬があるように感じられたのだった」
「ほんとうに優れた芸術は甘口専門ではない。もっと辛口で、苦い味わいを持っていたり、厳しく大衆を拒否したり、孤独で、深遠で、ときには近寄りがたい存在である。だが、そこを通り抜けてこそ、初めて真実の感動とめぐり会えるのだ。真実の感動は、人の存在自体を危うくするほどの力を持っている、と思う。[宇野功芳]」
仏は何のためにこの世に出現するのか
★一大事の因縁:開示悟入
諸仏世尊は、唯一大事の因縁をもっての故にのみ、世に出現したまえばなり。舎利弗よ、云何なるをか諸の世尊は唯一大事の因縁をもっての故にのみ世に出現したもうと名づくるや。
一、諸の世尊は、衆生をして仏の知見を開かしめ、清浄なることを得せしめんと欲するが故に、世に出現したもう。
二、衆生に仏の知見を示さんと欲するが故に、世に出現したもう。
三、衆生をして、仏の知見を悟らしめんと欲するが故に、世に出現したもう。
四、衆生をして、仏の知見の道に入らしめんと欲するが故に、世に出現したもう。
舎利弗よ、これを諸仏は、唯、一大事の因縁をもっての故にのみ、世に出現したもうとすなり。
一大事の因縁というのは、仏さまが、自分がこの世に出現する、あるいは存在する、その理由、意味合い、意義を、「一言で表現したら……」という内容なんです。つまり仏さまの最大の使命は、衆生を救うこと、それもただ救うのではなく、仏さまと同じレベルにまで引き上げ救うことなんだとおっしゃっているわけです。
この四つの段階、「(仏知見を開かしめ、示し、悟らしめ、道に入らしめる」を、私たちは「開示悟入」と呼びならわしておりますが、これこそ、仏さまのお仕事の設計図、青写真なんですよ。そこで次に、この四段階に分けられた、「悟りへの道すじ」というものを考えてみたいのです。
まず、「衆生をして仏知見を開かしめ清浄なることを得せしめん」という世界ですが、この「開」という世界が一番最初にきていることに注目してください。仏法は、とにかく、まず目を開くことが大事なんです。世間の価値観にどっぷり浸かり、利益追求にのみ走っていた人間が、ある時、どういうわけか「永遠なる価値観」に気がつく。そして、「ヘェー、こんな世界もあったのか」ということになるんです。ただし、またすぐに目をパッと閉じちゃダメなんですよ。新しい世界を発見したら、その世界に「強い強い憧れ」を持たなくちゃダメなんです。そうなると、どんな変化が起こるかというと、世間の人とはなんとなく違った生き方をするようになるんですね。このなんとなく違ったようす、これが世間の人には、「あいつ馬鹿じゃない」「あの人変わってるわ」から、だんだん「いい奴だな」とか「ああいう生き方がうらやましい」となっていくんです。こういうのが清浄という世界なんでしょうね。
次は、「衆生に仏知見を示さんと」ですが、私は四段階の中で、この段階が一番重要で、一番興味深い世界だと思っています。お経を習い始めた頃この部分を見ていて、「アレ?」と思ったことがあるんです。四つの言葉で、他のところはみんな「衆生をして」となっているのに、ここだけは「衆生に」となっているんです。そこで、「衆生をして」と「衆生に」では何が違うのか……、と考えてみたんですが、こりゃ行為の主体が違うなと気がついたんです。つまり、他の三つ、目を開くのも、悟るのも、道に入るのも、最終的にそれを行うのは私たちですよね。たとえ背後に仏さまの意志が強く働きかけているとしても、行う主体は私たちです。ところが、仏さまが仏知見を衆生に示すということになると、私たちが行う行為ではないですよ。示すのは仏さま、私たちはそれを受けるだけ。そうですよね。つまり、仏知見に目が開いた人間に対し、仏さまは何かを示してこられるというんです。そして、私たちは、その何かを、いやおうなく「体験させられる」といっているんです。仏法に目が開いたら、何かを体験させられる、そういう意味合いなんです。
実は、お坊さんたちがよく言う言葉に、「仏法に不思議なし」という言葉と、「仏法の不思議という正反対の言葉があるんです。仏法に目が開いた人というのは、深い霧のなかで迷っていたが、突然霧が晴れて、なにもかもがハッキリ見えてきたようなものでしょう。目から鱗が落ちるとでもいいますか。そこには、迷信や、まやかしや、意味もない恐れなどはなくなって、まさに見えている世界をまっすぐ歩けばいいのだという大安心、つまり「仏法に不思議なし」という感覚を持つのだと思います。しかし、そういう人も、この第二段階の、仏から「何か」を示されるという体験をすると、「仏法の不思議」というものを感じないわけにはいかなくなってくるんですね。
こうやって、その人の心に深さや陰影がどんどん加わっていき、やがて仏知見を悟るという世界に入っていくのでしょう。そして、最終段階の仏知見の道に入る。つまり、その人の行為そのもの、歩く、坐る、臥す、語る………すべてが仏知見そのものという状況が現われるのだと考えられます。
さて、この一大事の因縁を考える上で、意外と見落とされがちな、しかも非常に重要な視点があるのです。それは何かというと、この経文は、仏さまが説いたものです。つまり、これは仏さまの側から見た世界なんです。とすると、私たちの側から「仏の一大事の因縁」を見たらどうなるのかと考えなくてはいけないんですよ。そして、この問題は深く考えるべき必要があるのです。経文とにらめっこをしてください。実は、我々凡夫の立場からすると、四段階の解釈などより、「仏が出現する」という言葉のほうが、もっともっと重要なんです。つまり仏さまの存在自体がスゴク大きな意味を持っていることに気がつかなくてはいけないのです。仏さまという存在は、とてつもなく大きな観点から私たちを導いたり、不思議を示したりなさっているわけでしょ。とすると、仏さまと私たちの間には、圧倒的な違いが存在していることになります。そして、そのことが、ものすごく重要なんですよ。
現代は自我肥大の時代です。ですから、一人一人が、自己中心的な考えで行動したり、思考したりするようになってきております。そういう風潮ですから、「自分という一個人の中でものごとが始まり、自分という一個人の中でものごとが完結する」という感性が、ますます顕著になっているような気がします。危険だし、恐ろしいと思いますよ。このままだと、自分の外側がまったく見えなくなるかもしれません。しかしよく考えてみてください、人間なんてちっぽけなもので、大きな器の内部をあくせく動いているだけの存在かもしれないのです。
私は生物の本をよく読みますが、昆虫とか鳥とかさまざまな生き物の生態を見ていると、大自然の摂理を抜きにして、自分、自分というふうに、自己主張をする生き物などいないことに気がつきます。どの生き物も、自然の法則にのっとって、一番理にかなった生き方をしています。
じゃ、かれらは盲目的に自然にひれふしているのかといえば、決してそうでもないんです。前に、鳥が鳥となるには、二億年にもわたって〈空を飛びたい〉という夢を持続する必要があったと話しました。こういうのは、一羽の鳥の個の問題ではないんです。自己存在をはるかに超えた夢や願望ですよね。私は、人間の場合、そういう種類の夢や願望はどこに根づくのかと言ったら、信仰という世界に根づくのだと思っております。
さて、小さな小さな虫にだって、こういった信仰、あるいは夢や願望は存在しているんです。今ここに、セッケイカワゲラという虫のことを書いた本があります。長文の引用になりますが、この虫の変わった生態を理解すると同時に、実は、その背後に、ビックリするほど大きな意志が働いていることを知ってほしいのです。一匹の虫をとおして、個と全体の関係を考えてほしいのです。
雪の上を歩く虫:セッケイカワゲラ(Eocapnia nivalis)
仏の実在が感じとられてくると
コルベ神父のお話
衆生に仏の知見を示さんと欲するが故に、世に出現したもう。
「空」と「諸法実相」の違い
「諸法実相」⇒「法華経の世界観」
諸法(存在・現象)の、その実(真実・ありのまま)の相(すがた)
諸法実相とは、単純な構図で理解できる世界ではない
如来たちは偉大な驚嘆すべき不思議なものを得たのである。如来は最高の驚嘆すべきものを得たのだという、このような言葉で満足せよ。如来こそ、如来の教えを教示しよう。如来は個々の事象を知っており、如来こそあらゆる現象を教示することさえできるのだし、如来こそ、あらゆる現象を正に知っているのだ。すなわち、それらの現象が何であるか、それらの現象がどのようなものであるか、それらの現象がいかなるものであるか、それらの現象がいかなる特徴をもっているのか、それらの現象がいかなる本質を持つか、ということである。それらの現象が何であり、どのようなものであり、いかなるものに似ており、いかなる特徴があり、いかなる本質をもっているかということは、如来だけが知っているのだ。如来こそ、これらの諸現象の明白な目撃者なのだ。
仏教の世界観を考えると、「三宝印」が思い浮かびます。これは「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静」、そして「一切皆苦」を含めた四宝印とも呼ばれます。さらに深く考えれば、般若経に記された「空」の概念も浮かぶでしょう。この世界は本質的に「空」であるという観念です。「諸法実相」を理解するためには、まず「空」という概念を考察する必要があります。
全ての存在は本質的に「空」であり、この世のありとあらゆるものは、実体を持たず、「空」という状態や関係性で成り立っています。大乗仏教の基本思想は「空」ですが、法華経における「諸法実相」は、般若経の「空」を単にバリエーション化したものではないのです。
「空」という考え方は、物事を否定するプロセスであり、深く見つめれば何も実体がないという本質が明らかになります。重要なのは、表面の現象よりも本質である「空」を観じることです。
法華経は物事の本質を「空」として見ることを勧めているわけではなく、「物事をそのまま、ありのままに見なさい」と教えています。
一方は、まず疑ってかかれ、外観に騙されちゃいけないぞと教えていますが、一方は、この世には無限の多様性と無限の変化が存在している、それらを一つ一つ真実だと受け取りなさいと言っている。こういう違いがあるのです。否定と肯定数学で言うと、ベクトルが反対方向を示しているわけです。
物語を考えると、リアリズム小説と童話の違いがあります。リアリズム小説では、人間の生活や人生が現実的かつ写実的に描かれます。王も庶民も同じ悩みや苦しみを抱えており、矛盾や不合理に溢れた世界が表現されます。これにより、読者は人生の「空」さを感じさせられます。一方、童話はファンタジーに満ちており、日常の些細な事柄から始まる夢が物語を通じて大きく展開し、読者を驚かせます。この退屈な人生が輝かしい世界に変わる瞬間を提供します。
仏教の教えは、このようなファンタジーのような現実肯定ではありません。しかし、般若経のように否定から始まり、最終的に肯定的な世界を見出すより、すべてを最初から肯定する方が素晴らしいことでしょう。
しかし、人間は自己本位で利己主義的な生き物で、自然界の他の生き物と同様に、完全な肯定は困難です。般若経のように否定から始めて、「空」を見つけ出すことができるのはごく一部の人々に限られます。
諸法実相という世界観は、人間の理解を超えたものであると理解すべきです。法華経の中で、解空第一と讃えられた須菩提(スブーティ)でさえ、この世界観を完全には理解できず、外れた存在として描かれています。したがって、法華経の世界観は、一切皆空という単純なものではないと考える必要があります。
それなら諸法実相とは、どんなことをすれば見えてくる世界なのでしょう。
経文にはこう説明がしてあります。
如来は方便と知見波羅蜜とを皆己に具足したればなり。舎利弗よ、如来は知見広大・深遠にして、無量・無力・無所長・禅定・解脱・三味ありて、深く無際に入り、一切の未曾有の法を成就せり。舎利弗よ、如来は能く種種に分別し、巧みに諸の法を説き、言辞柔軟にして、衆のえっか心を悦せしむ。舎利弗よ、要を取ってこれを言わば、無量無辺の未曾有の法を、仏は悉く成就せり。
つまり、仏さまが獲得した智慧というのは、気の遠くなるほど長い年月、一心に修行を積み重ねることで得たものである。だから、その智慧は、おそろしく広くて深い。しかも、仏は相手の能力に応じて、もっともよい方法(方便)で、教えを説くこともできる。とにかく、その能力は無量であり、(限界がないくらい大きい)無礙である(何ものをも恐れるものはない)。しかも禅定に入り、深い三昧によって精神統一を完成させているのだ。とにかく、表現しようもないほど驚嘆すべき智慧を、仏は完成しているのです。
つまり、このような、仏さまだけが見ることのできる世界、これを「唯、仏と仏とのみ、乃ち能く諸法の実相を究尽せばなり」とおっしゃっているのです。
仏教には多様な教えが存在します。特に大乗仏教は、「空」という思想から出発した仏教の一派ですが、すべての大乗仏教が「空」だけで理解できるわけではありません。実は、大乗仏教の中には「空」だけでは説明しきれない、またはそれを超えた思想を持つ経典も存在します。その代表的なものが法華経です。
法華経では、仏性や永遠、進化した菩薩思想といった概念が中心となり、仏教の世界観を変化させています。時代が進むにつれ、「諸法はそのまま真実である」という新しい解釈が生まれました。これにより、「仏さまだけが物事をありのままに見る」という考えを超え、「すべてのものがそのまま真実である」という見方が広まりました。
日本の仏教は、この「ものごとはそのまま真実である」という教義を根底に持っています。しかし、教義が深まることは必ずしも素晴らしいことではなく、時にはその深化が仏教の衰退を招くこともあります。教義が高度に発展すると、それが無意味なものとなり、歴史から消えてしまう可能性があるのです。仏教には一種の「業」のようなものが内在しており、教義や教学を担う人々は、この内在的な問題をしっかりと見据える必要があります。教義は両刃の剣であり、その危険性を認識することが重要です。
法華経の中で、諸法実相の世界観は抽象的なものとして扱われますが、それだけに留まらず、具体的な要素も加えられています。舎利弗のような一部の人物にしか完全に理解できないものでありながら、その深みには実際にわかるような具体性が含まれているのです。
皆さん、とにかく経文を味わってください。いつかこれらの経文から、じわーっと何かを感じられるようになって欲しいなと思っています。どの経文も深い意味合いは、「仏だけが、ものごとの真実の姿を、ありのままに見極めている」という「仏の究極の智慧」が本源となっている言葉なんです。そして、何より特徴的なのは、仏さまの誓願が、「衆生の救済」にあるという姿勢なんです。
ものごとを「ありのままに見る」とは
「物事をありのままに見る」という考え方には、重要な問題点や疑問が内在しています。具体的には、煩悩や悪業などの汚れに対して仏はどのように向き合っているのかという疑問です。私たちが生きるこの世では、異質なものとの対峙が最も難しい課題です。思想や感性が異なるものとどう向き合うか、特に自分に害を与える可能性のあるものに対しては、「ありのままに見る」という態度だけでは対応できません。「存在するものはすべて真実である」という考え方は、簡単に受け入れられるものではありません。
法華経では、このような問題を扱い、具体的に説明します。特に第十二章「提婆達多品」では、悪人や女性の成仏を通じて、仏の見方を明らかにします。さらに、多くの仏弟子や菩薩に対して、将来仏になることを保証する授記が与えられます。これにより、仏の救済の概念が重要な位置を占めるようになります。法華経を読むと、その背後にあるのは仏の救済という思想であることが明らかにされています。法華経は、この点において非常に巧妙に計算された経典と言えます。
教義の話から一旦離れ、私たちの視点で「物事をありのままに見る」という世界について考えてみましょう。
芸術の中には、時折、不思議な力を持った作品が存在します。そういった作品は、しばしば人間の弱さや卑怯さ、嫉妬など、人生の汚れた部分をありのままに描き出しています。しかし、それらの作品には、どこか別の世界から静かな光が射しているように感じられる瞬間があります。また、寂寥感が昇華し、透明で結晶化したような作品もあり、彼岸からの風が吹いているような感覚になります。
たとえば、上野の西洋美術館に展示されているレンブラントのエッチング作品の中に、洞窟のような場所でキリストが貧しい人々に説教している作品があります。なにもかもが薄汚さでいっぱい、そういう画面です。 優雅とかエレガントなどとはおよそ無縁な画面です。ところが、この画にはどこかから寂光が一筋、静かに射し込んでいる不思議な絵です。
このような彼岸からの風や光が感じられる作品に出会うと、それは決して作者の意図や計算だけで生まれるものではないと思います。技巧や技術の問題を超えて、作者が世界を見つめる視線の奥深くに、すでに彼岸の風が吹いているのでしょう。このように、彼岸の光に照らされた視線は、物事をありのままに見つめ、描いていく過程で、透明な寂寥感が滲み出るのではないでしょうか。芸術作品を通して、私たちは彼岸の世界からのささやかなメッセージを感じ取ることができるのです。それは、物事をありのままに見るという姿勢が、単なる現実の描写を超えて、より深い真実に触れる瞬間をもたらすのです。
以前、池袋の文芸座で『私が棄てた女』という映画を見ました。映画の物語は、見かけ上魅力のない女性が、一途に愛を捧げ、最終的には命を捨てるというものでした。この映画が遠藤周作の小説を元にしたものだと知った時、驚きました。その後、私は遠藤周作の作品に再度目を向け、『哀歌』という短篇集を手に取りました。彼の作品には、まるで別の世界からの光が射しているように感じました。遠藤周作の変化の背景を探ると、彼は30代の終わりに重い病を患い、生死をさまよう大手術を経験していました。若い頃から死を見つめ、人間を深く観察してきた彼の視線は、初期の観念的なスタイルから深く、広い視野を持つ作家へと変貌を遂げていたのです。
この現象の背後には、法華経が説く「諸法実相」という世界のヒントが隠されていると感じます。「ものごとをありのままに見つめる」というのは、見方ではなく、視線の本源に重要性があると思います。その本源に、彼岸の世界からの寂寥に満ちた光が射していなければ、真の洞察は得られないのです。
また、「美」の概念について考えることも、諸法実相の理解への一歩です。人間の側面からではなく、彼岸の世界が深く関わる「美」の中には、人知を超えた領域が存在します。この美を二つに分けて考えると、一つは青春の真っただ中にいる人間が見る世界の美しさ、もう一つは末期の眼を持ってしまった人間が見る世界の美しさです。
青春の真っただ中にある美しさは、一度きりの絶妙な贈り物です。例えば、モーツァルトの音楽は、青春の輝きに満ちた美しさを表現しています。彼の晩年の作品には、彼岸から吹いてくる風のような美しさがあり、それは人間がこの世に「さよなら」を告げる際に見える美しさです。
同様に、お釈迦さまの最後の旅の途中での描写にも、このような美しさが見られます。死に向かう道のりで、彼は過去の思い出を振り返り、それぞれの場所に感慨深く言及しています。このような眼差しは、人間が特定の瞬間に経験するものです。例えば、卒業式の際に校舎を振り返るときに感じる深い感慨は、その一例です。
最終的には、「諸法実相」、つまり物事をありのままに見る世界は、このような経験を積み重ねていくことから始まると思います。それは、ただの抽象的な理念ではなく、具体的な経験と感慨の積み重ねによって形成されるものなのです。
譬喩品ひゆほん第三
譬喩品第三のあらすじ
仏の願いは、すべての人間を、たった一つの道、つまり一仏乗──本当の悟りの世界へ導くことである。仏が、今までやってきたこと、つまり人々の能力に合わせて、いく通りもの教えを説いたのは、結局、この一仏乗の教えに導くための方便(前提)だったのだ……、お釈迦さまはこういう説明をなさいます。この教えを聞いて、舎利弗(シャーリ・プトラ)は今までぬぐいきれなかった、さまざまな疑問がたちどころに消えていきました。その姿を見て、お釈迦さまは舎利弗に対し、舎利弗の前世の話をされます。そして、「お前は未来において華光如来という仏になるだろう」と予言(授記)をなさいます。
さて、智慧第一といわれた舎利弗ですから、お釈迦さまのご真意を理解することができました。しかし、舎利弗以外の者には、まだひとつよくわかりません。そこで、お釈迦さまはわかりやすく譬喩(譬え話)をもって説明をされるのでした。
大長者がいたとしよう。財産も豊富でたくさんの下僕もいる。そして、彼の邸宅は広大で、その中にはたくさんの人が生活をしている。ところがこの邸宅には門がたった一つしかない。その上、建物は朽ちはてて危険な状態であった。それに、この建物の中には人間以外に、さまざまな魑魅魍魎が跋扈していたのだ。
ある時、この家から火が出た。その火はまたたくまに燃えひろがりはじめた。長者は、この時邸宅の外にいて、火事が起こったのに気がついた。邸宅の中にはたくさんの彼の子供がいる。子供たちは火事の恐ろしさを知らないので、遊びほうけているばかりだ。長者はいろんな方法をこうじて、彼らを建物の外に連れ出そうとするが、いかんともしようがない。そこで一計を案じて、子供たちの大好きなものを思い出し「オーイ、珍しい羊の車があるぞ、鹿の車があるぞ、牛の車があるぞ。これをお前たちにあげよう」と呼びかけると、子供たちは欲しいものにつられて、猛火の家から出てきた。長者の喜びは大きなものであった。子供たちは、約束のものをくださいと願いでた。そこで長者は、子供たち全員に、それよりもはるかに素晴らしい、大白牛車という車を与えるのだった。(三車火宅の譬え)
長者とはもちろんお釈迦さまのことであり、子供たちというのは、迷える凡夫のことであります。そして、火に包まれた邸宅というのは、この世界のことです。お釈迦さまが一計(方便)を案じて、子供たちの好みに応じ、いくつかの車で、彼らの心を釣ったのが三乗(声聞乗・縁覚乗・菩薩乗)の教えであります。そして、最後に与えた大白牛車というのが、一仏乗の教えであり、この法華経だと言われるのでした。
心の眼が開く
法華経の第三章「譬喩品」には、「三車火宅の譬え」という名高い譬え話が含まれている。この話は、法華経の第二巻に位置しており、仏教徒にとって非常に重要な部分だ。この章では、仏陀がなぜ譬え話を語るのかという前提が示されている。先に、舎利弗が仏陀の教えを理解し、仏陀は彼に華光如来になるという予言を授ける。しかし、他の弟子たちは舎利弗の予言を喜びつつも、仏陀の真の意図を理解できずにいた。そこで仏陀は、彼らにも理解できるように、簡単な譬え話を用いて教えを説明しようとする。
しかし、法華経の解説書では、この譬え話の前半部分がしばしば省略されている。この部分は、舎利弗の心の眼が開かれるという重要な場面を含んでいるにもかかわらず、多くの著者がこの心理的過程を追いかけていない。このため、読者はしばしば不満を感じ、教義の深い理解に至らないことがある。
方便品の章では、仏陀が当初、法華経は難解であるため説かないと聴衆を拒絶する。しかし、舎利弗たちの熱心な懇願に応え、仏陀は教えを説くことを決意する。この段階で、舎利弗はすでに仏陀の本心を理解していた。この理解の鍵は、方便品の経文にある。仏陀の初めての言葉は、衆生に同じ悟りを与えたいという誓願を示している。これは、阿弥陀仏の第十八願と類似している。また、方便品には、仏陀が衆生に仏の知見を開かせるためにこの世に出現したという教えも含まれている。これは「一大事因縁」と名付けられ、仏の出現の理由を示している。
しかし、法華経が説かれること自体が、仏にとっての本願であり、舎利弗はこの点を理解していた。この理解により、法華経の説法が始まった時点で、すでに舎利弗は仏陀の心を理解していたのである。
忘れている自分を思い出す
仏教にはさまざまな流派があり、それぞれに異なる教えや視点が存在する。特に、禅宗や小乗仏教と大乗仏教では、教義に顕著な差異が見られる。大乗仏教は、「空」の概念だけではなく、「仏性」や「永遠」といったテーマも追求している。これらの概念は、空観の哲学だけでは説明がつかない深みを持っている。大乗仏教の特徴の一つは、「仏・菩薩の誓願」が強調されている点にある。一般的に人々は仏教の悟りや救いを、修行を通じて得られるものと捉えがちだが、大乗仏教では仏の慈悲や誓願の力がより重要とされている。これは、悟りが努力によって獲得されるものではなく、本来持っているものという視点への転換を意味する。
法華経を深く理解するためには、自己の内面を深く探求し、普段は意識しない自分自身と向き合うことが重要だ。例えば、法華経で舎利弗に授けられた授記は、物語のほんの始まりに過ぎない。法華経は多くの人物に授記を与え、その数は数えきれないほどになる。ただし、ここで忘れてはならないのは、授記と禅宗の「印可」は異なるものであるということだ。印可は師が弟子の悟りを証明する行為であるが、授記はまだ悟りを得ていない人に対し、将来仏になるという予言をする行為である。例えば、仏が道を歩いている際に出会った人に対して、「三百年後に〇〇如来になる」と予言するような場合、その人は驚くだろう。重要なのは、授記が未来において絶対的な確実性を持っているという点である。これは、現在の状況ではなく、未来への確固たる約束として理解されるべきだ。
舎利弗に対する仏陀の授記の前には、舎利弗への深い言葉がある。梵文訳を見ると、舎利弗が長い間仏陀の弟子であり、前世の修行と誓願を忘れ、「さとり」の境地に達したと誤解していたことが明らかにされる。仏陀は、舎利弗に前世の修行と誓願を思い出させ、智慧を目覚めさせるために法華経を説いたと述べられている。舎利弗は、過去の長い旅路を忘れ、現世の悟りにのみ執着していたが、真の悟りはそれだけではなかった。仏陀は、舎利弗に前世の修行と誓願を思い出させることで、真の智慧の目覚めを促したのだ。
この教えは、人間が現世だけを全てと見なすと、法華経のような教えは理解しづらいものとなるが、過去の生を思い出すことで、法華経の教えが身近なものに変わり始めることを示唆している。大河の水音のように、法華経は徐々に心に響くようになる。
人間はしばしば自己を探求しようとするが、外側に目を向けていることが多い。内面を見つめることは簡単ではないが、一旦内側に目を向けると、驚くべき発見をすることがある。法華経はこのような内面の転換を通じて、宝の蔵のような価値を持つ教えとなるのだ。
さて、授記をよく知るために、しっかりと理解しておかなくてはならないことがあります。ポイントになる部分だと思いますので、他の話は忘れても、この部分だけは理解して欲しいなと思っています。
道元禅師の『正法眼蔵』(仏性の巻)に、”仏の道理は、仏性は成仏よりさきに具足せるにあらず、成仏よりのちに具足するなり、仏性かならず成仏と同参するなり、この道理、よくよく参究功夫すべし。” という言葉があるんです。「エッ?」と思いませんか。
仏性はすべての生きとし生けるものに本来備わっているとされているが、道元は仏性の本質について異なる見解を持っていた。彼は、仏性は成仏するまでは存在せず、成仏した後に初めて「仏性が具足していた」と認識されると説いている。これは、仏性の実在は成仏というプロセスを経なければ確認できないということを意味する。道元にとって、仏性と成仏は紙の裏表のように密接に関連しており、別個の概念として扱われない。
この考え方は、子供たちのナゾナゾ「お母さんと赤ちゃんはどちらが先に生まれたか」という問いに似ている。このナゾナゾの答えは、「赤ちゃんを産むまでは女性だったが、赤ちゃんを産んで初めてお母さんになる」であり、お母さんと赤ちゃんは同時に生まれるということを意味する。道元の仏性に関する見解とこのナゾナゾは、相互に依存する関係を示している。
法華経もこのような考え方を示している。仏陀は法華経を説く時が来たと述べ、「わが所願の如きは、今、すでに満足し……」と言葉にした。これは、成仏という証がなければ、具足しない仏性のようなものだと示唆している。母親になる前の女性のように、道元の考え方によれば、成仏する前の仏性はまだ具足していない。このような観点から、法華経の「授記」が登場する。授記がなければ、法華経はいつまでも完結しない経典となる。この見解は、仏性と成仏の関係性を深く掘り下げ、仏教の深遠な教えを示している。
あちら側感覚とこちら側感覚
仏教でいう、あっち側とは、いわゆるあの世:霊界のことではなく「彼岸の世界」のこと。仏の価値観の世界。絶対の世界、あるいは価値観を超越した世界。日本仏教の怠慢の一つは、この「彼岸の世界」と「霊界」とを、キチンと区別して教えようとしないこと。むしろ霊界専門になって、祖霊供養を生業としてしまっている。もっとも日本人は、この霊界感覚が根深くて、やむをえない要素もある。⇒例:能の世界でいう「鏡の間」⇒仏教が表現する彼岸とは別感覚の世界。
「彼岸の世界」を「鏡の間(霊界・幽界)」と混同してしまうと、法華経の一番大事な部分が、歪曲されかねない。
『孤独な放浪者シューベルト物語』より
「前まえからなんどもなんども感じていたことだが、もしかしたら自分は今、仮の世に生きているのではないだろうか。自分のためのほんとうの世界はどこかほかにあって、いつかそこにいきつくまで、仮の世をさまよわなくてはならないのかもしれない。いつも『はみ出し者』のような気がしていたのはそのせいなのだ。」
音楽を全存在で愛し、短い生涯を駆け抜けたシューベルト。彼の心の中には、二つの世界が共存していたと想像される。彼は、本来の居場所が「あちらの世界」にあると感じていたが、現実には「こちらの世界」で生活していた。この状況から、シューベルトはおそらく、この世が一時的なもの、仮の人生であるという考えに至ったのだろう。
この「あちらの世界」という感覚が重要である。世俗的な価値観ではなく、永遠の価値観に目覚めた人は、この世の重要性が薄れ、「あちらの世界」に心が惹かれ始める。シューベルトの心の中では、この二つの世界が適切なバランスで存在していたのだ。このようなバランスが、彼の音楽に深い感情と豊かな表現をもたらしたと考えられる。シューベルトの音楽は、この世とあちらの世界の間に架かる橋のようなものであり、彼自身がその両世界を行き来しながら生み出した芸術の結晶だったのではないだろうか。
★本籍は「あっち側」、現住所は「こっち側」を生きぬいた人の話
実は、「あっち側」も「こっち側」もよく見える場所というのは、法華経がよく見える場所でもあるんです。また、法華経の底流をながれている基調音がよく聴こえる場所でもあるんです。
***
実は、法華経の難しさというのは、文字だけでは見えない、隠された世界があまりに広く、深すぎることなんです。知識ではダメで、感性でしか入っていけない領域があるということなんです。その上、感性でしか入っていけない世界は、なかなか他人と共有できないんですね。私が、この法華経講話の第一回から、悪戦苦闘して伝えようと努力している世界は、どちらかというと、この共有しにくい感性の世界かもしれません。ですから、こうした講話は、すごく意味深いとも言えるし、まるでムダとも言えるわけなんです。
1:スピノザ
バールーフ・デ・スピノザ、17世紀のユダヤ系オランダ人哲学者は、社会や人間の悪意に翻弄されつつも純粋な生き方を貫いた。彼の人生は、まるで物語のようなもので、社会科の教科書にもその名が登場する。汎神論の提唱者として知られ、西洋の一神教的背景の中で異端的な宗教観を持っていた。
スピノザの初めの挫折は20代で始まる。ラテン語教師の娘への恋愛と失恋、そしてその後の孤独と絶望から、彼は独学で哲学の道を歩み始める。しかし、そのすぐれた才能と独創的な思想が教会の怒りを買い、最終的には破門される。17世紀ヨーロッパにおける破門は、人間としての生きる道を断たれるほどの大事だった。
スピノザはこの逆境の中で、屋根裏部屋での孤独な生活を送りながら、レンズ磨きで生計を立て、肺病と闘いつつ、後世に残る著述を完成させる。44歳で静かに亡くなるまで、彼の思索は純粋なものであり続けた。後世の人々は彼を「屋根裏の哲人」「神に魅入られた人」と呼び、彼の信仰はどこか東洋的だった。
スピノザの一生を考えると、彼は本来「あちら側」の世界に属しているが、「こちら側」の世界で生きることを余儀なくされたように思える。もし私たちがスピノザのような人生を送り、「あちら側の世界」を持たないなら、反抗的になるかもしれない。しかし、「あちらの世界」が本籍で、「こちらの世界」が仮の世だという信念が強ければ、精神は天に向かって飛翔し、純粋なものへと昇華するかもしれない。スピノザの人生は、この世の逆境にもかかわらず、その精神性が純粋さを保ち続けたことを示している。
2:白隠禅師
法華経の譬喩品を考えるとき、白隠禅師の名が浮かぶ。臨済宗の僧侶であり、法華経によって深い悟りを得た人物として知られている。白隠は四十二歳の時に、ドラマチックな体験を通じて法華経の真髄を理解した。彼は既に二十代で二度の大悟を経験しており、修行や文芸においても非凡な才能を発揮していた。幼少期から法華経に親しんでいた白隠だが、出家後はその経典から離れていた。十五歳で出家し、肉身が火にも焼かれず、水にも濡れないような力を求めて苦行を続けたが、効果は見えず、心は満たされなかった。その後、法華経に再び目を向けるが、最初はその教えに疑念を抱いていた。
十五歳にして出家して自ら誓っていうには『どうか肉身でありながら火も焼くことができず、水も漏らすことができないような力を見なければ死んでも休まぬ』と昼夜一心不乱に誦経し作礼した。
病気や針灸の間において自己の力を調べてみても、その痛さは平生とまったくかわらないので、心はなはだ喜ばずしていうには『自分はすでに父母に背いて出家したが、まだ少しの効果も見えない。
自分が聞くところによると、法華経は一代の経王であって、鬼神も恐れかしこまる。たまたま幽冥界に落ちて苦しんでいる人が、他人に依頼して救いを求める時、必ず法華経を読んでもらうという。よくよく考えるに他人が読誦してさえも、その苦しみを除くことができる、まして自分自身で読誦すればどんな苦しみでも除けるのではないか。そのうえ、この経中には必ず深い勝れた教えがあろう』と。
そこで親しく法華経を手にとって、その教えを究めて見るのに、『ただ一乗のみ有り、諸法は寂滅である』という一文を除いては、他はみな因縁の説ばかりである。
この経にもしこのような功徳があるならば、六経や諸子百家の書もやはり功徳があろう。どうしてこの経だけ功徳があるというのか。そこで大いに平素の志をなくした。それは実に十六歳の時であった。

しかし、四十二歳の秋、白隠は「看経」という看板を掲げ、僧侶にマンツーマンで法華経を教え始める。そして、譬喩品を読み進める中で、部屋の外で鳴いていたキリギリスの声が彼の心に響き、突然、法華経の深い意味を悟った。白隠は感動のあまり号泣し、法華経がなぜ「経王」と呼ばれるのかを理解した。この時、彼は以前に理解していた法華経が、実際の教えとは似ても似つかないものだったと気づいた。
その時、白隠は、法華経がなぜ諸経の王と呼ばれるのか、その理由が、初めてわかったというのです。そして、自分が理解したつもりだった法華経は、本物の法華経とは似ても似つかぬものだったことに気がついたんですね。
この文章の後のほうに、「大覚世尊舌根両茎を欠く」という言葉があります。この言葉に注目してください。お釈迦さまといえど、法華経を語る(舌根)には、両茎、つまり両方を満たすことはできなかった……と気がついたんですよ、植物の茎は、地中深く根をおろしたと、外部の花や実の両方につながっていますが、法華経のように深い教えは、それができないんです。あまりに、深く、広い教えだから、お釈迦さまでさえ、因縁話でしか伝えられない経典だったんです。
私が思うに、禅宗の悟りと法華経の悟りとは、かなり違ったものだと思うんです。だから、白隠は二十代に大悟した内容を、四十二歳でもう一度くり返したのではないと思います。おそらく、まったく性格の違う悟りだったのではないでしょうか。
もちろん、四十二歳の時に得た悟りのほうが、はるかに深かったと想像されます。白隠はこの夜、法華経の扉の前で、偶然、向こう側をかいま見てしまったのではないでしょうか。
白隠は、この時の体験を契機として、一段と悟境を深めたといわれております。そして、しばしば法華経の講義をするようになったといいます。
また講義のたびに、「心の外に法華経なく、法華経の外に心なし」と言い、「真の法華経を一見しなければならぬ」と強調したそうです。
「真の法華経」、おそらくこれこそが、白隠が見つけた世界だったんでしょう。
白隠の逸話をとおして、私たちが、ぼんやりと理解できるのは、真の法華経というものが、とてつもなく深く、とてつもなく大きく、とてつもなく高く、とてつもなく広い世界なんだろうな……ということです。
法華経はなぜ破天荒な教えと言われるのか
舎利弗は、お釈迦さまから直接授記を受けたことに大きな喜びを感じていましたが、同時に一つの疑問が心に浮かびました。他の会衆が彼の授記を喜んでいる様子は見えたものの、彼らが本当にお釈迦さまの教えを理解して喜んでいるのか、舎利弗には疑わしいように思えたのです。彼らは単に舎利弗が授記を受けたことを喜んでいるだけではないかと。
この疑問を抱えて、舎利弗はお釈迦さまに願いを述べました。彼は、会衆が混乱し、法華経の教えに疑念を抱いていると感じ、お釈迦さまに、これらの疑問や混乱を晴らし、教えをやさしく再度説明するよう頼んだのです。
お釈迦さまは舎利弗の願いに応え、わかりやすい譬え話を用いて、仏の真意を説明することにしました。そこで語られたのが、「三車火宅の譬え」です。この譬え話は、この章の中心的な部分となり、このためにこの章は「譬喩品」と呼ばれるようになりました。
この譬え話に入る前に、いくつかの重要なポイントを理解する必要があります。お釈迦さま自身が法華経を説くことをためらっていたことを思い出しましょう。舎利弗が熱心にお願いしたことによって、ようやくお説法が始まったのですが、教えは非常に異例なものでした。舎利弗自身、心の中で、こんなことを考えながら聴聞していました。
「この世の指導者である仏の声をはじめて聴き、わたくしの驚きはすさまじかったのです。『悪魔が仏の姿をして、この世に現われて、わたくしを悩ますのであろうか』とさえ思いました。」と。
つまり、そのくらい破天荒な教えだったわけなんです。しかし、皆さんには、いったいどこがそれほど破天荒なのか、おそらく見当もつかないでしょう。いや、見当つかないのが当たり前です。しかし……そう、しかしなんです。この破天荒さが理解できないと、法華経の大テーマである「一仏乗」という思想も、「なるほど、ああそう……」で終わってしまうんです。
では、この破天荒さの源はどこにあるのか。実は、法華経から離れたとたん、次々に見えてくる仏教の景色というものがある。特に、大乗仏教経典には、二乗、つまり声聞の生き方と、緑覚の生き方を徹底的に否定した経典が散らばっている。
【大集経】声聞・緑覚の二乗は、自分ばかり六道の生死を離れて、再び生まれて来ないから、父母の恩に報いることができない。この人たちはちょうど、深い穴に落ち込んで、自分が出ることもできず、また人を救うこともできぬようなものである
【方等陀羅尼経】枯れた樹に花が咲かず、山の水が逆に流れず、一度火で炒った種からは芽が出ないように、二乗も成仏することはない
【首楞厳経】五逆罪のような罪人でも成仏の可能性があるが、二乗にはそれがない
【浄名経】二乗に施しなどしても功徳にはならない、むしろ二乗に供養するものは、かならず地獄に堕ちる
【維摩経】二乗の行う善業と、凡夫の犯す悪業を比較して、凡夫の犯す悪業のほうが救いがある
日蓮聖人が「我が御弟子を責め殺さんとにや」と驚愕するくらいんの内容。
声聞や縁覚の弟子たちは、ある種の状況に慣れ親しんでいました。彼らは、自分たちはもはや成仏の望みがないと感じ、失望に満ちた弱音を吐き始めていたのです。しかし、法華経が説かれると、事態は一変しました。お釈迦さまは、二乗も三乗もなく、すべての存在が成仏するという驚くべき教えを説き始めたのです。
この新たな教えを聞いた弟子たちは、驚きと疑念に包まれました。彼らは自分の目と耳を疑い、まるで悪魔が仏の姿をして彼らを惑わせているのではないかと感じたほどでした。舎利弗が心の中で「悪魔が仏の姿をして、この世に現われて、わたくしを悩ますのであろうか」と疑ったのも、そのためです。このように、二乗が成仏するという教えは、それほどまでに革新的で破天荒な内容だったのです。
二乗蔑視と、女人蔑視:インドの仏教の歴史を踏まえないと、このあたりはなかなかわからない。
チャーリー・チャップリンの映画「独裁者」は、ナチスドイツとヒットラーを風刺した作品でした。この映画では、チャップリンが狂気の独裁者とその双子のユダヤ人床屋を一人二役で演じていました。物語のクライマックスでは、床屋が独裁者に成りすまし、国外逃亡しようとする場面がありますが、偶然にも大演説会場に迷い込み、演壇に引っ張り上げられてしまいます。独裁者に成りすましていた床屋は、やむなく演説を始め、「人間はみんな兄弟です」という心に響くメッセージを伝えます。映画は、この力強い訴えで幕を閉じました。
法華経の教えも、この映画の演説に似た特質を持っていました。昨日まで一部の人々を排除するような教えがあったにも関わらず、今日には「みんな兄弟ではないか」という訴えに転じたのです。聞いていた人々は、この変化に驚いたでしょう。しかし、心に深く響く真の教えは、映画の中の偽独裁者床屋が語る「愛」の教えだったのです。お釈迦さまが仏乗という「心の真実」を説き始めた背景には、仏教全体の流れがありました。この背景があったからこそ、舎利弗の授記が他の会衆に与えた喜びは非常に大きなものでした。
そこへ到る道はただ一つ
「三車火宅の譬え」は、法華経の中でも特に印象的な部分です。この譬え話は、ある富裕な長者の家が火事に見舞われるという設定で始まります。家は古く朽ちており、多くの人々が住んでいますが、家には入口が一つしかありません。長者は、この火事から無事に脱出しますが、彼の多くの子供たちは家の中で遊んでおり、火事の危険を全く意識していません。
長者は最初、子供たちを力ずくで救出しようと考えますが、すぐにそれが不可能であることに気づきます。彼は代わりに、子供たちを家から誘い出すために、彼らが欲しがる玩具を外に用意すると告げます。その結果、子供たちは家から逃げ出し、無事に救出されます。しかし、長者は子供たちに約束した玩具の代わりに、もっと素晴らしいものを与えます。
お釈迦さまはこの譬え話を終えた後、舎利弗に質問をします。彼が最初に約束した玩具を与えず、最終的にはより優れたものを与えたことが嘘ではないかと。しかし、舎利弗は、長者が子供たちを救ったこと自体が重要であり、約束の違反ではないと答えます。
この譬え話は、仏道を進むには様々な方向があり、仏教には多様な教えが存在することを示しています。天台大師や日蓮聖人のような方たちは、この複雑さを深く考え、法華経にその答えを見出しました。
お釈迦さまは、この譬え話を説くにあたり、「理解のすぐれた人は唯一つの喩え話をしても、直ちにその意義をとる」と述べています。これは、聞く者が話の中から仏さまの真意を理解し、単に聞くだけでなく、深く考えることの重要性を示しています。
この話の構造を、簡単な図で説明してみましょう。つまり、法華経が説く、一仏乗(大白牛車)とはどういうものかという構造ですね。

多くの人々は、世界には多様な宗教があり、仏教内にも多くの宗派が存在するが、最終的にはすべて同じ頂点にたどり着くという考えを持っています。著者はこの考えに理解は示しても、法華経によれば、この発想は誤りです。法華経の中で語られる「三車火宅の譬え」には、古びた家に「唯一つの入口しかなかった」とあります。これは、我々が生きる迷いと煩悩に満ちた世界、つまり三界の特殊な構造を象徴しています。
まず①の図を見てください。三つの登山口から道が延びてますが、真ん中の菩薩道だけが頂上に通じていて、あとの二つ、声開道と縁覚道は、途中で行き止まりになっています。これが法華経以前の、大乗仏教の教えなんです。声聞と縁覚の二乗は永久不成仏といって、永久に頂上にはたどりつけない(成仏できない)のだという構造です。仏教徒たるもの、登山口としては、菩薩の道を選びなさい、と言っているわけです。しかし、法華経は、同じ大乗仏教ではありますが、この構造も否定し、まったく新しい考えを説いた教えなんです。それが②の図なんです。
さて、この図を見ると、①の図と同じように三つの登山口から道が延びていますが、山の途中から、一本の大きな道(直道)が頂上に通じています。そして、この大きな道が始まる高さのところに点線が入っています。実は、この高さというのが「三車火宅の譬え」に説かれる、子供たちが燃えさかる家から逃れ出たという場所なんです。そして、長者から、子供たちは平等に大白牛車をもらったとありました。つまりそれは、ここから先は、一本の道(一仏乗)が頂上に通じていて、その道のスタートラインに立つことができたという意味なんです。そして、この大道に立った者には、お釈迦さまは授記を与え、「この道を真っすぐに進みなさい。そうすればお前は仏となる(頂上にたどりつくぞ)」と予言、保証をするという構造なんです。
つまり点線より低い所では、一本の道ではなく、三本の道があるわけです。お釈迦さまに言わせると、これが仏の善巧方便(ぜんぎょうほうべん)、つまり計略だといわれているわけです。
『こんな面倒なことをせず、山のふもとから、ドーンと一本の大道を通したらいいのに』と考えてしまいますが、譬え話にもあったように、仏さまだって、最初はそうしたいと思ったんです。しかし、私たち凡夫は、煩悩にまみれていますから、そもそも山に登りたいという気持ちさえ起こさなかったというんですね。つまり、我々は、そのくらい救いがたい存在でもあるんですよ。もし、ふもとから頂上に向かって、ドーンと一本の道をつけられるなら、仏さまは、四十年も待たず最初から法華経を説けばよかったんです。ところが、点線の高さまでは、騙し騙しでも、我々凡夫を引き上げない限り、法華経(仏乗)は説けなかったんです。
「四十余年末顕真実」というのは、こういう理由があったというのです。
この章に説かれる「三車火宅の替え」という物語には、これだけの意味合いが含まれているんです。
そこで、先っぱしりになってしまいますが、この譬喩品に説かれた、悟りの構図にも、伏せられた秘密がたくさんあるんだと思ってください。
実は、法華経という経典は、個人の救いよりは、世界全体を仏国土にしようという経典なんです。ところが、譬喩品を丹念に読んでみると、一仏乗の教えというのは、世界全体の幸せというより、特別な人間のための教え、そういう性格を持っているんですね。
シャーリ・プトラよ、人間たちの中で賢い人々は世間の父である如来の言葉を信ずるのである。かれらは如来の言葉を信して、如来の教誠に傾倒し、それに従い、それを守ろうと努力する。(声聞乗)
また、他のある人々は、独りでみずから得た智慧を守り、自制と平静を得ようと欲し、自分自身の完全な「さとり」のために因縁の道理を理解しようとして、如来の教誡に傾倒する。(独覚・緑覚・辟支仏乗)
さらに他の人々は、一切を知り、みずから存在する仏の智慧を欲して、多くの人々の幸福と安楽を願い、また世間に対する憧れみから、大衆の利益のために、また神々および人間の幸福と安楽のために、すべての人間を完全な「さとり」に導き、如来の智慧の力と自信を理解させようとして、如来の教誠に傾倒するのである。(菩薩乗)
譬え話が終わり、お釈迦さまは、この物語に解説を加えていきますが、その時、「おーい、すばらしいオモチャがあるぞ」と言って、火宅から誘い出すべき人々とは、この三つの経文のように、やはり特別な人々だととらえられているわけです。
そうすると……三乗の教えすら歩めない本当の凡人は、燃えさかる家の中で焼け死んでしまうことになるんですかね?オヤオヤ、一仏乗というのはものすごく平等な教えかと思ったら、かなりエリートの教えのような気がしてきますが、実は法華経も先へ進むと、宮沢賢治の言う世界全体の幸せ、つまり「ほんとうのほんとうの、まことの幸い」というのがテーマになってくるんです。この話より、もっとスゴイ救いが語られるようになるんです。譬喩品は、そういう法華経の最初のとっかかりだと考えてもいいわけです。
火宅を一歩出てみると
さて、そこで今度はちょっと視点を変えて、火宅の向こう側って、どんな世界なんだろうということを考えてみましょう。私の講座には、しょっちゅう「あっち側」という表現が出てきますが、『あっち側ってどんな世界なんだろう』という好奇心、探求心、憧れをバカにしてはいけません。こういう心こそが、実は信仰ということなんですよ。信じるということも、遥かに仰ぎ見るということも、現実には見えない世界を相手にしていることなんです。ちゃんと見える世界が相手だったら、「信」も「仰」も必要ないんですからね。 さて、ハッキリ言うと、私たちは三界火宅の中に住んでいる人間です。そして、外に出たことはありません。ですから、「あっち側の世界」は知らない人間だということです。しかし、私たちは「あっち側」を強く意識せずにはいられない存在でもあるんです。
かつて、高校の先生から著者が聞いた物語があります。それはアフリカのキリマンジャロ山についてのものでした。赤道直下にそびえるアフリカ最高峰の山頂は、一年中白い雪で覆われています。ある日、登山隊がその高い場所で豹の死体を発見しました。その場所は通常、豹が生息する範囲ではないとされています。登山隊は、この豹が山裾で生活し、日々その威厳ある山を仰ぎ見ていたのではないかと結論づけました。山頂の雪に覆われた神々しい静けさと、深い青い空の背景に心を引かれ、豹は衝動に駆られて山を登り始め、力尽きたのだと。この話を聞いて著者は驚きました。なぜなら、著者自身が似たような体験をしていたからです。
幼い頃、著者は父の勤める社宅に住んでいました。その窓からは町を見下ろす山が見え、私は飽きることなくその山を眺めるのが好きでした。マーケットが近くにあり、騒がしい環境でしたが、山を見ていると、周囲の雑音はすべて消え去ってしまいました。山頂の神々しい静けさに心奪われ、真っ青な空の背景に小さな雲が流れる様子に魅了されていました。その素晴らしい場所への憧れは強く、アパートを出て山に近づこうとしました。しかし、人込みの中では山の姿が見えなくなり、結局迷子になってしまうのでした。そんな著者のために、母親は胸に木札を下げ、住所と名前を書いていました。
つまり、人間というものは、時として、こういうふうに、「あっち側の世界」を強く感じたり、激しく意識したりすることがあるんですね。そして、この感覚こそ、私はとても大切なものなのだと考えているんです。
経文からすると、三界の火宅を抜け出るためには、まずなにより、人間の心に、「火宅の向こう側」への渇仰心(かつごうしん)が起きないことにはどうしようもないんです。ところが、現実には、この渇仰心が薄い、あるいはほとんどないという状況がある。だからこそ、仏さまは、三乗とか、一乗とか、方便とか……こういう、ある意味では、非常に煩瑣な手段をこうじなくてはいけなくなってくるんですね。
かつて、ジャーナリスト立花隆は、宇宙を訪れたことのあるアメリカの宇宙飛行士たちの声を集め、その経験を「宇宙からの帰還」という書籍にまとめました。この本は昭和五十八年に出版され、地球の外で何を感じ、どのように変わったのかを探求しています。百人ほどしか存在しない、この特別な経験を持つ人々の話は驚くべき内容で満ちており、読む者に深い印象を与えます。
この本を通して、私たちは地球を外側から見た人々がどれほど変化するかを理解することができます。宇宙飛行士たちの言葉は、宗教的な感覚に満ちており、多くが「神」を感じたり、その存在を信じるようになったり、さらには伝道者になる人もいます。彼らはまた、地球を一つの生き物として感じるようになると言います。これは非常に興味深い点です。
この話から、我々は理解できない「あっち側」の世界、つまり宇宙の向こう側について考えることができます。私たちはそのような世界を直接知ることはないかもしれませんが、それを理由に外界に対して無関心でいるべきではありません。未知の世界を探求することは、私たちの理解を深め、新たな視点をもたらすかもしれないのです。
実は、立花隆さんは、この本の「むすび」で、こんなことを言ってるんです。
”……彼らの体験は、我々が想像力を働かせれば頭の中でそれを追体験できるというような単純な体験ではない。彼らが強調しているように、それは人間の想像力をはるかに越えた、実体験した人のみがそれについて語りうるような体験なのである(…略…)彼らにインタビューしながら、私は自分も宇宙体験がしたいと痛切に思った。彼らと話せば話すほど、写真やテレビや活字で伝えられている宇宙体験と実体験がどれほどちがうかがよくわかるのだ。そして、私が宇宙体験をすれば、自分のパーソナリティからして、とりわけ大きな精神的インパクトを受けるにちがいないだろうと思う。そのとき自分に何が起きるだろうか。私はそれを知りたくてたまらない。”
譬喩品の火宅の譬えを読むたびに、火宅を一歩でも外に出た世界とは、どんな世界なんだろうと考えたりします。おそらくそれは、立花さんが表現するように、「人間の想像力をはるかに越えた、実体験した人のみがそれについて語りうるような」世界なんだと思います。いや、そうだからこそ、私は、「あっち側」という世界が、人間にとって、ものすごく意味深い世界なんだと考えたいんです。
身心脱落について著者が悟ったこと
二日前の夜、私は法華経の譬喩品を研究していたとき、心の中に興味深い思考が浮かびました。この思考のおかげで、長い間解決できなかった疑問が、まるで霧が晴れるように解消されました。
その疑問は道元の禅語、特に「身心脱落」に関するものでした。道元は悟りを「身心脱落」と表現していますが、これが何を意味するのか、長らく私の心を捉えていました。もし身と心が失われるとしたら、人間として何が残るのでしょうか。これは困難な問題です。ある解釈では「身心脱落」の後に残る何かが悟りの本質だとされていますが、それは私には理解し難いものでした。また別の解釈では、人間は仏から何かを受け継いで生まれるとされていますが、これも完全には納得できませんでした。
しかし、譬喩品を研究している中で、「身心脱落」という言葉がふと頭に浮かび、「身と心が失われた後に何が残るか」という考えが変わりました。私は「身心脱落」とは、身も心も失われて完全に消え去ることを意味するのではないかと考えるようになりました。
この考えに至ったのは、燃え盛る火宅から、長者が「出ておいで」と呼びかけるシーンがあります。その呼びかけに応じて、一人のお坊さんが静かに出口から外へ出て行く姿を見て、私は「身心脱落」とは、そういうことなのではないかと閃いたのです。
身と心が失われた後に何が残るかを考える必要はないのです。
全てが「あっち側」、すなわち彼岸の世界へ移行することこそが重要なのではないでしょうか。
これは日蓮宗の僧侶による法華経の解釈に基づくものですが、私は今、「身心脱落」をこのように理解しています。そして、いつか私たちも仏さまの呼び声に応じて火宅の外へ出て、そこに広がる美しい光景を目の当たりにすることを願っています。静かで、泣きたくなるほど美しい景色、光が降り注ぐその光景を。
燃える家とは
法華経は二十八品(章)から成り立ち、その中で譬喩品は最も長い章です。さらに、法華経は八巻に分かれており、その「二の巻」は譬喩品と信解品のみで構成されていますが、その大部分を譬喩品が占めています。この譬喩品はお坊さんにとっても読むのが難しい章で、珍しい漢字がずらりと並ぶため、声に出して読むのは一筋縄ではいかないのです。漢字に詳しい人でも、譬喩品の漢字をすべて読める人はほとんどいないでしょう。
譬喩品の偈文、つまり詩的な部分には特に興味深い内容が含まれています。この偈文は、普通の文章とは異なり、韻文の形式を取っています。韻文は、詩や和歌、俳句のようにリズムを持つ言葉で、記憶に残りやすい特性があります。経文の中では、長行と呼ばれる通常の説法の部分を偈文で再度繰り返すスタイルが取られています。
法華経の中では、偈文が特に長く、譬喩品の中でも特に長大です。この偈文には、長行で語られた「三車火宅の譬え」が再度語られるだけでなく、長行にはない独特の内容が含まれています。例えば、謗法の罪について詳細に語られた部分や、法華経を誰に説くべきかという指示があります。
偈文の内容は大きく三つの部分に分かれています。一つ目は「三車火宅の譬え」の繰り返し、二つ目は謗法罪についての説明、そして三つ目は法華経を説くべき相手についての指導です。
特に興味深いのは偈文の視点や力点が長行の内容とは異なり、私たちが住む三界という「火宅」の恐ろしさを強調している点です。この偈文は、現代のオカルトやホラー映画のような戦慄を与える描写で満たされており、魑魅魍魎が跋扈する恐ろしい世界を描いています。これは、仏教の経典にしては異例の内容と言えるでしょう。
私は、ギブアップしましたが、他の方はどんな解説をしてるかな?と興味がわいたので、ちょっと調べてみましたが、あまりピンとくる文章はありませんでした。ただ、たった一つ、紀野一義さんが、『法華経の風光』の中で、こんなことを言ってるんです。
"「燃える家」の中には、子供たちには見えないけれども、すさまじいものどもが住みついている。その様は平楽寺本「『妙法蓮華経並開結』平楽寺書店」で実に四頁にわたって描写されている。私は最初に法華経を読んだ時、どうしてここまで執念深く描写しなくてはならないかと素朴に疑問を持ち、嫌悪感をさえ抱いたものであった。しかし、五十四年の人生を生きて来た今日、四頁くらいではとうてい人間の地獄図絵を描きつくすことはできないなという感慨を抱くのである。一見きれいそうに生きている人間どもが、その内心にいかにうす汚いものを抱いて生きているか、人生のどん底まで行って来た人間にはよく見えるのである。今では私は、法華経の作者はこの場面をもっと凄惨に十数頁にわたって描いておいてくれたらよかったなと思うものである。
この四頁は短いけれども「地獄変相図」である。この描写は浄土三部経の広大な「浄土変相図」に相対している。その意味でもこの「譬喩品」という章は貴重な存在である。
「燃える家」は大脳生理学にいう「古い皮質」である。そこにはあらゆる悪と戦いと殺傷の歴史が刻みこまれている。それを人間は一人一人、例外なく持ち、しかも気づかず、あるいは気づかぬふりをし、あるいは直って生きているのである。"
これを読んだら、なるほど、地獄変相図とはうまいこと言うなと感心しました。と同時に、生き地獄に対する、この異常なまでの関心がなんとなく理解できるような気もしてきたんです。法華経という偉大な経典の中に、こういう地獄が描かれていることを、かなり面白いことだと考えるようにもなりました。
この譬喩品の偈文を解説するためには、登場する魑魅魍魎、つまり怪物や悪魔たちを一つずつ詳しく説明し、難解な漢字の意味を解き明かさなければなりません。しかし、これだけで説明が終わってしまうと、実際の凄惨な地獄絵の伝達は難しいと考えました。
そこで、別のアプローチを取ることにしました。「もう一つの燃える家」というテーマを掘り下げることにしたのです。私たちの世界を表面的に見ると何も異常は見えませんが、その裏側には恐ろしい真実が隠されています。まさに燃え盛る家のようなものです。当初は、地球を蝕んでいる「環境破壊」について話すことを考えていましたが、そのテーマは抽象的で現実感が乏しいと感じました。そこで、もっと身近なテーマに目を向け、来るべき「超高齢化社会」について考えることにしました。私たちは皆、火の粉を浴びるか、火に焼かれるかのような近未来の現実に直面しています。
「火宅の譬喩」では、長者が一人であっち側に逃れ、燃え盛る家にいる子供たちに「この家は燃えている」と警告しました。私たちは、この警告を現実の中で捉え直し、本当に何が燃えているのかを問い直す必要があります。仏さまへの信仰や彼岸への憧れは大切ですが、現実的な危機感がなければ、それらはなかなか生まれにくいものです。
高齢化社会という火宅の様相
高齢化社会の問題は突如訪れる天災のようなものではなく、既に進行中です。加えて、子どもの数は歴史的に低下し、教育費の増加や社会的弱者の増加も予想されます。これらの問題は、現代の行政、医療、保険、年金システムに重大な影響を及ぼす可能性があります。
高齢化社会の問題は、単に老人福祉の問題ではなく、全社会的な課題です。将来、私たちはより若い世代が高齢者を支えるために強力なサポートが必要になるでしょう。しかし、現代の若者たちは、学業、いじめ、非行などの問題に直面しています。加えて、将来の介護を担うことになる女性たちは、現在さまざまな社会的課題に直面しています。
この超高齢化社会において、私たちが直面するであろう最大の課題は、心の問題です。私たちは、社会全体が高齢者をどのように扱うか、どのようにして彼らの尊厳を保つかを考えなければなりません。人間は、自然界の他の生物と異なり、弱者や不適応者と共存する唯一の生物です。しかし、合理主義や経済優先主義が、この人間の尊厳を脅かしている可能性があります。
この経をみだりに説いてはいけない
譬喩品の偈文の前半部分では、「三車火宅の譬え」が繰り返され、私たちが生きる世界の恐ろしさとおぞましさが描かれています。地獄変相図のように、私たちの世界がどれほど恐ろしい場所であるかが説かれているのです。そして偈文の後半部分には、長行にはない内容、「謗法」についての詳細な説明がされています。ここでの「謗法」とは、法華経の教えに反することを意味します。この部分では、法華経を謗ることの恐ろしい報いについて徹底的に語られています。
実際に、法華経や日蓮聖人に対して生理的な反発を抱く人もいます。彼らは、法華経や日蓮聖人を独善的、排他的であると捉え、地獄への脅迫と感じていることがあるのです。これは誤解であり、お互いにとって不幸なことです。法華経が謗法の罪を説く態度を単純に好きだとか嫌いだとか言うのは、表面的な解釈で、もっと深い理解が必要です。
「仏教電話相談」で、ある相談者が、宗教団体を辞めることについての相談をした際に、地獄に堕ちると脅されたという話があります。この相談者は、法華経の一節を読まされ、その経文には背信者が受ける恐ろしい報いが書かれていたため、辞められなくなったと語っていました。彼は、法華経が脅迫の道具として使われていると感じ、仏教に対して否定的な印象を持ったのです。これは間違った読み方であり、法華経が説く「謗法罪」は、このような意味ではありません。
法華経の真意は、恐怖を煽ることではなく、人間の心に深く訴えかけることにあります。謗法の話は、人間がどのように行動すべきか、どのような心構えを持つべきかを示唆しています。この偈文の解釈は、単なる文字通りの読み方を超え、より深い洞察と理解が求められるのです。
実際の経文を見ずに、あれこれと論じても、なかなか理解しにくいものです。そこで、ちょっと経文を覗いてみましょう。
譬喩品の偈文は、火宅の恐ろしさを執拗に説きましたが、この法の報いについても、負けず劣らず、執拗に説いております。これは、そのごく一部です。
ガンジス河の砂の数のように数多くの幾千万億劫のあいだ、彼は愚鈍な者となり不具者となる。これがこの経典を捨てた罪果報である。
地獄が彼の遊園地であり、環境の悪い土地(地獄)が住居となり、彼はこの世では常に騙馬や豚や犬や地面を嗅ぎまわる犬の間に暮らす。
人間の姿を得ても、彼は盲人となり、聾唖者となり、白痴者となろう。
また、他人にこき使われて、常に貧乏である。
そのとき、これらの不幸が彼の装飾品である。
また、種々の病気が彼の衣服となり、身体には幾千万億の傷が生じよう。
また、湿疹や疥癬にかかり、さらに白癬や白や病を患うて、悪臭を放つであろう。
個我に関して異端の見解を堅持し、また、彼の憤怒の力は増大する。
婬欲は激しく、彼は常に畜生の門を嬉しむ。(梵文訳)
「もういい加減にしてくれーっ!」と言いたくなる描写が、延々とくり返されております。おそらく、ここだけ読んだら、法華経の品性を疑わざるを得なくなるかもしれませんね。限度を逸脱したかのように、火宅の凄まじさを説き、謗法の恐ろしさを説く。確かに、喩品という章は、一歩読み方を間違えるとエライことになりそうです。しかし、謗法の恐ろしさを説いたあと、突然、仏さまは、
シャーリ・プトラよ、もし余がいま余の経典を捨て去る者の罪を数え上げるとすれば、たとい期を満了するまで数えたとしても、その終りに達することはできない。
そのことを洞察しているので、余は汝に指示しよう。シャーリ・プトラよ、『汝は愚かな人間の前で、このように隠れた経を決して語ってはならぬ』(梵文訳)
という警告を発し、その後は一転して、「しかしながら、~のような人には法華経を説きなさい」と指示を与えるんです。つまり譬喩品の偈文の構成のねらいが、「法華経とはみだりに説く教えではないぞ」というところにあると考えるべきなんです。
法華経の扱い方は、ダイナマイトや劇薬、あるいは原子力の扱いに似ていると言えるでしょう。これらはすべて、適切に使われれば人類に大きな恩恵をもたらしますが、専門家でない人によって扱われると大きな問題を引き起こす可能性があります。法華経もまた、その深遠な教えを理解する「機械」(仏教の理解能力)を持たない人々に語ることは、大きな矛盾や混乱を引き起こす恐れがあるのです。
法華経の方便品第二で、お釈迦さまが三昧から立ち上がり、初めて口にされた言葉は「この教えは難解難入だ」というものでした。
これは、法華経という未曾有の大説法に入る大前提となる重要な言葉です。ただの前提ではなく、この教えの核心を理解するための大きな手がかりとして捉えるべきなのです。
この点を心に留めることが重要です。法華経を学ぶには、その深い教えを理解するための適切な準備と心構えが必要であり、誰にでも簡単に理解できるものではない、というお釈迦さまの教えが、この経典の根底に流れているということなのです。
つまり、法華経という教えは、古今東西、すべての教えの中で、第一に難解な教えだということ、このことを忘れてはいけないんです。
しかし、この大前提の言葉も、方便品を読み終え、次の章である譬喩品の後半にさしかかってくるころになると、もう「第一稀有難解の法なり」ということを忘れてしまうんですね。車なんかでも、免許を取って一、二年すると、つい無謀な運転をするケースがあるでしょ。説く立場の人間が、そのことをコロッと忘れて、気やすく法華経を説いたりし始める。すると、大きな混乱が起きる。お釈迦さまですら、この経典を説くために、四十年以上も、人々の機根が熟するのを待たなければいけなかった。そこを忘れてしまうんですね。
だからこそ、こういう恐ろしい謗法罪を明記して、人々の注意を喚起する……まさに、「法華経の純粋性と、大切さを重視して欲しい」という切なる願いが、こういう過激な表現となったのではないでしょうか。
「原子力というものは、無分別に扱ったら、こんなに恐いんだぞ」というアピールに似てます。仏教史的に言えば、法華経菩薩団への非難、迫害が、この経文に影を落としているなんて言いますが、根本はやはり、大切なものを護ろうとする想いだと考えるべきでしょうね。
そこで、こういう認識に立って、譬喩品の最後の部分を読んでみましょう。
謗法罪のグロテスクさとはがらっと変わって、実に格調の高い美しい経文がつづいております。
しかし、この世に賢明で博識があり、記憶力すぐれ、学殖があり、智慧ゆたかで最高の勝れた「さとり」に進む者があれば、汝はかれらにこの最高の真実を説け。
幾千万の仏に見え、また数えきれないほどの美点を培い、そして信心の堅い人々がいるならば、汝はかれらにこの最高の真実を説け。
勇気があり、常に慈悲の心をもち、この世において長いあいだ慈悲を行ない、そのために生命を捨てる者があれば、かれらのために、その面前でこの経典を説け。
お互いの目的を尊重し、愚かな輩と親しまず、また山林などに満足する人々に、汝はこの素晴らしい経典を説け。
友人に仕え、そして悪友たちを遠ざける、このような仏の息子たちを見るとき、汝はかれらにこの経典を説き明かせ。
宝味か宝玉のように、絶えず仏の戒めを守り、この大乗の経典の習得に専念する、このような仏の息子たちを見るとき、かれらの面前で汝はこの経典を語れ。
怒ることなく、常に誠実で、すべての人間に憐れみ深く、仏を親しく崇める者があれば、かれらの面前で汝はこの経典を会衆の真中で、躇することなく、十分な心がまえをもって、幾千万億の例話を挙げて教えを語る者があれば、汝はこの者にこの経典を示せ。
頭を大地につけて合掌をし、一切を知る者(仏)の存在を悟って探し求め、さらに十方を遍歴して善き教えの言葉を探し求める僧があれば、この大乗の経典を信奉し、しかも他の経典を好むことなく、他経から一詩頌さえも信奉しようとしない人に、汝はこの勝れた経典を説け。
誰かが如来の遺骨を探しもとめて、それを捧持するのと同じように、このように勝れた経典を探し求めて得たときに、それを頭に頂く者があるならば、他のもろもろの経典のことを、いつ、いかなる時も顧慮することなく、愚かな者たちに相応しいローカーヤタ派や他の諸派の経論にかかわり合うことなく、それらを避けて、汝はこの経典を説き明かせ。
経文の奥にひめられた真実
法華経の難しさは、なぜ法華経を説くために方便が必要で、成熟するのに時間がかかるのかという前提を含んでいます。法華経の理解には、この特殊な世界を知ることが重要です。著者自身も、法華経が理解できなくなった時期があり、法華経の本質を探して迷った経験があったそうです。法華経を学ぶ者には、このような状況がよくあるようです。
法華経は、その素晴らしさや、読むことで得られる良い結果、そして功徳について述べられています。しかし、これを読んでも法華経の本質が何なのかはわかりません。西洋哲学の思考方法に慣れた人は、法華経に具体的な実体がないと感じるかもしれません。
例えば、猿が玉葱の皮をむいても中身がないように、法華経を学ぶ者も同様の肩透かしを経験することがあります。若い頃の白隠禅師も、法華経を理解するのに苦労した一人です。彼は法華経を薬の効能書きのように見ていましたが、後に眼を開いて法華経の真の意味を理解しました。彼の経験によると、真の法華は目に見えないが、奇縁で見えることがあると伝えています。
法華経の「難しさ」は、白隠さんの表現に倣えば、
「真の法華を見ることの難しさ」と言えるでしょう。
西洋には「カトリック作家」と呼ばれる文学者がいます。フランスのベルナノス、ジュリアン・グリーン、モーリアック、アンドレ・ジイド、イギリスのグレアム・グリーンなどがその一例です。日本には「仏教作家」という言葉はないのに、「カトリック作家」と呼ばれる人がいることが興味深いですね。遠藤周作、曽野綾子、高橋たか子などが有名です。
特に、「カトリック文学」の最高峰とされるモーリアックの『テレーズ・デスケールー』には驚かされました。神々しい内容を期待していた私は、全く逆の、神の存在が一切出てこない物語に拍子抜けしました。テレーズ・デスケールーという女性が夫を毒殺しようとし、裁判にかけられる恐ろしい物語でした。そして、グレアム・グリーンの『情事の終り』を読んだ時、初めてカトリック作家たちが目指す世界が見えたのです。
あらすじ:
第二次世界大戦の前後、ロンドンを舞台にした物語が展開します。主役はモーリス・ベンドリクス、少し名の知れた小説家です。彼は高級官僚を主人公にした小説の取材のため、ヘンリ・マイルズという役人と知り合い、その過程でヘンリの妻セアラと深い関係を築きます。ヘンリは面白みのない男で、夫婦関係は形だけのものでした。そこからモーリスとセアラの情事が始まり、彼らは互いに深く惹かれ合います。しかし、突如としてセアラはモーリスから離れてしまいます。その理由は、モーリスにも読者にも謎のままです。数年が経ち、ある雨の日、モーリスはヘンリと偶然再会し、再び彼の家に出入りするようになります。セアラとの再会はありますが、彼女は変わってしまっていました。なぜ彼女が変わったのか、その理由は誰にも分かりません。この時、ヘンリはモーリスに心の悩みを打ち明け、セアラが変わった理由を、別の男ができたためだと疑っていました。モーリスも同じ疑念を持ち、嫉妬心から探偵にセアラを調査させます。調査の結果、情事の相手がいないことが明らかになりますが、セアラは病に倒れ、結局は肺炎で亡くなります。ヘンリとモーリスにとって、セアラの死は共通の悲しみとなります。モーリスは、とうとうヘンリにセアラとの関係を告白しますが、セアラの死の意味は依然として謎のままです。
そして、セアラの日記が発見されます。彼女とモーリスが密会していた日、ロンドンがVロケットの爆撃を受け、モーリスが死んだと思い込んだセアラは、神に対して彼の命を救う代わりに永遠にモーリスと別れると約束します。しかし、モーリスは生きており、セアラは苦悩の中で神との約束に苦しむことになります。この日以降、セアラの生活は神との格闘に変わり、最終的には教会への通い疲れから肺炎で亡くなります。この物語は、セアラの突然の「情事の終り」の謎をめぐる、深く感動的な展開を見せるのです。
その日、モーリスとセアラは密会中にドイツのVロケット爆撃に遭い、モーリスが死にかけた瞬間、セアラは神に対して彼を救う代わりに永遠に別れることを約束します。モーリスが生きていたことに気付いた後、セアラの苦しみが始まります。この物語は「神」を描くのに非常に巧みで、神の力がすべての行動の背後に影響していることを示します。神は一度も登場しないが、この物語の中核となる存在です。
このカトリック文学を読んで、著者は法華経についての理解を深めました。法華経の経文の中に法華経の実体を求めるのは誤りで、法華経の真理は特定の状況の中で突然、鮮やかに見えてくるものだと気付いたのです。法華経を説くためには、正しい時期と方法、そして信じてついていく姿勢が必要であることも理解しました。
皆さんの中にも、法華経を読んだけど、薬の効能書きみたいで、どこがいいのかさっぱりわからんという方がいたら、諦めないで、とにかく法華経を読みつづけてください。文底に秘められた、真の法華が、突然、目の前に浮かび上がる日がきますから……その時、ムダに過ごしたと思っていた時間が、すべて意味があったことに気がつきます。そして、仏さまが、この経を指して、なぜ難解難入と強調されたのか、なぜみだりに説く教えではないとおっしゃられたのか、よーくわかってきますから。
信解品しんげほん第四
信解品第四のあらすじ
「三車火宅の譬え」を聞くと、四人の大弟子は、よろこびの声をあげます。舎利弗と同じように、お釈迦さまの真意を理解したからであります。
そこで、彼らは、お釈迦さまがなさったように、自分たちも譬え話でもって、自分たちの気持ちを表現するのでした。
「一人の子供がいました。その子は幼い頃に父を捨てて逃げ、長いあいだ他国を流浪し、やがて五十歳になろうとしておりました。彼は貧しさに苦しみ、衣食を求め、さ迷っているうち、無意識に生まれ故郷に向かいはじめていました。
一方、子供に去られた父親のほうも、子供のことが忘れられず、町から町を探し求めているうち、ある町にとどまり、そこで成功者となっていました。彼はたくさんの財産を見るたび、この財産をわが子に与えることができたらと考えておりました。
ある日、一人のみすぼらしい男が、屋敷の前を通りかかり、屋敷の中を眺めておりましたが、あまりに立派な建物なので、恐くなって逃げ出しました。屋敷の中にいた父親は、ひと目で、この男がわが子であることに気がつきました。そこで、使いの者に連れてこさせようとしましたが、長い間の貧窮のため、すっかり気持ちがいじけている男(わが子)は、どんなひどい目にあわされるのかと、恐怖のために失神してしまう始末です。
このようすを見て、父親は思案しました。そして、もっとも賤しい仕事を与えることで、男を屋敷の中にひきいれ、粗末な小屋に住まわせることに成功したのです。父親は、自分も汚い衣服に身をつつみ、おなじ賤しい仕事をしながら、男を励ましつづけました。月日がたち、やがて、男は立派になっていき、全財産を管理するにふさわしい人間となりました。そこで父親は、たくさんの人々を呼び集め、この男が自分の本当の子供であることを公表しました。そして、すべての財産をゆずることを伝えたのでした」
この譬え話を語り終えると、四人の大弟子(大声聞=声聞乗の教えで修行してきた須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、摩訶目揵連)は、自分たちが声聞乗の教えで満足していたこと、大乗(菩薩乗)の教えを学ぶ者が、自分たちをどんどん追い抜いていっても、もっと先にあるものを求めようとしなかったことを告白します。そういう賤しい心を持った自分たちが、お釈迦さまの大いなる御心によって、気がついたら、一乗の教えという、本当の悟りを与えられていたことに驚き、よろこびを表わすのでした。(長者窮子の譬え)
多くの人々の幸福のために生きよ
物語は、仏教の教えにおける重要な転換点に焦点を当てています。ここで、お釈迦さまが仏教の中の三つの生き方、すなわち三乗が、実は一つの究極の道へと導くための方便であることを明らかにされました。特に、声聞乗の代表である舎利弗に対して、お釈迦さまは彼が未来に華光如来となることを予言し、授記を与えます。これは、誰もが仏になれるという教えの具体化であり、法華経が究極の教えであることの証です。
この背景から、信解品では四人の大声聞がお釈迦さまの前に進み出ます。彼らは長い間僧団の指導者であり、空・無相無作の考え方に従い、この世を実体のない空と捉える生き方をしてきました。しかし、彼らは舎利弗が法華経により未来の仏となることを目の当たりにし、深い喜びに満たされます。
彼らはお釈迦さまに向かって、自らの心境の変化を譬え話を通して語り始めます。この譬え話は「長者窮子(ちょうじゃぐうじ)の譬え」として知られ、法華経の中の七つの譬え話の一つです。特筆すべきは、この話がお釈迦さまによって語られたのではなく、大声聞たちがお釈迦さまに対して語ったものであることです。
彼らは、これまで望んでいなかったり考えてもいなかった偉大な宝玉を得たと表現し、この新たな発見と理解に満ちた心境を、譬え話に託して伝えるのです。この譬え話は、彼ら自身の心の変化とともに、法華経の深遠な教えの理解を促すものとなっています。
実は、この譬え話、ザーッと読んだら、「なるほどな」くらいで終わってしまいます。しかし、本当はものすごく深い話なんです。
一語一語に甚深の意味があり、汲めども尽きぬ深さと思想が隠されているんです。中国の天台大師という方は、「天台学」といって、法華経をもっとも勝れた教えと位置づけ、そこから、すべての仏教を体系化した方です。
天台大師は、全仏教の体系化のために、重要な指針、つまり拠り所とする骨組を、どこに見たかというと、この「長者窮子の譬え」に見ていたのです。なぜなら、この物語には、一番低級な教えから一番すぐれた教えへと移っていく、人間の心のありようが説明されているからなんです。
それでは、物語を追いかけてみましょう。
かつて、幼い頃に家を出た若者がいました。彼は長年にわたり、国から国へと流浪し、貧しい生活を余儀なくされていました。その間、彼の父親は息子を探しに出てきていましたが、息子を見つけることはできず、ある町に定住し、やがて大富豪となりました。しかし父親は、息子のことを一日たりとも忘れたことはありませんでした。
時が経ち、不思議なことに、息子は故郷に戻り、父親の住む町に足を踏み入れました。父親の邸宅の前で、彼は驚くほどの豪華さを目の当たりにし、自分には居場所がないと感じて逃げようとしました。しかし父親は一目で彼が自分の失われた息子だと気づきました。息子が捕らえられると、恐怖に打ち震えて気を失いました。父親は息子の心が傷ついていることを知り、彼に水をかけて目を覚ますよう命じました。
息子は自分に適した仕事を探していましたが、父親は息子を引き留めるために、彼に便所掃除の仕事を提供しました。息子は仕事を引き受け、貧しい小屋で生活しながら働きました。父親はしばしば息子を遠くから見守り、彼に特別な待遇を与えることで、自分の実の子としての位置を与えようとしました。
長い年月が経ち、父親が死に近づいたとき、彼は息子を呼び、全財産を譲ることを発表しました。息子は驚き、深い喜びに満たされましたが、賤しい自己像に苦しんでいたため、依然として貧しい小屋での生活を続け、財産には手をつけませんでした。
父親の死が迫ると、彼は親族、国王、大臣、町の人々を呼び寄せ、息子が自分の実の子であることを明らかにしました。この瞬間、息子は自分の身分が変わり、父親の莫大な財産を受け継ぐことになりましたが、彼は自分が財産を受け継ぐことを望んでいなかったにもかかわらず、深い喜びを感じました。
この物語の中心となるのは、四人の大声聞たちの過去への反省と悔恨です。彼らはかつて、自分たちの教えや理解に満足していたため、他人の幸福や大勢の人々の幸せを軽視していました。この物語では、彼らが過去を振り返り、自身の心の貧しさや狭い見方を悔い改める姿が描かれています。
特に、譬喩品の「三車火宅の譬え」で示されたような、真実の一つの生き方や輝かしい未来への展望から、この章では、明らかに過去への視線が向けられています。彼らは自己の解脱を目標に、小乗仏教の教えに固執していたのです。この小乗の教えは、「自己の解脱のみを求め、他を顧みない」という思想で特徴づけられます。
しかし、彼らが教えを説く立場にあった時、他人には「大勢の人々の幸福のために生きよ」と指導していましたが、実際には自分たち自身にはそのような思いやりが欠けていたのです。この矛盾した行動により、彼らは深い反省に至ります。経文にも彼らが仏の教えに対して無関心であったことや、老齢で碌でなかったことが語られています。
この譬え話は、彼らの成長と変化の物語であり、自己中心的な考え方から脱却し、より広い視野を持つことの重要性を示しています。彼らは自らの過ちを認め、より大きな真実に目覚めたのです。
かつて、経文を熟読する著者の心に、ある種の啓示が訪れた。「これはまさに文学のようだ」と。文学は創造の芸術、しかし、それとはまた異なる、学問という世界が存在する。物語や詩、戯曲を学問の刃で解剖し、その深淵を探る。この仕事は、多くの大学の教授が行う。彼らもかつては創造の情熱に満ちていたはずだ。しかし、時が経つにつれ、彼らはその情熱を失い、学者へと変わっていった。そして、皮肉にも、学者としての地位や名声が彼らに付きまとうようになる。
一方、売れない作家や詩人の人生は、これとはまったく異なる。成功を収めた学者たちは、若き学生たちに創造の重要性を説き、彼らの心に火を灯す。しかし、彼ら自身はもはやその炎を持たない。それでも、学生の中には教授たちの言葉に触れ、創造者の道を歩み始める者が現れる。教授たちは、そうした若い才能を複雑な感情で見つめる。
さて、仏教の教えでは、我々は仏から派遣され、多くの求法者のために数えきれない例話や因縁を語り、究極の道を示す。仏弟子たちはこれを聞き、悟りへの道に専念する。皮肉なことに、大弟子たちは元々「多くの人々の幸福」を考えてはいなかったが、彼らの説法を聞いた菩薩たちはそうした生き方を始める。
仏は、これらの菩薩に対し、「やがて未来世に成仏する」と予言する。仏にとって、社会的地位など重要ではない。例えば、名声を得た大学教授に対し、仏が「全てを捨てて真の詩人になる気があれば、その道を開く」と言ったら、どんな反応があるだろうか?多くは現状に固執するだろうが、中には「本当の情熱を取り戻し、本物の詩人になりたい」と願う者もいるかもしれない。
かつて、仏教の教えが生まれ、広まった時代、小乗仏教はしばしば「自己の解脱のみを追求し、他者を顧みない」と非難された。しかし、これを深く考えると、人間にとって自己の解脱を求めることは自然なことではないか。小乗仏教の生き方を、高いところから見下ろすような立場を取る人が多い。しかし、そうした視点を著者は疑問視する。
実際、仏陀である釈迦ご自身も一時、「自己の解脱のみを求める」時期があったとされている。『律蔵大品』によれば、悟りを開いた後、釈迦は深い真理に到達し、その真理が人々には理解し難いと感じた。彼は、自己の教えが他者に理解されなければ、それは自身にとっての疲労や苦悩に過ぎないと考えた。
しかしその後、梵天という神が降臨し、釈迦に教えの普及を請うた。これに応じ、釈迦は「多くの人々の幸福のために」という思いで教えを広め始めた。この話は、重要な教訓を含んでいる。自己の解脱を追求する人々を単純に利己主義と決めつけ、軽蔑するのは適切ではない。彼らにも、それぞれの苦悩や願いがあるはずだ。小乗仏教を軽んじる人々に対し、彼らが本当に他者の幸福を求めているのかと問いたくなる。
著者は、小乗仏教も大乗仏教も、本質的には消滅していると考える。現代では、それらの区別に意味はなく、残っているのは利害に基づく「便乗仏教」や、思想的な基盤を失った「無乗仏教」のように思える。仏教の教えが、どれほど高尚であっても、他者を尊重しいとおしむ心がなければ、その教えの価値はない。
さて、こういう賤しい心持ちの窮子を、長者である父は、どんなふうに導いていったでしょう。譬え話のストーリーを追っていくと、ものすごくたくさんの紆余曲折が表現されています。詳細に検討していくと、「なるほど、なるほど」と感心するばかりです。天台大師が、この譬え話から、一大仏教体系を構想していったというのもうなずけます。もちろん、そのプロセス(過程)のすべては、長者の深い智慧と、行動力から出ていることを忘れてはいけません。
あらゆる手段で衆生を導く
何十年もの時間を経て、父親が息子と再会する場面から始まります。息子は、父の豪華な姿に圧倒され、逃げ出してしまいます。父は息子を無理やり連れ戻そうとするものの、これは失敗に終わります。ここから、教えや信仰を強制することの無効さが浮かび上がります。そこで父は策を練り、質素な人物を使って息子に接近し、低賃金の仕事を提案します。息子はこれに応じます。この点で、低能力者には彼らに適した教えを用いるべきだという教訓が示されています。しかし、息子は仕事に就く前に、実際の報酬を要求します。これは、宗教心の低い人々には現世的な利益を説く必要があることを示しています。
次に、息子が便所掃除に励む場面があり、父が彼を哀れんで、自らもその汚れた世界に降りていく様子が描かれます。父は卑しい姿で息子に近づき、食物や衣服、生活必需品を提供し、「父」と呼んでも良いと告げます。
この物語は、宗教の本質を、自らを低くし、他者の生活を共有することに見出しています。
この譬え話はまた、四大声聞の大弟子たちの信仰の告白でもある。彼らの悔恨と、長い間抱き続けてきた苦悩が、この物語を通じて表現されている。しかし、物語の結末では、これらのマイナス面が一転し、大いなる喜びへと昇華される。この物語は、単なる経文以上のものだ。法華経は、文学的な要素に溢れ、特に信解品の章はその最高峰に位置する。
法華経の経文は難解であるが、譬え話は面白く、容易に理解できる。一部の仏教学者は譬え話を低次元だと見なすが、その本質的な価値は計り知れない。譬え話の素晴らしさは、そのシンプルさにあるのではないか。
心の、最後の「ひっかかり」が取り除かれる
お坊さんになったばかりの頃、池上本門寺で経典が収められた場所を訪れたことがあります。その大きなお堂の上階には、漢訳された一切経が収められていました。一切経とは、経典のすべて、つまり「いっさい」という意味です。そこに足を踏み入れた瞬間、感動と驚きが混じった「エーッ」という声が自然と漏れました。その経巻の多さには本当に驚かされました。見ただけで頭がクラクラし、圧倒されるほどの膨大な量だったのです。
「一切経すべてに目を通す人はほとんどいない」と聞いていましたが、その場で納得しました。案内してくれたお上人さんが、長い竹竿を伸ばし、「ここが法華経です」と教えてくれた時、法華経八巻はその大きな経典群の中で、まるで山にとりついた蟻のようでした。この一切経の量のものすごさを皆さんにも見せたいと思いました。
仏教の教えが多種多様に分かれ、複雑化している原因は、経典の多さにあると私は感じています。俗に「八万法蔵」と呼ばれるこの多さは、内容が相反することが説かれる現象も生んでいるのかもしれません。一切経を目の当たりにしたことは、仏教の奥深さと、その複雑な問題を身体で感じる貴重な体験でした。
これまで、「法華経は複雑化し、多様化した仏教を統一した教え」と解説してきました。また、「法華経では、これを一仏乗という思想で表現している」とも説明しました。しかし、一仏乗の真の素晴らしさを伝えるのは難しいです。一仏乗は法華経独自の思想と見なされがちですが、他の経典も独自の思想を持っています。例えば、華厳経には華厳経独自の思想が、般若経には般若経独自の思想があります。
「一切経も、法華経の一仏乗に集約されている」と言うと、多くの人が疑問を抱きます。確かに、膨大な一切経と、たった八巻の法華経を比較すると、法華経が重いとは考えにくいです。
法華経を学問の対象とする人と、信仰の対象とする人とでは、ここで考えが分かれます。この分岐点を過ぎると、日蓮聖人を深く愛する人と、嫌う人とに分かれるのです。法華経という一つの経典が、仏教全体を覆い尽くすほど大きく見えるか、それとも単なる一つの経典と見るか。一仏乗を真に理解するためには、このような問題が出てくるのです。
信解品の「長者窮子の譬え」の中に実は、こういう経文があるんです。
長者、つまり父親は、放浪の旅をしている息子(窮子)に偶然めぐり合いました。その時、父親はすぐにも親子の名乗りをあげようとしました。しかし、息子の心が長い流浪生活で、すっかり賤しくなり、そんな名乗りをしても、とても受け入れられないことに気がつきました。そのくらい、息子は人間として、変わり果てていました。そこで、父親だと気づかれないよう、長者は、さまざまな手段(方便)をこうじ、息子に近づいていったというんです。
こうやって、かなり親しくなり、名前までつけてやり、本当の息子のように扱ったというんです。ところが、息子のほうでは、こういう扱いを、自分には分不相応な待遇だと思っていたんです。
こういう心境を、経文では「客作(やとい・かくさ)の賤人(せんにん)」といっています。
外見、あるいは表面上は、恵まれた生活をしていても、心の本音では、「自分は賤しい人間なんだ。もともと宿なしの流浪者で、これは本当の生活ではない、あくまで"お客さま"なんだ」と、思い込んでいたんです。
最近の若者には、ちゃんとした社会人になろうとせず、いつまでも半社会人でいようとする傾向が見られるそうです。そういう状況を表現した言葉に「モラトリアム」という用語があります。客作の賤人も、一種のモラトリアムかもしれませんね。
「自分はもう本物なんだ」と、自信を持って、堂々と一歩を踏み出さなかった。いや、踏み出せなかった……。これこそ、私たちの、最大の欠陥でした。四人の大声聞は、深い反省と、強い自責をこめて、お釈迦さまに対し、この物語を語っています。ところが、長者は、子供の心からいつまでも抜けない、この「賤人」根性にも、辛抱強く、慈愛をもって、つき合ってくれたわけです。二十年も見守ってくれたわけです。
部屋でゴロゴロしてる息子に、「もっとちゃんとしなさい」そう言って、尻を叩いたんじゃないんです。
ただ、ここで間違わないで欲しいのは、尻を叩いたほうがいい人間と、この経文のように、ただ辛抱強くつき合うべき人間を、ごっちゃにしたらダメなんですね。経文には、非常に、興味深い言葉があります。
『汝は常に作す時、欺怠・瞋・怨言有ること無く、都べて汝には、この諸悪の余の作人の如くなるもの有るを見ざればなり。』
おまえはここで仕事をしていて、悪いことも、不正なことも、不誠実なことも、何ひとつしなかったし、傲慢なところもないし、猫被りも一度もしたことがない。今後も決してしないだろう。いずれにせよ、おまえには、他の下男たちが仕事をしているときのような欠点は、何ひとつ見られない。(梵文訳)
つまり、こういう人間だったからこそ、長者は、辛抱強くつき合う道を選んだんですね。人間が本物になっていく時、最後に越えるハードルは、人さまざまだと考えるべきなんです。画一的にとらえたらダメなんですよ。経済的な問題さえ越えれば、それでいい人もいるでしょう。仕事のポストさえ与えられたら、それでいい人もいるでしょう。しかし、誠実で、正しくて、ひた向きで……、こういうタイプの人間で、心の内部に、どうしても越えられない、最後の「ひっかかり」を持ってる場合、この「ひっかかり」は、小さそうに見えて、実は、ものすごく大変で、ものすごく厄介なものなんです。
その大変さ、厄介さを本当に知っていて、どう接すればいいのか。どんな手段をもって、導いてやればいいのか。こういうことを本当に知っているのは、お釈迦さまだけだったことがハッキリわかりました。四人の大声聞は、自分たちが理解したことを、物語を借りて一生懸命お釈迦さまに伝えようとしたわけなんです。
そして、私たちは、お釈迦さまが深く危惧なさっていた、最後の、最後の「ひっかかり」が、今、やっと取れました……と、表明したわけなんです。
まあ、私たち凡人だったら、心のひっかかりの一つや二つ取れても、まだうんざりするほど残ってるでしょう。しかし、大弟子と言われる人(声聞)たちには、まさに最後の一つだったわけです。
実は、この最後のひっかかりが取れるというのは、かなり破天荒な出来事だと思うんです。人間って、妙なところがあって、心の中で、最後の「ひっかかり」が、孤軍奮闘、最後の戦いをしてると、なんとなく同情したり、肩入れしたくなったりするんですね。そして、ますます「ひっかかり」に執着したりするところがあるようです。
だから、これがスカーッと取れた時は、一瞬、頭の中が真っ白になるんじゃないでしょうか。そして、「あれ、何だろう。いったいどうしたんだろう」となるんだと思います。それから、急に、「ヤッター」って感じになるんじゃないですか。
『われ等は、本(もと)、心に悕(ねが)い求むる所有ること無かりしも、今、法王の大宝が自然(じねん)にして至り、仏子の応に得べき所の如きものは、皆已に、これを得たり、と説くなり。』
この経文は、まさに声聞たちの、「ヤッター」という歓声に似てませんか。動脈硬化的な、二乗のこだわり法華経という教えが、はじめて取り除いたということなんですね。譬喩品においては、仏さまのほうから、「三車火宅の譬え」として、一仏乗が説かれました。あの譬え話は素晴らしい教えでした。しかし、信解品における、この「長者窮子の譬え」は、素晴らしいというより、どちらかというと、感動的というのがピッタリくるようです。
魅力あふれる四人の高弟たち
さて、ここで、経文からちょっと離れることにします。法華経の解説を離れて何をするかというと、この信解品に登場する、四人の高弟(大弟子・大声聞)について話してみたいんです。お釈迦さまと、そのおそばにいらっしゃった、お弟子たちの間には、素晴らしい逸話がたくさん残っています。
ところが、日本のように宗派仏教になってしまうと、これらの逸話が、かえりみられないんです。反対に、小乗、あるいは劣った教え、そういうものを代表する人物として、不当に軽く見られたりしてるんです。私自身、お坊さんになりたての頃、宗門の大学で勉強していた頃、お弟子たちの話なんか、まるで知りませんでした。ところが、ある時期、原始仏教といって、小乗の経典を、徹底的に読んだことがあるんです。
そうしたら、お釈迦さまの素晴らしさ、お弟子たちの素晴らしさに、パッと眼が開いたことがあったんです。宗派仏教だけを学んでいたら、おそらく死ぬまで知らなかったかもしれませんね。それ以来、お釈迦さまの十大弟子は、私にとって、大切な尊崇の対象になっています。と同時に、小乗という言葉が、大嫌いにもなりましたね。
信解品に登場し、お釈迦さまに向かって、長者窮子の譬え話を語った、四人の高弟とはどんな人だったでしょう。経文の出だしを読み返してみてください。須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、摩訶目揵連……四人とも、お釈迦さまの十大弟子に入っております。では、一人ずつ話していきましょう。
その前に、ひとつお断りをしておきたいんですが、昔、日蓮宗の先輩僧から、「我々の宗祖・日蓮聖人さまは漢訳の経典を読まれた方である。その後につづく僧も、皆、漢訳の経典で学ばれた方ばかりだ。それなのに、最近、舎利弗のことをサーリプッタとかシャーリ・プトラなどと片仮名で読む人間がいる」と、あてこすりを言われたことがあります(サーリプッタはパーリ語、シャーリ・プトラはサンスクリット語の片仮名読みです)。
言いたいことの趣旨はわかりますが、私としては、舎利弗と漢字で表現すると、どうしても、脳裏には、中国人のイメージしか浮かんでこないんです。中国の町を、中国の服装をした、中国人の僧が歩いているイメージしか浮かんでこないんです。ところが、サーリプッタと表現すると、初めて、あの灼熱のインドが脳裏に浮かんでくるんです。そして、色の黒い、目鼻だちのはっきりした、インドの僧が、インドの言葉を話しているイメージになるんです。そういうわけで、ここではインドの発音に近い、片仮名の読み方で統一させてください。
スブーティ(須菩提)
スブーティ(サンスクリット語もスブーティ)は「解空第一」、つまり仏教の「空」の教えを、誰よりも体得していたお弟子として讃えられています。また、「無諍第一」、つまり決して他人と言い争いをしない人、あるいはまた、「被供養第一」、信者の供養を受けるに一番ふさわしい人などとも讃えられております。
「空」に徹していた……、こんなふうに言うと、ものすごく厳格で、人間離れしたイメージがわいてきがちです。なんというか、仏教語が持っている短所かもしれませんね。そんなことはないんですよ。「空」に徹するというのは、徹底的にこだわりを捨てること、つまりあらゆる執着を離れることです。だから、ばかみたいに無頓着だった人と考えてもいいんです。よくいますよね、あまりにも浮き世ばなれし過ぎていて、「バッカみたい」と言われるような人。
この方は、祇園精舎を仏教教団に寄進した、スダッタ長者(アナータピンディカ)の甥にあたる人です。そして、その祇園精舎の落慶式に参列した時に、お釈迦さまのお話に感激して出家をした方です。出家した頃は、〝自分はいいところの人間〟という意識が強く、仲間と衝突していたみたいですね。そこで、ある時、お釈迦さまは、スブーティに、当分の間、人に話しかけてはいけない。まわりの者もスブーティに話しかけてはいけないと命じられたそうです。現代の「いじめ」みたいな状況ですね。こういう辛い状況のなかで、スブーティは、本気で自分を見つめなおす修行をしたといいます。そして、悟ったのが、「空」の悟りだったといわれております。面白いのは、無執着を生きた人ですから、華々しい業績とか、波瀾万丈の物語などがあんまりないんです。ただ、スブーティの逸話として、常に引用される話がありますから、それをお話ししましょう。
お釈迦さまは、お悟りを開いてから八年目に、天界にのぼられ、亡くなられたお母さま(マーヤー夫人)に、お説法をされたことがありました。百日間ともいわれております。下界では、お釈迦さまの長期不在のため、お弟子の中には、心配や動揺があったようです。
やがて、お釈迦さまが天界から帰ってくることになり、誰もが我れ先にと出迎えに行こうとしたというんです。この時、スブーティは霊鷲山にいて、法衣を繕っておりましたが、お釈迦さまが帰ってこられると聞いて、自分も出迎えに行こうと立ち上がったといいます。しかし、二、三歩あるいて、ふと、考えたんですね。
「わたしが、これから拝もうとする仏とは、いったいどこにいらっしゃるのだろうか。一切のものは永遠ではない。すべては因縁によって生滅する仮のものである。一切は空でしかない。だとすれば、世尊のお姿も、地・水・火・風・空が寄り集まってできたものではないか。つまり、大地も、流れる水も、燃えさかる火も、吹く風も、大空も、どれ一つをとっても世尊のお姿でないものはない……」。
スブーティは、こう考え、また坐りなおし、法衣を繕いつづけたといいます。すると、地上に降り立ったお釈迦さまのお姿が、彼の心眼にあらわれたそうです。そこで、スブーティはこのお姿に礼拝をしたといわれております。
一方、お釈迦さまをお出迎えした、たくさんの人の中で、先頭は、神通力を使って天空を駆けたウッパラバンナーという尼僧でした。彼女は、得意満面で礼拝をしましたが、お釈迦さまは笑いかけながら、「残念だったね。お前が出迎えた私は仮の姿だよ。私の本当の法身を最初に出迎えたのはスブーティだよ」とおっしゃったという逸話があります。
また、こんな逸話も残されております。マガダ国の王、ビンビサーラ王は、お釈迦さまに深く帰依しておりました。ですから、仏弟子が自分の国にくると、いつも喜んで供養していたということです。王は日頃から、スブーティという、一風変わったお弟子の評判を聞いていましたが、ある時、その本人がやってきたんです。王は一目見るなり、このスブーティがすっかり気にいってしまったんですね。そこで、「いつまでも自分の国に滞在して、人々に説法をしてください」と頼んだそうです。そして、それにはまず、住む所を作らなければなりませんから、家来たちに、「大急ぎで小屋を建てよ」と命じたんです。ところが、政務に忙しい王ですし、もともと忘れっぽい人でしたから、土台ができ、柱が立ち、壁ができた時に、完成したものと勘違いして、スブーティに、「さあ、住んでください」とすすめたわけです。大工さんも大工さんです。「王さま、まだ完成しておりません」と、なぜ言わなかったんでしょう。
スブーティが、「それではありがたく」と礼を言って、出かけていくとビックリです。屋根がないのです。ですから、朝は早くから陽がさんさんと注ぎ、夜は月の光が煌々と射し込んできます。雲は悠々と頭の上を通りすぎていきます。普通の人だったら、「これじゃ困ります」と、すぐかけ合いに行くと思いますが、スブーティは平気な顔をして暮らし始めたんです。
周囲の人々は、「雨が降ったら、あの坊さま、どんなに慌てるか、こりゃ見ものだ」と、うわさし合っておりました。ところが、それっきり雨が降らないんですね。あんまり降らないから、お百姓さんたちは青くなってしまいました。それで、ビンビサーラ王のところへ、「雨が降らずに困っております。どうか、あのお坊さまの小屋に屋根を葺いてください」と陳情したわけです。それで、王は、「あっ、いけない」と気がついて、スブーティに詫び、すぐさま屋根を葺かせたといいます。やがて、雨が降り始め、作物は生き返ったという逸話が残っております。
まあ、このくらい徹底的に、ものごとに無頓着でいられたら、うらやましいかぎりですね。これが解空第一、無諍第一、被供養第一と讃えられた、スブーティというお弟子の話です。「あいつはできる。まるでカミソリのように切れる」。こういうのが、最高だと思ってる人は、スブーティのような生き方、見なおしてみませんか。
マハー・カッチャーナ(摩訶迦旃延)
名前の初めに「摩訶」という字がついております。この摩訶、あるいはマハーというのは、「大」という意味です。同じ名前の人が複数いたりすると、その中でも、「一番偉大な〜」という表現で、この字をつけたりするんです。
このマハー・カッチャーナ(サンスクリット語ではマハー・カーティヤーヤナ)というお弟子は、「論議第一」「広説第一」と讃えられております。仏教の教えは、そのまま理解できる人もいますが、「もうひとつよくわからない。わかったようだけど、今ひとつハッキリしない」という人のほうが多いと思われます。
こういう人には、噛み砕いた解説というものが必要です。お釈迦さまの教えを、もう一度、わかりやすく解説してあげる、こういう能力においては、この人に勝るお弟子はいなかったということなんです。
カッチャーナは、アバンティ国のマッカラカタ村に、バラモンの二番目の男の子として生まれています。小さい頃から、神童といいますか、非常に頭の良い子供だったようです。父親は、バラモンとして学問の深い人で、チャンダパッジョータ王の相談役を務めるような有力者でもありました。そういう家系ですから、お兄さんも優秀で、長い間諸国を歴訪し、学問をおさめる生活などをした方なんです。彼は家に帰ってくると、父親に頼み、たくさんの人を集めて、その大衆の前で勉強の成果を披露したことがあったんです。この時、ナーラカ(カッチャーナの幼名)も、兄の話を聞いていたんです。
ある時、父親が、「お前も、兄さんにまけないよう勉強してもらいたい」と言ったそうです。すると、ナーラカは、「わかりました。ではお父さん、もう一度たくさんの人を集めてください。兄さんの説いた教えを、そのまま説いてみせます」と答えたといいます。そして本当に、たくさんの聴衆の前で、よどみなくすべての教えを伝えたそうなんです。まだ七歳だったといわれてます。
「なんと賢い子供なんだろう」というので、集まった人々は、感心するやら、感心を通りこして呆れるやらだったわけです。ところが、このあまりに賢いことが禍になってしまいました。年の離れた兄のほうは、心中おだやかではありません。自分の地位も名声も弟に奪われてしまうと危惧したんです。それで、よからぬことを計画し始めたわけです。父親は、兄の計画をいち早く察し、ナーラカを、山中に住むアシタ仙人のところへ連れていきました。そして、わけを話し、アシタ仙人の弟子にしてもらったということです。
このアシタ仙人という人は、生まれたばかりのお釈迦さまを見て、涙を流したといわれる仙人です。「どうして泣くのか」と聞かれた時、「この赤ん坊は、やがて世を救う仏陀となられる方です。ところが、私は、このように年老いております。仏となられた姿も、その教えを聞くこともできないと思うと、それが悲しくて泣くのでございます」と答えた人です。
アシタ仙人は、ナーラカに、「お前は髪をそり、出家して仏法を修行せよ。そうすれば、自らを救い、他の者たちを救うこともできる」と言いきかせていたわけです。そうして、死んでいったんですね。ですから、ナーラカには、仏陀とか仏法というものは、頭の中に、強烈にインプットされていたと考えたほうがいいでしょう。しかし、この当時、ナーラカには、正しい法を求めようとか、仏の教えに帰依しようといった気持ちはなかったようです。むしろ、金銭や名声などに執着していたようです。
まあ、こうしてナーラカは、マガダ国において、素晴らしい賢者として生活していたわけです。ところが、ある奇縁があって、お釈迦さまの弟子となるのですが、それはこういう出来事だったんです。
バーラーナシーの近くに、人の住まない古城があって、そこの塔に偈文が彫られていました。しかし、その字はだれも判読できなかったんです。ただ、言い伝えでは、この世を救う仏陀が出現した時、その字が読めるようになるということなんです。その頃、お釈迦さまが、お悟りをひらかれ、人々にありがたい教えを説いているといううわさが、口々に伝わってきました。そうすると、人々は、「あの偈文が読めるかもしれない」と古城に集まってきたわけです。皆でウンウンやってましたら、不思議なことに、偈文が解読できたんです。
この世で最も自在な者とは誰ぞ?
染とは何か。無垢とは何か。
愚者とはいかなる者ぞ。流される者とは何者ぞ。
いかなる者を智者と呼ぶか。
解読はできたけれど、意味がさっぱりわからない。それに、文章がぜんぶ問いかけになっております。そこで、学問のある人たちが引っ張り出されたわけです。ところが、誰一人として、満足のいく説明のできる人がいない。
やがて、町の人々は、ナーラカの聡明なうわさを聞いて、彼をたずねてくると、この偈文の意味を聞いたんですね。ところが、さすがのナーラカにもさっぱりわかりません。困ったなと思っていましたが、うわさに聞いたお釈迦さまならこの難問が解けるかもしれないと考え、お釈迦さまをたずねて行くんです。ところが、最初は、お釈迦さまがあまりに若いので、「こんな年若い僧に答えられるはずがない」と引き返したんですね。しかし、考え直して、またたずねて行ったわけです。そして、お釈迦さまに、この偈文の意味を問いますと、お釈迦さまは即座に、こう答えられたんです。
自在の王とは他化自在天魔。
これに染められて 惑わされるを 染者と呼ぶが
一方で 他化自在天魔が いなくても
自分で迷う者もいる。
これこそ愚者で 暴流に住む
暴流の流れを 食い止めて
滅し尽くすを 智者という。
この言葉を聞いて、ナーラカはお釈迦さまの偉大さを知り、お弟子となったと言われております。彼には、ずば抜けた能力がそなわっておりましたから、やがて、教団の中でも人々の尊敬を受ける僧侶となっていきました。ナーラカの姓はカッチャーナだったので、人々はマハーをつけ、彼をマハー・カッチャーナと呼んで尊敬したということです。お釈迦さまも、「わが僧団の中で、わたしが説いた教えの真意を、よく理解し、ほかの者のために、わかりやすくかみくだき、そして説き広める、その第一人者は、マハー・カッチャーナである」と言われていたんです。
お釈迦さまの教えを、遠く辺境の地に布教して歩いた方で、そういう生活の困難さや、不自由さ、あるいは美しい逸話などがいっぱいあります。
マハー・カッサパ(摩訶迦葉)
マハー・カッサパ(サンスクリット語はマハー・カーシャパ)は、「頭陀第一」と讃えられているお弟子です。以前も話しましたが、お釈迦さま亡きあと、仏教教団を指導していった人です。そして、結集を開き、正しい教えを後世に遺すことに貢献した人でもあります。
ところで、この方が勝れていたという、「頭陀」とは何でしょう?
これは「仏弟子の修行」のことなんです。ですから、頭陀第一というのは、頭陀行を実行することにおいて、この人にまさる者はいなかったという意味なんです。そこで、マハー・カッサパの人となりを知るため、十二条におよぶ頭陀行を説明しておきましょう。
一:人里離れた山林に住む。
二:乞食によって生活をする。
三:家の貧富に関係なく乞食をする。
四:一日に一食しか摂らない。
五:鉢の中に与えられた量だけで満足する。
六:食後は飲食をしない。
七:ぼろで作った衣を着る。
八:三衣以外の衣服を所有しない。
九:墓場に坐る。(坐禅を組む場所)
十:樹の下に坐る。
十一:空き地に坐る。
十二:常に坐っていて、横にはならない。(寝る時も横にはならない)
これらの頭陀行を、カッサパは誰よりも厳しく守りつづけた人なんです。人なみはずれた意志の力と、仏法に対するひたむきさがなければ、おそらくできなかったでしょう。ただし、お釈迦さまは、お弟子に対し、怠けたり、快楽に溺れることは禁じられましたが、かと言って、極端な苦行を勧めた方ではありません。そこで、ある時、カッサパに向かって、「もう頭陀行はやめて、ほかの僧たちのように堂の中に住んだらどうか。お前も年をとったことだし」とおっしゃったことがあったんです。すると、カッサパは、「世尊よ、私は頭陀行が楽しいのでございます。一度たりとも苦しいと思ったことはございません」と答えたといいます。
こういう生活をしていますから、ボロボロの衣に、髭ぼうぼうのみすぼらしい姿をしているわけです。それに、常に山林で暮らしておりますから、仏弟子の中には、名前は知っているが、顔を知らないという人間もいるわけです。ある時、お釈迦さまがお説法をしている場所に、カッサパが入ってきたことがあったんです。聴衆は、「なんだいあれ」という感じで、ひそひそ袖を引っ張っては、目くばせをしています。すると、お釈迦さまは、いち早く聴衆の心を察したのでしょう。「マハー・カッサパよ。よく来た。さあ、ここへ」と言って、自分の隣を指さしたといいます。
また、カッサパは、托鉢に出る時、貧しい家を選ぶことが多かったともいわれております。ある時、一人の老婆のところへ出かけたそうです。この老婆は、極貧の老婆で、身寄りもなく、町で拾ってきたゴミくずを集めて、なんとか雨露をしのいでいるようなありさまでした。今なら、さしずめ、ダンボールの家に住むホームレスのような生活です。老婆は、他人さまが捨てた、米のとぎ汁を集めて、なんとか生きのびていたんですね。
そこへ修行僧が現われ、托鉢のため食を乞うたわけです。老婆は驚いて「私は、このようなあばら屋に住み、着るものも、食物もないありさまです。布施をしたくても何もありません。せっかくおいでいただきながら、お断りする悲しさをお察しください」と泣き泣き言ったんです。すると、カッサパは、声を励まして、こう言ったということです。
「老婆よ、布施をしたいという気持ちは、すでに貧乏ではないぞ。それに、申し訳ないという慚愧の心は、法衣を着けている人とおなじである。老婆は、すでにこの二つを持っているではないか。もう決して貧乏ではないぞ」
この言葉を聞き、老婆は夢かと喜びました。そして、欠けた瓦のくぼみに残っていた、米のとぎ汁をカッサパに捧げたんです。カッサパは、この半分腐った、酸っぱいとぎ汁を、「おお、甘露、甘露」と言って飲み干したということです。
この老婆が死んだ時、カッサパは懇ろに弔ったといいます。老婆は生前に、布施の喜びを知ったため、やがて忉利天に生まれ変わったといわれております。
マハー・カッサパは、「清貧」そのもののような人ですが、仏弟子になる前は、どうだったのかというと、これがおよそ「貧」とは無縁な人だったんです。インドは貧富の差が激しいといわれます。貧しい人間は、とてつもなく貧しいが、反対に、金持ちは桁違いに金持ちだと。実は、カッサパの生まれた家は、大富豪の家であり、カッサパは、その跡取り息子だったんです。それで、この家が、どのくらい金持ちだったかというと、その財産は、マガダ国のビンビサーラ王よりも多いといわれてたんです。
大邸宅の中にある、ピッパラ樹(菩提樹)の下で生まれたので、ピッパリと名づけられたそうです。ピッパリにはさっそく四人の乳母がつき、最高の養育スタッフが揃えられました。国中の学者、バラモンが邸宅に迎えられるわけです。両親にすれば、大金持ちの跡取りにふさわしい人間になってほしかったのでしょう。
ところが、周囲が、ピッパリに、財産や名誉を与えようとすればするほど、この子は、そういうものから遠ざかりたがったといいます。シッダルタ太子であったお釈迦さまと、よく似ております。さて、こういう状況になると、どこの親も同じで、美しい嫁を迎えれば、現世に執着もおきるだろうと考えたんですね。そこで、評判の娘を、次々と連れてくるわけです。ピッパリは困り果てて、一つの計画を思いついたんです。それは、純金で美しい娘の像を作らせ、この像よりも美しい娘がいたなら、その時は、嫁に迎えましょうと約束したんです。
両親は、大勢の人に命じ、美しいと評判の娘を、国中から連れてこさせました。しかし、この純金の像の横に立たせると、だれも、やはり見劣りがするわけです。ところが、こういう嫁騒動を、あるバラモンが耳にして、面白いことを考えついたんですよ。この純金の像を、美しい台に乗せ、花で飾り、香で焚きしめ、街中をねり歩いたんです。「さあさあ、娘さんたち、この像に願いごとをすると、どんなことでも叶えられます。しかし、自分で拝まなくてはいけません」と告げさせたんです。娘たちは家から出てくると、この金無垢の像に願いごとをするわけです。それを、ジーッと観察しながら、美しい娘を探したんですね。こうやって、町から町、村から村と行列を進めましたが、なかなか見つかりません。ところが、隣の国まで来た時、大勢の娘にまじって、一人の娘が、熱心に拝んでいる姿が、バラモンの目に入りました。この娘の美しさは格別で、さすがの金無垢の像も色あせたといいます。それで、そっとあとをつけていくと、ピッパリの家にまさるとも劣らない大富豪の娘だったんです。
こうして、ピッパリは、この娘を妻に迎えることになったのですが、さて、この娘が、金無垢の像に込めた願いというのは何だったのでしょう。実は、彼女も、ピッパリと同じように、現世の執着を離れ、真実の道を歩きたいという願いを持っていたんです。二人は、親を安心させるため、夫婦になりました。しかし、お互いの心を理解していたため、いつか修行生活に入ることを夢見て、男女関係を持たなかったといわれております。
こうして十二年が過ぎ、両親が亡くなると、「今こそ、修行に出る時だ」と決心し、ピッパリは家を出たのです。この時、妻に、「よき師に巡り合うことができたら、かならず迎えにくるから」と言い残したといいます。旅をしながら、ラージャガハに来た時、お釈迦さまが郊外の樹の下で、禅定に入っている姿を見ると、ピッパリは、その姿を見ただけで、この人以外に師はないと直感しました。進み出ると、地にひれふし、礼拝をしながら、「どうかわたしを弟子にしてください」と言ったといいます。感激と、崇拝の念とで、これだけ言うのがやっとだったのかもしれません。
こうしてカッサパ(ピッパリはカッサパ族の出身だったのでこう呼ばれました)は、お釈迦さまのお弟子となったわけです。そして、頭陀第一と讃えられる大弟子になっていったんです。マハー・カッサパの場合、逸話が多すぎますから、いくら話してもキリがありません。
マハー・モッガラーナ(摩訶目犍連)
マハー・モッガラーナ(サンスクリット語はマハー・マウドガリヤーヤナ)は、目連尊者という呼ばれ方をする場合もあります。仏弟子の中では、「神通第一」と讃えられてる方です。神通とは、神通力のことで、今風に表現すると、超能力ということです。こういう能力においては、この人の右にでる者はいなかったということなんです。マハー・モッガラーナは、仏教教団の中では、極めて重要な人物で、サーリプッタとともに、お釈迦さまの二大弟子ともいわれております。仏教の草創期に活躍し、広く教化に力を尽くした人です。
マガダ国のコーリタ村で、モッグラという婦人の子として生まれました。モッグラの子という意味で、モッガラーナと呼ばれました。一方、隣り村のナーラでは、サーリという婦人が、同じ日に、男の子を産んだのです。こちらは、サーリの子という意味で、サーリプッタと呼ばれました。二人は、幼い頃から大の親友でした。ただ、後年の偉大さを偲ばせるように、非常に感受性のつよい子供たちだったようです。
ある時、二人は、お祭りを見に出かけたといいます。ところが、人々の楽しげなようすとは逆に、何かむなしさが突き上げてきます。二人は、お互いに話しているうち、自分たちが、永遠に変わらない真実を求めていることに気がつくんです。そこで二人して、その頃一番有名な修行者である、サンジャヤの弟子になります。そうして、熱心に、勉学と修行に励んだわけです。たちまち二人は、師のサンジャヤの代わりに弟子たちを教えるほどになりました。ところが、二人は、サンジャヤの教えに満足できなかったんです。やがて、どちらからともなく、「このままでは、真の悟りが得られるとは思えない」「誰か、他の、良い師を見つけ、その教えを学んでみたい」「これからは、別々に師を探そう。もし、どちらかが先に、すぐれた師にめぐり合ったら、かならず知らせ合うようにしよう」ということで、新しい師を求めて、二人は旅立ったわけなんです。
以前、この法華経講話で、サーリプッタが、旅の途中、お釈迦さまに出会ったいきさつを話しましたが、サーリプッタは、この喜びを、モッガラーナに知らせます。二人は、そこでサンジャヤのところへ行き、「我々といっしょに、その、お釈迦さまという方のお弟子になりましょう」とすすめます。ところが、サンジャヤは一緒に行こうとはしません。そこで二人は、「それでは仕方がない。しかし、私たちはお釈迦さまのお弟子になります」と言い、「私たちの考えに賛成のものは、一緒に行こうではないか」と仲間をつのったんです。すると、たくさんの修行者が、二人についてきたんです。
この時、お釈迦さまは、二人が大勢の修行者をしたがえ、こちらにやってくるのを見ると、おそばにいるお弟子たちに、こう言ったそうです。「見よ。大勢の者たちを率いてくる、あの二人は、私の弟子たちの中で、最もすぐれた弟子となるであろう」と。
事実、彼らの能力は素晴らしいものでした。と同時に、二人は、まさに絶妙のコンビでもありました。理性が勝って、情緒も安定し、思索型のサーリプッタと、性格が激しく、超能力にすぐれ、行動型のモッガラーナは、まるで車の両輪のように、仏教の教えを広める仕事をしていったわけです。お釈迦さまは、「モッガラーナとサーリプッタは、私の二大弟子である。修行者たちよ、日頃から、この二人に親しみ、近づいて、その行いを見習いなさい。この二人は、修行する者にとって、良き指導者である。たとえて言うならば、サーリプッタはあたかも生みの母のようであり、モッガラーナは良き養育者のようなものである」と言われていたそうです。
ところが、この二人は、悲しいことに、お釈迦さまより先に亡くなってしまったんです。外道の中には、仏教教団が盛んになることを、快く思わない人たちがおりました。彼らは、中でも、豪胆で、頼もしげなモッガラーナを憎み、ある時、刺客を差し向けたのです。この襲撃は、三度くり返されたといいます。一度目、二度目は、モッガラーナも逃げたのですが、三度目の時は、「これも自分の宿業である」と悟り、されるままになって殺されたわけです。この時、虫の息のなかで、モッガラーナは、神通力を使うと、お釈迦さまと、サーリプッタに、別れの挨拶を告げに行ったそうです。サーリプッタも、この時、すでに死の病を持っていましたので、田舎へ引き込み、まもなく亡くなったといわれております。生まれてくる時も、遊ぶ時も、勉強する時も、修行する時も、そして亡くなる時まで、この二人はいつもいっしょだったんですね。
モッガラーナには、この他、お盆行事が起こるもととなる、母親の苦しみを救ったという、有名な逸話もあります。これはまた、機会があったら話すことにしましょう。
法華経を読み進めていくと、まだたくさんのお弟子たちが登場してきます。みなさんにとって、いくらかでも親しみやすい存在になるよう、そのつど説明を加えていきたいと考えています。
薬草喩品やくそうゆほん第五
薬草喩品第五のあらすじ
如来(仏)の慈悲というものは、一切衆生(すべての生きとし生けるもの)に等しく注がれるものである。しかし、人それぞれに能力の違いや、性格、特質の違いなどがあるため、如来が教えを説く時にも、さまざまな違いが出てくるのだと、お釈迦さまはおっしゃいます。そして、それをわかりやすい譬え話で説明なさるのでした。
何日も雨が降らず、乾ききった大地があるとしよう。そこに密雲がたれこめてきて、やがて雨を降らす。雨は地上に平等に降りそそぐが、大きな木は大きな木なりに雨を受け、小さな草は小さな草なりに雨を受ける。そして、それぞれが成長していく。
実は、如来の目でみれば、この人間にこの教えを説けば、どんな功徳があり、どんな変化が起こりうるのか等々……、すべてを見通すことができる。だから、教えを与える時に、さまざまな違いも出てくるのである。しかし、根本的には、如来の慈悲は絶対平等なのである。この絶対平等は、現象界にあるすべての差別相を、如来がありのままに見ることができるからなのだ。(三草二木の譬え)
薬草喩品は法華経二十八品の中では五番目の章です。法華経八巻の中では「三の巻」に入っています。この巻は、薬草喩品第五、授記品第六、化城喩品第七の三つの章からなっています。
さて、薬草喩品の経文に入る前に、今まで学んできたことを、ちょっと振り返ってみましょう。ここまでの法華経の大きな流れ、つまり思想・主張とは何だったでしょう。簡単に言うとこういうことでしたね。
まず、仏の説法には種々雑多の教えがありました。しかし、それら種々雑多な教えも、大別すると、三乗といって、三つの教えに分けられました。だから、仏道を求める者は、この三つの教えの中から、一つを選んで、その道(乗)を進んでいたのです。ところが、この三乗という大別は、仏さまが「真実」というものを、便宜的に分けて説いたもの、あるいは、「真実」を説く前提として、便宜的に説かれた教えだということが明らかにされました。しかし、仏さまは、どうして、こういう面倒な説き方をなさってきたのでしょうか。その最大の理由は、「真実そのもの」は説くことがきわめて難しく、当然、理解することもきわめて難しいからです。そして、その難しさの根底にあるのは、諸法実相(ものごとをありのままにみる)の智慧を持っているのが、実は、仏さまだけだったからでした。
ところが、時と機が熟して、つまり条件が整って、仏さまは長い間の宿願である、きわめて意味深く、特別な説法を始められたわけです。その教えこそ、他ならぬ『法華経』だった……ということでした。
そこで、いよいよ薬草喩品第五に入ることになります。この章をまたざっと概説しますとこうなります。
摩訶迦葉をはじめとする四人の大声聞の説く「長者窮子の譬え話」を聞き終わると、お釈迦さまは、「善い哉、善い哉。迦葉よ、善く如来の真実の功徳を説けり。誠に言う所の如し」と、お前たちの理解の仕方に間違いはない、そのとおりであると認められるんです。そして、仏というものがどれほど偉大な存在であるか、その智慧というものがどれほど深いものであるか、そして、究極のところ、仏の慈悲は「一相一味」であると「三草二木の譬え」を借りて、仏の立場をわかりやすく説いていかれます。
前にも話しましたが、法華経の前半あたりまでは、「一仏乗」の思想と、「授記」というものが大きなウエイトを占めています。ですから、皆さんも、「法華経はなぜ一仏乗、一仏乗と、馬鹿の一つおぼえみたいにくり返すのだろう?」などと思わずに、皆さんなりに考えてみてほしいのです。
実は、種々雑多に分かれ、複雑多岐になってしまった仏教の真っ只中で、「一仏乗」つまり「たった一つの本当の真実」を声高に宣言するのは、選挙前に政治家が「住みよい社会を作ります」と語る選挙演説と同じです。ある意味では、不可能で空虚な公約でもあるんです。皆さんだって、「住みよい社会を作ります」と言われて素直に信じられますか。しかし、政治家が不可能ではないと主張するなら、私たち有権者を納得させるだけの、具体的な施策、具体的な制度、具体的な予算等々を示さないことにはどうにもなりません。そういう説得力のない公約なら、「本当かな?」「絵に描いた餅じゃないか」と思われるだけですよ。
法華経も同じなんです。この一仏乗という、ある意味では、破天荒な大理想が、決して虚言でないことを、仏さまはさまざまな教えによって、私たちに理解させ、納得させようとしているわけなんです。そういうものが、今、私たちが勉強している部分の、法華経の中心テーマなんだと考えてください。この具体的な(施策・制度・予算)などに相当するものが、「仏の偉大さ」や「諸法実相」とか「授記」というものに当たるわけなんです。
さて、法華経は、この「三乗の教えは方便であり、一乗の教えこそが真実である」という主張を、譬え話を使ってくり返しております。これらの譬喩をただ漫然と読むと、「オイオイ、また同じ話かい」になってしまいますが、そうではないのです。それぞれに見る角度が違うことに留意してください。
譬喩品第三の「火宅の譬喩」は、全体の構造をわかりやすく説いた話です。
信解品第四の「長者窮子の譬喩」は、導いてもらう側から見た一仏乗の話です。
そしてこの「三草二木の譬喩」は、導く側である仏の立場から見た一仏乗の話になっています。
またこれから先に出てくる、化城喩品第七という章で説かれる「化城宝所の譬喩」というのは、仏と衆生との関係を、遠い過去からの因縁を込めて、最後の仕上げといった形でくり返したものです。
このようにして一仏乗の教えを多面的に伝えようとしているのが、法華経の前半部分だと考えてください。ですからそれぞれの教えが、どれもこれも大切なわけです。この全体性を押さえないで、ただ「授記」とは何か、「諸法実相」とは何かを説明していっても、何も見えないまま、知識だけは増えたというふうになりやすいんです。
オット、どうしてこういう全体的な話をしたのか、はじめにそれを話しておかなくてはいけませんでした。
実は、この間、将棋のプロ棋士の話の中に、プロとアマチュアの違いについて、こんな言葉を発見したのです。プロ棋士が一番一生懸命考えるのは、序盤から中盤、つまり駒と駒がぶつかり合う前の段階だそうです。なぜならそこの部分が一番大切だからなんだそうです。大局観といって、全体を見渡す作業らしいですね。ところが、アマチュアの場合、一番ウンウン考えるのは、駒と駒がぶつかって修羅場になったところなんだそうです。つまり終盤にさしかかったところらしいですね。一方、プロは終盤になると、考えるというより、直感みたいなもので指していくというんです。
この話、私はすごく面白いなと感心したんです。「全体と部分」これ将棋や囲碁における、プロとアマの違いだけではなく男性と女性の違いにも通じるような気がします。音楽とか、絵画、文学なんかもそうらしいんですが、特に音楽では女性がなかなか一流になれない。後世に名を残すような作品を創れないのは、「全体」を見渡す眼が貧弱だからみたいなのです。音楽という芸術は、ちょっと考えると、きわめて感覚や感性の芸術のように思われがちですが、その実、ものすごく「全体」が大切なんだそうです。女性の作曲家がなかなか育たないというのも、そこに原因があるみたいですね。
しかし……、作曲家ではなく、すぐれた音楽家ということになると女性は多いんですよ。そもそも、音楽学校でも、成績の優秀な生徒は女性で占められているみたいです。ですから、技術とか、学力とか、知能とか、情熱などでは女性が上ということは不思議でもなんでもないんです。文学も、絵画も、哲学も、数学や物理学ですら、大学を卒業する時、成績が一番なのは女性が多いといいます。それなのに、創造の分野になると、どういうわけか、女性は皆無に近くなってしまう。
私は、堅固な「全体」を持った芸術が好きで、他人から「どうしてそんなのが好きなの?」とよく聞かれます。小説なら原稿用紙で四千枚とか五千枚といった作品、俗に言う「大河小説」です。音楽なら一時間半もかかるブルックナーなんかが好きで、終わったらまた最初から聴いたりすることもあります。つまり、一つ一つの文章とか、一つ一つのメロディーを楽しむというより、堅固な「全体」そのものを楽しみたいほうなんです。だから、短い作品でも、「全体」ががっちりしたものが好きですね。たとえば、ポーの短篇とか、音楽で言えばベートーヴェンのような作品です。
オット、日頃の恨みつらみ(?)から女性の悪口になってしまいそうです。もうしわけありません。いえ、女性でも、私が無条件に尊敬してやまない人もいるんです。たとえば『源氏物語』を書いた紫式部です。この方のものすごさは……、ウーン、なんと言うか、ものすごいとしか言えませんね。
仏の智慧とは?
迦葉(かしょう)よ、当(まさ)に知るべし、如来は、これ諸法の王なれば、若し説く所有らば、皆虚しからざるなり。一切法において、智の方便をもって、これを演説し、その説く所の法は、皆悉く一切智地(ちじ)に到らしむ。如来は、一切諸法の帰趣する所を観知し、亦、一切衆生の深心(じんしん)の所行をも知りて、通達し無礙なり。また、諸法を究尽(くじん)して明了にし、諸(もろもろ)の衆生に、一切の智慧を示すなり。
かつて、迦葉と他の三人の大声聞が「長者窮子」の譬えについて話し合い終えた時、お釈迦様は彼らの理解を肯定し、「その通りだ。お前たちの理解は正しい」とおっしゃった。続いて、お釈迦様はこの経文の重要な言葉を語り始められた。「如来とは、あらゆる教えの王であり、嘘偽りはない」と断言されたのだ。如来の教えは、すべての者を究極の智慧へと導く。
「薬草喩品」という章の特徴は、仏陀が自らを「真理を知る者、仏である」と高らかに宣言する場面にある。その宣言の言葉は力強い。これと対照的に、「長者窮子」の章では、「客作の賤人(かくさのせんにん)」というフレーズが登場し、深く根付いた劣等感を示している。これらは鋭く対比されている。しかし、薬草喩品では、同じ一仏乗を説いているものの、それが仏の立場から語られることで、仏の智慧が多角的に展開されている。
一切智地とは、真実の世界、仏の世界といった、根本的な基盤を意味する。この基盤に触れることは、仏の教えの核心に触れることだ。
この概念を理解するために、留学生の例を考えよう。異国の地で文化や風土に悪戦苦闘している留学生がいる。知識だけでは文化の真髄を理解するのは難しい。しかし、同じ日本出身の人に出会うと、共通の土台があるため、すぐに打ち解けることができる。これは、深いレベルで共有されている世界観があるからだ。
同じように、「皆悉く一切智地に到らしむ」という教えは、私たちが内面の深い部分で、仏の世界を共有することを意味する。仏の教えは、表面的な理解を超え、見えない深い部分から影響を及ぼす。それは、知識ではなく、心の奥深くからの共感と理解である。
如来は、一切諸法の帰趣する所を観知し、亦、一切衆生の深心の所行をも知りて、通達し無礙なり……
私にとって、薬草喩品の中で、一番すごいなと思う経文は、実はこの経文なんです。もちろん、このあとに仏の智慧とは何ぞや、仏の力とはどういうものかと、いろいろと説かれておりますが、この経文を敷衍していったものと考えていいんじゃないでしょうか。そこで、ここでは、この短い経文を、できる範囲内で、追いかけてみようと考えているのです。
法華経における「仏の智慧」について考えると、その真髄はなかなか掴みにくいものだと感じます。法華経では、この智慧は直接的に詳細に説明されているわけではないのです。多くの場合、「仏の智慧は非常に理解しにくい」という表現が繰り返されるだけで、具体的な内容には踏み込まれていません。仏教における教えが根本的には一つであるという主張がされつつも、その理由を探ると「仏だけが真理を完全に理解しているから」という結論に戻り、再びその智慧の難解さを強調する形になっています。
薬草喩品では、この「仏の智慧」とは何かを説明しようとしています。ここでは、真理の本質について少し詳しく説明しようという試みがなされていると言えます。しかし、結局のところ、仏の智慧の本質は依然として明らかにされていないのが現状です。このように、法華経は仏の深淵な智慧について触れながらも、その全貌を完全に明かすことはありません。それは、究極的には理解が困難な、深遠なものとして描かれているのです。
言葉を変えれば、諸法実相をもうちょっと説明しておこうという章でもあるのです。
そこで注目しなくてはいけないのは、「一切諸法の帰趣する所を観知し」という言葉と、「一切衆生の深心の所行をも知りて」という二つの言葉が重なっていることなんです。私はこれを、「広さ」と「深さ」の二方向から見なくては理解しにくいと思っています。単純に「知る」とか「理解する」なんて表現しますが、よーく考えてみたら難しいんですよ。
たとえば、西洋人が「知る」という時、それは、横への広がりが大部分を占めているような気がします。社会観でも、芸術でも、横へ横へと広がっていくんですね。一人の人間がいて、そこに家族関係ができて、やが地域社会を作り、国になって……という具合に。その人と人との関係に、政治や経済とか制度とか、文化などが関わっていき、喜びが生まれ、苦しみが生まれる……という具合に。だから、社会の中に、何か事件が起きたら、それがどんどん波紋を広げて、やがていろいろな結果をもたらしていく。
経文で言うと、「一切諸法の帰趣する所」という世界です。
こういう世界を把握することに関しては、西洋の知識は非常にすぐれていると思います。西洋の小説は、登場人物がドンドン多くなって、それに併せて事件も多くなり、人と人との葛藤も複雑になって、容物が次第に大きくなっていく。例えば、トルストイの『戦争と平和』のような作品は、多くの登場人物や複雑な出来事を通じて、この広がりを詳細に描き出しています。
仏教の経典では、このような広がりを完全に理解する力が仏の智慧として説明されています。
仏さまには、こういった「広がりを観知する力」が、完全にそなわっていると経文では表現しております。だから、この人間界に、小石が一つポトンと落ちたら、それが結局、どんな波紋を投げかけ、どこにどんな影響を及ぼすのか、その細部にいたるまで、すっかり見通しているのが、仏さまの智慧だというわけです。
しかし、ここに問題があります。知るという行為は、そういう有機的な広がりだけなんだろうかという疑問です。実は、ここから宗教の宗教たる世界が始まるのですが、知る世界には、もう一つあって、それが「深さ」という世界なんですね。深さといっても、地の底がどうなっているか……、ということではないんですよ。心の世界のことなんです。
著者は、仏像がただ座っていることについて、非常に奇怪な質問を受けました。質問者は、仏像がただ坐っているのを「怠慢」と捉え、観音さまやお地蔵さまのように積極的に動き回るべきだと考えていたのです。この質問は、現代のビジネスマンたちの価値観を象徴しているように思えます。彼らは忙しく活動していますが、それはあくまでも横方向の動きで、精神的な成長や内面的な深さといった縦方向の広がりには気づいていないのではないでしょうか。現代社会の価値観と仏教の教えとの間にあるギャップを深く感じ取りました。
仏さまはただ坐っているようですが、実はこの縦方向の広がりを、縦横無尽に旅していらっしゃる方なんです。横には一歩も動かないが、縦にはものすごい動きをしていらっしゃるんです。その仏さまの「深さ」こそ、尊崇の対象だということに気づくべきなんですよ。「一切衆生の深心の所行をも知りて」というのは、この「深さ」を表現していると受け取ってください。
ですから、「如来は、一切諸法の帰する所を観知し、亦、一切衆生の深心の所行をも知り、通達し無なり」というのは、仏さまの智慧が完全なのは、この横と縦、二つの方向において完全なのだと考えるべきなんです。つまり諸法実相(ものごとをありのままに見る)ということは、常に、広がりと、深さと、二つの奥行があるということです。
さてそこで、話がもう一つ複雑になってきます。薬草喩品では、仏の智慧を少し具体的に説明していますが、私は、仏の智慧を考える場合、この「広がり」と「深さ」だけでは不十分な気がするんです。法華経という経典は、一つの話をして、「ああ、そうなのか」と、その時は納得できても、先へ進むと、「なんだ、大事なことが言い残されていたんだな」と驚かされることがあります。そういうことのくり返しなんですよ。どこまで底が深いのかわからない経典ですからね。そこで、仏の智慧にもう一つの要素があることを、ここで話しておきたいんです。
仏さまの智慧には、「広がり」と「深さ」以外に、実は「次元」という要素もあるんです。実は、ここにこそ、法華経の法華経たる特徴があるんです。法華経らしい世界、ここがわからないと、諸法実相もよくわからなくなるんです。
法華経を通じて、仏の智慧が多次元的であること、そしてそれが我々人間には理解しがたいことを感じ取る。立花隆の『宇宙からの帰還』は、宇宙飛行士たちの内的体験に焦点を当てており、通常のインタビューとは異なる深い話が展開される。宇宙飛行士たちの体験は、地球上の経験とは根本的に異なる特殊なものであること、そして彼らが感じる「地球の美しさ」や「宇宙における神の感覚」について言及する。
宇宙空間と多次元世界の関連性に触れ、宇宙空間が疑似異次元の世界である可能性を探る。人間は現世以外で生きることができず、そのため「神」や「仏」の真の理解は困難であると結論づける。この本から、宇宙空間の特殊性とその体験の重要性を再認識する。
宇宙、その果てしない空間は、我々の地球での日常とはまるで異なる世界です。想像してみてください。そこには「上」も「下」もなく、方角の概念すら失われています。重力の不在は、物体が上から下へと落ちるという私たちにとっての常識を完全に覆します。鉄の塊も羽毛も同じ重さで、重さそのものが意味を持たなくなるのです。時間さえも、地球時間を持ち込まなければ、一日も一週間も区別がつかない曖昧なものになります。そして、その一歩外には、完璧な沈黙と無が広がり、この宇宙空間に足を踏み入れた者を包み込むのです。地球上で当たり前とされているものが消え去った瞬間、人間の心には大きな衝撃が走るでしょう。
さて、私たち人間にとって「上」と「下」の概念は、思考や感情、生活の根底に深く根ざしています。重さと軽さの区別も、私たちの認識にとって欠かせない要素です。しかし、この上下や軽重と無縁の空間で、人間はその思考をどう変えるのでしょうか。宇宙空間へと放り出された人間には、「内側」と「外側」の区別しか残らないと言われています。この変化は興味深いものです。心は、この宇宙の真空の中で、純粋なものにならざるを得ないのです。
法華経の平等観と人間の平等観
仏の智慧には、諸法の帰趣する所を見る眼と、深心の所行を見る眼、そして時空を超えた異相を見る眼がそなわっているということなんです。それが「諸法実相を究め尽くす」という根底にあると考えてください。そこで、この章の中心であります「三草二木の譬え」を読んでいくことにしましょう。【梵文訳】
カーシャパよ、この三千大千世界には、さまざまの色をした、数多くの種類の雑草や灌木や薬草や喬木などが、地上に、あるいは山や渓谷に生い繁っており、また種々の名称をもつ植物の群落があるが、それらの上に大水の満ちた雲が立ちのぼり、三千大千世界のすべてを覆いつくして、到るところに一時に雨を降らすとしよう。その場合、この三千大千世界における雑草や樹木の類は、若くて柔らかい茎や枝や葉や花弁をもつものも、大きく成長した茎や枝や葉や花弁をもつものも、すべて、こうして大きな雲から降りそそいだ雨から、それぞれの力に応じ、また成育の場所に応じて、水を吸い上げるのであるが、それらは同じ雲から降りそそがれた同じ味の水によって、それぞれの種子に応じ、遺伝により、成長して大きくなり、また太くなるのである。さらに、花を咲かせ、実をみのらせるのだ。しかも、それぞれに異なった種々の名称を得る。同じ土地に生えているものはすべて、薬草の群落にせよ、いかなる種子から生えた植物の群落にせよ、それらはすべて同じ味の水によって潤される。まさしく、このように、完全に「さとり」に到達した如来は、この世に出現して、すべてを一様に潤すのだ。大きな雲が立ちのぼって雷鳴を轟かせるように、如来もこの世に出現すると、世間に音声を轟かせて、神や人間やアスラに如来の出現したことを告知するのだ。例えば、大きな雲が三千大千世界のすべてを覆いつつんで雷鳴を轟かせるように、如来は神も人間もアスラも一緒に住む世間に向かって、大声をあげ、音声を聴かせるのだ。
高く澄んだ空に、ひとつの雲がぽつんと現れる。まるで物語の幕開けのように、その雲はじわじわと広がり、やがては空一面を覆い尽くす。そして、雨を降らせ始める。この雨は、大地の草木を潤し、彼らを成長させ、花を咲かせ、実を結ばせる。雨雲も大地も一つだが、雨の恵みを受けて育つ草木にはそれぞれの個性が現れる。人間もまた、この草木のように、仏の教えを各々の能力や素質に応じて理解していくのだ。
仏教の教えの核心、慈悲の精神に触れています。慈悲には差別がないが、その教えを受ける者たちには無限の多様性がある。平等と差別は、本質的には一つでありながら、現象的には異なるものと捉えられる。
仏教は多様で複雑に枝分かれしているが、その根底は一つであるという教え。多様性は表面的な現象に過ぎず、本質を見極めることの重要性を説いている。これを理解するには、法華経の一仏乗という立場が不可欠であり、それが仏の教えの大きな目的の一つである。
一仏乗という概念を通して、「平等を根底にした差別」が育んでいく、「ほんとうの、ほんとうの幸い」への道筋を示しているのです。それは、多様な存在が共に成長し、教えを通じて真の幸せを見出していく過程を物語っているのです。
ここで、ちょっと面白い話をしてみたいと思います。
実は、日本人は、他のどんな民族よりも法華経の影響が強いと言われております。ところが、戦後の日本を見ていると、法華経の一仏乗思想とはおよそそぐわない、一種独特の「平等観・差別観」に振り回されているような気がします。
これは心理学者・河合隼雄さんの一九七六年初版の『母性社会日本の病理』という本からの引用です。皆さんは、この文章をとおし、法華経が説く、本当の平等というものを、あらためて考えてみてくれませんか。
”日本人の平等性の主張は背後に母性原理をもつために、能力差の問題にはできるだけ目を閉じてゆこうとする傾向をもつ。あるいは、時にそれはタブーにさえ近い。それが完全にタブーとなった状態を、筆者は『平等信仰』と呼びたい。ここに、わざわざ信仰などという言葉を用いたのは、能力差という事実は、真に残念なことではあるが、現実に存在するからである。このような断言に対して攻撃を加えたい人もあろうが、(…中略…)能力差の存在の事実を、欧米の教育ははっきりと認めている。それを端的に示しているのは、小学校で落第や飛び級制度があることである。
欧米の小学校に落第制度があることは、最近よく紹介されるのでご存じの人も多いと思う。たとえば、昨年フランス全体で小学校一年生の留年率が三三パーセントというのだから驚かされる。三分の一が落第しているのである。フランスで五年間一度も落第せず、ストレートで卒業した子は二七パーセントのみである。これは日本ではとうてい考えられない数字である。筆者は十年前にスイス留学中、小学校に落第のあることを知って驚いたのであったが、そのとき、スイスの先生はまた日本に落第のないことを不思議がり、「そんな不親切な教育をしてもいいのか」と言われたのが、私には非常に印象に残った。能力差の存在を当然のこととすると、能力も無い子を無理に進級させるのは不親切であると考えるのであろう。”
また、日本人の平等意識の病理を分析しながら、こんなことも言われております。
”われわれ「日本人」の平等信仰は非常に根強いので、すべての人間は平等の能力を持って生まれていることを無意識的に前提としている。そこで学力差が生じてくると、その差をそのままその人間の存在価値にまで拡大してしまうのである。差が無い筈なのにあるということは、本人の努力が足りないとか心がけが悪いと見なされる。これでは下積みになったものはたまらない。平等信仰と一様序列性が結びつくとき、実に多くの人に、みじめさや劣等感コンプレックスをもたせることになる。
生徒に劣等感をもたせないようにと教育者で注意する人は多い。しかし、自分が劣等であることを認識することと劣等感コンプレックスをもつことは同じではない。"
どうですか?実に根の深い問題でしょう。法華経と対照しながら、皆さんは、皆さんなりに考えてみてください。
如来を名で呼んではいけない
お釈迦さまは「三草二木の譬え」をとおして、こんなことを言われました。「仏の教えは、聞く人によって、その結果にさまざまな相違が現われる。しかし、根源的な部分では、仏の教えは平等である。そのような平等を真に理解すること、それを一仏乗と言い、仏の唯一絶対の立場なのだ」と。こうして、仏の目から見た、あるいは仏の立場から、平等と差別の意味が説明されたわけです。本当の平等とは、差別の向こう側にある、もっと深く大きな世界だというわけでした。お釈迦さまは、この譬えを説き終わるとすぐこのような言葉を出されているんです。
迦葉よ、当に知るべし、如来も、赤、また、かくの如し。世に出現すること、大雲の起るが如く、大音声をもって、世界の天・人・阿修羅に普遍せしむること、かの大雲の、遍く三千大千国土を覆うが如し。
そしてさらに、仏というものは、威風堂々とこういう宣言をするのだと言われます。
大衆の中において、しかもこの言を唱う『われは、これ如来・応供・正遍知・明行足・善逝・世間解・無上士・調御丈夫・天人師・仏世尊なれば、未だ度らざる者をば、度らしめ、未だ解らざる者をば、解らしめ、未だ安んぜざる者をば、安んぜしめ、未だ涅槃せざる者には涅槃を得せしむ。今世・後世を如実に、これを知るをもって、われは、これ一切を知る者・一切を見る者道を知る者・道を開く者・道を説く者なり。汝等、天・人・阿修羅衆よ、皆応にここに到るべし、法を聴かしめんがための故なり』と。
また、こういう表現もされております。
唯、如来のみ有りて、この衆生の種と相と体と性と、何の事を念じ、何の事を思い、何の事を修し、云何に念じ、云何に思い、云何に修し、何の法をもって念じ、何の法をもって思い、何の法をもって修し、何の法をもって何の法を得るや、ということ、とを知ればなり。衆生が種種の地に住せるを、唯、如来のみ有りて、如実にこれを見、明了にして無礙なり。
仏さまというものは、「わたくしのような若輩ものが、こういう高い席からお話ししますこと、まことに恐縮でございますが……」といったしゃべり方はしないんです。「われは何々である。われはこういう者である……」と、自分を宣言するのだというのです。それは、真に悟った者だけが、卑屈ではなく、もちろん傲慢さでもなく、堂々とした態度で、言葉を発し、教えを説くことができるという意味でもあるんです。仏さまとはつくづくスゴイもんだなと感心しませんか。
実は、仏さまの偉大さについてなんですが、仏教を学ぶ人たちで、意外と、わかっているようでわかってないことがあるんです。
私自身の恥をさらすようですが、学生の頃、仏典を読んでも物足りない時期がありました。『法句経』のような経典を読んでいると、なんだ単なる修身道徳じゃないかと思えてしかたがなかったんです。
それまでは、哲学書の、あの難解な言い回しに慣れてたので、その落差がよけいに大きかったんですね。
特に、『六方礼経』だったと思います。お釈迦さまが、人々の生活に即して、具体的な指針を説かれると、誰もが無条件で、お釈迦さまに帰依するシーンがあったんです。私はこれを読んでいて、こんな当たり前なことで、こうまで頭を下げるとは、インド人というのは、よっぽど単細胞か馬鹿かと腹を立てたんです。今、思い出すと顔が赤くなりますが……。そして、この軽悔(けいぶ)の念は、ずっとあとまで残ってたんです。ところがある授業で、学生の一人が、私が感じたと同じことを、先生にぶつけたことがありました。この時、先生は苦笑いいしながら、
「経典を文字として読むからそうなってしまうんだよ。たとえば、君がタイムマシンに乗って、お釈迦さまの前に出たと想像してごらん。本物の、本当のお釈迦さまの前だよ。どうなると思う。お釈迦さまの顔を見ながら、そのお声を聞くという体験が、どのくらい強烈なものか……言っとくが、お釈迦さまは日本語はしゃべらないよ、だから、『今日はいい天気だな』とか『ああ、腹がへったな』というインド語かもしれん。しかし、どんな言葉でも関係ないな。我々は地に平伏して頭を下げるに決まってる。お釈迦さまという方は、半径五メートル内に入ったら、誰でもそうなってしまう方だと思う」
こういう趣旨の返答をされたんです。私自身、この話を聞いて、目からウロコが落ちるような気がしましたね。「そうか、お釈迦さまの言葉が経文なんだ。お釈迦さまが説かれたからこそ、経典というのだった。あれは文字というより、お釈迦さまなんだ」と気がついたんです。文章として読み、文章としての内容を吟味する、そういうのが経典の読み方ではなかったわけです。
仏とは何か、この問いに焦点を当ててお話ししましょう。
仏とは、私たち凡夫とは根本的に異なる存在です。特に法華経において描かれる仏は、その特異性が強調されます。「われこそは仏なり……」という宣言は、その差異を端的に示しています。
お釈迦さまが悟りを開いた瞬間、その教えを人々に初めて説いたのが、「初転法輪」として仏教で知られています。しかしこの時点で、お釈迦さまは仏という存在が私たちとは絶対的に異なるものであることをはっきりと示されました。原始仏典『律蔵大品』の冒頭部分には、お釈迦さまの伝記が記されており、そこには重要な言葉が刻まれています。
しかし、話を進める前に、お釈迦さまと五人の比丘の関係について触れておきましょう。お釈迦さまが出家され、六年間の厳しい苦行を行なったことは周知の事実です。そして、肉体の苦痛だけを伴う苦行には意味がないと悟り、その道を捨てられました。この五人の比丘は、お釈迦さまが苦行を捨てるまで共に修行していた仲間たちです。彼らにとって、お釈迦さまは途中で挫折し、堕落した者と映ったのです。
さて世尊[お釈迦さま]は次第に遊行して、バーラーナシー国、イシバタナの鹿野苑にいる五人比丘たちの群れのところへ近づいた。
五人の比丘たちの群れは世尊が遠方より来られるのを見て、互いに約束した。
「友らよ、あそこに贅沢で、努力することをやめ、奢侈に陥った沙門ゴータマがやって来る。かれに挨拶してはならない。起って迎えてはならない。かれの鉢と上衣を受け取ってはならない。しかし坐る所は設けてやらなければならない。もしかれが望むならば、坐るであろう」と。
ところが世尊が五人の比丘たちの群れに近づくにつれて、かれら五人の比丘たちの群れは、自分の約束を守ることができず、世尊を起って迎え、ある者は世尊の鉢と上衣を受け取り、ある者は坐る所を設け、ある者は洗足の水、足台、足を拭く布を持ってきた。
世尊は設けられた座に坐り、そして足を洗われた。
ところでかれらは世尊を名[ゴータマ]で呼び、また「友よ」という言葉で話しかけた。
このように話しかけられたとき、世尊は五人の比丘たちの群れに次のように言われた。「比丘たちよ、如来を名で呼び、『友よ』という言葉で話しかけてはならない。比丘たちよ、如来は尊敬さるべき人、正しくさとった人である。比丘たちよ、耳を傾けよ。不死が得られたのだ。私は教えよう。私は教えを説こう。教えられたように行うならば、遠からず良家の息子たちがまさしく家から出て出家者となった目的であるかの無上の清浄な修行の完成を、この現世において自ら知り、自分自身で体験し、体現するであろう」
このように言われたとき、五人の比丘たちの群れは世尊に次のように述べた。
「友、ゴータマよ、あなたはあの修行、あの修道、あの苦行によっても、普通の人以上の状態、真に聖なるすぐれた知見を得なかった。あなたはいま贅沢で、努力することをやめ、奢侈に陥っているのに、どうして普通の人以上の状態、真に聖なるすぐれた知見を得ることができるでしょうか」
このように言われたとき、世尊は五人の比丘たちの群れに次のように言われた。
「比丘たちよ、如来は贅沢ではない。努力することをやめたのではない。奢侈に陥ったのでもない。比丘たちよ、如来は尊敬さるべき人、正しくさとった人である。比丘たちよ、耳を傾けよ。不死が得られたのだ。私は教えよう。私は教えを説こう。教えられたように行うならば、遠からず良家の息子たちがまさしく家から出て出家者となった目的であるかの無上の清浄な修行の完成を、この現世において自ら知り、自分自身で体験し、体現するであろう」
このようにして、お釈迦さまは、五人の比丘たちに、仏の教えを説かれていったわけなんです。そして、これが、仏教が世界的な宗教となっていく、その初めでもあったわけです。とりわけ興味深いのは、この間まで修行仲間であった五人に、「比丘たちよ、如来を名で呼び、『友よ』という言葉で話しかけてはならない。比丘たちよ、如来は尊敬さるべき人、正しくさとった人である」と、告げていることです。ここには、修行僧としてのゴータマはもはや見られません。いるのは、堂々とした如来(仏)の姿だけです。
仏の領域に足を踏み入れた詩人
さて、ここまでは、仏さまという存在がいかに大きく、偉大なものか、そういうことを話してきました。しかし、ちょっと視点を変えてみましょう。
威風堂々とした態度、あたりを払う威厳……、仏さまの偉大さを思うたび、私はすごいなあと感じます。しかし、その反面で、人間の弱さとか、哀しさみたいなものが、対照的に見えてくることもあるんです。特に、そういう時、心によみがえってくるものとして、宮沢賢治の一つの詩があるんです。
「仏とは何なのか」と同じように、「人間とは何なのか」を深く考えさせられる詩だからなんです。それは、詩集『春と修羅第二集』の詩で、三一四番と番号が付された作品です。詩集の中では、『夜の湿気と風がさびしくいりまじり』と表題がついております。こういう詩なんです。
夜の湿気と風がさびしくいりまじり
松ややなぎの林はくろく
そらには暗い業の花びらがいっぱいで
わたくしは神々の名を録したことから
はげしく寒くふるへてゐる
賢治の詩には、何遍読んでもわからない作品もありますが、この詩のように、何度も読み返していると、「アッ」と気づかされるものもあるんです。
さて、この詩に特徴的なのは、その暗い色調です。決して、明るくて、爽やかだとは思えないでしょ。そしてドキッとするのは、三行目の「そらには暗い菜の花びらがいっぱいで」という言葉です。なんだかわからないが、暗いけど、妖しいほど美しいイメージが広がってきませんか。
そらには……とありますが、視点を変えると「わたくしの心象には……」と読んでもいいと思うんです。
「暗い業の花びら」という言葉を話し始めたら、おそらくキリがないので、あまりふれません。今、問題にしたいのは、次の二行、つまり、「わたくしは神々の名を録したことからはげしく寒くふるへてゐる」の部分なんです。どうしてこの二行が、薬草喩品とかかわるのかという話をしたいのです。
ご存じのように、賢治が評価され、文学や生き方が理解されるようになったのは、死後かなりたってからです。いや、ひょっとすると、まだ理解されることを拒んでいる、そういう存在かもしれません。それは、なぜなのか?
実は、賢治は、時として、詩人という営みを飛びこえて、「神々や仏の領域に足を踏み入れた」と自ら感じた人のようです。
しかも、彼は踏み入っただけでなく、それを録したと表現しています。賢治は詩を書く人ですから、つまり詩にうたったという意味です。この言葉だけ読んでも、ただの詩人だったとは思えません……
皆さんはどう思われるかわかりませんが、私は、賢治がウソを言ってるとは思えません。正直な言葉だと捉えています。
おそらく、彼は、時として、ものすごい高みにのぼったり、ものすごい透徹した目を持つことがあったのではないかと想像します。
もう、人間の限界を超えたとしか思えないようなね。だが、いくらそんな世界に入っても、人間は人間です、やがて人間世界におりてこなくちゃいけません。そういう時ですよ、賢治は反動で、はげしく、そして寒さにふるえるしかなかったんじゃないですか。
実は、『春と修羅第二集』に載せられた決定稿とは別に、全集には異稿として先駆形のものが、二編載せられているんです。
その異稿はもうちょっと長くて、三一四〔夜の湿気と風がさびしくいりまじり〕という表題のあとにこういう言葉がつづいてるんです。
三一四 業の花びら〈先駆形A〉
夜の湿気とねむけがさびしくいりまじり
松ややなぎの林はくろく
そらには暗い菜の花びらがいっぱいで
わたくしは神々の名を録したことから
はげしく寒くふるへてゐる
ああたれか来てわたくしを抱け
しかもいったい
たれがわたくしにあてにならうか
どんなことが起らうと
わたくしはだまってあるいて行くだけだ
……どこかでさぎが鳴いてゐる……
松並木から雫がふり
空のずゐぶん高いところを
風がごうごう吹いてゐる
わづかのさびしい星群が
西で雲から洗び出されて
その偶然な二っつが
真鍮の芒で結んだり
巨きな秋の草穂の影が
残りの雲にうつったりする
三一四 業の花びら〈先駆形B〉
夜の湿気が風とさびしくいりまじり
松ややなぎの林はくろく
空には暗い業の花びらがいっぱいで
わたくしは神々の名を録したことから
はげしく寒くふるへてゐる
ああ誰か来てわたくしに云へ
億の巨匠が並んで生れ
しかも互ひに相犯さない
明るい世界はかならず来ると
どこかでさぎが鳴いてゐる
……遠くでさぎがないてゐる
夜どほし赤い眼を燃して
つめたい沼に立ち通すのか……
松並木から雫が降り
わづかのさびしい星群が
西で雲から洗はれて
その二っつが
黄いろな芒を結んだり
残りの巨きな草穂の影が
ぼんやり白くうごいたりする
おそらく賢治は、自分と同じように遥かな高処にまでのぼり、そして同じように人間としての弱さを体験している、そういう魂を探していたんでしょう。しかし、いるわけないですよね。だから、「たれがわたくしにあてにならうか どんなことが起らうと わたくしはだまってあるいて行くだけだ」と言うしかなかったし、「遠くでさぎが鳴いてゐる 夜どほし赤い眼を燃して つめたい沼に立ち通すのか」と嘆くしかなかったんじゃないですか。
世の中には、こういう、誰とも共有できない、特殊な孤独があるんですね。賢治の嘆きを読んでいると、画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの嘆きが重なってきます。ゴッホもまた、時として、とてつもない透徹した眼を持ったために苦しんだ人です。そして、普通の眼に戻った時に「はげしく寒さにふるえた」人でもあります。最後は、その落差に自らの精神を侵されてもいます。つまり、人間の限界を突きつめた所、そういった、常人が立ちえない場所に、立っていたと言ってもいいんじゃないですか。前に話した、『戦争と平和』の作者トルストイも、一日中著作に没頭し、書斎から出てくると、妻の前にひざまずき、「ああ、僕はまた一日をインク壺の中に落っことしてしまった」と泣いたといいます。そして、衝動的な自殺を恐れ、自分の周りに猟銃や縄のたぐいを置かせないようにした時期もあったといいます。
人が、人以上のものを見たり、人以上の世界に足を踏み入れた場合、「人でなし」にならないかぎり、苦しみ悶えるしかないと思いますよ。それを偉大な巨匠ともてはやすのは世間の側で、本人にとっては、「もう、たまらん」と悲鳴をあげたくなるんじゃないでしょうかね。
一般的に、お坊さんは「仏さまの眼と、仏さまの心を持ちましょう」と簡単に言いますが、これ、よく考えたら、かなり矛盾した言葉です。生身の人間が、この限りある現世の中で、ほんのひとときでも、仏の心や、
仏の眼を持ったなら、どれほど「はげしく寒くふるへ」なくてはいけないか……、そこを考えなくちゃいけません。実は、私が賢治を好きなのは、彼が「はげしく寒くふるへ」た人だったからです。そして、「わたくしは神々の名を録したことから」と表現するような、とてつもない詩を本当に書いた人だったからです。
見えているようで、見えていないのが人間
さて、話を戻しましょう。仏さまとは真如の世界そのものなんです。だから、みずからを、「われは如来なり」つまり真如の世界からやって来た者と表現するわけです。真如の世界から来たといっても、仏さまは、人間の世界でふるえたりなどしません。ここがすごいところなんです。なぜなら、仏さまとは、前にも話したように、無限の広がりを見、無限の深さを知り、無限の時空間を生きる存在だからなんです。仏さまとは、人間のように、次元に限定され、肉体の枠に縛られた存在ではないんです。だから、威風堂々と、みずから名乗りを上げるわけなんです。そして、次のような、興味深い言葉を語られたりするんです。
それ衆生有りて、如来の法を聞き、若しくは持ち、読誦し、説の如く修行するも、得る所の功徳は、自ら覚知せざるなり。
梵文訳では、
人々は如来が教えを説いているのを聴き、それを記憶し、それに傾倒しても、かれらは自身で自身を知らず、気づきもせず、また、さとりもしないのだ。
功徳というものは自分ではわからないのだと、こう言っているわけです。なぜ人間は、自身の功徳というものを、覚知できないのかというと、次のような説明がつづいております。
所以はいかん。唯、如来のみ有りて、この衆生の種と相と体と性と、何の事を念じ、何の事を思い、何の事を修し、云何に念じ、云何に思い、云何に修し、何の法をもって念じ、何の法をもって思い、何の法をもって修し、何の法をもって何の法を得るや、ということとを知ればなり。
梵文訳では、
それは何故かといえば、如来こそこれらの人々がいかなる者であり、どのような生活をしているか、また何に似ているか、かれらが何を考え、どのように考え、どのような手段で考えるか、またかれらが何に専念し、どのように専念し、どのような手段で専念するか、またかれらが何を達成し、どのようにして達成し、どのような手段で達成するかを、ありのままに知っているからである。
ここに特徴的なことは、仏の認識のしかたが、やはり、「ありのままに知る」「ありのままに見る」というところから来ていることでしょう。逆に言うと、人間は、ものごとをありのままに見たり、ありのままに理解することができないと考えてもいいと思います。
実は、人間が覚知する、つまり「見る」「知る」「覚える」「わかる」といった行動は、心の表層でやってる場合がほとんどなんです。
意識とか理性とか、そういう認識からほとんど出ることができない。しかし、覚知する人間の側から言うと、それしか見えてないのだから、彼にとっては、それが世界のすべてであるわけです。
たとえて言うと、真っ暗闇をヘッドライトをつけて、車が進んでいるようなものです。ヘッドライトの光(意識や理性)に照らされている領域しか、覚知しようにも覚知しようがない。じゃ、見えない部分はどうなのか……という議論になりますが、残念なことに、人間というものは、まったく覚知できないものを、イメージしたり、想像することのできない生き物らしいですね。
それならば……「ありのままにすべてが見える」仏さまというのは、特別製のヘッドライトや、ものすごい光線を所有しているのか?という議論がおこりそうです。これも、そういう単純なことではないんです。仏さまは特別製のヘッドライトや、ものすごい光線を
持っていると考えるより、存在そのものが、朝と昼のように、すべてがありのままに見える、そういう別次元に立っていると考えるべきなんです。
「如来は已に三界の火宅を離れて寂然として閑居し林野に安らかに処せり」という経文が、譬喩品の偈文にありましたよね。この別次元という立場から、「諸法実相」というものが現われ、「難解難入」という言葉が発せられ、なぜ仏がこの世に出現するのか「一大事の因縁」という大前提が説かれているわけなんです。
早い話が、「仏が見つめている諸法実相の世界は、なぜ難解難入なのか?」と設問を作ったとします。しかし、この設問には、もともと答えなど存在しないと考えるべきです。仏が見つめている世界ならば、我々には難解難入なのが当たり前なんです。我々にはわからない、だからこそ仏は「一大事の因縁の故に世に出現したもう」わけですよ。
この薬草喩品を読んでいると、仏と凡夫とは、絶対的に違うのだなとつくづく感じます。そして、人間というのは、見えてるようで何も見えていないし、わかってるようで何もわかっていないんだなと考えさせられますね。
そこで、人間というものが、いかに自分に対し盲目であるか、また自己を見つめるといっても、その見つめ方が、いかに表層的でしかないか、そういうことを考えてみようと思います。
みなさんは「内観」という言葉を聞いたことがありますか?そうですね、白隠禅師の内観とはちょっと違ったものなんです。吉本伊信さん(1916-1988)という方が、昭和の初期に始めた「自分を見つめる行」なんです。宗教とも違うし、心を病んだ人の療法とも限定できない、ちょっと変わった行なんです。自分の内心を観察させるための行とでもいいますかね。
どういうことをやるのかというと、部屋の隅に屏風を立てて、およそ一メートル四方の場所に内観者を坐らせ、何日間にもわたり、幼少期から今にいたるまで、主に母親との関係を調べさせていくという行なんです。教えや教義を与えるのではありません。だから宗教とはいえません。かといって、カウンセリングのように、専門家が、心の問題を掘りだしていくというのとも違います。心を病んだ人、精神に問題がある人という限定もありません。また、心を見つめるといっても、「様式」とか「無」とか、そういうゴチャゴチャ煩わしいものに縛られる禅とも違います。まあ、あえて言ったら、自由な「瞑想」に近いかもしれませんね。ただし、内観の場合、単純に内側を見つめるだけではありません。「調べる」という姿勢がポイントになってくるんです。
心を見ると同時に、自分で自分を裁こうとするわけです。懺悔あるいは反省のための内観といってもいいでしょう(ちなみに、法華経の結経といわれる「仏説観普賢菩薩行法経」という経典は、懺悔の意味と、功徳と、そのやり方を説いた経で、「法華経の中で、懺悔というものがどういう位置にあるか」を見事に伝えた経典です。
さて、内観の場合、その基本を、自己を調べるという部分に置くのは、それなりにルーツがあるんです。吉本伊信さんの『内観への招待』を読んでみましょう。
身調べというのは、内観法の開発の基盤となった浄土真宗の特殊な一派に伝わる修行法であります。これは強い求道心をもった信者を一定の場所にひとりだけ隔離し、肉親との面会も許さず、数日間の断食・断水・断眠という厳しい条件の下で、「今死んだら自分の魂はどこへ行くのか。地獄行きか、極楽行きか?と、真剣に無常をとりつめて、身・命・財の三つを投げ捨てる思いで反省せよ」と指示を与えられて、今日までの自分の行ないを反省させるものです。そして二時間おきくらいに代わるがわる信仰心のあつい先輩たちが面接にきて下さっては、現在の心境を聴き、説教し、激励します。こうして信者に罪悪深重の身を自覚させ、仏の救いにあずからせようとするものでありました(これを「一念に遇う」といいます)。
私は、内観のポイントを、無常感をもつことよりも罪悪感をもつということにずらしました。(…中略…)無常感を自然に自発的に感得している人ならば、すでに救われつつある人といえるはずであります。それより、どうしたら無常感を感じられるようになるのか、ということのほうが大事であり、それには、罪悪感から進んで行くほうが順序であり確実ではなかろうかと考えたからでありました。
"我が身は悪きいたずら者と思えば自力はすたるなり"
簡単なお言葉ではありますが尊い法話であります。自分の罪を知ることが死をとりつめる近道なのです。今までは「死んでも恐しくない。自殺してもなんともないのだ、死んだらそれまで」と簡単に思っていた人が、自分の罪を知ることによって「これは大変だ。こんな恐しい罪を犯してきた私が、もし死んだらどうなるのだろう」と考えるようになるのです。物事を正しく見てこそ真実を知る知恵が養われるはずであります。
無常は、とりつめても、とりつめてなくとも無常です。罪を罪と知るその深さに比例して、無常であることも自然にわかってくるのであります。それなのに、われわれは迷っているから、自分が罪を犯しており、口先では私は罪人ですといっておっても、他人から泥棒と言われると、何を!と怒るのであります。怒るということは「私は罪人でございます」と言っているのが、実は表面だけのことなのだということを示していることになります。本当の罪人と自覚するには、深い深い反省が必要です。罪人が罪人だったと悟った時、真理の目が開けるのです。本当の無常感を感じるためには、本当に罪悪を感じられるようにすることから訓練すべきだと思って、従来からの重点の置き方を変えたのであります。
従来秘密にしていたことも公開にきり変えました。
したがって、だれが面会に来られても「ああどうぞ、いま二階に坐っておられますから」といった調子で「小さい声で五分以内にして下さいよ」といって逢ってもらうことにしました。家出の娘が来て坐っておられる時、どんなところへ足をふみ込んだのか心配だと親が来られるようなことがあっても「逢って下さい」「連れて帰ってもよろしいですか?」「さあどうぞ連れてお帰り下さい」という形で応対ができます。これならば邪推も誤解も生まないはずであります。
次に、断水・断眠・断食という方針はすべてやめて、食べさせ飲ませ眠らせるということに改めました。
その理由は、腹がへっては戦が出来んのたとえ通り、たとえば和裁洋裁を習うにしても、やはり食べるな、寝るな、では練習を阻害することにしかならないのは明らかであり、それと同じことだと考えたからであります。
反省が深く進むと、今死んだらどこへ行くのだろうと恐しくて、本心から無常感が熾烈になって、飯を食べても砂を食べているような気しかしないようになります。晩、寝ても目がぎらぎらさえて眠れないというふうに、自然にそうなるのだったら無理に食べなくてもいいし眠らなくてもいいでしょう。
内観の順序の確立ということも大きな問題であります。
というのは、昔は細かいテーマというのは何ひとつなく、ただ「死んだらどこへ行くか?」と「それからどんなことを調べてもらいましたか?」と聞くだけでありました。しかし、現在では、どんな問題を抱えて来ても「お母さんに対して小学校時代低学年の自分を調べて下さい」とお願いしています。まず、お世話になったこと、そしてして返したこと、迷惑かけたことを反省していただき、その次には中学時代、それから高校時代、というように年を追って反省していただいています。
うっかりしていると、うちのお母さんはああいう人で、こういう人で、ということになりますが、「あなたのお母さんはどういう人ですか」と聞いているのではありません。お母さんに対する自分はどうであったかを調べるのが内観です。こういう注意は常に怠ってはなりません。
心の表面であれこれ考えていてもはじまらないということでしょう。深層の奥で眠っているものを揺り起こさねばならないということです。
かつて九州大学の心療内科の池見先生がおっしゃっていましたが、わかっちゃいるけどやめられない、というふうなのをやめさせるには間脳にわからせるしかないそうです。
酒飲んだらいかん、ばくちしたらいかん、喧嘩したらいかん、そんなことはやる前からわかっているけど歯どめがきかない。この間脳までしみ透らすにはどうしたらいいか、これが内観です。
なかなか根気のいる仕事ではありますけれども、何回もくり返し反省を深めていただくのが、内観の特徴なのです。
内観しているうちにこんなにも親に迷惑をかけ、お世話になっていたとは知らなんだ。しかるに私自身が親にどれだけ尽してきたか。何にもご恩は返していない。
何かひとつくらいあったはずだろう、と探して見るけれど、何ひとつないと気づいてくださいますよ。悪かった、すまなかった、と懺悔のあまり畳にしがみついて号泣慟哭して、十日も二十日も泣きあかすような人も、ときたまあります。そういう人こそ目付きや人相まで変わります。
一週間内観して下さることによって、間脳といいますか、脳の中の『奥の院』に作用し、魂の底から目ざめてくると、心のすみかの大転換がはかられるのです。
私たち人類は、見事な文明社会を築き上げてきました。この輝かしい成果は、人類の知恵と創造力の賜物であり、その偉大さを過小評価することはできません。しかし、文明社会の華やかな表面に惑わされることなく、もっと深く、人間の叡智に目を向けるべきです。思いを馳せてみてください。「文明というものが、もしかしたら人間の表層意識の産物に過ぎないのではないか」と。そして、「心の奥底に眠る真の叡智は、まだ未だに隠されているのではないか」と。
薬草喩品を読むと、仏と比べた際の人間の無力さが際立ちます。しかし、それと同時に、人間が持つ潜在的な力、未開発の可能性への希望や期待も感じさせます。「得る所の功徳は、自ら覚知せざるなり」という言葉は、まさに人間の本質を突き詰めたものかもしれません。この経文は、私たちがまだ自覚していない深い智慧や、内に秘めた可能性を示唆しています。人間という存在は、表面的な文明の成果を超えて、もっと深い次元での自己認識と成長を求められているのです。
[一]に込められた深い意味
薬草喩品のところで重要な経文がありました。皆さんと一緒に考えてみたいと思います。それは、こういう経文なんです。
かの大雲の一切の卉木(くさき)叢林(そうりん)及び諸の薬草に雨(あめふ)るに、その種性に如(したが)って、具足して潤を蒙り、各(おのおの)生長(しょうちょう)することを得るが如し。如来の説法は、一相、一味なり。
「三草二木の譬え」にあったように、差別や変化は、受ける側に生ずるのであって、与える側の仏からすると、説法は相も、味わいも一つのものだとおっしゃっている経文です。この経文の中でも、特に「一相、一味なり」と表現された[一]について考えてみたいんです。つまり経文の語句よりも、この一だけに焦点をあてて……、ちょっとしつこいんじゃない、というくらいに考えてみようと思っているんです。
なぜかといいますと、法華経の場合、この[一]をキチンと把握しないままだと、〈読んでもよくわからないな〉という感じがいつまでも残る可能性があるんです。法華経の前半は、「一仏乗」と「授記」が中心テーマです。もっと極端にいうと、[一]とは何なのか、[一]とはどういう意味なのか、これがテーマでもあるわけです。
さて、この一仏乗ですけど、「たくさんの、種々雑多な、多様性に富んだ仏教が現実に存在している。しかし、この多様性の大本にあるのは、一仏乗という、たった一つの仏の立場だけである」と、まあこういうことを言ってるんですね。だいたい法華経を勉強している人は、こういう言葉を読んで、ぜんぜんわからないのに、〈ああ、そうなのか〉と無理に自分を納得させるところがあります。大学の学生でも、「一仏乗を説明せよ」と問題を出されたら、今みたいな紋切型の答えをそのまんま書く者が多いです。徹底的にこの[一]について考え、「何なのだ、どうしてなのだ、なぜ……」と自問する人がいないようです。それじゃダメなんですよ。
法華経を説く前提として、お釈迦さまは何のために、「この経は第一希有、難解の法なり」と表現されたのか、どうして晩年になるまで説くことを躊躇されたのか、それを考えたら、法華経という経典は、紋切型で理解できるような教えじゃないと、こころえるべきです。
実は[一][1]くらいすごいものはないんです。ちょっと視点を変えて一緒に考えてみましょう。まず数学の世界で考えてみましょう。たとえば、偉大な数学者にこういう質問をぶつけたとします。高校生で数学がよくできる秀才くらいじゃ、まだダメです、数学者と言えるくらいの人にですよ。
「あのー、数学で1ってなんですか?」と聞いたら、おそらくこういう言葉が返ってくるでしょう。「1ですか?ウーン、すごい質問ですね。何て答えればいいんでしょう」と苦笑すると思います。そして、ある人は、「そうですね、数学で一番大切なものです」と言うかもしれません。またある人は、「ハハハ、1ですか。そうですね、数学という学問そのものが、1を説明しようとする学問だと言うべきかな」「とにかく数学で一番重要な概念です」といった言葉が返ってくると想像されます。
数学との出会いは、幼少期に「1、2、3、4」と数を数えることから始まりました。特に「1」は、私の数学的旅の出発点となりました。最初は単純な数え上げでしたが、学校で数学を学ぶにつれ、「1」の概念は驚くほど複雑になっていきました。例えば、小学校で「1」を「1/3」に分割することを学びました。この瞬間、「1」という数がどれほど柔軟であるかを理解し始めたのです。また、「1対1」の関係性も学びましたが、比較対象が変わると「2対1」になり、まったく新しい次元の「1」が出現しました。
さらに、貯金の利息で「1パーセント」と「1割」の違いに直面しました。同じ「1」でもその使用方法によって、まったく異なる影響を与えることに気づきました。時間の概念においても、13時が午後1時となることは、私にとって「1」の相対性を教えてくれました。
数学的な旅を進む中で、「1」は常に私の考えを刺激し続けてきました。二次関数や楕円の方程式において、同じ「1」が異なる形で表現される様子は、その神秘性をさらに強調しました。虚数の「1」は、また別の次元の話ですが、それでも「1」の核心は変わりません。
このように、私の数学的探求は、「1」という数字の多様性と複雑さの中で展開してきました。「1」には無限の表現があるという事実は、数学の魅力の一端を示しています。私は、今後もこの不思議で魅力的な数字、「1」の探求を続けていきます。
ですから、「仏の説法は、一相、一味なり」と言われたら、その[一]という言葉には、ものすごい深みがあるんだろうなと考えるべきなんですね。それはちょうど数学者が、学んで学んで、勉強して勉強して、苦しんで苦しんで、その果てに、「数学で一番大切なものは1なんだな」と痛感する。そういう深みが必要だという意味です。だから、なんの紆余曲折もなく、ただ紋切型に一仏乗といっても、おそらく一の意味はわからないんじゃないですか?〈なぜなんだろう?〉〈どうして、お釈迦さまは、晩年になって、法華経をとおし、一仏乗ということを言いはじめたのだろう〉そういう疑問を持つべきなんです。つまり、私たちも、偉大な数学者と同じように、ああそうか、一番大切なのは、一という立場だったんだなと気がつかなくちゃいけないんです。機械的に、仏教辞典や法華経辞典を読んで、一仏乗の解説をまる暗記してもしかたがないんですよ。
さて、法華経のみならず、大乗仏教では、[一]が思想の中核をなしています。[一]というものは、ものすごいものだぞ、素晴らしいものだぞというのが大乗仏教だと表現してもいいかもしれません。だから基本的には、仏教の中心も[一]なんですね。ただ、間違えやすいのは、キリスト教の中心も[一]だから、「仏教もキリスト教も同じじゃないか」と同一視しやすいことなんです。キリスト教は、最初から最後まで[一](神)ですが、仏教は最初は〔〇〕(空)なんです。それが、どこかで、どういうわけか、[一]になるわけです。このどこかで、どういうわけか、ヌーッと「無」から「有」が生まれるところがおもしろいんです。つまり仏教の[一]とは、こういう[一]なんですね。
この[一]を、真っ正面から表現している経典に『華厳経』があります。「重重無尽」とか、「一即一切、一切即一」などという考えは、皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。この華厳経の中で、一のオンパレードみたいな経文があるので、ちょっと読んでみましょう。これだけ一が並ぶと、〈一というのは、なんかすごいことなんだな〉とボンヤリわかってくるんじゃないですか。『華厳経』の普賢菩薩行品第三十一という章に出てくる経文です。
所謂一切の世界は一毛道に入り、一毛道は不可思議の刹を出だす。一切衆生の身は悉く一に入り、一身に於て無量の諸身を出たす。不可説の劫は悉く一念に入り、一念をして不可説期に入らしむ、一切の仏法は悉く一法に入り、一法をして一切の仏法に入らしむ。一切の諸人は一人に入り、一入をして一切の諸入に入らしむ。一切の諸根は一根に入り、一根をして一切の諸根に入らしむ一切の諸根は非根の法に入り、非根の法は一切の諸根に入る。一切の諸相は悉く一相に入り、一相は一切の諸相に入る。一切の語音は一語音に入り、一語音は一切の語音に入る。一切の三世は悉く一世に入り、一世をして一切の三世に入らしむ。
こうなると、一というのは、ただの数とは思えなくなってきます。心臓があって血が流れ、口があって呼吸してる、そういう生き物みたいなーなんですね。数学者が研究に研究を重ね、悩みに悩み、最後に、「なーんだ、数学で一番重要な概念は[一]だったのか。数学は[一]に始まり[一]に終わるのか」という立場、これを一仏乗というんです。だから、お釈迦さまは、法華経の中で、種を変え品を変え、「たったひとつの立場」というものを、何度も何度もお説きになるわけです。法華経の前半、つまり全体の半分くらいが、一仏乗のくり返しといっても言い過ぎじゃないですからね。
すると、機根の高い舎利弗は、方便品のところで、「アッ!」と気がつくわけです。しかし、それ以外の弟子は、まだポカーンとしてるわけです。そこで譬喩品が説かれます。すると、また何人かが「アッ!」と気づくわけです。
そうですね、先ほどの数学の話で説明すると、方程式には根(答え)というものがあり、一次方程式には一つの答えがあります。
たとえば、A子チャンは、百円持って買い物に行きました。りんごを二つ、なしを三つ買ったら、三十円足りませんでした。次の日、二百円持って買物に行き、三十円をおじさんに返し、りんごを三つとなしを二つ買うと、お金がちょうどなくなりました。さて、りんごとなしは、一ついくらなんでしょう。
こういう問題ですね。こういう問題は方程式を立てて答えを出します。ところが二次方程式、三次方程式などになると、二次方程式なら根は二つ、三次方程式なら根は三つありますから、答えの中に虚数の答えが出現し始めるんですよ。現実には存在しない数、つまり数のまぼろしですね。しかし、根が「虚数」であるとしても、それがまぼろしの数であろうと、数学から言えば、正しい答えと考えなくちゃいけないんですね。
法華経が言う、三乗は仮の説で、一乗が本当だという考えは、この三次方程式の解法に似ています。三つの答えのうち、二つは虚数の根になってしまう、そういう方程式のような感じです。数学的には、三つとも本当の答えには違いない、間違いではない、しかし、二つの答えは、現実には存在しない「虚数」になってしまう。
ですから、虚数の答えに惑わされず、実数で出た答え、つまり「ほんとうの、ほんとうの、まことの答え」を突き進みなさいと言ってるような気がするんです。妙な表現でしたか?
ここでガラッと話を変えましょう。
「日本人と[一]という関係を考えてみましょう。実は、日本人くらい[一]という感性を持った民族は、世界中のどこにもいないんです。日本人を考えていたら、[一]に突き当たるといっても言い過ぎではないかもしれません。ところが、外国人は、日本人を評して、「日本人には主体性がない」「自分というものがない」と表現します。「自分という一」を持たない、なんとなくボワーッとした国民だと言ったりします。日本人で西洋思想にかぶれたインテリなんかは、そういう考えに追従して、「だから日本人はダメなんだ」なんて言う人がいます。たしかに、日本人には、「西洋的な一」は希薄です。これは、私も認めます。そのとおりですから。しかし、これが「仏教的な一」になったら、話は違いますよ。こういう[一]に対する感性だったら、逆に、西洋人はまずかなわなくなるはずです。
さて、どこから話を始めましょう。そうですね。こういうのはどうですか?一つの架空の物語ですよ……
ある町に道路が通ったとします。その道路の脇には、なんとも奇妙な姿をした、枝ぶりのおかしな樹が、ポツンと一本残されたとしましょう。道を行き来する人は、なんとなくこの樹が気になってしかたがありません。
ちょうどそんな時、誰かが、偶然、小さな皿をこの樹の根元に置き忘れたとします。二、三日して取りに行ったら、小銭が何枚か入っていました。そこで、「あれまあ」と思って、皿の代わりにもっと大きな箱を置いておきました。すると、どんどん小銭が入るようになりました。そのうち、また別の人が、この奇妙な形をした樹に、注連縄を巻いたとします。今度は、出勤や通学で、その道を行き来する人が、立ち止まってなんとなく手を合わせるようになります。
やがて、この樹のもとに、お供えものが見られるようになります。また朝の散歩で、十円玉を手に、この樹まで来ては賽銭をあげ、手を合わせるのが日課のお婆ちゃん、お爺ちゃんが現われるようになります。するとそういう人のなかで、「あの樹を拝んでいたら病気が治った」という人が出てくるとします。その話は、町から町へ伝わって、「ありがたい樹があるそうじゃ」と評判になってくるんですね。そこで、地元の町では、神主さんを呼んで、祝詞をあげてもらったり、町内を歩いて寄付金をつのり、小さなお社を作るようになります。そして、町内の会合で、年に一回、お祭りをしようといった意見が出されるようになるとします……。
さて、皆さんは、この架空の話を聞いて、どう思われましたか。おそらくそれほど不思議だとは思わないで、それどころか、なるほど、そりゃ、おおいに有り得る話だと感じたのではありませんか。話を聞きながら、ウンウンとうなずいていた人がいましたもんね(笑)。しかし、よーく考えてみてください。ここにはなに一つとして、主義もなければ、思想もありません。宗教としての教義もなければ、本尊すらありませんよ。そもそも、この樹に名前すらついてないですよ。それなのに、既成の事実として、しっかりと宗教が成り立ってしまうんですね。日本以外の国で、こんな感じで、宗教が成り立ったりするでしょうか?どうですか?また、この樹に銭をあげた人が、「わたしは詐欺にあった」などと告訴したりしますかね。そもそも誰が騙したことになりますか。そんなこと騒いでいたら、「このバチあたりめ」と、周囲の人に叱られるだけです。
これは架空の話ですが、日本人だったら、なぜだか、妙に「わかる」話なんです。理屈抜きに「ありがたや」という気持ちが理解できるとでもいいますかね。ですから、この樹に対し、西洋風に、ものすごい理論や、完璧な教義体系などが整えられたら、反作用として、「嫌だな」と言って、離れる人が出てきたりするもんです。
さて、こういう日本人を、「原始的だな」とか、「無知だな」とか、「低級だな」と思っている人が多いようです。しかし、そうじゃないんです。私が話したいことは、こういう日本人の中にこそ、仏教が言う[一]があるんだぞと言いたいんです。
日本人特有の自然認識の仕方
実は、世の中に、さまざまな日本人論がありますが、その中でもピカイチに素晴らしい本をここで紹介したいと思います。『日本人の脳脳の働きと東西の文化』と『右脳と左脳―脳センサーでさぐる意識下の世界』で、どちらも、作者は角田忠信(つのだただのぶ)さんという方です。何が書かれているかといいますと、世界的に見て、日本人の感性というものは、どんなに特殊なものなのか。あるいは、物事に対する認識作用が、日本人はいかに特殊であるか。そういうことを、脳の研究をとおし、科学的データの集積から論じた本だと思ってください。この角田さんという方は、もともと耳鼻科のお医者さんだったんです。そういうところから、聴覚、つまり「聴く」という作用が専門だったわけです。
"耳鼻科の場合も、耳の末梢だけを治療していますが、研究をしていくとなると、基本的なメカニズムを理解しようとしますでしょう。特にことばの分野では、聴力という問題が基本にあって、単に音として聴くだけではなく、ことばの認識ということがからんできます。そうなると、どうしても脳と取組むことになってくるんです。"
耳から入ってくるものは、大きく分けると、「言葉」と「ノイズ(言葉でない音)」に分かれます。そして、一般的に、「言葉」は左脳の中の言語脳が処理し、「言葉でない音」は、右脳が処理するんです。
ところが、実に不思議な結果が出てきたんです。日本人にかぎり、耳から入るほとんどのものが、左脳の中の言語脳に入ってしまうんですね。日本人にかぎりと言ったのは、日本人以外では、韓国人でも、中国人でも、こんな結果は出てこないんですよ。世界中で日本人だけが示す、きわめて特殊な言語脳の働きがわかったという意味なんです。
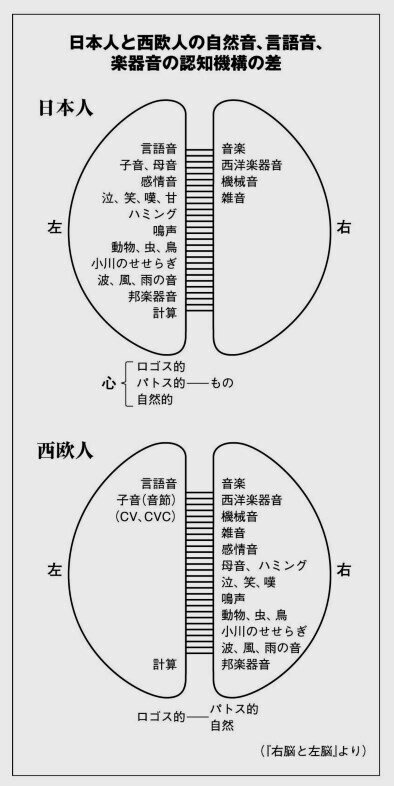
右脳を見るとわかりますが、日本人が、「言葉ではない音」、つまりノイズ、無機的な音として聴くのは、わずかにこのくらいなんです。あとはみんな言葉として受け取っているんですね。一方、日本人以外の脳の働きを見てください。日本人以外ということは、人類の一般的なパターンと考えてもいいということですよ。この場合、言語脳が処理するのは、まさに「言葉」に限られています。ハハハと笑う声、ワーワー泣く声、アエイオウという声(母音)ですら、ノイズとして聴いてるんです。考えてみたら、言語脳というのは、言葉を専門に担当するのですから、このパターンのほうが、当たり前と言ったら当たり前かもしれません。むしろ、おかしいのは、日本人のほうです。どうして何もかもが言葉として脳に入ってくるのか。大いに疑問を感じてしまいます。そうなんです。どうして日本人だけは、耳から入ってくるものを、ほとんど言葉として受けとめているのでしょう?
日本人以外の脳は、論理脳(ロゴス)といわれる左脳では、知的なものだけを受け入れ、それ以外のものは、情緒・イメージ脳(パトス)といわれる右脳で処理しています。だから、右脳・左脳の機能が、公式どおりに働いていることになります。ところが、日本人の場合は、実にややこしい、奇妙な機能を持っていることがわかります。もともとは論理(ロゴス)をつかさどる左脳に、きわめて情緒(パトス)的な、自然の音、イラストを見ればわかりますが、動物の鳴き声、虫の声、鳥の声、小川のせせらぎ、波、風、雨の音……、などが入ってきてるんです。しかも、これらを「言語」として処理していることがわかります。 みなさんの場合、今、話を聞いたばかりだから、「ヘエー、そうなの」くらいにしか思えないでしょう。しかし、家に帰って、もう一回、よーく考えてみてください。これって、実は、ものすごく不思議なことなんです。そして、そこから引き出される、さまざまな問題を、一つ一つ追究していったら、〈オイオイ、日本人って、とんでもなく変わった民族だな〉と驚くはずです。
さっきも言いましたように、こういう脳の働きをするのは、世界中で、今のところ日本人だけなんだそうです。それは何を意味するかというと、つまり、日本人だけが、きわめて不思議な方法で、自然を認識するということになります。どういう認識方法かというと、自然に対しては、言葉によって、コミュニケーションをしているというわけです。言葉の意味が通じるかどうかとはまた別ですよ。つまり、私たちが外国人を相手にしている状態に似ています。もちろん「目で見る」場合には、どんなふうに、自然を認識しているかはわかりません。が、とにかく、聴覚においては「言葉によるコミュニケーション」ができているわけです。
実は、角田さんの研究によって、日本文化の特殊性、あるいは日本人の特徴が、なんとなくではなくて、ハッキリと、表面に出てきたといっても過言ではなくなったんです。多くの「日本人論」の裏づけが、科学的になされたわけです。そこで、こういうことをふまえて、ちょっと角田さんの話に耳を傾けてみましょう。
『いまここで私たちは話をしておりますが、そのときにも日本人ですと、部屋の外でコオロギが鳴いても、われわれは話しながらすぐわかるわけです。話しながらコオロギの音にハッと気がついて、いいなと思ったり、秋を感じたりするわけですが、西洋人はそういうことは絶対ないのですね。虫が鳴くということを知らない人も多いし、話をしながら途中で虫の音に気づくようなことはまずないのです。西洋人は虫の音を知らないのです。私もじつはアメリカで経験したのですが、虫の音というものにはひじょうに無関心です。これは池田摩耶子さんの随筆にも書かれているのですが、アメリカで、たとえば外務省でつくった教科書で日本語を教えている場合に、秋の虫の音を使ったような文章がありましても、アメリカ人はだいたい虫の音というものを知らない。日本人ですと、「八月の一〇日前だが、虫が鳴いている」というと、なんだかピンとわかるのですが、アメリカ人に、八月一〇日前というのに虫の音が聴かれるといっても、それは何のことか、虫が鳴くということがアメリカ人にはわからない。虫というのはこういうものだと、日本語の教室のなかで虫の鳴き声をまねてみせる。それくらいわからないのです。』
日本人以外では、自然の作り出す音(虫の音もそうですが)というものは、バケツを叩く音と同じように、無機的な音、つまりノイズでしかないわけです。ですから、コオロギの鳴き声だって、種々雑多なノイズのなかに埋没してるわけですね。反対に、日本人だと、言葉として聞こえてきますから、窓の向こうで、子供たちが遊んでいる声と、基本的には同じように聞こえてくるわけです。ですから、アメリカ人に向かって、自然の作り出す音を、日本人のように聴きなさいといっても、それは始めから無理な注文だったわけです。
しかし、もう一歩進んで考えてみたら、こういう事実も出てきます。つまり、日本人に向かって、動物の声、虫の声、鳥の声、小川のせせらぎ、波の音、風の音、雨の音……、こういうものを、ノイズ(ただの音)として聴きなさいといっても、日本人にはできないということなんです。「よーし、ただの雑音として聴いてやるぞ」と意志しても、耳から入ってきたら、それは左脳のほうへ入り、言語脳が処理してしまうわけです。
こういう結果から、どういうことがわかるでしょう。日本人の持つ自然観は、世界の民族のなかで、おそらく、きわめて特殊なものだろうという推測ですね。ひいては日本文化そのものが、きわめて特殊じゃないかという想像ですね。
日本人は、自然の中にいると、相手が人間か自然かという違いだけで、言葉というコミュニケーションはいつでもしているわけです。だから、日本人には、西洋人のように自我が発達しないというのも道理なわけです。
つまり対立概念や、孤独が生じるための、「隔絶した自分」というものが、非常に希薄な民族なんです。みなさんも少しずつ、「こりゃスゴイ発見だな」とわかってきましたか?私が、角田さんの研究を、数ある日本人論の中でもピカイチの日本人論だと表現したのは、こういう理由からなんです。
それなら、一番肝心なことですが、なぜ日本人の脳はこんな変わった特殊な働きをするんでしょう。これも本当ならば、角田さんの研究成果に沿って、詳しく話すべきなんですが、時間がないので、結論だけを話すことにしましょう。
実は、こういう日本人の特殊性、とくに聴覚における、独特の自然認識をもたらした原因は、実は「日本語」だったんです。
角田さんは、最初、日本人の身体的な特殊性に目を向けていました。つまり日本人の脳の構造が特別じゃないかと。しかし、いろいろ検査をしますと、同じ日本人でも、二世や三世のように、外国語を母国語とする人の場合、結果は西洋型を示すわけなんです。ですから、こういう特殊な結果を生むのは、日本語を母国語として育ち、日本人として生活している人だけだとわかったわけなんです。
ではなぜ日本語を母国語として育った者は、こういう聴覚の働きを持つようになるんでしょう。
実は、世界の言語の中で、日本語はきわめて珍しい言語なんです。どういうことかというと、日本語というのは母音主体の言葉でできているんですね。
ア・イ・ウ・エ・オというものです。そして、この母音的発声でカ・キ・ク・ケ・コとくるわけです。ちょっと難しいですが、日本語には純粋な子音というものが非常に少ないんです。さらに、単母音であるアにもイにも、それぞれ意味があるという変わった言葉なんです。
みなさん仏教の声明とか、民謡を思い出してください。声を出してる時間の九〇パーセント以上は、アエイオウのどれかを、アーアーアーとか、ウーウーウーとやってるだけですね。そういえば、北海道の「江差し追分」なんかは、九九パーセントがアエイオウだけですよね。
日本語という、母音を偏重した言葉を、赤ちゃんの時から、毎日、耳にして育ったのが日本人というわけです。母音というのは、もっとも原始的、原初的な音なんですね。だから、母音を偏重した日本語は、日本人の耳には、自然界の作り出す音にきわめて似てるわけなんです。まあ、こういうわけで、日本人には、世界中のどの民族も持てない、あの独特な自然観ができてくるんだと考えられるわけです。
いや、長々と話してしまいましたが、私が言いたかったことは、日本人という民族は、仏教の「一即一切、一切即一」を理解することでは、おそらく世界一すぐれた民族ではないかということなんです。理知的にではなく、理屈以前の感覚において、かなり深く理解できる民族だと思うんです。
ですから、法華経の「一仏乗」という思想も、仏教辞典を暗記するようなやりかたではなく、みずからのハートで理解しようと努力して欲しいんです。また、そうしないと、法華経の知識がいくら増えたって、心は深まりません。
[一]は、数学において、もっとも大切なものです。と同時に、仏教においても、[一]は同じくらい大切なものなんです。当然、法華経が言う、「仏には一仏乗というひとつの立場しかないのだ」という言葉も、同じくらいに深く、重要な言葉だと考えてください。
参考文献
序品第一
『法華経(上)』坂本幸男・岩本裕訳注/ワイド版岩波文庫
『原始仏典九・仏弟子の詩』テーラガーター(長老の詩)早島鏡
正訳/講談社出版研究所
『モオツァルト・無常という事』小林秀雄/新潮文庫
『妙法蓮華経並開結』法華経普及会編/平楽寺書店
『どくとるマンボウ昆虫記』北杜夫/新潮文庫
『新潮国語辞典現代語・古語』新潮社
『原始仏典一・ブッダの生涯』―大いなる死(大般涅槃経)岩松浅
夫訳/講談社出版研究所
『仏教説話体系1釈尊の生涯』仏教説話体系委員会著/中村元・増谷文
雄監修/すずき出版
『新釈尊伝』渡辺照宏/大法輪閣
『原始仏典一・ブッダの生涯』―成道から伝道へ(律蔵大品十一)
畝部俊英訳/講談社出版研究所
『生命のニューサイエンスー形態形成場と行動の進化』ルパート・
シェルドレイク/幾島幸子+竹居光太郎訳/工作舎
『八木重吉詩集』佐古純一郎編/彌生書房
『新約聖書』日本聖書刊行会発行
『沈黙の世界』マックス・ピカート/佐野利勝訳/みすず書房
『良寛詩集譯』飯田利行/大法輪閣
『歎異抄』金子大栄校注岩波文庫
『正法眼蔵』鴻盟社
方便品第二
『法華経(上)』坂本幸男・岩本裕訳注/ワイド版岩波文庫
『大乗仏典4法華経Ⅰ』松濤誠廉・長尾雅人・丹治昭義訳/中央公論社
『妙法蓮華経並開結』法華経普及会編/平楽寺書店
『新訳仏教聖典』木津無庵編/大法輪閣
『仏教聖典』仏教聖典刊行会/平楽寺書店
『現代語の法華経』庭野日敬/佼成出版社
『原始仏典四・ブッダのことば』一対の思い(双考経)/関稔訳
談社出版研究所
『わたしの生涯』ヘレン・ケラー/岩橋武夫訳/角川文庫
『冬の紳士』大佛次郎/講談社(文庫コレクション)
『佛教大事典』小学館
『シッダールタ』ヘッセ/高橋健二訳/新潮文庫
『教師宮沢賢治のしごと』畑山博/小学館
『名演奏のクラシック』宇野功芳/講談社現代新書
『週刊朝日百科/動物たちの地球1大自然の不思議』日高敏隆/朝
日新聞社
『人と思想コルベ』川下勝/清水書院
『奇蹟』曽野綾子著/文春文庫
『モーツァルトの手紙』吉田秀和編訳/講談社
『原始仏典一・ブッダの生涯』―大いなる死(大般涅槃経)/岩松浅
夫訳/講談社出版研究所
譬喩品第三
『法華経(上)』坂本幸男・岩本裕訳注/ワイド版岩波文庫
『正法眼蔵』鴻盟社
『シューベルトー孤独な放浪者―』ひのまどか/リブリオ出版
『破門の哲学―スピノザの生涯と思想―』清水禮子/みすず書房
『日本の禅語録十九白隠』鎌田茂雄/講談社
『宇宙からの帰還』立花隆/中公文庫
『法華経の風光第二巻燃える家』紀野一義/水書坊
『高齢化社会』吉田寿三郎/講談社現代新書
『この国は恐ろしい国―もう一つの老後―』関千枝子/農山漁村文化
協会
『世界文学全集15テレーズ・デスケールー』遠藤周作訳/集英社
『グレアム・グリーン全集12情事の終り』永川玲二訳/早川書房
信解品第四
『法華経(上)』坂本幸男・岩本裕訳注/ワイド版岩波文庫
「原始仏典一・ブッダの生涯』―成道から伝道へ(律蔵大品六)畝部
俊英訳/講談社出版研究所
『仏教説話大系2~3釈尊の弟子たち(1)~(二)』仏教説話体系
委員会著/中村元・増谷文雄監修/すずき出版
『聞き語りお釈迦さまのお弟子たち1~3』
薬草喩品第五
『法華経(上)』坂本幸男・岩本裕訳注/ワイド版岩波文庫
『宇宙からの帰還』立花隆/中公文庫
『母性社会日本の病理』河合隼雄/中公叢書
「原始仏典一・ブッダの生涯』―成道から伝道へ(律蔵大品一〇~一
四)一畝部俊英訳/講談社出版研究所
『宮沢賢治全集I』ちくま文庫
『内観への招待』本伊信/朱鷺書房
『NHKこころをよむ華厳経』鎌田茂雄/日本放送出版協会
『右脳と左脳脳センサーでさぐる意識下の世界―』角田忠信/小学
館ライブラリー
『日本人の脳脳の働きと東西の文化』角田忠信/大修館書店
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
