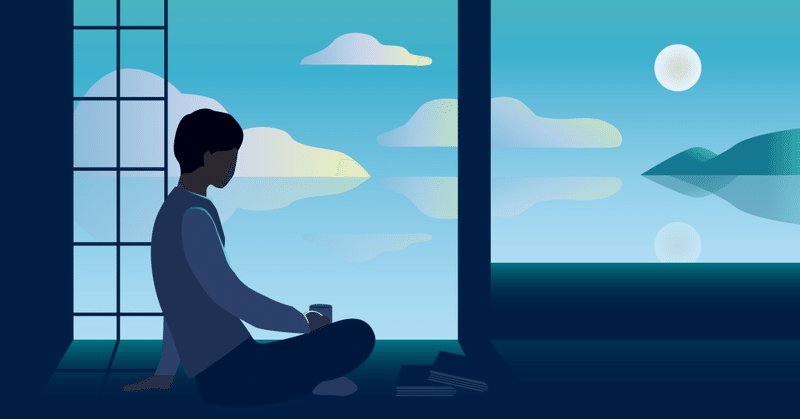
週休3日を考える(4)
12月24日の日経新聞で、「ランボルギーニ、週休3日 欧州製造業、導入広がる」というタイトルの記事が掲載されました。日本でも一部の企業で制度化される例があるものの、まだ一般的にはなっていない週休3日制について、欧州では広がっているという内容です。
以前も週休3日のテーマで考えたことがありますが、今回改めて考えてみます。
同記事の一部を抜粋してみます。
イタリアの高級スポーツ車、ランボルギーニが工場で働く従業員に週休3日制を導入する。労働時間が減るが賃金水準は逆に引き上げる。オフィスワーカー以外での適用は世界的に珍しい。ドイツの鉄鋼業界でも工場で賃上げと週休3日を可能にするなど、働き方の新常態が欧州の製造業でも広がりつつある。
ランボルギーニはこのほど労働時間の削減と子育て支援などを盛り込んだ協定で労働組合と暫定合意した。土日などの休日に加え、2交代制の工場従業員は2週間に1日、3交代制では3週間に2日、金曜が新たに休みとなる。それぞれ年22日間、31日間の労働時間削減となる計算だ。
月給は据え置いたうえで、変動賞与額を50%引き上げ12月中に1人あたり1063ユーロ(約17万円)の一時金を支払うため、賃金水準は上がる。正式な協定を作成し、成立すれば少なくとも2026年まで適用する。
フランスの眼鏡メーカー、エシロール・ルックスオティカもイタリアの工場従業員を対象に週休3日制を試験導入することで労組と合意した。年20週を対象とし、賃金水準は据え置く。
欧州最大の産別労組IGメタルはドイツの鉄鋼業界に対し、工場従業員の週の労働時間を35時間から、週休3日に相当する32時間に短縮するよう求めた。労使交渉の末、5.5%の賃上げに加え、週35時間が標準労働時間のままだが、33時間分までの賃金補償を盛り込んだ32時間労働を可能とする協定で12月中旬に合意した。
ワークライフバランスの意識が高い欧州では2010年代から賃金を保ちつつ労働日数を減らす試みが広がった。英国では22年、61社が「賃金100%、労働時間80%」を目安に週休3日制を試験導入。生産性が向上したとして92%の企業が23年以降も制度を続けている。ドイツやスペイン、ポルトガルでも同様の取り組みが始まっている。
日本でもZOZOなどが週休3日制を導入する。ただ欧州も含め、賃金据え置きで週休3日制を取り入れる企業は柔軟な働き方が可能なオフィスワーカーが中心だ。シフト制が原則で、勤務時間が生産量に直結する工場従業員は対象外だった。
こうした状況が変わりつつある最大の理由は欧州製造業の人材不足だ。欧州委員会によると、人手不足が原因で生産を制限する欧州連合(EU)メーカーの割合は、機械業界が29%(23年四半期平均)、自動車業界で同24%と1991年の調査開始以来、最多だった。
これから急速に週休3日が広まることは想定しにくいですが、労働時間短縮の流れは基本的なトレンドとして続きそうです。日本もこの影響は受けることが想定されます。
同記事から2つのことを感じました。ひとつは、自社の商品・サービスの付加価値の高さ、情緒的価値がますます大切になるということです。
商品・サービスがもたらす価値について、「機能的価値」と「情緒的価値」の観点から語られることがあります。「機能的価値」とは、商品・サービスの品質や機能がお客さまに提供する価値のことです。「情緒的価値」とは、その商品・サービスを体験したときに、顧客が感じる精神面での価値のことです。「その商品・サービスを使うと、どんな気分になるか」と言い換えることもできます。
世の中で「ブランド品」と言われる商品・サービスがあります。確かに、モノはいいのだろうと思われますが、類似の商品・サービスと比べて本当に値段の差ほど価値があるのかと言われると、理屈では答えられないことも多いものです。「○○というブランド名で納得・満足しているから」としか説明ができないことがあります。
ランボルギーニはその典型だと思います。消費者は、ランボルギーニの値段に見合う品質や耐久性(機能的価値)だけを求めて買うわけではなくて、ステータスや雰囲気(情緒的価値)で買っているわけです。
ランボルギーニを買うような人は、「値段が上がったから」といって買い控えをしようとはしないでしょう。よって、値崩れしませんし、強気な値上げも可能です。だからこそ、従業員の賃金水準を引き上げた上で休日を増やすことが可能だと言えます。
これが、情緒的価値を伴わない商品・サービスだと、値段の維持や値上げをすることが難しくなります。よって、従業員の休日を増やす=生産量を減らすなら、賃金水準はよくて維持、通常なら休んだ分引き下げとなるはずです。
汎用品になればなるほど、商品・サービス間で品質などの機能性には差がなくなっていきます。残るのはブランドに関するストーリーの違いのみ、という商品・サービスも少なくありません。自社としてのブランドストーリーを訴求できるかどうかの重要性はますます高まると考えます。
2つ目は、日本においてもますます労働供給力は減退し、アジア圏の労働供給力との差異が広がる可能性があるということです。
2023年11月28日の日経新聞記事「IT大国インドにもモーレツ主義? 出社や労働時間巡り論争」では、次のように紹介されていました。(一部抜粋)
インドのIT(情報技術)産業で、労働環境を巡る議論が盛んだ。新型コロナウイルス禍を機に在宅勤務も広がったが、大手で出社回帰の動きが進んでいる。労働時間を巡っても、インフォシスの創業者が「週70時間労働」の必要性を訴えて論争を呼んだ。
インド大手財閥タタ・グループ傘下のIT大手TCS(タタ・コンサルタンシー・サービシズ)は10月に開いた決算記者会見で、このほど社員に在宅勤務でなく出社を求めるようにしたと認めた。
TCSのミリンド・ラッカド最高人事責任者(CHRO)は出社の重要性について「TCSの価値観や方法を学んで理解し、身につけられる唯一の道だ」と語った。「顧客と従業員にとって何が最良か引き続き検討していく」とも述べたが、すでに社員の7割がオフィス出勤に戻っているという。
インドでは新型コロナの発生により、政府が厳格なロックダウン(都市封鎖)を実施した。外出自粛で在宅勤務が広がり、特にIT企業での導入・定着が顕著だった。しかしインフォシスやウィプロなどのIT企業でも、出社奨励へ回帰する動きが出ているという。
足元で話題になっているのは、在宅勤務の可否だけではない。「若者には『私は週70時間働きたい』と言ってほしい。これがまさにドイツと日本が第2次世界大戦後に実施してきたことだ」。10月にインターネット上で公開された対談動画で、インフォシス創業者のナラヤナ・ムルティ氏は仕事熱心な姿勢がインドの成長に不可欠だと訴えた。
ムルティ氏は英国のスナク首相の義理の父としても知られる。インドの労働生産性の低さなどにも苦言を呈したが、とりわけ「週70時間労働」に関わる発言が注目を集めた。
国際労働機関(ILO)の統計によると、インドの労働者1人あたりの労働時間は週47.7時間だった。すでに日米中より長く世界でも上位の水準にあるとの指摘も出たが、他の経済人から「インドと先進国は状況が違う」との声も寄せられた。
配車アプリや電動二輪「オラ」などの事業を手がけてきたバービッシュ・アガルワル氏もX(旧ツイッター)で「70時間どころか140時間だ。週末はない」と投稿した。
欧州や日本はいかに労働時間を減らすかの議論が盛んですが、インドでは必ずしもそうではなく、いかに労働時間を増やすかの議論すらあるということです。同記事の経営者のような考えは一部の方に限られるかもしれませんが、日本ではこのような発言が出ることすら考えにくいでしょう。労働時間が長いことは必ずしも良いことではなく、その是非についてここでは触れません。
そのうえで、ひとつ言えそうなことは、「経済先進国と言われる地域は労働時短に熱心だが、新興国と言われる地域はそうではない。むしろ貪欲に長時間労働を受け入れる土壌も相応にあるかもしれない」ということです。
仮に週70時間労働するとなると、週35時間程度の労働時間を目指す欧州や日本の倍となります。もしそうなれば、人口約14.2億人のインドと1.2億人の日本における労働時間の差は、28.4:1.2かもしれないということです。
これぐらいの圧倒的な労働供給力の差の中で経済活動・企業活動を営んでいく、その中で何をすべきかを考えないといけないという外部環境は、視野に入れておくべきだと思います。
<まとめ>
圧倒的な労働供給力の差異に対応していくうえでは、商品・サービスの「情緒的価値」をいかに出せるかがカギかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
