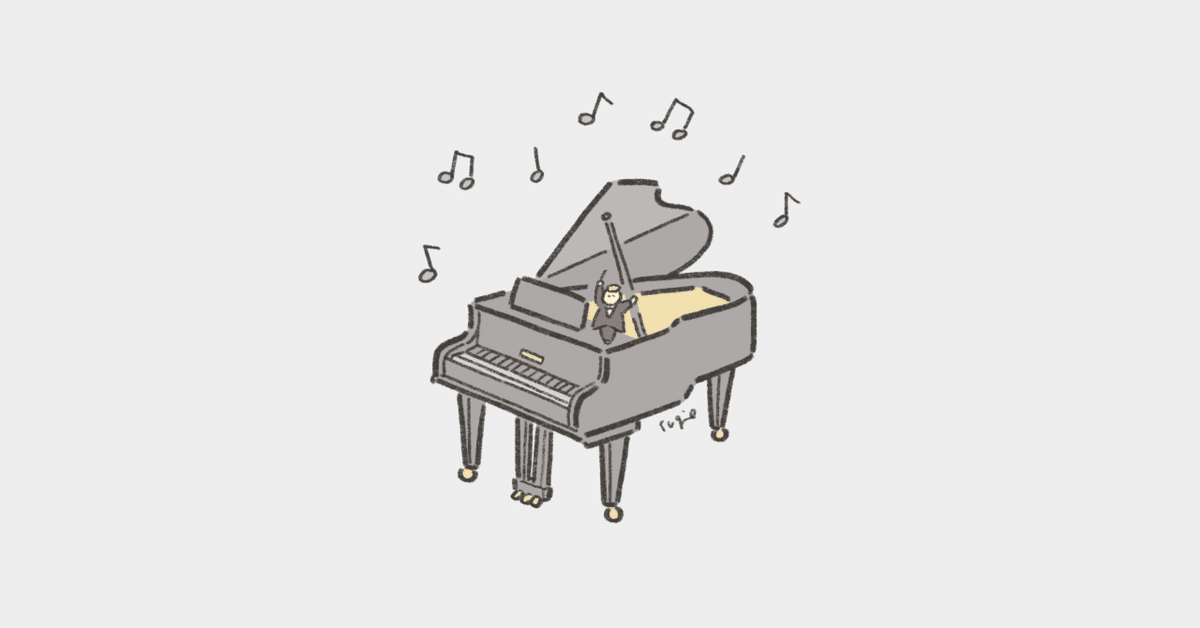
vol.6 どのような教室をつくるか
大学期間にスポットライトを当てたnoteは最後になります。
前回はキャリア選択について書きましたが、今回は学校現場に入った後のVisionについて書きます。
Visionと言っても、様々な粒感の捉えがありますが、今回は「どんな教室を(子どもたちと)つくりたいか?」という問いで言語化します。
もちろん、子どもたちと共に創ることを大切にしたいので、実際は対話しながらですが、自分の軸を持っておくことは必要だと確信しています。
確信の背景にあるのは、実際に現場に赴任した先輩方の声です。
・めまぐるしく過ぎていく日々の中で、どうしても簡単な方、楽な方にアクションを取ってしまう
・目の前のいろんな仕事に追われる中で、やりやすい方に流れる
現場に入ると目の前のことに必死になり、大切にしたいこと、子どもたちに伝えたいことが見えなくなってきます。
そんな時に、このnoteを読み返して「やっぱり自分が目指したいのは、この方向性だった」と自らの学習観に立ち返るためにも、育んできた自分の軸をアウトプットすることにしました。

自他を価値ある存在と実感できる教室
第一の軸は「認知的な能力に関係なく、安心して学ぶことができる場」というユニバーサルデザインの観点です。
学びにつまずきのある子の中には、失敗への恐怖が強いため難しいことを回避する傾向があります(学習無力感)。
そして、大事なのは認知的な能力に関わらず、自己有用感が低い子どもが多くいることです。間違いに敏感な子に共通するのは、自身の自己肯定感が育まれていないからです。
では、どのように「間違いから学ぶことができる場」をつくっていくか。
色々とhow toベースでも考えてますが、試したい仮説としては「批評する文化」です。
お互いに批評できることで、子どもたちが互いの価値を認め合い、助け合う雰囲気が生まれます。そのような教室環境をつくるのが自分の役割だと思います。
学習の評価を教師からできる限り手放し、自己評価、ピア評価などの生徒同士がお互いに評価をするようにすることで、子どもはより主体的に自分を知り、他者を理解しようとするようになる。
自分と向き合うことは、できない自分や間違いから逃げようとする自分と出会うことでもあります。そんな時に、自分なりに考えて改善のサイクルを回したり、他の子どもにサポートを求めたり、協同してそれぞれの課題を乗り越えたり。
このような学びのプロセスを生み出す環境をつくることで、比較して互いを下げる文化ではなく、自他を価値ある存在と実感できる教室を目指したい。
オーセンティックな思考や実践が生まれる教室
オーセンティックな学びとは、「具体的な本物の場面に即して学びをデザインすること」を意味しています。
例えば、「バスケットボール」の能力を評価する場面を考えてみます。ドリブルやパス、シュートといった個々のスキルがうまいからといって、本物の試合で上手にプレーできるとは限りません。本物の試合で活躍するには、刻一刻と変化する試合の状況のなかで、いかに適切にスキルを選択できるかといった判断力や、いっしょにプレーする仲間との協調性などが必要です。
つまり、スキルや事実を基盤とした2次元のカリキュラムと指導ではなく、概念的理解を基盤とした3次元のカリキュラムが求められると言えます。
僕自身は、教科内容を教えることよりも、教科を通して力をつけることに関心があるため、教科をまたいだ抽象的な力(概念)を授業の中心に置き続けたいと思います。
下記書籍の表現を引用するならば、
「カリキュラムを教科の重要かつ転移可能な理解を中心に構成すれば、考え(理解)を実証する関連事実やスキルの選別が容易になる」
そんな授業づくりを自分自身が探究していきたいと思います。
どれだけ授業準備に追われようとも、以下の3点は明確にした上で、子どもたちが学びに対して深く、ひたむきな好奇心を持つように、子どもたちの感情、創造性、知性に働きかけたい。
①事実として知ってほしいこと
②概念的に理解してほしいこと
③スキルとプロセスを使ってできるようになってほしいこと
「自律」とゆるやかな「協同」が共存する教室
個別最適な学びと協同的な学びは、どのようなプロセスを通して一体的に充実するのでしょうか?
協同の前に、独自学習、つまり、個人による深い探究がある。
だからこそ、まずは一人ひとりが学びにとことん関わることが大切になる。
ひとりでどんどん深めていく、いい意味で煮詰まってくる。
すると、同じように学んでいるお友達の考えを聞きたくなる。
自律的な学びをサポートする多種多様なツールはありますが、そこから、ゆるやかな協同を生み出すのは、まだ全くイメージできていません。
幼児教育のモデルは完全に個別最適的な学びであり、環境による教育である。そして、特別支援教育のモデルは、個別最適な学びと協働的な学びにつながる土台ではないか。
最近、そんな仮説が生まれたので、特に幼児教育については今後の探究テーマになりそうです。
最上位目的を決める意味
では、上に書いたようなことができるの?、少し抽象論すぎないと。
「できないこと」と「目指さないこと」は全くの別物。
そして、自分が納得できる根本的な考え方(原理)を置いて初めて、その「内実」を力強く具体的に考えていけるようになると言える。
逆に、この抽象的な原理が明らかにならなければ、わたしたちは、社会・教育構想のために、何をどこから考えていければよいか分からなくなってしまうのである(110ページ)。
このnoteも、根本的な原理を置くための1つの雪かき作業だと思います。
自らの在り方
表現者は、どこか不完全を持っている。
プレシャーを感じながら、舞台に上がることが一番真摯である。
自分の表現をぶつけようとすると、批判も1セットでついてくる。
最近すごくプレシャーを感じることが多いです。不安は尽きません。そして、批判を恐れる自分もいます。
特に評価を手放すことや、抽象的な力を評価対象にするのか?というところは賛否が分かれると思います。
不安を感じる自分を受け止めつつも、まずは自分が教員という仕事にやりがいと誇りを持つこと(クラフトマンシップ)。そうすることで、クリエイティブな授業が生まれ、クリエイティブな子どもが育つ。
そんな背中は、どんな現場であっても一貫していきたいと思います。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
