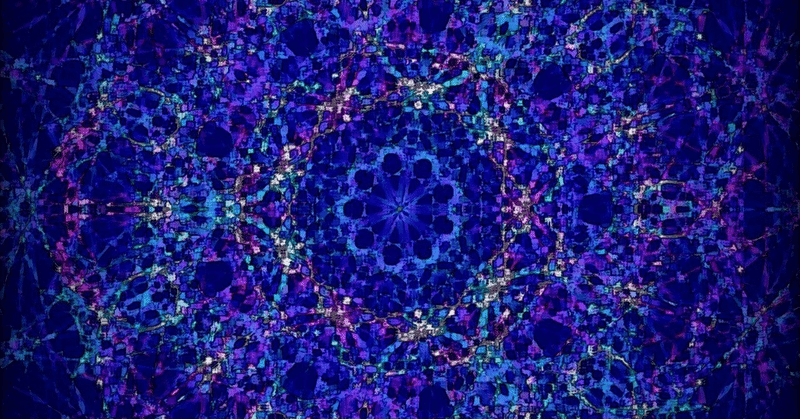
じぇらしぃ #7/7完
売れない小説家の私は、若い女編集者に担当が代わったのを機に一念発起。仕事は順調そのものでしたが、思いがけず妻の日記を盗み読み、自身の存在についての真実というものに重大な疑念が生じるのでした。
「お着物なんて、なん年ぶりかしら」
そういって妻は笑うのでした。そんな晴れやかな笑顔を見せたのは、それこそなん年ぶりのことかわからない。赤と黄の大振りの薔薇が満遍なく配置されその余白を深い青の葉叢が埋める銘仙に、ローズピンクの繻子地に薔薇と小鳥の刺繍の施された名古屋帯という合わせ。
「奥様、ほんとにステキだわ」
本日なん度目かのお愛想を口にするTもまた和装。こちらは白地に赤黒鼠の三色の水玉散らした銘仙に、臙脂と黒の市松格子の兵児帯を前結びにしたモダンな出で立ち。こちらはこちらで素敵にちがいないけれど、年増のほうにやはり軍配は上がる。古色になずむのが伝統というもので、Tの腰の位置が分配的にやや高過ぎる感があるのに比して、妻の着こなしにはしかるべき安定感が備わっている。この人も着物がしっくりくる年齢にいつか届いていたのかと、今更のように感慨深いのでした。
ホテルをこっそり抜け出したのはKのアイデアでした。両手に花では自分としてもバツが悪いし、授賞式に出席していた老小説家と老評論家とについて、あのふたりが犬猿の仲であるのは文壇で知らぬ者はなく、二次会以降も彼らが同席するようなら関係者は受賞者そっちのけでふたりのご機嫌取りに奔走するはずで、そうなればTと妻とがコンパニオン役を担わされるのは必至とKはいうのでした。案の定、先にホテルのラウンジへ案内された老小説家のほうが、「早く今日の主役をここへ連れてきなさいよ!」と誰かに声を荒げるのが聞こえてきて、ホトホト顔で見交わす周囲にあって、Kばかりは蒼白になって緊張するようでした。
「あら、おもしろそうじゃない」
妻がいうのへ、後ろからそっと袖を引いて首をかすかに横に振ったのはほかならぬT。つまらないことになる、と顔にありありと書いてあるのでした。
着付けのお直しとかなんとか口実設けてトイレへ向かうふりして袖を引かれるままエントランスを出ると、車回しに停まった先頭のタクシーの助手席から窓越しにKがさかんに手招きする。ふたりして大童になって後部座席に乗り込むと、車はゆるゆると滑り出した。とたんに誰からともなく吹き出して、いつか車内を一同の哄笑が包んでおりました。ふと窓外を見やると、並木の葉桜の樹冠の上、藍を流したような空にひときわ明るく輝く星がひとつあるのを認めて、ようやく妻は人心地ついたのでした。
さる伯爵の別邸が戦後払い下げられて、その白亜の豪邸を改修してなった老舗の洋食屋へKは皆を案内するのでした。そこの三階にあるテラスを借り切ったというのだから相当の散財だったでしょう。いえいえ、あなたへの御恩は、こんなことでお返しできるものでは到底ございませんとKはいうのでした。レストランは山の手の高台にあって、テラス側は東京に珍しく、広々と開けて眼下にパノラマを展開するのでした。瀟洒な住宅の屋根屋根が緩勾配を下っていき、平地のはじまる際から徐々に建物は高さを増しながら立て込んで、ちょうど窪地の中央に位置する按配に先刻までいたホテルのガラスの塔が似たようなビルを三、四としたがえて屹立し、それらビルの谷間から明々とともる巨大な灯、ライトアップされた東京タワーがぬっと姿を現して、一同思わず声を上げた。
「ここからがほんとうのセレブレイションですよ」
パノラマの真向かいに座る妻の耳元にKがささやくと、折しもボトルが台車に載って運ばれてきました。ステンレス製のワインクーラーの凸面に、夜景が引き伸ばされている。
「あなたの御生誕年のシャトーマルゴーとも思いましたけど、ふだんフランチャコルタをお飲みになるようですから、シャンパンがよろしいかと思い直しましてね」
ウエイターがバケツから瓶を取り出してラベルを差し向ける。
「2006年のクリュッグでございます」
「その出来栄えから異名を持つシャンパンです。〇〇と〇〇。〇〇にはそれぞれ漢字ふた文字が入ります。あなたにピッタリだと思ってご用意したのです。どうです、お当てになっては」
「天使と悪魔」
いかにも妻らしい即答ぶりでした。妻はどんな場合も逡巡するということがないのです。会話とは間合いを含むものでありその機微をこそ楽しむものであってみれば、この性急ぶりはいま目の前に醸成されつつある親和的な空気にときとして水を差すことになりかねず、かねてから冷や冷やさせられるところではありましたけど、今宵の彼女は主賓ですし、KもTも気心は知れております。年下の利かん気の娘に面食らうような素振りを大仰に見せながら、
「なんともあなたらしいお答えですね。わたしもいつか、そんな名前の逸品に預かりたいものです。ところでこちらは」
Kがウエイターへ目配せすると、
「奔放と寛容、でございます」
年嵩のウエイターは落ち着き払ってそう答え、銘々のバカラに黄金の三鞭酒を注いでいくのでした。
「『細君モノ』としては、空前のベストセラーになるかも知れません」
Kはいうのでした。
「太宰も谷崎も死後に配偶者や愛人の手記やらエッセイやらがいくつも出ましたけどね。そこまで売れたわけではないし、どれも文学的価値が高いわけではなかった。武田百合子はちょっと別格でしょうけど、あなたの場合も、誰それの妻という肩書きを離れて、あなた自身の個性として独り立ちする可能性が十分にある。このたびの日記小説は極めてスキャンダラスで、ミステリとしても異彩を放っています。改めて、その才能を祝福させてください」
「ありがとうございます」
「T君も、ここまでよく頑張ってくれました」
「ありがとうございます」
Tはかすかに涙ぐむように見えました。
「それから先生にも、ぜひとも御礼をいわなければ」
「ほんとうに」
「ほんとそうね」
Kが妻とTへ二杯目を注ぎ、自らの杯へも注ぐと、ふたたびの「乾杯」を合図に三人してグラスを掲げ、それから申し合わせたように片目を瞑り、泡立つ液体越しに彼方の東京タワーを覗き込むのでした。そうして目を宙へ泳がすと、三人同時に私の視線をとらえる瞬間が訪れて、
「あれ、いまそこに、先生が……」
と口々にいい合った。
*
(俺ダッテ賞ヲモライタカッタ! チヤホヤサレテ、タダデくりゅっぐ飲ミタカッタヨ!)
そう私は駄々をこねるのでした。
(絶対ニ恨ンデヤル! 絶対ニ呪ッテヤル!)
そうもいい募って忿怒をあらわにするのです。私は書斎で布団巻きの刑に処されて天井から吊るされて、首から先と膝から先とを覗かせたきり、まったく身動き取れないのでした。
(クソッ! 俺ヲコンナニシテオイテ、アイツラバカリ楽シンデイヤガル。コンナコト、許サレテタマルモノカ!)
「でもね、先生、もう締切は過ぎてるんですよ。原稿をまた落とすわけにはいかないでしょう。明日の十五時まで待ってくれると向こうはいってくれてるんです。死ぬ気で書かなければ、ね、三十枚」
(オマエハソンナトコロデナニヲシテイルノダ)
「待ってるんです」
(ナニヲ)
「先生の談話に決まってるじゃありませんか。今回は私が筆記を買って出たんです」
(アイツハイツ帰ルノ)
「わかりません。あるいは今夜は帰らないかもしれない」
(オマエハソレデイイノカ)
「うーん、いいも悪いも仕方がないでしょう。今夜はあれの晴れ舞台ですし、その間も誰かがお相手しなければならないんですから」
(カタジケナイ)
あの手この手でなだめすかして私をその気にさせようとするのですが、どうにも今宵は気が乗らぬようで、ウンウン唸って搾り出そうとして、口を開けばドロドロとまた始まる愚痴やら恨み節。詰ろうものなら臍を曲げるとこちらもよくよくわかっているから、ここは我慢のしどころで。
(ドンナ苦シイ、例エバ労働ニシテモ、病気ニシテモ、永クソノ苦痛ヲ続ケテイルウチニハ、飽キテ来ル。人生ノドンナ好イ刺激ニモ飽キテ来ル……)
「物語のタネが必要ですか」
(ソウネ。アルニ越シタコトハナイダロウネ)
「こんなのはどうです。さる街なかの高層ビルの屋上から、女子高生が飛び降りた。ところがこの自殺、不首尾に終わる。高さがビルの半ばまで来て、途端に落ちゆく軀体は減速して、しまいは鳥の羽のごとくふわりと地面に着地した。それ以来、この国では人は自由落下し得なくなる」
(アア、自殺者ガ生還スルト、死ナズニ済ンダト喜ブノガ大概ラシイネ。イッポウデ、りとらいシテ完遂スル輩モ少ナカラズイルトイウカラネ。ソレデソノ女子高生ハドウシタノ)
「恥じるんです。なにせ大勢の人間に見守られてゆっくりと地面に着地したのだから」
(すかーとガメクレテぱんつガ丸見エニナッテイタトカネ。チョットイイ話ジャナイノ)
「バッドエンドでもハッピーエンドでも、どちらにも振れますでしょう」
(イッソ、ウント馬鹿馬鹿シクテ、底ナシニ明ルイモノガ、書キタイナ。アイツラノコトヲ思ウト、ムシャクシャシテショウガナイガ、ソウナルト、ナンダカ俺ラシクナイモノヲ書イテミタクナルンダネ)
「ああ、その調子、その調子。書きたいものを書きましょうよ。そのほかのことはなんにも考えず。先にタイトルから決めましょうか」
(オマエコソ、モット、自由ニナレヨ)
こんなふうに、私は私を慰める。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
