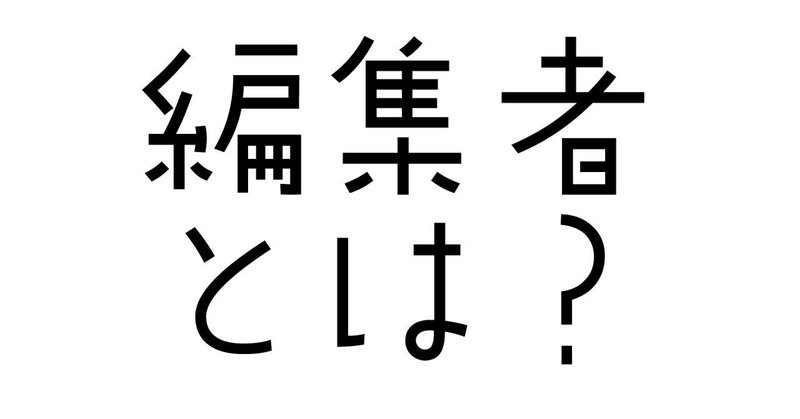
【出版の裏側】「編集者」の定義がむずかしい件
ソニーと小さな町工場が、同じ製品を市場に売り出すことはないだろう。テレビを町工場で作り、売り出すことはむずかしい。ところが出版はまったくちがう。書籍という形式はみな同じである。机ひとつ電話一本の出版社も、1000人の出版社も、同じかたちのものをつくれる。そして現に同じ市場で競争している。しかも大手が勝つとは限らない。電機とか自動車といった産業とはちがう側面をもっている。
この一文が好きです。
これは講談社で活躍した鷲尾賢也さんという編集者が書いた『編集とはどのような仕事なのか』(トランスビュー)という本の一節。
いま手元にあるのは2004年初版のもの。
10年後に新版が出ているようです。
編集者向け(しかも書籍編集者!)ということで、きわめて読者対象が狭いため、ベストセラーにはなりにくい。しかしながら、版を重ねて商品としていまなお流通しているところが嬉しいですね。
それもそのはず。
これほど「編集者」というものの本質をとらえ、エピソードを交えて読ませながら、微に入り細に穿つ本はありません。
以下「これは的を射たり」という箇所をご紹介します。
編集とはなにか
テレビドラマでは
編集とは何か。このように大上段に問われると、どうしてもいいよどんでしまう。日ごろの事を振り返れば、忸怩たる思いが先に立ってしまう。たいしたことはしていない。優れた著者がいれば、編集者などいなくてもそれほど支障はないからだ。
しかし、仕事としての編集者の内部に立ち入ってみると、なかなか複雑なものがある。いわくいいがたさがあり、それは体験してみないとわからない、といわざるを得ないところがある。
出版社を舞台にしたテレビドラマをときおり見かける。よく怒鳴る編集長が登場し、デスクなどにだらしなく足を放り出している。また美人の敏腕編集者がかならず出てくる。はっきりパターン化しないと、見ている人にはわからないので仕方がないことだが、正直いって違和感は否めない。
かならず酒を飲み交わす場面が出てくる。まあ大きくはまちがっていないが、編集部そろって、毎日のように飲んでいては仕事にならない。当たり前のことだ。もっと地味な日々の作業がある。それは、テレビではどうしても表現できないことだ。
(中略)
じつは私は一般企業からの転身組である。大学卒業後、キヤノンに二年弱つとめ、そののち途中入社で出版社に入った。小さいときから知っている近所のガラス屋のおじさんから、「せっかくいい会社に入ったのに、とうとう鷲尾さんの坊やも水商売になった」といわれた。これは三十数年前の常識なのである。しかし、その言葉は、いまでもそれほどまちがってはいないと思う。
出版は不安定な職業である。少数の大手出版社を除けば、経営基盤が安定しているとは逆立ちしてもいえないからだ。近年は大手出版社も苦しくなっている。また労働環境も千差万別。たしかに給与水準の高いところは存在する。しかし一方で、出版社の大部分を占める中小はお世辞にも高給とはいえない。劣悪なところすら珍しくない。それが同じように出版社と呼ばれている。
ソニーと小さな町工場が、同じ製品を市場に売り出すことはないだろう。テレビを町工場で作り、売り出すことはむずかしい。ところが出版はまったくちがう。書籍という形式はみな同じである。机ひとつ電話一本の出版社も、1000人の出版社も、同じかたちのものをつくれる。そして現に同じ市場で競争している。しかも大手が勝つとは限らない。電機とか自動車といった産業とはちがう側面をもっている。
また、編集者とひとくちにいうが、それも一様ではない。定義が、だからとてもむずかしいのである。
たとえば辞書の編集者と女性週刊誌の編集者。おなじ編集者である。しかし仕事の中身はかなりちがう。片方は長い時間をかけて(10年単位も珍しくない)のデスクワークである。地味を絵にかいたような業務だ。週刊誌はそれこそ毎日追われている。1週間たてば次の取材、というわけだ。ある意味でむなしいところもある。
コミック編集と学術書の仕事でも、それこそ天と地ほどの差があるだろう。何百万部という発行部数が、一方では日常的だ。しかし学術書など、よくて2000~3000部。もっと少部数の場合も十分あり得る。後者は、とてもテレビドラマの舞台にはならない。
文芸編集とファッション誌編集の違いでも、同じことがいえよう。作家に密着していかに書かせるかということが文芸編集者の主な仕事であるのに対し、モデルや、スタイリスト、カメラマンなどとの撮影に多くの時間を割くファッション誌編集部。両社は同じ出版社のなかでもあまり接触がない。
つまり出版は、規模も、対象とする領域(医学や科学・技術だけを対象にする専門出版社もあれば、コミックだけの出版社もある)も、じついに多様なのである。それらをひっくるめて出版というから分かりにくくなるのだ。それが雑誌、書籍という形式(誰がつくろうとも同じかたちになる)のなかで競争しているのである。
以上は、編集者を一言で定義づけられない理由の背景である。
一個の人格として
編集とは何か。そのストレートな問いに答えてくれる書物は意外にすくない。よくいわれるのは、黒子、あるいは触媒。イメージとしてはなんとなく分かるが、どうも十分ではない。仕事がら、編集論とか編集者の回顧録などを読むことは多い。今回それらを渉猟してみても、あまりはっきりした姿はみえてこなかった。そのなかで気がついた点を一、二、あげてみよう。
編集者というのは、それぞれの個性とか人格とか、人生観だとか、また知識とか教養とか技術とか、さらに日々の生活の仕方なども含めて、いわばその人の持っているものすべてを総動員して、専門家である著者や、本を直接作る人びとと関係していく仕事であろう。奇妙ないい方になるが、どれひとつということではなく、すべてが総合された一個の”人格”が、編集者には必要だということである。考えてみれば、編集者なるものも、数多く世の中に存在する職業のなかのひとつであって、これのみが“志”を問われたり、とりたてて何かをいわれることもない気がするが、編集者のありようがさまざま問われるのは、著者という一個の精神と対面し、かかわり、それを”本”という形で読者に手渡すという、いわば知的で人間的な構想力を編集者が要求されるからである。
何よりも心得ておかねばならないのは、編集者が作品に何かをつけ加えることはないという点です。編集者にできるのは、せいぜい作家の手足となって奉仕することだけです。自分自身が重要な役割を果たしていると思うのは禁物です。編集者は何ひとつ創造するわけではなく、そこにエネルギーを投入するぐらいのことしかできないのです。
松本晶次さんは、埴谷雄高、花田清輝、平野謙、橋本文三、杉浦明平、野間宏といった著者を担当した名編集者である。またパーキンズは、ヘミングウェイ、スコット・フィッツジェラルドなどを発掘した文芸編集者である。彼らのいう編集者、編集に対する認識はたしかにそのとおりなのであるが、現代日本の出版において、定義がそれで十分かといえば、そうとはいえない。
いい悪いは別にして、ここ10年間のコンピュータを中心にした技術変化、印刷から来る技術革新とコスト管理、取次・書店などの流通の変貌、こういった外部的要因は、編集という仕事を大きく変化させている。さらにいえば、肝心かなめの読者がいままでのようではなくなっている。「読書」自体が試練にさらされているといってよい。よいものを作ればかならず読者に届くはずだ、という信念はいまもたしかに生きているだろうが、正直いって現実はそれほど甘くない。志や情熱、思いだけでは通じない事態が進行しているのである。
編集とは何かと問われたとき、つい口ごもり、ひとくちで言い表すことができないのは、そういった環境の変化にともなう仕事の範囲が、以前にくらべて広がっていることも大きい。取材、企画案作成、原稿依頼、原稿催促、入稿実務、ゲラ(校正刷り)のやりとり、刊行後の版版のための宣伝、売り込み、著者とのつきあい。おそらくこの流れは、以前と本質的に変わらないだろう。しかしそのひとつひとつが、かつてのように牧歌的ではなく、時間やコストを重視した、ある一定の管理の下に進行せざるをえなくなっているのである。
たとえば、企画が編集会議で通ったとする。するとふつうは正式な企画書を作り上げなければならない。著者、タイトル、狙い、読者対象、想定部数などとともに、編集側で考えたプロットなどを付記した文書を会社に提出する。そこで基本的に企画が成立し、著者に依頼してよいということになる。その企画案作成のとき、にわか仕込みかもしれないが、自分の教養が試されるのである。
次に著者に依頼する。そこでは相手を説得しなくてはならない。どうしても書いてもらわなければ困る。読者がその本をいかに待望しているかとか、多くの読者を獲得できるとか、あるいは意義・価値があるかといった説得材料をもとに、相手に「うん」といわせるのである。ここでは押しの強い商人的なもの言いや、なんとなく「そうかなあ」と思わせる宗教家的弁舌も必要になるだろう。
原稿を書く仕事はつらいものである。書くことが楽しくてしかたがないという人は少ない。だからどうしても原稿は遅れがちになる。そこで催促が必要になる。うまく催促し、原稿を完成させるのも編集者の手腕である。きつく督促すれば、著者の気分が損なわれる。しかし締め切りはある。やさしいことばかりいっていては仕事にならない。そこをどう進めるのか。これも編集者の重要な機能である。強引なサラ金的催促だけではむずかしい。
ようやく脱稿したとしよう。つぎはその原稿を書籍という形につくりあげる作業が待っている。どのような版面にするか、図版・写真の入れ方、目次の作り方、小見出し、そして装丁、それらのすべてにおいて、編集者のセンス・識見が問われることになる。このときがたぶん一番楽しいはずだ。しかし多くの場合、それほどのゆとりはない。猛烈な進行スケジュールのもとにこなしていくことになる。そして著者とのゲラのやりとり。数々の、まことに即物的な事務作業が待っている。職人的なさばきが必要になる。
なんとか完成した。つぎはそれを、より多くの読者に読んでもらいたい。PR活動、書評依頼、書店へのお願い。ここでは広告会社に似た仕事が、編集者を待っている。
幸せな結果ばかりではない。思ったより売れないことも多い。しかし、著者との関係はつづく。第二弾を書いてもらうのか、それともしばらく時間をおくのか。つまり人間づきあいの問題になるのである。
いま、一冊の本ができるまでを簡単にスケッチしてみたが、編集者がそのつどそのつど、相貌をかえていることが理解いただけるだろう。しかし、多様な側面に何かが共通して流れている、「一個の人格」が必要という松本晶次さんの思いは、このことを意味しているのではないだろうか。一個の人格のもとに、その場面、その局面でプロであることが要求される。そこにはじめて、編集者という具体的な仕事が立ち上がってくるのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
手元にある『編集とはどのような仕事なのか――企画発想から人間交際まで』(鷲尾賢也・著)は2004年3月の初版なので、実に18年前の本となります。
「編集者とは」の本質的な部分は変わらないでしょう。
40年経っても、50年経っても。
私は大学卒業後、ろくに就職活動もせず、百科事典の編集のアルバイトという仕事からこの業界に潜り込んだのですが、晴れて書籍の編集ができる出版社に入ったものの、そこは就業管理はガチガチな一方、本づくりにかんしてはクソ自由放任主義で、誰も仕事を教えてくれない環境でした。
だから、こうした先人たちの書籍や雑誌を貪るように読んでいた時期がありました。そんななかで手に取った1冊が『編集とはどのような仕事なのか――企画発想から人間交際まで』(鷲尾賢也・著)です。
著者のプロフィールを見てみましょう。
鷲尾賢也(わしお・けんや)
1944年、東京の下町に生まれる。慶應義塾大学経済学部卒業。1969年、講談社入社。「週刊現代」編集部をスタートに、「講談社現代新書」編集長、PR誌「本」編集長などを歴任。書き下ろしシリーズ「選書メチエ」を創刊し、また「現代思想の冒険者たち」(全31巻)、「日本の歴史」(全26巻)などの記念碑的な企画を世に送り出す。学術局長、学芸局長、取締役を経て、2003年退任。
「いい悪いは別にして、ここ10年間のコンピュータを中心にした技術変化、印刷から来る技術革新とコスト管理、取次・書店などの流通の変貌、こういった外部的要因は、編集という仕事を大きく変化されている」と書かれていますが、こうした傾向は18年前の当時よりもさらに加速しており、いまでは、電子書籍の編集、SNSの発信、WEB広告の運用、メルマガ配信など、インターネットのコモディティ化に伴うあらゆる「雑務」が編集者の仕事の多くの時間を奪っています。
「編集者」の定義についても、当時にはなかった「ウェブ媒体の編集者」というのがいまでは加わっています。ウェブ編集者もこれまでの編集者像とは相当異なる相貌をしているのではないでしょうか。
編集者はいわば「雑務の集積」のような仕事ではありますが、自分としてはこんなに面白い仕事はないと思っています。
形やインターフェースは変われど、編集者の本質は未来永劫変わらない。
そういう意味で『編集とはどのような仕事なのか』(トランスビュー)という本は今でもなかなか参考になるので、また後日ご紹介します。
(フォレスト出版編集・寺崎翼)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
