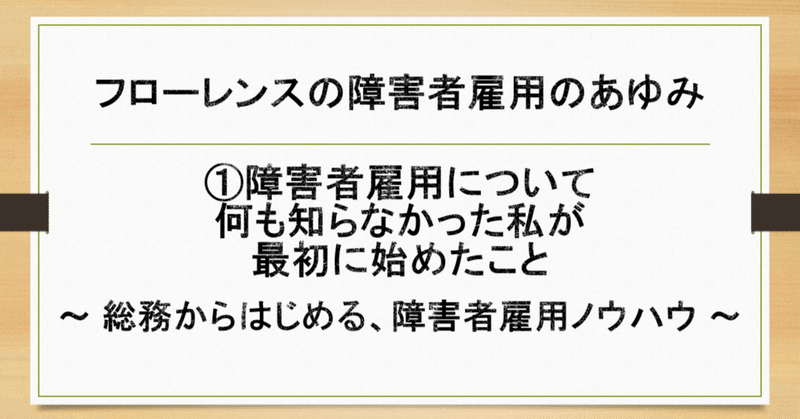
障害者雇用について何も知らなかった私が最初に始めたこと~総務からはじめる、障害者雇用ノウハウ~
はじめに(チームより)
フローレンスは、親子を取り巻く社会課題の解決を目指しているNPOで、現在、約700名が所属しています。多様なメンバーの「働く」を支えているのがバックオフィス業務を主に担っている働き方革命事業部、通称「ハタカク」です。
ハタカクは人事、経理、法務、総務、といった業務で構成されていて、障害者雇用チームも含まれています。フローレンスの事業を裏で支えるハタカクメンバーの業務や仕事への思いをnoteに投稿しています。
認定NPO法人フローレンスで、障害者雇用スタッフのジョブコーチ (*1)を担当し6年目となる石橋です。これまでの特別支援学校等からの採用者は7名とけっして数は多くありませんが、定着率は100%、全社から集める年間4,000時間近い仕事は単純作業から事務作業まで多岐にわたっており、各方面からその仕組みにご注目いただく機会も増えてきました。
フローレンスがどのように障害者雇用を立ち上げて運営してきたのか、成功したこと失敗したこと、そしてたくさんあった課題を振り返ってnoteでご紹介していきます。
これから、障害者雇用を立ち上げようとしている方への情報として、お役に立てれば幸いです。
フローレンスの障害者雇用チーム、通称「オペレーションズ」は、特別支援学校からの入社スタッフで構成したチームで、全社的な総務業務と、各事業部から依頼があったファイリングやデータ入力といった様々な業務を請け負っています。
*1「ジョブコーチ」 企業に在籍し、同じ企業に雇用されている障害のある労働者が職場適応できるよう様々な支援を行う人を、企業在籍型ジョブコーチといいます。
「はじめての障害者雇用担当」
障害者雇用制度も法定雇用率も知らなかった6年半前、当時の人事マネージャーから突然声をかけられました。「ねぇ。障害者雇用の立ち上げをやってみない?」同じ経験をされている方も多いと思うのですが、その声がけは唐突で「障害者雇用って…?」という「?」マークとともに一体どんな仕事になるのかという不安が先に立ちました。そのころの私が知っていた障害者雇用は、A型・B型と呼ばれる継続就労支援機関での就労であり、一般企業ではありませんでしたし、身体障害以外の障害を持つ人と健常者が一緒に働くというイメージは持てていなかったのです。
当時、私は赤ちゃん縁組事業部で意図せぬ妊娠で悩む女性への相談支援という、バックオフィスとはかけ離れた業務に携わっていました。自分に障害者雇用で活かせそうな経験があるのだろうかととまどいつつも、どこかワクワクする可能性のようなものを感じてマネージャーの声がけに「やってみます」と答えたことを覚えています。
「まずは研修受講」
声がけがあってから3ヶ月。2018年2月に赤ちゃん縁組事業部から障害者雇用の担当者として総務チームに異動しました。人事チームに前職で特例子会社に勤務していたメンバーがいたので、分からないことがあればサポートはしてもらえるということでしたが、直接障害者雇用に関わるのは私一人です。
すでに人事主導で支援学校から1名、紹介事業者から2名、計3名の4月入社が決まっている状況のなか、準備期間は2ヶ月しかありません。その期間で「障害者雇用スタッフのサポートの方法」を知ることが必要でしたので、まず実施したのは各種講座への受講申し込み。そして、Amazon検索で「障害者雇用」でヒットした本を数冊購入することでした。
※おすすめの研修、書籍は記事の最後にまとめています。
「情報収集」
今でも、障害者雇用関連の研修や勉強会があれば足を運ぶことと、障害者雇用に関する情報を逃さず読むことを心がけています。便利に活用しているのが「Googleアラート」。欲しい情報に関する単語を登録しておくことで、新聞記事やネットニュースでの該当情報を毎日Gmailで受け取ることができて、とても便利です。
「準備を通じて得たもの」
「すべての障害児家庭がなんにでも挑戦でき、笑って希望を描ける社会。」を目指して障害児保育事業を各種立ち上げて運営しているフローレンスにおいての障害者雇用は、障害のあるお子さんを育てているご家族にとって一つの未来想像図となり得ます。障害のあるスタッフを受け入れるための準備を進める中で、子どもたちとそのご家族がよりよい未来を想像できるように「働くことを楽しいと思える障害者雇用」でありたいという気持ちが強くなり、そのために必要なものは何かを考えるようになりました。
フローレンスの障害者雇用で大切にしていることをこちらの記事にまとめています。
■東京しごと財団
職場内障害者サポーター養成講座
2日間かけて障害者雇用の基礎から学べます。座学だけではなく特例子会社等の見学もあり、障害者雇用の現場を見ることができるので、初めて障害者雇用を担当する方もおすすめ。受講後、自社で障害者のサポートをする際に、支援員の訪問を受けて助言を受けることができる。
フローレンスでは障害者雇用担当者以外のスタッフも受講を推奨しています。
■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修
集合研修4日間、実技研修4日間の養成研修。障害者本人への支援だけでなく、業務の切り出し方や社内での障害者雇用促進等についても学ぶことができます。受講希望者が多く、申込み状況によっては受講できないことも多い研修ですが、私は運良く1回目の申し込みで受講が叶いホッとしたことを思い出します。
■当時手にした本
障害者の経済学 中島隆信 (東洋経済新聞社)
これからの発達障害者「雇用」 木津谷岳 (小学館)
書籍ではありませんが……
障害者.com 当事者の方の気持ちを知るのに「成年者向けコラム」がオススメ
今回は障害者雇用について何も知らなかった私が、スタッフを迎え入れる前に少しでも準備をしておこうと試みた方法をご紹介しました。障害者雇用を担当している方にとっては当たり前のようなものばかりですが、当時の私はこれらを知ることが最初の仕事でした。
次回は初めてスタッフを受け入れた時の試行錯誤をお伝えしたいと思います。
執筆の背景
障害者雇用関連の情報は、採用・育成の事例やノウハウばかりで、採用した障害者雇用の社員に「どのような業務を、どうやってもらうのか」のノウハウが足りていません。
そこで、実務ノウハウや、障害者雇用チームの立ち上げ経緯などを公開することで、障害のある社員自身や総務担当者が、はじめの一歩を踏み出せるシリーズを立ち上げました
▼過去記事一覧はこちら
ここまでお読みくださりありがとうございます。一つだけお願いをさせてください。
認定NPO法人フローレンスは障害児の保育・支援問題、ひとり親の貧困問題、赤ちゃんの虐待死問題、などの子どもや子育てに関わる社会課題の解決に向けて多くの方からのご支援をいただきながら取り組んでおります。何かの形で応援したい、と思ってくださった方は、フローレンスへの寄付をご検討ください。
フローレンスの障害者雇用についての視察や講演などの問い合わせは、 https://florence.or.jp/contact/ の取材・広報申込みフォームよりご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
