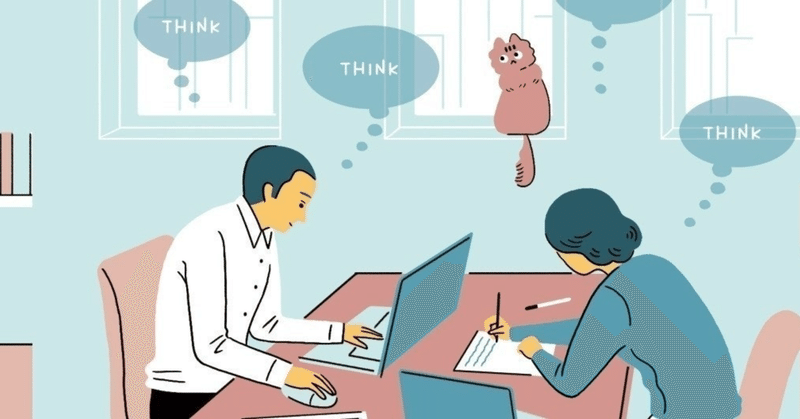
Slackで起きる問題の本質は何か
Slackを使い慣れてくると、使い始めた頃の気持ちなど忘れてしまうと思う。ITリテラシーの高い人からすると、リテラシーの低い人材はどう見えているでしょうか? よくある(?)問題の本質を考えます。
※私が働いてきた複数の職場で実際に学び、感じてきたことをミックスした考察記事です。
DMしか使わない人の気持ち
DM(ダイレクトメッセージ)を使わないよう注意しても、DMしか使わない人がいます。
仕事を見える化するため、また検索可能にするためにはチャンネル上で会話を進めないといけない。そうしないと後から余分な仕事が発生する恐れがあるのだけど…と、何度説明しても頑なにDMを使う人はどこにでもいます。
DMしか使わないのは、なぜでしょうか。
それはひとえに他のスタッフの目が気になるから。聞いてみると、業務をスムーズに回すとか改善することよりも、他人にどう思われるかが重要という考え方にとらわれているようです。とにかく自分の意見をオープンにしたくない&人前で失敗したくない。
DMという閉鎖空間での連絡が多くなると、DMを受けた人が余分に情報整理することになります。はっきり申し上げて時間・精神的コストが増します。
やがてチャンネル上で発信するのは一部のスタッフに限られ、チャンネルに参加しないことを選んだスタッフはSlackをあまり見ないようになる悪循環が生まれることも。
非正規労働者(医療介護系)の多い場所で仕事をしてみると、口頭伝達が非常に多いことが分かります。テキストは時間がかかるからとみんな残したがりません。もちろん会話が大事なのは前提としてあるものの、テキストによる記録は避けて通れない。ニュアンスがうまく伝えられませんが、Slackの利用は電カル利用とは少し事情が異なります。
さすがにテキスト入力は出来ても、文章を組み立てるトレーニングをしないままスタッフはどんどん高齢化。文章を作るのにとても時間がかかる。挙句、手書きの手紙で受け取った側の仕事が増える。そう、これが現実。
結婚出産を機に正社員を離れざるを得ない女性が多いのは周知の事実。中には社会人数年目できちんと教育を受けないままに離職、数年後に仕事を再開。文章力はなくて当然です。
幼少時から失敗に関して厳しく指導されてきた経験がある人は、自分の意見を述べないようになります。よく言われる医療・介護業界のFAX問題とか以前の、社会的な問題。個人の努力の範疇ではない気がしています。
失敗しても良いという考えのもとに
Slackでの問題を解決すべく、いくつか記事を書いてきました。何かの参考になれば幸いです。
練習チャンネルでいくらでも練習できるようにした例です。
ルールは利用当初から作りあげていくもので、根気がいる。
時間外に連絡することで生じる人間関係のひずみはもっとも避けたほうが良い。時間外のSlackの通知をオフにするとか、送信側が予約投稿を使うとか。
世の中、問題のないSlackなんて自分ひとりで使うSlackぐらいなもの。なので諦めずに頑張ろう。
失敗は成功の母
読んで下さりありがとうございます。読みやすいコラムを目指します。
