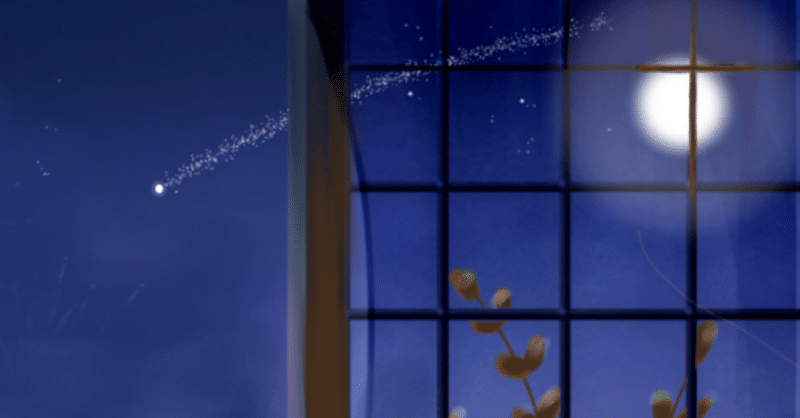
厄咲く箱庭 ― 花巫女と災いの神(3) 弐.二律背反
創作小説『厄咲く箱庭 花巫女と災いの神』の第二幕部分(R15未満)
※フィクションです。実在の人物、土地、出来事とは関係ありません。
弐.唯我独尊
保護
――…………
……遠い、遠い彼方から、何か……聞こえる。
キャン、キャン、と叫ぶ、悲鳴のような子犬の鳴き声。
『かえして。おねがい。しんじゃうわ』と必死に乞う自分の弱々しい叫び声。その場に座り込んで、ひっく、ひっく……としゃくりあげる。
涙と鼻水で濡れた顔がみっともなくなり、慌てて拭おうとした瞬間――自分と変わらない大きさの柔らかな手が、その手を包んだ。
続いて、ぶたれた痛みがまだ残る額を、ぎこちなく撫でてくれた大きく固い指……二種の淡い温もり……
『ねえさま…… じいさま……』
見上げた二人の顔は、其々霞みがかかっていて判らない。けれど、静かに、哀しく、優しく微笑んでいた気がした――
――…………
霧が薄らいだように朧気な脳裏が覚醒していく。頭は鉛のように重い。ぼやけた視界に、見慣れない木目調の天井が映る。身体は柔らかな布団と寝具に包まれ、白無垢は襦袢らしき寝間着に変わっていた。髪もほどかれている。
布の柔らかな感触。軽い頭痛に喉の渇き……暗がりだが冥土ではなさそうな事、どうやら自分はまだ生きているらしい事にアマリは戸惑い、動揺する。
――どうして……?
ふと、強烈な視線を感じ、反射的に眼球をぐるり、と動かす。朱の瞳と目が合いおののいた。あの夜、厄妖神の青年が連れ、黎玄と呼んでいた鷹がいたのだ。
あの時は、ギラギラとした怪しげな光を放っていたが、今は紅珊瑚のように澄んでいる。半分が障子で閉じられた円形の窓の縁に留まり、じっ、と観察するように、自分を見ていた。
「……?」
困惑する彼女を確認すると、焦茶の翼をバサッ、と羽ばたかせ、外へ飛び立って行った。後に見える空は宵闇に染まっている。細々とした上弦の月が浮かんでいた。あれから何日経ったのか、今いる場所はどこだろう……と不安に駆られる。八畳程の畳部屋……という事位しか判らない。
「失礼致します」
暫し後、突然、凛とした女性の声が襖の向こうから聞こえた。
「お身体の具合はいかがですか?」
すっ、と襖を開けて入って来たのは、菖蒲のような青紫の忍装束の若い女性だった。濡羽玉の艶やかな黒髪を後ろに束ね、団子状にして銀の簪を挿している。琥珀色の猫目に笹形に尖った耳が、涼やかな顔立ちを一層映えさせているのが、暗がりでもわかった。
小鍋や急須などを乗せた盆を手に、無表情に佇んでいる。……何故だろうか。どこかで会ったような、懐かしく温かい思いが、アマリの胸の中にわき上がった。
「貴女は……? ここは、何処ですか……?」
「厄界の長……荊祟様の御屋敷の離れでございます。私はこちらの警護などを担っている者。貴女様が目覚められたと伺い、お食事と薬をお持ちしました」
颯爽と傍に寄って正座し、礼儀正しく頭を下げる、くノ一のようなこの女性が纏う冴えた空気に、アマリは圧倒された。
「長様より、貴女様の看病と身の回りの世話、そして護衛を申し付けられました。今後は私がなるべく同行させて頂きます。どうぞよろしくお願い致します」
「……せ、世話? ……護衛!?」
予想外の単語の連続に耳を疑い、困惑する。
「……この界には……貴女様を良く思わぬ者もおります故…… どうかご容赦ください」
「そ、そうでしょう……!? 厄……長様は、私を生かしておかれるのですか……?」
すっかり錯乱したアマリは、早口でまくし立てる。信じられない事態に、まだ覚醒し切っていない頭がなかなか追いつかない。
「……殺される、と思っていらしたのですか?」
静かに頷く彼女に女性は初めて表情を崩し、眼を見開いた。労りと情けの交じる複雑そうな素振りを見せる。紅の唇が一文字に結ばれ、長い睫毛が扇のように臥せた。
「あの方が、そうお決めになられた事ですので……ご自分でお尋ね下さい。貴女様のお身体が回復次第、お会いされるそうです」
そんな事があるのだろうか。何故、今更自分と対面するのか……理由が全く解らない。アマリが困惑する中、女性は部屋の行灯に火を点した。暖かな光が、室内をほのかに包む。
「私は隣の部屋に住まいます。何か御用がありましたらお呼び下さい。……多少の異変は察知できますが」
つまり、アマリが何か仕掛けたりしても分かるという事だ。おそらく、このくノ一の仕事は、厄病神……荊祟への報告も兼ねてなのだろう。彼女に罪は無いが、少し悲しく思った。
――ここでも監視されるのね……当然だけれど……
膳を布団のすぐ側まで運び、改めて正座した女性は、小鍋の中の湯気立つ白い物を、てきぱきと椀によそい始める。
「玉子粥です。長様も召し上がっておられる、人族の身体に合わせた物です。毒などの類いは入っておりませんのでご心配なく」
「……わかりました」
――確かに、今更改めて……なんて無意味よね
不可思議で複雑な思いを抱きながらも、少し安堵して頷く。あの時、彼は、確実に自分を殺せたはずなのだから。
「後程、湯浴みのお手伝いも致します」
終始、毅然とした態度を崩さない、この礼儀正しい女性に、アマリは尊敬と感謝の意を抱き始めていた。
「何から何まで、ありがとうございます」
「務めですので。お気遣いなく。仰々しい格好で申し訳ありませんが…… いつ何が遭っても御守りできるように、なるべくこの姿でご一緒させて頂きます」
手際よく食事の支度を進める彼女に、少し遠慮がちに申し出た。
「それは……大丈夫です。ただ、あの……」
「何か?」
不都合な事があるのか、と言いたげな様子だ。
「お名前を……伺ってもよろしいですか?」
手を止め、女性は驚いたように眼を見開き、戸惑いが垣間見る声色で問い返す。
「何故でしょう?」
「これからお世話になる方なのですから、知っておかなくては……と思って。その、貴女のご迷惑にならなければ、ですが」
彼女があの冷徹な厄神に叱られるのなら知らなくてもいい。だが、声も顔もはっきりと覚えていないが、先に神界に旅立った、姉の雰囲気にどこか似ている気がしたのだ。個人的な思い入れだったが、彼女に親しみを感じ始めていた。
そんなアマリの答えに、女性はまた表情を崩す。今度は、微かに和らぎを見せた。
「――カグヤ、と申します」
「まぁ、綺麗な名……お似合いだわ」
いつか読んだ古のお伽噺を思い出す。彼女なら月から来た姫だと言われても納得する。それほど聡明で理知的な美しさがあった。
「……私共からしたら貴女様の方が、異星からいらしたようなものですよ」
――それは、違うわ……
自虐的に哀しく思った。自分は歓迎されていないし、持て囃されている訳でもない。
「あ、申し訳ありません。私は……アマリ、と申します」
我に返り、慌てて自分も名を告げる。
「アマリ様。了解致しました。――それから」
律儀に復唱し、深く頷くカグヤは、また少し表情を和らげ、付け足す。
「私は貴女様と同年ですので、そんなに気負いされないで下さい」
てっきり年上だと思っていたアマリは、不意打ちを突かれ茫然とした。そんな彼女を他所に、カグヤはこれまた手際よく、薬膳茶を淹れ始める。
独特の臭いが漂う湯呑みを差し出され、反射的に口を付ける。今度はしっかりと苦味を感じた。
同刻。屋敷の主人である荊祟、側近と従者数名が、奥座敷の一室で神妙に話し合っていた。勿論、議題はアマリの件だ。
この百年程、尊巫女の輿入れが皆無だった彼らにとって、彼女が献上されるという知らせは、それこそ天変地異並みの大事件だったのだ。
「カグヤの報告ですと、随分な心身の疲労、睡眠不足で未だに衰弱しているようです。何も看病までしなくとも……」
「そうですよ。放っておけばよろしいではありませんか……そのうち死にます。厄介払いになり、結構ではありませんか」
行灯の灯りに照らされた素顔の主人に、従者達はそんな非情な行いを促す。明らかに渋い表情をしている彼らを横目に、荊祟は重く、深いため息を吐いた。
「どんなに忌み嫌われようが、たとえ汚れ腐ろうが、我らは神族の者。神々に仕える女……増して尊巫女。見殺しにする訳にはいかないだろう」
「長様…… まさか、情を懐かれたなんて事はあり……」
従者の言葉は途切れた。切り裂くような黄金の眼光がギラッ、と向けられ、ヒッ、と喉奥が引きつる音が鳴る。
「全く……本当に面倒な事になったものだ。相も変わらず、人族共はいらぬ事ばかりする」
心底うんざりしたように、一族の長は、鋭利な眉を思い切りしかめた。
歪な自由
厄界、この屋敷の離れに住み込んでから、一週間程が過ぎた。カグヤの看病の甲斐あり、体の具合が良くなってきたアマリは、布団の中でぼんやりとする毎日だった。
始めの数日は、体の怠さや苦しさにひたすら耐えるだけだったが、少しずつ回復してきた今は、落ち着かなくなっていた。
『無理の無い程度なら構いませんので、お好きに過ごして下さい』とカグヤに言われたが、この状況で何をどうしたら良いのかわからない。
そもそも、この部屋には布団とちゃぶ台、衣装箪笥以外、本当に何もなかった。自害させない為か、あらゆる物らしい物が消えている。
今までなら、今刻は『仕事』か、芸事の稽古の時間だった。しかし、ここには仕事を促す者も、依頼人もいない。そんな体力はまだなかったが、よっぽど具合が思わしくない限り、今までは行っていた。
唄……詩吟は軟禁されている今、目立つ事は避けたい。屋敷の者も不快かもしれない。読み書きや勉学は、教本も師範もいない為、出来ない……
窓から見えた池囲いの庭園に出てみようか……と少し思ったが、カグヤは別の任務で数時間不在な今、勝手に出て良いものかわからない。帰る場所も頼れるアテも無い自分には、逃げ出す事も不可能……
だが、何もしないまま一人きりで過ごしていると、今までの様々な事を思い出し、余計な考え、良からぬ感情がわき始めてしまう。痛みの治まった頭が、再び喚き出した。忌まわしい囁きが、耳元で聞こえ始める。
『――何故、生きている? お前はもう用無しだろう』
『――お前が生ける場所など、もう何処にもない。息する理由があるのか?』
『――今更、生き長らえて何になる? 何故、全てを賭けてきた?』
振り切ろうと眼を閉じ、落ち着かせようと深呼吸を繰り返す。激しい孤独感、憤り、悲しみ……そんなどうにもならない感情が吹き出してしまいそうになった時、人族の社に居た頃に行っていた鎮静法だった。
だが、沈んでいる心がどんどん深みにはまり、奈落の底へ堕ちていく。止まらない。止められない……
――……怖い。怖くて堪らない。気を紛らわさないとおかしくなりそう……
――何か……何でもいいわ。何か……
すくっ、と取り敢えず立ち上がる。布団を出て、寝間着のまま手足を動かし、長年の習慣で身に染み着いた動作を始めた。ゆらり……ゆらり……と、両腕を宙に舞わす。稽古で習った舞だ。扇子の代わりに、側にあった汗拭き用の半巾を咄嗟に掴む。
足取りのおぼつかない踊りは思うようにいかず、すぐに手順を間違えた。師範の叱咤が飛んでくるのを察し、反射的に動きを止め、思わず身を縮めた。が、何も聞こえない。間違った足を叩く腕も伸びて来ない。何の痛みも感じない。
――…………?
しん、と静まり返っている室内の中、どく、どく、という怯えた心音だけが聞こえる。至極、奇妙な感覚が襲ってきた。
……何だろう。未知の状況への戸惑いと怯えに加えてやってくる、不思議な安堵感。自分一人しかいないという、不慣れな空気にアマリは狼狽える。
そんな自身の様子を、部屋のあの円い小窓から、朱の眼の鷹がまた見ていた事にも気づかなかった。
「……な、に?」
その夜。黎玄が荊祟の部屋まで飛んで来た。彼らの意思疎通は言葉ではなく、所謂、精神感応のようなもので行っている。
定例の報告――アマリの情報を読み取った荊祟は、らしくなく間の抜けた声をあげ、唖然とした。
翌朝。突然、『夕刻、長様が御会いに来られるそうですので、この部屋でお待ち下さい』と、カグヤに言われたアマリは動揺した。心の準備は全く出来ていない。どんな顔をして、どのように振る舞えば良いかわからないままだ。
恐ろしい力を持つ非情な厄神と聞いていたが、こうして何故か生かされているという不可解さ。一方、場合が場合なら、夫になるかもしれなかった相手でもある。何とも奇妙な心持ちで、ただ時が過ぎていくのを受け入れるしかない自分が、滑稽にも思えた。
「アマリ様。長様がお見えになりました」
夕刻の黄昏時。襖越しのカグヤの声掛けに、反射的にびくつく。急いで梅鼠色の羽織を着込み、正座する。神妙な面持ちで、アマリは両手を膝に乗せた。
「は、はい」
返答と同時に、すっ、と襖が開き、慌てて頭を下げる。視界の端に、畏まりながら膝をつくカグヤの姿が見えた。その陰から、見覚えのある漆黒の履き物が忍びやかな足取りで部屋に入って来る。
「顔は上げてよい」
心なしか、あの夜より落ち着きある口調で、促す玲瓏な青年の声。その魅惑的な低音に惹かれるようにアマリは顔を上げる。瞳に映った姿に、思わず息を呑んだ。
素顔を晒している彼の瞳は、澄んだ琥珀色だった。あの夜、稲妻のような眼光を放っていた瞳と同じとは思えない。だが、あの時と同じ藍鼠色の長着物に鋭利な眉、笹形の耳、非対称に分けられた濃灰の髪が、同一人物だと判別させた。
黒地の首巻きで隠されていた肌は小麦色。すっ、と通った鼻筋、きつく結ばれた薄めの唇。腰元には日本刀らしき刀。荒く野性的な気を纏うが、顔立ちや眼差しは涼やかという対称的な魅力を兼ね持っている。そんな厄病神――荊祟の出で立ちに、アマリは今の状況を忘れ、見入ってしまっていた。
「回復したらしいな」
「は、はい…… お陰様でこの通り……」
いつの間にか少し離れた場所に座り込み、胡座をかきながら淡々と、彼は声を掛けてきた。我に返ったアマリは、少し目を伏せ恐々と、だが、なるべく丁寧に応える。
「だな。この状況で踊りをする位、余裕綽々のようだ」
そんな彼女に、荊祟は容赦なく皮肉を投げる。
黎玄の存在には気づいていたので、昨日の行いも知られているかもしれないとは思っていた。しかし、そんな風に改めて言われると決まりが悪くなる。悪い事をした訳ではないが、どうにも居たたまれない。
「も、申し訳ありません。いつもなら仕事か稽古の時間だったので…… どう過ごしたら良いかわからなくて……」
「……仕事、か」
しまった、とアマリは自分の迂闊さを呪った。この厄神は、自分に課された企てをどこまで感づいているのだろう。どう説明しようかと、瞬時に脳内を転らせる。
「いえ、あの、大した事では……」
「よい。どうせ今回の件に関するのだろう」
どうでもよいとばかりに、ふん、と彼は軽く鼻を鳴らす。図星だったアマリは何と答えたら良いのか判らず、俯く。元々、上手く誤魔化すという所業は苦手な性分だったが、この厄神にはどんな小手先も通じない。そんなぴりつく空気が、辺りに漂っていた。
「あの…… 長様」
厄病神とも本名の『ケイスイ』とも、さすがに口にしづらく、アマリは無難な呼び方をした。
「何だ」
僅かに戸惑いの色を交え、無表情のまま厄神は問いかける。
「あの時…… 助けて頂きありがとうございました」
改めて、両手を前について頭を下げた。そんな彼女に、荊祟は胡散臭げな猜疑の眼差しを向ける。
「その後も看病して、こうして生かして下さり…… 正直、驚きました」
「お前の為ではない。奴らの所業を見逃すと、界の秩序と風紀が乱れる。故に処罰したまで」
「お察ししております。ですが、そのおかげで身を守れたのは事実でございますから」
彼にとってはあくまで義務で、不本意な行いだったのは理解していた。だが、女としての尊厳だけでも傷つけられないで済んだと考えていたアマリは、それだけは礼を言いたかった。
「めでたい頭だな。お前が厄介な存在なのも事実だ」
ばっさりと辛辣に返し、珍妙な生物を見るような眼差しで、厄神は目の前の尊巫女を凝視する。理解不能、という意思がにじみ出ていた。
厄介者
この厄神は、一族の長で神様ある割に、情感豊かだとアマリは思った。長である特権と余裕もあるのだろうが、実家の主である父……両親の方が、よほど取り繕った能面の顔をしていた気がする。
「承知しております」
「……お前は、民に崇められる『尊巫女』なのだな。どこまでも」
どこか皮肉めいた口調で、ぼそり、と彼は呟き、口角を僅かに歪めた。
「お前を襲った輩どもから聞いた。あの尊巫女は、俺を『厄病神様』と呼んでいたと」
あの時、そして今の自分の状況を改めて思い出し、痛みの伴う複雑な思いに絞られる。
「わざわざ此処に送り込む位だ。相当、狡猾か酔狂な女を寄越したのだろうな、と思っていたが……違ったようだ」
一呼吸した後、荊祟はアマリの淡い瑠璃色の瞳をじっ、と凝視し、言い放った。
「『清廉な尊巫女』として、髪から爪先に至るまで培養された人族の女、だな」
内心、情けなく思っていた自身の在り方を見抜かれ、更に言い当てられてしまった。惨めな思いが胸を締め付け、いたたまれなくなる。
この相手に遠慮は要らぬとふんだのか、煽って自分を試しているのか、彼は痛いところばかり突いてくる。きまりの悪さが一転、少し腹立たしくなったアマリは、ずっと聞きたかった事を吐き出す。
「あ、貴方こそ……変わった神様でいらっしゃいます。贄にして喰う事も、殺す事もなさらない。……私の存在などお邪魔でしょう?」
一寸の沈黙が流れた後、ぽつり、と荊祟は言い放った。
「どんなに忌まれようが疎まれようが、神族の長だ。無意味な殺生はしない」
意外な彼の答えに、アマリは驚き、思わず彼の琥珀の瞳を凝視した。尊巫女として様々な人族と応対してきた彼女は、明らかに見栄を張ったり、取り繕うとする素振りや、瞳の色は判別出来るようになっていた。
だが、目の前のそれは、自分に嘘偽りを吐く眼差しではなかった。彼は、無差別に人族の地や命を脅かす厄病神……破壊神ではなかったのか……
「厄界の者に悪影響が出るやも知れぬし、亡き者にしたところで人族共への後始末に困る。無益でしかない」
彼女の心中を見抜いたように、ふ、と僅かに自虐的な笑みをこぼす。その瞬間、琥珀の瞳に微かな陰りが入ったのが、アマリには見えた。心の中に小さな波紋が起こる。
「なら私は、どうしたら良いのですか……?」
「とりあえず、もう暫くの間、この屋敷に身を置け。お前への対処については、もっと家臣と話し合う必要がある」
またアマリは少し意外に思った。この一族の長は、重要事項を独断で決めない。少なくとも、彼は暴君では無いようだという事実に、彼女の中で想像していた厄病神の像が薄れ、崩れていく。
再び唖然とした面持ちで彼を凝視したアマリを、また不審そうに眺めた後、荊祟は改まった厳格な口振りで告げた。
「カグヤ同伴なら、今後は屋敷内をうろついても良い。但し、妙な真似はするな。悪目立ちして、界の者の反感を買ったら面倒だぞ」
その命令を最後に、彼は忍びやかな足取りで部屋を出て行った。残されたアマリは変わらず茫然としている。心配して、そっ、と近くに寄ってきてくれたカグヤに気づき、少し躊躇った後、恐る恐る問いかけた。
「あの……カグヤさん」
「何か?」
いつも同じ表情で、声色すらあまり変わらない彼女の心や真意が判らず、アマリは不安だった。だが、自分の言葉一つ一つを、こうして律儀に返答してくれる対応が、今の混乱した状態では心底ありがたいと思う。
「長様は……いつも、あのような振る舞いをされるのですか?」
「あのような、とは?」
「こう……呆れたり、苦笑したり、少し哀しまれるような素振りを、貴女や家臣の方にもされるのでしょうか」
輿入れの夜に出会った時は、もっと非情で義務的な言動、主らしい冴えた威厳を纏っていたが、さっきの彼は少し違う人のように感じた。何というか……人形のように生きていた自分より、よっぽど人族らしい。
「いいえ。私の知る限りですが…… 基本的に冷静沈着で、毅然とされています。動じられる事はほとんどございません」
「そう、ですか……」
「貴女様には、先程の長様がそんな風に見えられたのですか」
アマリが静かに頷くと、カグヤは少し怪訝そうな素振りを見せた。彼女は少し離れた襖越しに待機していたが、くノ一の彼女なら察知出来そうな位の変化だ。少し考えた後、カグヤは続けた。
「確かに…… らしく無いご様子ではありましたが」
彼女の言葉で、彼――荊祟という厄病神の事がますます分からなくなり、アマリは混乱した。
その夜の夕餉時。何時ものように、てきぱきとカグヤが支度を進める。自分も手伝う事をアマリは申し出たが、『長様から命じられた、私の務めですので』と丁重に断られた。
こんなに生真面目で責任感の強い女性だから、あの厄神……ケイスイも信頼しているのだろう、と今までは思っていたが、先程の彼とのやり取りで、それだけでは無いような気がしていた。新たに生まれた違和感を確かめたく、向かい合って座るカグヤに対し、アマリは思い切る事にした。
久方ぶりに誰かと食事をしているという慣れない状況で、相手は心を許している訳ではない異種族の者…… 膳の皿が全て空になった頃、恐る恐る、切り出す。
「あの……カグヤさん」
「何か?」
「……出過ぎた問いである事を承知で……お尋ねしたいのですが」
改まった彼女の様子に、カグヤは飲んでいた茶の湯呑みを置き、身構える。
「はい。何でしょう」
「……あの方は、人族の地に……何を、なさったのでしょう……?」
アマリの予期せぬ問いに驚いたのか、あの厄神と同じ琥珀の大きな瞳を見開く。彼女の瞳孔は、明らかに揺らいでいた。
「……それはお知りにならない方が良いかと。貴女様にとっては、きっと気分の良い話ではありません」
神妙な声色で律儀に返すカグヤの言葉に、ぐっ、とアマリは息を詰める。ある程度の予想は、勿論していた。今までに両親や従者から見聞きしてきた、人族を襲った数々の厄災――火災、氾濫、地盤沈下、飢饉、悪化する治安。
どれが、どこまでが、彼の仕業なのか知らない。ずっと社から出ていなかったアマリに外の状況はわからなかった。しかし、願掛けの為に、わざわざ遠くから社に訪れる悲痛な面持ちの民の姿は、数え切れない程……何度も見てきた。
だが、何故か知りたかったのだ。あの厄神が、どんな事を、どんな力で今までしてきたのか。どんな風に生きてきたのか。無性に気になり、仕方なかった。
「……貴女の事を、とても信頼されているように見えました。家臣の方の事も気にかけていらっしゃるようで……」
続ける言葉を失い、俯く。あの厄病神は、少なくとも他者を不幸にして楽しむような、享楽的な神ではないように見えたのだ。何か致し方ない、どうにもならない理由があるのではないか、彼自身にとっても不本意な行いではないのか――あの夜、自分を助けたように。
「……以前、私はあの方に身を救われ、居場所を頂いたのです。それで勝手に恩を返しているだけの事」
はっ、とカグヤの顔を見た。彼女の眼差しには、確固たる決意と覚悟の光が宿っている。
「アマリ様もあの方に危機を救われたからなのでしょうが…… 決して貴女様の為ではありません」
「……」
「私がこのような事を物申すのも妙ですが…… よく知らぬ他者を簡単に信用し、好意的になられるのは危険でございます。対立的な立場にある者なら尚の事。貴女様を油断させる策略、巧みな話術やもしれません……私とて同じです」
自分の監視役でもある眼前のくノ一を、アマリは思わず凝視した。
↓次話
#創作大賞2023 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
