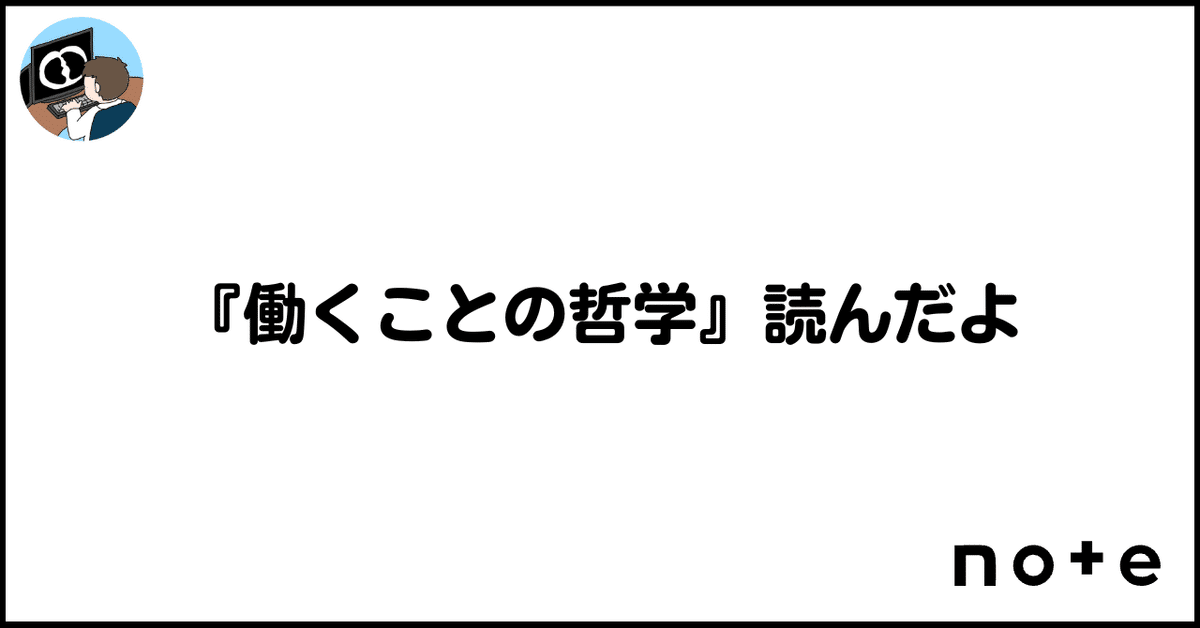
『働くことの哲学』読んだよ
ラース・スヴェンセン『働くことの哲学』読みました。
たまたま見かけて手にとった本です。
著者のラース・スヴェンセンはノルウェーの哲学者。
内容は題名通り「働くこと」を考える本です。
この題名と著者をどこかで見たようなと思ったら、ベンジャミン・クリッツァー『21世紀の道徳』で引用されていたのと、國分功一郎『暇と退屈の倫理学』でスヴェンセンの過去作にあたる『退屈の小さな哲学』が言及されていたのでした。
最近興味深く読んだ両書とも関連があるならば、「働くこと」について常々思索中の江草でもありますから、これは読んでみるべきだろうと思ったわけです。
良い本でした
読後の感想としては、全般を通してそこはかとなく香ってくる著者の潜在的な主張には正直納得できなかったのですけれど、タイトルに恥じず「働くこと」を考える上で良い足場になる本だったなと思います。
語り口も語彙もカジュアルで、ボリュームも多くなくて読みやすい。それでいて様々な示唆を与えてくれる。
普通に良書です。
「現代社会の働き方の常識」を掘り返す
で、軽くどんな話が展開されてるかをご紹介しますと。
たとえば、一般的には仕事とは収入を得るための活動ととらえられています。
「食ってくために働かなきゃならねえ」などとよく言いますよね。
ですが、著者は現代社会において仕事には自己実現としての手段としての役割が強く期待されてることを喝破します。
現代的なリーダーは、従業員に当人の仕事がたんに仕事であるわけではなく、自身の潜在能力を丸ごと実現し、「真の自己」となるためのファンタスティックな機会だと納得させる存在とみなされている。
そして、仕事上のマネジメントにおいても、こうした「仕事は自己実現の場であり楽しくて充実している活動であらねばならない」という思想が通底しているために、「楽しみ相談役」や「楽しみ調達人」という滑稽な役回りが出現したり、従業員が自発的に企業スピリットを内面化させるように促すなど、企業が実質カルト宗教化している現状を皮肉をこめて批判しています。
ここでの信念とは、それに参加している者たちの「共同魂」としての企業スピリットへの全面的な信仰のようなものだ。管理や人的資源、企業文化やブランド化といった領域は、すべて一緒になってひとつの聖なる合一をもたらすものとみなされる。消費者はたいがい「信者」で、従業員は「伝道師」、CEOが「霊的指導者」だ。
(このくだりが一番著者の記述がもっとも辛辣な箇所で他のところはもっとマイルドなのですが)このように本書では、普段ほとんどの人が特に疑問に思ってない「現代社会の働き方」の常識がガシガシ掘り返されていきます。
さすが哲学者、容赦ない、という感じで、とても楽しい刺激的な読書体験が得られます。
「勤労主義リアリズム」そのものの本書の見解
ただ、さきほど江草は著者の主張に納得できないと書きました。
それはなぜかと言えば、著者が本書を通じてずっと述べている主張が、まさしく江草が問題視している「勤労主義リアリズム」であるからです。すなわち「仕事がない生活なんて考えられないから私たちは大人しく仕事をし続けるしかない」という態度です。
あくまで本書は特定の主張を行うものでないと著者は釘を刺してはいますが、結びで結局著者の見解めいたものは提示されています。
江草なりに著者の主張を解すると、
「現代社会の人々は自己実現やら楽しみやらなんやら仕事に過度の期待をしすぎである。完璧な幸福を求めるそんな期待がまずかなうことはない。万一、理想の仕事に出会えたとしても仕事中毒となって人生における仕事以外の大切なものを見落とすことになり、なお悪い。
とはいえ、仕事をただの金儲けの手段とみなすのもよくない。今後仕事が世の中からなくなることはまずないし、たいていの人間は余暇の時間も効率よく活用しようとしてかえって参っているのが現状だ。無為に過ごすのも人間には耐えられない。
結局のところ私たちは仕事から離れられない。ならば、いくら退屈であったとしても仕事とほどよく付き合おうとするべきであろう。仕事から得られるものには人生の意味など収入以外のものがやはりあるのだから」
といったところでしょう。
過度な期待もせず、かといって見限るわけでもない、仕事とのバランスのとれた距離感を目指す中庸的提言。
もちろん、ひとつの真っ当な意見ですし、決して愚かな発想ではないのですけれど、やっぱりこう「仕事のない世界なんて想像できないよね」という一種の諦めみたいなものを感じてしまって、哲学者ならそこにこそもっと踏み込まんかーいと思ってしまうんですよね。
國分功一郎『暇と退屈の倫理学』が批判する「諦めがち」なスヴェンセンの姿勢
この辺は、國分功一郎『暇と退屈の倫理学』がスヴェンセン『退屈の小さな哲学』を批判していた文脈と感覚が近いところがあります。
スヴェンセンのそれは、退屈の原因となるロマン主義的な気持ちを捨て去るべし、という消極的な解決策である。そして、消極的な解決策は、解決策でないことがしばしばだ。
これでは、退屈してしまうことが問題であるのに、退屈している君が悪いと言い返しているようなものである。それが言い過ぎだとしても、このような解決策にはだれもが途方に暮れる他ないだろう。どうやってロマン主義を捨て去ればいいのか? 自分の心のどこに、どのような形でロマン主義があるのかも分からないのに?
そもそも、ロマン主義的な心性をもった人間がそれを捨て去ることはできるのか? スヴェンセンの言うように、それは単に「諦める」ということではないのか? つまり、「お前はいま自分のいる場所で満足しろ」「高望みするな」というメッセージにすぎないのではないか?
扱ってるトピックが「退屈」と「仕事」であり厳密には異なるものの、本書『働くことの哲学』でも「仕事の退屈さ」を念頭に置いているのは間違いないですし、やはり同著者だけあって基本的なメッセージはほぼ同じに見えます。
すなわち、國分が批判しているようにスヴェンセンはどうも「諦めがち」なのです。
「勤労主義リアリズム」に屈した仕方なしの諦念
もっとも、著者のスヴェンセンも別に「仕事の退屈さ」を積極的に肯定しているわけではない点は考慮されるべきところでしょう。
本書においても節々で「不毛な仕事」に対する批判的な姿勢が見受けられます。
「神々はシーシュポスを罰して、終わりなく岩を山頂まで運ばせたが、岩は山頂近くまで来るとその重みでふたたび転落してしまう。神々が、不毛で望みなき労働以上に残酷な罰はないと考えたのも、たしかにもっともなことだ」。だが、カミュはこのエッセーの最後にこう書きつける。「私たちはシーシュポスが幸福なのだと考えねばならない」。なぜそう考えなければならないのか。私にはどうにも理解しがたい。
つまり、マーク・フィッシャーが『資本主義リアリズム』の中で、我々はずっと資本主義に抗おうとしつつもどうしても資本主義のオルタナティブが見つけられないという諦念を描いていたのと同様に、本書も仕事に抗おうとしてもどうしても仕事のオルタナティブが見つけられなかったための仕方なしの諦念ではあるのでしょう。
この諦念、にじみ出る悔しさ、苦悶、そして妥協。
だからこそ本書はまさしく『勤労主義リアリズム』と呼べる一冊となっているのです。
「勤労主義リアリズム」的諦念への挑戦書の数々
確かに「仕事のオルタナティブ」を探すのはかなり険しい挑戦です。スヴェンセンが諦めたくなるのも無理はありません。
しかしながら、最近では本書が諦めている各要素において突破口を開こうとする動き、あるいは本書が早計であった箇所を修正する動きが出てきているように思います。
ダニエル・サスキンド『WORLD WITHOUT WORK』
たとえば、9章の「仕事がなくなることはない」とする論説。
仕事がオートメーション化されてゆく規模はこれからも拡大しつづけるだろうが、それによって過去の遺物と化す職業が出てくる一方で、新しい職種も創造されつづけるだろう。私たちの前に広がっているのは、仕事のない世界ではなく、仕事が減ってゆくなどということがありそうもない世界だ。
これはAI革命なりなんなりがあっても仕事がなくなることはないという立場の主張として定番のものですが、この主張こそダニエル・サスキンド『WORLD WITHOUT WORK』がガッツリ紙面を割いて丁寧に反論しているものです。
本当に仕事がなくなることはないのかという点には大きな疑義があります。
もし、仮に世界から仕事がなくなっていくのであれば、スヴェンセンの描いている仕事観も大きな見直しを迫られることでしょう。
オリバー・バークマン『限りある時間の使い方』
また、著者は「余暇を効率よく活用しよう」とする私たちの習性を否定的にとりあげています。
週末と祭日にはとりわけせきたてられる感じが強まる。そこにはかぎられた時間しかないのだから、そのなかですべてのことをこなそうとするなら、無為になどすごしてはいられない。
「映画を倍速で観る人々」なんかが象徴的なように、私たちの余暇時間に効率主義が入り込んでることは確かに認めざるをえません。
ただ、この私たちの習性についてもオリバー・バークマン『限りある時間の使い方』がベストセラーになるなど見直しの機運が高まっています。バークマンは時間に限りがあるからと効率的に動こうとするとかえってその限りある時間を毀損してしまう罠があることを強く訴えています。
スヴェンセンの「どうせうまく使えないから余暇を求めるのはやめて仕事をするしかない」という態度は妙に人間への諦めが早いのではないでしょうか。
ジェニー・オデル『何もしない』
本書を通じて、著者は「無為」に対してとにかく拒絶反応を示します。
少なからぬ作家が、レジャーよりも仕事のほうが好きだと語っている。『幸福論』のなかで、バートランド・ラッセルはこう言っている。
だから、仕事が望ましいものなのは、なによりもまず退屈を防いでくれるものとしてだ。なにしろ、興味はないがどうしてもやらねばならない仕事をするときに感じる退屈は、その日にやらねばならないことがなにもないときに感じる退屈と比べるなら、ゼロに等しい。
ラッセルはさらにつづけて、「どれほどつまらない仕事でさえ、ほとんどのひとにとっては無為ほど苦痛ではない」とも言っている。ラッセルのもっともよく知られた著作の表題が『怠惰のすすめ』であり、そのなかでまさにこれとは逆の主張が展開されていることからすると、この主張はつじつまが合わないように思われるかもしれない。それでも、仕事はしばしばまったくの無為ほどには苦痛ではないというラッセルの主張は正鵠を射ていよう。
こういった「私たちは無為に過ごすのに耐えられない(だから仕事をするしかない)」という著者の感覚も、それこそ仏教が紀元前からその苦痛を乗り越えようと説いているところですから、いきなり無為から逃げ出すのはいかがなものでしょう。
そもそも仏教ほど大げさでなくとも、昨今のマインドフルネス瞑想の流行などは、私たちが無為を受け入れようとし始めていることの証左でしょう。
本当に私たちが「無為」に向き合えないかどうかは疑問の余地があります。
たとえば『何もしない』という書籍でも「無為に耐えられないこと」こそ私たち現代人特有の病理であることをつまびらかに指摘しています。
「無為が嫌だから仕事に逃げる」というのは私たちが無為に耐えられないと勝手に思い込んでるだけの可能性があるのです。
橋本努『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』
著者は「私たちはもっと多くを消費するために労働時間を短くするより生産性を向上することを選んだ」という見解を提示しています。
私たちは余暇よりもショッピングを選んだ。かつて人びとは、自分なりの優先事項をもっていた。近代以前の時代と現代のはじめごろまでは、賃金が上昇すれば人びとがその分だけ働かなくなるようになることを示す顕著な証拠があった。産業革命以降になってもまったく同じように、給料をもらった後の最初の数日は仕事に来ない労働者が相当数いるという事態を、雇用者はたびたび眼のあたりにしたものであった。「余分なお金」つまり日々の暮らしにどうしても必要な分として支払わねばならない額以上のお金は、たいていは自分の物質的富を増すことにではなく、仕事を休むために使われていた。そのころとこんにちの私たちの優先事項はまったく変わってしまった。
大きなトレンドとしては確かにそうなのですが、昨今では消費ミニマリズムの流行によってこのトレンドに楔が打たれたと言えるのではないでしょうか。
断捨離やこんまりメソッドの世界的な流行も世に知られています。
『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』が豊富な具体例を提示しているように「多く消費すること」は少しずつ選ばれなくなってきています。
ですから、「多く消費すること」と「労働時間を短くすること」の天秤の傾きがとうとう入れ替わる可能性がないとは言い切れないでしょう。
デイヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』
そして國分が批判しているような「仕事は退屈なもんなんだから、退屈している君が悪い。諦めろ」といわんばかりの著者の姿勢は、昨今議論を読んでいる「クソどうでもいい仕事」――いわゆる「ブルシット・ジョブ」――を前にしても貫けるものではないでしょう。
デイヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』で提示されてる様々な実例は「これはさすがに辛いわ」と言うべき無為な仕事で目白押しです。
そもそも本書でも、スヴェンセン自身、先に挙げたシーシュポス的労働だけでなく、ピンを大量生産するような単純分業作業や、無意味に管理される仕事の辛さを認めています。
逆に、おそらく私たちのなかには、こんなピン製造工場で働くくらいなら、頭に銃弾を撃ちこむほうがましだと思うひとも少なくないかもしれない。そんな作業は、端的に言って人間にふさわしい労働とは思われない。
だが、いったいなんのためにこんなことをしているのかについての明確な見とおしはなかった。一年間このプロジェクトに参加した――その間ひたすら「なにかに興じ」たわけだが――ものの、じっさいにはなにもなしとげられなかったことがわかって、私は計画からおりた。全員がなにかに興じるだけでいっさい仕事をしなければ、倦怠に陥るだけだ。
「無為に過ごすよりはつまらない仕事の方が良い」としているスヴェンセンも結局は「無為な仕事」は耐えられなかったようです。
確かに、「真の自己になるためのファンタスティックな仕事」を求めて職を延々と変えてるジョブホッパーに対しては「退屈している君が悪い」と言うべきかもしれません。
しかし別にそういう過度な期待をしていたわけでもないのに「無為な仕事」に陥ってしまった者に対して言うのは酷でしょう。
「人は無為なことに耐えられない」を前提とする本書の立場を鑑みても「退屈な仕事にも限度がある」はずではないでしょうか。
スヴェンセンさんごめんね、僕らは諦めが悪いんです
さて、このように、本書で示唆されてる「勤労主義リアリズム」的主張は(一定の妥当性があるのは認めつつも)まだまだ吟味すべきところがふんだんに残されているように思うのです。
とはいえ、一応フォローしておくと、本書の第一版が出たのは2008年と、リーマンショック前でもありますから、最近のトレンドまでおさえた見解を打ち出すことは現実的には難しかったと思われます(今回読んだ第2版も2015年とのこと)。
本書が書かれた時代から月日が経って「さすがになんかおかしいぞ」とみなが気づき、働き方・生き方を見直そうと動き始めてきているわけです。
実はみんなスヴェンセンさんと違って諦めが悪いんですよ。
ですから、スヴェンセンさんもぜひとも諦めずに「勤労主義リアリズム」に対抗する「仕事」に参加してくれることを期待しています。(といっても、これが「過度な期待」にあたらなければいいのですが)
まとめ
というわけで、なんか批判ばっかりになっちゃった気もしないでもないですが、これは江草がこだわりがあるテーマだから勝手に熱くなってしまっただけで、本書はやっぱりとても良い本です。
少なくとも「年収が高くてたっぷり納税して長時間働いてる俺は偉いんだぞ!」とか「仕事でみんなで楽しく自己実現!」みたいな仕事に関する俗観とは一線を画する内容です。
読みやすく示唆深い本書は「働き方」について考えたい人にオススメです。
【余談】ベンジャミン・クリッツァー『21世紀の道徳』におけるスヴェンセン援用の問題点
別書を焦点とした話になるのでここからは完全に余談ですが、以上の本書の立ち位置を踏まえると、本書のスヴェンセンの一節(p168−169)を引用して『ブルシット・ジョブ』を批判している『21世紀の道徳』の試みは妥当ではないと言えます。
スヴェンセンも論じているように、仕事とは、わたしたちに賃金だけでなく「意味」や「満足感」をもたらす可能性を秘めたものであることは間違いない。世の中にはブルシットでない仕事も多数あるし、ブルシットな仕事すらからも、なにかしらの意味や満足感を得られる可能性は残っているのだ。
(スヴェンセン側の引用文はさすがに長かったので割愛)
前述の本書の引用箇所等を鑑みても、このクリッツァーの主張(二文目の後半)はおよそスヴェンセンが同意するとは思えないものとなっています。
なぜなら、クリッツァーが「どんな仕事にも意義がある可能性」を期待しているのに対し、スヴェンセンはあまりの単純作業や無為な仕事の残酷さを認めているからです。しかも、スヴェンセン自身があまりに無為なプロジェクト(事実上のブルシット・ジョブ)に嫌気が差して辞した経験までも提示しています。
そんなスヴェンセンが「どんな仕事も可能性がある」という感覚を共有するとはとても思えません。
シーシュポス的な不毛な労働をしている人を目撃したならば、きっとスヴェンセンは「その仕事にもなにかしらの意味や満足感が得られる可能性があるよ」などと言わず、「この仕事で幸福になれると考えねばならないだなんて理解しがたい。そんなブルシットな仕事は早くお辞めなさい」と言うことでしょう。
あくまで、スヴェンセンが本書を通して批判しているのは「仕事に対して過度な期待を持つこと」および「仕事をただ収入のためとみなしてその人生的意義に無関心であること」です。
そして、クリッツァーが引用しているスヴェンセンの一節は後者を批判している文脈の箇所であって、スヴェンセンはそこでは「収入以外の仕事の意義に関心を持て」と言ってるに過ぎません。
ところが「人間味がある意義ある仕事がしたい」として「ブルシット・ジョブ」に苦しむ人々は仕事の意義に無関心どころかむしろ関心がある側です。関心があるのにもかかわらずどうしても自身の仕事に意義が見いだせない彼らに対して「それでもあなたの仕事に意味や満足感を得られる可能性はある」と期待し続けることを促すのはスヴェンセンも想定外の援用でしょう(むしろ「仕事に意味なんか求めるな」と言う方がかえって救いになりそうです)。
「普通の仕事」に対してファンタスティックな自己実現や完璧な幸福を期待するような「過度の期待」をスヴェンセンは批判しています。
であるならば同様に、不毛かつ無為な「クソどうでもいい仕事」に対して延々諦めずに「意味や満足感が得られる可能性」を期待し続けることはむしろスヴェンセン的「過度な期待」の範疇に入ってしまうでしょう。
従って、クリッツァーの主張はスヴェンセンから批判されこそすれ支持されることはおよそないと思われます。少なくとも、本書のスヴェンセンの論を援用して『ブルシット・ジョブ』批判の論拠とすることは妥当とは言い難いところです。
【補注】「無為な仕事」にも人は耐えられる?
さらに蛇足で、補注を置いときます。
『何もしない』の節で「人が無為に耐えられる可能性」を提示しましたが、ならば「人は無為な仕事にも耐えられる可能性があるのではないか」と思われるかもしれません。ところが、無為を受け入れる代表的な教義である仏教を見てみると、無為を受け入れる過程で「こだわり」がなくなってしまうために「仕事をすべき」というこだわりも同時に消失してしまうようです。従って、たとえ無為に耐えられるようになったとして、「無為な仕事」にわざわざ従事しなければいけない理由はいずれにしても存在しないのです(仕事にこだわることなくただ無為に過ごせばよい)。一般常識的には「仕事」というものは有意義であることを暗に前提としていますから、「無為な仕事」は本質的に矛盾を内包してしまっているわけです。そして「無為な仕事」であるにもかかわらずあたかもそれを「有意義な仕事」を行っているかのように振る舞わなければいけないところに「ブルシット・ジョブ」の残酷さの核心があることも忘れてはいけません。これこそスヴェンセンが批判していた「信仰を強制するカルト的ビジネスマネジメント文化」の一様態とも言えるでしょう。
関連記事
言及した各書籍の感想文は以下。(『資本主義リアリズム』と『21世紀の道徳』については記事として感想文を書いてなかったです)
この記事が参加している募集
江草の発信を応援してくださる方、よろしければサポートをお願いします。なんなら江草以外の人に対してでもいいです。今後の社会は直接的な見返り抜きに個々の活動を支援するパトロン型投資が重要になる時代になると思っています。皆で活動をサポートし合う文化を築いていきましょう。
