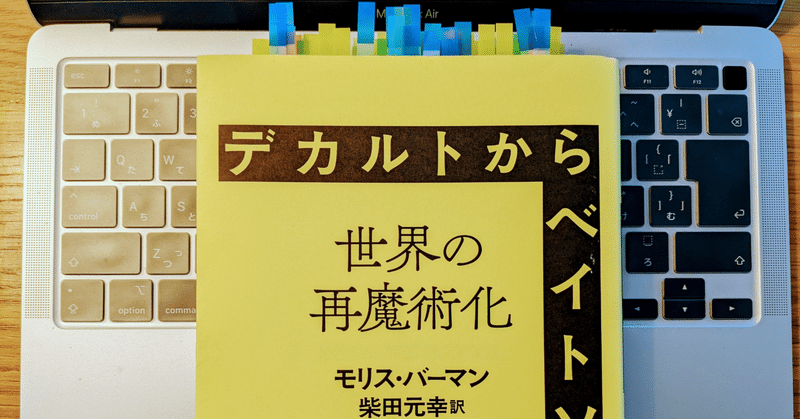
誰が発達障害者を生きづらい社会にしたのか?を探る『デカルトからベイトソンへ』②
前回の記事にて、近代化により世界は「たしかなもの」が失われ、人間は社会が規定したシステムに最適化することが求められる排他的な世界観の中で生きているということを提示した。
発達障害とは、この根拠のない社会が自立するためだけの本末転倒システムを維持するために「排除された」存在のことをいう。
だから『自己責任』なのね。
今回は引き続き『デカルトからベイトソンへ』から引用し、そんな近代社会システムがそもそも成立していないという話をしてみよう。
科学ってそもそも正しいの?
近代社会システムは科学の発展とともに醸造されていったわけだが、皮肉にも最新の科学によりその根拠が崩れさった。
それは不確定性原理、量子力学の誕生だ。
といってはみたものの、非常に難解な話なので僕は理解できなかった。
なんとか簡単に説明してみよう。
前回の記事のとおり、科学は主体(記載する機構)と客体(測定される現実)を分けることから始まった。
しかし、量子力学の実験において、観察者の行動だけでなく意識すること自体が実験に影響を与えていることがわかった。科学実験の最低条件である全くの0はあり得なかったのだ。
主体(記載する機構)と客体(測定される現実)を含めた全体が「世界」であり、科学とは変遷のプロセスの一部を抜き取っていただけだったのだ。
要するに、変遷のプロセスの一部だけを現実としてきたのが近代化だったのだ。
グレゴリー・ベイトソンのいう<精神>とは、「個々の精神を小さなサブシステムとして含む広大な精神」であり、これは無意識であり、神とされてきたものであり、そして社会システムなのである。
それ自体で存在する客体はなく、すべては全体の中での関係だったのだ。
全体は意識の流れにつながっており、それをベイトソンは<精神>といった。
中世までの人間は、全体の流れの中で生きてきた。それがアニミズムや東洋思想であり、西洋近代社会とは真逆の倫理だ。
科学=計測する行為とは、様々な暗黙知が一つの関係を作ることであり、あるのは相対的真性であり、知識を生み出した環境に見合った知識でしかない。
ベイトソンは中世までの人間は「参加する意識」の中にあるといったが、これは「自然と人間の関係にある内在的な真理秩序」なのである。
発達障害者は世界の中心で生き、普通の人々は小さな世界をいくつも持っている
僕の穿った考察だが、発達障害とは「全体の意識の流れ」と親和性の高い個性のことだと思う。
他者と自分の距離感がつかめないのは、全体の流れの中で生きているからであり、断絶された主体と客体の非人間的関係の作る社会の意識が共感できないからではないのかと思う。
「空気が読めない」の空気とは、自己を環境や人間関係の場の中で、いちいち主体と客体を断絶して数値シミュレーション化した結果であるからだ。
「自分は自分である」という意識が、<精神>に根ざしているからこそ、社会システムにより隔絶された小さなサブシステムが乱立する現代社会では『障害』とされてしまうのではないか?
社会は小さなサブシステムの集合体であり、相対的な関係の中から忖度するのが社会の中に生きる人間の真理秩序とされている。
これは裏を返せば、「全体の流れ」の中からよくわからない倫理(宗教、歴史、文化、資本主義・・・)でいくつかの小さなサブシステムを引き抜いてカテゴライズされているだけに過ぎない。それが秩序だとされているのだ。
いわゆる社会人とは与えられたいくつかの小さなサブシステムの中で忖度して生きるように品種改良されたものであり、発達障害者は全体の流れからでしか環境にアクセスできないのだ。
社会人とは、自己のアイデンティティを分裂して小出しにすることができる。
発達障害者は、自己は一つであり、環境が変わろうが自分は自分なのだ。
この世界とのアクセスの差が、症状となって現れる。
だから発達障害者は、世間の人間はウソばかりついていると思ってしまう。
これはウソではない、彼ら彼女らは相対的な個人をいくつか持っているだけなのだ。
発達障害者は「自分が中心の精神世界の住人」であり、普通とされる社会人は「小さな世界をいくつも持ち歩くサバイバー」なのである。
果たして、これはどちらが病気なのだろうか?
病気とは?
社会システムによる去勢の方法
では、このような社会人が生み出されるプロセスとは何なのであろうか?
ちなみにこれは精神病の歴史でもある。
まず、現代人の育成プロセスを見てみよう。
目も見えず耳も聞こえない状態で生まれた幼児は、世界を触覚で知る。身体的な知だ。
世界は体感的であり、無意識により世界を知る。
本来人間は、この無意識による世界の知のままで成長していく。未開文化とされる人々の生活がほとんど似通っているのも、無意識の世界の知で構成された社会システムが人間本来の感覚だからだ。
西洋近代化により、先天的な無意識の世界の抑圧が始まった。
近代化は意識の世界となった。
意識を生むのは自我であり、その自我は文化により作られる。
近代では自我力が強いことを是とされたが、要するに自我力とは近代社会を生きる上での道具でしかない。
存在の方法としての自我なのだ。
この抑圧は性的疎外であり、フロイトはここに着目していた。
近代の機械論的哲学は、抑圧により弱った/相容れない人間を異分子(神経症や精神病)として追いやった。
この抑圧は理性的な視点のみであり、感情はない。感情がないから人間は自己や自然と一体化できなくなってしまった。
この抑圧から生まれた自我は、キャラクターといったらわかりやすいかもしれない。
自我とは抑圧から生まれるものなのだ。
FBIに著書を燃やされた唯一の思想家であるウィルヘルム・ライヒは、西洋工業社会は抑圧された本能を希求しかつ憎悪していると主張した。これは、抑圧された身体的な知の重要性を言い表している。
身体的な知を抑圧され、情動ではなく理性だけの社会システムを強迫的に教育することで、現代の自我とは愛なき世界になってしまった。そこで行われるのは、愛を得るための支配である。だがこれは両立しない。
神経症とは、愛を怖れるように教えた世界で愛を求めた結果なのだ。
ライヒが科学的に証明しようとしたのは、身体的な知(全体論的知覚)は決して無くならないということだった。なんせ幼児期に誰しもが体験していることなのだから。
現代社会は意識的知覚の世界であり、その中で全体論的知覚の世界の住人は「未開人」や「狂人」とされている。
ライヒは、子供の自発性を両親が社会化のために抑圧することで「性格の鎧」ができるといった。
これにより、自発性を怖れ、人工的な性格を身に着けた子供は、身体の動きも硬直性を帯びてくる。我を忘れて経験の中に没入する能力が失われてしまうのだ。
神経症とは、この性格の鎧にコントローラーされている状態をいう。
性格の鎧は他者に対する防御であり、自らの無意識、身体に対する防御でもあるのだ。
社会システムに去勢されない方法
この対策とは、一体化=意識と身体が連続している感覚を持ち続けることだ。
抑圧の本質は、社会のイデオロギーの再生産であり、それは時代によってグラデーションが変わっている。
対策とは要するに、社会の当たり前を自動的に受け入れて自らを抑圧しないことだ。
無論、何をしても良いという意味ではなく、「抑圧の自動化」を避けることが重要なのだと僕は思う。
与えられたものを無反応で受け入れ続けることは、マトリックスの世界だ。
そうではなく、情動的な、身体的な感覚を忘れないこと。そして社会システム発の抑圧から来る感情と、本来の情動的な感情を分けること、これが最高のライフハックだと思う。
社会システム=「全体」だと洗脳されているからこそ、自分を当たり前のように責めたり、自分を卑下する、この負のスパイラルこそ抑圧の本質だ。
社会システムは自分が所属する<精神>の、小さなサブシステムの一つに過ぎない。まずはここから始めることだ。
哲学者マルクス・ガブリエルの著書「なぜ世界は存在しないのか」のいう存在しない世界とは、社会システムという虚構の世界のことであると思う。
小さなサブシステム、マルクス・ガブリエルがいう小さな世界、例えばユニコーンが存在する世界は確かに存在する。それは社会システムしかない世界ではなく、自分の好きな世界をいくつも持つことが可能であるという示唆でもあると思う。
これは現代の社会人が、社会システム内で生きていくために持っているいくつかの小さなサブシステムとは本質的に違う。
自己が産み出した、自分が主役の世界。それを社会システムという生活の場の世界と折り合いをつけながら、自己が産み出した世界(身体的な知から生じる自己が納得のいく価値観を持つ世界)をフレキシブルに移動しながら生きること、これが発達障害者が現代社会で生きる上での対策だと思う。
例えば趣味がある人は幸福感が高いというが、これも身体的な小さな世界だろう。他にも地域の共同体の関係、宗教、ボランティアなども幸福度が高いという。
社会システムの中で囚われている場合、こういった避難できる聖域がない。ヒエラルキーや仕事やカネに囚われ、将来の(金銭的な)不安に苛まれることは、ひいては社会イデオロギーの再生産の抑圧に陥る。社畜なんかがそうだろう。メディアで一生懸命自己アピールをしている人も同じである。
社会学者の宮台真司は、意識高い系を「結局はポジション争い」と切って捨てていたがまさしくそうだろう。
まずは社会システムに囚われているという自覚をすること、そしてそれにストレスを感じているのであれば、押し付けられた社会システムの価値観を打ち破るか、もしくはうまく付き合うか、それしかない。
発達障害者は、この抑圧に先天的に拒否感が強いのだ。ただそれだけのことであり、むしろそれが人間本来の反応だといえる。
「味わう」ことなく知った現実は、我々にとってその現実性が長続きすることはない。何かをリアルにするためには、我々がその何かのところに出ていって、身体を通してそれを吸収しなくてはならない。
まだまだ続きます
絶版後、一冊20000円とかしていたベイトソンの名著が新訳文庫化します。
やってね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
