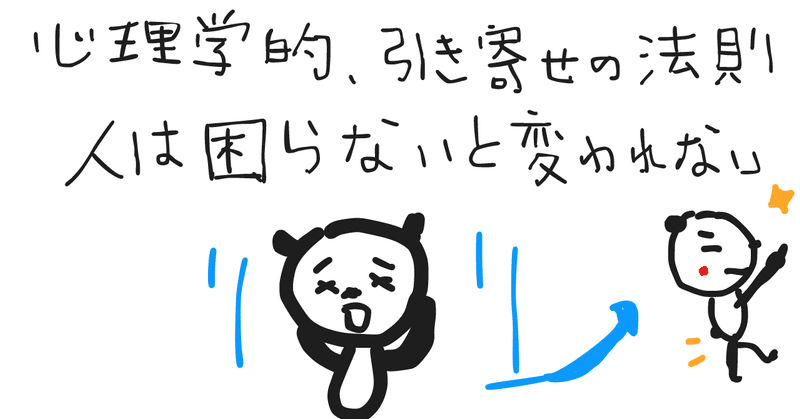
心理学的、引き寄せの法則 人は困らないと変われない
1 裏の欲望の自分を知る
もし幸せになりたい、成功したい、お金持ちになりたい、いい人生を送りたいと思って引き寄せを願ったのに、なぜか叶わない本当の理由は、「実は、叶ってもらっては困る」からだ。
人生を変えるとは、受身ではなく自分から「行動」することだ。しかし、人間の一番の嫌いなことは「変化」なのだ。つまり人生を変えるとは、「行動して変化」することができるかだなのだ。
また、「悩む」と「考える」も違うのだ。
悩むは「現状維持」であり、考えるは「行動」となるからだ。
「悩んでいるから、引き寄せをしてみた」は、「自分は何もしないで、誰かが何かしてくれて、勝手に願いが叶う」とか「願ったから、突然に閃きや運が降りてきて人生が変わる」は、「行動しないで、変化してほしい」となるのだ。
さらに「変化」とは「捨てる」ことになる。
変化できないのは「保証や安定」を望むからだ。
「捨てたくないし、保証や安定もしてもらいたい」の欲が、自分を信じる気持ちや自己愛を狂わしてしまい、生きている目的が分からなくなってしまう。
その結果、「変化」も「行動」せず、恐怖を感じるくらいなら「叶わなかった!」としようとなるのだ。
引き寄せとは、現実を捨て、引き寄せたものを「行動」で確実な真実とできるかなのだ。
2 人は困らないと変われない
もともと動物は、貴重なエネルギーを無駄に使いたいくないのだ。
しかも人は、群れて生き残る選択をした結果、集団の中で自分が不当に活動させられていないかに過敏になってしまった。
他人の行動、他人の取り分、他人の充実、他人からの評価が気になるのだ。
そして、現代人には重労働はないのもかかわらず、他者のリサーチに多くのエネルギーを使って消耗してしまうという矛盾がある。
つまり、人は困らないと変わらないのだ。
結局は、モチベーションの問題なのかもしれない。
エネルギーの観点からも、人の心は単に理屈だけで変わるもようなものではない。
その為、ある程度の体験やトレーニングをすることが必須になってくる。 人はエネルギーを大切にする動物なので、本当に心の底から求めているものでなければ、それをやろうとするエネルギーを出さないのだ。
例えば、うっすらとしたモチベーションを持ち、もしそれが一回の講演に出る程度の労力で身につくものなら身につけたい心理では、講演などで良いことを聞いても、それを一人でこつこつとやるという人は非常に少ない。
それで、また困ったことに遭遇した時は、何かが欲しいと思ってしまう。
習得すればおそらく自分の人生をかなり充実して、楽に過ごせる技術になるとは分かっていても、
今何かに困っていないと、その技術を実際に試してみることさえしない。それでは身につけることは難しい。
3ヒリヒリ体験で成長する
人はピンチになると呼吸が浅くなり、二酸化炭素が低下し不安が生まれる。
この時、成長のためのシナプスが伸びるそうだ。
危機に直面すると、生命体は必死に全力で考察し学習しようとする。
ヒリヒリするからこそ、そのたびにぐっと実力を伸ばしてくるのだ。
つまり本当の変化し行動する時は、ピンチの時だけなのかもしれない。
人は困らなければ変わらないので、ちょっと苦しいと感じるときが、成長のチャンスにもなる。
ただ、あくまでも「ちょっと苦しい」というのがポイントだ。
本当は苦しすぎる状態になっているのに、それを我慢できている。
成長できたという快感でごまかしていると、長期になればなるほどいつか急に人は壊れてしまうのだ。
苦しみの快感でごまかさず、自分の身体と心の声をきちんと聞く機会を持つことも重症なのである。

4引き寄せに適さないタイミング
引き寄せとは、古い習慣を書き換える作業でもあるのだ。
ところが人はいったん習得した習慣や技術をなかなか捨てることができないものだ。
それは、なぜだろう。実はタイミングの問題があるのだ。
1つ目は、本当に困っていないとき。
人は困らない限り、変われない生き物なのだ。
2つ目は、エネルギーが足りないとき。
変わるためにはかなりのエネルギーが必要だ。エネルギーが低下していると変わることに抵抗する。
3つ目は、自信がないとき
自分のプライドを守るために、新しい技術を必死で否定してしまいう。
その為、プチうつ状態の時は引き寄せの習得が難しいのだ。
プチうつ状態の時は、大変苦しいから、引き寄せをやってみようというニーズが大きくなってくる。
しかし、自信やエネルギーが低下しているので、どうしても変化を受け入れたり、継続してトレーニングするのが難しいのだ。
では、引き寄せを最も習得しやすいのはいつかというと、うつのリハビリ期(スランプを抜けたとき)、または、それから半年ぐらいの間だと考える。
エネルギーと自信は回復しているが、一方でスランプのつらさも覚えて、ニーズもあるからだ。
引き寄せを経験し「大変面白い、役に立つ」と感じたが、結局引き寄せられなかったのは、タイミングが悪かっただけかもしれない。

5 体験しないと納得はしない
人は体験してみないと納得しないし、成長しないのだ。
体験とは単なる経験ではなく、経験をもとに自分なりに考え、自分の価値観を磨いていくことを意味する。
机上の学びは、何となくわかった気になる。
多くの知識人は、「だれそれの説ではこうだ」と理論を説明できるが、実際に本当に納得して深く理解し、それを現実の活動に適応できているかどうかは別である。
実際に実習あるいは少しずつ現場で使ってアレンジしてみて、ようやく「なるほどこういうことか」と、深く納得できる段階が訪れる。
このようにして、しっかり自分のものにできるのだ。
わかった気の物理論の数を増やすのではなく、自分で経験し自分で考え、しっかりとした自分理論を構築していく必要がある。
世の中にはエビデンスと称されるデータや権威の意見などがあるが、それは単なる情報に過ぎない。
体験してみなければ、自分の能力・性質や自分の現場にとっての価値や効果は、わからない。
通常は何かを習得しようとする時は教科書なものがあり、その手順通りに一斉にやってみる。そして、うまくいく人もいるがうまくいかない人もいる。
うまくいかない人は、なんとなく自信を失いそのツールが嫌いになるパターンが多い。なぜかというと人は文字を読み、話を聞き、イメージを作る。しかし、たいがいそこで終わるのだ。
ここで実際に行動に起こしてみると、またかなり違った実感を伴うものだ。その実感が引き寄せを進める。
しかし、真面目な人ほどたくさん本を読み、勉強をしているという実感を得やすいが、技術そのものに対する成長の実感は十分ではない。
もしその努力に応じて実力が向上していないとすれば、足りないのは、「行動して、感じてみる」ことなのだ。
さらに、体験するのとしないのではイメージに差がる。
体験は、イメージにもつながる。
人は悩むと時もイメージ(問題、人、出来事)によって悩み、そのイメージが現実的より悩まなくて済む物語に変えていくのがセラピーになる。
ただ理屈だけのセラピーは、体験感が伴わないのでイメージの変化がとぼしいのだ。
体験感を決めるのは情報量の多さであり、さらには現物に触れるのが一番だが、次に情報量が大きいのが感情を伴うことである。
6 試行錯誤(練習回数)が必要
これをやれば「どんな場面でも、だれがやっても正解」というような真実や原則のようなものはなく、個人によって最適なものが変わるのだ。
好みの音楽や味があるのように、自分に最適なものを見つけるまで、どうしても試行錯誤が必要で、しかもTPOによっても変わるのだ。
それが普通なのだが「正しいやり方」があり、自分はそれを知らないから苦しんでいると考える人がいる。
いつまでも正しい方法を探し続け、何かを見つけるけれど、それがうまくいかない時にできない自分を責め、すぐにあきらめ、また新しい魔法のツールを求めるというサイクルに陥ってしまう。
色んな状況に応じて適応的な対応ができるためには、いくつかの方法を試し、自分にとってどれが好ましくどんな効果があり、どんなマイナス面があるかを知っておく必要があるのだ。
最初はうまくいかなくても、やっているうちにその方法の楽しさを見出すこともあり、また逆もあり得る。
このように自分に合うものを見つけていく過程には、どうしても経験が必要になるのだ。経験とはつまり、実体験か練習の数のことだ。
つまり、これをやれば、全員にうまくいくという魔法のような方法はない。自分で試してみて、自分なりにアレンジしたり、取捨選択しなければならない。
事前に次はこれを試してみようという計画が必要になり、それがどれぐらいうまくいったかという評価も欠かせないのだ。この回数をこなすことが、引き寄せを身に着ける一番のコツなのだ。
さらに学生時代にスポーツか音楽をやっている経験がある人の方が、引き寄せの習得が早いかもしれない。
おそらく勉強よりスポーツの学習の方が複雑な要素を含み、成長も直線的ではなく、波を描いて上達するからかもしれない。一時的に成績が落ちたり、スランプになっても、ある程度継続して練習を続けていると、次第に実力が向上していく。そういう経験を積んでいるかいないかは、社会に出てからの様々な習得に大きな差をもたらす可能性がある。
面白いのはスポーツや音楽で優秀な成績を上げた人の中には、逆に引き寄せ胃は習得に難しさを感じる人も多いようだ。
それは、スポーツや音楽を訓練する過程で、「頑張れば必ず報われる、結果が出ないのは頑張りが足りないからだ」というルールを覚えすぎている場合があるからだ。
また栄光がありすぎると、ある課題で人より出来ない自分に対して、一般の人より大きな挫折を感じてしまうという側面もある。
そんな人が何らかのきっかけでうつになると、
努力にしがみつき、
普通の人以下になった自分に自信を失い、
うつからの脱出、つまり引き寄せの習得が普通の人より時間がかかることがある。頑張るやり方、できるはずの自分固執してしまうのだ。
まとめると、引き寄せを習得しやすいのは、スポーツや音楽をやったが、それほど一流ではなく、いろんな苦労をした人なのかもしれない。
7 引き寄せは、ズバリ「正しい答えはない」
「柔軟な思考」を鍛えるとは、同時に引き寄せを身に着けることでもある。
また引き寄せには、正しい答えがないというところに特徴があるのだ。
「ない」というのは正確ではなく、「正しい答えは人それぞれ」と言うべきかもしれない。
また、いったんたどり着いた答えも、状況が変わると変化する。
正しい答えがあると学んだ学校教育で優秀だった人が、必ずしも引き寄せの学びがスムーズではないのだ。学校教育で優秀だった人の半分は、引き寄せの習得に大変苦労する。
一方で、引き寄せの習得でも非常に優秀な人もいるので、引き寄せはセンスでもある。
引き寄せを身に着けにくい人は、すぐに成果が出ない努力を続けることができなく、成果が出ないとすぐに止めてしまう人が多いようだ。状況に応じて様々なパターンを経験し、今の状況に適応できそうなものをあてはめ、さらにそれを微修正していくことが必要なのだ。
つまり、一応の最適解に至るまでに、かなりの時間がかかるのが普通なのだ。しかも、最適解にたどり着いても、自分の感性や体調が変われば、また変化させなければならない。
現実にも、努力をしてもがすぐに成果に現れないということだ。
むしろ、努力しても成果が一時的に落ちてしまうことがよくあり、スポーツなどで新しい技術を身に着けるときによく見られる現象も起こる。
学校の勉強は覚えているかそうでないかで、デジタルに決まることが多い。覚えている、知っていることなら完璧な答えが出せるが、そうでなければ答えは出ない。
努力が成果に直結するタイプの学習だ。この学習体験に慣れてしまうと、努力しても成果を感じられない課題には、じっくりと取り組むことができなくなるのだ。
柔軟な思考のトレーニングをしていても、あと少し頑張れば何らかの変化を自覚できるのというところで、止めてしまう人もいる。そんな人の多くが学校や社会では優秀だったようだ。
自己啓発本などを読んで「よし、これをやって人生を変えよう」と思っても、なかなか続けられない人や、ダイエット情報を見るたび始めては継続できない人は、「この努力、意味がないな」と感じた時点が大切である。
そこで「あと一歩続けてみる」ことを意識することで、思わぬ成果を感じられることがあるのだ。
また成果が出ないとすぐに止めてしまうのは、単にトレーニングのつらさやその単純作業の繰り返しを辛抱できないからだけではない。
成果の出ない自分を感じたくないのだ。
すぐに成果の出ない自分を「ダメな自分」と感じている傾向があり、若いころ勉強だけを行い、スポーツや音楽などの継続的な努力が必要な経験を積んでいない人に多いようだ。
すぐに成長しない自分がいると、極端に自信がなくなり、さらにその課題を避けるようになる。
本当に自信がある人は自分の潜在能力を信じているので、たとえ今すぐに答えが出なくても、ある程度努力を継続していれば何らかの成長を感じることができると感じている。
そんな人は、引き寄せの習得訓練においても、試行錯誤とパターン練習の「回数」をこなすことができる。
そして、引き寄せを身に着けていけるのだ。

8 引き寄せたいなら、行動練習するのみ
試行錯誤がない頭だけの学習だと、「程度の違いを認識できない」のだ。
知識学習では、言葉でしか覚えられない。
その言葉の印象、特に程度は受け取り手によってだいぶ変わってしまう。
現実的に自分が思う程度でやってみて、それを人に相談しながら、少しずつ自分なりに適応できる知恵に修正し育てて行く過程が不可欠なのだ。
知識で覚え、自分なりに思い込んでいる程度の行為をかたくなに守り続けようとすればするほど、逆にパフォーマンスが低下する。
例えば、ゴルフや野球では「腕でなく身体で投げる」とか「腰を切る」などの表現でコツが伝えられる。
これらの表現は言葉としてはわかるが、なかなか実感を得られない。
その言葉を意識しすぎると、逆に変な癖がつくこともある。
特に、現場を踏まないし練習をしない人は、この言葉の真意はいつまでもつかめない。
練習して試行錯誤を繰り返すうち、「ああ、これが身体で投げる」ということかという感覚をつかめる。
ただそれで終わりではなく、そのうち次第にスランプに陥り、そしてまた、「やっぱり身体で投げることが大切だ」と再び気づくという、その繰り返しで成長していく。
表現された言葉にとらわれるのではなく、できるだけそれらが表現している実態に近づき、その実態へ対応していくスキルを磨くのが引き寄せの方法だ。
その際に頭を使ういわゆる勉強は最低限で十分で、後は自分で実態をつかみ、それに対する自分なりのコツを見つけなければ、いつまでも本物の引き寄せはこない。つまり行動あるのみだ。
「知りさえすれば実行は簡単」というジャンルもある。
受験はほとんどがこれだ。ただ同じ受験でも、英語の聞き取りは少々違う。センスやトレーニングが必要だ。知っていることと、それができることには大きな差があるというジャンルもある。
引き寄せを知識で行うものと誤解している人が多いが、引き寄せの本質は行動なのだ。
人は自分が思うように行動できないことが多い。
それを修正していく過程が絶対的に必要だ。
いくら理屈を学んでも、それだけで行動がうまくいくわけではない。
やはり行動しながら試行錯誤が必要な分野なのだ。
本当に引き寄せの実力をつけたいなら、スピリチュアルの本や講座の世界に閉じ籠っていてはいけない。
9 「あきらめる」は敗北ではない
人は成長することが大好きで、これは原始人的に備わった性質でもある。
なぜなら成長すれば、より環境に適応して生きていけるからだ。
だから人には学習意欲があり、向上心があり、そして自分のDNAを受け継ぐ子孫たちにも成長することを望む。
ところが一般的にあることを習得するまでには、かなりの時間と労力が必要だ。1万時間セオリーというものもある。
人に抜きんでた技術を習得するためには、1万時間ぐらいの反復練習が必要になるというルールだ。だから通常、成長のための練習は苦痛との戦いにもなる。
また人は、苦しいことを人はやりたがらない。
行動が喜びよりも我慢の苦痛の方が大きくなった場合に、人はそれをやり続けられない。
だから成長もない。
ある行動をしてみて、たまたま好き、面白い、成長を感じる、仲間を感じる、楽な時間ならばその能力が鍛えられる。
しかしそうでもない場合は、さっさと諦めて他のテーマに移った方が、人生を有効に使える場合が多い。
みんながやるからという弱い動機では、この継続の苦痛を乗り切りにくいのだ。
また、罰や理屈で意欲を刺激しようとしても限界がある。
ネガティブな動機によって、確かにある程度のスキルは身につけることができるかもしれない。
しかし、一流にはなりにくい。
一流を目指すには、ある程度の才能をベースにとにかく楽しい行動、つまり総合的に快楽になってるかがポイントになる。
もしスランプになった時は嫌々続けるより、少し休んだ方がスランプを乗り越えやすく、その後の継続行動にもつながりやすいのかもしれない。
さらに「あきらめる」というのは、人生にとってとても重要なテーマになる。
「あきらめる」ことは、決して敗北ではない。
大きな目的に向かって前進するために、どこかを捨てるのだ。
しっかり全体像がつかめていないと、目先の損失だけにとらわれて、あきらめることができなくなる。
見せかけの欲望にとらわれているときほど、あきらめるという高等作業がしにくくなるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

