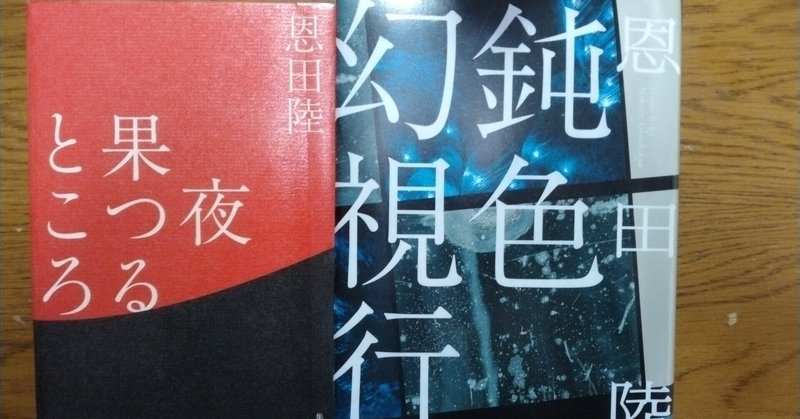
恩田陸『夜果つるところ』『鈍色幻視行』(毎日読書メモ(524))
恩田陸『夜果つるところ』『鈍色幻視行』(集英社)を続けて読む。というか、この2作は、関連を持って書かれているので続けて読まなくてはならない。たまたま『夜果つるところ』を先に読んだが、正解だった。『鈍色幻視行』の中でネタバレされちゃうので。ただし、『鈍色幻視行』を先に読んじゃっていても、テキストが膨大すぎるので、ネタバレの部分を読みながらスルーしちゃっていて、気づかない可能性もあるか、そんなボーっとした読者はわたしだけか。
近刊だが近作ではない。『夜果つるところ』は2023年6月刊だが、「小説すばる」に連載されていたのは2010-2011年。『鈍色幻視行』は集英社のウェブサイトで2007-2012年に連載され、その後「小説すばる」で2013-2022年に数ヶ月おきに連載され、単行本は2023年5月刊。単行本化にあたって大幅に加筆、修正。
一昨年、『愚かな薔薇』読んだ時にも驚いたのだが(感想ここ)雑誌連載を14年も続けた末(2006-2020年)に2022年にようやく単行本化、とか、『蜜蜂と遠雷』(幻冬舎)だって、2009-2016年雑誌連載後2016年に単行本化されている。恩田陸は文学研究の対象にはあまりなっていないイメージだが、発表されている各作品の連載→単行本化の年表を作ると、多くの(そして全然経路の違う)大作がいくつも並行して書かれていることに驚嘆してしまいそうである。
どうやって頭を切り替えて、その作品世界に没入し、続きを書き継いでいけるのだろう。朝起きて、今日はこっちの続きが書きたい気分、とか思うんだろうか?
閑話休題。まずは『夜果つるところ』。
表紙に書いてある作者名は恩田陸だが、中表紙は、恩田陸の名前の内側に「飯合梓 夜果つるところ」(出版社名 照隅舎)という別の中表紙がもう1枚挿入されており、奥付も、飯合梓が1975年に刊行した『夜果つるところ』の奥付が1ページ挿入されている。著者略歴は「北海道出身。本書が初めての著作となる。月のない夜と海をこよなく愛する」となっている。
これは、ある日墜月荘という不思議な施設に連れてこられたビィちゃんという子どもが、産みの母、育ての母、戸籍上の母の3人及び墜月荘で働く人々とともに大きくなっていく物語で、閉鎖された空間で、何か秘密を明かされないまま育っていく子どもの物語は、ちょっと『麦の海に沈む果実』の水野理瀬を思い出させる。
不穏な空気。だれも謎解きをしてくれない中、ひっそりと生きるビィちゃん。墜月荘を訪れる男たちとその相手をする女たち。
「カーキ色」と呼ばれる軍人たち。蜂起。その蜂起で、時代背景がほのみえる。太宰を想起させる作家(ちょっと太宰と時代はずれるけれど)。それぞれがそれぞれの不幸と切望を抱え、そこから抜け出せない。ぞわぞわするゴシックロマン。
墜月荘の月観台に登り、遠く、山の向こう、ほのかに光のちらつく場所を、育ての母莢子から、あそこは夜の終わり、と教えられたビイちゃん。墜月荘の滅びの日、その夜果つる場所へ向かうビィちゃん。
陰惨さ、淫靡さ漂う墜月荘の空気。ビィちゃんの出自の謎。読者はじわじわと真綿で首を絞められるような心地を味わいながら、終末の日を見届ける。
最後の文
「莢子が待っているあの場所、私の長い長い夜が終わる場所、いつも遠くに見えるだけで決して手の届かない、夜の汀の果つるところに。」(p.283)
は
『鈍色幻視行』の最後の一文
「我々の長い夜が終わる場所、誰もが遠くに仰ぎ見ながらも、決して手の届くことのない、我らの夜の汀が果つるところを。」(p.653)
と呼応する。
そしてその『鈍色幻視行』は、1975年に刊行されたということになっている『夜果つるところ』に魅せられた人々の語る、この本と作者飯合梓の謎を解き明かそうとする物語。
作者自身を投影したかのような作家蕗谷梢、再婚同士の夫雅春と共に、客船クルーズに出かける。その船には、『夜果つるところ』を映画化しようとして頓挫してきた、歴代の関係者が集まってきており、船上で、映画化が失敗に終わってきた経緯について関係者の証言を聞いたり、飯合梓はどんな人だったか、という、エピソードを披露しあったりする。『夜果つるところ』に関する本を書いてみようと思う梢は、座談会の録音を起こしてみたり、各関係者に一人ずつでインタビューをしたりして、少しずつ核心のように見えるものに迫っていく。
恩田陸の自己分析を投影したと思しき部分が興味深い。また、過去の様々な映画や俳優たちのエピソード、ミステリ小説について思い出そうとするシーンなどの博覧強記ぶりも面白い。そうした様々な要素が散りばめられ、また、雅春の前の妻であった笹倉いずみは何故、3回目の映画化が試みられた『夜果つるところ』の脚本を書き上げた直後に、遺書も残さず自殺してしまったのか、という謎に迫ろうとするミステリにもなっている。
恩田陸の小説では、これでもかこれでもかと魅力的な謎が繰り出され、この物語の落としどころはどこにあるんだろう、と、残りのページ数を見て首をひねっていると、回収されない要素が沢山残されたまま、ふつりと物語が終わってしまう、ということが沢山あった。そこまでのワクワク感とのバランスが難しく(恩田陸の直木賞受賞が遅くなったのはそのせいかな、と思っている)、この謎の答えもほしかった、あっちの謎も説いてほしかった、と思うことが多かった。この小説も、謎めいた小説、死んだと言われているが、死亡日も死因もわかっていない小説家の謎の生涯、3度にわたって映画化が失敗に終わってきた経緯、という、テーマを列記するだけでお腹いっぱいになるような謎が最初に提示され、集められた関係者も、関係者とはいえ、最初に映画化しようとした際に助監督だった、往年の映画監督とその妻(女優)、小説が文庫化された時の編集者とその妻、映画評論家とその同性の恋人である若者、監督の遠縁で飯合梓マニアの漫画家姉妹(雅春のいとこでもある)、二度目の映画化の際のプロデューサー、と、ストレートな関係者ではないので最初から、ストレートに核心に迫れるはずはないとわかっていて、読者は隔靴搔痒感と共に読み進めることになる。
なので、逆に、この物語には明確なおとしどころはなく、こういう可能性もある、こういう可能性もある、という漠然とした不確実な答えがゆるやかに提示されて終わる(集約ではなく広がり)という予感を持って読み進めたのだが、流石恩田陸、ちゃんと読者を裏切る、というか、これまでに発表された作品の中で一二を争う、押し出しの強い結末がわたしの前に提示された、そんな読後感だった。
飯合梓は一体誰だったのか、とか、『夜果つるところ』の映画化が毎回頓挫するのは呪いなのか何か他に理由があるのか、といった謎は、幾つかの手掛かりが提示される以上の展開はなく終わるが、クルーズが終わって上陸していく関係者たちの顔は、乗船前より明るくなっている。色々な不幸により映画化がかなわなかったのだから、色々な不幸があったことを忘れることはないけれど、表現することの業とか、何かに夢中になることの至福とかが、それぞれの登場人物のモノローグの中からにじみ出てきている。
わたしにとって一番印象的だった一節。
でもな、俺は言いたい。
君らが充実させたいと願っている君らの人生。その中に真実はないぞ、と。
事実はある。現実はある。生活はある。感情もある。たまには感動なんかもちょっぴりあるかもしれない。
しかし、真実はない。人生の中に真実はないのさ。
はっきり言おう。
真実があるのは虚構の中だけだ。
もっと正確に言えば、虚構の中には、真実に触れられる瞬間がある。
これは断言できる。人間の人生は、それだけで精一杯で、真実の紛れ込む余地なんかないんだ。人生を生きている当事者には、その中の真実は見えない。
だからこそ、我々は、映画館の暗がりに、小説の中に、真実を求めに行く。探しに行く。
そうだろう?
なぜ監督は映画を作るのか。なぜ人は虚構の物語を作ろうと望むのか。それは、その中にしか出現しない真実に触れるためだ。
映画評論家が、蕗谷梢からのインタビューの際に語った、本人の見識みたいなものだが、つくりものってどうして大切なんだろう(つくりものなんて全く意義を認めない人もいるだろうけれど)と思ってきたわたしにとって、答えのひとつとなるような気がして、とても腑に落ちた。
作者は、先に『鈍色幻視行』を書き始め、『夜果つるところ』の部分引用を作っているうちに、小説全体を構築したくなって、結局一冊まるまる新しい小説を書いてしまったんだろうな、と思うにつけ、虚構を構築できる人の至福がつくづく羨ましく、その至福をお裾分けしてもらえることに感謝する。
そして、また、次の物語を楽しみに待つ。
#読書 #読書感想文 #恩田陸 #夜果つるところ #鈍色幻視行 #集英社 #小説すばる #飯合梓 #墜月荘 #愚かな薔薇 #蜜蜂と遠雷 #麦の海に沈む果実
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
