
Interview Marcelo Galter:アフロブラジル音楽において重要なのはメロディやリズムだけでなく独特の訛り
アマロ・フレイタスのインタビューを機に僕はブラジル北東部バイーア州やペルナンブーコ州のアフリカ系ブラジル人=アフロブラジレイロの音楽をリサーチしている。少しずつではあるがようやく彼らの音楽のことが見えてきた。
そもそも僕は彼の音楽にブラジル音楽のローカルな部分と、現代的でユニバーサルな部分が同居しているところに関心を持っていた。
西アフリカのヨルバに由来するブラジルの宗教音楽カンドンブレがあらゆるブラジル音楽の源流であることにフォーカスしつつも、そのカンドンブレ由来の要素が持つ可能性を現代的な理論や技術で引き出そうとしているところにこそ僕は惹かれていた。現在、アフロブラジレイロが作っている音楽からは過去も現在も未来も聴こえるような気がしていた。
その後、取材をした故レチエレス・レイチのグループであるオルケストラ・フンピレズのメンバーに話を聞いたときも同じことを感じた。そこでは過去へのまなざしの深さや解像度の高さに驚いた。僕がリサーチしているアフリカン・アメリカンやUKカリビアン、UKアフリカンたちが行っていることと同等、もしくはさらに高い解像度で掘り進めているようにも感じていた。今、アフリカン・ディアスポラの文脈ではブラジル北東部が最も刺激的な場所のひとつなんだろうなと思った。
そのレチエレス門下の中でも最も興味深い存在がピアニストのマルセロ・ガルテルだった。彼のリーダー作『Bacia do Cobre』にはアフロブラジレイロの歴史を研究しまくった彼の深さが聴こえるし、それと同時に僕がアマロ・フレイタスに感じたような現代のジャズにおける新しさに通じるものもかなり含まれていると感じた。そのふたつが驚異的なバランスで成り立っている『Bacia do Cobre』はコンテンポラリー・アフロブラジレイロの傑作であり、グローバルな文脈においてももっと知られるべき作品だろう。だからこそ、マルセロ・ガルテルには一度じっくりと話を聞かねばと。
この取材では最終的にはアフロブラジレイロの、というより、アフリカン・ディアスポラの音楽にとっての重要な、そして、本質的なポイントの話に辿り着いた。マルセロの言葉のおかげで、アフロブラジレイロ音楽へのリサーチはもっと先に進めそうだ。
◆取材・編集:柳樂光隆 , 江利川侑介| ◆通訳・編集:島田愛加
◉マルセロ・ガルテルのバックグラウンド
――バイーア州のサルヴァドール出身とのことですが、アフロブラジルの音楽には子供のころから親しんでいたのですか?
私はサルヴァドールのピラジャー(Pirajá)という地区に生まれ、育ちました。サルヴァドール近隣の街で、人口の多くは低所得層のアフリカ系ブラジル人です。サルヴァドールにはアフロブラジル文化がありとあらゆるところに存在しています。そのため、子供のころからパーカッシブな音楽や、仲間と集まって音楽を演奏する機会がありました。集まってホーダ*をしたり、太鼓を叩いたり、時には缶を叩いたり。こういった音楽は、お祝いやカンドンブレなどで演奏されています。
――音楽を専門的に学んだことはありますか?
ピアノは独学で始めました。両親が4オクターブのカシオのキーボードを買ってくれて、兄弟で時間を分けて練習していたのですが、私は4人兄弟の末っ子なので、自分の番が回ってくる時にはキーボードが熱くなってしまって練習できないなんてこともありましたよ(笑)
音楽理論を学んだことはなかったので、耳で音をさぐりながら弾いていました。専門的に学ぶようになったのは、16歳の時。地元の先生にピアノを習い始め、その先生がバイーア連邦大学の音楽学部に入学できるように手ほどきをしてくれました。
バイーア連邦大学では、ピアノ科に入学し、クラシックを勉強しました。
◉影響を受けたピアニスト・作曲家
――学生時代に特に研究していたピアニストは誰ですか?
大学時代はバッハの音楽性に夢中だったほか、セロニアス・モンクや、エルメート・パスコアルに強い興味がありました。エルメートとは、サルヴァドールで共演する機会にも恵まれました。また、ジョアン・ドナートの作品にも魅了されました。彼らはピアノ界のヒーローですね!
同時に、いつも他の器楽奏者にも興味を持っていました。例えば、マイルス・デイビスや、私たちの文化を代表する楽器であるビリンバウの偉大な奏者ロウリンバウ (Lourimbau)。彼の作品をいくつも聴いて書きとめ、それをピアノで試してみたりもしました。
――ロウリンバウとは、どんなミュージシャンですか?
ロウリンバウは偉大なビリンバウ奏者、作曲者です。バイーアにおいて、ビリンバウはカポエイラの音楽と強い関係をもっています。それは伝統的なアフロブラジル音楽とはまた違ったものです。ロウリンバウはカポエイラでの演奏だけでなく、また別のシーンにビリンバウを取り入れました。また、彼は奇数からなる拍子のメストリ(達人)でもあります。
私にとってロウリンバウはトラディショナルな音楽にコンテンポラリーを取り入れるお手本となった人です。私のアルバムにも彼へのオマージュとして作った「Lourimbau」という曲があります。
――特に研究したコンポーザーだと誰になりますか?
クラシック音楽の作曲家で最も研究したのはバッハです。彼の作品は私のような小さな手をもつピアニストとぴったり合うんです。同時に、コントラポント(対位法)やポリフォニー(多声様式の音楽)にも惹かれました。ブラジルを代表するクラシックの作曲家であるエイトル・ヴィラ=ロボスの作品にもバッハの影響をみることができますね。バッハはこの世で最も重要な芸術を作り出した人物の1人だと思います。彼の音楽は様々な音楽と相性が良いだけでなく、そこに浸透し影響を与えています。私のバッハへの興味はそういったところにあります。
◉アフロブラジレイロから見たエルメート・パスコアル
――卒業後にも研究していたピアニストはいますか?
エルメートがピアノで作り上げたものは、私にとって啓示を得るようなものでした。私が前のめりになるほど夢中になった作曲家でもあります。エルメートと何度かのリハーサルを通して一緒に過ごせたことは非常に幸運なことでした。
ブラジルでは長い間、ピアノの作品とはショーロやサンバの伝統に関係していたんです。例えばセーザル・カマルゴ・マリアーノやジョアン・ドナートのようなピアニストはエルネスト・ナザレやシキーニャ・ゴンザーガのスタイルを現代化させて弾いています。一方でエルメートは北東部の音楽など、ピアノの作品として演奏されていなかったものを取り上げました。同時に、伝統だけでなくコンテンポラリーな要素も付け加えていますね。エルメートはピアニストとして、作曲家として最も私がインスピレーションを受けた人物です。
――なるほど。
それと、彼の手も私と同じように小さいので、重なる部分があるのかもしれません。リハーサルの際、エルメートは私の手と自身の手を合わせて「僕の手の方がちょっとだけ大きいね」なんて冗談を言っていましたよ(笑)。 ショパンなど、クラシックのピアノ作品は基本的に大きな手に合わせて書かれるものが多いですし、そういった点でエルメートは新しい奏法を見せてくれました。
――エルメートのピアニストとしての特徴をもう少し聞かせてもらえますか?
エルメートはリズム的な部分で革新をもたらしました。鍵盤楽器以外の楽器からのヒントも取り入れていますよね。例えば、彼のピアノからはスルド(サンバに使われる大太鼓)やトライアングルの音など、パーカッションやそのアンサンブルの音が聴こえてくるんです。あとはバイアォンやピファノ(北東部で使われる笛)のアンサンブルなども引用しています。
――エルメートって作曲家としてもあまりに独特なスタイルなのですが、彼はどんな影響を昇華して自身のスタイルを確立したと思いますか?
彼は「音楽」だけでなく、「自然」との間に強いつながりを持っています。彼は研ぎ澄まされた精神の持ち主で、小さい頃から林の中に入って動物の声や自然の音を聴いていました。エルメートが誰かしらの作曲家と繋がりがあったかということはわかりませんが、彼の聴力というのは非常に豊かで幅広いものです。エルメートの音楽はまるで別世界なので、私には一言で語り切れませんね。
――プロになってから特に研究したコンポーザーはいますか?
ドリヴァル・カイミです。彼の音楽はバイーアの風景をとても美しく描いていますね。メロディの書き方も前例がありません。彼のギター奏法はビリンバウからヒントを得たと本人がインタビューでも答えています。また、バイーアの古き良き詩情に満ちた音楽を私に教えてくれました。オリジナリティある音楽ですね。
――アメリカやキューバのピアニストからの影響はどうでしょうか?例えば、スティーブ・コールマンのバンドにいたピアニストとか。
パーカッシブで、開放的なセロニアス・モンクのピアノは、まさに私が求めていた音でした。彼の奏法はピアノ的ではないかもしれませんね、どちらかというと濁ったような音ですし。
セシル・テイラーの奏法にも魅了されました。あとはキューバ人ピアニストのダヴィ・ビレージェスも素晴らしいと思います。クレイグ・テイボーンの弾き方も好きですね。
実はスティーブ・コールマンとは共演したこともあります。彼はバイーアに家を持っているので、夏になると遊びに来るんですよ。彼の楽曲を教えてもらったり、モウ・ブラジルのレコーディングにも一緒に参加したんですよ。
◉マルセロ・ガルテルのこれまでの活動
――次はあなたのキャリアについて聞きたいのですが、これまでどういった音楽活動をしてきたのでしょうか。
私のプロとしての活動は、サルヴァドールで小編成のインスト音楽から始まりました。その後、大きな編成のグルーポ・ガラージェン(Grupo Garagem)や、既にバイーアの音楽に即興を取り入れていたギタリストのモウ・ブラジル(Mou Brasil)のグループやバイーア・ブラッキ(Bahia Black)でも演奏しました。
バイーア出身のギタリストで現在はフランスで活動しているネルソン・ヴェラス(Nelson Velas)と演奏する機会もありました。彼は私の音楽に強い影響を与えています。
また、7年間ダニエラ・メルクリのバンドに所属した時期もありました。他にもカルリーニョス・ブラウンやマルガレッチ・メネゼスなどバイーアのパーカッションの影響を強く受けているポップス音楽=ムジカ・ポッピ・バイアーナのサポート経験もあります。それとマリア・ベターニア!彼女との共演は私に衝撃を与えました。イタリア人ジャズ歌手マリア・ピア・デ・ヴィト(Maria Pia de Vito)の伴奏をしたこともあります。
このように、基本的にインスト音楽とムジカ・ポッピ・バイアーナが中心で、最も多いのはインスト音楽ですね。
――そのインスト音楽ってどんなものなのでしょうか?
始めの頃はジャズやボサノヴァのレパートリーなど、即興が入る演奏していました。そのあと、バイーア・ブラッキやモウ・ブラジル、チト・オリヴェイラ(Tito Oliveira)。レチエレス・キンテートのメンバー)などと一緒に演奏するようになって、もっと創造的なインスト音楽を演奏するようになっていきました。チトのアルバムをプロデュースする機会にも恵まれ、私やルイジーニョ・ド・ジェジ(Luizinho do Jêje)の楽曲をレコーディングしました。
◉レチエレス・レイチとの関係
――あなたにとってレチエレス・レイチは特別な存在だと思います。彼と出会って、共演するようになったきっかけを教えてください。
大学で勉強をし始めた頃、私の前にレチエレスが現れました。当時、彼はブラジルで大変有名な歌手イヴェッチ・サンガーロのバンドで演奏していましたが、アフロブラジル音楽を元にしたインスト曲の作曲も始めていて、既にプロジェクトのスケッチをしていました。彼はタンボール(太鼓)の話や、アフロブラジル音楽をインスト音楽として演奏する事の可能性について話していましたが、当時の私にはまだ理解ができないこともありました。
しばらくしてレチエレスはオルケストラ・フンピレズという大きな編成のバンドを立ち上げましたが、彼は小さな編成のグループも作りたいと考え、2001年*にレチエレス・レイチ・キンテートを結成します。そこに私はピアニストとして参加することになりました。キンテートはフンピレズと平行して活動していましたが、1枚目のアルバム『O Enigma Lexeu』がリリースされたのは2018年になってからのことです。このグループでは口承伝統のリズム体系や、バイーア音楽のパーカッションに根差した演奏をするというチャレンジをしています。即興についても、タンボールのフレーズを活用することをレチエレスはよく話していました。
彼の近くにいられたことは非常に特別なことで、彼が作った多くの作品に参加し、演奏する喜びを味わいました。彼との出会いは、私のアーティストとして、プロフェッショナルとしての人生の分岐点です。また、レチエレス監修のマリア・ベターニアのショー『Claros Breus』にも参加するなど、彼を通して多くの素晴らしいブラジルのアーティストと共演できました。
――オルケストラ・フンピレズとは異なり、レチエレス・キンテート、そしてあなたのカルテットはコード楽器であるピアノが入ります。フンピレズとレチエレス・キンテート、そしてこの『Bacia do Cobre』では、どういった違いがありますか?
フンピレズでは、管楽器奏者たちは楽譜に書かれている音符を演奏することに限定されています。レチエレスは作曲家として、全てのメロディを書いていました。オーケストラの中で、楽譜に書かれていないことを演奏していたのはパーカッショニストたちです。彼らはアフロブラジル宗教のカンドンブレのリズムを多く取り入れています。レチエレスはそれらをフォーマットしながら新しいもの作り上げていました。即興部分もありますが、基本的にはオーケストラのひとりひとりに既に役割が決められているような感じです。
一方でキンテートは楽曲を作る過程は全て口伝えで行われるんです。レチエレスはメロディとコードがメモされたシンプルな楽譜をもってくることがあるくらいです。ベースラインや曲調などは、リハーサルで口伝えにて創り上げられていきます。そのため、リズムの上で即興して音楽を作るなど、実験的なプロセスもあります。長い間それを繰り返し、メンバーはこの表現法を身に着けていきました。そうなると各自が自分の言い分を持ち始めますね。それぞれ自分のグループを始めたりします。
そして、レチエレスのキンテートと私のカルテットの大きな違いはパーカッションです。私はジャズトリオの基本的な編成であるピアノ、ベース、ドラムのドラムを2人のパーカッションに置き換えることにしました。更に、宗教的な音楽に精通するルイジーニョ・ド・ジェジ、バイーアのパーカッショングループで活動しながらもジャズにも詳しいヘイナルド・ボアヴェントゥーラ(Reinaldo Boaventura)というバックグラウンドが異なる2人を起用しました。私はピアノ、コントラバス、2人のパーカッションという4人が合わさる音を考え、それを実現させました。また、このグループではそれぞれに異なるリズムを演奏する試みもしました。そのため、リズムが非常に複雑になった上での即興演奏は常にチャレンジになっています。
◉デビュー・アルバム『Bacia do Cobre』
――あなたのアルバム『Bacia do Cobre』について聞かせてください。このアルバムではサルヴァドールの環境保護地域の名前から取られています。そしてジャケットに使用された絵の作家であるジェナーロ・ヂ・カルヴァーリョ(Genaro de Carvalho)は、木、花、鳥を頻繁に描き、バイーアのフォークロア要素を含む作風のタペストリー作家でした。そのタイトルやアートワークが意味するところを教えてください。
タイトルになったバシア・ド・コブリは私が育ったピラジャー地区に位置します。かつてはトゥピナンバー(Tupinambá)の先住民が暮らし、奴隷制の時代には反抗した奴隷たちによるキロンボ・ド・ウルブ(Quilombo do Urubu)という集落も作られ、アフロブラジル宗教において神聖な場所でもあります。そして、ブラジルに残された最後の大西洋岸森林であり、かつてはブラジル独立に伴って勃発したピラジャーの戦いの舞台ともなりました。ブラジルの歴史だけでなく、バイーアの歴史においても重要な場所です。
私はここに生まれ、この場所に関する多くの言い伝えや神話を聞いて育ちました。美しい動物の群れ、流れる川は地域の人々の生活を満たし、非常にエネルギッシュです。私が生きてきた中で最も素晴らしい場所だと思います。 しかし、残念なことにこの近隣に住む人々の暮らしは厳しく、この場所の素晴らしさに目を向ける状況にないのが現実です。そのため、私はこの場所へのオマージュをすることにしたのです。
ジェナーロ・ヂ・カルヴァーリョについてですが、アルバムのジャケットになったのは1966年に描かれた『Parque dos Girassóis』(ひまわりの公園)という作品です。彼はフランスで絵画とタペストリーを学びました。ブラジルに帰国してからはヨーロッパのテクニックとバイーアの大衆的な芸術の融合を行いました。外国の影響を受けながら、自分が持っているものを継続する、これは私の音楽と重なる部分があると感じました。
――次は音楽におけるコンセプトについて聞かせてください。
このアルバムはグループとしての経験に基づいて生まれたものです。私は作曲したというよりメロディやハーモニーを提案し、グループでどのようにそれを表現できるかメンバーと共に考えました。メンバーは私の尊敬するミュージシャンたちで、みな同じ言語を話し、同じような環境で育っていますから、音楽的にも同じエッセンスを持ち、一緒に成長してきています。
アルバムの全ての曲が、アフロブラジル宗教で使われる3つのタンボールや、フィーリョス・ジ・ガンジー(Filhos de Gandhi)やイレー・アイレーのようなカーニバル的なパーカッションのグループなど、バイーアのパーカッション・アンサンブルから影響を受けています。私が生まれた土地で聴かれる音楽を表現したいと考えたんです。
同時に、制限なく即興することや、型から外れることを受け入れました。ミスをしそうなシチュエーションや危機感こそが、私たちの自発性と創造性を掻き立てたんです。
◉『Bacia do Cobre』のリズム面でのアプローチ
――『Bacia do Cobre』は2人のパーカッションを軸にした4人のリズム面でのチャレンジが印象的でした。
リズムのボキャブラリーを増やすことは、即興演奏をする音楽家にとって常に重要なことです。このリズムへの課題は私たちが自発的に演奏するための非常に強力なツールとなります。その言語(リズム)を何度も聴いているからこそ、身体と結びついていて自動的に演奏することができるのですが、完全に一直線ではないため、その有機性がミュージシャンにとって常に刺激的なのです。
私たちはレコーディングをする前に40回のリハーサルをしました。残念ながら、パンデミックの影響で、お客さんを迎えて演奏することは一度もありませんでしたが。このリハーサルで私たちが求めていたのは、身体とつながるリズムと、流れるようなグルーヴをもつ音楽を作ることでした。そんな中、グループのメンバーは刺激的なリズムの中で様々な提案をしてくれました。私は個々の音楽性を取り入れ、活かすことにしました。
ルイジーニョによるカンドンブレの伝統、ヘイナルドは拍子の達人であり様々な音楽性を持ち合わせています。コントラバスのレジソン・ガルテル(Ldson Galter)はこのようなパーカッシブなインスト音楽のスペシャリストです。例えば、パーカッションのグループにも低音(域の楽器)があり、カンドンブレなら3つのタンボールのうち最も低い音をもつのは“フン”という楽器です。フンは同時にソリストの役割を持つんですが、レジソンはそういったパーカッションの役割を損なわないようにコントラバスを演奏することができます。
――『Bacia do Cobre』には主にアフロブラジレイロのリズムが使われていると思いますが、それ以外のリズムも入っているように聴こえるんですが、どうですか?
既存するリズムがベースになっているのですが、殆どが様々なリズムが混じり合ったものです。「Cobra Coral」はカビーラというサンバの祖先となっているリズムが基盤となっていますが、拍子を変えています。
「Bacia do Cobre」はカンドンブレのジンカー(Jinká)というリズムに基づいて作られていますが、ルイジーニョだけがこのリズムを演奏し、私たちはそれとは全く異なる11拍からなるグルーヴを演奏してるんですよ。
つまり、ベースになるリズムからインスピレーションを受けていますが、それをもとに新しいものを作っているような感じです。例えば、ヴァーシ(Vassi)という12拍子のリズムがあるんですが、それを9拍子として演奏するようなこともやっています。
――ミニマルに反復が続く曲が少なくありません。その中でピアノはジャズのピアノトリオのような役割というよりは、リズムの一部になって、打楽器的な役割を担っている部分も大きいと思います。リズムのアプローチに関して、インスピレーションになっているピアニストはいますか?
名前を挙げるならエルメート・パスコアルでしょうか。ピアニストは、左手の奏法が非常に特徴的で、それによって識別されることが多いと思うんですが、私はピアニストではなくいつも異なるところからインスピレーションを受けてきました。例えばバイーアのリズムとハーモニーの役割を果たすヴィオラ・マシェッチ(Viola machete)という楽器や、アフリカのカリンバの弾き方などを、よりパーカッシブな音を創るうえで参考にしてきました。これらの楽器表現は非常に豊かなんですよ。私は音程がありながらもパーカッシブな楽器を演奏している意識なので、ピアニストよりも、他の楽器を参考にすることが多いんです。
――『Bacia do Cobre』でのあなたのピアノはリズムセクションの上でどんどん展開するというよりは、リズムと同化しつつ旋回するような印象です。ただ、情感や質感は少しずつ変化している。ピアニストとしてのリズム面以外の演奏についても聞かせてください。
すべての思考は、繰り返し循環するモチーフを中心に展開されています。
ピアノの役割は多くの場合でアンサンブルの中で起こっていることを観察する感じですが、ソリストになることもあります。ソリストになった時は、それまでグループ全員で(協調して)パフォーマンスしていたのと変わって、(他のメンバーを)挑発をしたりするんです。それでグループがより盛り上がることもあります。主役のソリストを務めるピアニストというよりも、挑発人/仕掛け人のような存在です。
メロディに関してはアフロブラジル音楽を勉強した時にペンタトニック・スケール上に書かれている事に気づいたこと、そして、ネルソン・ヴェラス(前述)が教えてくれたフランスの作曲家オリヴィエ・メシアンからも影響を受けています。メシアンが著書に記した移調の限られた旋法も参考にしていて、「Cobra Coral」はこの旋法の第3番に基づいて考えました。非常に開放的なメロディですね。また、メシアンの音楽から感じる強い精神力にも魅了されました。より深く研究する機会はなかったのですが、何曲かの作品を勉強し、彼の著書を読んだことがあります。
◉口承文化の重要性
――レチエレスは、本作『Bacia do Cobre』に寄せたライナーノーツにおいて、「オラリティ」=口承文化について言及しています。これはアフロブラジル文化、そしてその祖先であるアフリカにおける文化継承の特徴かと思います。文字を媒介として文化を人々に波及していくリテラシーではなく、オラリティがベースにあることの重要性について、あなたの考えを教えてください。
アフロブラジル音楽では、メロディやリズムだけでなく独特の訛りが非常に重要なんです。レチエレスは、このようなアフロブラジル音楽に強いインスピレーションをうけた現代的な楽曲にも、非常に明確な訛りが感じられると言っていました。オラリティはそれを伝えていくうえで最も有力な方法です。このような音楽をヨーロッパのシステム、つまり楽譜に書き表して学ぶと、多くのギャップが生じます。例えば私が楽譜を正確に書いて、それを元にサンパウロ州のミュージシャンと演奏したら、私が思う結果にはならないと思います。
私たちの教育システムが口承文化を認識していないことを、はっきりと受け止める必要があります。文化は、言葉があり、それを表現する方法があり、リズムがあり、そのリズムに対する感覚があるというように、厳格に組織化されています。
フンピレズはレチエレスが今の世代の音楽家に対して様々な挑発を行ったという意味で、革命的なグループでした。彼は亡くなる前に、私に向けて壮大なピアノソロ曲を作ったんですが、彼は楽譜を書いただけでなく、楽曲をソルフェージュ(メロディを歌うこと)し、その元となったリズムや、音楽への感情を吹き込んだ声の録音を残してくれました。レチエレスはこの口承文化の効果を信じていたんです。
――僕は少し前に、南アフリカ人ピアニストのンドゥドゥーゾ・マカティニのインタビューをしました。西洋的なテキストや譜面による教育とアフリカらしい口承による教育についての話を聞きました。彼は今、そういったことが考慮されるようになり、南アフリカの音楽教育の在り方が変わってきていると話してくれました。ブラジルでもそういった傾向はありますか?
彼の音楽は知っています。例えばレチエレスが立ち上げたフンピレズ・インスティチュートでは、身体を使って音楽を感じることから始めます。輪になってソルフェージュをしたり、身体を使ってリズムを感じたりするんです。
私のカルテットでも、楽譜は使いません。コントラバス奏者は私の兄ということもあり、メロディは全て私が歌って覚えてもらいました。パーカッションのパターンなども、全て歌って口伝えで説明しています。楽曲のエッセンスが伝わりやすいという利点もありますね。
――あなたのアルバムの楽曲には楽譜が1枚もないんですか!?
「Cobra Coral」のコントラバスのフレーズだけ非常に複雑なので書きましたが、それ以外にはありません。パーカッショニストの2人は楽譜を読む習慣もなく、いつも読まずに演奏していますよ。
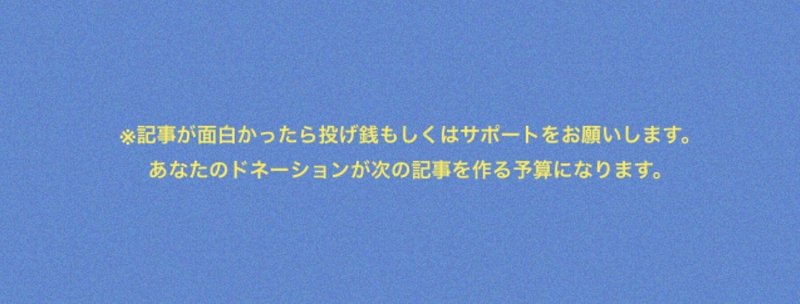
ここから先は
¥ 250
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
