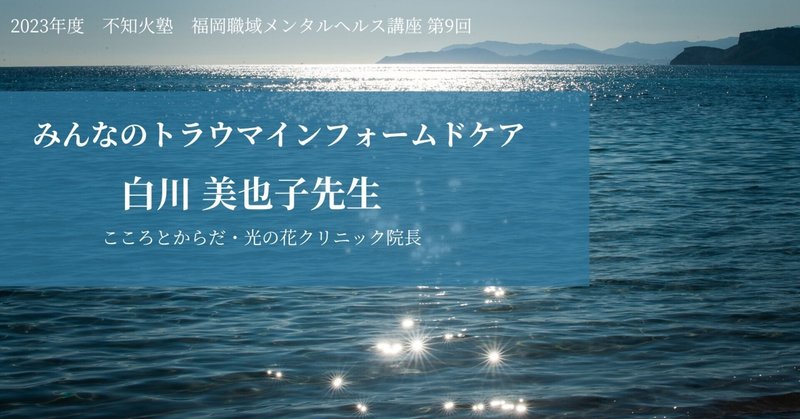
日本人の32%が抱える「トラウマ」の理解とアプローチ
トラウマと聞いて思い出すことはありますか。
自分にとって嫌な体験を想起する人も多いのではないでしょうか。実は私自身もそうです。
日本人の約32%がトラウマを抱えていると言われていています。
不知火塾 第9回目は、こころとからだ・光の花クリニック院長 白川 美也子先生による「みんなのトラウマインフォームドケア」がテーマでした。
白川先生はトラウマは公衆衛生問題だとお話されます。
1.トラウマ概念の拡大化
◆ 新しいトラウマ概念-関係性トラウマ-
関係性トラウマは、信頼できる関係性が不足していることや、暴力や虐待などの経験によって発達上の損失や精神的なトラウマを引き起こすことを指すとのこと。
意識せずに行われる安全に関する知覚を、ニューロセプションと呼ぶと述べられます。
トラウマは①トップダウンの調整不全をきたす②ニューロセプションの形成により安全な繋がりを実現する自律神経回路を構築するボトムアッププロセスを妨げる③調整とレジリエンスの発達を阻害し、人との繋がりを防衛的なパターンに変え、他者との関わりを損なうそう。
トラウマの後遺症はトラウマ記憶だけでなく、早期の生存反応による自律神経系の習慣的なパターンも影響するとおっしゃいます。
◆ 児童期逆境体験
児童期に虐待やネグレクト、両親の離婚などの逆境体験が多ければ多いほど、神経発達の障害、社会的・情緒的・認知の障害、健康を害する行動による順応、疾病、障害、社会不適応が発生する確率が高くなるそうです。
4つ以上の逆境体験があると、20年以上早く亡くなってしまうデータもあるとのこと。
◆ トラウマ記憶は冷凍保存記憶
トラウマ記憶は圧倒的な体験により、特殊なメモリーネットワークが生じ、そのときの五感、感情、認知、思考がまるで冷凍保存されたように残ってしまうことだと話されます。
● 無時間性
● 想起に苦痛な情緒を伴う
● 言葉になりにくい
フラッシュバック中に神経の興奮が偏在していることが明らかになっており、人間の精神に対して個人の対処能力を超える圧倒的な体験が、心的メカニズムに不可逆的な変化を被らせることがわかっているそうです。
回復過程の障害といわれるPTSDは、トラウマによるネガティブな影響の極型といわれているとのこと。
以下の4つを主要症状として説明されました。
● 再体験症状
● 回避・麻痺症状
● 過覚醒症状
● 出来事に関係する認知と気分の否定的変化
PTSDの危険因子(保護因子)は以下の3つに分けられると話されます。
● 体験前の要因(子ども期の逆境体験など)
● 体験要因(体験の強度、生命の危険度など)
● 体験後要因
メンタルヘルス専門職が介入できるのは体験後要因(保護因子)であり、体験後の治療や社会的サポート、二次被害の予防などを挙げられました。
その他にも発達性トラウマやアタッチメント・トラウマなどを白川先生の実体験を交えながら紹介いただきました。
ひとえにトラウマといっても、多種多様なタイプがあるのだと学ぶことができました。
2.いじめやハラスメントの及ぼす影響の深刻さ
◆ いじめとトラウマ
白川先生は学校でのいじめが、職場いじめに繋がっていることがあるため、いじめをみたら関係性トラウマを疑うことを指摘されました。
幼少期のいじめは成人期まで深く伝播し、成人期早期にうつ病を発症する可能性が2倍、成人期のうつ病の約29%は、思春期の仲間による被害に起因すると述べられます。
◆ トラウマの関与
白川先生はパニック障害、不安性障害、PTSDのすべてにトラウマが関係していると考えておられます。
● パニック障害:発達性トラウマが関与しており神経系の変化と身体的ショックと関連するニューロセプションの形成され、過去の体験からくる恐怖がある。
● 不安性障害:関係性トラウマが関与。アタッチメントと関連するニューロセプションの形成があり、未来に対する不安がある。
● PTSD:トラウマ記憶の関与が大きい。
◆ 複雑性PTSDとPTSD
複雑性PTSDとPTSDの違いは、自己組織化の問題の有無だとおっしゃいます。
複雑性PTSDは、ニューロセプションによる神経系の調整機能やメタ認知の形成不全が自己感に影響を及ぼし、少しの刺激でパイ生地のように崩れやすいと話されます。
それに対しPTSDは、トラウマ記憶が問題でトラウマが起きる前の健康な状態に戻れるように介入することが大切だとおっしゃいました。
● 対人関係障害
● ネガティブな自己概念
● 感情の調節障害
● 脅威感
● 再体験
● 回避
ただし二分できるものではなくこれを両極として、さまざまな状態があり得ることをハラスメントの事例を通して知ることができました。
◆ 組織的トラウマとは
組織的トラウマとは組織や職場の環境で発生し、その環境内の個人や集団に影響を与えるトラウマの一種とのこと。
自然災害、労働災害など職場で起こるその他のトラウマ的な出来事など、さまざまな要因によって引き起こされるとおっしゃいます。
下記の2つのレベルに分けられるそうです。
● 個人レベル:トラウマが組織内の個々の従業員やグループに与える影響
● 集団レベル:トラウマが組織全体に与えるより広い影響
トラウマは個人的なものだと考えていましたが、組織自体がトラウマ化されることもあるのだと知りました。
3.トラウマインフォームドケア
◆ トラウマインフォームドアプローチの概要
以下を元にした、トラウマの情報に基づく相互交流やトラウマの情報に基づく中核技術(トラウマレスンポシブケア)を説明いただきました。
①安全
②信頼性と透明性
③ピア・サポート
④恊働と相互性
⑤エンパワメント:VoiceとChoice(声を与え、選択させる)
⑥文化・歴史・ジェンダーへの配慮
安全・安心の確立を第一段階とし、心身の状態に対処すること、自分一人でも感じられる心地よさを身体のなかに探し、安全感を作ることが大事だと述べられます。
1. 安全・安心の確立
2. 再想起・服喪追悼
3. 社会的再結合
セルフケアとして、セーフ・プレース・エクササイズを紹介いただき、身体の中に安全感をインストールするという視点を持つことができました。
フラッシュバックや解離への対処法も事例を交えて具体的な手法を説明いただきました。
再想起と服喪追悼が第二段階となり、ここで初めてトラウマのストーリーを語る段階となるそう。
第三段階は再結合であり、過去との和解を達成した後、新しい自己を成長させ、自分を支える信念を改めて発見し、新しい関係を育て、未来を創造する段階だと説明されました。
◆ トラウマインフォームドな交流スキル
以下の3つを中心に、クライアントとの交流スキルを紹介いただきました。
①クライアントに何かをするべきか指示することを避け、選択権と主導権を提供するエンパワメントするアプローチ
②何を頼りにサバイブしてきたかを認識し強みに焦点化し、すべてのポジティブな選択を指摘、目標を達成させる助けになる能力や技量への選択に繋げる
③心理教育を行い、情報を提供し知識を力として身に付けてもらう
次に何が起こるのか予想できるように手助けしていくことを事例をもとに示されました。
クライアントに対する言葉の使い方として指示ではなく質問をするように心がけることが大事だと話されます。
ただし「なぜ」は使わないとのこと。
「どうやって」「どんなふうに」にと質問し、内的過程を言葉で説明してもらうようにといった具体的なアプローチ方法も紹介いただき、非常に実践的なお話を聞くことができました。
最後に1人で患者さんに向き合うのではなく、仲間とともにいる感覚をもって向き合うこと、自分も人も癒していくこと、癒し手として自分をみていくことの大切さを教えられました。
白川先生の実体験に裏打ちされた、お話はどれも貴重で非常に勉強になりました。
ありがとうございました。
不知火塾の詳細はこちら
次回は「職場で遭遇する睡眠問題」について
次回案内はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
