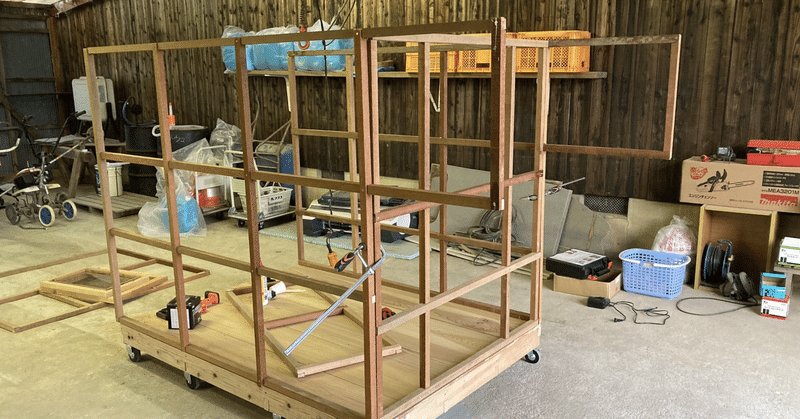
家づくりにおいて②
家づくりにおいて②
リフォーム/リノベーションの定義はどうかかわっているのだろうか、リフォームというのは、住まう人の思いや感情に左右されることなく、必然的な修繕や修理・修復と言われるメンテナンス性、住設機器又は電化製品等の交換等の機能回復と定義できる。新築時に存在している機能なので、これらが機能不全に陥ると、修理をしたり交換することが求められる。クロスが剥がれたり汚れて張り替えたりする模様替えも含まれるだろう。
一方でリノベーションの定義となるものは、住まう人の思いに関わること、例えば二部屋を一部屋に改装するとか、逆に一部屋を二部屋に仕切るとか、これらの要素は新築時の「仕様」から、異なる仕様へ改修するものであるが、そこには人の思いが存在する。
思春期を迎えたから子供部屋を儲けたり、逆に子供たちが独り立ちして出ていったので「仕切り」を無くすとか、人の思いが関わっている。また、耐震性や断熱性能を向上させたいという性能向上も、新築時よりも向上させることによって、大掛かりな工事になってしまうのだが、やはり人の思いが関わっている。何らかの店舗だったが居住専用にしたりするコンバージョンも「人の思い」が関わっているのである。っとすれば、人の思いが関わっているかいないかで判別することができる。
「機能回復」「メンテナンス」はリフォーム、「仕様改善」「性能向上」はリノベーション。また、コンバージョンなどの転換工事もリノベーションと定義づけることができるであろう。しかしながら、流行語やインターネットなどの検索用語、新しい言語などは恐いもので、現状ではこれらの定義とは関係無く全て「リノベーション」と言われるようになっている。検索用語としても「クロス張替え」のリノベーションなど、定義は関係無く、テレビ放映された用語ではリノベーションが短縮されて「リノベ」となっている。まぁ定義付けなど消費者には関係の無いことで、リフォームもリノベも「生活文化」の向上を図るものであり再構築と記した方が良いのだろうか。(ちなみに建築用語には「改装」は存在しない。あくまでも造語である)
家づくりにおいて学ぶ機会はそうそう無いだろう。そういう学校?と評した集客モデルがあるようだが、あくまでも民間企業の戦略である。投資授業が高等教育に義務化されているのだから、住宅においても義務教育過程にあっても問題無いと思います。日本は資源国では無いし、伝統ある文化を敬っています。その中で人々が暮らして来た街の中には必ず「家」である住宅が存在した。その集合体が集落を作り、今の社会が作られ、今の時代も人々は暮らしの生活どころに「家」という存在があり、切っても切り離すことが出来ないものである。ところがこの「住宅」を学ぶ機会が無い、コンテンツは色々あるだろうが、〇〇時代の暮らし方だけでなく、住宅の存在感や「家」として「人」との関わり方など、最低限の暮らしの営みである原点の「家」を学ぶべきと思われる。
今日では家を購入することや建てることもデジタル化しているようだが、衣食住の文化に関わることは、むしろ国民の授業の義務として行った方が良いと思います。インターネット含め住宅展示場の販売方法は、単に情報を整理するだけのマッチングであって、業者選定や予算、性能等など、暮らし方や文化などは教えてくれない。そもそもそういう事は論外であるからだ。話す人の思い入れもない。恐らく理解はできるだろうが、納得できるレベルではないと思われる。
今の時代では住宅の「性能」がキーワードになっているようだ。性能と言ってもたくさんあるし、ピンと来ないかも知れないが、長期優良住宅(新築共に改修もあり)に掲げられている住宅性能表示というものである。しかも断然的に温熱環境の性能軸がキーワードとなっている。
昨今のエネルギー需要を含めヒートショック等の健康問題面も明らかになって、住宅会社はこぞって、この温熱環境の性能にしのぎを削っているようです。もちろん国策としてCO2の脱炭素削減問題なども合わせて、補助金や助成金に莫大な予算を掛けている。では、一方で消費する生活者が購入決定とする優先順位は何かというと、確かに性能面は当たり前のように要望はあるものの、最終決定となる優先順位は「意匠性」が圧倒的に高い。
これには色々と理由があるのだが、暑い寒いという温熱環境は、理論や理屈となる根拠はあるものの、古い家での暮らしや今までの環境に馴染んでいるので、それよりも大幅に向上するだけで満足しているのである。つまり「今よりは良くなるよね」的な感じである。
意匠性というのは、理屈や理論の根拠ではなく、「カッコ悪い」「ダサい」という「感性」の問題である。
「暮らし」というのは四六時中を部屋の中で過ごすことになり、目に付くところである。「性能」というのは、どちらかという前に大半が目に見えないところであり、実際のその時にならなければ、その効果も発揮できない。耐震であれば「地震」が来た時であろうか、それでも極端な大地震が局所的に発生しない限りは倒壊するどころか、避難さえ無い。むしろ集中豪雨による川の氾濫などの方が、時期的に多発する傾向がある。今では、各自治体ごとにハザードマップが作成され、これらも一目瞭然で回避できることが可能となっている。では暑い寒いではどうだろうか。今よりも良いということは、電気代も下げるだろうし、設備機器も新しい機器ほど節電効果も高いというイメージがある。(イメージだけでなく実際にそうなのである)寒ければコタツに入って鍋を囲む風物詩がある。暑ければエアコンで凌ぐこともできるし、オシャレで機能性の高い夏服や小型で持ち歩きできる扇風機とかも販売されている。酷暑の時は校庭集会や部活動も制限されているし、大型施設に入り込めば寒いくらいのエアコンで冷やされている。浴衣を着て盆踊りや花火大会へ出掛けたり、風鈴などの感性に委ねる「涼」の取り方はあるものの、アイスキャンディーなどやスイカなど、夏ならではの風物詩もたくさんあるのである。(冬場も同様のアイテムは多く存在する)
だからこそと言及するわけではないが、住宅に限っては人を招いたり、四六時中過ごす自分の室内はオシャレとは言わないまでも、カッコ悪いくてダサいのはダメなのであり、頭では性能面を理解していても優先順位としては低い位置づけになってしまうのである。最初は予算を組んでいたとしても、ある程度妥協(削っても)しても意匠性の方を優先するのである。我々建築側からすれば、軒ナシ屋根や天窓などは防水面や日射遮蔽とか、雨水の処理なども問題を抱えるが、購入する側からすれば、我々がプロである以上、なんとかしてくれるものであり、何かあればクレーム等含め保証内で対応できることを知っている。
どんなに優れた知識を持ち合わせていても、売れない住宅を作っている企業は廃業に追い込まれる。どんなに売名行為でのし上がって来ても、売れなかったら市場から淘汰されてしまう。だからこそ「デザイン」は大事である。とびっきりの性能を求める生活者は稀であろうが、とびっきりカッコイイデザインは、人を魅了し購買意欲を掻き立てるのである。これからの住宅は一世代で建て替えることは無いだろう。その家で生まれた子息達にとっては、かけがえのない「実家」になるであろうし、一生の想い出を刻む「暮らし」なのである。寒かった事も、暑かった事も思い出になるだろうし、地震や台風がきた時も覚えているだろう。家づくりにおいて重要なことは、この想い出となる我が家の在り方であり、暮らし方であり、歳の取り方である。それぞれの家庭や家族構成でライフスタイルは異なるであろうし、事件や事故に全く巻き込まれないという保証はない。これからの経済事情等を鑑みても多くの予算でリフォームやリノベーション工事ができることが少なくなることも考えられる時代が来る。そうなると、有料顧客の囲い込みやメンテナンス性など多機能工事ができる人材の育成とかが戦略になって来ることが予測されます。
家づくりにおいてこそ、生活者である消費者と向き合うことが、どれだけ重要だということか、また向き合っていかなければならない事だと、学ぶ必要がある。そして、建てる供給側には人間性が高い倫理観と誠実さが求められるのだろう。
この度、地方自治体の古参の団体(官民一体)、リフォーム委員会の委員長に再任することになりました。思えば悪徳リフォーム詐欺事件の発端で、急遽委員会を立ち上げた経緯があるのですが、14年間勤めていました。わけあって前職の卒業と同時に後進へバトンタッチしたのですが、様々な機関より再度の就任要請の声が上がり、五年間の空白を経て、この度再任することにしました。
就任するにあたり、いくら創設者であるとはいえ「目的」という方針を再度掲げたのですが、やはり原点回帰というわけではありませんが「県民」という大儀を掲げました。
企業で言えば顧客にあたるものですが、何事にも手弁当である自治体の活動には、競合企業や仕事上に付き合いのある関連事業者と活動を行うのですが、やはり制限があるのは事実です。好き勝手に活動できるものでもなく、会員企業の会費や税金などの予算で行ういじょう、中途半端な業務、自社や個人を優位にするものではなく、もちろん営利目的であってはならないのです。本業とは異なる運営の仕方ではあるものの、やはり目的を明確に掲げることは基本中の基本となるものです。
寒くなってきましたね。
なんの変哲もない、アルミ鍋に水道水で昆布出しも他の具もなく豆腐が一丁ぐつぐつと煮立っている「湯豆腐」。ポン酢とぬる燗で、うまぁ〜い!日本人に生まれてきて幸せだと思う瞬間でもある。
