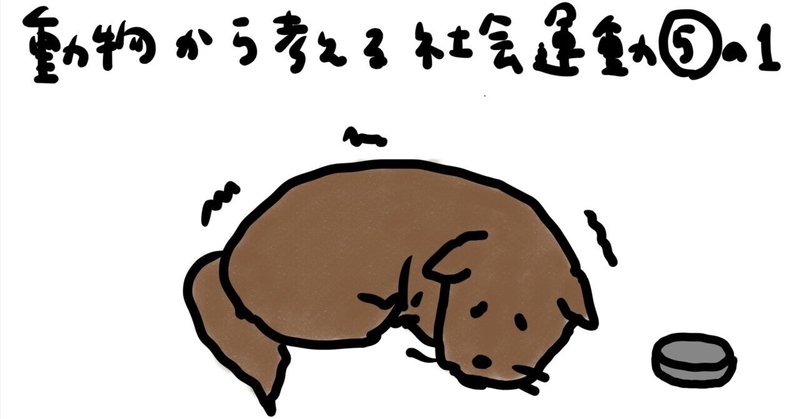
動物から考える社会運動⑤の1 自分たちの加害性・特権性を考える
わたしたちはなぜハラスメント運動/野宿者支援をしながら動物の運動をするのか?——動物問題連続座談会の一回目第5弾。野宿者支援・労働運動など複数の問題に携わってこられた活動家の生田武志さん・栗田隆子さんをゲストにお呼びし、交差的な運動についての議論を深めていきます。
【参加者】
深沢レナ(大学のハラスメントを看過しない会代表、詩人、ヴィーガン)
生田武志(野宿者ネットワーク代表、文芸評論家、フレキシタリアン)
栗田隆子(フェミニスト、文筆家、「働く女性の全国センター」元代表、ノン・ヴィーガン)
司会:関優花(大学のハラスメントを看過しない会副代表、Be With Ayano Anzai代表、美術家、ノン・ヴィーガン)
※ 動画は後半と同じものです。記事化にあたり、動画⑤の内容を分割し、加筆・修正しています。
罪悪感ベースの運動は可能か?
——(司会:関) わたしは自分が支援活動しているなかで、自分が加害をしてしまう可能性というのが、深刻な問題としてあります。わたしは被害当事者じゃないという立場や特権があって、ちゃんと家があって、お母さんがいて、毎日ご飯食べられているという状況にある。大学にも行ってたし、アートもやっている。そういう自分の立場について考えると、申し訳なさがベースの運動——運動が申し訳なさを解消するためにやっている感じになっていくんです。それって自分の中ではプラスマイナスゼロになってるんですが、気分的にはあまりいいものではなくて、このまま何年も続けていけるのだろうか、と考えたりします。
フェミニズムやハラスメントについては詳しくなっていく一方、この間アーティストレジデンスで台湾に滞在することがあったんですが、行ってみたら台湾のアート界の雰囲気として、フェミニズムなんて当然のことで話題にもならず、トランス女性も普通にトイレに入っていたし、みんな「日本のコロニアルの時代は・・・」などと戦後の歴史認識についての態度をそれぞれが持っていて、それについて普通に会話している。そんな環境で、日本人として日本の台湾統治についての見解を暗に求められているような気がしたんですが、それにちゃんと応答できないということがありました。日本でフェミニズムとハラスメント問題でいっぱいいっぱいだったわたしが台湾に行ったら、昔の日本が何をしたかといったような教科書の知識もおぼつかなくて、どんどん罪悪感みたいなものを抱えていって。台湾でも複数人のヴィーガンのアーティストと出会いました。それでアートの現場においても動物のことも考えなきゃ、というのもあって。本を読めばいいんだけど、どこから手をつけていいかわからないし、実際生きていくためにバイトしなきゃいけないし・・・といったような中で、何も知らない私が「アートってやる意味あんのかな」みたいにも思えてきています。
わたしは20代後半で、レナさんとも運動に対するスタンスが違うと思うんですけど、こういう世代がいろんな問題に対してどういって対処していけばいいかなど教えてください。
深沢 関さんの気持ち、わたしもすごくわかります。わたしは今30代だけど、子どもの頃は社会のことに無関心だったんです。わたしの場合、身近なところに社会問題をやっている人がいたんだけど、その人が世間的には“良いこと”をやっていると評価されているけど、「女の仕事と男の仕事を同じと思うな」とか平気で言うし、女子どもに愚痴ばっかり言っているという姿を見ていたから、社会運動に対して冷めていた。
でも、自分がなんで無関心だったかを考えると、さっきの関さんと同じで、自分が生き延びるだけで精一杯だったんだよね。遊びまくってたわけではなく、そのときはそのときで必死に生きていた。今もわたしは無知なこといっぱいあって、日本のコロニアルの歴史も全然勉強不足で、東南アジアに旅行したときも「勉強しなきゃいけないな」と思いながらも、でも日本に帰ってくると裁判があって、ヴィーガンに対するちょっとした嫌がらせがあって・・・って、本当に、うちら、必死だよね(苦笑)。事件なく過ごせる月がほとんどない。そういうなかで、「もっともっと勉強しよう!」と頑張る方向にはどうしてもなれない。
それと、知識を持っているかどうかを個人単位で判断するような傾向になっちゃっているところも問題なんじゃないかと思います。何らかの問題について、当事者ではない人たちから、すごいきつい物言いで「もっと勉強してください」と叱られることがあるんだけど、じゃあわたし1人が本読んで勉強すれば解決して終わりなのかというと、そういう部分もあるかもしれないけど、でも、わたしだけじゃなく同世代——大学の友達も高校の友達も、日本のコロニアルのことはたぶんほとんど知らないと思う。それはもはや構造の問題だから、とにかくまずは学べる場を作る必要がある。「そんなも知らないの?」と、相手の罪悪感というか、羞恥心を煽るような形で叩いていても、それを知っている人と知らない人の溝が深まるだけだから、「(その人は)なぜ知らないんだろう?」という背景まで踏み込んで解消していかないといけないと思う。たとえば、わたしも動物問題について話してると、あまりにも知らない人が多すぎて、周囲との認識の差に絶句することも多々あるんですけど、わたしだって他の問題については無知なことはあるから、そういう互いの無知を叩き合うのではなく、詳しい人がそれぞれの問題を教え合うような場を作れたらいいなと思ってます。
栗田 基本的に面白くないと学べないというところがあると思うんだよね。「学ばなきゃ」と罪悪感で学ぶのは辛いよね。わたしは罪悪感はあんまりよくないんじゃないかと思ってるんですよ。なんでかというと、罪悪感って、ともすると自分全否定みたいになっちゃいがちで、行動を直したり、具体的に何かを変えるエネルギーに実はつながりにくいんじゃないかな。もちろん自分が特権を抱いているということの自覚はいるけど、罪悪感から学んでいる人を見ていても、そこでエネルギー使い果たしちゃって、何かをしようという気になれないんじゃないかな、って思うんだよね。
わたしがアメリカとかいったときには、勉強はみんなでしてるよね。あんまり1人で孤独にやらない方がいいんだろうな。ワークショップとかで集まって、ある程度意見を交換しながら学ぶというのが基本。日本の学校って、そういうことしないじゃん。少なくともわたしはそんな一緒に学び合うような良い学校には行ってなくて、学校でみんなで安心してトークできる中で学んだ経験はない。わたしは不登校をして、女性センターの講座や修道院といった、学校以外のところで基礎をようやく学べた気がする。
しかも私のこの話は1980年代だから、今では女性センターとかは潰されたり、或いは全然違う講座——婚活講座とかやっちゃったりしてる施設もあるから、時代の問題もあると思うんだ。逃げ場がない感じというのは、わたしが子どもの頃よりも、時代的にも強まっている可能性はある。台湾で日本がかつて何をやってきたかとか、フィリピンで何やってきたか、というのは、わたしは環境の中で学んだような気がする。人の話を聞いたり。わたしが10代の頃は、戦争の経験者が生きてたしね。だから80年代にはあったそういう環境が、2020年代の今は消えているという問題もあるよね。
じゃあ学ぶ場を作らないといけないね、と結論はたぶん同じようなところに落ち着くと思う。ただ、罪悪感ということに対しては、それで学ぶことができる人もいるかもしれないけど、そういう人はすごくまじめな人だと思う。全員それができるわけじゃない。罪悪感で勉強を詰めていける人はそんなに多くはないような気がするからこそ、いろんなやりとりで学ぶ場が必要なんじゃないかな。
生田 僕は学生の頃に釜ヶ崎に通っていたんですが、ある意味、罪悪感はあったと思うんです。つまり、自分は親から金をもらって生活しているけど、野宿の人って自分で稼いだのにお金がなくなって野宿しているわけじゃない? 僕らが夜回りして、声かけて、一緒に役所行って、生活保護や病院に入ったら、野宿の人が感謝してくれて、「助かりました、ありがとうございます」って言うんですが、どう考えても僕は感謝される立場じゃない。でも感謝されるわけで、「自分、こんなことでいいんだろうか」とずっと思っていました。
なので、大学出たら日雇いをはじめて同じ立場になろうとしたんだけど、でも結局、日雇いをやっても同じ立場になれるかというと、なれないんですよ。野宿者の多くは集団就職世代で、中学を出ていろんな仕事をして、日雇いになって、最終的に野宿になった人が多いんです。そういう人と、大学を出て自分から望んで日雇いをやる僕らが同じ立場であるはずはない。近づこうと思えば近づけるところもあるけど、最終的には同じ立場になれない。だから、距離をもちながら、どうやってそれでも一緒にやっていったり支援できるかということが問われると思うんです。それに、罪悪感についても、今となっては違う面から考えるようになりました。たとえば「日雇いと野宿」の問題って、2000年あたりからフリーターや不安定な労働に就く多くの人たちに広まっていったわけで、全然特殊な問題じゃなくて自分たちの問題になっていった、と考えています。
それと、今から思えば、日雇いの人って発達障害の人が多かったんです。ずっと車の中で独り言言っている人とか、ほとんど人と話せない人とか、人間関係でかなりで偏った感じの人とか。今、中高生で発達障害の子が多いし、そういう意味では、関われば関わるほど、問題が多様化していって、しかもいろいろな問題で関連していることが見えてくる。自分ができることはそのうちの一部なんだけど、それでもやっていくしかないんだな、という感じで、自分の当初の罪悪感というのは見方が変わってきた感じがします。
常に揺らぐものとして捉える——フェミニズムとトランス差別
——みなさんは加害性・特権性についてどう考えていますか?
栗田 加害性・特権性という話でいうと、さっき話した教会の中のセクハラ・性暴力・性虐待については、わたしは被害を受けてなかったから、完全に傍観者という性暴力を加担する側になっていた立場だった。それは一つ大きな事実なのだけど、もう一つは、今社会に浮上してきているトランス女性に対する一部のフェミニストの対応というのはすごく生々しい話です。
【トランスジェンダーへの差別問題】
2010年代前半からLGBT関連の情報の流通が加速していくなかで、2010年代終盤以降、フェミニズム系のアカウントを中心にSNSでトランスジェンダーに敵対的な言説が増加。2020年代には、トランスの権利擁護への反対という一点で、フェミニストやリベラルが、道徳的、宗教的保守派との「共闘」に組み込まれていく流れが出てきている。
女性の問題は社会問題として認知はされてきているんだけど、じゃあ問題が解決されているかというと、性暴力がなくなるとか賃金格差がぐっと狭まるということはあんまりないから、女性たちが「自分たちはずっと相変わらず辛いのに・・・」となりがちなのかもしれない。でもトランス女性はシス女性とは全然立場の違う苦労を強いられる部分があります。
そもそも社会はシスを前提に成立しているから、仮に男として育っていてもトランス女性であることを隠していたり表に出せなかったり等々で、それこそいじめっ子の男がそのことになんとなく勘付いていじめてきたりということもある。だからこそ「シス」という立場だけで有利な現実もある。でも、そのことを認められない人と認められる人がいて、わたしの周りでも人間関係がものすごく割れたんですよ。トランス女性に対する差別のひどい人は極右とくっついて、セクシャルマイノリティを弾劾する立場にいっちゃってたりもするから、すごく困難な状況になっている。
そういう問題が出てきたときに、「こんなに大変なのに」という自分の被害だけを頑強に打ち出していくのはいいとは思えない事態になっている。たとえば、トランスを差別する女性たちから、「トランス女性を擁護する人たちは所詮インテリのエリートで、そういう難しい理論もおわかりなんでしょうけど、わたしたち市井しせいの女性たちはそんなインテリの女性たちのいう理論にはついていけないし、シス女性の問題は全然解決していないし、そんなトランスなんて・・・」というような意見が最近強くなってきているんですね。
わたしの『ぼそぼそ声のフェミニズム』を読んでいた人のなかには、そういう人が案外いたみたい。それでわたしが、トランス女性の話がやたらトイレとお風呂場とスポーツの話だけにされてしまっていることに対して、「さすがにそれはおかしいんじゃないか」と言ったら、「栗田隆子なんて最低だ。お前の声なんか聞きたくない。ぼそぼそ声がデカすぎる」みたいなことを言われたりする。
自分が被害を実際受けたときに、自分のことを「被害者」だと受け止めるのって、ものすごくパワーがいるんですよ。それなのにトランス差別の話のときに急に「わたしたち被害者は」「市井の女性は」とバーっと言い出すというのはなんか違うという気がしていて。またこういうことを言うと女性たちに批判されるんだけど、「被害者」という言葉が、パワーを振るう道具みたいになっちゃう使い方は、被害という言葉を歪めちゃったり、被害者という言葉の持つパワーさえ削っちゃったりする意味でもよくない。あと単純にトイレで覗きなんかを一番多くやっているのは普通のいわゆるシスの男性やん、という問題すらかき消しちゃう。
*こういった記事もある
しかも「市井の女性なんだからわたしはそんな難しい理論わからないわよ」と言われたとき、たしかにわたしは学歴があるから、それは特権だといわれても仕方がない。だけど、特権があるからって、あきらかに違うと思うことに対して何も言わないでその相手の言うことを聞いてていいのかというと違う。じゃあ、ネット右翼が言う言葉にも、「お前は特権があって、俺たちの言うことなんか今まで聞いてこなかったじゃないか」と言われたときにその意見を黙ってきかなきゃいけないのかというと、やっぱりそれは違う気がする。
野宿の人の支援というのは、最初にわたしが特権と被害の関係を考えさせられた大きなきっかけで、経済的な力でみれば、当時は野宿の人よりはわたしのほうが力があった。だけど男/女という関係になったら、それが逆転する。そういうことを常に揺らぐものとして捉えないと何かがずれてくるんだと思う。
とはいえ、すごく難しいんだよね。「絶対的加害者・絶対的被害者はいない」という言い方もするけど、ある事件においては絶対的に被害者になっちゃうこともあるわけじゃないですか。「この事件においては自分はどう考えても被害者だ」という場合もある。だから、さっきレナさんが言った環状島じゃないけど、自分の立ち位置がどの事件におけるどの立ち位置なのかと意識することは必要なんだろうな、と改めて思います。「いついかなるときも被害者」ではなく、「この事件のこのとき、この場においては、どう考えても自分は被害者だし、でもこの時のこの場においては違う」と、具体的に考えていかないとポジションを間違えていくのかなあ、と思うこの頃です。
→⑤の2「学ぶ場所がない!」へ
(構成:深沢レナ)
大学のハラスメントを看過しない会は、寄付を原資として運営しています。いただいたサポートは裁判費用、記事・動画作成に充てさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
