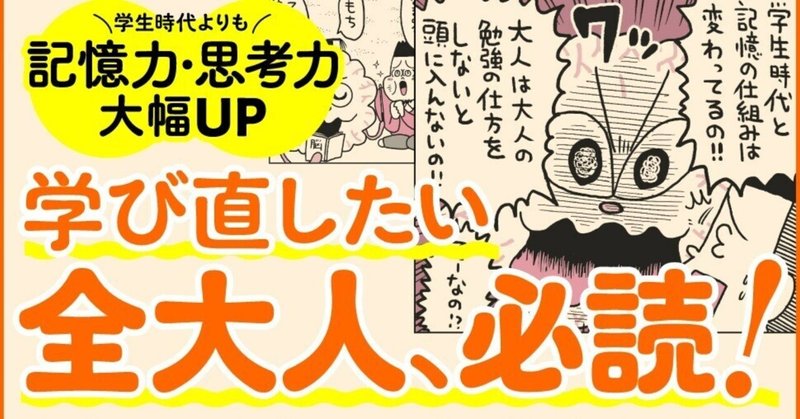
本の紹介9冊目:「一生、頭がよくなり続けるすごい脳の使い方」加藤俊徳(え、いつまで学生時代と同じ勉強法やってんの?)
私、桐島は過去に各種の資格に挑戦してきました。
以下の記事で、過去に取得した記事に触れました。
過去にそれなりの数の資格を取得した私も、徐々に年をとるにつれて、脳力に自信がなくなってきました。
そんなタイミングで、「大人の脳は学生時代より『いい状態』になっています」、「脳は年を経るにつれて、仕組みが変わっています!」
という書籍に出会いました。

脳力復活に興味のある私が、最近、購入した書籍は以下です。
●「認知心理学者が教える最適の学習法 ビジュアルガイドブック」
●「私は合格する勉強だけをする」
●「試験勉強のすごいコツ」
●「夢をかなえる勉強法」
●「夢をかなえる時間術」

これらと比較しても、図解・説明のわかりやすさが、群を抜いています。
目次
序章 大人には大人のすごい勉強法がある
1章 大人脳のすごい取り扱い説明書
2章 大人脳にあったすごい記憶力アップ法
3章 大人脳をやる気にさせるすごい学び方
4章 脳番地の特徴を活かしたすごい勉強法
5章 大人の脳力を強化するすごい習慣術
それでは、以下にこの書籍のポイント(要点)をまとめます。
大前提
●記憶力の低下も物覚えの悪さも、加齢による脳の老化が原因ではなく、得意な脳のルートばかりを使ってきたせいで、脳の使い方の偏重が出て、「脳のおじさん化」現象が起き、脳全体の機能が下がっているため。
●30代以降になると、学生時代の勉強法を続けていても、費やした時間に比例する効果は得られないため、大人になった今の自分の脳に合う勉強法に切り替えていく必要がある。
●以下の図のとおり、脳は怠け者で飽き性で洗脳されやすい。

脳番地の特徴の違い
●以下の図のとおり、脳には8つの脳番地がある。
●これらをうまく連携させて使うと、脳がよくなる。

脳番地の役割
●私たちは、優れた脳番地たちで形成された株式会社ブレインの監査役。
●脳の社長は、意思決定のかなめの思考系脳番地。
●社長のよき理解者でありパートナーである常務が理解系脳番地。
●あまり表舞台に出てこないが、記憶系脳番地は総務部長的役割。
●この3人が、株式会社ブレインのトップ。
●脳に入ってきた情報をもとに、3者が意見交換し、最終的な決断は社長の思考系が下しています。

●トップ3以外には、社長が下した決断をパワーポイントでまとめて資料を作成したり、社外に伝えようとするときが、広報の伝達系脳番地の出番。
●トップ3に冷静さを促したり、イケイケに感情を高ぶらせるように仕向けたりする陰で株式会社ブレインを操っているのが感情系脳番地。
●社内で情報を集めたいときには、現場での情報収集をメインとする運動系・視覚系・聴覚系の営業部門に声がかかります。
●基本的には、これらのプレイヤー全員が怠け者なので、風通しの良い働きやすい環境にしないと、生産性が下がります。
脳を良くするのは?
●すべてのプレイヤーに働いてもらう工夫(仕掛け)をする。
●記憶する際は、声に出すこと、書いてまとめることなど意識的に伝達系を使ってアウトプットの量を増やせば増やすほど、インプットの質も上げる。
●頭がボーっとするときには、まず運動をする。
●自分が、視覚系なのか聴覚系なのか(目からと耳からのどちらからの情報が理解しやすいのか)把握して、得意な能力を使うようにする。
●「腕時計」をさかさまから、言ってみて下さい。この際に、頭の中に文字を映像として思い浮かべた人は視覚系、音を頼りにさかさまに読んだ人は聴覚系の強い人と推測できる。
大人になると丸暗記できなくなるのはなぜか?
●聞いたものをそのまま吸収できる学校での勉強に適した「学生脳」は18歳頃から徐々に衰え始め、それ以降、10年ほどかけて対応力や創造力など、より高度な機能を備えた「大人脳」へ脳のシステムが切り替わるため。
●子供時代に勉強ができたのは、「耳から聞いた情報を素直に記憶する力が強かった」ということ。
●子供のときは、最初に聞いて覚え(聴覚系→記憶系)、覚えてから理解する(記憶系→理解系)という順番で脳を働かせている(例:母語の習得)が、大人になると思考系や理解系が発達しているため、記憶する前に疑問が湧いてきて、意味を理解して記憶する「意味記憶」が優勢になる。
●何かを覚えるときは、「覚えよう」と思いより「理解しよう」と頭を働かせるのが正解。
(=付箋を貼ったり蛍光ペンを引く作業では、記憶に残すことはできない)
大人になってからの記憶の方法
●喜怒哀楽を伴ったエピソード記憶は、無条件で長期記憶へ送られる(例:休日に家族と出かけた観光地のレストラン)。
●ワクワクとした前向きな感情で勉強に向かうと、シータ波が出て海馬が活発に働くようになるため、普通に勉強するよりも25~50%の時間と体力で欲しい知識が記憶に入る(例:大好きなカフェラテを飲みながらハッピーな気持ちで勉強に取り組む、試験に合格した自分へのご褒美を決めておき、そのご褒美を思い出しながらテキストを開く)。
●その日のうちに、覚えたことを復習する。復習専用の復習ノートを作成して、翌日に自分が講師になったつもりで声に出してスピーチをするのがおすすめ。
●復習をするときは、1番記憶に残りにくいテキストの真ん中からスタートする。
●海馬は、過去に見聞きしたものに反応するため、勉強で学ぶ分野に関するキーワードとあらかじめ顔馴染みになり、覚えたい知識と自分の親密度をどんどん上げる(例:学習のスタートで関連漫画やYoutubeの動画を見る、勉強前に5分間参考書をパラパラと見る)。
●聴覚は、朝一番に活動を始め、1日の最後の寝る直前まで活動を続けるため、日中、どうしても時間が取れずに仕事で疲れ切ってしまった際には、オーディオブック等の耳から学べるツールを寝る前に使うと効果的。
●毎日ウォーキングをするなど、運動系脳番地を積極的に動かすことで、脳番地のエネルギーがアップする。
●就寝前に復習したら、その後スマホやテレビなどを見てはいけない。脳は、より最新の情報を上書きする仕組みがあるため、就寝前の記憶に定着しやすいタイミングで、他の情報を入れると重要な知識として認識する。
●脳は注意力散漫なため、デッドライン(期限)を設けたほうが集中力が高まり働きやすい。脳にとって集中力が高まる時間は、20~50分。
●記憶を司る海馬は、時間と関連づけることで、迷いなく働いてくれることが脳科学で明らかになっている。
●朝、学んだ内容を移動時間や隙間時間にこまめに復習し、1日を通して脳との連続性を維持し続ける。そして、寝る前に仕上げの復習をすれば、記憶としてしっかり定着させられる♪
●勉強中に集中力が切れることは、ものすごい量の情報を処理して、脳が大量の酸素を消費して、酸素不足に陥っていて「疲れた」「飽きてきた」というサインを出し始める。ここで作業をやめずに同じ脳番地をずっと使い続けることを繰り返していると、自律神経のバランスが乱れて、不眠、めまい、肩こりなどの不調を招く。
●ずっと座って勉強したり、パスコン作業をしているなら、立ち上がって軽くストレッチをする、さらに良いのは、静かな場所で目を閉じて何もしないこと。
●休憩中にスマホを見たり本を読むのは、勉強やパソコン作業で使う脳番地とほぼ同じなので、リフレッシュにならない。
久々の学習
●長年使っていなかった内容は、記憶系脳番地は、その学んだ内容が記憶の保存庫のどこにあるのか探すことから始めるため、脳が適切な情報処理をし始めるのに75時間かかる(例:留学していたアメリカに戻った際に、脳が英語脳に戻るまでに、1日10時間×1週間ほどかかる)。
●これは、新しい勉強を受け入れて、好意的に脳が動き出すために必要な時間を同じ。
Comment and Key Takeaway for me(コメントと私が実践したいこと)
脳に様々な役割があることは知っていましたが、この本が明瞭に示してくれました。普段、PCワークをしたり、読書をして一定時間経過すると、集中力が切れることの意味を理解していませんでしたが、脳の一部の番地の使い過ぎによる酸素不足だとわかり、休憩することの重要性をはじめて認識しました。
朝起きたタイミングと寝る前でのタイミングの勉強の重要性は全く意識していなかったため、しっかりとタイミングを意識した勉強を実践したいと思いました。
これから、資格試験に挑戦するときも、勉強をするときも、本書で学んだ内容を実践していくことが楽しみになりました♪
最後に、20代のおすすめの脳の使い方は、「30代の脳に向けて、浅く、広くでもいいので、幅広い分野の知識を身につけることが大事。本の多読がおすすめ。幅広い物事の知識を身につけ、疑問や興味を持ち始めると、未熟な理解系脳番地も働きやすくなる」と記載されています。
私の読書術・速読術講座も20代の方向けに提供してきましたので、有用なことがこの書籍で証明されて、安心しました(*‘ω‘ *)
なお、30代のおすすめの脳の使い方は、「20代で学んだ知識の中から、興味があることをとことん掘り下げて専門性を深めてみよう。脳の個性を確立させる助けになる。20代から専門性の高い仕事に従事している人の場合、30代半ばから新しいことをやりたがらない『脳のおじさん化』が始まる人もいる。そういったケースでは、おじさん化を防ぐためにも、仕事でも趣味でも、新しい分野へ挑戦して脳を活性化させることが大事。」と記載されています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
