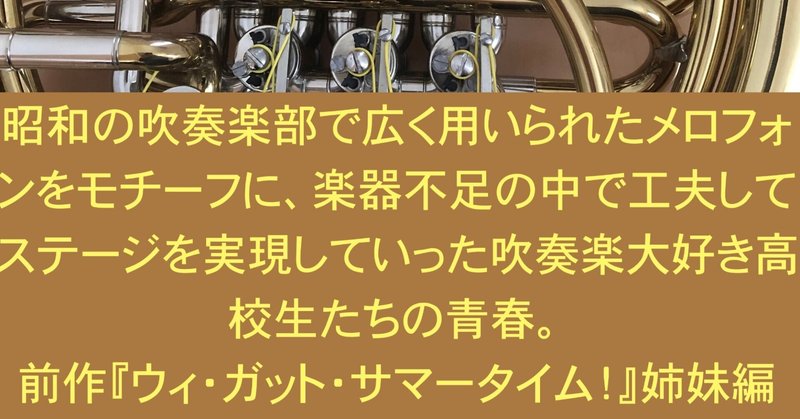
土居豊の新作小説、刊行!『メロフォンとフレンチ』第1章まで試し読み!

土居豊の新作小説、刊行開始!
『メロフォンとフレンチ』(Kindle版)
https://www.amazon.co.jp/dp/B09QJWC25X/ref=cm_sw_r_tw_dp_4MESSV8RD00RQ8H4SXF5
昭和の吹奏楽部で広く用いられたメロフォンをモチーフに、楽器不足の中で工夫してステージを実現していく吹奏楽大好き高校生たち。17歳の友情と恋の青春を描く。
音楽小説『ウィ・ガット・サマータイム!』の姉妹編。
※あらすじとキャラクター、作品背景について→ 音楽小説『メロフォンとフレンチ』土居豊
https://note.com/doiyutaka/n/n64f59ad3b2f3
※解説動画
新作の小説『メロフォンとフレンチ』は吹奏楽部の青春群像を描く音楽小説です。現在よく売れている、大規模校が吹奏楽コンクールを目指すお話ではなく、地元密着で生徒だけの活動による演奏会づくり、地元の3つの高校が協力して合同演奏会を実現するお話です。
内容と作品背景について、作者の土居豊自ら語っています
配信動画
↓
https://youtu.be/OfCYRXiSqt8
前作の音楽小説『ウィ・ガット・サマータイム!』解説動画もご覧ください
↓
https://youtu.be/ySKZY_Geh_0
以下、第1章まで無料で読めます!
『メロフォンとフレンチ』
土居豊 作
第1章「メロフォンとフレンチ・ホルン」
(1)
1)女子高生吹奏楽部員の悩める日常
谷山みすずの悩みのタネは、ホルンのマウスピースが唇に食い込んでできる丸く赤い痕だった。吹奏楽部でフレンチ・ホルンを始めて、もう1年以上経つのに、ずっと直らない。悪い癖だ。それというのも、こういう醜い痕が唇にくっきりと残るのは、ホルンの吹口(マウスピースと呼ぶ)である真鍮製の金属を強く押し付けすぎるからなのだ。
だが、マウスピースを強く唇に押し付けないとホルンがうまく鳴らない。そのこと自体、根本的に演奏法を間違えているからなのだと、今となってはみすずにもわかっている。けれど、高校生で初めて吹奏楽部に入り、ホルンを始めたみすずにとって、そもそも楽器を鳴らせるようになるまでが一苦労だったのだから、仕方がないことだった。
最初にホルンの吹き方を教わったのは1学年上の熊本先輩からで、みすずはただ先輩の言う通りにやっただけだった。間違った方法で教わってしまって、実はそれが間違いだったとわかっても、一度身についた吹き方はなかなか直らない。
ただでさえ女子の唇は大切だというのに、毎日毎日、金属の丸い吹口を2時間近くも押し付けて楽器を吹き鳴らしている。するとデリケートな唇の皮膚が荒れてしまって治らない。丸い金属の型が唇にすっかり残ってしまって、腫れているように感じられた。だが1年生だったその頃はまだ、自分が教わったホルンの音の出し方がまさか間違っているとは思わなかった。そのうちに唇も元に戻るだろう、とたかをくくっていた。
やがて夏休みになり、それでも唇の痕は治らなかった。夏休みの終わりの方になって、三校合同の演奏会練習で他校の吹奏楽部員たちと一緒に練習するようになって、初めて自分のやり方が違っていることを知った。時すでに遅し、みすずのホルンの吹き方は、数ヶ月の練習で、すっかり間違った方法に慣れてしまったのだった。
みすずは関西府立晴日山高校の吹奏楽部のホルン担当で、2年生だ。ホルン・パートの同学年には男子が1人いた。後輩の1年生は3人いたのだが、1人は引っ越してしまい、もう1人はなかなか部活に出てこないようになっていて、このところ、3人で教室で練習することが多い。
吹奏楽部の練習というのは、平日はたいてい楽器パートごとに分かれて普通教室を借りて、そこでまとまって基礎練習や曲の合わせをやる。だが夏休み中は吹奏楽コンクールのための合奏が多く、近隣の3つの高校が集まってやる合同演奏会の練習で他校へ移動していることもよくあった。
みすずはホルンのパートリーダーなので、その度に練習場所を確保したり、臨時の合奏の予定に合わせてパートの合わせを仕切ったり、何かと忙しい毎日だ。その上、練習に出てこない後輩の分の楽譜に、指揮者が合奏であれこれいう注意を書き込んでおいたり、隣で演奏している1年生女子がなかなか上達しないのを気に病んだり、苦労が絶えない。
「ほんとはねぇ、こんなことばっかりやってるの、嫌なんだ」
みすずは、ついつい愚痴ってしまうのだが、2年生のホルン担当の葛西慎二は、そういう愚痴をスルーしてほとんど反応しない。その方がみすずには気分的に楽ではあるが、時々もの足りないこともあった。
「こんなことって?」
この日は、めずらしく話に乗ってきた葛西に、みすずは、逆にどう返そうかちょっと迷った。
「自分の練習、ちっともできないよ。パート練習の段取りとか、あの子の説得とか。そんなのばっかり」
「ああ、そういうこと。おれ、もっと手伝えばいいんだろ?」
葛西は、ホルンを机の上に載せて、ちょっと一息ついてから答えた。
「そうだなあ、パート練習は、なんならおれ、仕切ってもいいよ」
「あー、それより、あの子に電話してくれる方が助かるかな」
みすずはこのタイミングを逃さず、葛西にやっかいごとを一つでもまかせてしまいたかった。
「いや、それはちょっと、な。1年女子の家に、おれがしょっちゅう電話するのは、さすがにまずい」
葛西は、真ん丸な目をさらに大きく見開いて、いささか慌てた表情でみすずをながめながらぼそぼそと言った。
「そうお? あの子、そんなの気にしないって」
「おれが気にするんだよ」
でっぷりと肉付きがよく、いつも陽気な表情を丸顔に浮かべている葛西は、日頃のイメージと似合わないことを言ってから、自分で照れたらしくそっぽ向いてごまかした。みすずは、そう言われるとどう答えたものか、つっかえてしまった。
「まあ、男子、だもんね」
「そりゃ、男子だよ」
間の抜けたやりとりをしながらお互い顔をじろじろと見合い、みすずと葛西はほとんど同時にニヤッとした。
『この子いつもこんな感じだから、まだ救われてる、かな。少なくとも気は使わなくてすむし』
みすずは気をとり直して、自分もホルンを机に載せた。基礎練習を終えて一休みしたら、今日の合奏の曲を指揮者に確認して、パート練習を仕切らなければならない。
『やっぱり葛西くんのお言葉に甘えて、今日は練習の仕切り、まかせようかなあ』
ひとりごちつつ、みすずは手鏡で自分の唇を映してみた。マウスピースの丸い痕が腫れぼったくついているのを、冷水機の水で冷やしにいこうと、パイプ椅子から勢いよく立ち上がった。
魔が差した、としか言いようがない。
立ち上がったはずみで、楽器に手が引っかかった。
あ、と思った時には遅かった。
彼女のフレンチ・ホルンは机から落下して、派手な金属音を立てた。
結局、被害はまともに床にぶつかったキーの部分が一番大きく、4つあるキーのうち2つも壊れてしまった。こうなるともう、部品を交換しないと演奏できない。
夏休みの終わりぎわだからまだよかったが、これがコンクールの前だったらどうしようもないところだ。
みすずは、壊れたフレンチ・ホルンを学校帰りに楽器店に持ち込んで、修理に出そうと考えた。修理が終わるまで、練習できないのは仕方がない。
『楽器庫にあるメロフォン、久しぶりに出してみるか。フレンチの修理終わるまで、あれで基礎練習だけでもやっとこう』
と、みすずは思いついた。
2)メロフォンとフレンチ・ホルン、どっちがどっち?
谷山みすずは、中学生の時は軟式テニス部だったので、高校に入ってから吹奏楽を始めた初心者だ。FMラジオでジャズを聴くのが好きなので、本当はトランペットをやりたかったのだが、希望者が多くて、楽器選びの抽選で外れてしまった。希望調査の第2希望にホルンを書いたのは、トランペットのほかに名前を知っている楽器があまりなかったからだ。
だから1年生の頃、初めはホルンの音がなかなか出なかったのも、辛くはあったがまあこんなものだろうとあきらめていた。
もう一人のホルンの同学年、葛西は中学の吹奏楽でもホルンをやっていた経験者で、入部してすぐに楽器を吹き始めた。楽器も葛西の個人持ちだったから、ずいぶん恵まれているなあ、とみすずはうらやましかった。なにしろフレンチ・ホルンという楽器は、金管楽器の中でも値段がやたら高いのだ。トランペットやトロンボーンと比べても倍以上の価格だ。それもそのはず、フレンチ・ホルンは構造として長さ4メートル近くある金属の管を、複雑にぐるぐる巻いてある。トランペットやトロンボーンよりもずっと長さが長いから、材料だけでも値段が高くなるのは当然といえば当然だ。
それで、みすずは入部した当初自分のフレンチ・ホルンがないので、初心者向きのメロフォンという楽器をあてがわれた。
メロフォンといのは、形はホルンのようにまんまるく巻いてあり、大きなアサガオ(ベルと呼ぶ)があって、ホルンに似て見えるのだが、実は全く異なる楽器だ。そんなことも、みすずは最初知らなかった。そもそも見た目が、フレンチ・ホルンは左手で持ってキーを押すのに対し、メロフォンは右手で持ってピストンを押すようにできている。
楽器の持ち方も、フレンチ・ホルンの場合はもう一方の手をベルの中に深く差し入れているのに、メロフォンはベルの平たい端を手のひらに載せるように持っている。
唇を当てるマウスピースも、両者は形がかなり違う。それもそのはず、もともとが全く違う楽器なのだ。楽器の調性は同じF管だが、鳴らせる音域が全く違う。フレンチ・ホルンは4オクターブにわたって音が出る。
そんなこととは知らないまま、みすずは2年生の熊本先輩に教えられるまま、メロフォンを吹いて基礎練習の音階などを吹いていた。同学年の葛西が、先輩と一緒にぴかぴかのフレンチ・ホルンを吹いているのを横目に見つつ、自分だけ古ぼけたメロフォンで音階の練習をしていると、かなり気分がへこむのだった。
メロフォンという楽器は、外見はホルンに似ていても成り立ちが全く違う。英国のブラスバンドの楽器、サクソルン系中音域のアルト・ホルンの代用としてマーチングなどで使われるが、楽器の系統としてはサクソルン系ではない。アルト・ホルンと音域がほぼ同じで調性はF管なのだが、メロフォンは差し替え管を使ってE♭管にもできる。
そういう便利さ、手軽さが、日本で広く普及した理由なのだろう。子どもでも演奏しやすいことから太平洋戦争後、教育用楽器として学校でよく使われた。中学校、高校などの吹奏楽部で、フレンチ・ホルンが値段的になかなか買えない学校では、代用としてメロフォンを使う場合も多かった。
みすずが1年生の時の春、4月の放課後だった。楽器のパートごとに分かれた練習が始まった頃のこと、ホルン・パートではアンブシュアとバズィングという練習を最初にやらされた。アンブシュアというのは金管楽器を吹く時の唇の形のことで、バズィングとは唇をブルブル震わせて鳴らす練習法だ。唇の形をアンブシュアにして思い切りお腹から息を吹き出すと、ちょうど蜂が飛ぶ羽音のような音が出る。見た感じは子どもの遊びのようで、みすずも初心者だが簡単にできると思っていた。ところがそうはいかない。
「気にすることないわ、すぐできるよ」
熊本先輩は、口調は優しくそう言いながらも、『もっと気にしろ』というような顔つきをした。
このホルンの2年生の先輩は、外見は華奢でお嬢さんっぽい雰囲気を漂わせて、服装もその印象を裏切らないおしゃれな服をいつも着ているが、性格的にも、お嬢さんの印象を裏切らず非常に厳しい先輩だった。ちなみに、晴日山高校は制服がなく、生徒はみな私服だ。
熊本先輩としては、吹奏楽コンクール金賞を目標に毎日がんばって練習しており、悪気はないのだが、1年生2人をとことん鍛えることを義務だと思い込んでいた。
ホルンの音を鳴らすための準備運動として、バズィングという練習法ができるようにひたすらやらされたが、みすずはなかなかうまくいかない。そもそも管楽器の練習というのは、ほとんど運動部並みに体力を必要とする。管楽器をきちんと鳴らすには、普段の呼吸とは違って、横隔膜を強く動かす腹式呼吸というのが不可欠だ。その練習をするとしばらくは、お腹がぐうぐう音を立てるので、特に女子にとっては非常に辛い。
そのあとがバズィングなのだが、みすずは相変わらずうまく鳴らせない。音は立てているが、熊本先輩や葛西がやるような、蜂の羽音みたいな鋭い音は出ない。
そのうちに、メロフォンのマウスピース(吹口)を唇に当てて鳴らす練習も始まった。これは、バズィングをやりながら金属製のマウスピースを唇にそのまま当てる、という曲芸のようなやり方で、金属が当たったとたんに、思わず息を止めてしまうため、かえってうまくいかなかった。普通にマウスピースを唇に当てて息を強く吹き込んで鳴らそうとしたほうが、スムーズに音が出た。
「まあ、いいけど。音さえ出れば」
と、熊本先輩は、自分がやらせた練習法がうまくいかなかったことが残念そうだ。それでも結果よければよし、と微笑んでくれた。笑みを浮かべた熊本先輩は、慈悲深いお嬢さまそのものに見える。
4月末には、みすずはマウスピースをメロフォンに付けて音を鳴らす練習をし始めた。ようやく腹式呼吸で力一杯楽器に息を吹き込むコツがつかめてきて、ある程度は音が鳴るようになってきた。
「そろそろ、フレンチに切り替えようか」
熊本先輩が言い出したのは、5月の連休の後だった。
それまでは、みすずだけメロフォンで、先輩と葛西はどんどんフレンチ・ホルンで曲の練習をやっていたので、置いてきぼりをくっている情けない気分が付いて回った。ようやく自分もフレンチを吹けることになって嬉しかったのだが、実際にはそう簡単にはいかなかった。
「メロフォンの時と同じよ。マウスピース付けて。左手は指をしっかり掛け金に引っ掛けて。そうそう。で、右手はベルの中に、こう、こんな感じで」
熊本先輩がやるのを真似して、学校の備品楽器のフレンチ・ホルンを持ってみる。熊本先輩のホルンや葛西のと見かけがちょっと違う。備品のホルンはシングルというF管だけの楽器だからだが、それでもみすずはフレンチを持つだけで心が浮き立つのだった。
だが、フレンチを初めて吹いてみると、ほとんど鳴らなかった。
「あれ?」
みすずは、試しにマウスピースをフレンチの細長いマウスパイプから抜いて、マウスピースだけで鳴らした。これはちゃんと鳴る。メロフォンの場合と同じだ。もっとも、フレンチのマウスピースはかなり細長く薄べったいので、当てている唇がすぐに痛くなる。
もう一度、楽器を鳴らそうとしてみるが、やはりちゃんと鳴らない。息を吹き込む時の抵抗感が、メロフォンとは全然違うのだ。
それもそのはず、メロフォンよりも数倍、金属の管の長さが長いし、息を吹き入れるマウスパイプも非常に細い。
けれど、それだけでもなさそうだった。メロフォンでは音階を吹けるのに、フレンチは音階どころか、ロングトーンで4拍の間、音を吹き続けることもままならない。
『なんでこんなに難しいの?』
みすずは、途方にくれる思いで、フレンチ・ホルンを太ももの上に載せて、つくづくと眺めるばかりだった。
だが、熊本先輩の仕切るパート練習は、情け容赦ない。
「もっと腹筋使って!」
と先輩は不機嫌そうにはっぱをかける。
「ホルンって、難しいことで有名でさ、世界一難しい楽器でギネスブックに載ったらしいよ」
などと、同学年の葛西は、何の慰めにもならないことを教えてくれるばかりだ。
フレンチ・ホルンを鳴らせるようになるまでがこんなに大変だなんて、みすずは想像していなかった。
『やっぱりトランペットがよかったのに』
3)中古のフレンチ・ホルンを買いましょう
みすずの高校の吹奏楽部も、学校備品のフレンチ・ホルンは古いF管シングル・ホルン1本しかないため、代用にメロフォンを使うこともあった。けれど、高校レベルの吹奏楽部では、メロフォンの音域では足りないような曲も演奏する。だから、本番でメロフォンを使うのは無理があるのだった。
みすずも、1年生ながら本番のステージに出るためには、自分のフレンチ・ホルンを調達する必要があった。だがフレンチ・ホルンは、みすずの家の経済状態ではとても新品は買ってもらえない。国内メーカー大手のシングル・ホルンで、一番安いものでも10数万円する。しかもそれは楽器の調性がF管、あるいはB♭管1種類だけのシンプルなタイプだ。
「フレンチ・ホルンはF管とB♭管のどちらも必要なのよ」
と2年生の熊本先輩が言った。
みすずは、その時はよく理解できなかった。どうやら、F管の楽器とB♭管の楽器で出せる音が違うらしい。
だが、FとB♭を切り替えられるダブル・ホルンという種類になると、値段が倍近くに跳ね上がる。これはみすずには到底、買えっこない。
もちろん、みすずだけでなく、ホルンを新品で買える部員は少数派だ。そこで、晴日山高校の代々のホルン担当部員はどうしているかというと、OB・OGの先輩から中古を買ったり、楽器屋で中古販売されているものを探したりする。
そんなわけで、みすずは、高校の吹奏楽部のOGから中古のダブル・ホルンを7万円で買った。これはみすずが小学生の頃からせっせと貯金していた銀行預金を全部下ろして、さらに両親に高校の合格祝いにもらった1万円を足して、ようやく出せる金額だった。
それまで名前も顔も知らなかった吹奏楽部OGの先輩は、5月の中頃の日曜日、母校に自家用車でやって来た。今はもう大学も卒業して証券会社に勤めているというOGは、1年生の後輩に自分の使い古しのホルンを渡し、お小使い貯金の結晶である7万円を受け取ると、楽器の扱い方や手入れの仕方を細々とレクチャーしてくれた。
「楽器の掃除は、1ヶ月に一回はするようにね。キーは、なるべくネジを外したりしないで、調子悪くなったら楽器屋さんにみてもらって」
熊本先輩も、OGの前ではひたすらかしこまっていて、いつものいばった口調ではなく、やたら丁寧な口のききかたをするのが、みすずにはおかしかった。
そうやって、手に入れたヤマハのダブル・ホルンだが、みすずはまだ十分に鳴らすことができない。メロフォンでは音階をスムーズに上がり下がりできるようになり、簡単な曲を吹いていた段階だったが、フレンチ・ホルンに切り替えたら、思うように鳴らせなくなった。
メロフォンのマウスピースとフレンチのそれとは、一見して違うほどではないが、明らかにふちの分厚さや内側の深さが違っていた。メロフォンのものは分厚くて、唇に当てていてもあまり負担はない。ところがフレンチのマウスピースは、ふちがとてもとがった感じで、鳴ることは鳴るのだが、吹いていると唇に金属の端が食い込んで、すぐに唇の神経が痺れたように麻痺してくる。手鏡で見ると、唇の外側にくっきりとマウスピースの円形の痕が残り、まるで金属の輪で圧迫する拷問でも受けたみたいな感じになっている。
「押し付けすぎなのよ、あなた」
2年生の熊本先輩は、きつい口調でそう言って、みすずの口元をじろじろにらんだ。
「そんなに押し付けたら、唇腫れちゃうでしょ。バズィングの時、そんなに指を押し付けなかったでしょ?」
そう言って、先輩は自分の唇に右手の人差し指と中指を軽く開いて当てがった。ちょうどVサインを狭くしたぐらいの幅の2本の指先に、唇がちょうど外側だけ隠れるような感じで、その残りの真ん中の部分は口を尖らせたときのように指の間から突き出している。その唇の真ん中を微妙に振動させてブブー、と音を出すのが、バズィングという練習方法なのだ。
もちろん、みすずはバズィングはできるようになっていたので、同じように先輩の後から唇を震わせてブー、と鳴らした。
「ちょっと、やっぱり指押さえすぎなんじゃない? 指なしでバズィングやってみて?」
先輩は、みすずの口元を見とがめるようににらみ、うながした。
「こうですか?」
みすずは、今度は指を唇から離して、そのまま息を強く吹き出して唇をブー、と振動させた。
「あなた、アゴが引けてないんじゃない?」
先輩は、ハッとしたようにみすずの顔に顔を近寄せてきた。
思わず顔を引きそうになったが、みすずは我慢して、そのままバズィングを続けた。
『唾が先輩の顔にかかったらどうしよう? 怒るかな? 怒るよねきっと』
などと、気が気でなかったが、みすずはバズィングを続けた。
「ちょっと、触ってみて?」
先輩は、みすずにバズィングをやめさせると、自分のやり方を指で触って確かめさせた。先輩の唇のすぐ下のあたりをおそるおそる触れてみたものの、みすずは感触がどう違うのか、よくわからなかった。
アゴが引けていない、と指摘されたみすずは、それから毎日、鏡に顔を映して、アゴを下に引っ張るように力を込める練習をした。
そうやって、アゴを下に引き、唇を左右に引き結んで唇を緊張させ、思い切り息を吹くと、確かにバズィングは楽にできるようになった。そのままの要領で、フレンチ・ホルンのマウスピースを唇に当て、なるべく押し付けないようにして鳴らすとホルンのマウスピースは振動し、それらしい音が鳴るようになった。あとは、マウスピースだけで鳴らすのと同じように、ホルンのマウスパイプに差し込んだマウスピースに息を吹きこむだけだ。初めて自分のフレンチ・ホルンがきちんと音程を鳴らせた時は、みすずは思わず涙をこぼしそうになった。
4)ホルンのテクニックという本を読んでみた
ところが、この成功が、後になってとても高くつく罠になってしまおうとは、もちろん初心者のみすずにはわかるはずもなかった。
つまり、2年生の熊本先輩がレクチャーしてくれたホルンの吹き方が、そもそも間違っていたのだ。
晴日山高校の吹奏楽部には、大人の指導者はいない。音楽の先生は合唱が専門なので、部活は主に合唱部を指導している。他に吹奏楽や管楽器の専門の先生などはおらず、時々来校するOB・OGが、それぞれ担当楽器を指導してくれるのがせいぜいのところだった。
ホルンの場合も、現在は大学の吹奏楽部で演奏している先輩が主に指導してくれていた。けれど来校回数は限られていたし、初心者のみすずが最初にメロフォンで音の出し方を教わったのは、2年生の熊本先輩だった。
残念ながら、先輩自身も教えるのがそんなに上手とはいえなかった。彼女は、細かいことは教則本を見て覚えるようにと、メロフォン・アルトホルン教則本という本をみすずに渡して、基礎練習のメニューを指示した。熊本先輩自身も、コンクール曲の練習ともう一人の1年生の葛西への指導で大忙しだった。
その教則本には、このように書いてあった。
※引用
『メロホーン・アルトホルン教則本』(改訂) 広岡淑生 著 音楽之友社 刊
《吹口の当て方 吹口を口に当てる位置は主として唇や歯列によりますから、吹く人によって違って来ます。しかしだいたいの当て方としては唇を真一文字に結んで微笑したかたちにして、その中央部に吹口を当て、ぶどうを食べてその種をプッと吹き出すようにして、らっぱの管の空気を振動させて発音させるのです。強い息を吹込んで発音するのではありません。その時頬をふくらまさないで、むしろ微笑しているような口の形で吹奏するのです。》
《美しい音を出すのも高い音を出すのも唇の工夫と練習で、息を多く使うのではありません。》
《音が高くなるにしたがって唇の中央を中心にして引きしめなさい。息を強く吹き込んで高い音を出すのではありません》
みすずは、メロフォンの教則本を読み、あとは書いてあるメニューにそって、毎日基礎練習をした。そうやって、だんだんとメロフォンなら曲を吹けるぐらいまで上達していた。
それからフレンチ・ホルンに切り替えたわけだが、今度はもう教則本はなく、いきなり熊本先輩と葛西と一緒に基礎練習をして、曲の楽譜を見ながらちょっとずつ吹けるようになってきた。
ところが曲の練習の時、五線譜の上の方の音を出すのがとても難しいことがわかって、みすずは混乱した。メロフォンで別の曲をやったときには十分鳴らせた音だったのに、フレンチ・ホルンではその音がどうしてもうまく吹けない。
熊本先輩に言うと、
「慣れたらできるようになるよ。練習あるのみ!」
と決まり文句のように言われるばかりだった。
けれど、みすずは行き詰まってしまっていた。
メロフォンでうまく鳴った音が、フレンチで鳴らせないのは、楽器が悪いのか、自分の吹き方が悪いのか?
そこで、ホルンの吹き方のコツを書いたものはないかと部室を探してみた。
『ホルンのテクニック』というタイトルの、埃をかぶった参考書みたいな本を書棚から掘り出すと、みすずは音の出し方のあたりを読んでみた。
※引用
『ホルンのテクニック』 ガンサー・シュラー 著 西岡信雄 訳 音楽之友社 刊
《まず唇をごく普通に閉じた(けっしてきつくむすんだようにではなく)状態にしなさい。つぎに、マウス・ピースを取り、だいたい上唇のふたつの山がリムにあたるように、リムの上半分をあてる。こうすると、リムの最上部の曲線が白い皮膚にあたりマウス・ピースが、だいたい口のまん中にくるはずである。つぎに、下唇を動かしたりさげたり(すなわち、上唇にあわせて)しないで、両唇を均等に緊張させて、軽くすぼめた形にしよう。これで、リムの下がわの曲線が、ちょうど下唇の赤い部分にあたるはずである。こうしてできた適度に緊張した唇をとおして、ある一定の速度で楽器に空気を吹きこむと、はじめてある音程が生まれる。
この順序に従ってゆけば、両唇が正しい形を保ったと同時に、マウス・ピースのリムの圧力が上下の歯の上に、ちょうど歯ぐきのきわまでかかるような状態に唇と接着するはずである。
奏者の中には、マウス・ピースのリムが両唇の赤い部分より外側にくるようなあてかたをする人もいる。人によっては、こういった状態でも吹けないことはないのだろうが、わたくしとしては、これには賛成できない。
(中略)
とにかくわたくしのいうマウス・ピースの位置によれば、ホルンの完全な4オクターブの音域をかんたんに、しかも切れめなしに跳躍することができる。》
《口の両端は(どんなに緊張していても、どんなにゆるんでいても)つねにおなじ位置に静止していなければならない。いいかえれば、唇の両端はどんな場合にもつりあがったり、さがったりしてはならない。
(中略)
音が高くなるにつれて、唇の両端が(笑った時のように)横にひろがらないように、とくに、注意しなさい。》
「全然違う!」
みすずは、『ホルンのテクニック』を読みながら思わず茫然としてしまった。その本に書かれているホルンの音の出し方は、2年生の先輩に教わったやり方とは全く違った。さらに困ったことに、メロフォンの教則本に書かれている方法とも、かなり違っていたのだ。
「どっちがほんとなの?」
みすずは、途方に暮れてしまった。
それでも、練習はどんどん先に進んでいってしまう。何しろ、7月に吹奏楽コンクールがあり、みすずの高校の吹奏楽部は出場するのだが、ホルン・パートはもともと人数が少ないため、全員出ないと足りない。だから、初心者のみすずも、なんとか7月にはコンクールに出られるぐらいにホルンを吹けるようになっていなければならないのだ。
けれど、教則本を見ても高い音は出せないため、みすずはだんだんと練習に行くのが嫌になっていった。風邪をひいたとか、お腹が痛いとか理由をでっち上げて、数日、練習を休んでしまった。
けれど、あまり長く休んでいると、ただでさえ居心地の悪いホルン・パートの部屋に、ますます行きにくくなってしまう。中学校の頃、一度、クラスの中で孤立してしまい、数ヶ月学校に行けなくなった経験のあるみすずには、これは二度と陥りたくない状況だった。
「葛西くんなら、わかってくれるかも」
と期待して、一度、電話でそれとなく、音の出し方の悩みを相談しかけた。しかし、葛西はどうやらホルンの音の出し方に困った経験がないらしい。電話でみすずの悩みごとを聞いてはくれたが、解決策はわからなさそうだった。
「まあ、大丈夫だよ。その音のところ、おれが二人分鳴らすようにする」
と、根本的な解決にはならないが、助けてくれるようなことを言ってくれたので、みすずは、とりあえず葛西を頼って、2年生の熊本先輩にはこれ以上心配かけないようにしようと思い直した。
だが、そういう気づかい、というか遠慮がかえって良くなかったのだ。
結局、みすずは1年生の間ずっと、五線譜の上の方の高い音が苦手なままだった。高い音は唇をマウスピースに強く押し付けるようにして、無理に鳴らす悪い癖をつけてしまうはめになったのだ。
2年生になって、今のような忙しい部活生活を続けるうち、自分の苦手の部分はごまかす、というもっと悪い癖までついてきた。
それでもみすずは吹奏楽部での毎日が、楽しいことは楽しかった。音楽をやるのはもともと好きだったし、上手に吹けないままでも合奏でみんなと曲を吹いていると、心がのびのびと開放されていくのが嬉しかった。
けれど、そのままでいいというわけでもなかった。後輩の指導はしなければいけないし、自分たちが上級生の今年は吹奏楽コンクールの演奏も責任重大だった。吹奏楽部の秋からの行事や演奏会も、成功させるにはホルンのパートリーダーとしてそれなりの重圧がかかってくるのだ。
もっとも、12月にある近隣の高校との合同演奏会だけは、他校のホルンの生徒たちと練習するのがものめずらしくて、みすずにとっては息抜きになるのだ。昨年、1年生の時も、この三校合同演奏会の練習だけは、気持ちが楽で気分良くホルンを楽しむことができたのだった。
(2)
1)三校合同の演奏会はけっこう大変だ
戦前まで関西府の北摂地域、片桐市にあった旧制中学校と旧制女学校が、戦後合併して2つの新制高校になった。それが、府立片桐高校と府立晴日山高校だ。どちらも重厚な近代建築風の古い校舎があり、のちに建て増しされた昭和的な真四角の校舎が混在している。どちらも敷地が公立高校としては広く、古い樹木が高くそびえている。だが似ているのはそこまでで、校風は正反対だった。
その2校の生徒は、何かにつけて周囲から比較され、優劣を競わされているのだが、実際のところ勉強面でも、評判面でも片桐高校がリードしているのは昔からのことだった。両校の生徒は、街で見かけても明らかに外見が違う。それというのも、片桐高校の制服がいかにも旧制中学の面影を残す黒の学ランと正統派のセーラー服であるのに対して、晴日山高校は制服がなく、生徒は普段着で登校しているからだ。
学生気質も、片桐がいかにも優等生っぽい雰囲気なのに対して、晴日山は遊び人っぽい生徒が多く、自由気ままな雰囲気を漂わせている。
この2校と関西府千里市にある府立丘上高校が、偏差値では校区ベスト3の座を守っていた。学区内の府立高校は戦後にできた高校が多く、個性を競うというより、いかに進学実績を伸ばすか、クラブ活動の大会で有名になるか普段から競っている。そういう中にあって、丘上高校は千里市の新興住宅地の中にあり、1970年関西万博で切り開かれた、新しい土地の住民の期待を背負った高校というイメージだった。旧制中学時代ののどかな空気感を持った2校と比べて、いかにも堅実で真面目な雰囲気を醸し出していた。そのイメージは、戦後の新制高校的な新しい感じの女子制服、ブレザーとブラウスとひだスカートにあるのかもしれなかった。
そんなわけで、この3つの学校の生徒は一緒にいても見間違えようがない。学ランとセーラー服、きっちりしたブレザー姿、だらしなくも自由奔放な普段着、という三者三様の服装で、この3校の生徒が喫茶店に集まっている様子は、この学区のトップ3の高校生集団、というよりも、ランダムに組み合わされた10代という感じだった。
そのバラバラに見える取り合わせの6人が集まる広い丸テーブル席に、一人だけ年かさの青年が座り、引率者というよりはオブザーバーといった感じで話に耳を傾けている。
この集団は、片桐高校と晴日山高校、それに丘上高校のそれぞれの吹奏楽部の代表者たちで、青年は、その演奏会を指揮することになった大学生、伊勢尚之だ。
伊勢は片桐高校の出身で、今は府の教育大学特設音楽科で打楽器を専攻している。自分も高校生の時、この三校の合同演奏会に吹奏楽部員として参加したOBだ。毎年、片桐市の大ホールで行われるこの演奏会は、持ち回りで3校それぞれのOB・OGから指揮者が出て、全体演奏をまとめることになっていた。今年は、片桐高校出身の伊勢が指揮者を引き受けて、この日、初めて3校の代表生徒たちと顔合わせをした。
喫茶店の丸テーブルを囲んだ高校生たちは、全部で6人いた。
片桐高校吹奏楽部の部長の2年生、増田康司は、見るからに頭が切れる、できる人のイメージで、実際にも市の第一中学でずっと優等生だった。高校受験の模試の上位常連でもあったのは、高校内でよく知られている。楽器はユーフォニウムの担当だ。
同じく指揮者の2年生、田口正二郎は、部長の増田とは対照的に、見るからにエキセントリックでマニアックな人物だ。隣の高山市から通学していて、中学の吹奏楽部でも指揮者をやっていた。子どもの頃からクラシック音楽が大好きで、将来は世界的な指揮者になるのが夢だ。楽器はクラリネットをやっている。
丘上高校吹奏楽部の部長の2年生、斉田京一は、容姿端麗だが天然キャラで、生真面目な生徒だ。千里市内の高層住宅が立ち並ぶニュータウンに住んでいて、隣近所と同じように典型的なサラリーマン家庭の子だ。体つきは華奢だが文武両道を器用にこなし、スポーツも万能だ。トロンボーンを担当している。
同じく2年生の指揮者、藤崎裕は、部長の斉田と対照的に立派な体格だ。関西市の東区から通っている。子どもの頃から上昇志向が強く、中学校でも激しい競争に打ち勝って来た筋金入りだ。めぐまれた体格のおかげで、ケンカはめっぽう強いがめったに自分から手は出さない。楽器は、その巨体に似合ったチューバ担当だ。
3校目、晴日山高校吹奏楽部の部長の2年生、櫻井敦士は、豪放そうな外見だが神経が細かく、よく気がつく性格だ。藤崎と同じく、中学生の時から吹奏楽部でチューバを吹いている。
同じく指揮者の2年生、立花かおるは、この6人中唯一の女子だ。女の子の指揮者というのは、吹奏楽部では珍しい存在だ。背が高くすらりと痩せた体格、天然ボケの多いユニークなしゃべりっぷりで、愛すべき人柄だとみられていた。
喫茶店の大きな丸テーブルを囲んだこの6人は、議論が大いに盛り上がっていた。
「メインの曲はどうする? メインだけでも今日決めてしまわないと、楽譜の手配もあるし。おしゃべりは仕事してからにしようよ」
仕切り役を買って出た晴日山高校の部長・櫻井は、話を進めようと躍起になっていた。
「去年のマーラーがあんまりむずかしかったから、今年はもっとわかりやすいのがいい」
と、丘上高校の部長・斉田が生真面目な性格そのままによく考えて答えた。
「わかりやすいって言っても、ある程度のボリュームがないと、大編成でやるのに似合わないよ」
と、すぐに激しく反論したのは、片桐高校の指揮者・田口だ。
「チャイコフスキーの『1812年』は、どう? 前からやってみたかったんだ」
と、いきなり個人的な好みを主張したのは、マイペースな晴日山高校の指揮者・立花だ。
「うーん。あの曲、前半がけっこう退屈じゃない? チャイコフスキーなら『スラブ行進曲』の方がいいよ」
と、片桐高校の部長・増田が、こちらも完全に個人的な好みだけで反論する。
「クラシックのアレンジ曲じゃなく、吹奏楽のオリジナル曲は?」
と、真っ向からみんなと異なる方向の意見を言うのは、丘上高校の指揮者・藤崎だ。
「あれだけの大編成でやるオリジナル曲って、なかなかないな」
と、片桐の田口が反論する。
「ホルストの『第1組曲』とか、どうだろう?」
と、丘上の斉田が提案する。
「それなら、エルガーの『威風堂々』はどうだ?」
と、仕切りの晴日山の櫻井もようやく議論に口をはさんだ。
「あれはクラシック曲だよ」
と、すぐに素っ気なく否定するのは丘上の藤崎だ。
「え? そうなの? 今まで知らなかった!」
と、素っ頓狂な声を出してみんなの注目を集めてしまうのは、天然キャラそのままの晴日山の立花だ。
こんな調子で、3校の運営委員たちの意見が全然まとまらないので、司会を買って出ている晴日山の部長・櫻井は、だんだんイライラしてきた。
「でもまあ、今回から2年生だけの合同にするのなら、思い切って難しい曲に挑戦しようぜ」
と、あえて難題を投げ込むのは、丘上の指揮者・藤崎だ。まとまりかけていた空気が、一瞬でまた混沌とした。6人は、それぞれに考え込んでしまった。
「難しい曲って、例えば?」
と、櫻井はしぶい表情で聞き返す。
「『春の祭典』とか、どう? ストラヴィンスキーだ」
と、自分たちの演奏技術を考慮しないで完全に無茶な提案を平気でするのは、片桐の指揮者・田口だ。
「ええ? それはちょっと、さすがに無理だろう?」
と、片桐の部長の増田は、あくまで冷静だ。
「無茶すぎると思うよ、さすがに『春祭』は」
と、丘上の部長・斉田も客観的に否定する。
「いいよ『春祭』、やってみても」
と、突然、口をはさんできたのは、合同演奏の指揮者であるOBの伊勢だった。みんな、仰天して思わず絶句してしまった。丸テーブルの周りに、しばらく沈黙が続いた。
さすがに、真剣にあのストラヴィンスキーの難曲を演奏することを考えると、威勢良い言葉を発言していた面々も、思わず黙って考え込んでしまったのだ。
「いや、冗談だよ。まず楽器編成が無理だから」
そう付け加えると、伊勢は端正な面長の顔に微苦笑を浮かべて一同を見回した。
「冗談ですか!」
「きついですよ」
「あーびっくり」
口々に声を出して、高校生の面々は思わず笑い声を立てた。
この演奏会を指揮することになった伊勢は、片桐高校OBで府の教育大学特設音楽科に在籍し、打楽器を専攻している。高校時代にも吹奏楽部の指揮者だったが、現在は大学で専門的に音楽を学びつつ、時々母校の吹奏楽部を指導に来ている。
3校の合同演奏会の運営委員会議は、こんな感じに話があちらこちら飛びながらも、合同演奏のメインをワーグナーのオペラ『ニュルンベルクのマイスタージンガー』前奏曲にすることに決まった。
合同演奏を2年生だけでやる、というのは、3校合わせたら部員数が多くなりすぎて、市民会館のステージに全員のるのは不可能、とわかっていたからだ。
元々がこの演奏会は、3つの高校の吹奏楽部がそれぞれ単独で定期演奏会を開くのがまだ難しかった時代に、合同で資金を出し合って演奏会をやったのが始まりだった。その頃にはまだ、部員数が3校合わせても、ちょうどステージをほどよく埋めるぐらいの人数だったのだ。その後、それぞれの高校で吹奏楽部の人数が増えて、とうとうステージに乗り切らないほどになった。
それでも、合同演奏会をやり続けているのは、自校だけでやるのと違って、3つの高校それぞれの個性をぶつけ合って演奏会を作り上げる楽しさを、一度味わうとやみつきになるからなのだ。
それに、3つの高校の吹奏楽部は状況が異なるとはいえ、部長と指揮者、という立場は同じであり、何かと文句の多い部員たちを引っ張ってまとめていく苦労を、みんな思い知ったメンツばかりだった。お互い、苦労話をぶつけ合って、日頃の鬱憤を晴らす場としても、この3校合同の演奏会会議は、貴重なものだった。
2)三校合同の演奏会は大変だが、楽しい
片桐市の大ホールで毎年、合同演奏会を一緒にやっている3つの高校は、府下の同じ学区内にあったが鉄道路線が違うため、運営委員の生徒たちが相談のために集まる場所は転々と毎回変わった。
関西府立片桐高校は私鉄の片桐市駅の近くにあった。そのため、近辺に喫茶店やファーストフード店があったので集まるのに便利な立地ではあった。しかし、千里市にある府立丘上高校の最寄りの路線から来ようとすると、関西市内のジャンクション駅まで出て乗り換える必要があった。一方、片桐市の国鉄駅のそばにある晴日山高校から来ようとすると、かなり歩かなければならないが、それでも時間的には千里市内から私鉄でくるよりは早く到着できる。結局のところ、3校のメンバーが片桐高校と晴日山高校の中間あたりの店に行くのが一番スムーズだった。
この3つの高校の生徒たちはいずれも府立に通っているだけあって、裕福な家庭の子どもというわけではない。今回の三校合同の演奏会運営委員も、毎度毎度、喫茶店に入って注文するだけの財布の中身は持っていない。だから、安いメニューのあるファーストフード店に集まることが多かった。そこで、片桐市の国鉄駅から私鉄駅に向かって少し歩いたところにあるハンバーガー屋が、よく会合に使われた。この店は2階の客席があり、そこに居座って長居しやすいという事情もあった。またこのハンバーガー店は国内のチェーン店で、そのせいなのか、アメリカ発祥のチェーン店よりはやや値段も安く、いつも金欠である高校生たちの会合場所にふさわしかった。
春先に初めて運営委員のメンバーが顔合わせした際、今年の合同演奏会は過去の演奏会の路線をそのまま続けるのではなく、自分たちの新機軸を出すという点を合意していた。新しい何かをやってみたいと思っているメンバーが多いので、運営委員たちは会合で会うたび親密感が増してきた。
6月のこの日、運営委員の会合は土曜日の午後、片桐市の国鉄駅の近くのハンバーガー店で、お昼ごはんを兼ねて開催となった。
晴日山高校の吹奏楽部の部長・櫻井は、土曜日の授業が終わるとすぐにリュックを背負って教室を出た。吹奏楽部の部室に寄らないでそのまま校門に向かう。指揮者の立花かおるは、合奏練習のために今日の会合には出ないのだが、副部長の木下幸が代わりに櫻井と一緒だった。会合が長引いた場合、副部長の木下が学校に戻って練習終わりの時の片付けを指示することになった。
ついでながら、この木下幸は櫻井が目下、付き合っている相手でもあった。部長と副部長という役職になったのは1年生の冬だったのだが、それ以来、何かと相談することが多かったこともあり、今年のバレンタインデーで木下が櫻井にチョコを渡したことをきっかけに、付き合うようになったのだ。
今日の会合では、合同演奏会に向けての夏休みからの練習日程とその内容をつめておくことになっている。だから、長居がしやすい例のハンバーガー店を場所に選んだ。櫻井はチューバを練習するのは嫌いではないが、元々の世話好きの性格もあって、部長の仕事で外で駆け回っている方が性に合っていると、この頃自覚するようになった。それもあって、三校合同で集まる運営委員の会合が毎回楽しみだった。それに、自分の高校の吹奏楽部員たちとのつきあいでは、部長という立場が災いしてなかなかハメを外しにくかった。その分、運営委員同士では、自分たちが日頃鬱憤をためている部員たちのあれこれを、遠慮なく吐き出すこともできるのだった。
同じ頃、千里市の丘上高校から片桐市まで、私鉄のジャンクション駅で乗り換えて向かおうとしているのは、丘上高校吹奏楽部の部長の斉田京一と、副部長の龍本知恵子だ。指揮者の藤崎裕は、午後から合奏を予定していて出られないので、代理で副部長の龍本が行くことになった。
斉田は目立つほどに眉目秀麗なので、そこそこ混み合った私鉄の車内で二人並んでつり革を持って立つと、隣にいる龍本は居心地が悪かった。日頃意識はしないが、校外で隣同士立っていると、この目立つ男子の引き立て役にされているようで、いい気分ではなかった。
けれど斉田の方はそんなことはお構いなしで、普段から自分の存在が周囲に与える印象など、まるで気にしていなかった。今もつり革を持って立ったまま窓の外をながめて、沿線のあれこれについて、うるさいぐらいに隣の龍本にしゃべりかけてくる。
『うるさいなあ』
内心、辟易しながら、龍本は生返事ばかりしていた。
「あ、見えてきた。片桐」
斉田は、窓の外に見える片桐高校の広々としたグラウンドを指差して言った。
「知ってるよ。いちいち指差さないで、恥ずかしい」
龍本は、思わず身を遠ざけながら斉田をにらんだ。
そんな調子で丘上高校の二人は、私鉄の片桐市駅で降りると国鉄駅近くのハンバーガー店まで急いだ。道すがら、同じく会合場所に向かう片桐高校吹奏楽部の二人、部長の増田康司ともう一人の女子部員、上野愛子に出くわして、声をかけ合った。片桐高校も、合奏のために指揮者の田口は学校に残ったのだった。
それぞれにお昼ごはんがわりのハンバーガーセットなどを注文して、一同は店の2階の広々とした壁際の席に陣取った。窓の外には、国鉄の線路が見えている。
晴日山の櫻井は、今日は練習に戻らないつもりであることをみなに言った。
「うちは定時制があるから、とにかく5時には練習終わって全員外に出なきゃいけないんだ」
櫻井が理由を説明すると、他校の面々は、目を丸くした。
「じゃあ、居残り練習もできないの?」
丘上の龍本は、首を傾げて尋ねた。
「できないよ」
櫻井が言いかけると、副部長の木下が補った。
「だからその分、昼練やるのと、あとは土日の練習で補うのよ」
「へえ。それは悪条件だね。うちの場合、居残りは前日に申請出せばできるからなあ」
片桐の部長・増田が気の毒そうに言った。
「前日申請でも顧問の先生、付き添ってくれるの? うちは練習延長は1週間前が締め切りだよ」
丘上の部長・斉田は尋ねた。
「いや、顧問いなくても大丈夫」
増田が言うと、丘上の龍本は驚いた。
「え、それいいなあ。うちの場合、顧問の付き添いなかったら普段でも活動できないよ」
それを聞いて、片桐の上野は逆に驚いたように答えた。
「そりゃまた、杓子定規だね。うちは顧問じゃなくても、別の先生に頼めたらそれでいいんだ。たいてい誰か遅くまで残ってる先生いるから、頼みに行く」
片桐の上野は、丘上の龍本と同じホルン担当の2年生で、昨年の合同演奏会以来の顔見知りだった。龍本は、羨ましそうに答えた。
「うちは、それはないなあ。やっぱ、伝統校の強みだね」
片桐の増田は、皮肉っぽく苦笑しながら答えた。
「伝統しかないからな」
「そんなことないだろ? みんな、ハイレベルの大学に行くじゃない」
晴日山の櫻井が口をはさむと、上野が答えた。
「でも、一浪が多いよ、先輩たちも」
木下がうなずいた。
「うちもそうね」
「2年の終わりまでで引退する吹奏楽と違って、運動部は3年の夏まで部活やるからね」
上野はよくしゃべる人だった。
「うちの場合、人数少なかった頃は、3年の先輩がコンクールまで残ったみたい。今はもう、人数たりてるからいいけど」
丘上の斉田が自分の学校の事情を語った。
「コンクールは、そうだな、人数制限あるからな。1、2年だけで足りなかったら、先輩にお願いするしかないな」
片桐の増田がうなづくと、櫻井は、増田に尋ねた。
「コンクール、どう? 今年はどっちに出る?」
「うちは、Aで出るよ」
増田が、当然のように答えると、丘上の斉田はちょっと残念そうな顔で言った。
「うちはまだBだな」
「出ろよ。金賞、狙おうぜ」
櫻井が言うと、斉田は生真面目に答えた。
「僕も、そう思ったんだけど、反対する部員がたくさんいたんだよ」
「なんでAに出るのに反対するの?」
木下が不思議そうな顔で尋ねると、龍本は悔しそうに答えた。
「たぶん、自信ないんじゃないかなあ」
「誰だって自信なんかないよ。だから練習するんだよね」
木下は、龍本を慰めるように言った。すると、櫻井も重ねて言った。
「それはそうだ。そのために、年中無休で練習してるんだよ」
すると、片桐の増田がため息まじりに言った。
「でもねえ、練習するのがいやなやつもいるから」
「ああ、いるいる」
「ああいうのは、やっかいだよね」
「あんまり強く言うと、もめごとになっちゃうから」
口々に、同感する声が上がった。
「練習さぼるやつ、お荷物だよな正直」
真面目な顔でズバッときついことを言ったのは、斉田にしては珍しかった。この面々の中にいると、根っから生真面目な斉田でも、つい安心して本音が出るのだ。
「うんうん。そうなんだよ。ちょっと言えないけどね」
と、丘上の龍本もうなずいている。
「今度、代わりにガツンとそいつに言ってやるよ。他校のおれが言うなら問題ないだろう?」
と、増田が本当にそうしかねない勢いで言うと、斉田はあわてて首を横に降った。
「いやいや、やめといてくれ。僕が後でひどい目に会う」
そう言う斉田が、本当に慌てていたので、みんなおかしがって笑った。
「そうか? まあ、いいけど」
「斉田くんもっと威張ったらいいのに。せっかくルックスいいんだから」
木下がそういって茶化すと、斉田はまともに受けとって答えた。
「いや、顔はこの際、関係ないと思うよ。僕は威厳がないから。そういえば櫻井君は威厳あるよね」
そう言われて、櫻井はあわてて言い返した。
「いや、体がでかいだけ」
すると、増田も同調した。
「いや、体格は重要だよ。おれなんか、威厳も何もあったもんじゃない」
「でも、増田くんはよく口が回るから羨ましいな」
斉田が言うと、増田は苦笑した。
「ここではね。部活では、あんまりしゃべらないんだ」
上野も横から口を挟んだ。
「部活の時の増田くん、いっつもすごく機嫌悪そうだもんね」
ところが、櫻井は増田の顔を見て大いにうなづいた。
「わかるなあ、わかる。うっかり余計なこと言えないものな」
すると、龍本が不思議そうな顔で尋ねた。
「そうなの? どうして? うちの学校、斉田くんなんかは、余計なことでも言ってしまうよ」
斉田は、そんな龍本をちらっと見て、端正な顔をほころばせた。
「まあ、言っちゃう方だね」
あとの面々は、顔を見合わせてニヤニヤした。
「この人の人徳だな」
「人徳だね。うらやましい」
「この人を見よ、だな」
「ニーチェかよ」
「なんだよ、君たち。ちょっと感じ悪いぞ」
斉田がまた生真面目に反論しようとすると、残りの面々はドッと笑った。
「そろそろ、戻って練習終わりの指示してくれる?」
櫻井が腕時計を見てあわてて言うと、木下は名残惜しそうに、運営委員の面々を見てうなずいた。
「しょうがない。じゃあ、また練習でね」
「後でまた戻ってきたら?」
と、龍本が引き留めた。
「そうしたいけど、今日は帰ってご飯作らなきゃ」
「それは大変だね」
「気をつけてね」
運営委員のメンバーたちは口々に言った。
木下は立ち上がってから、櫻井の耳元に顔を近づけてささやいた。
「浮気したらダメだよ」
「え?」
櫻井が、うろたえ気味に聞き返すと、木下は、笑顔を見せて背を向けた。
3)ホルンの練習方法はこんなに違うの?
6月下旬になって、初めて3つの高校の吹奏楽部全員が顔合わせをした。会場は、関西府立片桐高校の広い講堂だ。
この時期、各校とも夏の吹奏楽コンクールへ向けて合奏を始めていて、練習スケジュールがタイトなので、この時期しか顔合わせするタイミングがないのだった。
関西府立晴日山高校の吹奏楽部の面々は、部長の櫻井の指示で土曜日の午後、みんなでぞろぞろと片桐高校に出向いた。晴日山高校は片桐市の中心街のやや北寄りにあり、国鉄の片桐駅から徒歩数分の好立地だ。学校の正門前の道路がまっすぐ南に伸びて、市役所と市民ホールの横を通り、私鉄の片桐市駅まで続いている。この2車線道路が片桐市の中央通りであり、そのまま行っても片桐高校には着かない。片桐高校へ行くには、晴日山高校から国鉄駅の手前の高架橋を潜り抜け、駅前の狭い商店街を抜ける道筋がもっとも近道だ。もう一つ、市民ホール前から市役所の方へ元の川沿いの道を直角に曲がって、少し行ってからまた南に向かうルートもあった。
晴日山高校吹奏楽部のメンバーは総勢60名近いので、狭い商店街を歩くと邪魔になる。だから二手に分かれ、片方はまっすぐ市民ホールに向けて中央通りの歩道を歩いた。自転車通学組は先行して、国鉄駅横の商店街を抜けて片桐高校に向かった。部長の櫻井は徒歩組を引率して、中央通りの歩道を歩いた。副部長の木下幸は、こういう移動の時には念のため最後尾を歩いて行くことになっている。木下と仲のいい2年生女子数人が一緒に最後尾を歩いていた。
今日の予定は盛りだくさんなので練習はできないが、それぞれの楽器パートに分かれて、3つの高校のメンバー顔合わせをする。まずは仲良くなることが最優先だった。あとは、合同演奏会のための各楽器のパートリーダーを決める。
丘上高校は私鉄沿線にある高校なので、片桐市の私鉄駅まで電車でやって来る。そこからは徒歩で片桐高校まで数分で着く。この関西府の代表的な私鉄は京都が始発で、片桐市を東西によぎって、関西市内に乗り入れてくる。淀川を越える手前のジャンクション駅で千里市の方に乗り換えるローカル路線があり、丘上高校はローカル線の終点の一つ手前が最寄り駅だ。吹奏楽部員が大勢で乗り換えなければならないから、みんなで揃って乗るのは難しい。だから、適当に分散して片桐高校へ向かっているのだ。自転車通学の生徒たちは、片桐高校までかなり距離はあるが自転車で直行する。
片桐高校は敷地が広く、私鉄電車の車窓から見えるグラウンド側からは、クリーム色の古い校舎は遠くに望めるだけだ。正門は市役所のある公園通りから直角に、元の片桐川の堤防の上から下りてくる道に面している。晴日山高校の吹奏楽部の面々がぞろぞろ歩いて公園通りから下りてくると、すでに自転車組が正門前に到着していた。部長の櫻井は、最後尾の木下が視界に入ると、片手を振って合図し、自転車組にも声をかけて、正門に入った。真正面に校章が目立つ玄関がそそり立っていて、正門から見ると威圧的な印象だ。櫻井は、この片桐高校のいかにも名門然とした玄関の作りが嫌いだった。晴日山高校の方は、正門から入って延々とグラウンドや校舎の間を歩いて、こぢんまりとした玄関口にたどり着くような作りになっていて、まるで大学のキャンパスのような印象だ。櫻井はそういう自由な雰囲気を感じさせる晴日山の校舎が、最初にみた時から気に入っていた。
それに、生徒は片桐高校に入るのに玄関からは入らない。ぐるりと回ったところに校舎の入り口があるのだが、いちいち回らされるのが面倒なのだった。この片桐高校と晴日山高校はどちらも戦前からある古い校舎のため、校舎に土足のまま入る。生徒は、最初は中学校のように上履きに履き替えないことにとまどうのだが、すぐに土足生活の便利さに慣れて、上履きのある学校をばかにし始める。
一方、丘上高校は戦後新設の高校で上履きがあるので、3校合同の練習で最初に片桐高校に行くと、丘上の1年生はみなびっくりするのだ。
丘上高校の吹奏楽部の面々は、晴日山高校より20分ほど遅く到着し、正門を入ると校舎の裏に回って、階段を上がって講堂へ向かった。
片桐高校は片桐市の中心部にあり、広いグラウンドが元の片桐川に沿って広がり、校舎はクリーム色の重厚なコンクリート3階建て、戦前の旧制中学校時代からの校舎が残っていた。3つの高校の吹奏楽部の面々がまず集合したのは、この古い校舎に並んで建っている古い講堂だ。
この講堂は吹奏楽部の練習場所だが、戦前からある古くてだだっ広い建物で、屋根裏にどこかから鳩が入り込み、梁の間などに巣を作っていた。吹奏楽部が練習している間にも、天井から鳩のフンが時々落ちてきたりする。本来なら校舎の中に鳩が巣を作っているのは撤去しなければいけないはずだが、この高校の先生たちはのんきなのか、長年放置されていた。吹奏楽部も、鳩のフンを我慢しながら、講堂で練習を続けている。他の2校の生徒は、さすがに最初はびっくりするのだが、すぐに慣れてしまって、講堂のニスが黒光りする木の床が鳩のフンで汚れていても、適当に避けて座り、演奏するのも平気になっていくのだった。
3つの高校の吹奏楽部員が講堂に揃うと、総勢150人を超える。さすがに壮観だが、その前に立って挨拶する指揮者の片桐高校OB・伊勢は慣れた感じで、さばけた口調の挨拶を短くすませた。この日、伊勢はまだ練習を見ることはせず、挨拶だけ済ませるとまた大学に戻って行った。そのあと、部員たちは楽器ごとに顔合わせをするのだが、運営委員のメンバーたちは選曲会議を講堂でやるのだった。合同ステージでやるポップス曲の候補を持ち寄って、絞り込むことになっていた。
その間、3校の部員たちは各楽器のパートに分かれた。校舎のそこここに分散して、普通教室にぎっしり集まる。それぞれにパートリーダーを決めて自己紹介などをしながら、顔見知りになっていく予定だ。親睦を深めようと、早々に中庭に出てみんなで輪になってレクリエーションをやっているパートもあった。
2階の普通教室の一つに集まったホルンのパートは、約1年ぶりの再会を笑顔で交しあった。
丘上高校の2年生・龍本知恵子は、ホルンのパートリーダーの2年生、加川真純と二人で教室に行き、ホルンのハードケースを机の上に載せると、晴日山高校のホルンの2年生、谷山みすずの方に手を振った。
「久しぶりだね! 谷山さん!」
「こんにちは! えっと、たきもとさん?」
「龍本ですよ! ひどーい、忘れてる」
「あ、ごめんなさい。たつもとさん」
「あたしは、加川さんですよ!」
と、丘上高校のホルン・パートリーダーの加川真純がニヤニヤしながら手を振った。
「ええと、そちらのみなさん、1年生だね? あの男子君は?」
「あ、葛西君、今日は休みなんだ」
谷山みすずは、この日、同じホルンの2年生の葛西が休みなので、一人で後輩たちを他校のホルン奏者たちに顔合わせさせるという、憂鬱な事態に気が重かった。けれど、それもつかの間、実際に同じ教室に入ってみると、半年ほど前の3校合同演奏会の時の親密さが、たちまち戻ってきた。
「遅れた? 悪い!」
そう言いながら、片桐高校の2年生ホルンの2人が教室に入ってきた。
「ええっと、みなさん、適当に座ってね。今日は自己紹介だから、丸く円陣組もうか?」
「さっさと自己紹介しちゃって、これで遊ぼうよ」
片桐高校のホルンのパートリーダー・上野愛子は、他校のホルンの部員たちににこやかに手をふり、もう一人の2年生・榊原絵美はビーチボールを両手で投げ上げて受け止めて見せた。
ホルンの2年生は片桐高校も丘上高校も女子ばかりで、晴日山の葛西が唯一の2年生男子だった。そこで、みすずは他校の2年女子と相談し、一人だけ男子の葛西にパートリーダーを引き受けさせることにしてしまった。
「あの子が、うちらの中で一番うまいのは間違いないし、それがいいよ」
「去年から、パートリーダーみたいに仕切ってたしね」
「そうそう、そんな感じだったね」
女子同士笑いさざめいて、ホルン奏者たちは愉快そうに欠席裁判でパートリーダーを決め、あとは自己紹介を簡単にした。さっそく、1年生たちを促して、中庭でビーチボールで遊ぶことにした。
ひとしきり遊んだあと、中庭のヤシの木の下にかたまって座り、ホルンの2年生女子たちは、お互いの近況報告をしながら、おしゃべりを脱線させていた。
「ねえ、高音が出ない時、どうする?」
ふと思い立って、谷山みすずは他校の2年生たちに聞いてみた。
「唇押し付ける」
「うーん、息の速度を速くする?」
「喉を締める」
「ああ、そうか。喉ね。そういう方法もあるんだ」
みすずは、感心して答えた。すると、片桐高校の上野愛子が異議をとなえた。
「喉締めるのは、ダメなんじゃなかった? ほら、声帯なるべく開けておけって言われたよ」
そう聞いて、喉を締めることを提案した榊原が顔をしかめて両手を上に向けてみせた。
「ふーん、そうか。難しいね」
「どのくらいの音? 高いって」
丘上の龍本がみすずに尋ねた。みすずは、ためらいがちに答えた。
「あ、いや、どの音ってわけじゃなく、上のFより上になると、しんどくない?」
「そうだねえ、上のB♭から上は、ちょっとしんどいかな」
龍本が小首を傾げると、丘上の加川はさらに質問した。
「音階でinB♭でやる時、2オクターブってなるとオクターブ下げる、みたいな感じ?」
龍本がうなづいた。
「そうそう。あれ、きついよね。木管とか普通に2オクターブ上下できるからって、うちらも一緒にやらされるの、つらい」
すると、片桐の上野が驚いたように言った。
「音階で、2オクターブ上下、やるの? それはしんどいな」
「うちは、音階とかしないなあ」
榊原もうなづいてみせた。すると、晴日山と丘上の2年生たちは顔を見合わせた。
「ええ? やらないんだ。いいなあ」
「自分ではちょっとやるけど、基礎練の合奏とかでは音階はやらないよ」
榊原は、当然のように言った。上野もうなづく。
「その方がいいよね。あれ、B♭管の楽器だけでやったらいいのに。うちら、あんまり関係ないし。あ、でもB♭管、ダブル・ホルンだと付いてるか」
「でも、B♭の楽譜じゃないしね。Fシングルの子はどうせ移調になるし」
榊原は苦笑しながら、それでも自説を曲げない。
「もともとホルンはF音階だものね」
榊原に賛意を示そうと、みすずが言うと、榊原は驚いて聞き返した。
「え、そうなの? F音階って、やってないかも」
それを聞いて丘上の加川が驚いて聞き返した。
「ええー? じゃあ、どうやって音階練習するの?」
「ええっと、Cからかな? 普通にドレミファで」
榊原が当然のように答えると、丘上の二人は顔を見合わせて言った。
「うわ、それは初耳だ」
「逆にすごいよ。それ、なかなか難しい。だって、上のCまで上がって下りてくるんでしょ?」
「いや、下のCからチューニングB♭の上のCまで」
そういう榊原に、同じ片桐の上野は、呆れたように問い返した。
「あんた、そんな練習やってたのか。どうりで、いつも音階が合わないなあって思ってた!」
そんな片桐のホルン2年生二人ののんきすぎる様子に、他の2校の3人は大笑いした。
「それ、いいかもね。だってピアノで音程合わせられるし」
そういって、加川が賛意を示すと、榊原は首を横に振った。
「いやいや、ピアノなんか練習部屋にないよ」
「うちは音楽室で合奏してるから、ピアノでよくチューニングするよ」
丘上の龍本は、怪訝そうな顔で言った。
「えー、そうだったんだ、いいなあ」
「うちも、普通教室で合奏」
みすずは、片桐の2人とうなづきあった。
「しかもうちは、あの鳩のフンだらけの講堂だし」
「どっちもいやだな。夏暑いしね」
「クーラー、ほしいよね」
「ほしい。あの講堂、風通らないから暑いんだ」
「教室なんか、狭くて酸欠になるよ」
彼女たちは、口々に言い合っては笑いさざめいた。女子の身でホルンを演奏する苦労話は、尽きることがなかった。
(第1章 ここまで)
※続きは、電子書籍版の本作をお求めください
↓
『メロフォンとフレンチ』(Kindle版)
土居豊 作
https://www.amazon.co.jp/dp/B09QJWC25X/ref=cm_sw_r_tw_dp_4MESSV8RD00RQ8H4SXF5

昭和の吹奏楽部で広く用いられたメロフォンをモチーフに、楽器不足の中で工夫してステージを実現していく吹奏楽大好き高校生たち。17歳の友情と恋の青春を描く。
音楽小説『ウィ・ガット・サマータイム!』の姉妹編。
※あらすじとキャラクター、作品背景について→ 音楽小説『メロフォンとフレンチ』土居豊
https://note.com/doiyutaka/n/n64f59ad3b2f3
【あとがき より】
昭和の吹奏楽部で広く用いられたメロフォン、その魅力と欠陥を一つのモチーフとして、楽器不足の中で工夫してステージを実現していった吹奏楽大好き高校生たちの青春を描き出そうと挑戦してみました。
本作は、前作『ウィ・ガット・サマータイム!』と同じ吹奏楽部で、ホルンを担当する女子部員・谷山みすずが主人公です。
みすずは吹奏楽の初心者で、抽選に落ちてフレンチ・ホルン担当になるのですが、なかなか音が鳴らせません。厳しい先輩にびくびくしながら練習するうち、間違った吹き方で悪い癖をつけてしまいます。
1年生のはじめの頃、楽器不足のために一時的にあてがわれていたメロフォンを、2年生になってからあるきっかけで吹いてみたみすずは、フレンチ・ホルンよりもうまく音がなるように感じます。その後、近隣の高校との合同演奏会の時、指揮者をしてくれる他校OBの大学生が、ジャズでホルンを使ったものがあるのを教えてくれたこともあって、彼女はメロフォンをジャズ演奏に使ってみることになるのです。
本作のテーマの一つは、吹奏楽では目立たない楽器でアンサンブルをする喜びを描くことでした。そのためには、地味な中音域の楽器担当のキャラクターを主人公にする必要がありました。
昭和の吹奏楽部にたいていいくつかころがっていたメロフォン、この奇妙な楽器はどこから? なぜ学校に? そして日本のブラスバンドになぜ使われることになった?
戦後の音楽史の一つの謎といえます。
主人公のみすずにとってメロフォンは最初、フレンチ・ホルンの代替楽器だったのですが、ジャズで吹くようになるとこの性能的には不十分な楽器に惹かれていきます。
小説の最後、高校卒業後の進路を迷うみすずですが、意外な展開を示唆して物語は終わります。
小説の中では、ひょんなきっかけでメロフォンのジャズを演奏することになるのですが、当時、日本ではメロフォンのジャズを聴いた人はいないはずでした。
だから、彼女はメロフォンジャズの第一人者になれるかもしれないのです。
本作のもう一つのテーマとしては、演奏会を企画運営するリーダーたちの陰の苦労、縁の下の力持ちたちを描くことがあります。こちらの方は、前作と共通するテーマですが、今回は、他校の仲間との交流が、登場人物たちの精神的成長につながっていきます。
小説の背景
【作品舞台】
関西府の北摂地域にある片桐市、そこに戦前から旧制中学校と旧制女学校があったが戦後、合併して2つの新制高校になった。関西府立片桐高校と府立晴日山高校だ。
どちらも重厚な近代建築風の古い校舎があり、のちに建て増しされた昭和的な真四角の校舎が混在している。どちらも敷地が公立高校としては広く、古い樹木が高くそびえている。だが似ているのはそこまでで、校風は正反対だった。学生気質も、片桐がいかにも優等生っぽい雰囲気なのに対して、晴日山は遊び人っぽい生徒、自由気ままな雰囲気を漂わせているのだった。
そういう2校に加えて、千里市にある府立丘上高校がこの校区のベスト3だった。
丘上高校は新興住宅地の真っ只中にあり、70年万博で拓かれた新しい土地の住民の期待を背負った高校、というイメージで、学区2位の進学実績を誇っていた。特徴としても、旧制時代ののどかな空気感を持った2校と比べて、いかにも堅実で真面目な雰囲気を醸し出している。
【物語の時代背景】
1983年の関西府。
冷戦の時代。バブル前であり、景気は良くないが、国の雰囲気は安定していて、いかにも平和な空気があった。まだポケベルも携帯も、パソコンさえなかった時代。昭和の最後の数年、公立高校の生徒たちは、部活一色の生活をエンジョイしていた。
【前作】
音楽小説『ウィ・ガット・サマータイム!』
土居豊 作

販売サイト
↓
※KadokawaのBOOK⭐︎WALKER
https://bookwalker.jp/de6c5f7f12-9f7d-4914-bd67-000c63cc50a8/?_ga=2.87758878.783377174.1586495988-1573749936.1586495988
※Kindle版
https://www.amazon.co.jp/dp/B086YGXN5N/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_x2eKEbNW7MH19
※kobo版
https://books.rakuten.co.jp/rk/576dbfe4d03936f8bfb5bb3c0b7f7f7b/
※noteでは5章まで無料で読めます!
小説『ウィ・ガット・サマータイム!』
土居豊 作
第1章 ユニゾン1〜謎の楽譜1
https://note.mu/doiyutaka/n/na42f2da287a0
第2章 ソロ1〜ジャズ喫茶と古本屋
https://note.mu/doiyutaka/n/n7db884b63b97#Yo2Xq
第3章 ユニゾン2〜謎の楽譜その2
https://note.mu/doiyutaka/n/n80179135076e
第4章 ソロ2〜チェと南蛮屋
https://note.mu/doiyutaka/n/n322cc89320b4
第5章 ユニゾン3〜吹奏楽コンクール
https://note.mu/doiyutaka/n/n8223681c5ff2
吹奏楽好きの方、ジャズ好きの方、80年代に学生時代を過ごした方、昭和の青春群像を懐かしみたい方、あるいは、これまでの吹奏楽もの小説に不満足な方、新しい吹奏楽ものを読みたい方、ぜひ!
※解説動画
新作の小説『メロフォンとフレンチ』は吹奏楽部の青春群像を描く音楽小説です。現在よく売れている、大規模校が吹奏楽コンクールを目指すお話ではなく、地元密着で生徒だけの活動による演奏会づくり、地元の3つの高校が協力して合同演奏会を実現するお話です。
内容と作品背景について、作者の土居豊自ら語っています
配信動画
↓
https://youtu.be/OfCYRXiSqt8
前作の音楽小説『ウィ・ガット・サマータイム!』解説動画もご覧ください
↓
https://youtu.be/ySKZY_Geh_0

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/
