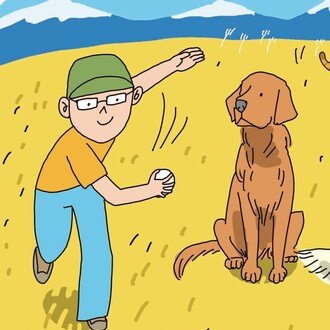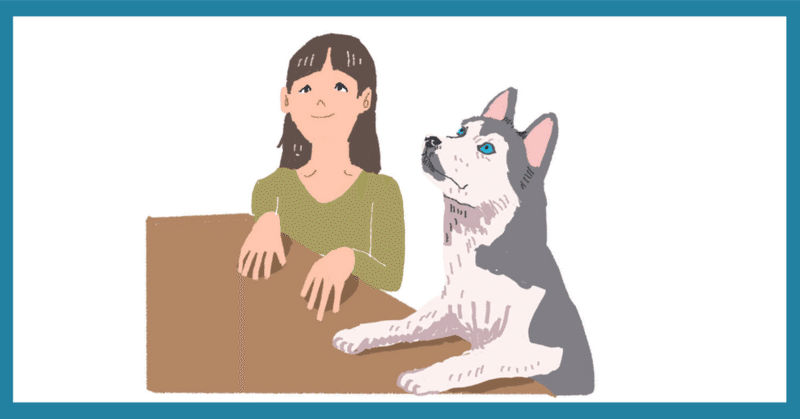
ここまでわかった犬たちの内なる世界 S2 #02犬にミラーニューロンはあるのか?
ミラーニューロンと聞けば、皆さんも何度か耳にしたり口にしたりした言葉だと思います。
1990年代に発見され、「DNAの発見に匹敵する」といわれるほど科学界にセンセーショナルな話題を提供したのが、ミラーニューロンと呼ばれる脳細胞です。
ミラーニューロンとは、
🅰️自分が行為を実行する
🅱️他者が同様の行為をするのを(自分が)観察する
この🅰️のときにも🅱️のときにも反応する脳内の神経細胞
です。
ミラーニューロンは、他の個体の行動を見て、まるで自身も同じ行動をとっているかのように"鏡"のような反応をすることから名付けられました。
ソフトクリームがもたらした新発見
このニューロンは 、1996年マカクザル(ニホンザルの仲間)の脳波の計測中に偶然発見されました。
いきさつはこうでした。
ある大学院生がソフトクリームを手に持って研究室に入った。サルが彼を見つめた。サルは動いておらず、大学院生が ソフトクリームをつかんで口に移動するのを観察しただけなのに、 脳領域のある神経細胞が発火することを知らせるモニターが鳴 った。
その後、科学者たちは、 人がピーナッツの殻を割ったときにそれを見ていたサルの脳領域で発火した細胞を発見しました。同じことがバナナ、レーズンなどその他のあらゆる種類の物にも起こったといいます。
その後の研究で、ミラーニューロンは、人や鳥類(鳴き鳥)にもその存在が確認されています。

サルや類人猿はもとより、おそらくゾウ、イルカ、イヌは、初歩的なミラーニューロンを持っている、
と考えているミラーニューロンの専門家がいると報告している。写真はラオスのルアンパパーンで撮影。 早朝、僧院で修行する少年たちが僧侶と共に托鉢に出向くところに、通りがかりのイヌが近づいてきた
映画を見ても発火する?
ハーバード大学のホームページにUPされたある神経科学者のミラーニューロンを題材にしたブログに、「自分はすこぶる奇妙な症状のある多発性硬化症の患者だ」と前置きした上で、 以下のようなコメントが寄せられています。 ミラーニューロンをイメージする上で参考になると思いますので、紹介しておきます。
例えば、映画の中で脚に怪我をしたカウボーイが出血を止めるために熱した鉄で焼灼しているのを見たときでさえ、自分の脚のまったく同じ部位に極めて強い灼熱感と痛みを感じます。痛みにさらされたその人の行動を見ていなくても、怪我の状態を見るだけで、痛みが私の脚に現れ、放射状に広がるのです。
ミラーニューロンはテレビや映画などの映像を見るだけで働くことはないと断言する学者もいますが、このコメントを読む限り、一概にそうとは言えないようにも思えます。
そういえば、2本足の犬(私のことです)自身、映像を見るだけでミラーニューロンが発火しているような思いになることがあります。
例えば、『僕のワンダフルライフ』 という映画があります。
原作は、『 野良犬トビーの愛すべき転生』(原題:A Dog's Purpose) という小説なのですが、飼い主に会うためにイヌが何度も生まれ変わるという異色のストーリーです。
それだけに、ベイリーという名のイヌと飼い主のそれぞれに感情移入できる点で、2倍感動できるという映画です(あくまでも 筆者の場合の話です)。
ベイリーとその飼い主に、自分自身を鏡に二重写ししたかのような感覚になって、作品の中に入り込めるのです。
🔽1分30秒ほどの予告編を拾っておきますね。
(C) 2017 Storyteller Distribution Co., LLC and Walden Media, LLC
映画を手がけたのは、『HACHI 約束の犬』『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』のラッセ・ハルストレム 監督です。
ゾウ、イルカ、イヌにも
ミラーニューロンについては、学者の中でも評価が分かれており、人間の社会活動にとってすこぶる重要な意味を持つことがそのうち証明されるだろうと主張する 一部の学者がいる一方で、ミラーニューロンの重要性が誇張されすぎていると述べる向きもあります。
ここでは、学者の議論は脇に置いておきましょう。
注目すべきは、このミラーニューロンが他者の行動やその意図を理解する手助けになると考えられている神経細胞だということです。
そして、上のラオスの托鉢の写真のキャプションで示したように、おそらくゾウ、イルカ、イヌは、初歩的なミラーニューロンを持っていると推断する専門家もいます。
イヌたちのコミニケーション能力を考えると、ミラーニューロンが「ない」と考える方が不自然な気がしますが、皆さんはどうお考えでしょうか?
明らかに変わった、その日
ここからは、 筆者自身のささやかな体験をお話します。
筆者が、 最初の本を出す前、八ヶ岳の牧草地を拠点にしていたことは、『ここまでわかった犬たちの内なる世界』(シーズン1)の中で何度か述べました。
牧草地で育てた「ルイ」と「ロンド」の兄弟犬には、同腹のきょうだいがいて、その中に筆頭株とでもいうべき雄のゴールデンレトリバーがいました。
骨量の豊かな、 純白の被毛におおわれたその子イヌの容貌は、往年の名力士を彷彿させたので、「ウルフ」と呼んでいました。
(由来は、千代の富士のニックネームが「ウルフ」だったことによる)

3カ月齢の頃のルイ(右)ロンド(左)ウルフ(中央)。背後にいるのは「イルカ」という名の母イヌ
ウルフは早熟で幼い頃から優れた認識力を示しました。
一方ルイは、いたずら好きでいたってマイペースな子イヌでした。
6頭いた兄弟犬が筆者に一斉にじゃれつくことがあります。 その際、決まって “後方支援 “に徹する子イヌがいました。後ろに回り込むとジーンズの太腿に歯を当ててくるのです。当てるだけではすみません。糸ノコギリのような鋭い切歯を情け容赦なく筆者の柔肌に食い込ませ、皮膚を引っ張ろうとするのです(乳歯の頃の子イヌはみんな尖った切歯を持っている)。 この子イヌこそルイです。
少し身体が大きくなると、歩行中の筆者の隙を見て、両太腿の間に飛び込んで来て股をくぐり抜けようとします。また、これがくすぐったくて仕方がない(筆者は内心楽しんでいたんですが)……そんな “悪さ“が、この子イヌのルーティーンになっていました。

そのすぐ後ろにいるのはウルフ。左端で押さえ込んでいるのはロンド
まったく、やれやれ、という感じです。
ところが、4ヵ月齢の頃、そんなルイが変貌を遂げた1日がありました。
最後まで読んでくださりありがとうございます。 皆様からのサポートは、より良い作品をつくるためのインプットやイラストレーターさんへのちょっとした心づくしに使わせていただきます。