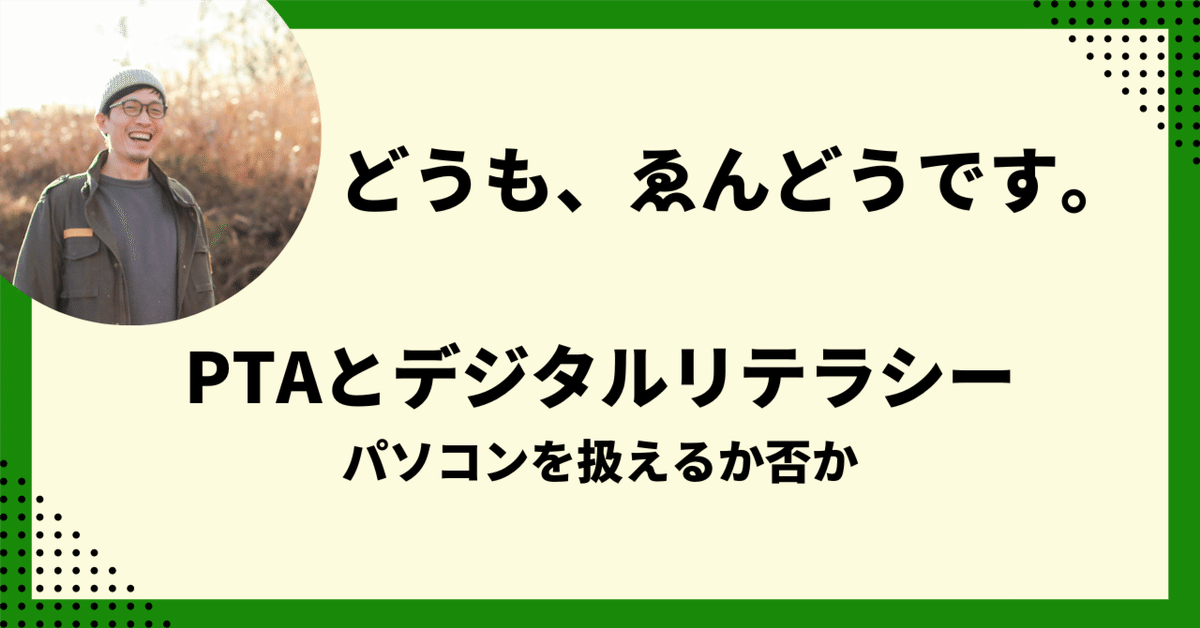
PTAに関するデジタルスキルやITリテラシーに関する一考察
どうも、ゑんどう(@ryosuke_endo)です。
PTAって謎の組織ですよね。
謎の組織すぎて興味津々になってしまったので「中の人になってみよう」とPTA幹事(執行部)として活動することになりました。ちなみに、前年も不登校児童の学年委員長として活動しているため、二期連続での活動ということになります。
まぁ、なんというか、ほんとに多くの保護者にとって「できれば役を担いたくないもの」として認識しているのに、前面に出る会長や副会長といった前面に出る人たちは「子どもたちのために」と否定しがたい真っ当なことを述べていたりします。
このあり方自体が異様な様相を呈していると実感せざるを得ないのですが、歴史的なことを踏まえてみると行動経済成長期に発足が重なったこともあり、「PTA=女性」といった構図が出来上がったものの現代においては共働き世帯が多くなったことから忌避されるような状態になっているのだろうと思われます。
その辺を書いたnoteもあるので興味がある方は以下をお読みください!
誰にでも門戸が開かれているのではなく「子ども」といった人質を取られている構図
で。
そもそも誰もが活動に参加できるようにしなければならないって前提があるPTAな訳で、活動への参加に経済的な差、つまり世帯収入の多寡によって参加の可否が決められるだなんてことはありません。
学校に通う児童生徒たちの保護者であれば、子どもたちへの教育活動が充実するように支援したいのなら誰だって参加していい。それが謎の組織PTAの姿であり、そうなる以上は持続可能な組織にしなければいけません。
持続可能な組織ってどうやってやるのかといえば、誰でも参加できて運用に何の支障も生じないような体制や仕組みを構築する組織ってことです。「〇〇ができなければ参加できない」などといった敷居が設けられる組織ではなく、誰にも平たく門戸が開かれた組織ってことです。
その建前は別に問題がないように思われますが、PTAの活動対象は児童生徒ですが、当然ながら、その保護者に向けた発信が主となります。
そうなれば人数の多い学校では100名単位、1000名単位での発信となりますから、ちょっとした中規模企業みたいな話になってきます。中規模企業であれば、まだ「利益を叩き出すために」とトップダウンで号令を出して一気呵成に業務を行うことが可能でしょうが、PTAは違います。
そもそも学校に子どもが通うことに目的意識を持っている保護者なんて多くありませんし、子どもが通うことに支障があれば口や手を出したくなるでしょうが、そうでないのなら手も口も出したくない。むしろ、穏便に何もさせないでほしいとすら思っていることでしょう。
つまり、向いている方向が異なる人たちを無理やり「子ども」といった(言い方が悪くなるのは申し訳ないのですが)人質を取られており、その「人質のため」といった大義名分に保護者だけでなく学校関係者、さらに地域関係者まで巻き込んで活動を行うことが求められますから、保護者たちは逆らうことができない中で活動をしなければならないといえます。
デジタルスキルやITリテラシーといった面での課題
ただ、そうはいってもPTAがあるからこそ学校の行事や運営が成り立っている側面は否定できません。
「子どもたちの健全で充実した教育活動のために」といった大義名分を本当の実現しようとしているのがPTAであり、中の人たちは日常の生活がある中で大変ながらも必死に汗をかきながら取り組んでいるのは事実で、そこには何の悪意もありません。
だからこそ、苦しくなってくる場面や苦々しく活動に取り組まなければならないって心情になるのでしょう。
先ほども書きましたが、100名や1000名単位に発信する文章などを作成するためには、どうしたってPCで作成しなければいけません。正確にいえば、ドキュメントを作成できる何かしらのソフトを扱える必要があります。
別に何だっていいのだとは思いますが、ここで前提に立ち返らなければいけません。
PTAは誰でも参加できる、むしろ、参加できなければならない組織体であって、何かしらのソフトを扱ってドキュメントを作成できない、パソコンを持っていない、パソコンを扱うことすらできないからといって参加を拒んでいい組織ではないのです。
しかし、以下のような記事が出るように、自宅にPCがない家庭もあるでしょうし、そもそも20代の保護者にはPCがない家庭だってあることでしょう。
だからと言ってPTAの活動ができないわけではありませんし、そうなればそうなったで「できること」を最大限に取り組んでもらうことがPTAにおける本義であるはず。
ですが、PC等を利用してドキュメントの作成が求められるのに、それができないからといって「それまでに発行してきた書類」や「それまで行ってきた活動」が止まることは許されません。
なぜなら「子どもたちのため」だから。昨年度までの子どもたちが体験できていたこと、昨年度までの子どもたちが何の支障もなく学校教育を味わうことができていることが途絶えてしまうことは絶対に避けなければならないのです。
よって、「前例踏襲型の組織」として活動しなければならないだけでなく、その活動におけるドキュメントの作成なども「前年と同じ形で」などとなりがちとなります。
その善し悪しは問うものではなく、そうであるからそうであるべきだと言わんばかりに無言の圧力が働きますが、それは誰が悪いわけでもありません。
「子どもたちの充実した学校生活」といった自らの人生ではない人生が傷ついていいわけではありませんから、保護者は必死に前例踏襲し、PCを持っていなかったとしても、スキルがなかったとしても懸命にドキュメントを発行し続けるのです。
持続可能な組織ってなんだ
前提踏襲型の組織運営は、別に悪いものではありません。だって、それであれば何も考えずにPTAの活動を継続して行えますし、それこそ持続可能な組織だと言えるでしょう。
でも、そうなってくると問題になるのは「面倒なことも面倒なまま」ってことです。
前例踏襲型となると、問題があるのに問題だと認識されなかったり放置され続けることにもなり、結果として「誰のために」とか「誰が考えたのか」と文句を言いたくなる状態に陥ってしまいます。
PTAが子どもたちのために取り組まれるものであるのなら、保護者の生活が安寧であるべきです。そもそも、それが侵されるような状態に陥っているのであれば、それこそ「子どもたちのため」にはならないでしょう。
また、下手にデジタル化やITを導入してしまっているために情報を個人が保有するような状態に陥っている組織も少なくはないはずです。
個人情報の入ったデータをUSBメモリに保存し、それを持ち歩きながら買い物に行くなど、通常の企業運営においては絶対にしないような行動をとっていることに何の危機感もない状態は非常に危うく、絶対に避けなければいけません。
そもそものあり方として、抽選形式でPTAの役員(担当)を決めるような状態を是正する必要があります。
何なんでしょうね。任意なのに嫌がりながら担当しなければならないって。「子どもたちのため」といった目的からは到底かけ離れた思想といえますし、非常に悲しいじゃないですか。
できる人ができることをする。
そうやって役割分担が明確になっておらず、「平等」の名の下に「できないのにやらなければならない」とか「PCなんて扱えないのに…」といった個人の状況を無視した「前例踏襲」があるから不平や不満が出てくるのでしょう。
こんな状態を避けた方がいいってことを避けるようにすることこそ、「子どもたちのため」になるんじゃなかろうかって思うのですよ。
おわりに
興味本位で入っている謎の組織PTAですが、正直なところ、改革したいとかそんなことは微塵も思っていません。思っていませんが、「イヤイヤながら参加する」なんて状態が是正されたらいいのになぁ…とは思っています。
ポンコツながらも少しは役に立つことができるのであれば、ぼくの人生にとっても少しは有益に働くのかもしれません。
そんな感情で動いています。
ではでは。
ゑんどう(@ryosuke_endo)
#えんどうnote 、マガジンをフォローすると通知が届きます!
X(Twitter)もやってますのでフォローしてください!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
