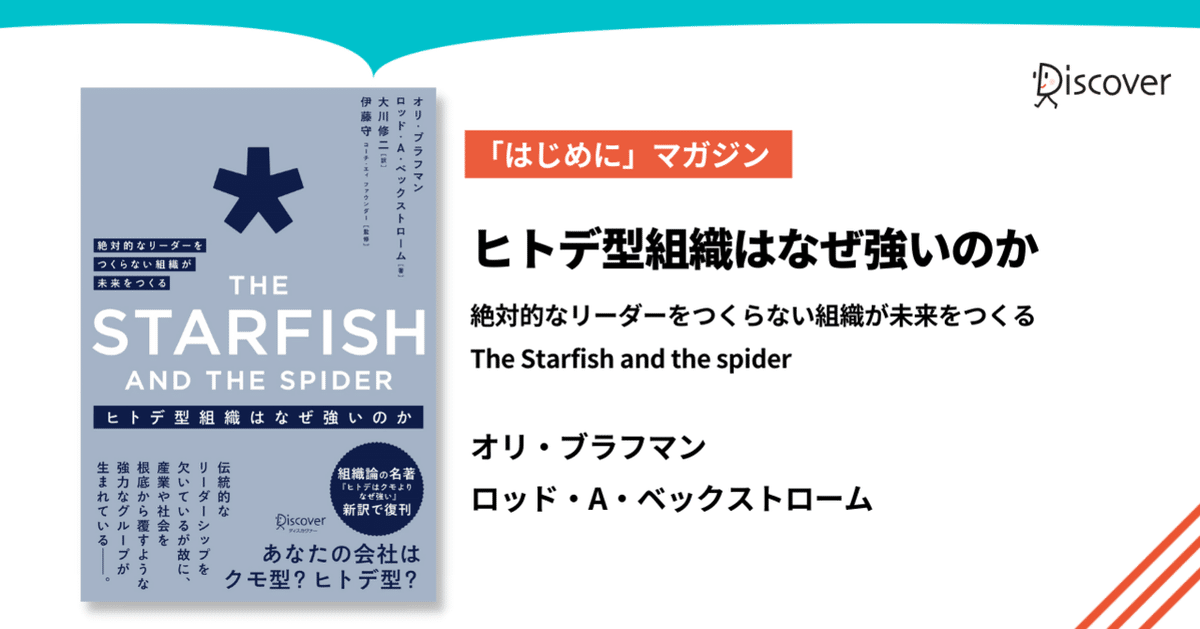
【「はじめに」公開】組織論の名著が新訳で復刊『ヒトデ型組織はなぜ強いのか』
本書は、組織論の名著『ヒトデはクモよりなぜ強い』の新訳版。
分権型組織(ヒトデ型組織)が、中央集権型組織(クモ型組織)に比べ、いかに創造的で、従来の秩序を破壊し、経済的なインパクトを与えるのか。
ナップスター vs. 巨大エンターテインメント企業MGM、スカイプ vs. AT&T、アパッチ族 vs. スペイン軍、そして、イーベイ、ゼネラル・エレクトリック、トヨタ…様々な事例からまとめた、最強の組織をつくるヒントがまとめられた一冊です。
このnoteでは本書の冒頭部分「はじめに」を公開します。
はじめに
そのゲームは、あの『ウォーリーをさがせ!』によく似ていた。ただし、プレイしていたのは子どもたちではなく、世界屈指の神経科学者たちだった。ターゲットもウォーリーではない。髪をカールしたセーター姿のおばあさん、それも各プレイヤー自身のおばあさ
んを、めいめいが探し続けていた。
神経科学者たちは、ある質問―最初は、すぐに答えが見つかりそうに思われた質問―に答えようとしていたのだ。人は誰しも記憶をもっている。初めて学校に行った日の記憶、おばあさんの記憶、などなど。ところで、こうした記憶はいったいどこにしまわれているのだろうか―これがその質問だった。やがて彼らが見出す結論は、生物学上の謎に留まらず、世界中のあらゆる産業や国際テロ、世界各地のさまざまな共同体に秘められた謎を解き明かすことになるのだが、このときはまだ誰もそのことを知る由もなかった。
科学者たちは長きにわたって、人間の脳は複雑な機械と同じく、トップダウン構造を備えているのではないかと考えてきた。確かに、一生にわたる記憶を貯蔵し管理するためには、脳が命令系統を備えている必要がある。統括しているのは海馬という器官で、その管理下に特定の記憶を貯蔵する神経細胞がある。人が何かを思い出せるのは、高速コンピュータのような働きをする海馬が特定の神経細胞から記憶情報を引き出すからに違いない。初恋の思い出は神経細胞18416番から、小学校4年生のときの先生の思い出は神経細胞46124394から、といった具合に。
この仮説が正しいと証明するには、特定の記憶を思い出そうとすると、毎回同じ神経細胞が活性化するということを示す必要がある。こうして1960年代以降、被験者に電極やセンサーを取り付け、ごくありふれた品物の写真を見せるという実験が行われるようになった。科学者たちの予想では、被験者が同じ写真を見せられるたびに、毎回決まった神経細胞が刺激を受けるはずだった。被験者たちは長時間にわたって写真を凝視し続けた。科学者たちは観察し、特定の神経細胞が発火するのを待ち構えた。じっと待った。さらに待ち続けた。
結局、特定の神経細胞と特定の記憶が1対1で対応しているという事実は見出せず、謎だけが残った。被験者は同じ写真を見せられているのに、反応する神経細胞は毎回違っていたのだ。それだけでなく、異なる写真を見ているのに、同一の神経細胞が反応するときもあった。
科学者たちは、当初、こうした事態は技術的な問題によるものだと考えた。おそらく、センサーの精度が低いからだ、と。その後数十年、神経科学者たちは似たような実験を繰り返した。実験装置の感度は向上したものの、依然として意味のある結果は得られなかった。いったいどうなっているのだろうか。記憶が脳のどこかにしまわれているのは間違いないはずなのに。
この謎を解明したのは、ジェリー・レトビンというマサチューセッツ工科大学の科学者だった。彼によると、一定の記憶が1つの細胞内に存するという考え方そのものが、まったくもって間違いだという。科学者たちは脳の中にヒエラルキーを見出そうとしてきたが、そんなものは元から存在しないというのがレトビンの主張だった。彼の説によると、記憶は、海馬の監督下にある特定の神経細胞に蓄えられているのではなく、脳内のさまざまな部位に広く分散しているのだ。彼は、人が自分のおばあさんの記憶を蓄えている架空の神経細胞を想定し、これを「おばあさん細胞」と名付けた。レトビンの思い描いた脳の構造は、一見すると原始的で無秩序なものだ。なぜこれほど複雑な思考機械が、こんな奇妙な発達の仕方をするのだろうか。
こうした分散構造は、直感的には把握しづらいが、脳が「打たれ強い」のは、実際のところこの構造のおかげなのだ。たとえば、誰かの脳からある記憶を消したくなったとしよう。もし脳内にヒエラルキーが存在するならば、その記憶が蓄えられている神経細胞を特定して攻撃すれば目的は達せられる。だが、レトビンの提唱したモデル通りだとすれば、そんな簡単なやり方で記憶は消せない。この場合、神経細胞のパターンを攻撃しなければならず、はるかに難度が高くなる。
神経科学者がおばあさん細胞を探し求めるのと同じように、われわれは脳の外の世界についても、ごく当たり前のように秩序を見出そうとする。周囲の世界のあらゆるところにヒエラルキーの存在を求めてしまうのだ。対象がフォーチュン500企業であれ、軍隊であれ、地域社会であれ、「誰が仕切っているのか」に自然と目が向いてしまう。
本書のテーマは、誰も仕切る者がいなかったらどうなるかということだ。それはまた、ヒエラルキーが存在しないとどうなるかということでもある。混乱し、場合によってはカオス状態に陥るのではないかと思うかもしれない。しかし、多くの分野で、伝統的なリーダーシップを欠いているが故に、産業や社会を根底から覆すような強力なグループが生まれている。
要するに、われわれの周りでは、猛烈な勢いで革命の嵐が吹き荒れているのだ。
1999年、ノースイースタン大学の学生ショーン・ファニングは、寮の自室で椅子に座ったまま世界を変えようとしていた。だが、当時は誰もそれに気づいていなかった。18 歳の大学1年生ファニングは、パソコンに向かいながら、ふとこんなことを思った。みんなで音楽ファイルを交換できるようになったら、どうなるんだろう、と。こうしてナップスターが誕生し、彼のふとした思いつきはレコード業界に壊滅的な一撃を加えることとなった。ただし、ファニングが先頭に立って攻撃を仕掛けたわけではない。音楽ファイルを交換し合うティーンエイジャーや大学生が、そして最後にはiPod を持ち歩くビジネスマンまでが加わって、まるで軍隊のごとくレコード業界に襲いかかったのである。
場面は変わって、アメリカから地球を半周分離れた中東の地。ウサマ・ビンラディンがサウジアラビアを出てアフガニスタンに向かったとき、この男が数年後、世界一のお尋ね者になろうとは誰も思いもしなかった。当時は誰もがビンラディンの力を見くびっていた。洞穴から指令を出す? そんなやり方で何ができるというんだ、と。しかし、アルカイダが大きな力をもつようになったのは、ビンラディンが伝統的なやり方でリーダーシップを発揮しなかったからこそなのである。
1995年、一人の内気なエンジニアが、サンフランシスコ・ベイエリアで開催予定のイベントをリストにして、インターネット上に公開した。クレイグズリストである。このとき、クレイグ・ニューマークは、自分が立ち上げたサイトが新聞業界を永遠に変えようとは夢にも思っていなかった。2001年、元オプション取引のトレーダーが、ネット上で全世界の子どもたちに向けて、勉強に役立つ情報を無料で公開し始めた。やがてこの試みが発展して、お互い見ず知らずの何百万人という人々が、「ウィキ」というシステムを使い、世界最大の情報サイトを生み出すのだが、当の本人はそんなことは夢想だにしなかった。
レコード業界を突然襲った一撃、9・11の同時多発テロ、ネット上の三行広告サイトや執筆者参加型百科事典の成功。これらに共通しているのは、ある未知の勢力によって引き起こされたという点だ。この勢力を攻撃すればするほど、相手はますます強くなる。バラバラに見える分、かえってしぶとさを増す。コントロールしようとすればするほど、ますます予測不可能な動きを見せてくる。
権限の分散化(分権化)は、過去数千年にわたって、眠れる獅子のごとき存在であった。だが、インターネットの出現によってついに目覚めたこの獅子は、伝統的なビジネスを打ち倒し、産業界全体に変化をもたらし、人と人との交わり方を変え、世界の政治に影響を及ぼすようになった。構造やリーダーシップ、公式組織を欠くことは、かつては弱点と見なされたが、現在では大きな強みとなっている。一見するとまとまりに欠けた集団が、これまで支配的だった組織や体制に戦いを挑み、勝利を収めている。ゲームのルールが変わったのだ。
この事実が、アメリカの連邦最高裁判所において、白日の下にさらされることになった。そこでは、世間の耳目を集めたある裁判が、驚くほど奇妙な展開を示そうとしていた。
(1章に続く)
***
目次
第1章 MGMの失策とアパッチ族の謎
第2章 クモ、ヒトデ、インターネットの社長
第3章 ヒトデだらけの海
第4章 5本の足で立つ
第5章 触媒の秘めたる力
第6章 分権型組織との対決
第7章 コンボ・スペシャル:ハイブリッド型組織
第8章 スイートスポットを探して
第9章 新しい世界
著者について
オリ・ブラフマン(Ori Brafman)
生まれながらの起業家。これまでに、ワイヤレスサービスの新規事業、健康食品の擁護団体、公益プロジェクトに取り組むCEOのネットワークなどを創設した(CEOネットワークはロッド・ベックストロームと共同で)。カリフォルニア大学バークレー校で平和及び紛争研究の学士号を、スタンフォード大学ビジネススクールでMBAを取得。サンフランシスコ在住。
ロッド・A・ベックストローム(Rod A. Beckstrom)
トゥイッキー・ネット社の会長兼チーフ・カタリスト(主席触媒)。CATSソフトウェア社を創設し、CEOとして株式公開を果たす。環境防衛基金及びジャミイ・ボラ・アフリカの役員も務める。スタンフォード大学で学士号とMBAを取得。学生時代はフルブライト奨学生でもあった。カリフォルニア州パロアルト在住。
***
本書は、分権型組織がクモのような中央集権型組織よりも強いことを説明しています。 『ティール組織』を読まれた方、"心理的安全性"や組織学習に興味のある方にはおすすめの1冊です。
(営業部 伊東)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
