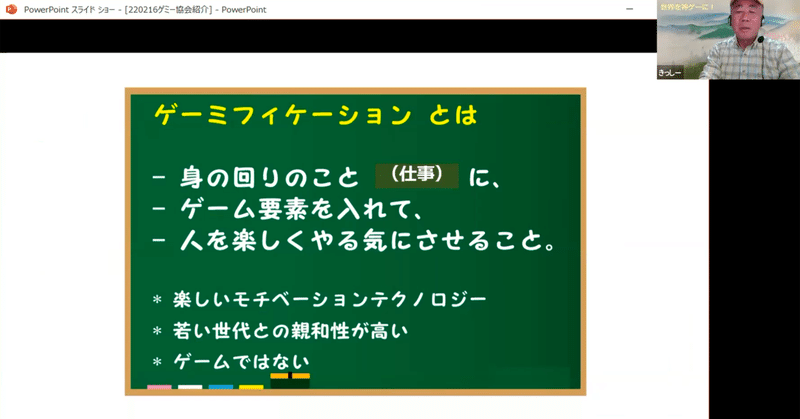最近の記事

タカハシ教授が語るビデオゲーム50年史:オデッセイとラルフ・ベア(デジタル・エンターティメント研究会第58回定例会レポート)
6月15日(水)に、第58回定例会「タカハシ教授が語るビデオゲーム50年史」を開催しました。講師はメディア・プロデューサーで京都芸術大学特任教授の高橋信之さん。 高橋さんは、今年から2024年にかけての3年間を「ゲームアニバーサリー」と名付けています。ビデオゲームのレジェンドにまつわる記念年が続いているのです。 ゲームのレジェンド・アニバーサリーカレンダー 2022年 「オデッセイ」発売50周年、ラルフ・ベア氏生誕100周年 『スペースウォー!』発明60周年 アタリ社創

7月20日(水)、「これからのカリキュラマシーンの話をしよう」(デジタル・エンターティメント研究会定例会 第59回)を開催します。
書籍『カリキュラマシーン大解剖』(彩流社)刊行記念! 1970年代に過激なギャグの連発で当時の子どもたちを虜にした伝説の教育番組、『カリキュラマシーン』。最近ではそのユニークなテーマソングがNHKの『チコちゃんに叱られる!』で使われていることでも有名です。その裏には「テレビの黄金時代」を支えたディレクター・プロデューサーほかスタッフの創意工夫と、その後のテレビバラエティ界を牽引する構成作家たちの奇想天外な発想、そして綿密に構成された「こくご」と「さんすう」のカリキュラムがあり