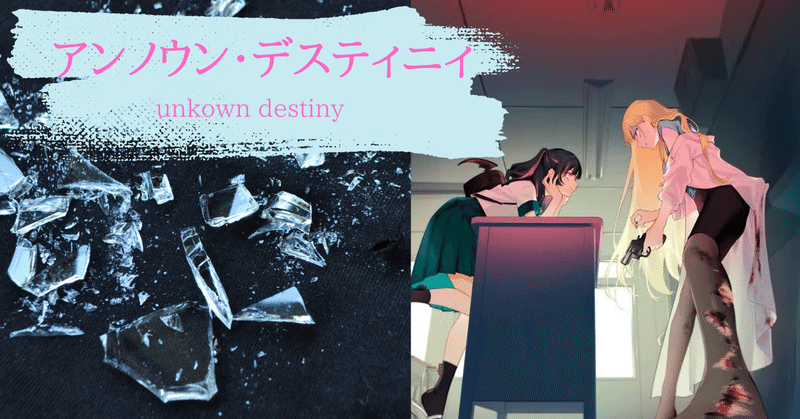
アンノウン・デスティニィ 第6話「日なたと日かげ」
第6話:日なたと日かげ
【2034年9月2日、神奈川・D大学湘南キャンパス】
丘の上にあるキャンパスは晴れていると相模湾を一望できる。主に科学系の研究室を集めたキャンパスは学生もまばらで静かだ。白衣姿が数人ずつ連れだって闊歩している。潮風が気まぐれに坂道を駆け上ってくる。
山際調査事務所の鬱蒼とした温室も気に入っているけれど。こんな爽やかな風の通る環境での研究は心地いいだろうな。ベージュのパンツスーツの腰に手をあてアスカは海に顔を向ける。ウエーブのかかったオレンジブラウンの髪が風にあおられる。黒革のビジネストートを肩に提げ、右手には横浜で人気のスイーツ店の紙袋。本日のコンセプトは製薬会社の新人営業職だ。
『プロジェクトX』のもう一人の被験者つまり精子提供者が判明したのは内調に呼びだされてから2週間後、8月も終わりかけていた。
相手を知る必要などない。政府が極秘で選定した天才はだれなんだろうという好奇心にすぎなかった。
ノリ気になったのはシンちゃんのほうだ。内調のコンピュータシステムに侵入し、その底の底に厳重に鍵をかけて秘匿されている情報にアクセスする。「日本のインテリジェンスの裏をかくなんて、こんな痛快なこと。腕がなります」興奮で目がぎらついていた。山際事務所によるハッキングとばれたらまずいっしょ、と自宅籠城を決めこんだ。
シンちゃんはつくば駅近くのマンションに住んでいる。
つくばエクスプレス一本で秋葉原まで行けるから便利なんだという。休みにはアキバの電気街を物色しジャンク品や戦利品をかついで帰ってくる。一人暮らしのくせにファミリータイプの2LDKの部屋を借りていた。70平米はある物件なのに、室内は何台ものコンピュータや周辺機器に占拠され足の踏み場もない要塞と化している。クーラーをがんがんにかけていても室内はCPUが発する熱がこもり熱中症になりそうだ。
「日向透、28歳。D大学生命理工学部准教授」
シンちゃんがプリントアウトした情報を手に2週間ぶりに事務所に現れた。
「28歳で准教授とはな。その年齢で准教授になれるのか」
「今の肩書もすごいですけど」シンちゃんがテーブルから乗りだす。
「彼のすごいところは」シンは何日も徹夜したのだろう、充血した目を見開いて続ける。「14歳でハーバードに入学、16歳で首席卒業。翌年マスターを取得。19歳でドクターつまり博士号まで取得しています。驚異的です」
眼鏡のブリッジを指であげる。
「ハーバード入学のときに騒がれてたな、たしか」
「卒業後はハーバードで研究室をひとつ任されてたようです。まさに若き天才ですね。3年前にD大学から三顧の礼で迎えられてます」
「ふうん、そんなすごい人か。政府が熱望するわけだ、その人の遺伝子」
アスカものぞきこむ。
「シン、おまえもすごいよ。よく内調の極秘情報を掘り当てた」
バンバンと、シンちゃんの肩を叩いてねぎらう。
山際は冷蔵庫から缶ビールを取り出しシンとアスカに投げてよこす。自らの缶をおもいっきりシェイクすると、シンに向かってプルタブを引く。炭酸ガスのエネルギーを駆動に琥珀の液体が放物線を描いてシンを直撃する。
「なにすんですか、ボス」
シンちゃんが濡れた子犬のように頭をぷるぷると振る。
「ビールかけに決まってんだろ」
床も書類もびしょびしょだ。ビールがシンの汗臭さを中和する。
ぬるい夕風がログキャビンの笑い声をかきまぜる。
アスカは「ほんものの天才」に会ってみたくなった。きらびやかで恵まれた経歴。日なたの人生を歩む人物とはどんなヤツなのか。
「姓まで『ひなた』なんて。そのままね」アスカは薄い笑みを浮かべる。羨望がざらざらと胸をこすった。
日向研究室と記されたプレートを確認する。
本日のプロットは単純だ。日向研究室は第3棟の最上階5階にある。第2棟5階の薬学部・藤枝研究室を代役で訪ねる製薬会社の新人営業員が建物をまちがえたという設定。どんな人物かをのぞき見するだけだから、ほんの数分でいい。ちょっと会話でもできれば儲けものかな。
よしっ、と気合を入れてノックする。
「藤枝教授、遅くなり申し訳ございません。大宝製薬の布川と申します。大崎の代わりに試薬をお持ちしました」
アスカは勢いよく扉をあけ、ほがらかな声を響かせた。白衣の人物が立ちあがる。窓から射し込む光がまぶしく顔がよくわからない。
「やあ、いらっしゃい。鳴海アスカさん。コードネーム、眠り姫さん」
「え?」
名前を言い当てられたことにも驚いたが、コードネームまで挙げられアスカの頬が凍りつく。肩に提げたバッグに右手をつっこみスタンガンを握る。
「ごめん、ごめん。そんなハリネズミみたいにならないで」
寝ぐせのついた髪を押さえながら日向があわてる。
アスカはまだ警戒を解かない。
「あなたの来訪はわかっていたし、あなたについても知っている。その髪はウイッグですか」
アスカは驚く。これまで潜入工作で変装を見破られたことはない。
「あたしのこと、どこまで知ってるの」
スタンガンを握ったまま天井のカメラの位置を確認する。それに気づいたのだろう。
「この部屋にカメラはありません。そんなのがあったら、発表前の論文や研究が盗まれてしまいます。研究の世界も競争社会です。そのへんに適当に座ってください。飲み物はコーヒーでいいですか」
アスカの警戒にはおかまいなしに日向は背を向けて窓際の流し台へと向かい、流しに置きっぱなしのビーカーを洗う。棚からマグカップをひとつ取り、それとビーカーにコーヒーを注ぐ。
「砂糖とミルクは?」
アスカが首をふると、オーケーといって日向は両手にマグカップとビーカーを持って戻る。長テーブルの上の山積みの資料や書籍を肘で押しのけ、わずかばかりの余白をつくるとそこに置いた。「どうぞ」とアスカにすすめ、日向はビーカーを手にする。ひと口飲んでから「あ、毒は入ってないからね」といって、棒立ちのアスカに笑いかける。
「あなたのことは上田情報官から聞きました」
「あたしは相手の情報開示を断られた。国家の機密事項だからって」
「ぼくはごねたから」
「ごねた?」
「卵子提供者の情報を開示してもらえないなら、精子提供できないってね」
「その程度で」アスカはため息をもらす。「国はあなたの遺伝子だけが欲しかったのよ、あたしはただの受け皿」
人生に優劣はついて回る、それだけのこと。動物だって優秀な遺伝子を残すためにおかしな方法で競っている。
日向は携帯用のボイスレコーダーをテーブルに置く。
「証拠として会話を録音していたから、これで脅した」
「身体検査はなかったの?」
「この部屋にご足労願ったからね。庁舎までは忙しくて行けない。研究室に来てくれたら話は聞くって言ったのさ。インテリジェンスの本拠地に一人でのこのこ出かけていくなんてリスクが高いだろ」
さも当然というように、ビーカーのコーヒーを啜る。
「教えてもらったのは、鳴海アスカさん、26歳。山際調査事務所調査員ということだけ。あとはぼくが調べた」
「コードネームも?」
「眠り姫、すてきだと思った」とうなずく。
「あたしがきょう訪問することは、どうしてわかったの。所長にも言ってないのに」
「ぼくは、ほんの少し先の未来を透視できる」
「は?」
「信じられないよね。誰にも言ったことはない。あなたがはじめてだ」
日向は最初から嘘やごまかしを混入せずに話している。生命科学の研究者としてコンタミすることを忌避するように。信じがたいことだけど、信じられる気がした。
「未来のことがなんでもわかるの?」
「何本かの道の入口が見えるというのかな、そんな感じ。道の先がどうなっているかはわからない。それにね、透視はよほどのことがないとしない」
「なぜ?」
「激しい頭痛に襲われるから。けど、きょうみたいに不意に映像が浮かぶこともある、ぼくの意識とは関係なく」
「そうだ、正確に毒をコントロールできるんだってね」
とつぜん思い出したように話題を変えた。
「そうね。眠っている時間も、目覚める時間もかなり正確かな。眠りが長くなるほど難しくなるけど。ちゃんと目覚めてくれるか気になる。殺しが目的じゃないから」
「じつに興味深い」
「企業秘密だから、レシピは教えられないわよ」
「薬の配合よりも、なぜ眠り姫になったのか。あなたの半生に興味がある」
アスカの表情が急にこわばる。椅子を蹴って立ちあがるとウィッグとコンタクトをはずす。ストレートロングの金髪がほどける。
「あなたが日なたの人生を歩んでいる間、あたしは日かげを歩んできた。それを聞きたい?」
きっと睨みつける。
「日なたの人生ね」
日向は寂しげに瞳をゆらす。
「光は影も生むんだよ。ちょっと失礼」
席を立ちアスカのほうにテーブルをまわりこむ。白衣を脱いで、ジーンズのファスナーに手をかける。
「待って。なにをするつもり」
アスカはスタンガンを向ける。
「ごめん。30秒いや10秒でいい。がまんしてください。ぼくはパラフィリアでも露出狂でもない。事実を見てもらえば納得できると思う」
そういいながら、ジーンズとトランクスをひと息におろす。
アスカは両手で口をふさぐ。
ペニスだけではない、鼠径部にまで本来の皮膚がわからないほど無数の傷痕があった。おぞましいことにそれらの傷はパンツで隠れる範囲に巧妙に収まっていた。傷はかなり薄くなっているけれど、斜めに走る切り傷に混じって火傷とおぼしき痕もあった。
トランクスをあげようとする手をアスカがとっさに握って止めた。
「待って、この傷は?」
火傷の痕を指す。
「煙草を押しつけられた。もういいかな。さすがに恥ずかしいんでパンツをあげさせて」
「あ、ごめんなさい。ひょっとして……」
アスカはその先の言葉を呑む。
「そう、父親による虐待」
沈黙が横たわる。日が高くなってきたのだろう。窓から射す光の裾は、ふたりの前にはもう届かない。
「ぼくはアメリカに逃げたんだ」
そういって日向は語りだした。
「ぼくは答えが見えるんだよ」
たとえば数学の問題でも。問題を読んだだけで、ぱっと解答が浮かぶ。学校の勉強だけじゃない。ミステリードラマなんかでも、犯人が登場したとたんにそいつが犯人だってわかる。みんな「どうしてわかるんだよ」っていうけど。ぼくにしたら、なぜわからないのかふしぎだった。そのうちまわりが「天才だ」って騒ぎはじめた。母も有頂天になった。ぼくも子どもだったから、おとなたちが誉めてくれるのがうれしくて、どんどん難しい問題を解いた。小学4年生になるころには大学受験の問題を解いてた。メディアでも騒がれるようになって。家庭はぼくを中心にまわりはじめた。父は同じ男だから嫉妬したのかもしれない。仕事でうまくいかないことも重なったのかもしれない。そのころからなんだ。虐待がはじまったのが。
「お母さんは……お母さんは気づいてなかったの?」
「気づいてたんじゃないかな」
「じゃあ、どうして」
「怖かったんだろうね。父による虐待が明るみにでたら、生活が崩壊してしまうから」
アスカは絶句する。
13歳のときにハーバードのボリス教授から招待を受けた。教授は脳科学のオーソリティでね。君の脳を研究させてくれるなら、ハーバードへの入学を許可しようと。父から逃れられると思った。アメリカは虐待に厳しいから父はついてこないだろうけど、保険はかけておこうと考えた。下腹部の写真を撮って教授に送り父による虐待を明かした。そして条件を出したんだ。両親とは離れて暮らしたいと。教授が親とどんなふうに交渉したかは知らない。ぼくは教授の家で暮らすことになった。
「帰ってくるつもりはなかったんだけどね。D大学の足立理事長の熱意に負けた。それに、ぼくはもう父に対抗できるくらい十分におとなだから」
日向はビーカーのなかですっかり冷めたコーヒーを一気にあおる。
「親がいれば幸せとはかぎらない。ぼくが被験者に同意した理由がそれ」
「あたしと反対ね」
アスカは日向を見つめる。
「あたしは孤児。親も、親の愛も知らない」
生後ひと月も経たないころに赤ちゃんポストに捨てられた。「アスカ」ってメモだけが産着の胸もとにはさまれてたんだって。だから名前はアスカ。鳴海は施設長が適当に考えれくれた。金髪で瞳の色も日本人と違うでしょ。子どもって容赦ないから。この外見のせいで恒常的にいじめを受けてた。園庭の隅で植物だけを遊び相手にしてたの。植物は裏切らない。きちんと世話をすれば応えてくれる。5歳のときにね、太田さんっていう若い職員さんが入ってきた。気にかけてくれて「ないしょよ」って植物のポケット図鑑をこっそりくれた。しばらくすると太田さんはいなくなった。あたしに対するいじめを訴えて辞めさせられたんだって。ずいぶん経ってから聞いた。いじめはがまんできた。でも。
14歳のとき2歳上の男子にベッドで襲われそうになって、急所を蹴りあげて夜中に飛び出した。植物図鑑だけをポケットにつっこんで。走って、走ってコンビニ前でしゃがんでいるところを山際に声をかけられた。「食べるか」ってあんパンとジュースを少し離れた場所から投げてよこした。「刑事の張り込みじゃないんだから」って笑うと、「もんく言わずに食え」って。あたしが食べ終わるまでしゃがんで煙草をふかしながら、じろじろ見ていくやつらをしっしっと手で追い払ってた。「警察に行くか」と訊かれて首をふると、煙草を消して立ちあがった。「行くあてがなかったらついて来い」といいながら腕を伸ばすの。「これよりも離れてついて来るんだぞ。俺が何かしようとしても逃げられる距離だから」ぼさぼさの髪によれよれのシャツ、素足にデッキシューズを履いたおっさん。見るからにうさんくさそうなのに、信じられるおとなだと思った。
それから山際調査事務所で暮らしてる。草ぼうぼうの敷地に温室を建ててくれた。護身術の特訓も受けた。大学の薬学部にもいかせてもらった。山際は仕事について最初に正直に話してくれて、おまえはおまえの好きなことをしろって言ってくれた。でも、もともと植物が好きだったし、観賞よりも効能のほうに興味があったし、それに実験って楽しいでしょ。恩返しっていったら、耳をひねりあげられそうだけど。
「あたしたちって真逆なのに、似ているのね」
親を知らない子ども。親から逃げた子ども。
「その薬草園と温室をぜひ見てみたいな」
「いつでも。雑草だらけでびっくりするかも」
(to be continued)
第7話に続く。
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
