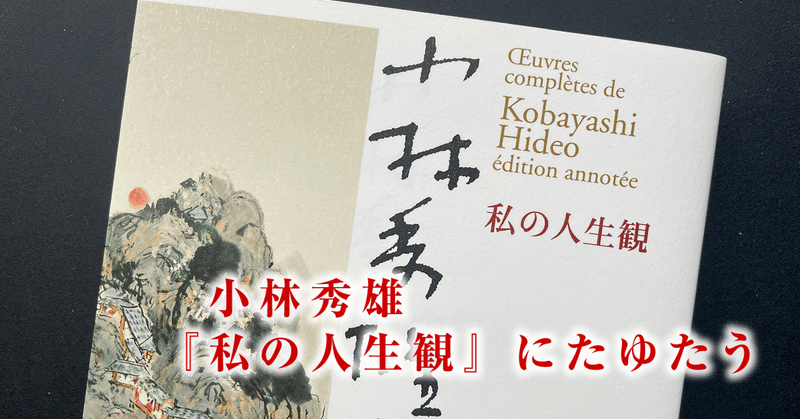
身をもって相手と交わり、生まれるのが「言葉」だ
禅というのは考える、思惟する、という意味である。そして「考える」というのは、本居宣長によれば、物に対する単に知的な働きではなく、物と親身に交わることだ。物を外から知るのではなく、物に身を感じて生きる、そういう経験なのだと小林秀雄は語る。
この「物」は、本居宣長が用いたままであり、当時はとても常識の言葉だったという。しかし小林秀雄が先の考察を『考えるという事』として発表した1960年代も、そのあと半世紀をゆうに過ぎた現在でも、「物」といえば物質的な「物」と解釈されがちだ。いまなら「もの」と表記するか、物質や概念を問わず「対象」「相手」と言い換えたほうが、通じやすいかもしれない。
小林秀雄を私淑し、大胆にも「恋文」まで書いた哲学者の池田晶子は、『考えるヒント』を本歌取りした『新・考えるヒント』を発表している。あまりに敬愛しているので、各項のタイトルを拝借しただけでなく、その文体まで似てしまったことを認めたうえで、みずからの「哲学する」すなわち「考える」ことの軌跡を記している。
そんな『新・考えるヒント』には、もちろん本歌とおなじく『考えるということ』という文章がある。そして小林秀雄の「物に身を感じて生きる」ということを池田晶子自身の言葉で的確に説明している。
「物」という「何か」とは、私は私なりの拙い言い方で言えば、在るところのもの、「存在」ということになる。考えるとは、存在を考え、存在と交わることだ。ところが、「存在」と言っても、その意味での絶対抽象を考え慣れないと、どうしても何らかの「存在者」、実体としての存在者を表象してしまうようである。眼前に一輪の花が存在する。しかし、存在するその花と、それが存在するということとは違うことだ。存在者は目に見えるが、存在そのものは目には見えない。それは、考えるという抽象によってのみ把まれる、その意味での一種の「物」なのだ。
さらに池田晶子は、「妙な言い方だが」と前置きしたうえで、「考えるとは、存在と交わる、存在と交情する、存在との恋愛関係に這入るようなものではなかろうか」とたとえる。さらに「言葉とは、存在との交情によって考えを妊娠し、生まれた子供のようなものであろうか」と語る。大胆な比喩だが、すんなり理解できる。
人間は、言葉がなければ思考ができない。いまから1分間、一切言葉を使わないで「考える」ことをしてみればいい。当然、不可能だ。また、言葉なしでは、「感じる」こともできない。これから晩秋に向かうというのに、まるで冬が来たような昨日・今日の肌寒さを、一切言葉を使わないで「感じ」てみよ。それも不可能だ。
考えることに言葉は不可欠であり、「物」という存在と身をもって交わるときに生まれるのが「言葉」なのである。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
