
朝井リョウの才能に殺される季節が来た。就活生が『何者』を読むと、血が出る。
僕は就活を控えた大学3年生。「朝井リョウの才能に殺されそう」と、思わず呟いたのは2週間前のことだ。
新潮文庫の帯にはこうある。
299ページ12行目、物語があなたに襲いかかる――。

この帯は脳の奥のほうをぐっと掴んで離さない。こんな予告をされてしまえば、見開きのページから、からだが準備をしはじめる。どんな伏線も目いっぱいに回収できるように、念入りに読むことを決めた。
のっけから、直木賞作家の観察力は、分不相応な場所に潜んでいる大学生をぐっと捕らえて日の目にさらす。
ドン、と、誰かの肩が当たって、リズムが崩れた。曲のテンポの波から外れた自分の体は、光太郎の歌声が作り出す空間そのものからポンと押し出されてしまったようだ。そのとたん、ライブハウスなんていう全く似合わない場所にいることを誰かに見つけられた気がして、急に恥ずかしくなる。(p.7)
身に覚えのある経験をつつかれて、羞恥心でくすぐったくなる。
こんなかんじで、終始「就活をくさすフレーズ」や「主人公の視線装置から放たれる分析的な語り」に息を巻いていた。「くっそー面白いな…」と言いながら付箋を貼り付けて。
「就活って、トランプでいうダウトみたいなもんなんじゃねえの。一を百だって言う分には、バレなきゃオッケー。ダウトのとき、1をキングだって言うみたいにな。でも、裏返されてそれが1だってバレれば終わりだし、カードがなければ戦いに参加することもできない。つまり、面接でもゼロを百だって話すのはダメ。それはバレる。」(p.49)

「あー現実に居そうこういうやつ」というような脇役の作り方も手が込んでいる。
最近どう? と聞いてくる人は、たいてい、相手の近況を聞きたいわけではなく、自分の近況を話したくてたまらない。ESを見せ合おうよ、と言ってきたあの子はきっと、誰かのESを参考にしたいのではない。自分の完璧なESを見せびらかしたくてたまらないのだ。(p.66)
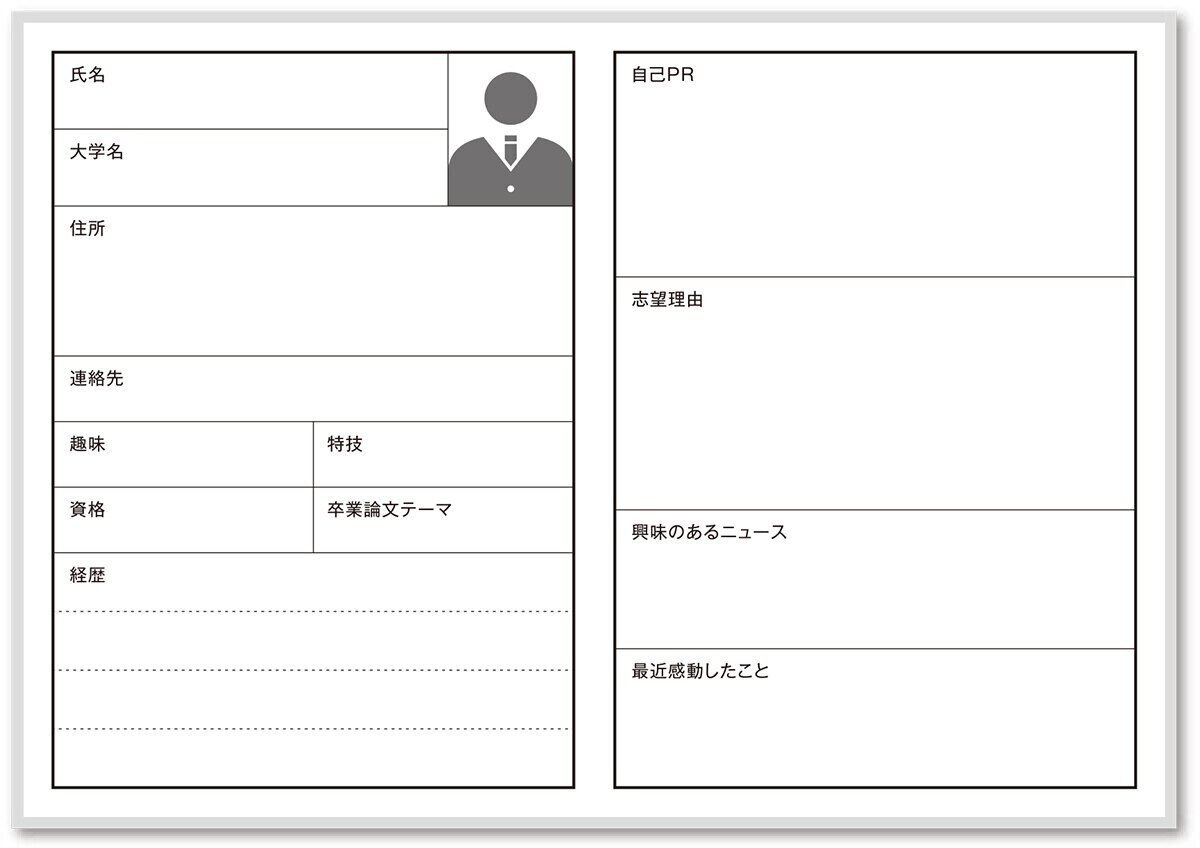
そうして気付けば250ページを回り、主人公たちの就活が終わりかけている。「あれ。。。 おかしいな。」と本の帯を見直す。まだ50ページ以上を残して、物語は一通りの終わりを迎えそうなムードなのだ。「一体これから何が起こるのか。」該当箇所に近づくにつれ、心拍数があがる。
280、281、282、283、284 ...
昔から「怖い怖い」と言われているものは、「パッと見やってそれが何かわかったらすぐ視線を逸らす」という適切な付き合いができない。
289、290、291、292、293 ...
怖いものが得意でないクセに、ぐーっと瞳孔を開いてゆっくりじっくりと戦慄を味わって、あとで寝る前に後悔してしまう。
294、295、296、297、298 ...
299ページをそうっと手繰り、目を覆うようにして12行目に視線をやった。
文字通り、ここでピンポイントに、物語が急転する。
詳しい顛末は自分の目で確かめて欲しい。が、僕はというと、そこから結末までの30数ページはもうトラウマがフラッシュバックするようにして脳裏に焼き付いている。
(ここで終わってはただのステマだ。noteに書く意味がない。続ける。)
その中の一節、女の子が主人公にこう言い放った。
「拓斗くん(主人公)はさ、自分のこと、観察者だと思ってるんだよ。そうしてればいつか、今の自分じゃない何かになれるって思ってんでしょ?」(p.301)
僕は朝井リョウが
「観察者」
の3文字に込めた鋭利な
「きみってこうでしょ?」
という含み笑いがはっきりと聞こえた。
はっとして、ページを前へ前へ手繰る。拓斗(主人公)の分析はいつも、距離を置くのだ。拓斗の挙動の全てが、不自然に見えてきた。批評の的になるのは、つねに脇役(に見えている)誰か。誰かのダサさをくさす自分は、いつも安全地帯だ。
思えば、それを読んで僕は、
終始「就活をくさすフレーズ」や「主人公の視線装置から放たれる分析的な語り」に息を巻いて
いた。
斜に構えた主人公を、称賛している。
なぜそんなことができたのか。
現に僕が、「就活をくさして」いるからだ。本格化する前年の夏から、早々と本気になりたくない。できるなら、ぎりぎりまで先延ばししていたい。
・・・ 暗雲が立ち込めてきた。
続けて僕はこうも言っていた。
「あー現実に居そうこういうやつ」というような脇役の作り方も手が込んでいる。
脇役?笑わせんな。
拓斗(主人公)がくさす人たちは、恐る恐るでも、ダサくても、自分の気持ちと折り合いをつけて、就活に染まる自分を、受け入れようとしていた。
一方で、拓斗は、「現時点での自身の力を受け入れている人たち」を一歩引いたところから批評することで、「自分は、今の自分じゃない何かになろうとしている、主人公なんだ」と思おうとしている。
僕もきっと、この主人公に似ている。だから、簡単に「脇役」という言葉が出てくる。
本当は、批評している側の人間こそが、脇役なのに。
・・・ 胸に突き立てられた刃が奥へ奥へと入ってくる。
拓斗に向かって女の子がぶつける言葉が、傷口に塩をぬったように沁みる。
「自分は自分にしかなれない。痛くてカッコ悪い今の自分を、理想の自分に近付けることしかできない。みんなそれをわかってるから、痛くてカッコ悪くたってがんばるんだよ。カッコ悪い姿のままあがくんだよ。だから私だって、カッコ悪い自分のままインターンしたり、海外ボランティアしたり、名刺作ったりするんだよ。」(p.310)
部屋には僕ひとり。誰も見ていないのに、カッと耳が熱くなって、一瞬、カメラのピントがずれたように文字がぼやけた。
そこからはもう、駆け抜けるように―。いや、心掛けてゆっくりページを手繰った。痛かった。だからこそなおさら、「これはお前だ。」と、沁み込ませようとした。どこも切れていないのに、本当に、血が出そうだった。
物語の最後に、就活に臨んでいる拓斗の姿がはじめて描かれる。『メッキが剥がれた』という形容がこれほどまでにハマることはそうそうないだろう。
336ページの、弱り切った〈観察者〉を見届けたあとは、もう、動けなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
